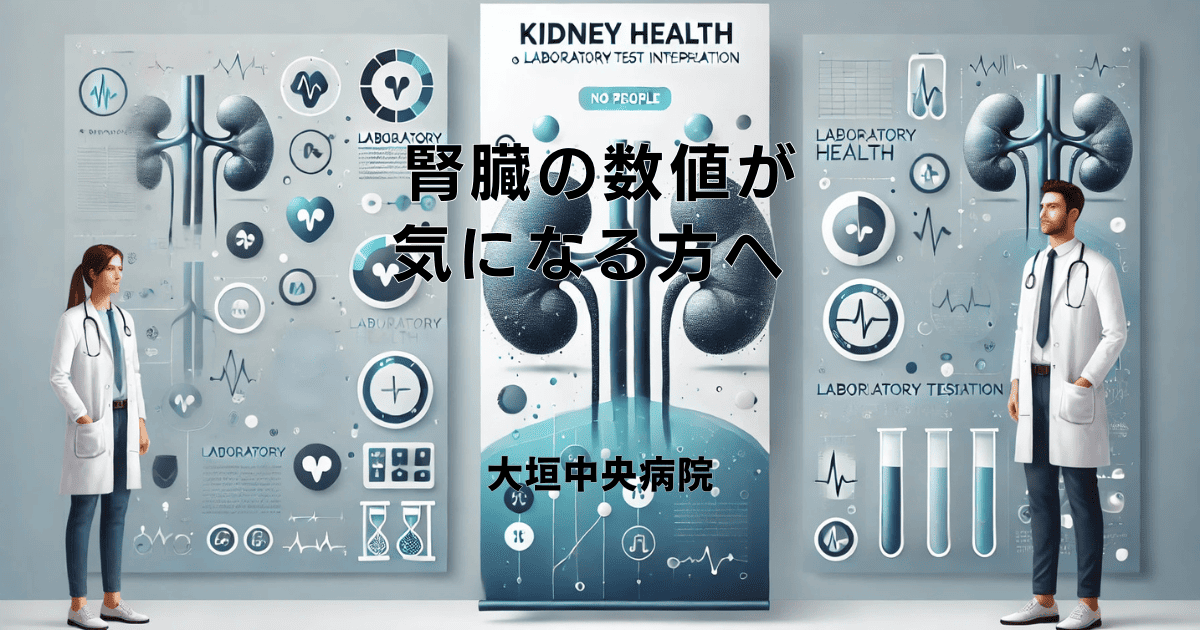腎臓の働きに異常があると、採血や尿検査の結果に変化が生じやすくなります。腎臓の数値が高い状態が続くと、体調面で悩みが生じたり、将来的に透析へと進むリスクが高まる場合もあります。
普段から検査値をよく理解し、生活習慣を見直すことが重要です。本記事では、腎臓の数値が悪い方や腎臓の数値が気になる方に向けて、検査値の基本や改善につながるアプローチを幅広くお伝えいたします。
腎臓の働きと検査値の基礎知識
腎臓は体の老廃物や余分な水分を排出し、血液中の成分バランスを整える大切な臓器です。腎臓がうまく働かなくなると、採血や尿検査で異常が見つかることが多く、初期段階で気づきにくい特徴もあります。
早めに検査値の変化を捉え、腎臓への負担を軽減する対策を考えることが鍵になります。
腎臓の基本的な役割
腎臓は体内のろ過器として働き、血液中の不要物質をろ過して尿として排出します。また電解質や水分の調整、血圧の調整にも関わっています。
腎臓の数値が悪い状態に陥ると、老廃物が体内に蓄積しやすくなり、全身に影響が及ぶ可能性があります。
- 血液中の老廃物をろ過して尿を生成する
- 電解質や水分を調整し血圧をコントロールする
- エリスロポエチンを分泌して造血を助ける
腎臓の働きには多角的な側面があるため、数値をチェックして異常を早めに発見すると、進行を和らげるきっかけにつながります。
腎臓の数値を左右する仕組み
腎臓には糸球体というろ過機能の中心となる部分があります。血液をろ過して老廃物を取り除き、たんぱく質やブドウ糖など必要な成分は再吸収する複雑な仕組みです。
加齢や高血圧、糖尿病などにより血管やろ過膜にダメージが蓄積すると、腎臓の数値が高い結果として検査に反映されます。
腎臓の主な構造
| 部位 | 役割 | 特徴 |
|---|---|---|
| 皮質 | 糸球体や近位尿細管などが存在する | ろ過と再吸収の初期段階を担う |
| 髄質 | ヘンレ係蹄や集合管などが存在する | 水分や電解質の再吸収をより強く行う |
| 腎盂 | 尿が集められ腎臓から排出される通り道 | 尿は尿管を通り膀胱へ送られる |
こうした構造全体が連携して血液をきれいに保つため、少しでも問題が起こると検査値に反映されやすくなります。
検査値の変化が起きやすい要因
多量の塩分やたんぱく質の摂取、喫煙、高血圧や糖尿病などが腎臓に負担をかける代表的な要因です。運動不足や過労、睡眠不足が続くと血管へのダメージが増え、腎臓への血流量が減少しがちになります。
腎臓に負担をかけやすい背景
- 長期にわたる高血圧
- 慢性的な高血糖状態(糖尿病)
- 塩分や動物性たんぱく質の過剰摂取
- 不規則な生活リズムやストレスの蓄積
こうした要因を見直すことが、腎臓の数値を改善するための第一歩となります。
腎臓の数値が高い原因と考え方
腎臓の数値が高いと言われると、多くの人はクレアチニンや尿素窒素、尿酸などをイメージします。実際には、これらの数値が上昇する背景にはさまざまな疾患やライフスタイルが絡み合っている場合があります。
原因を正しく把握し、適切な手段で改善を目指すことが重要です。
クレアチニンとBUNが上昇するメカニズム
クレアチニンは筋肉の代謝産物で、腎臓のろ過機能の状態を反映しやすい項目です。尿素窒素(BUN)はたんぱく質の分解産物であり、腎臓の排泄能力の指標とされます。
両者が上昇した場合、腎臓が老廃物を十分に排出できていない可能性が高いです。
クレアチニンとBUNの特徴
| 項目 | 主な由来 | 意味合い |
|---|---|---|
| クレアチニン | 筋肉の代謝産物 | 腎臓のろ過機能を直接的に示す |
| BUN(尿素窒素) | たんぱく質の分解産物 | 腎臓の排泄機能が低下すると上昇しやすい |
クレアチニンやBUNが基準値を超えて高値を示すときは、腎臓の働きに障害がある可能性があります。
ただし高タンパク食や脱水、運動量の増加などでも変動しやすいため、単発ではなく継続的なチェックが大切です。
腎臓の数値が悪い背景疾患
高血圧や糖尿病などが続くと、糸球体や血管にダメージが蓄積し、腎臓の数値が悪い方向へ傾きやすくなります。脂質異常症や肥満も血管機能を損ない、腎臓への血流を減少させる一因となります。
また、自己免疫系疾患や感染症などが腎機能を急激に低下させるケースも少なくありません。
早期発見と早期対策の意義
腎臓は一度大きく機能を落とすと回復しにくい臓器です。腎臓の数値が高いと指摘された段階で迅速に対策を講じると、進行を抑え、透析などのリスクを軽減する可能性が高まります。
腎機能低下を抑える上で大切な点
- 定期的に血液検査と尿検査を受ける
- 高血圧や糖尿病を管理する
- 管理栄養士や医師に相談して食事内容を調整する
こうした継続的な取り組みによって、腎臓の数値をコントロールしやすくなります。
検査値の具体的な種類と見方
腎臓の状態を知るには血液検査や尿検査など、複数の観点から数値を評価する必要があります。
それぞれの検査項目がどんな意味を持ち、どのように評価すべきかを理解すると、腎臓の数値が気になる方でも具体的な対策を立てやすくなります。
血液検査の主な指標
代表的な指標としてはクレアチニン、BUN、eGFR(推算糸球体ろ過量)などがあります。
eGFRはクレアチニン値、年齢、性別などから算出し、腎機能の大まかなステージを知る手がかりとなるため、多くの医療機関が活用しています。
血液検査の項目と目安
| 項目 | 基準値の目安 | 意味合い |
|---|---|---|
| クレアチニン | 男性0.6~1.2mg/dL程度、女性0.5~1.0mg/dL程度 | 筋肉量や年齢によっても変動 |
| BUN | 約8~20mg/dL | 高たんぱく食や脱水でも上昇 |
| eGFR | 90以上が正常の目安 | 60を下回るとCKDの疑いが強まる |
これらの数値が変動する原因は多岐にわたるため、主治医は患者の生活状況や身体計測値も併せて総合的に評価します。
尿検査の重要性
尿タンパクや尿潜血、尿沈渣などを見ると、糸球体の炎症や出血、感染などが推察できる場合があります。腎臓の数値が悪い人は、尿検査でさらに原因や病態を深く調べることが多いです。
- 尿タンパクが持続的に陽性なら糸球体障害が疑われる
- 尿潜血が続けば腎炎や尿路系の病変も考えられる
- 特殊検査で尿中アルブミン量を測定し、早期の腎障害を捉える
こうした結果を踏まえ、腎機能低下の進行度合いを正確に掴みやすくなります。
画像検査や特殊検査
超音波検査(エコー)で腎臓の形態や血流を見ると、結石や腫瘍、萎縮の有無などを把握できます。
CTやMRIなどが必要になる場合もありますが、主に腎臓の大きさや腫瘤の評価を行うことが目的です。また血管造影検査で腎動脈の狭窄などを調べることもあります。
画像検査の種類と役割
| 検査方法 | 主な目的 | 特徴 |
|---|---|---|
| 腎エコー | 腎臓の形態や腫瘤、結石、血流の確認 | 侵襲が少なく、外来でも比較的簡単に実施可能 |
| CT | 腎臓周辺の構造、腫瘍の詳細把握 | 放射線被ばくがあるため必要性を吟味 |
| MRI | より詳細な軟部組織の評価 | 金属が体内にある場合は注意が必要 |
これらの情報を総合的に判断して、腎臓の状態をより立体的に把握します。
生活習慣による腎臓の数値への影響
腎臓の数値が高い方には、生活習慣が密接に関わっているケースが多いです。食事内容や運動習慣、睡眠、喫煙などを整えると、腎機能を長期的に守る手段として大変有用です。
食事面の特徴
塩分やタンパク質、カリウムの過剰摂取は腎臓に負担をかけやすいです。一方で摂取不足による栄養不良も、免疫力や筋肉量の低下を招きかねません。バランスを見極めながら食事管理を行うことが大切です。
食事管理を実践するうえで注目したい要素
| 要素 | 大まかな目安 | 注意すべき点 |
|---|---|---|
| 塩分 | 1日6g未満を推奨 | 高血圧を合併している場合はさらに減量 |
| たんぱく質 | 体重1kgあたり0.6~0.8g程度を目標 | CKDのステージによって調整が必要 |
| カリウム | 2,000~2,500mg程度を意識 | 血清カリウム値が高い場合は調理法に工夫 |
| 水分 | 1日1.5~2L程度を目安 | 心不全などがある場合は主治医と相談 |
管理栄養士の指導を受けると、個々の病態や生活スタイルに合わせた食事プランを組みやすくなります。
運動習慣と休養
軽いウォーキングやストレッチなどを定期的に行うと、血流の改善や血圧コントロールにつながり、腎機能をサポートしやすいです。
ただし、過度な運動は筋肉量の急な増加や脱水につながり、クレアチニン上昇の原因になる可能性もあるため、適度を意識すると良いでしょう。
ストレスと喫煙の影響
ストレスが長期間蓄積すると交感神経が高ぶり、血圧上昇や食欲の変動によって腎臓の数値が気になる状態が長引きやすくなります。
喫煙は血管を収縮させ、腎臓への血流を下げてしまうため、できるだけ禁煙に向けて行動することがおすすめです。
生活習慣を整えるための主なポイント
- 適度な塩分制限とバランスの良い栄養摂取
- 継続可能な軽~中程度の運動
- ストレスマネジメントや十分な睡眠
- 禁煙や節酒の取り組み
小さな改善でも積み重ねると腎臓への負担を和らげる大きな力になります。
腎臓の数値が悪いときに注意したい合併症
腎臓の数値が悪い状態を放置すると、高血圧や貧血、心血管系トラブルなど、さまざまな合併症を引き起こしやすくなります。特に慢性腎臓病(CKD)は心臓や血管への影響が大きく、重症化を防ぐことが大切です。
高血圧との関連
腎機能低下と高血圧は相互に悪影響を与え合います。腎臓の血管が損傷すると血圧はさらに上昇し、高血圧が持続すると腎臓のろ過機能が損なわれやすいという負の連鎖が生じます。
適切な降圧薬の選択や塩分制限などの生活習慣改善がポイントです。
貧血とエリスロポエチン
腎臓はエリスロポエチンという造血ホルモンを分泌しているため、腎機能が下がると貧血を起こしやすくなります。貧血が進むと疲労感や息切れが強まり、生活の質が低下します。
エリスロポエチン製剤の使用を検討する場合もあるので、定期的にヘモグロビン値を確認してください。
合併症と主な特徴
| 合併症 | 主な症状 | 主な対策 |
|---|---|---|
| 高血圧 | 頭痛、めまい、動悸 | 塩分制限、降圧薬によるコントロール |
| 貧血 | 倦怠感、息切れ | エリスロポエチン製剤、鉄剤の適宜投与 |
| 心不全 | 息苦しさ、浮腫 | 利尿薬、生活習慣の調整、適度な運動 |
軽度の段階で手を打っておくと、合併症の深刻化を防ぎやすくなります。
心血管疾患との関係
CKDが進行すると動脈硬化が進みやすく、心筋梗塞や脳卒中などのリスクが上昇します。腎臓の数値が気になる方は脂質管理や喫煙習慣の見直しも含め、総合的な対策を行うことが望ましいです。
食事と水分管理のポイント
腎臓の数値が高い状態の改善には、食事と水分の管理が欠かせません。過剰摂取を避けながら、栄養をしっかり確保するバランス感覚が求められます。
管理栄養士のアドバイスを受けると、具体的な献立や調理法について相談しやすくなります。
たんぱく質の摂り方
腎臓の負担を軽減するために、過剰なたんぱく質を控えることが重要です。
ただし、低たんぱく食を意識しすぎて不足になりすぎると、筋肉量や免疫力の低下を招きます。適度な量を守り、良質なたんぱく質源を選ぶことが大切です。
食材のたんぱく質量の目安
| 食品 | 100gあたりのたんぱく質量 | 例 |
|---|---|---|
| 魚(鮭、鯖など) | 約20g前後 | 切り身1枚(80~100g)で約16~20g |
| 鶏ささみ | 約23g | 1本(50g程度)で約11~12g |
| 豆腐(絹ごし) | 約6g | 半丁(150g)で約9g |
| 牛乳 | 約3g | 200mL1杯で約6g |
これはあくまで目安なので、自分の体重や病状に応じて調整してください。
塩分とカリウムのコントロール
腎臓の数値が悪い方や高血圧を併発している方は、過度の塩分摂取によって体内に水分やナトリウムがたまりやすくなります。
またカリウム値が高くなる傾向がある場合、野菜や果物を食べる際に茹でこぼしをするなどの工夫が必要になることもあります。
- 野菜を茹でてから調理し、カリウムを減らす
- 塩分の多い加工食品やインスタント食品を控える
- だしや香辛料で風味を加え、塩分を抑える
これらの取り組みを継続して行うと、腎臓の数値を安定させやすくなります。
水分摂取の適度なバランス
腎臓の状態によっては、水分制限が必要になることがあります。特に心不全や重度のむくみがある場合は主治医が制限量を設定することもあります。
一方で、脱水が進むと血液が濃縮されて腎臓の負担が増す可能性もあるため、過剰でも不足でもないバランスが望ましいです。
水分管理で意識したい項目
| 状況 | 対応 | 主な目的 |
|---|---|---|
| 心不全のリスク | 水分摂取量を控えめに調整 | 循環血液量の過剰増加を回避 |
| 脱水のリスク | こまめに少量ずつ水分を摂取 | 腎臓への血流確保 |
| 電解質異常 | カリウムやナトリウムのバランスを定期的に検査 | バランスを崩さないよう管理 |
主治医と相談しながら、自分に合った水分摂取方法を検討してください。
腎臓の数値を改善するための受診と治療
腎臓の数値が気になる段階から、定期的に医療機関を受診し、状態を把握することが大切です。早期に治療を始めると、透析導入のリスクを下げたり、合併症を軽減したりする可能性が高まります。
腎臓内科や総合病院への受診
腎臓内科では血液検査や尿検査、画像検査のほか、必要に応じて専門的な治療を組み合わせることができます。総合病院であれば多職種連携が取りやすく、合併症のある方でも同時に各診療科のサポートを得やすい利点があります。
受診時に意識したい項目
- 自覚症状の有無や変化を具体的に伝える
- 服用中の薬やサプリメントのリストを準備する
- 普段の食事や運動習慣を書き出す
- 気になる点や疑問点をメモしておく
これらを医師と共有すると、より的確な診断と治療方針を立てやすくなります。
薬物療法の可能性
腎臓の数値が悪い方は、降圧薬や利尿薬、糖尿病薬などを組み合わせて腎機能を保護する場合があります。血圧コントロールや血糖管理が進むと、腎臓への負荷が軽減するため、定期的な検査で効果を確認しながら薬の調整を行います。
貧血がひどい場合はエリスロポエチン製剤の使用も検討されます。
主な薬物療法の一例
| 薬の種類 | 主な目的 | 注意点 |
|---|---|---|
| ACE阻害薬/ARB | 血圧を下げ、糸球体の負担を軽くする | 咳や腎機能変動などの副作用に注意 |
| 利尿薬 | 余分な水分を排出し血圧や浮腫を抑える | 脱水や電解質異常を起こさないよう定期検査 |
| エリスロポエチン製剤 | 貧血を改善して体力やQOLを向上させる | 適正なヘモグロビン値の維持が目標 |
主治医や薬剤師と相談しながら、自分の状態に合った薬を選択してください。
透析や腎移植の検討
腎機能が大幅に低下して透析が必要になる場合があります。透析は血液透析と腹膜透析が主な方法ですが、いずれも定期的な処置が必要になります。
腎移植という選択肢も存在し、ドナーとの適合性などを考慮しながら検討を進める方もいます。
- 血液透析:週に複数回の通院が必要
- 腹膜透析:自宅での透析管理が中心
- 腎移植:ドナー提供の条件や免疫抑制薬の使用が必要
透析を始める時期や方法、腎移植の検討などは医師や看護師、家族と十分に話し合って決めることが重要です。
総合病院のサポート体制
腎臓の数値が高い、腎臓の数値が悪いといった状態を放置すると、生活の質を大きく損なうリスクがあります。総合病院ならば各診療科や専門スタッフが連携を取り、複雑な病態や合併症にも一括して対応しやすくなります。
多職種連携のメリット
腎臓内科、循環器内科、糖尿病内科などが連携することで、患者の病態を総合的に評価し、より効率的な治療を提供しやすくなります。
管理栄養士や薬剤師、臨床工学技士なども加わると、食事指導や服薬管理、透析装置の扱いなどがスムーズに行えます。
総合病院に在籍する主な専門スタッフ
| 職種 | 主な担当業務 | 関連性 |
|---|---|---|
| 腎臓内科医 | 検査・治療方針の決定 | 腎機能の評価と治療全般を担う |
| 看護師 | 患者のケア、バイタルサイン管理 | 日々の体調変化を見守りながら連携を図る |
| 管理栄養士 | 食事プランの作成、栄養指導 | 腎臓の数値をコントロールするうえで要となる |
| 薬剤師 | 処方薬の選択・調整、相互作用の確認 | 多剤併用でも安全性を確保しやすくなる |
| 臨床工学技士 | 透析装置や医療機器の操作・管理 | 透析治療の安定稼働を支える |
| 医療ソーシャルワーカー | 経済的・社会的問題の相談対応 | 受診継続や福祉サービス利用の支援 |
多角的な視点でアプローチし、腎臓の数値が悪い背景を探り、改善への道筋を示しやすくなります。
通院サポートと検査体制
総合病院では1度の受診で複数の診療科を受けたり、画像検査や血液検査をスムーズに行ったりできる場合があります。合併症がある方や遠方からの通院者も、専門家の意見を同時に聞けるため負担を軽減しやすいです。
定期的な検査はCKDの進行を早期に捉え、対策を講じるための指標になります。
相談窓口やサポートプログラム
腎臓の数値が高い方は、透析への移行や生活習慣の大幅な変更など、先行きに不安を抱えることが多いです。総合病院では専門の相談窓口を設けており、社会資源の利用方法や心理面のフォローに関する相談が可能です。
チーム医療と併用して、患者と家族を包括的に支える仕組みを整えています。
サポートを活用する際に意識したいポイント
- 不安や疑問をため込まず、適宜専門スタッフに相談する
- 社会保険や障害年金などの制度の利用を検討する
- 心理面や生活上のストレスも医療スタッフに打ち明ける
- 定期受診や血液検査を欠かさず続ける意義を再認識する
こうした取り組みによって、モチベーションを保ちつつ腎臓の数値を改善する可能性を高められます。
以上


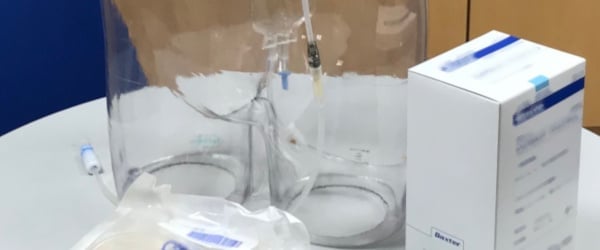
透析センター(人工透析) | 大垣中央病院(医療法人社団豊正会 )
参考文献
GOUNDEN, Verena; BHATT, Harshil; JIALAL, Ishwarlal. Renal function tests. In: StatPearls [Internet]. StatPearls Publishing, 2024.
MYERS, Gary L., et al. Recommendations for improving serum creatinine measurement: a report from the Laboratory Working Group of the National Kidney Disease Education Program. Clinical chemistry, 2006, 52.1: 5-18.
STEVENS, Paul E.; LEVIN, Adeera; KIDNEY DISEASE: IMPROVING GLOBAL OUTCOMES CHRONIC KIDNEY DISEASE GUIDELINE DEVELOPMENT WORK GROUP MEMBERS*. Evaluation and management of chronic kidney disease: synopsis of the kidney disease: improving global outcomes 2012 clinical practice guideline. Annals of internal medicine, 2013, 158.11: 825-830.
LEVEY, Andrew S., et al. Definition and classification of chronic kidney disease: a position statement from Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO). Kidney international, 2005, 67.6: 2089-2100.
TANGRI, Navdeep, et al. A predictive model for progression of chronic kidney disease to kidney failure. Jama, 2011, 305.15: 1553-1559.
LEVEY, A. S., et al. Chronic kidney disease as a global public health problem: approaches and initiatives–a position statement from Kidney Disease Improving Global Outcomes. Kidney international, 2007, 72.3: 247-259.
HERZOG, Charles A., et al. Cardiovascular disease in chronic kidney disease. A clinical update from Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO). Kidney international, 2011, 80.6: 572-586.
STAR, Robert A. Treatment of acute renal failure. Kidney international, 1998, 54.6: 1817-1831.
HEMMELGARN, Brenda R., et al. Relation between kidney function, proteinuria, and adverse outcomes. Jama, 2010, 303.5: 423-429.