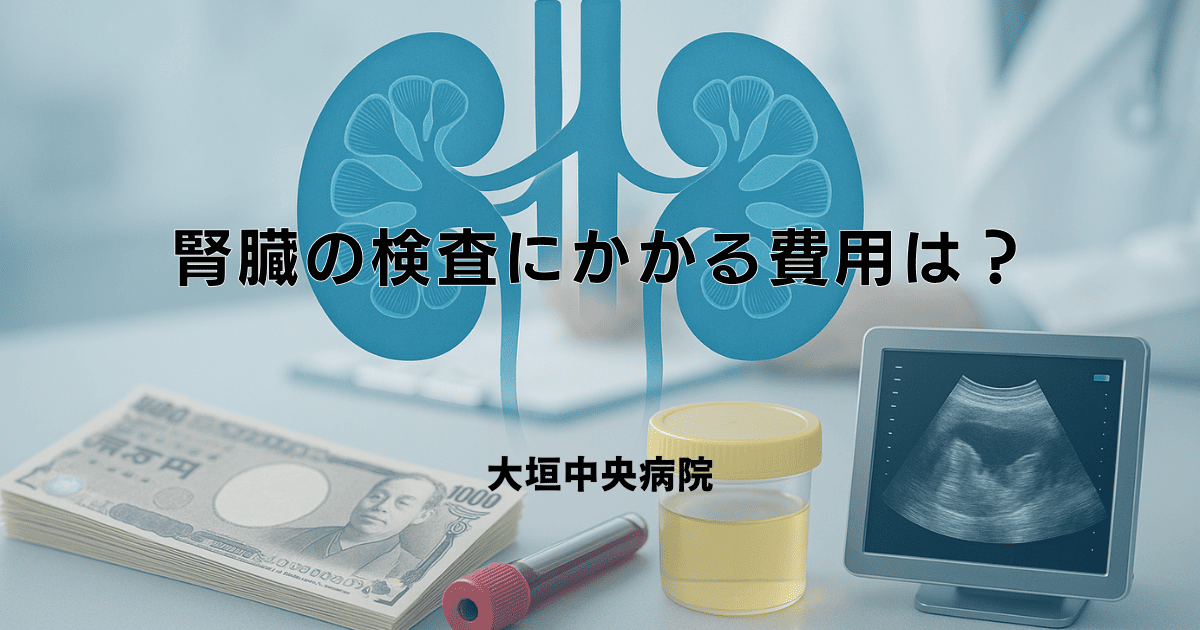腎臓は体内の老廃物を排出し、水分やミネラルのバランスを調整する重要な臓器です。しかし、腎臓の機能が低下しても自覚症状が現れにくいため、「沈黙の臓器」とも呼ばれます。
症状が現れたときには、すでに病気が進行していることも少なくありません。そのため、定期的な検査による早期発見が何よりも大切です。
この記事では、「腎臓の検査にはどんな種類があるのか」「費用はどのくらいかかるのか」といった疑問に答えるため、尿検査や血液検査、画像検査など、主な検査の内容と費用の目安を詳しく解説します。
なぜ腎臓の検査が重要なのか
腎臓の主な働きと役割
腎臓は、背中側の腰骨の少し上あたりに左右一対で存在する、そら豆のような形をした臓器です。一つが握りこぶしほどの大きさでありながら、私たちの生命維持に欠かせない多様な役割を担っています。
最もよく知られている働きは、血液をろ過して老廃物や余分な塩分、水分を尿として体外に排出する機能です。この働きにより、体内の環境は常にきれいに保たれます。
また、体液の量やイオンバランス(ナトリウム、カリウムなど)を一定に保つ調整機能、血圧をコントロールするホルモンの分泌、赤血球の産生を促すホルモンの分泌、そして骨の健康維持に必要なビタミンDを活性化する働きも持っています。
これらの機能が一つでも損なわれると、体にさまざまな不調が生じます。
症状が出にくい「沈黙の臓器」
腎臓の機能が低下し始める慢性腎臓病(CKD)は、初期段階ではほとんど自覚症状がありません。
体のだるさ、貧血、むくみ、夜間の頻尿といった症状が現れることもありますが、これらは他の病気でも見られる症状のため、腎臓の異常とは気づきにくいのが実情です。
多くの人が「何かおかしい」と感じて医療機関を受診したときには、腎臓の機能がかなり低下してしまっているケースが少なくありません。機能が一度失われると、回復は難しい場合が多いです。
だからこそ、症状がないうちから定期的に検査を受け、腎臓の状態をチェックすることが極めて重要になります。
早期発見・早期治療のメリット
腎臓病は、早期に発見し、適切な治療や生活習慣の改善を行うことで、病気の進行を遅らせることが可能です。
例えば、高血圧や糖尿病が原因で腎機能が低下している場合、原因となる病気の管理を徹底することで、腎臓への負担を軽減できます。
食事療法(減塩やタンパク質の制限など)や薬物療法を早期から始めることで、将来的な透析治療や腎移植を回避できる可能性も高まります。
検査によって自分の腎臓の状態を正確に把握することは、健康な生活を長く続けるための第一歩と言えるでしょう。
定期的な検査が推奨される人
特に以下のような方は、自覚症状がなくても定期的に腎臓の検査を受けることが推奨されます。
- 糖尿病や高血圧の治療を受けている方
- 家族に腎臓病の人がいる方
- 過去に健康診断で尿蛋白や尿潜血を指摘されたことがある方
- 65歳以上の方
- 肥満やメタボリックシンドロームを指摘されている方
これらの危険因子に当てはまる場合は、かかりつけ医と相談の上、定期的な検査計画を立てることが大切です。
腎臓の検査費用の全体像
保険適用の基本ルール(1割~3割負担)
日本国内で腎臓の検査を受ける場合、医師が病気の診断や治療のために必要と判断した検査は、原則として公的医療保険(健康保険)の適用対象となります。
保険が適用されると、窓口で支払う自己負担額は、かかった医療費の総額の一部で済みます。自己負担の割合は年齢や所得によって異なり、一般的には以下のようになっています。
- 6歳(義務教育就学前)まで:2割負担
- 6歳から69歳まで:3割負担
- 70歳から74歳まで:原則2割負担(現役並み所得者は3割)
- 75歳以上:原則1割負担(現役並み所得者は3割)
この記事で紹介する費用は、主に現役世代の方が多い「3割負担」を想定した目安金額です。
初診料・再診料について
医療機関で検査を受ける際には、検査そのものの費用に加えて、初診料または再診料が別途かかります。初めてその医療機関を受診する場合は「初診料」、2回目以降の受診では「再診料」が発生します。
これらの料金は国によって定められており、2024年現在、3割負担の場合の初診料は約870円、再診料は約220円(診療所の場合)が目安です。紹介状なしで大病院を受診した場合は、これに加えて特別な料金が加算されることもあります。
検査内容によって費用は変動する
腎臓の検査費用は、どのような検査をどのくらい行うかによって大きく変わります。
健康診断で行うような基本的な尿検査だけであれば費用は比較的安価ですが、より詳しく腎臓の状態を調べるために血液検査や腹部超音波検査などを追加すると、その分費用も加算されます。
医師が患者さんの状態に応じて必要な検査を組み合わせるため、一概に「いくら」とは言えないのが実情です。まずは基本的な検査から始め、異常が見つかった場合に精密検査へ進むのが一般的です。
費用について不安がある場合は、検査を受ける前に医師や医療機関のスタッフに確認することをお勧めします。
健康診断と精密検査の費用の違い
健康診断などで行う基本的な検査と、専門的な医療機関で行う精密検査では、費用に差があります。以下に一般的な費用の目安を示します。
| 検査の種類 | 主な内容 | 費用目安(3割負担) |
|---|---|---|
| 健康診断(基本的な検査) | 尿検査(蛋白・糖・潜血など) | 数百円~1,500円程度 |
| 精密検査(初診時) | 初診料+尿検査+血液検査 | 3,000円~7,000円程度 |
| 精密検査(画像検査追加) | 初診料+尿・血液検査+超音波検査 | 7,000円~12,000円程度 |
【基本の検査】尿検査の費用と内容
尿検査でわかること
尿検査は、腎臓の検査の中で最も基本的で、体に負担なく行える検査の一つです。尿は腎臓で作られるため、尿を調べることで腎臓や尿路(尿管、膀胱など)の状態に関する多くの情報を得られます。
主に「尿蛋白」「尿潜血」「尿糖」などを調べます。尿蛋白は腎臓のフィルター機能の異常を、尿潜血は腎臓や尿路からの出血を示唆します。これらの異常が持続する場合は、腎臓病のサインである可能性があります。
健康診断などで異常を指摘された場合は、放置せずに必ず医療機関を受診してください。
尿蛋白・尿潜血検査の料金目安
尿蛋白や尿潜血などを調べる「尿定性検査」は、比較的安価な検査です。通常、これ単独で行うことは少なく、初診料や再診料、その他の検査と組み合わせて実施します。検査費用自体は、3割負担で数百円程度が目安です。
試験紙を使って短時間で結果がわかるため、多くの医療機関で広く行われています。
尿沈渣(にょうちんさ)検査とは
尿定性検査で異常が見られた場合などに追加で行うのが、「尿沈渣」という精密検査です。これは尿を遠心分離機にかけ、沈殿した成分(赤血球、白血球、上皮細胞、円柱、結晶など)を顕微鏡で詳しく観察する検査です。
どのような種類の細胞や成分がどれくらい含まれているかを調べることで、腎臓のどこにどのような病気が隠れているのかを推測する手がかりになります。
例えば、特殊な形をした赤血球や「円柱」と呼ばれる成分が見つかれば、腎臓の糸球体という部分の病気(腎炎など)が強く疑われます。
尿検査の主な項目と料金目安
尿検査にはいくつかの種類があり、それぞれ料金が異なります。以下に主な項目と3割負担の場合の費用目安を示します。
| 検査項目 | 主な目的 | 費用目安(3割負担) |
|---|---|---|
| 尿定性検査(蛋白、潜血、糖など) | 腎臓や尿路の異常のスクリーニング | 約80円 |
| 尿沈渣(顕微鏡検査) | 腎炎など病気の詳細な鑑別 | 約80円 |
| 尿中微量アルブミン | 糖尿病性腎症の早期発見 | 約150円 |
【詳細な検査】血液検査の費用と内容
血液検査でわかる腎臓の状態
血液検査は、尿検査と並んで腎臓の機能を評価するために非常に重要な検査です。血液中には、本来であれば腎臓から尿として排出されるはずの老廃物が含まれています。
腎臓の働きが低下すると、これらの老廃物を十分に排出できなくなり、血液中の濃度が上昇します。そのため、血液中の特定の物質の濃度を測定することで、腎臓がどの程度機能しているかを数値で客観的に評価できます。
特に重要なのが、後述するクレアチニン(Cr)値と、それをもとに計算するeGFR(推算糸球体濾過量)です。
クレアチニン(Cr)とeGFR(推算糸球体濾過量)
クレアチニン(Cr)は、筋肉を動かす際のエネルギー源であるクレアチンが代謝された後にできる老廃物です。クレアチニンは腎臓でろ過されて尿中に排出されるため、血中のクレアチニン値は腎機能の指標として広く用いられています。
腎機能が低下すると、クレアチニンをうまく排出できなくなり、血中濃度が上昇します。
そして、この血清クレアチニン値に、年齢と性別を加味して計算されるのが「eGFR(推算糸球体濾過量)」です。eGFRは、腎臓が1分間にどれくらいの血液をろ過できるかを示す値で、健康な腎臓では100mL/分/1.73㎡前後です。
この数値が低いほど腎機能が低下していることを意味し、腎臓病の重症度分類にも用いられます。eGFRが60未満の状態が3ヶ月以上続くと、慢性腎臓病(CKD)と診断されます。
尿素窒素(BUN)や電解質の検査
クレアチニンの他に、腎機能の指標として「尿素窒素(BUN)」も測定します。これはタンパク質が体内で利用された後にできる老廃物で、これも腎臓から排出されるため、腎機能が低下すると血中濃度が上昇します。
ただし、尿素窒素は食事内容や体内の水分量などの影響も受けやすいため、クレアチニン値と合わせて総合的に判断します。
また、腎臓はナトリウム(Na)、カリウム(K)、カルシウム(Ca)、リン(P)といった電解質のバランスを調整する働きも担っています。
腎機能が低下すると、これらのバランスが崩れ、特にカリウム値が高くなると不整脈など命に関わる状態を引き起こすことがあります。そのため、血液検査でこれらの電解質濃度を調べることも重要です。
血液検査の主要項目と料金目安
腎機能の評価に直接関連する主要な血液検査項目と、その費用目安は以下の通りです。
| 検査項目 | 何がわかるか | 費用目安(3割負担) |
|---|---|---|
| クレアチニン(Cr) | 腎臓の老廃物排泄能力 | 約30円 |
| 尿素窒素(BUN) | 腎臓の老廃物排泄能力 | 約30円 |
| eGFR | (計算項目であり、直接の費用は発生しない) | 0円 |
その他の関連する血液検査項目
腎臓病は他の生活習慣病とも深く関連するため、以下のような項目を同時に調べることもあります。
| 検査項目 | 腎臓との関連 | 費用目安(3割負担) |
|---|---|---|
| 尿酸(UA) | 高いと痛風や腎臓障害の原因になる | 約30円 |
| 電解質(Na, K, Cl) | 腎機能低下によるバランス異常を調べる | 約100円 |
| 血糖値・HbA1c | 糖尿病の管理状態を把握する | 約30円~150円 |
【精密な検査】画像検査の費用と内容
画像検査を行う目的
尿検査や血液検査で腎機能の低下や異常が疑われた場合、その原因をより詳しく調べるために画像検査を行います。
画像検査の主な目的は、腎臓の形、大きさ、位置に異常がないか、結石や腫瘍、嚢胞(のうほう:水のたまった袋)といった構造的な問題がないか、また腎臓への血流は正常かなどを視覚的に確認することです。
これにより、尿路閉塞、腎硬化症、多発性嚢胞腎といった病気の診断に役立ちます。体にメスを入れることなく腎臓の内部構造を観察できるため、診断において非常に有用な検査です。
腹部超音波(エコー)検査の料金目安
腹部超音波(エコー)検査は、体に無害な超音波を当て、その反響を画像化して内臓の状態を調べる検査です。痛みや放射線被ばくの心配がなく、比較的簡便に行えるため、腎臓の画像検査としては最初に行われることが多いです。
腎臓の大きさや輪郭、腎盂(じんう)の拡大の有無、結石や腫瘍の存在などをリアルタイムで観察できます。特に腎臓の萎縮の程度は、慢性的な腎臓病の進行度を判断する上で重要な情報となります。
費用は3割負担で約1,600円程度と、他の画像検査に比べて安価です。
CT検査・MRI検査の料金目安
超音波検査でさらに詳しい情報が必要と判断された場合や、腎臓の腫瘍などをより詳細に評価したい場合には、CT検査やMRI検査が行われます。
CT検査はX線を使って体を輪切りにしたような詳細な画像を得る検査で、小さな結石や腫瘍の発見に優れています。MRI検査は強力な磁気と電波を使って体内の状態を画像化する検査で、特に腎臓の血管の状態や腫瘍の性質を調べるのに有用です。
これらの検査では、必要に応じて「造影剤」という薬剤を注射して、より鮮明な画像を得ることがあります。造影剤を使用するかどうかで費用は大きく変動します。
各画像検査の費用比較
腎臓を調べる際の代表的な画像検査について、費用を比較したものが以下の表です。造影剤の使用有無によって料金が変わる点に注意してください。
| 検査名 | 特徴 | 費用目安(3割負担) |
|---|---|---|
| 腹部超音波検査 | 手軽で被ばくがない。基本的な形状評価に用いる。 | 約1,600円 |
| CT検査(単純) | 短時間で広範囲を撮影。結石や腫瘍の検出に優れる。 | 約5,000円~7,000円 |
| CT検査(造影) | 血流や腫瘍の詳細な評価が可能。 | 約9,000円~12,000円 |
腎臓の検査費用を抑えるための制度
健康保険の活用
前述の通り、医師が必要と判断した腎臓の検査は健康保険が適用されます。これにより、実際の医療費の1割から3割の自己負担で検査を受けることができます。
体調に不安を感じたり、健康診断で異常を指摘されたりした場合は、ためらわずに医療機関を受診することが結果的に医療費の抑制にもつながります。
自己判断で受診を先延ばしにすると病状が悪化し、かえって治療費が高額になる可能性があるためです。
高額療養費制度の概要
高額療養費制度は、1ヶ月間(月の初日から末日まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合に、一定の上限額を超えた分が後から払い戻される制度です。この上限額は、年齢や所得によって定められています。
腎臓の検査だけでなく、入院や手術などで医療費が高額になった場合に、家計の負担を大きく軽減してくれます。
払い戻しを受けるには申請が必要ですが、事前に入院などが分かっている場合は「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することで、支払いを自己負担限度額までに抑えることも可能です。
高額療養費制度の自己負担限度額(70歳未満・年収約370~770万円の場合)
所得区分によって自己負担限度額は異なります。ここでは、一例として標準的な所得の方の場合の目安を示します。
| 所得区分 | 自己負担限度額(月額) | 多数回該当※ |
|---|---|---|
| 年収約370~約770万円 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
| ※多数回該当:過去12ヶ月以内に3回以上上限額に達した場合、4回目から適用される限度額。 | ||
特定健診・人間ドックの利用
40歳から74歳までの方を対象とした「特定健診(メタボ健診)」では、基本的な尿検査(尿蛋白・尿糖)と血液検査(クレアチニン)が含まれています。
多くの市町村や健康保険組合では、自己負担が無料または少額で受けられるため、腎臓の異常の早期発見に非常に有効です。
また、任意で受ける人間ドックでは、より詳しい腎機能検査や腹部超音波検査をオプションとして追加できる場合があります。
これらを活用して定期的に自分の体の状態をチェックすることも、費用を抑えつつ健康を維持する賢い方法です。
腎生検など特殊な検査の費用
腎生検が必要になるケース
尿検査や血液検査、画像検査を行っても診断が確定しない場合や、腎臓病の種類を特定して治療方針を決定する必要がある場合に行われるのが「腎生検」です。
これは、腎臓に細い針を刺して組織の一部を直接採取し、顕微鏡で詳しく調べる検査です。特に、学校検尿で発見された無症候性の血尿や蛋白尿、急速に腎機能が悪化している場合、ネフローゼ症候群などが疑われる場合に行われます。
確定診断を下し、最も適切な治療法を選択するために重要な検査です。
腎生検の検査内容と流れ
腎生検は、出血などのリスクを伴うため、通常は数日間の入院が必要です。局所麻酔の後、うつ伏せの状態で背中から超音波で腎臓の位置を確認しながら、専用の針を刺して米粒程度の大きさの組織を数本採取します。
検査自体にかかる時間は30分程度ですが、検査後はベッド上で安静にし、出血がないかなどを慎重に観察する時間が必要です。採取した組織は、さまざまな染色を施して病理専門医が詳細に診断します。
入院を伴う場合の費用目安
腎生検は入院を伴うため、費用は比較的高額になります。検査そのものの費用に加え、入院基本料、投薬料、食事療養費などがかかります。
入院期間や病院の設備によっても異なりますが、一般的な3割負担の場合、総額で10万円から15万円程度が目安となります。
ただし、前述の高額療養費制度が適用されるため、実際の自己負担は所得に応じた上限額までとなることがほとんどです。
腎生検の費用内訳例(3割負担)
入院期間を4~5日と想定した場合の、おおよその費用内訳です。
| 項目 | 内容 | 費用目安(3割負担) |
|---|---|---|
| 検査・手技料 | 腎生検の実施、病理診断など | 約30,000円~50,000円 |
| 入院料・その他 | 入院基本料、食事代、投薬料など | 約70,000円~100,000円 |
| 合計 | (高額療養費制度適用前の概算) | 約100,000円~150,000円 |
よくある質問(Q&A)
- 検査当日の食事や飲み物に制限はありますか?
-
検査内容によって異なります。尿検査のみの場合は特に制限がないことが多いですが、血液検査で血糖値や中性脂肪などを同時に調べる場合は、検査前の食事が結果に影響するため、絶食の指示が出ることがあります。
腹部超音波検査では、食事によって胆のうが収縮したり、腸管ガスが発生したりして観察しにくくなるため、朝食を抜いて来院するようお願いすることが一般的です。
水やお茶など、糖分を含まない水分は摂取しても良い場合が多いです。事前に担当の医師や看護師の指示を必ず確認してください。
- 検査結果はどのくらいでわかりますか?
-
これも検査の種類によります。尿の定性検査や、院内で測定できる一部の血液検査項目は、当日中に結果がわかることもあります。
しかし、詳しい血液検査や尿沈渣、腎生検の病理診断などは、外部の検査センターに依頼する場合が多いため、結果が出るまでに数日から2週間程度の時間が必要です。
画像検査の結果は、放射線科医の読影レポート作成後に説明されることが一般的です。次回の診察時にまとめて説明を受けることが多いでしょう。
- 費用について、事前に病院へ問い合わせても良いですか?
-
はい、もちろんです。費用について不安がある場合は、遠慮なく医療機関の会計窓口や医事課などに問い合わせてください。
どのような検査を行うかによって費用は変動するため、正確な金額を事前に確定させることは難しいかもしれませんが、おおよその目安を教えてもらうことは可能です。
高額療養費制度の利用についても、相談に応じてくれます。
- 複数の検査を同日に行うことは可能ですか?
-
はい、可能です。多くの場合は、診察、尿検査、血液検査、そして必要であれば超音波検査までを同じ日に行うことで、患者さんの来院負担を減らすように配慮します。
ただし、CTやMRIといった大規模な検査機器は予約が必要なことが多く、後日の検査になることもあります。効率よく検査を進めるためにも、医師の指示に従い、計画的に受診することが大切です。
以上
参考文献
CUSICK, Marika M., et al. Population-wide screening for chronic kidney disease: a cost-effectiveness analysis. Annals of internal medicine, 2023, 176.6: 788-797.
MANNS, Braden, et al. Population based screening for chronic kidney disease: cost effectiveness study. Bmj, 2010, 341.
MENDU, Mallika L., et al. Clinical predictors of diagnostic testing utility in the initial evaluation of chronic kidney disease. Nephrology, 2016, 21.10: 851-859.
BOULWARE, L. Ebony, et al. Screening for proteinuria in US adults: a cost-effectiveness analysis. Jama, 2003, 290.23: 3101-3114.
BOULWARE, L. Ebony, et al. Screening for proteinuria in US adults: a cost-effectiveness analysis. Jama, 2003, 290.23: 3101-3114.
YEO, See Cheng, et al. Cost-effectiveness of screening for chronic kidney disease in the general adult population: a systematic review. Clinical Kidney Journal, 2024, 17.1: sfad137.
GAITONDE, David Y.; COOK, David L.; RIVERA, Ian M. Chronic kidney disease: detection and evaluation. American family physician, 2017, 96.12: 776-783.
CAIULO, Vito Antonio, et al. Ultrasound mass screening for congenital anomalies of the kidney and urinary tract. Pediatric nephrology, 2012, 27: 949-953.
CAVANAUGH, Corey; PERAZELLA, Mark A. Urine sediment examination in the diagnosis and management of kidney disease: core curriculum 2019. American Journal of Kidney Diseases, 2019, 73.2: 258-272.
BHUTANI, Harpreet, et al. A comparison of ultrasound and magnetic resonance imaging shows that kidney length predicts chronic kidney disease in autosomal dominant polycystic kidney disease. Kidney international, 2015, 88.1: 146-151.
O’NEILL, W. Charles. Renal relevant radiology: use of ultrasound in kidney disease and nephrology procedures. Clinical Journal of the American Society of Nephrology, 2014, 9.2: 373-381.