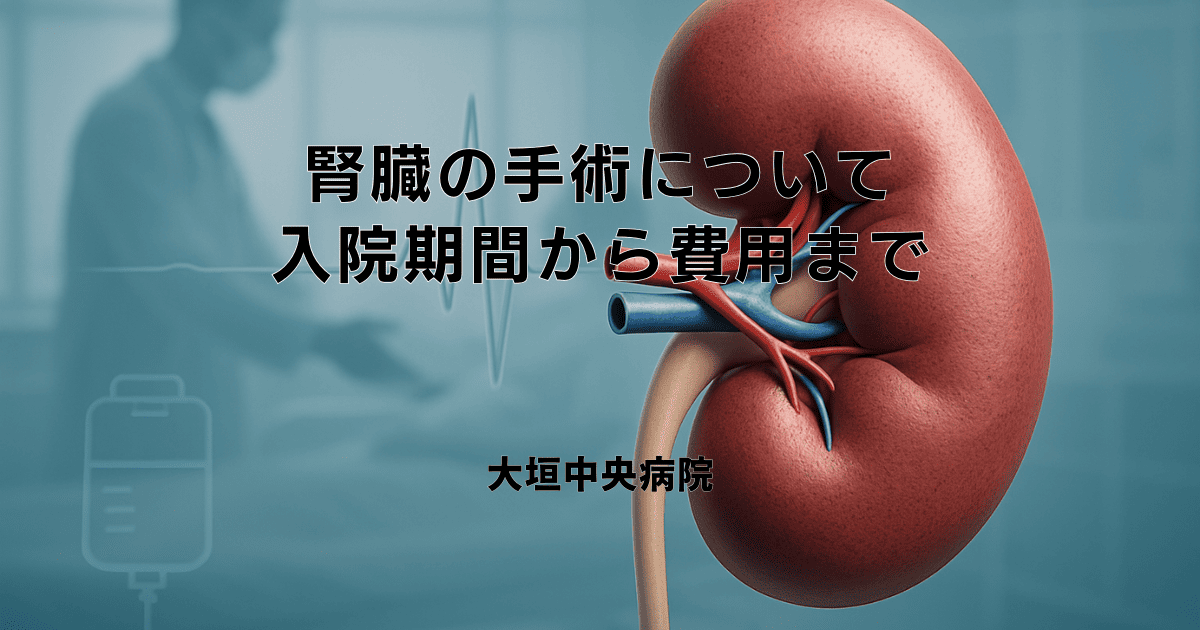腎臓の機能が低下すると、透析を検討する必要が生じる場合があります。そのようなリスクを軽減する目的で腎臓の手術を選択するケースが増えています。腎臓手術と一口にいっても、多彩な治療法や目的が存在します。
腎臓の状態や病気の進行度によっては、腎臓手術入院期間の長さや腎臓摘出手術費用など、事前に知っておきたい情報が多岐にわたります。この内容を踏まえて、腎機能を守りつつ治療を進める上で押さえておきたいポイントを解説します。
腎臓の構造と機能の基本
腎臓は血液をろ過して老廃物を排出したり、水分や塩分のバランスを調整したりする重要な臓器です。2つの腎臓が連携して全身の環境を安定させる働きを担います。
しかし、腎臓にトラブルが生じると、病状によっては手術を検討する段階に至ることがあります。まずは腎臓の構造や役割を理解することが大切です。
腎臓の形状と仕組み
人の腎臓はソラマメのような形をしており、左右1つずつの合計2つがあります。腎臓の内部には糸球体という血液をろ過する部分や尿細管などがあり、体内の老廃物を尿として排出する働きがあります。
ろ過機能が低下すると体内に老廃物が蓄積し、高血圧などの合併症を招くリスクが高まります。
医療スタッフは症状に応じて、血液検査や尿検査、画像診断を組み合わせて腎機能を評価します。
腎臓に起こりやすい疾患
腎臓は血液を大量にろ過するため、糖尿病や高血圧、動脈硬化など全身的な疾患の影響を受けやすいです。ほかにも腎臓結石や腎腫瘍といった病気があり、それぞれの病状に応じて治療方針が変わります。
慢性腎臓病(CKD)が進行してGFR(糸球体濾過量)が低下すると、透析の可能性が高まります。手術の適応は腎機能を温存できるかどうか、あるいは腫瘍や結石の大きさなどを総合的に考慮して判断します。
腎臓を守る日常の管理
医師は腎臓病の進行を抑制するために、食事療法や生活指導を提案します。塩分やタンパク質の摂取量を管理するだけでなく、血圧コントロールや血糖値の調整、適度な運動なども重視します。
状態が悪化すると手術を要する可能性があるため、早期に腎機能を保つ管理が必要です。
腎臓に対する治療の選択肢
腎臓病の種類や重症度によって、保存的な内科的治療から手術療法、透析や腎移植などの移行が考えられます。腎臓手術を要する場合は、結石除去や腫瘍切除、場合によっては腎臓摘出など治療法は多岐にわたります。
手術内容に応じて術前の検査や術後の管理が変わるため、事前に理解しておくと安心です。
腎臓の働きを理解する上での要点
- 血液をろ過して老廃物を排出する機能を担う
- 塩分や水分を調節して血圧のコントロールにも関与する
- 全身的な疾患の影響を強く受けやすい
腎臓手術が必要となる代表的な病気
手術を行うかどうかの判断は、病気の性質や進行度、患者の状態などに左右されます。腎臓手術には大きく分けて腫瘍や結石を対象としたもの、機能温存を目的としたものがあります。
腎臓手術の種類を知っておくと、治療方針を考える際の理解が深まります。
腎腫瘍
腎臓に発生する腫瘍には良性・悪性があり、大きさや転移の有無によって治療方針が変わります。小さな腫瘍であれば、部分切除や凍結療法など局所的な治療を検討します。悪性の腫瘍が大きい場合は腎臓摘出が必要な可能性があります。
腎結石
腎臓に結石ができると、排尿障害や痛みなどの症状が現れます。結石の大きさや位置によっては体外衝撃波砕石術や内視鏡手術を検討します。
結石が腎盂や尿管に大きく影響している場合、腎臓自体の機能を守るために手術を選択することがあります。
水腎症
腎盂の部分に尿がたまって拡張し、腎機能が低下する状態です。原因としては結石や腫瘍、尿路の狭窄などが考えられます。重度になると腎臓手術による外科的な治療で尿の流れを確保する必要があり、放置すると透析に至るリスクが高まります。
血管性疾患
腎臓を栄養する動脈に狭窄があると、高血圧を引き起こしやすくなります。薬物療法で改善しない場合、バイパス手術や血管拡張術など外科的手術を検討し、腎臓の血流を改善する方法を選びます。
腎臓手術の検討材料
- 腫瘍や結石の大きさと進行度
- 血液検査や画像診断での腎機能評価
- 合併症の有無や全身状態
腎臓手術の種類と方法
腎臓手術は切開の大きさやアプローチ方法によって分類できます。近年は侵襲を抑える方法が増えていますが、病状によっては広範な切開が必要になる場合もあります。
開腹手術
腹部を大きく切開して腎臓を直接視野に入れて行う手術です。腫瘍が大きい場合や複雑な血管処置が必要な場合に選択されます。術中に確認できる範囲が広いため、確実な処置を行いやすいメリットがあります。
医師は開腹手術により、腎臓の状態を直視しながら迅速な対応を取ります。
腹腔鏡手術
小さな穴を数カ所開けてカメラや特殊器具を挿入し、映像をモニターで確認しながら腎臓にアプローチする方法です。開腹手術より体への負担が軽く、術後の回復が早い傾向があります。
医療スタッフは高度な技術を要しますが、患者は傷が小さく術後の痛みも軽減する可能性があります。
ロボット支援手術
ロボットシステムを活用し、遠隔操作で精密な動きを行う手術です。医師がコンソールで操作することで、微妙な角度の調整が可能になります。腹腔鏡手術と同様に傷が小さい利点がありますが、適応となる病状や施設の環境に限りがあります。
部分切除と全摘出
腎臓の腫瘍などを部分的に除去するか、あるいは全体を摘出するかは病変の大きさや位置によって決定します。可能であれば部分切除で残る腎臓機能を温存し、透析のリスクを低減することが理想です。
しかし、大きな腫瘍や重篤な病変がある場合は腎臓摘出手術費用やその後の生活面も考慮し、全摘出を検討せざるを得ないケースもあります。
腎臓手術に関する手技の比較
| 手術の種類 | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 開腹方式 | 腹部を大きく切開 | 広範囲に直接確認しやすい | 体への負担が大きく回復が遅い |
| 腹腔鏡方式 | 小さな穴を通して実施 | 傷が小さく術後の痛みが軽い | 技術を要し適応が限られる |
| ロボット支援 | ロボット操作で精密に実施 | 高い精度が期待できる | 設備のある医療機関に限られる |
腎臓手術入院期間と術後の経過
腎臓手術入院期間は、手術の方法や患者の体力、合併症の有無などに左右されます。開腹手術では長期入院になりやすく、腹腔鏡やロボット支援の手術は比較的短い期間で退院できることがあります。
退院後の経過や通院も踏まえて治療計画を立てることが大切です。
入院前に準備すること
医療チームは入院前に詳細な検査を行い、手術に耐えうる体力や血液状態を確認します。血液検査や心電図、レントゲン検査などを実施し、治療計画を固める流れです。
食事制限や禁煙が必要になる場合があり、術後のリハビリテーションを考慮するためにも、事前準備を十分に行います。
術後の痛みとケア
手術後は創部の痛みや腎機能の変化に注意が必要です。看護師や理学療法士が歩行訓練や創部の管理を行い、患者自身も体力回復を意識して日常動作を少しずつ再開します。退院後は定期的に外来受診し、検査や内服管理を続けます。
退院までの流れ
| 時期 | 主な内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 手術前日 | 最終検査・食事制限 | 不安や疑問は医療スタッフに相談する |
| 手術当日 | 手術施行(全身麻酔など) | 麻酔による合併症リスクを考慮 |
| 手術翌日以降 | 点滴管理、痛みのコントロール、リハビリ開始 | 早期離床を行い合併症のリスクを下げる |
| 退院前 | 創部チェック、日常生活に関する指導 | 運動や食事制限などの方針を確認 |
| 退院 | 外来通院のスケジュール決定 | 術後合併症を防ぐため通院を怠らない |
家庭での過ごし方と注意点
退院後は定期的に診察を受けながら、腎機能に負担をかけない生活を続けることが望ましいです。具体的には塩分制限、適度な運動、定期的な血圧測定を続けます。痛みや違和感が続く場合は早めに病院に相談し、合併症の早期発見に努めます。
術後の生活で意識したいこと
- 塩分摂取を控えて血圧を安定させる
- 水分バランスを保ち尿量をチェックする
- 定期受診で腎機能や創部の状態を確認する
腎臓摘出手術費用やその他の費用負担
腎臓摘出手術費用は、保険の種類や手術方法、病院の施設基準などによって変動します。全摘出だけでなく部分切除の場合でも、手術費用と入院費用を合わせると決して安くはありません。
経済的な負担を把握しておくことで、治療計画をスムーズに進められます。
保険制度と医療費
日本の公的医療保険(国民健康保険や社会保険など)を利用する場合、自己負担は通常3割です。ただし高額療養費制度を活用すれば、一定額以上の自己負担を抑えられます。
収入や年齢によっては自己負担割合が変わる場合もあり、事前に医療ソーシャルワーカーや病院窓口に相談することが大切です。
主な医療費の内訳
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 手術費 | 医師や手術スタッフ、手術室使用料など | 手術時間や方法によって増減 |
| 入院費 | 病室料や看護ケア、食事代など | 大部屋か個室かで費用が変わる |
| 検査費 | 血液検査、画像検査、心電図など多岐にわたる | 術前・術後の回数や範囲によって変動 |
| リハビリ費 | 理学療法士による運動指導など | 退院後にも通院リハビリ費用がかかる場合がある |
| 薬剤費 | 麻酔薬や術後に使用する鎮痛薬、抗菌薬など | 院外処方の際は薬局での負担も考慮 |
個室利用や先進技術への費用
個室を利用する場合、差額ベッド代が加算されます。また、一部の特殊技術やロボット支援手術は保険適用外の場合があり、その分自己負担額が増える可能性があります。
保険制度の適用範囲を事前に確認し、必要に応じて家族や金融機関と相談して支払い計画を立てます。
透析が必要になった場合の費用
腎臓の手術後に十分な腎機能が回復せず、透析を行う必要が生じるケースもあります。透析費用は公的保険の対象ですが、定期的な通院と自己負担が継続するため、金銭面と生活面の両方で計画的な準備が重要です。
費用に関する相談先
- 病院の医療ソーシャルワーカー
- 地域の保健所や自治体
- 民間の医療保険や保険代理店
腎臓手術と透析の関係
腎臓手術を受ける患者の中には、将来透析を要するリスクを抱えているケースがあります。腎臓の機能がどの程度残せるかは手術の方法や病気の進行度によって異なります。
術後の腎臓機能が低下した場合、血液透析や腹膜透析の導入を検討する必要があります。
透析とは
透析は腎臓の代わりに血液をろ過する治療法です。血液透析では体外に血液を取り出して人工腎臓装置で老廃物を除去し、腹膜透析では体内に透析液を入れて腹膜をろ過膜として老廃物を排出します。
腎機能が著しく低下した場合、透析導入で生命維持を図ることが可能ですが、患者の生活リズムや身体的負担が大きく変わるため注意が必要です。
代表的な透析方法の比較
| 透析方法 | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 血液透析 | 週3回程度、病院や透析施設で実施 | 透析液の交換は専門スタッフが行う | 施設に通う必要があり時間的拘束が長い |
| 腹膜透析 | 自宅で透析液を交換する方法 | 自宅で実施できるため外出の制限が少なめ | 感染リスクへの注意や日々の管理が必要 |
腎臓手術後の透析導入リスク
腎臓の部分切除や腎臓摘出などで腎機能が低下すると、残った腎臓で十分なろ過が行えない可能性があります。特に糖尿病や高血圧などの基礎疾患を持つ場合は、術後の腎機能低下が進行しやすいです。
医師は術前から患者の状態を評価し、必要に応じて透析導入のタイミングを見極めます。
透析と生活の両立
透析が始まると、定期的な病院受診や透析機器の管理など、生活の大部分を治療が占めるようになります。仕事や家事との両立は不可能ではありませんが、一定の調整が必要です。
家族の協力や職場の理解、行政サービスの利用など、周囲のサポートを受けながら生活設計を進めることが大切です。
透析中の生活を円滑にする対策
- 定期的なスケジュール管理で透析と仕事を調整する
- 機器の取り扱い方法をしっかり学び感染予防を徹底する
- 血圧や体重、食事内容をこまめにチェックする
腎臓手術後のリハビリと食事管理
腎臓手術を受けた後は、腎機能の安定と合併症予防を念頭に置きながらリハビリテーションを進める必要があります。無理なく回復を目指すために、医療チームと協力して身体機能や食事のコントロールを継続することが重要です。
体力回復を支えるリハビリ
手術翌日から、ベッド上での軽い体操や呼吸訓練などを行い、血流を促します。痛みをこらえながら動くのではなく、医師や理学療法士の指導のもとで無理のない範囲で行うことが大切です。
退院後も散歩や自転車こぎなど、有酸素運動を少しずつ取り入れて筋力低下を防ぎます。
食事療法のポイント
腎臓に負担をかけないよう、塩分やタンパク質の摂取量を調整します。手術後は創部の回復も考慮して、バランスの良い食事を心がけます。栄養士によるカウンセリングを受けながら、自宅でも実践できるレシピを学ぶと継続しやすくなります。
腎臓への負担を抑えたい食事の例
| 食材 | 理由 | 食べ方の工夫 |
|---|---|---|
| 野菜や果物 | ビタミンやミネラルを多く含む | 茹でる・蒸すなどで塩分を控えて摂取 |
| 魚や白身肉 | 良質なたんぱく源として活用しやすい | 高脂質の肉よりも胃腸への負担が少ない |
| 大豆製品 | 植物性タンパクを取り入れやすい | 豆腐や納豆など塩分少なめの製品を選ぶ |
| だしやハーブ類 | 味付けに変化をつけやすい | 醤油や味噌を多用しなくても風味が出せる |
定期的な検査とフォローアップ
リハビリや食事管理を行っていても、腎臓の状態が急変する可能性があるため、定期的に血液検査や尿検査、画像検査などのフォローアップが必要です。医師や看護師が検査結果をチェックし、必要に応じて治療や生活指導の修正を行います。
主なフォローアップ項目
- 血液検査(クレアチニン、尿素窒素など)
- 尿検査(タンパク尿や潜血の有無)
- 超音波検査(腎臓の萎縮や腫瘍の再発有無)
- バイタルサイン(血圧や体重の測定)
腎臓手術の合併症と対処法
腎臓手術では他の外科手術と同様に、出血や感染などのリスクを伴います。さらに腎機能が低下している患者は、全身的な合併症が起こりやすいため、術前・術後の注意が必要です。
問題が発生した場合に迅速に対応することで、重篤化を防ぐことが期待できます。
代表的な合併症
- 出血
手術中や術後の創部からの出血が起きる可能性があります。血管を縫合して止血する処置を行い、必要に応じて輸血を検討します。医師は持病や薬剤の服用歴を確認しながら、術前に止血機能を評価します。 - 感染
開腹手術や腹腔鏡手術では外部から器具を挿入するため、感染リスクが高まります。抗菌薬の投与や創部の清潔管理で対処し、発熱や炎症反応が認められたら直ちに検査を行います。 - 血栓症
手術後は体を動かす機会が減りがちで、下肢静脈に血栓が形成されやすいです。弾性ストッキングの着用やこまめな下肢の運動が予防策になります。 - 腎機能障害
部分切除や全摘出後、残存腎機能が十分でない場合、急激な腎不全に陥るリスクがあります。定期的な血液検査を行い、尿量の変化を注意深く観察します。透析が必要になることも考慮して治療計画を立てます。
術後に注意すべき症状
手術後に高熱や排尿困難、強い痛みが持続した場合は要注意です。医療スタッフは症状の訴えを細かく聞き取り、検査や診察で原因を特定します。早期の発見・治療で回復が早まるため、患者自身も体調の変化に敏感になることが大切です。
合併症が疑われる際の目安
| 症状 | 想定される原因 | 対処の一例 |
|---|---|---|
| 38度以上の発熱 | 創部感染、肺炎、尿路感染など | 抗菌薬投与、創部の再チェック |
| 尿量の急減 | 腎不全、尿路閉塞など | 透析の検討、カテーテルの再確認 |
| 下肢の腫脹や痛み | 深部静脈血栓症 | 血液凝固検査、血栓溶解療法 |
| 創部からの出血 | 血管の不完全な止血 | 再縫合、輸血、圧迫止血など |
早期発見と医療スタッフの連携
合併症を早期に発見して対処するためには、患者の症状報告や看護師の観察、医師の診断など多職種の連携が重要です。入院中だけでなく、退院後も症状や検査データを共有し、速やかに対応できる体制を整えます。
よくある質問
腎臓手術や腎臓手術入院期間、腎臓摘出手術費用などに関して、患者から寄せられる質問は多岐にわたります。代表的なものを以下に示します。疑問点を早めに解消しておくと、安心して治療に臨めるでしょう。
- 腎臓が片方になっても生活に支障はないですか?
-
一般的には、健康な腎臓が1つ残っていれば日常生活を送ることは可能です。しかし、残った腎臓に負担がかかりやすくなるため、定期的な受診や食事制限などを継続する必要があります。
高血圧などの合併症を起こさないよう、生活習慣の見直しが大切です。
- 腎臓手術入院期間はどのくらいかかりますか?
-
手術方式や個々の病状によって異なります。開腹手術では10日前後、腹腔鏡手術やロボット支援手術の場合は1週間程度が目安です。ただし合併症の発生や回復の状況によって入院期間が延びる場合もあります。
主治医は術前の状態を踏まえておおよその日数を提示します。
- 腎臓摘出手術費用は高額になりますか?
-
高額療養費制度を活用すれば、自己負担が一定額に抑えられます。ただし差額ベッド代や先進的な手術機器の費用(保険適用外の場合)が加算されると、負担が増えることがあります。
保険制度や制度の利用可否を病院で相談し、計画的に支払いを考えておくと安心です。
- 腎臓手術後に透析が必要になる可能性はどの程度ですか?
-
あらかじめ腎機能が低下していた場合や、重度の疾患で腎臓を大きく切除した場合は透析リスクが高まります。
部分切除で機能温存を図れれば透析を回避できるケースもありますが、術後の経過や基礎疾患のコントロール次第で必要になる場合があります。定期的な検査と医師の診察で判断します。
以上
参考文献
KIM, Simon P., et al. The relationship of postoperative complications with in‐hospital outcomes and costs after renal surgery for kidney cancer. BJU international, 2013, 111.4: 580-588.
ROSIELLO, Giuseppe, et al. The effect of frailty on post-operative outcomes and health care expenditures in patients treated with partial nephrectomy. European Journal of Surgical Oncology, 2022, 48.8: 1840-1847.
HOBSON, Charles, et al. Cost and mortality associated with postoperative acute kidney injury. Annals of surgery, 2015, 261.6: 1207-1214.
STANG, Andreas; BÜCHEL, Christian. Renal surgery for kidney cancer in Germany 2005–2006: length of stay, risk of postoperative complications and in-hospital death. BMC urology, 2014, 14: 1-8.
UZZO, Robert G., et al. Comparison of direct hospital costs and length of stay for radical nephrectomy versus nephron-sparing surgery in the management of localized renal cell carcinoma. Urology, 1999, 54.6: 994-998.
JEONG, In Gab, et al. Association of robotic-assisted vs laparoscopic radical nephrectomy with perioperative outcomes and health care costs, 2003 to 2015. Jama, 2017, 318.16: 1561-1568.
TAN, Hung-Jui, et al. Patient function and the value of surgical care for kidney cancer. The Journal of urology, 2017, 197.5: 1200-1207.
LARCHER, A., et al. Mortality, morbidity and healthcare expenditures after local tumour ablation or partial nephrectomy for T1A kidney cancer. European Journal of Surgical Oncology (EJSO), 2017, 43.4: 815-822.
OKHAWERE, Kennedy E., et al. Comparison of 1-year health care expenditures and utilization following minimally invasive vs open nephrectomy. JAMA Network Open, 2022, 5.9: e2231885-e2231885.