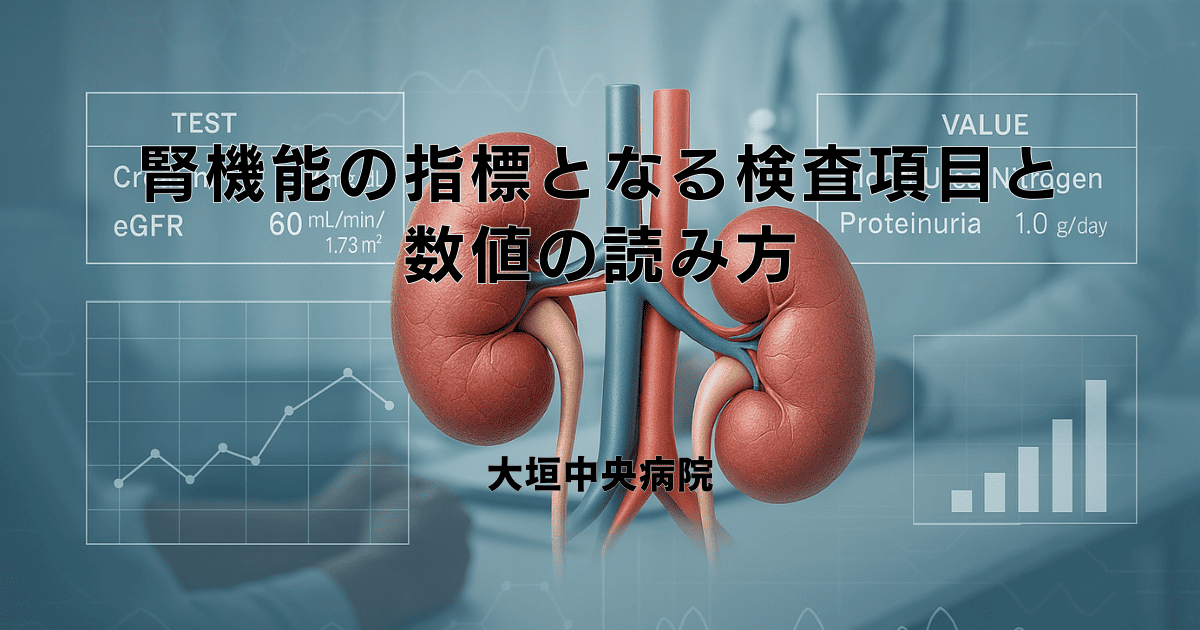腎の働きは生命維持に直結し、血液中の老廃物や余分な水分を排出するうえで重要です。これらの働きを数値化して把握する方法として、いくつかの検査項目が存在します。
腎機能指標を定期的に確認すると、慢性的なトラブルや将来的な透析のリスクにいち早く気づけます。
この記事では、腎の機能指標として代表的な検査と数値の読み方を紹介しながら、腎臓を守るうえで注意したい日常生活の過ごし方や透析を検討する段階などを丁寧に解説します。
腎臓の役割と特徴
腎臓は血液をろ過して老廃物を尿として排出するとともに、身体全体の水分バランスや電解質の調整、ホルモンの産生など多様な役割を担います。そのため、腎臓にトラブルが起こると身体のさまざまな部分に影響が及ぶ可能性があります。
腎機能指標を把握しながら早期に対処することで、慢性腎不全や透析の段階に進みにくくなることが期待されます。
腎臓の働き
腎臓は左右に2つ存在し、腰のあたりに位置しています。体重や体型によって大きさや形には個人差がありますが、基本的には握りこぶし程度の大きさです。
これらの臓器は1日に約150リットルもの血液をろ過し、その過程で老廃物や過剰な水分を尿に変換します。
血圧や電解質の調整にも関与し、骨を強化するホルモン(エリスロポエチンなど)の産生にもかかわるため、全身の健康を維持するために重要です。
腎臓の構造
腎臓は外側の皮質と内側の髄質に大きく分かれています。細かい単位はネフロンと呼ばれ、ろ過機能の中心的役割を果たします。
ネフロンには糸球体やボウマン嚢、近位尿細管、ヘンレ係蹄、遠位尿細管などの構造があり、段階的に血液中の成分をろ過・再吸収して最終的に尿を作り出します。
この仕組みにトラブルが生じると老廃物の排泄がうまくいかず、さまざまな症状が現れます。
腎機能が低下する原因
加齢や生活習慣の乱れだけでなく、糖尿病や高血圧などの基礎疾患によって腎機能が低下するケースが多いです。また、薬剤の副作用や自己免疫の異常など、多岐にわたる原因が存在します。
腎機能指標を定期的に確認して小さな変化を見逃さないことが、透析に至るリスクを抑えるうえでも大切です。
透析への影響
腎臓の機能が著しく落ち込むと、最終的には透析が必要になります。透析では人工的に血液をろ過して老廃物や余分な水分を体外へ排出します。
しかし透析を始める段階になる前に、食事療法や生活習慣の見直し、投薬などで腎機能の悪化を抑える方法があります。腎機能指標を把握しながら早めに対策を行うと、透析導入を遅らせたり防いだりできる可能性があります。
腎に関わる主な特徴
| 項目 | 特徴 |
|---|---|
| 血液ろ過 | 毎日多量の血液をろ過し老廃物や毒素を尿へ |
| 水分調整 | 血液中の水分量を適切に保ちむくみや脱水を防ぐ |
| 電解質調整 | ナトリウム・カリウムなどの濃度を細かく調節し体内バランスを保つ |
| ホルモン産生 | 血圧調整や造血を補助するホルモンを分泌 |
| 酸塩基平衡 | 血液のpHを適正に保ち細胞の働きを正常に維持 |
- 腎機能の低下は全身の健康状態に直結する
- 透析のタイミングに影響を及ぼす
- 生活習慣や基礎疾患の管理で腎機能を保ちやすくなる
腎における機能指標の基本
腎機能指標を示す数値には、血液検査や尿検査など複数のものがあります。目的や状況に応じて選択する検査は異なりますが、それぞれの数値を正しく理解し、変化の傾向をつかむことが腎を守る近道です。
継続的なフォローを受けながら検査を行うことで、症状の進行を予防できる可能性があります。
検査の目的
腎の機能指標を測定する最大の目的は、腎臓の状態を早期に把握して対策を講じることです。腎臓は多少のダメージでは症状が出にくく、かなり進行してから初めて自覚症状が現れる場合も珍しくありません。
定期的に数値を確認しながら、問題があれば医師と相談し治療の方向性を決めます。
検査数値の読み方の基本
検査結果には基準範囲が設定されています。多くの場合、検査結果には「基準値」と「あなたの数値」が併記され、基準値からのズレを元に医師が判断します。
腎機能指標の代表例にはクレアチニン、BUN(血中尿素窒素)、eGFR(推算糸球体ろ過量)などがありますが、それぞれの数値がどのような意味をもつのかを理解する必要があります。
腎機能を調べるタイミング
症状がない段階でも、健康診断や人間ドックでの血液検査・尿検査で腎の機能指標を把握できます。高血圧や糖尿病などのリスク因子をもっている方や、過去に腎疾患の家族歴がある方は、より頻繁に検査を受けることがすすめられています。
早期発見がダメージの蓄積を抑えるために重要です。
生活習慣との関係
高塩分の食事や過度なたんぱく質摂取、アルコールの多飲などは腎臓に負担をかけます。一方で適度な運動や十分な水分補給は腎機能を支えるうえで役立ちます。
腎の機能指標の数値を見ながら、食事や運動などの生活習慣を調整すると、トラブルの進行を遅らせる可能性があります。
腎機能指標を把握する意味
| 意義 | 期待できるメリット |
|---|---|
| 早期発見 | 症状が出る前にダメージを察知し予防策を練りやすい |
| 治療方針の明確化 | 検査結果に応じて薬や食事療法などを計画的に進められる |
| リスクファクターの管理 | 高血圧や糖尿病など他の疾患管理にも好影響が期待される |
| 透析の導入を遅らせる・予防する可能性の向上 | 腎機能に合わせた対応で透析を回避または遅らせるチャンスとなる |
血液検査による腎の機能指標
腎臓の状態を評価する際、血液検査は重要な役割を担います。血中に存在する老廃物の濃度や代謝産物のレベルをチェックして、腎臓が老廃物を排出できているかを推測します。
中でもクレアチニンやBUNは代表的な腎機能指標として幅広く用いられています。
クレアチニン値
筋肉の代謝産物であるクレアチニンは、腎臓でろ過されて尿中へ排出されます。腎機能が低下するとクレアチニン値が上昇しやすいため、腎臓の状態を把握するうえで指標としてよく用いられます。
一般的に男性の基準値は約0.6~1.2mg/dL、女性で約0.4~0.9mg/dLとされることが多いですが、筋肉量などによって個人差があります。
BUN(血中尿素窒素)
BUNは血液中の尿素窒素量を指し、体内のたんぱく質代謝の最終産物です。腎臓が尿素を排出できなくなると血中濃度が高まり、基準値(約8~20mg/dL)を超える場合があります。
ただしBUNはたんぱく質の摂取量や脱水状態などでも変動するため、単独の数値だけで腎機能を判断しないよう注意が必要です。
eGFR(推算糸球体ろ過量)
eGFRはクレアチニン値、年齢、性別などの情報をもとに糸球体ろ過量を推定したものです。腎機能を総合的に把握できるため、慢性腎臓病(CKD)のステージ分類にも活用されています。
eGFRが60mL/分/1.73㎡未満になると腎機能低下のリスクが高いとみなされ、30未満になると重度の腎不全が疑われます。
血中カリウムやリン
腎臓が果たす機能の中には電解質のバランス調整も含まれます。カリウムやリンのレベルが高まると心臓や骨などへの負担が増大する可能性があります。透析の対象となる方では、血中カリウムの値が高くなるケースが多くみられます。
腎の機能指標となる血液検査
| 検査項目 | 基準値目安(成人) | 特徴 |
|---|---|---|
| クレアチニン | 男性:0.6~1.2mg/dL女性:0.4~0.9mg/dL | 腎臓のろ過機能を比較的反映しやすい |
| BUN | 8~20mg/dL | たんぱく質摂取や水分量の影響を受けやすい |
| eGFR | 90~60:正常~やや低下60~30:中等度低下30~15:高度低下15未満:末期腎不全 | CKDのステージ分けに活用 |
| カリウム | 3.5~5.0mEq/L | 心筋への影響が大きく腎不全で上昇しやすい |
| リン | 2.5~4.5mg/dL | 骨や歯の健康に影響し腎不全では上昇傾向 |
- eGFRは腎機能指標として広く用いられる
- BUNは食事内容や水分バランスに左右されやすい
- クレアチニンは筋肉量の多い人でやや高めに出やすい
尿検査による腎機能指標
血液検査に加え、尿検査も腎の状態を評価するうえで大切です。腎臓で作られた尿には、老廃物やタンパク質、血液成分などが含まれる場合があり、その組成を調べると腎機能のトラブルの有無をある程度推測できます。
尿たんぱく
腎臓の糸球体はタンパク質を血液中に再吸収する仕組みがありますが、損傷や炎症などによりタンパク質が尿中に漏れ出すと尿たんぱく陽性となります。
通常はほとんど含まれないため、尿たんぱく検査で陽性が出たときは腎機能指標の面でも注意が必要です。腎炎や糖尿病性腎症などで頻繁にみられます。
尿潜血
本来は尿中に血液成分が出にくいですが、腎臓や尿路系に炎症・損傷があると赤血球が混じり、尿潜血陽性を示す可能性があります。
石や腫瘍などの他の病気も考えられますが、腎機能低下が背景にあるケースもあるため、要チェック項目といえます。
尿比重と尿量
尿比重は尿の濃さを示す値で、腎臓がどれだけ水分の再吸収を行えているかを推測できます。慢性腎不全が進行している場合、腎臓が十分な濃縮を行えず比重が低い状態が続きます。
また、尿量の減少(乏尿)や増加(多尿)も腎臓のろ過・再吸収機能に異常があるサインかもしれません。
その他の尿検査
尿沈渣を顕微鏡で観察すると、円柱や細胞などの存在が確認できます。尿細管がダメージを受けると円柱(細胞のかたまり)が出やすくなるなど、病変の部位や程度を推測しやすくなります。
尿に現れる腎機能指標
| 検査項目 | 主な確認事項 | 意味合い |
|---|---|---|
| 尿たんぱく | 蛋白質が混在しているか | 糸球体の異常や高血圧・糖尿病性腎症の疑い |
| 尿潜血 | 血液成分が混在しているか | 尿路結石・腎炎・腫瘍など多様な原因を含む可能性 |
| 尿比重 | 尿の濃縮度の程度 | 再吸収能力の評価に有用で腎不全が進行すると低下 |
| 尿沈渣 | 円柱や結晶・細胞などの存在 | 腎・尿路の炎症や損傷の部位を推測しやすい |
- 尿たんぱく陽性は初期の腎障害を示唆する場合がある
- 尿比重が常に低いと腎機能が低下している可能性あり
- 尿潜血は腎だけでなく膀胱や尿管のトラブルのサインにもなる
画像検査と腎機能評価
血液検査や尿検査では得られない情報を補うため、超音波(エコー)検査やCT、MRI、造影検査などの画像診断も行います。腎臓の形状や大きさ、腫瘤の有無などを調べて腎機能の低下につながる構造的異常を確認する狙いがあります。
エコー検査
超音波を使ったエコー検査は身体への負担が少なく、妊娠中の方にも行いやすいのが特徴です。腎臓の大きさや輪郭を把握し、腎結石や腫瘍などが疑われる場合に有用です。
腎機能を評価するうえでは、腎臓の萎縮や腎血流の状態を視覚的に捉えることができます。
CT検査
X線を用いた断層撮影であるCTでは、腎臓の断面構造をより細かく把握します。結石や腫瘍だけでなく、腎臓周囲の血管や他臓器との位置関係も明らかになるため、手術や生検などの方針決定にも役立ちます。
一方で放射線被ばく量がある点は知っておきたい部分です。
MRI検査
強い磁場と電波を使うMRI検査では、放射線被ばくの心配はありません。CTより撮影時間が長く、装置の構造上、閉所感に不安を感じる方もいますが、組織の違いをより明確に映し出しやすい特徴があります。
腎臓の構造だけでなく血流状態を評価するためのMRA(MRアンギオグラフィ)なども存在します。
造影検査の注意点
造影剤を使う場合、腎機能が低下していると造影剤が体外に排出されにくくなり、腎障害が悪化する可能性があります。とくにヨード造影剤などを使用するCT検査や血管造影などでは、医師が腎機能指標を確認して造影を行うか慎重に判断します。
主な画像検査の特徴
| 種類 | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| エコー | 超音波による非侵襲的検査 | 被ばくがなく施行しやすい | 細部の描出力はやや劣る |
| CT | X線を使った断層撮影 | 高い空間分解能で腎臓の詳細を把握できる | 放射線被ばくがある |
| MRI | 強磁場と電波を使い放射線被ばくがない | 軟部組織のコントラストが明瞭 | 時間がかかり閉所感がある |
| 造影検査 | 造影剤を注入して血管や組織の形態を明確に映し出す | 血流や腫瘍の性質を把握しやすい | 腎機能低下時にはリスクが増す |
- 腎機能指標が低いときは造影剤使用に注意を要する
- エコー検査は身体負担が少ないため初期検査として広く活用される
- MRIは細かい組織描出力に優れ対象の病変を精査しやすい
数値が示す段階的な腎機能の変化
慢性腎不全は段階を踏んで進行し、初期にはあまり症状がありません。検査数値の変化を定期的に追うことで、どの段階にあるかを早めに把握できます。
対策を開始するタイミングを逃さないよう、腎の機能指標をベースとしたステージの考え方を活用します。
腎不全の分類
腎不全は急性と慢性に大きく分けられます。急性腎不全は短期間のうちに腎機能が急激に低下する状態で、原因が解消されれば元の状態に回復する可能性があります。
一方で慢性腎不全は数カ月から数年という長期にわたり腎機能が徐々に落ち込む状態です。慢性腎不全はCKD(慢性腎臓病)のステージ分けで管理することが多く、eGFRの値で分類します。
透析を検討する基準
末期腎不全と呼ばれる状態になると、腎臓が老廃物を排出する能力が大幅に下がり、血液中の毒素が蓄積します。
一般的にeGFRが15mL/分/1.73㎡未満になると透析の検討が始まり、さらに悪化して尿量が極端に減少するなどの症状があれば透析導入を考慮します。透析を開始するタイミングは医師と患者さんの話し合いによって決定します。
注意したい合併症
腎機能が落ちて血液中に老廃物が溜まると、以下の合併症が起こりやすいです。
- 高カリウム血症による不整脈リスク
- 血中リン上昇による骨ミネラル代謝異常
- 体液貯留によるむくみや高血圧
- 尿毒症による倦怠感・食欲低下
腎機能指標が下がり始めた時点で、これらのリスクを視野に入れた治療を行うと悪化を緩やかにできます。
定期的なフォローアップの重要性
腎臓病の進行は個人差が大きく、数値の変化も人それぞれです。無症状でも腎機能が低下している場合があるため、定期検査で数値をチェックし続けることが重要です。
主治医との連携のもと、適切なタイミングで投薬や透析の検討を行うことが望ましいです。
CKDステージ分類の目安
| ステージ | eGFR値(mL/分/1.73㎡) | 状態 |
|---|---|---|
| G1 | ≧90 | 正常または高値 |
| G2 | 60~89 | 軽度低下 |
| G3a | 45~59 | 軽度~中等度低下 |
| G3b | 30~44 | 中等度~高度低下 |
| G4 | 15~29 | 高度低下 |
| G5 | <15 | 透析や腎移植などが視野に入る状態 |
- ステージG4~G5は医療的な介入が強く求められる
- 透析導入の基準はeGFRだけでなく症状や合併症も考慮する
- 進行を遅らせるための生活習慣管理が欠かせない
腎の機能指標を維持するための日常生活
腎機能が落ち込む原因の多くは、生活習慣や基礎疾患との関連が大きいです。日々の食事や運動、薬の管理などを意識すると、腎機能指標の悪化ペースを緩やかにできる可能性があります。
透析が必要になる前に実践しておきたい取り組みについて整理します。
食事管理のポイント
塩分やたんぱく質の摂取量を調整することが大切です。過剰な塩分は血圧を上昇させ、腎への負担を強めます。たんぱく質は身体に必要な栄養素ですが、過剰な摂取は老廃物の増加につながり、腎臓が負担を受けるおそれがあります。
医師や管理栄養士と相談しながら、無理のない範囲で制限することが望ましいです。
運動と水分摂取
軽度の有酸素運動やウォーキングなどは全身の血流を促し、腎臓の働きをサポートする可能性があります。ただし激しい運動を急に始めると腎臓だけでなく心肺機能にも負担がかかるため、体調や年齢に応じて調整すると安心です。
また、水分は脱水や尿路結石の予防という面で大切ですが、心不全や腎不全がある場合は過剰摂取にならないよう注意が必要です。
医薬品の使用上の注意
腎臓に負担をかける薬剤には注意します。痛み止めの一部や降圧薬の中には、長期使用で腎機能を低下させるリスクが指摘されるものがあります。主治医の指示を守り、用量・用法を守りつつ、定期検査で腎機能指標を確認してください。
市販薬やサプリメントも自己判断で長期にわたって使用しないよう気をつけましょう。
かかりつけ医の連携
腎臓専門医だけでなく、基礎疾患を管理している内科医やかかりつけ医との連携が必要です。高血圧や糖尿病をコントロールしつつ、腎機能指標を定期的にチェックする体制を整えると安心できます。
小まめに受診し、体調や数値にわずかな変化があったときにも相談しやすい関係を築くことが理想的です。
腎を守る日常の工夫
| 取り組み | 内容 |
|---|---|
| 塩分控えめの食事 | 1日6g未満を目安に塩分をコントロール |
| 適度なたんぱく質 | たんぱく質制限が必要な場合は医師・栄養士の指示を守る |
| 有酸素運動 | ウォーキングや軽いジョギングなど無理のない範囲で実施 |
| 水分バランスの調整 | 脱水と過剰摂取の両面を避けながら適度に摂る |
| 薬剤管理 | 処方薬やサプリの種類と量を定期的に見直す |
- 食事・運動・薬の3つが腎機能指標を維持する基盤となる
- 多職種の協力を得ると安心して日常生活の改善を続けやすい
- 定期検査で実際の数値変化を把握しながら調整すると効果的
よくある質問
- 腎機能指標が少しだけ正常範囲を超えた場合、すぐに透析が必要なのでしょうか?
-
正常範囲をわずかに超えた程度では、ただちに透析を始めるケースは少ないです。むしろ、その段階で生活習慣や食事、薬の使用状況などを見直し、腎機能の維持に努めることが大切です。
ただし、基礎疾患の有無や上昇の速度によっては注意が必要な場合もあるので、定期的に主治医の診察を受けて方針を決めると安心です。
- eGFRが60を下回ったと言われました。食事以外に何を気をつければよいでしょうか?
-
eGFRが60未満になるとCKDステージG2~G3に該当する場合があります。食事制限と合わせて、血圧管理や運動習慣の調整が大切です。
過度のアルコールや喫煙は腎血流を乱す可能性があるため控えめにするなど、総合的な生活習慣の改善を検討するとよいでしょう。
- 血液検査でカリウム値が高いと言われました。どのようなリスクが考えられますか?
-
血中カリウムが高い状態(高カリウム血症)は、心臓への影響が大きく不整脈を招くことがあります。腎機能が低下している場合は余分なカリウムが排出されにくいため、食事や薬でのカリウムコントロールが大切です。
リンやナトリウムのバランスも含めて主治医に相談し、早めに対処すると安心です。
- 腎臓病の検査をなるべく早期に受けたいと考えています。どの検査から始めるのがおすすめですか?
-
初期段階では血液と尿の基本的な検査が有用です。健康診断や人間ドックでもクレアチニン値、BUN、eGFR、尿たんぱくや尿潜血などを調べられます。
異常が見つかった場合は、腎臓専門外来でさらに詳しい検査(画像検査など)を検討すると、腎の機能指標を総合的に把握しやすくなります。
以上
参考文献
GAITONDE, David Y.; COOK, David L.; RIVERA, Ian M. Chronic kidney disease: detection and evaluation. American family physician, 2017, 96.12: 776-783.
LOPEZ-GIACOMAN, Salvador; MADERO, Magdalena. Biomarkers in chronic kidney disease, from kidney function to kidney damage. World journal of nephrology, 2015, 4.1: 57.
ARICI, Mustafa. Clinical assessment of a patient with chronic kidney disease. In: Management of Chronic Kidney Disease: A Clinician’s Guide. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2014. p. 15-28.
FERGUSON, Michael A.; WAIKAR, Sushrut S. Established and emerging markers of kidney function. Clinical chemistry, 2012, 58.4: 680-689.
SNYDER, Susan; PENDERGRAPH, BERNADETTE. Detection and evaluation of chronic kidney disease. American family physician, 2005, 72.9: 1723-1732.
VASSALOTTI, Joseph A.; STEVENS, Lesley A.; LEVEY, Andrew S. Testing for chronic kidney disease: a position statement from the National Kidney Foundation. American journal of kidney diseases, 2007, 50.2: 169-180.
GOWDA, Shivaraj, et al. Markers of renal function tests. North American journal of medical sciences, 2010, 2.4: 170.
BAGSHAW, Sean M.; GIBNEY, R. T. Noel. Conventional markers of kidney function. Critical care medicine, 2008, 36.4: S152-S158.
BOSTOM, Andrew G.; KRONENBERG, Florian; RITZ, Eberhard. Predictive performance of renal function equations for patients with chronic kidney disease and normal serum creatinine levels. Journal of the American Society of Nephrology, 2002, 13.8: 2140-2144.
CHEN, Teresa K.; KNICELY, Daphne H.; GRAMS, Morgan E. Chronic kidney disease diagnosis and management: a review. Jama, 2019, 322.13: 1294-1304.