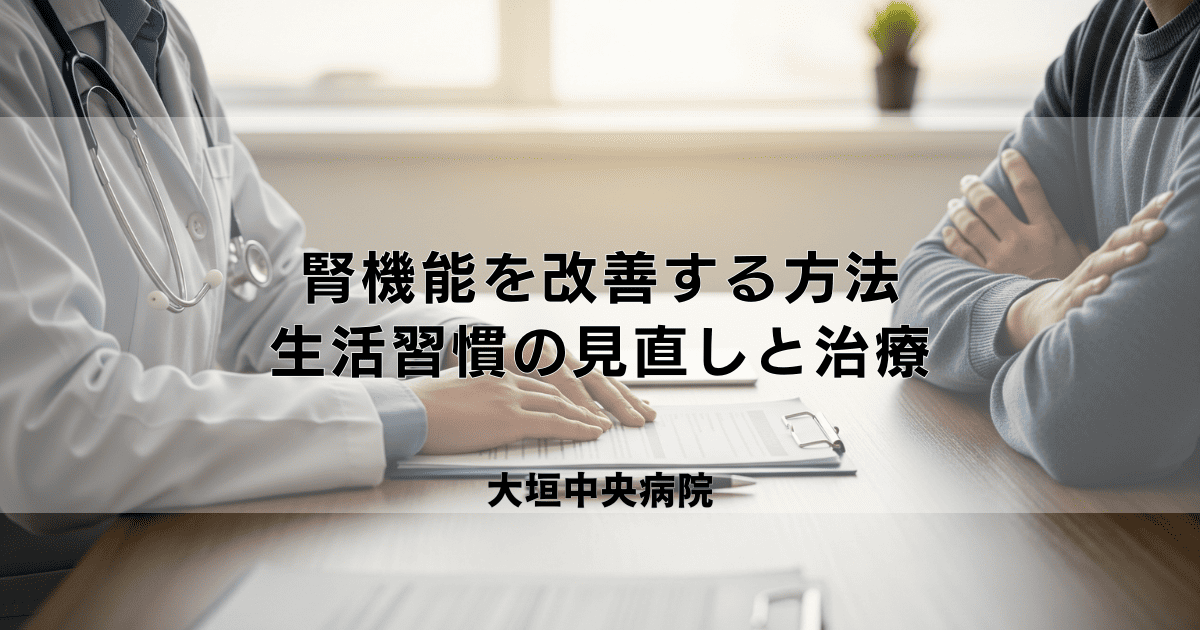健康診断で腎機能の低下を指摘されたり、ご自身の体調の変化から腎臓の健康が気になったりしていませんか。
腎機能は一度低下すると、完全に元通りにすることは難しいと言われていますが、早期に適切な対策を講じることで、機能の低下を緩やかにし、現状を維持することは十分に可能です。
この記事では、腎臓の基本的な働きから、機能が低下する原因、ご自身で気づける体のサイン、腎機能を守るための生活習慣の見直し方や治療法について、詳しく解説します。
腎機能とは?
私たちの体の健康を陰で支える重要な臓器、腎臓。その働きは非常に多岐にわたりますが、具体的にどのような役割を担っているのでしょうか。
腎臓の主な働き
腎臓は、腰のあたりに左右一対ある、そら豆のような形をした臓器で、最もよく知られた働きは、血液をろ過して尿を作り、体内の老廃物や余分な水分を排出することです。
腎臓の役割はそれだけにとどまらず、体内の水分量や電解質(ナトリウム、カリウムなど)のバランスを調整したり、血圧をコントロールするホルモンを分泌したりします。
さらに、赤血球を作るホルモンを生成したり、骨を丈夫に保つビタミンDを活性化させたりと、生命維持に欠かせない多様な機能を担っていて、体を常に健康な状態に保っているのです。
腎臓が担う生命維持活動
| 主な働き | 具体的な内容 |
|---|---|
| 老廃物の排出 | 血液をろ過し、不要な物質を尿として体外へ排出する。 |
| 体液の調整 | 水分やナトリウム、カリウムなどの量を一定に保つ。 |
| 血圧の調整 | 血圧をコントロールするホルモン(レニン)を分泌する。 |
腎機能を表す指標
腎臓がどのくらい働いているかを示す客観的な指標として、血液検査で測定するクレアチニン値と、そこから計算されるeGFR(推算糸球体ろ過量)が用いられます。
クレアチニンは筋肉で使われるたんぱく質の老廃物で、本来は腎臓から尿中へ排出されますが、腎機能が低下すると、血液中にクレアチニンが溜まり、数値が高くなります。
eGFRは、年齢、性別、血清クレアチニン値から、腎臓が1分間にどれくらいの血液をろ過できるかを推算した値で、健康な人のeGFRは90以上ですが、この数値が低いほど腎機能が低下していることを意味します。
定期的な検査で数値の推移を確認することが、腎臓の状態を知る上で非常に重要です。
eGFRによる腎機能のステージ
| ステージ | eGFR (mL/分/1.73m²) | 腎機能の状態 |
|---|---|---|
| G1 | 90以上 | 正常または高値 |
| G2 | 60~89 | 正常または軽度低下 |
| G3a | 45~59 | 軽度~中等度低下 |
| G3b | 30~44 | 中等度~高度低下 |
| G4 | 15~29 | 高度低下 |
| G5 | 15未満 | 末期腎不全 |
慢性腎臓病(CKD)とは何か
慢性腎臓病(CKD: Chronic Kidney Disease)は、腎臓の障害や、eGFRが60未満の状態が3ヶ月以上続く病気の総称です。
初期段階では自覚症状がほとんどないため、静かなる病気とも呼ばれますが、進行すると腎機能が徐々に失われ、最終的には末期腎不全に至り、透析治療や腎移植が必要になることがあります。
また、CKDは心筋梗塞や脳卒中といった心血管疾患の大きな危険因子であることもわかっていて、日本の成人のおよそ8人に1人がCKDと推計されており、誰にとっても無関係な病気ではありません。
早期に発見し、進行を抑えるための対策を始めることが何よりも大切です。
腎機能が低下する主な原因
腎機能は、さまざまな要因によって少しずつ低下していき、特に、私たちの普段の暮らしに深く関わる生活習慣病が、腎臓に大きな負担をかけていることが少なくありません。
どのような原因があるのかを知り、ご自身の生活を見直すきっかけにしましょう。
生活習慣病との深い関わり
腎機能低下の最も大きな原因として挙げられるのが、糖尿病と高血圧で、日本の透析導入原因の第1位と第2位を占めています。
糖尿病では、高血糖の状態が続くことで腎臓の細い血管が傷つき、ろ過機能が損なわれます(糖尿病性腎症)れ、高血圧では、高い圧力が常に血管にかかることで動脈硬化が進行し、腎臓への血流が悪くなることで腎機能が低下します(腎硬化症)。
このほか、脂質異常症や肥満、高尿酸血症(痛風の原因)なども腎臓に負担をかける要因で、生活習慣病をしっかり管理することが、腎臓を守る上で極めて重要です。
腎機能低下につながる主な病気
| 原因となる病気 | 腎臓への影響 |
|---|---|
| 糖尿病 | 高血糖により腎臓内の毛細血管が傷つき、ろ過機能が低下する。 |
| 高血圧 | 高い圧力が血管に負担をかけ、腎臓の動脈硬化を進行させる。 |
| 慢性糸球体腎炎 | 腎臓の糸球体に炎症が起き、ろ過機能が徐々に失われる。 |
加齢による自然な変化
年齢を重ねるとともに、体のさまざまな機能が変化していくのと同様に、腎機能も自然と低下していきます。
一般的に、40歳を過ぎるとeGFRは年に約0.4ずつ低下するといわれていて、これは生理的な老化現象であり、誰にでも起こりうることです。ただし、生活習慣病や喫煙、肥満などの要因が加わると、腎機能の低下速度はさらに加速してしまいます。
加齢による変化自体を止めることはできませんが、腎臓に負担をかける要因を一つでも減らすことで、機能低下のスピードを緩やかにすることは可能です。
その他の原因
生活習慣病や加齢以外にも、腎機能低下を引き起こす原因はあり、腎臓のろ過装置である糸球体に免疫の異常で炎症が起こる慢性糸球体腎炎や、遺伝的な要因で腎臓に多数の嚢胞(のうほう)ができる多発性嚢胞腎などです。
また、一部の薬剤、特に痛み止めとして使われる非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)の長期的な使用が腎臓に負担をかけることもあります。自己判断で薬を長期間服用することは避け、医師や薬剤師に相談することが大切です。
腎機能低下のサインを見逃さないで
腎臓は我慢強い臓器として知られており、機能がかなり低下するまで自覚症状が現れにくいという特徴がありますが、注意深く観察すれば、体からの小さなサインに気づくことができます。
初期症状はほとんどない
腎機能が軽度から中等度に低下している段階(CKDステージG3程度まで)では、ほとんどの場合、自覚症状はありません。多くの人が、健康診断の血液検査や尿検査で異常を指摘されて初めて腎機能の低下に気づきます。
症状がないからといって安心するのではなく、検査結果で「要経過観察」や「要再検査」と判定された場合は、必ず医療機関を受診してください。この段階で対策を始めることが、将来の腎機能悪化を防ぐための鍵となります。
気づきやすい体の変化
腎機能の低下がさらに進行すると、体にさまざまな変化が現れ始め、老廃物や余分な水分が体内に溜まることで、以下のような症状が出ることがあります。
症状は腎機能低下以外の原因でも起こりますが、複数当てはまる場合や、症状が続く場合は注意が必要です。
- むくみ(特に足や顔)
- 貧血(めまい、立ちくらみ、動悸)
- 体のだるさ、疲れやすさ
- 食欲不振
- 夜間の頻尿
特にむくみは、腎臓の水分排出能力が落ちているサインとして比較的気づきやすい症状です。靴下の跡がなかなか消えなかったり、夕方になると足がパンパンになったりする場合は注意しましょう。
また、腎臓は赤血球を作るホルモンを分泌しているため、機能が低下すると貧血になりやすく、階段を上るだけで息が切れるといった症状が現れることもあります。
定期的な健康診断の重要性
自覚症状に頼らずに腎機能の低下を早期に発見するためには、定期的な健康診断が何よりも重要です。年に一度は、血液検査(クレアチニン、eGFR)と尿検査(尿たんぱく)を受けましょう。
尿たんぱくは、腎臓が傷ついていることを示す早期のサインで、本来、血液中のたんぱく質は腎臓でろ過される際に尿中にはほとんど漏れ出しませんが、腎臓に障害があると尿中にたんぱく質が漏れ出てきます。
検査で異常が見つかった場合は、症状がなくても必ず医療機関を受診し、詳しい検査を受けてください。
腎機能改善に向けた生活習慣の見直し【食事編】
腎機能を守り、低下の進行を緩やかにするためには、食事療法が非常に重要な役割を果たします。腎臓に負担をかけない食事の基本は、塩分、たんぱく質、カリウム、リンの摂取量を管理することです。
塩分を控えることの重要性
腎機能が低下している場合、まず最初に取り組むべきなのが減塩です。塩分を摂りすぎると、体内に水分が溜まりやすくなり、むくみや高血圧の原因となり、高血圧は腎臓にさらなる負担をかける悪循環を生み出します。
日本人の食事摂取基準では、成人男性で1日7.5g未満、成人女性で6.5g未満が目標とされていますが、高血圧やCKDの治療では、1日6g未満の塩分制限を目指します。加工食品や外食は塩分が多くなりがちなので注意が必要です。
だしや香辛料、香味野菜などを上手に活用して、薄味でも美味しく食べられる工夫をしてみましょう。
塩分を多く含む食品の例
| 食品の分類 | 具体的な食品名 |
|---|---|
| 加工食品 | ハム、ソーセージ、ちくわ、かまぼこ |
| 漬物・佃煮 | 梅干し、漬物、佃煮 |
| 汁物・麺類 | ラーメン、うどんの汁、みそ汁 |
たんぱく質の摂取量を調整する
たんぱく質は体を作る上で重要な栄養素ですが、摂取しすぎると体内で老廃物(尿素窒素など)に分解され、腎臓から排出する際に負担がかかりるため、腎機能の低下が進んだ場合には、たんぱく質の摂取量を制限することがあります。
制限の程度は個々の腎機能の状態によって異なります。自己判断で極端なたんぱく質制限を行うと、筋肉が落ちてしまったり、栄養状態が悪化したりする可能性があるため、必ず医師や管理栄養士の指導のもとで行うことが大切です。
良質なたんぱく質を含む食品を、適切な量だけ摂ることを心がけましょう。
たんぱく質を多く含む食品
- 肉類
- 魚介類
- 卵・乳製品
- 大豆製品
カリウムやリンの制限が必要な場合
腎機能が低下すると、カリウムやリンといったミネラルを尿中にうまく排出できなくなり、血液中に溜まりやすくなります。血中のカリウム濃度が高くなりすぎると、不整脈など心臓に重大な影響を及ぼすことがあります。
また、リンが増えすぎると、骨がもろくなったり、血管の石灰化を進めて動脈硬化の原因になったりします。カリウムは生の野菜や果物、いも類に多く含まれ、リンは、たんぱく質の多い食品や、加工食品、乳製品に多く含まれています。
制限が必要かどうかも腎機能の状態によりますので、医師の指示に従い、管理栄養士から具体的な食品の選び方や調理法について指導を受けることが重要です。
カリウムを多く含む食品の例
| 食品の分類 | 具体的な食品名 |
|---|---|
| 野菜 | ほうれん草、かぼちゃ、アボカド |
| 果物 | バナナ、メロン、キウイフルーツ |
| いも類 | さつまいも、じゃがいも、里芋 |
エネルギーをしっかり確保する
食事制限を行う上で忘れてはならないのが、十分なエネルギーを確保することで、たんぱく質などを制限すると、食事全体の量が減り、エネルギー不足に陥りがちです。
エネルギーが不足すると、体は不足分を補うために自身の筋肉を分解してエネルギー源として使おうとし、筋肉の分解によって老廃物が発生し、かえって腎臓に負担をかけてしまいます。
エネルギーを確保するためには、ごはんやパン、麺類などの炭水化物や、油や砂糖を上手に利用することが大切です。食事療法は、単に何かを減らすだけでなく、体に必要なエネルギーをきちんと摂るという視点も忘れないようにしましょう。
腎機能改善に向けた生活習慣の見直し【運動・その他編】
食事と同様に、日々の生活習慣を見直すことも腎臓を守るためには欠かせません。適度な運動や禁煙、ストレス管理など、今日から始められる取り組みが、腎機能の低下を防ぐ力になります。
適度な運動を取り入れる
適度な運動は、肥満の解消、血圧や血糖値の改善、心肺機能の向上など、さまざまな良い効果をもたらし、腎臓への負担を軽減します。激しい運動は必要ありません。
ウォーキングや軽いジョギング、サイクリング、水泳など、体に大きな負担がかからない有酸素運動を、無理のない範囲で継続することが大切で、1回30分程度の運動を週に3~5日行うのが目安です。
運動を始める前には、現在の体の状態について医師に相談し、どの程度の運動が適切かアドバイスをもらうと良いでしょう。楽しみながら続けられる運動を見つけることが、長続きの秘訣です。
日常生活に取り入れやすい運動
- ウォーキング
- 軽いジョギング
- サイクリング
- ラジオ体操
- 水中ウォーキング
禁煙と節酒を心がける
喫煙は、血管を収縮させて血圧を上昇させ動脈硬化を促進するため、腎臓の血流を悪化させる大きな要因で、腎機能の低下速度を速めることが多くの研究で明らかになっており、腎臓を守るためには禁煙が必須です。
また、過度な飲酒も血圧を上昇させたり、他の生活習慣病のリスクを高めたりするため、腎臓に良い影響はないので、飲酒は適量を守ってください。厚生労働省が示す節度ある適度な飲酒量は、1日平均純アルコールで20g程度とされています。
休肝日を設けるなど、お酒との付き合い方を見直しましょう。
十分な睡眠とストレス管理
十分な睡眠をとることは、体の修復やホルモンバランスの調整に重要で、睡眠不足は血圧の上昇や血糖値の乱れにつながり、間接的に腎臓に負担をかけることがあります。
質の良い睡眠を確保するために、寝室の環境を整えたり、就寝前のスマートフォン操作を控えたりする工夫が有効です。また、精神的なストレスも血圧を上昇させる要因になります。
趣味の時間を持つ、リラックスできる音楽を聴く、親しい人と話すなど、自分に合った方法で上手にストレスを発散させることも、体の健康維持には大事です。
睡眠の質を高めるための工夫
| 工夫のポイント | 具体的な行動例 |
|---|---|
| 生活リズムを整える | 毎日同じ時間に起き、同じ時間に寝る。 |
| 就寝前の過ごし方 | スマートフォンやパソコンの強い光を避ける。 |
| 快適な寝室環境 | 自分に合った寝具を選び、部屋を暗く静かにする。 |
市販薬やサプリメントの注意点
頭痛や生理痛などで、市販の痛み止めを常用している方もいるかもしれませんが、一部の痛み止め(非ステロイド性抗炎症薬:NSAIDs)は、長期間または大量に服用すると腎臓の血流を低下させ、腎機能に悪影響を及ぼす可能性があります。
また、健康のために良かれと思って摂取しているサプリメントの中にも、腎臓に負担をかける成分が含まれている場合があります。
市販薬やサプリメントを利用する際は、自己判断で安易に手を出すのではなく、必ず医師や薬剤師に相談し、腎臓への影響を確認してから使用してください。
注意が必要な市販薬の成分
- 非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)
- 一部の漢方薬
医療機関で行われる治療法
生活習慣の改善に加えて、医療機関では腎機能の低下を抑えるための専門的な治療を行います。
原因となっている病気の管理から、薬物療法、そして腎機能が著しく低下した場合の腎代替療法まで、病気の進行度に応じてさまざまな治療法が選択されます。
原因疾患の治療
腎機能低下の背景に糖尿病や高血圧、慢性糸球体腎炎などの病気がある場合、その原因となっている病気の治療が最も重要になります。
糖尿病が原因であれば、食事療法や運動療法、薬物療法によって血糖値を良好な状態にコントロールすることが、腎症の進行を抑える鍵です。
高血圧が原因であれば、減塩に加えて降圧薬を用いて、目標とする血圧値を維持することが腎臓の保護につながります。原因疾患をしっかりと治療することが、腎機能の悪化を防ぐための基本です。
薬物療法による腎臓の保護
原因疾患の治療と並行して、腎臓そのものを保護し、機能低下の進行を遅らせるための薬物療法も行い、代表的なものは、アンジオテンシン変換酵素(ACE)阻害薬やアンジオテンシンII受容体拮抗薬(ARB)といった種類の降圧薬です。
これらの薬は血圧を下げる効果に加えて、腎臓の血管への負担を軽減し、尿たんぱくを減らすことで腎臓を保護する作用も持っています。
最近では、SGLT2阻害薬という種類の糖尿病治療薬にも、血糖値の改善とは別の働きで腎臓を保護する効果があることが分かり、糖尿病のないCKD患者さんにも使用されるようになっています。
その他、必要に応じて、老廃物を吸着して排出を助ける薬や、貧血を改善する薬、ミネラルバランスを整える薬などが使われます。
腎代替療法(透析、腎移植)
残念ながら腎機能の低下が進行し、末期腎不全(eGFRが15未満)に至った場合、自分の腎臓だけでは生命を維持できなくなり、その際、失われた腎臓の働きを代替するのが腎代替療法です。
腎代替療法には、血液透析、腹膜透析、腎移植の3つの選択肢があります。
血液透析は、週に2~3回医療機関に通い、機械を使って血液中の老廃物や余分な水分を取り除く方法で、腹膜透析は、自宅で自分のお腹に埋め込んだカテーテルを使って透析液を出し入れする方法です。
腎移植は、ドナーから提供された腎臓を移植する手術で、最も根本的な治療法です。どの治療法を選択するかは、体の状態やライフスタイルなどを考慮し、医師と十分に相談して決定します。
腎代替療法の種類と概要
| 治療法の種類 | 概要 |
|---|---|
| 血液透析 | 医療機関で機械を使い、血液を浄化する方法。 |
| 腹膜透析 | 自宅などで、自分のお腹の膜(腹膜)を利用して透析を行う方法。 |
| 腎移植 | 親族などから、あるいは亡くなった方から腎臓の提供を受けて移植する手術。 |
よくある質問
最後に、腎機能に関して多くの方が抱く疑問についてお答えします。
- 一度低下した腎機能は元に戻りますか?
-
急激に腎機能が悪化する急性腎障害の場合は、原因を取り除くことで機能が回復する可能性があります。
数ヶ月から数年にわたってゆっくりと腎機能が低下していく慢性腎臓病(CKD)の場合、残念ながら失われた腎機能を完全に元通りに回復させることは現在の医療では困難です。だからといって諦める必要はまったくありません。
食事療法や運動療法、薬物療法などを適切に行うことで、腎機能がそれ以上低下するスピードを大幅に緩やかにし、透析導入を先延ばしにしたり、避けたりすることは十分に可能で、早期発見と早期治療が何よりも重要です。
- 腎臓に良い特定の食べ物はありますか?
-
よく「これを食べれば腎臓が良くなる」といった情報を見かけることがありますが、特定の食品だけで腎機能が劇的に改善することはありません。
腎臓を守る上で大切なのは、特定の食品を摂ることよりも、食事全体のバランスを整えることで、特に、塩分を控えることは、どのステージのCKDにおいても基本です。
その上で、ご自身の腎機能の状態に合わせて、たんぱく質やカリウム、リンなどの摂取量を調整していくことが求められます。
健康食品やサプリメントの中には、かえって腎臓に負担をかけるものもあるため、利用する前には必ず主治医に相談してください。
- どのくらいの頻度で検査を受けるべきですか?
-
必要な検査の頻度は、現在の腎機能の状態や原因となっている病気によって異なります。腎機能が正常な方でも、年に1回は健康診断で血液検査と尿検査を受けることが推奨されます。
腎機能の低下を指摘されている場合は、病気の進行度に応じて、3ヶ月に1回や半年に1回など、主治医が指示する頻度で定期的に通院し、検査を受けることが大切です。
定期的な検査によって、腎機能の微妙な変化を捉え、治療方針を適切に調整していくことができます。自己判断で通院を中断しないようにしましょう。
以上
参考文献
Kanauchi N, Saito C, Nagai K, Yamada K, Kai H, Watanabe T, Narita I, Matsuo S, Makino H, Hishida A, Yamagata K. Effective method for life-style modifications focused on dietary sodium intake in chronic kidney disease: sub-analysis of the FROM-J study. BMC nephrology. 2024 Aug 26;25(1):274.
Yamagata K, Makino H, Iseki K, Ito S, Kimura K, Kusano E, Shibata T, Tomita K, Narita I, Nishino T, Fujigaki Y. Effect of behavior modification on outcome in early-to moderate-stage chronic kidney disease: a cluster-randomized trial. PloS one. 2016 Mar 21;11(3):e0151422.
Yamagata K, Makino H, Akizawa T, Iseki K, Itoh S, Kimura K, Koya D, Narita I, Mitarai T, Miyazaki M, Tsubakihara Y. Design and methods of a strategic outcome study for chronic kidney disease: Frontier of Renal Outcome Modifications in Japan. Clinical and experimental nephrology. 2010 Apr;14(2):144-51.
Takeuchi H, Uchida HA, Katayama K, Matsuoka-Uchiyama N, Okamoto S, Onishi Y, Okuyama Y, Umebayashi R, Miyaji K, Kai A, Matsumoto I. The Beneficial Effect of Personalized Lifestyle Intervention in Chronic Kidney Disease Follow-Up Project for National Health Insurance Specific Health Checkup: A Five-Year Community-Based Cohort Study. Medicina. 2022 Oct 26;58(11):1529.
Imai E, Yamagata K, Iseki K, Iso H, Horio M, Mkino H, Hishida A, Matsuo S. Kidney disease screening program in Japan: history, outcome, and perspectives. Clinical journal of the American Society of Nephrology. 2007 Nov 1;2(6):1360-6.
Iseki K. Nutrition and quality of life in chronic kidney disease patients: a practical approach for salt restriction. Kidney research and clinical practice. 2022 Jan 21;41(6):657.
Kimura H, Asahi K, Tanaka K, Iseki K, Moriyama T, Yamagata K, Tsuruya K, Fujimoto S, Narita I, Konta T, Kondo M. Health-related behavioral changes and incidence of chronic kidney disease: The Japan Specific Health Checkups (J-SHC) Study. Scientific Reports. 2022 Sep 29;12(1):16319.
Imai E, Horio M, Nitta K, Yamagata K, Iseki K, Tsukamoto Y, Ito S, Makino H, Hishida A, Matsuo S. Modification of the modification of diet in renal disease (MDRD) study equation for Japan. American Journal of Kidney Diseases. 2007 Dec 1;50(6):927-37.
Abe M, Hatta T, Imamura Y, Sakurada T, Kaname S. Effectiveness and current status of multidisciplinary care for patients with chronic kidney disease in Japan: a nationwide multicenter cohort study. Clinical and Experimental Nephrology. 2023 Jun;27(6):528-41.
Toyama K, Sugiyama S, Oka H, Sumida H, Ogawa H. Exercise therapy correlates with improving renal function through modifying lipid metabolism in patients with cardiovascular disease and chronic kidney disease. Journal of cardiology. 2010 Sep 1;56(2):142-6.