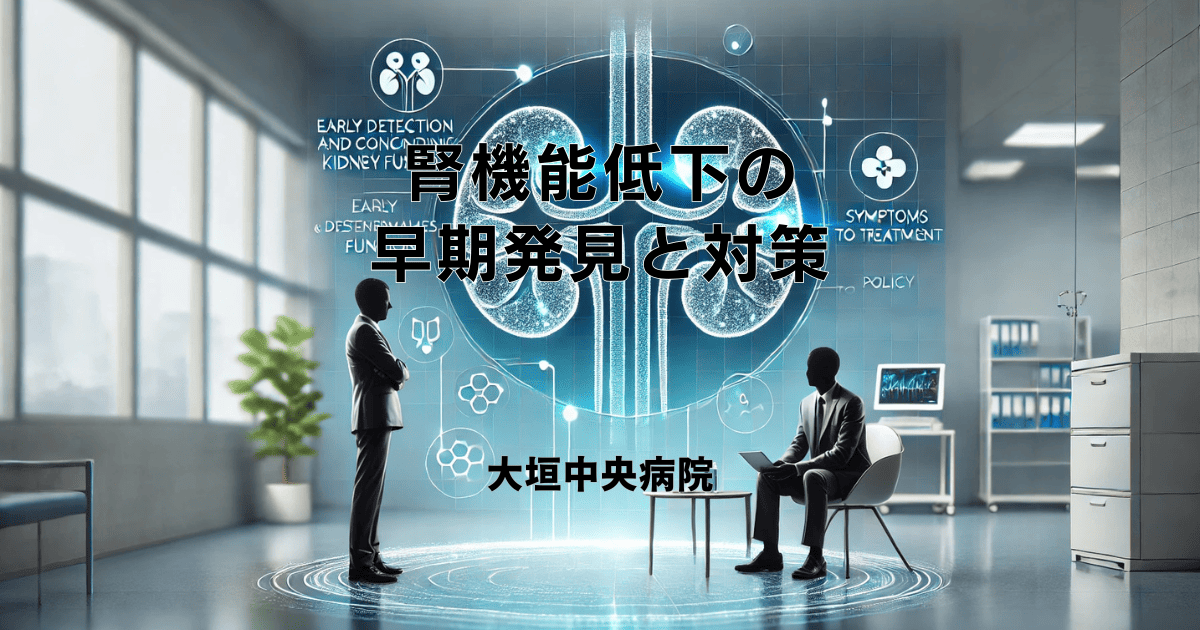腎臓は血液から老廃物を取り除き、水分や電解質のバランスを調整する重要な役割を担います。何らかの要因で腎機能が低下すると、身体の状態全体に大きく影響を及ぼします。
軽度の段階では目立った異常を感じない場合もありますが、放置すると腎障害症状が進行し、重度になると透析が必要になるケースもあります。
本記事では腎機能低下の基本的なメカニズムから腎機能低下症状や腎機能悪化症状の特徴、検査方法や治療の選択肢までを、総合病院の視点からわかりやすく解説いたします。
腎機能と腎機能低下の概要
腎臓は体内の老廃物処理に大きく関わっています。多くの方は、腎臓の不調を具体的に意識する機会が少ないため、腎機能がどのように働いているかを再確認してみましょう。
腎臓の基本的な役割
腎臓は後腹膜腔と呼ばれる背中側の体腔に左右1対存在し、以下のような働きを担っています。
- 血液中の老廃物をろ過し、尿として体外に排出する
- 体内の水分量や電解質(ナトリウム、カリウムなど)のバランスを調整する
- 血圧や貧血に関連するホルモンを産生・調整する
このように、腎臓は身体の恒常性を支える臓器の1つです。腎機能が低下すると、老廃物が排出されにくくなり、体内の電解質バランスや血圧のコントロールにも支障を来たします。
腎機能低下とは
腎機能が低下するとは、ろ過機能や調節機能が通常より弱まっている状態を指します。血液検査でクレアチニン濃度が高まったり、推算糸球体濾過量(eGFR)が低下したりすることで診断します。
eGFRは腎臓がどの程度血液をろ過できているかを表す指標です。
腎機能低下は徐々に進行する場合が多く、初期段階では自覚しにくいのが特徴です。しかし、放置すると腎機能悪化症状が顕著化し、最終的には透析治療や移植を検討しなければならない段階まで進むことがあります。
腎機能低下の原因の多様性
腎機能が低下する原因は多岐にわたります。糖尿病や高血圧のような生活習慣病のほか、慢性腎炎、遺伝性の腎疾患なども要因となります。
また、高齢化による加齢的変化や、腎臓に負担をかける薬の長期使用が関連する場合もあります。
原因を分類した表
| 主な原因 | 具体例 |
|---|---|
| 生活習慣病 | 糖尿病、高血圧、高脂血症など |
| 糖尿病性腎症 | 血糖コントロールの不良による腎損傷 |
| 慢性糸球体腎炎 | 免疫異常や感染症が関連 |
| 遺伝性腎疾患 | 多発性嚢胞腎など |
| 加齢や薬剤の影響 | 長期的な薬剤使用や老化による腎機能低下 |
原因を把握することは治療方針を立てるうえで重要です。単一の要因だけでなく、複数の因子が重なり合って進行するケースもあります。
腎機能低下症状の特徴
腎機能低下症状は進行度合いによって異なります。初期段階ではほとんど自覚症状がないため、腎機能悪化症状を見過ごしてしまいがちです。
初期段階での腎機能低下症状
初期の腎機能低下症状は非常にあいまいです。例えば、むくみや疲労感、血圧の上昇などが挙げられます。ただし、これらはほかの疾患にもみられる一般的な症状なので、腎機能の異常を連想しにくいかもしれません。
腎機能悪化症状の現れ方
腎機能がさらに悪化すると、以下のような症状が徐々に明確化します。
- 尿量の減少(ときには増加)
- 尿に泡立ちが見られる
- 倦怠感や体力低下
- 食欲不振や吐き気
- 皮膚のかゆみ
これらの腎機能悪化症状は身体に蓄積した老廃物や水分バランスの乱れが直接原因となって発生します。特に、尿に泡立ちが見られる場合はタンパク質が尿中に漏れている可能性があり、腎臓に問題があるサインかもしれません。
腎障害症状の進行パターン
腎障害症状が中期から後期に進むと、自力で老廃物や余分な水分を排出することがさらに難しくなります。高血圧のコントロールが難しくなり、心臓や血管にも負担がかかります。
さらには、貧血や骨の異常、全身の浮腫などが顕著化し、日常生活への支障も増します。
腎障害症状の主な進行度合いを示す表
| 進行段階 | 自覚症状の特徴 | 対応の必要性 |
|---|---|---|
| 初期 | むくみ、軽い倦怠感 | 定期的な検査が重要 |
| 中期 | 尿異常、血圧上昇、貧血など | 食事管理や薬物療法を検討 |
| 後期 | 尿量の大幅変化、重度の倦怠感、皮膚症状など | 透析や腎移植などを視野に入れる |
腎障害症状は一度進行すると元の状態に戻すのが難しいケースが多いです。だからこそ、早期発見と対策が大切です。
腎機能低下を早期に見つけるための検査
腎機能が低下しているかどうかは、血液検査や尿検査を通じて比較的簡単に確認できます。定期健診で異常を指摘された場合や、症状を感じる場合は、早めに医療機関を受診するとよいでしょう。
血液検査のポイント
血液検査では主にクレアチニンや尿素窒素(BUN)を測定し、推算糸球体濾過量(eGFR)を算出します。クレアチニンは筋肉活動によって生じる老廃物で、腎臓でろ過される指標です。この値が高いほど腎機能の低下が疑われます。
血液検査で注目する主な指標の表
| 指標 | 意味 | 注意点 |
|---|---|---|
| クレアチニン | 筋肉から生じる老廃物 | 筋肉量が多い方では上昇しやすい |
| 尿素窒素(BUN) | タンパク質代謝の最終産物 | 食事内容によって変動しやすい |
| eGFR | 腎臓のろ過機能を示す推算値 | 年齢や性別によって基準が異なる |
| カリウム | 高値だと心臓に負担がかかる可能性がある | 腎機能が低下すると排出しにくくなる |
定期的に血液検査を行うことで、自覚症状が出る前から腎機能の低下を把握できる可能性があります。
尿検査の活用
尿検査では、尿蛋白や尿潜血、尿中のアルブミンなどを調べます。尿に含まれる成分から、腎臓のろ過機能の状態を推察できます。尿蛋白が陽性の場合、糸球体や尿細管に障害があることを示唆します。
また、糖尿病が原因となる糖尿性腎症では、微量アルブミン尿の段階から腎機能低下症状が始まっていることが少なくありません。
画像診断による評価
超音波検査(エコー)やCT、MRIなどを活用することで、腎臓の大きさや形態、血流を視覚的に確認できます。腎結石や腫瘍、先天性の形態異常などが腎機能の低下に関与していないかどうかを判断する際に有用です。
生活習慣のヒアリングの役割
検査だけでなく、患者様が日常的にどのような生活習慣を送っているかを確認することも重要です。飲酒量や喫煙習慣、食塩や蛋白質の摂取量、運動の有無などを総合的に把握することで、腎機能悪化症状のリスクを推定しやすくなります。
とくに高血圧や糖尿病、肥満などがある方は、腎障害症状が進行する可能性が高まるため、早期発見に向けた検査を積極的に受けることが望ましいです。
腎機能低下の主な治療方針
腎機能低下に対しては、原因や重症度に応じてさまざまな治療方針が考えられます。血液透析を含めた治療法は患者様の状態に合わせて選択します。
食事療法
腎臓への負担を軽減するためには、食事の内容を見直すことが大切です。塩分やタンパク質を制限し、カリウムやリンなどのミネラル摂取量にも注意を払います。
必要に応じて管理栄養士の指導を受けることで、生活の質を保ちながら腎臓に優しい食事を実践しやすくなります。
食事療法の主なポイントをまとめた表
| 食事要素 | 留意すべきポイント |
|---|---|
| 塩分 | 高血圧を招く恐れがあるため控えめにする |
| タンパク質 | 量を制限して腎臓への負担を減らす |
| カリウム | 血中濃度の上昇は心臓に負担 |
| リン | 骨の健康維持に関わるが過剰摂取は要注意 |
| 水分量 | むくみや血圧の変動を抑えるために調整 |
食事療法は自己判断で制限が強くなりすぎると栄養不足になりかねないため、医療者からの適切なアドバイスが重要です。
薬物療法
腎機能の低下を抑える薬としては、血圧をコントロールする降圧薬や、血糖値を調整する糖尿病治療薬などが中心になります。また、腎臓の保護作用が期待される薬も存在します。
腎機能が低下すると薬の代謝や排泄能力が下がるので、用量や種類の選択には慎重さが求められます。
血液透析・腹膜透析
腎臓によるろ過機能が著しく低下した場合、老廃物や余分な水分を体外へ排出するために透析が必要になります。一般的には血液透析を思い浮かべる方が多いですが、自宅などで行う腹膜透析を選択するケースもあります。
患者様のライフスタイルや合併症の有無を踏まえ、どの透析方法が適しているか判断していきます。
腎移植
腎臓の機能が著しく低下し、薬物療法や透析で対応が難しくなった場合、腎移植という選択肢があります。
ドナーから提供された腎臓を移植し、体内で腎機能を代替させますが、手術の適応や術後の免疫抑制薬など、総合的な検討が必要となります。
透析が必要になる前に考える対策
腎機能低下症状が軽度の段階で気をつけるべきポイントを押さえれば、透析開始を遅らせたり回避したりできる可能性があります。
塩分とタンパク質の制限
高血圧と腎機能の悪化には密接な関係があります。塩分を多く摂取すると血圧が上がりやすく、腎機能低下が進む恐れがあります。
さらに、過剰なタンパク質摂取は尿蛋白の増加や腎臓への負担を大きくするため、適切な量を保つことが大切です。
適切な水分摂取
水分を過度に制限しすぎると脱水になりやすく、腎臓の血流が減少してかえって機能を落とす原因になります。一方で、過剰に摂りすぎるとむくみや血圧上昇を招きます。体重や合併症、季節などを考慮しながら、適度な水分摂取を心がけましょう。
血圧・血糖の管理
高血圧や糖尿病がある方では、腎機能悪化症状を引き起こすリスクが高まります。血圧と血糖値を目標範囲内にコントロールすることで、腎機能をできるだけ維持しやすくなります。
必要に応じて薬を用いつつ、生活習慣も総合的に見直していきましょう。
血圧・血糖管理に関わる要素を整理した表
| 管理要素 | 注意点 |
|---|---|
| 血圧 | 塩分制限や適度な運動、降圧薬の適切な使用 |
| 血糖 | カロリーコントロール、糖質の種類に気を配る |
| 日常の体重測定 | 体重変動が大きい場合は水分バランスに留意 |
| 定期受診 | 数値の変化に応じて治療方針を微調整するための機会 |
血圧と血糖のコントロールが難しい場合、医師や専門スタッフと相談して薬物治療や食事指導を適切に組み合わせることが望ましいです。
定期的な通院と検査
腎機能低下症状をいち早く見つけるためには、定期的な通院と検査が重要です。特に生活習慣病がある方や腎臓に負担をかける薬を長期間使用している方は、医療機関で定期的に腎機能のチェックを行いましょう。
- 血液検査(クレアチニン、BUN、eGFRなど)
- 尿検査(蛋白尿、潜血、アルブミン尿など)
- 血圧測定や血糖値の確認
これらを定期的に行うことで、腎機能悪化症状を早めに捉えて治療や生活習慣の見直しが進めやすくなります。
生活習慣が与える影響
腎機能低下を防ぐためには、日々の生活習慣の改善が大切です。特に食生活や運動、喫煙・飲酒の習慣を見直すことが肝心です。
食事バランスの見直し
栄養バランスの偏りは腎機能低下のリスクを高めます。カロリーや塩分、タンパク質だけでなく、ビタミンやミネラルの摂取も考慮してください。
主食・主菜・副菜をバランスよく配置した献立を心がけると腎臓への負担を軽減しやすくなります。
バランスを考えた献立例を示す表
| 献立例 | 内容 |
|---|---|
| 朝食 | ごはん、焼き魚、野菜の味噌汁、果物 |
| 昼食 | 雑穀米のおにぎり、鶏肉のサラダ、牛乳 |
| 夕食 | 玄米、魚の煮付け、野菜炒め、海藻の酢の物 |
| 間食 | ナッツ類やヨーグルトなど |
過度な制限ではなく、腎機能や体調に合わせた調整がポイントです。
運動の導入
定期的な運動は血圧や体重のコントロールに役立ち、腎機能低下の進行を遅らせる可能性があります。ただし、負荷が高すぎる運動は逆に血圧上昇や脱水を引き起こす恐れがあるので、医師に相談しながら無理のない範囲で取り組むことが大切です。
ウォーキングや軽い筋力トレーニング、ストレッチなどが継続しやすい例として挙げられます。
アルコールと喫煙の制限
アルコールの過剰摂取は血圧を上昇させ、利尿作用による脱水を引き起こす可能性があるため、腎臓に負担をかけます。また、喫煙は血管にダメージを与え、腎臓への血流を低下させる一因となります。
腎機能を守るためにはアルコールと喫煙の制限も重要です。
睡眠習慣の調整
睡眠不足や不規則な睡眠習慣はホルモンバランスを乱し、高血圧や糖尿病のリスクを高めます。その結果、腎臓にも悪影響が及びやすくなります。夜更かしを避け、質の高い睡眠を確保することが腎機能悪化症状の予防につながります。
- 規則正しい睡眠時間の確保
- 寝る前のスマートフォン使用の制限
- 就寝前の軽いストレッチやリラックス法
これらを取り入れると睡眠の質が上がり、生活習慣病のリスクを抑えやすくなります。
当院での腎機能低下への包括的なアプローチ
総合病院として、多職種が連携して腎機能低下の治療や透析導入前のケアに取り組んでいます。一人ひとりの患者様に合わせたプランを提案し、安心して治療を続けられるよう支援します。
チーム医療の強み
当院では医師、看護師、管理栄養士、薬剤師などが連携したチーム医療を展開しています。腎機能低下の原因が多岐にわたるため、各専門分野の視点を持ち寄り、総合的な対策を立案しやすい体制を整えています。
チーム医療における主な専門職と役割を示す表
| 専門職 | 主な役割 |
|---|---|
| 医師 | 診断や治療方針の立案、薬剤選択 |
| 看護師 | 日常生活の支援や症状の観察 |
| 管理栄養士 | 食事療法の提案と指導 |
| 薬剤師 | 薬物療法の適切な服薬指導、薬剤調整 |
| ソーシャルワーカー | 生活背景の把握とサポートの調整 |
各職種が連携して定期的にカンファレンスを行い、患者様の状態や希望を確認しながら治療計画を見直す体制を取っています。
透析の準備とサポート
腎障害症状が進み、透析が必要になった方に対しては、血液透析や腹膜透析のメリット・デメリットを丁寧に説明し、患者様のライフスタイルに合った方法を一緒に検討します。
透析導入後も定期的に状態をチェックし、合併症予防や生活の質を向上させるためのサポートを実施します。
合併症管理
腎機能低下は高血圧や心不全、貧血、骨粗しょう症など、多くの合併症と関連します。当院では各科の医師や専門スタッフが連携し、合併症を包括的に管理するよう努めています。
腎臓だけでなく、全身の健康状態を考慮しながら治療を進めることで、よりよい予後を目指します。
受診の流れ
腎機能低下が疑われる方は、まずは当院の内科(もしくは腎臓内科)を受診していただきます。必要に応じて血液検査や尿検査、画像診断を行い、状態を評価します。
その結果をもとに食事指導や薬物療法、場合によっては透析の検討へと進みます。入院が必要な場合も、ほかの科との連携によってスムーズに治療に移行できます。
- 内科外来の受診
- 血液・尿検査や画像検査
- 結果説明と治療方針の検討
- 専門家による栄養指導や薬剤調整
- 必要に応じて透析の導入や入院治療
患者様の症状やライフスタイルを尊重しながら、最善の治療やケアを一緒に考えていきます。
Q&A
腎機能低下に関して多く寄せられる質問と、そのポイントを挙げます。透析に対する不安や、腎機能低下症状への具体的な対処など、気になる点を解消する一助になれば幸いです。
- 腎機能低下はどのくらいの期間で進行するのですか?
-
進行速度は個人差が大きく、数か月で急激に進む場合もあれば、数年から十数年かけてゆっくり悪化する場合もあります。
高血圧や糖尿病などがある方は進行しやすい傾向がありますが、早期発見と生活習慣の改善により進行を抑えられるケースも珍しくありません。
- 腎機能悪化症状がないのに、検査で異常値が出ました。どうすればよいでしょうか?
-
初期段階は腎機能低下症状がほとんど現れない場合があります。自覚症状がなくても、血液検査や尿検査の結果を踏まえて早めの対策を始めることが大切です。
定期的な通院や食事・運動習慣の見直しで、より重度の腎障害症状への進行を抑えることに努めましょう。
- 透析はいつから始めるべきなのでしょうか?
-
一般的には、eGFRが15mL/分/1.73㎡以下になるなど腎機能が大幅に低下し、日常生活に支障が出るレベルになると透析を検討します。
ただし、患者様の体調や合併症の有無、生活背景によって開始時期は異なるため、主治医との相談が重要です。
- 食事療法だけで透析を回避できるのでしょうか?
-
食事療法は腎臓への負担を軽減するために有用ですが、それだけで透析を完全に回避できるとは限りません。薬物療法や血圧・血糖コントロール、適度な運動などを組み合わせて総合的に対策を行うことが必要です。
継続的な検査で状態を確認し、適切な時期にほかの治療を導入する可能性も考慮してください。
以上
参考文献
ROMAGNANI, Paola, et al. Chronic kidney disease. Nature reviews Disease primers, 2017, 3.1: 1-24.
LEVEY, Andrew S.; CORESH, Josef. Chronic kidney disease. The lancet, 2012, 379.9811: 165-180.
WEBSTER, Angela C., et al. Chronic kidney disease. The lancet, 2017, 389.10075: 1238-1252.
TANGRI, Navdeep, et al. A predictive model for progression of chronic kidney disease to kidney failure. Jama, 2011, 305.15: 1553-1559.
CHEN, Teresa K.; KNICELY, Daphne H.; GRAMS, Morgan E. Chronic kidney disease diagnosis and management: a review. Jama, 2019, 322.13: 1294-1304.
LEVEY, Andrew S., et al. National Kidney Foundation practice guidelines for chronic kidney disease: evaluation, classification, and stratification. Annals of internal medicine, 2003, 139.2: 137-147.
KALANTAR-ZADEH, Kamyar, et al. Chronic kidney disease. The lancet, 2021, 398.10302: 786-802.
RUIZ-ORTEGA, Marta, et al. Targeting the progression of chronic kidney disease. Nature Reviews Nephrology, 2020, 16.5: 269-288.
EL NAHAS, A. Meguid; BELLO, Aminu K. Chronic kidney disease: the global challenge. The lancet, 2005, 365.9456: 331-340.
LEVEY, Andrew S., et al. Definition and classification of chronic kidney disease: a position statement from Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO). Kidney international, 2005, 67.6: 2089-2100.