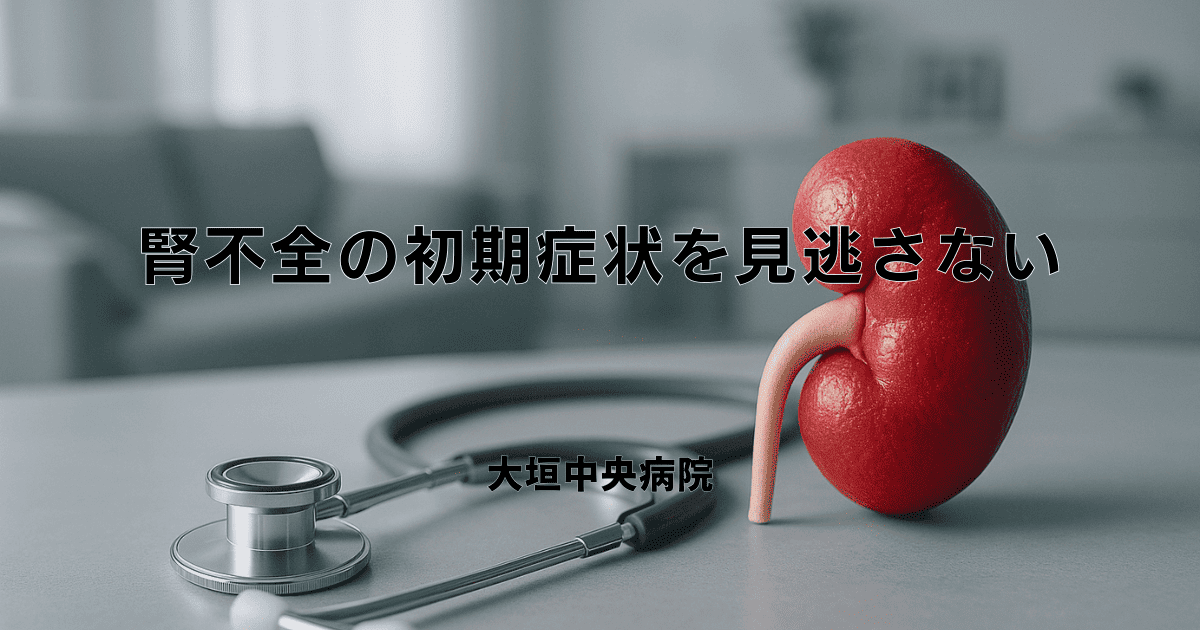腎不全は、腎臓の機能が低下し、体内の老廃物や余分な水分を十分に排出できなくなる状態を指します。初期には自覚症状が乏しいため、気づかないうちに進行していることも少なくありません。
しかし、早期にサインを発見し、適切な対応を始めることで、進行を遅らせたり、合併症を防いだりすることが期待できます。
この記事では、腎不全の初期症状や早期発見の重要性、そして必要な対応について詳しく解説します。
腎不全とは?基本的な知識
腎臓は私たちの体にとって非常に重要な臓器です。その機能が低下する腎不全について、まずは基本的な知識を深めましょう。腎不全を正しく理解することが、早期発見と適切な対応への第一歩となります。
腎臓の主な働き
腎臓は、単に尿を作るだけの臓器ではありません。生命維持に欠かせない多くの重要な役割を担っています。これらの働きが損なわれると、体に様々な不調が現れます。
日々の健康を支える腎臓の働きを理解することは、腎不全のサインに気づく上で大切です。
腎臓の多岐にわたる機能
腎臓は主に以下の働きをしています。
- 老廃物の排泄: 血液をろ過し、体内で不要になった老廃物や毒素を尿として体外へ排出します。
- 水分・電解質の調節: 体内の水分量やナトリウム、カリウム、カルシウムなどの電解質バランスを一定に保ちます。
- 血液の酸性・アルカリ性の調節: 血液のpHバランスを適切に維持します。
- 血圧の調節: レニンというホルモンを分泌し、血圧をコントロールします。
- ホルモンの産生: 赤血球を作るエリスロポエチンや、骨を丈夫にする活性型ビタミンDなどのホルモンを産生します。
これらの機能が一つでも低下すると、身体全体のバランスが崩れる可能性があります。
腎臓の働きと影響
| 働き | 具体的な内容 | 機能低下時の影響 |
|---|---|---|
| 老廃物のろ過と排泄 | 血液中の尿素窒素やクレアチニンなどを尿として排出 | 尿毒症症状(だるさ、吐き気、食欲不振など) |
| 水分・電解質のバランス調整 | 体液量、ナトリウム、カリウムなどの濃度を一定に保つ | むくみ、高血圧、不整脈など |
| 造血ホルモンの産生 | エリスロポエチンを分泌し赤血球の産生を促す | 腎性貧血(めまい、息切れ、動悸など) |
この表は腎臓の主な働きの一部を示したものです。他にも重要な役割があります。
腎不全が起こる原因
腎不全は、様々な原因によって腎臓の機能が著しく低下した状態です。原因を理解することは、予防や対策を考える上で重要です。腎機能が低下する主な原因には、生活習慣病である糖尿病や高血圧が挙げられます。
これらは腎臓の血管にダメージを与え、徐々に腎機能を悪化させます。
糖尿病性腎症
糖尿病の合併症の一つで、高血糖が続くことで腎臓の毛細血管が傷つき、ろ過機能が低下します。血糖コントロールが不十分な状態が長く続くと、腎臓のフィルター機能が徐々に損なわれていきます。
これは、日本において透析導入の最大の原因疾患となっています。
腎硬化症
高血圧が長期間続くことで腎臓の動脈が硬化し、血流が悪くなって腎機能が低下します。高血圧は腎臓内の細い血管に常に高い圧力をかけ、血管壁を厚く硬くさせます。
これにより、腎臓への血液供給が減少し、腎組織が酸素不足や栄養不足に陥り、徐々に機能が低下します。
慢性糸球体腎炎
糸球体という腎臓のろ過装置に慢性的な炎症が起こる病気の総称です。IgA腎症などが代表的で、免疫反応の異常などが原因と考えられています。炎症により糸球体が傷つき、ろ過機能が低下します。
多発性のう胞腎
腎臓に多数の「のう胞」(液体がたまった袋)ができ、徐々に大きくなることで正常な腎組織を圧迫し、腎機能が低下する遺伝性の疾患です。のう胞が増大するにつれて、腎臓全体の機能が損なわれます。
その他、薬剤の副作用、膠原病、尿路の閉塞(結石や腫瘍などによる)なども腎不全の原因となることがあります。原因は多岐にわたるため、正確な診断が重要です。
急性腎不全と慢性腎不全の違い
腎不全には、急激に腎機能が悪化する「急性腎不全」と、数ヶ月から数年にわたって徐々に腎機能が低下する「慢性腎不全」があります。両者は経過や治療法、そして腎機能回復の可能性において異なります。
急性腎不全
数時間から数日の間に急激に腎機能が低下する状態です。原因としては、重度の脱水、大量出血、薬剤の副作用、急激な血圧低下、感染症、尿路の閉塞などが挙げられます。
原因を特定し、速やかに適切な治療を行うことで腎機能の回復が見込める場合がありますが、重症化すると生命に関わることもあります。
慢性腎不全
数ヶ月から数年かけてゆっくりと腎機能が低下し、多くの場合、失われた腎機能の回復は困難です。初期には自覚症状がほとんどなく、進行すると様々な症状が現れます。
慢性腎臓病(CKD)とも呼ばれ、進行すると末期腎不全に至り、透析療法や腎移植が必要になります。生活習慣病が主な原因となることが多いです。
急性腎不全と慢性腎不全の主な相違点
| 特徴 | 急性腎不全 | 慢性腎不全 |
|---|---|---|
| 発症の速さ | 急激(数時間~数日) | 緩徐(数ヶ月~数年) |
| 主な原因 | 脱水、薬剤、感染症、尿路閉塞など | 糖尿病、高血圧、慢性糸球体腎炎など |
| 腎機能の回復 | 原因除去により回復の可能性あり | 多くの場合、進行性で回復は困難 |
どちらのタイプの腎不全も、早期の発見と対応が重要です。
見逃しやすい腎不全の初期症状
腎不全の初期症状は非常に気づきにくく、他の体調不良と間違われることもあります。しかし、注意深く観察することで、いくつかのサインに気づくことができます。これらのサインを知っておくことが、早期発見につながります。
体のむくみ(浮腫)
腎機能が低下すると、体内の余分な水分や塩分をうまく排出できなくなり、むくみ(浮腫)が生じやすくなります。初期には、夕方になると足がむくむ、靴下の跡がくっきり残りやすいといった症状が現れることがあります。
これは体液が組織の間に溜まることで起こります。
むくみが出やすい場所と特徴
- 足やすね: 特に夕方になると顕著になることがあります。指で数秒間押すと、へこんだ跡が残るのが特徴です(圧痕性浮腫)。
- まぶたや顔: 朝起きた時に、顔全体やまぶたが腫れぼったい感じがすることがあります。
- 手: 指輪がきつくなったり、手が握りにくくなったりすることもあります。
体重が短期間で急に1~2kg増えた場合も、むくみが原因である可能性があります。
ただし、むくみは心臓病や肝臓病、甲状腺機能低下症、薬剤の副作用など他の原因でも起こるため、自己判断せずに医療機関を受診することが大切です。
尿の変化(量、色、泡立ち)
尿は腎臓の健康状態を反映する重要なバロメーターです。尿の量、色、泡立ちなどに変化が見られたら注意が必要です。日常的に自分の尿を観察する習慣をつけましょう。
注意すべき尿の変化
腎機能が低下すると、以下のような尿の変化が現れることがあります。
- 尿量の変化: 夜間の尿量が増える(夜間頻尿)、あるいは逆に尿量が極端に減る(乏尿・無尿)。健康な成人の1日の尿量は1000~1500ml程度です。
- 尿の色の変化: 健康な尿は淡黄色ですが、赤褐色(血尿)、濃い黄色、コーラのような色、白濁などが見られる場合は注意が必要です。ただし、食べ物や薬の影響で色が変わることもあります。
- 尿の泡立ち: 尿の泡がなかなか消えない場合、尿中にタンパク質が多く含まれている(タンパク尿)可能性があります。タンパク尿は腎機能低下の重要なサインです。
これらの変化に気づいたら、早めに医師に相談しましょう。
尿に関する具体的な注意サイン
| 変化の種類 | 具体的なサイン | 考えられること |
|---|---|---|
| 尿量 | 夜中に何度もトイレに起きる、1日の尿が極端に少ない | 腎臓の濃縮力低下、排泄機能低下 |
| 尿色 | 赤っぽい、茶色い、濁っている | 血尿、タンパク尿、感染症の可能性 |
| 尿の泡立ち | 泡が細かく、なかなか消えない | タンパク尿の可能性 |
全身の倦怠感・疲労感
腎機能が低下すると、老廃物が体内に蓄積したり、腎性貧血が進行したりすることで、原因のはっきりしないだるさや疲れやすさを感じることがあります。
十分な睡眠をとっても疲れが取れない、以前よりも体力が落ちたと感じたら、腎機能低下のサインかもしれません。
倦怠感・疲労感の主な原因
- 老廃物の蓄積: 尿として排泄されるべき毒素(尿毒素)が体内にたまり、神経や筋肉の働きに影響を与え、だるさや集中力の低下を引き起こします。
- 腎性貧血: 腎臓でつくられるエリスロポエチンというホルモン(赤血球の産生を促す)が減少し、赤血球が十分に作られなくなるため貧血状態になります。貧血になると、体中に酸素が十分に行き渡らず、疲れやすさや息切れ、めまい、顔面蒼白などの症状が現れます。
これらの症状は徐々に進行するため、本人が気づきにくいこともあります。
その他の注意すべきサイン
むくみや尿の変化、倦怠感以外にも、腎不全の初期には様々なサインが現れることがあります。
これらの症状は他の病気でも見られるため、一つ一つの症状だけで腎不全と判断することは難しいですが、複数の症状が重なる場合は特に注意が必要です。
その他の初期症状の例
| 症状 | 詳細 |
|---|---|
| 食欲不振・吐き気・嘔吐 | 老廃物の蓄積により、消化器系に不調が現れることがあります。口臭(アンモニア臭)がすることもあります。 |
| 皮膚のかゆみ | 尿毒素が皮膚に刺激を与えたり、皮膚が乾燥したりすることで、全身にかゆみが生じます。 |
| 息切れ・動悸 | 腎性貧血や体液貯留(心不全)により、少し動いただけでも息切れや動悸が起こることがあります。 |
| 集中力の低下・頭痛 | 老廃物の蓄積が脳機能に影響を与えることがあります。また、高血圧に伴い頭痛が起こることもあります。 |
| 高血圧 | 腎臓は血圧調整にも関わっており、機能低下で高血圧になる、または既存の高血圧が悪化します。 |
これらの症状が続く場合は、放置せずに医療機関を受診して原因を調べることが重要です。
なぜ初期症状に気づきにくいのか
腎臓は「沈黙の臓器」とも呼ばれるほど、機能がある程度低下するまではっきりとした自覚症状が現れにくい臓器です。そのため、腎不全は発見が遅れがちになります。その理由を理解しておきましょう。
症状がゆっくり進行するため
慢性腎不全の多くは、数ヶ月から数年という長い時間をかけてゆっくりと進行します。そのため、体は少しずつ腎機能の低下に適応してしまい、明らかな症状として感じにくいのです。
例えば、徐々に進行する貧血や倦怠感に対して、本人は「年のせいかな」「最近忙しいからかな」などと考え、病気のサインとは認識しにくいことがあります。
腎臓の機能が半分以下になるまで、はっきりとした症状が出ないことも多いのが特徴です。
他の病気と間違えやすいため
腎不全の初期症状であるむくみ、倦怠感、食欲不振などは、他の多くの病気でも見られる一般的な症状です。そのため、これらの症状が現れても、まさか腎臓が悪いとは思わず、風邪や疲労、胃腸の不調、更年期障害など、別の原因を考えてしまうことがあります。
特に、高血圧や糖尿病などの持病がある方は、それらの病気による症状と区別がつきにくく、腎機能の悪化を見逃してしまう可能性があります。
自覚症状がない場合もある
腎臓は予備能力が非常に高い臓器で、片方の腎臓が機能しなくなっても、もう片方が正常であれば、ある程度までは機能を代償できます。
また、両方の腎臓の機能が徐々に低下する場合でも、残っている腎組織が代償的に働くため、腎機能がかなり低下する(例えば、正常の30%以下になる)まで全く自覚症状が現れないことも珍しくありません。
健康診断などで尿検査や血液検査を受けて初めて腎機能の異常を指摘され、驚く方も多くいます。自覚症状がないからといって安心せず、定期的な健康診断を受けることが早期発見には非常に重要です。
早期発見の重要性
腎不全は進行性の病気ですが、早期に発見し、適切な治療や生活習慣の改善を行うことで、その進行を遅らせ、より良い生活の質(QOL)を維持することが期待できます。早期発見がなぜそれほど大切なのか、具体的な理由を見ていきましょう。
進行を遅らせるために
一度失われた腎機能を完全に元に戻すことは、現在の医療では困難な場合が多いです。
しかし、早期の段階で腎機能低下の原因となっている病気(糖尿病、高血圧、慢性糸球体腎炎など)を特定し、その治療をしっかりと行うことで、腎機能の低下速度を緩やかにすることができます。
食事療法や薬物療法を早期から開始することで、腎臓への負担を軽減し、末期腎不全への進行を遅らせることが治療の大きな目標となります。
CKD(慢性腎臓病)のステージ分類とGFR
腎機能の評価には、eGFR(推算糸球体ろ過量)が用いられます。eGFRの値によって、慢性腎臓病(CKD)の進行度がステージ分類されます。
早期発見により、より初期のステージで介入することができれば、それだけ進行を遅らせる効果が期待できます。
| ステージ | eGFR (mL/分/1.73m²) | 腎機能の状態 |
|---|---|---|
| G1 | 90以上 | 腎障害あり(タンパク尿など)、または腎機能正常 |
| G2 | 60~89 | 腎障害あり、腎機能軽度低下 |
| G3a | 45~59 | 腎機能軽度~中等度低下 |
| G3b | 30~44 | 腎機能中等度~高度低下 |
| G4 | 15~29 | 腎機能高度低下 |
| G5 | 15未満 | 末期腎不全(透析や腎移植が必要な状態) |
eGFRは血清クレアチニン値、年齢、性別から算出されます。定期的な検査でご自身のeGFR値を知っておくことが大切です。
合併症を予防するために
腎機能が低下すると、様々な合併症を引き起こすリスクが高まります。
代表的な合併症には、高血圧、心血管疾患(心筋梗塞や脳卒中など)、貧血(腎性貧血)、骨の異常(ミネラル骨代謝異常、骨粗しょう症など)、電解質異常(高カリウム血症など)、栄養障害などがあります。
これらの合併症は、生活の質を著しく低下させるだけでなく、生命に関わることもあります。早期に腎不全を発見し、適切な管理を行うことで、これらの合併症の発症を予防したり、進行を遅らせたりすることが可能です。
治療の選択肢を広げるために
腎不全が進行し末期腎不全になると、自身の腎臓だけでは生命を維持できなくなり、透析療法(血液透析または腹膜透析)や腎移植といった腎代替療法が必要になります。これらの治療法は、患者さんの生活に大きな影響を与えます。
早期に発見し、進行を遅らせることができれば、腎代替療法への移行を遅らせたり、場合によっては回避できる可能性もあります。
また、仮に腎代替療法が必要になった場合でも、早期から病状や治療法について十分な情報を得て準備を進めることで、精神的・身体的な負担を軽減し、よりスムーズに治療に移行することができます。
腎不全の検査と診断
腎不全の疑いがある場合、または定期的な健康チェックとして、いくつかの検査が行われます。これらの検査によって、腎機能の状態や原因を評価し、適切な診断を下します。主な検査には尿検査、血液検査、画像検査があります。
尿検査でわかること
尿検査は、腎臓の異常を早期に発見するための簡単で重要な検査です。採取した尿を用いて、尿中のタンパク質、糖、潜血(血液の混入)、白血球、細胞成分などを調べます。
特にタンパク尿と血尿は腎臓病の重要な手がかりとなります。
尿タンパク
健康な人の尿には、タンパク質はごく微量しか含まれません。尿中にタンパク質が多く漏れ出ている状態を「タンパク尿」といい、腎臓のろ過機能に障害がある可能性を示唆します。
持続的なタンパク尿は、慢性腎臓病の重要なサインであり、その量が多いほど腎機能が悪化しやすいとされています。
尿潜血
尿中に赤血球が混じっている状態を「血尿」といいます。肉眼で見て赤いとわかる血尿と、顕微鏡で確認しないとわからない尿潜血があります。腎炎、尿路結石、膀胱炎、腫瘍など様々な原因で起こりえます。
尿検査の主な項目と評価の目安
| 検査項目 | 評価の目安(一般的な例) | 腎機能低下との関連 |
|---|---|---|
| 尿タンパク | (-) または (±) | (+)以上が持続する場合、腎障害の可能性が高い |
| 尿潜血 | (-) | (+)以上の場合、腎臓や尿路からの出血が疑われる |
| 尿糖 | (-) | (+)以上の場合、糖尿病や腎性糖尿などが疑われる |
これらの結果は総合的に判断されるため、異常値が出た場合は医師の説明をよく聞き、必要に応じて精密検査を受けましょう。
血液検査でわかること
血液検査では、腎臓のろ過能力や体内の老廃物の蓄積度合い、電解質バランス、貧血の有無などを調べます。腎機能の評価には、特に血清クレアチニン値とeGFR(推算糸球体ろ過量)が重要です。
血清クレアチニン(Cr)
筋肉運動の老廃物で、主に腎臓でろ過されて尿中に排泄されます。腎機能が低下すると、血液中のクレアチニン値が上昇します。ただし、筋肉量によって影響を受けるため、年齢、性別、筋肉量によって基準値が異なります。
同じクレアチニン値でも、筋肉の少ない高齢者や女性では、より腎機能が低下している可能性があります。
eGFR(推算糸球体ろ過量)
血清クレアチニン値、年齢、性別から計算される指標で、腎臓が1分間にどれくらいの血液をろ過できるかを示します。腎機能の評価に広く用いられ、慢性腎臓病(CKD)のステージ分類にも使われます。
値が低いほど腎機能が低下していることを意味します。
血液検査の主な項目と評価の目安
| 検査項目 | 評価の目安(一般的な例) | 腎機能低下との関連 |
|---|---|---|
| 血清クレアチニン | 男性: 0.6~1.1 mg/dL 女性: 0.4~0.8 mg/dL | 高値の場合、腎機能低下が疑われる |
| eGFR | 60 mL/分/1.73m² 以上 | 60未満が続く場合、慢性腎臓病(CKD)の可能性が高い |
| 尿素窒素 (BUN) | 8~20 mg/dL | 高値の場合、腎機能低下のほか、脱水や消化管出血なども考慮 |
これらの値は、他の検査結果や症状と合わせて総合的に評価します。定期的な検査で経時的な変化を見ることが重要です。
画像検査(超音波検査など)
画像検査は、腎臓の大きさや形、結石や腫瘍の有無、血流の状態などを視覚的に確認するために行います。代表的な画像検査には、超音波(エコー)検査があります。
これは体に負担の少ない検査で、腎臓の形態的な異常(萎縮、腫大、のう胞、水腎症など)を調べることができます。その他、必要に応じてCT検査やMRI検査が行われることもあります。
これらの検査は、腎不全の原因を特定する上で役立ちます。例えば、腎臓の大きさが小さくなっている(萎縮)場合は慢性的な腎臓病が、左右差がある場合は片側の腎臓に問題がある可能性などが考えられます。
腎生検について
腎生検は、腎臓の組織の一部を採取して顕微鏡で詳しく調べる検査です。尿検査、血液検査、画像検査だけでは診断が難しい場合や、腎炎の種類を特定し治療方針を決定する必要がある場合などに行われます。
局所麻酔下で背中から細い針を刺して腎組織を採取します。入院が必要な検査であり、出血などの合併症のリスクも伴うため、医師が必要性を慎重に判断した上で行います。
腎生検によって正確な診断が得られれば、より適切な治療法の選択につながります。例えば、治療によって改善が見込めるタイプの腎炎なのか、あるいは進行を抑える治療が中心となるタイプなのかなどを判断するのに役立ちます。
初期対応と生活習慣の見直し
腎不全の初期と診断された場合、あるいはその疑いを指摘された場合、医師の指示に従い、生活習慣を見直すことが進行を遅らせるために非常に重要です。早期からの取り組みが、将来の腎機能を守ることにつながります。
医師の指示に従う
まず最も大切なことは、医師の診断と指示を正確に理解し、それに従うことです。自己判断で治療を中断したり、科学的根拠のない民間療法に頼ったりすることは、かえって病状を悪化させる可能性があります。
処方された薬は用法・用量を守ってきちんと服用し、定期的な通院と検査を欠かさず受けましょう。不明な点や不安なことがあれば、遠慮なく医師や看護師、管理栄養士などの医療スタッフに相談し、納得のいく説明を受けることが大切です。
治療は長期にわたることが多いため、医療チームとの信頼関係を築くことも重要です。
食事療法のポイント
腎機能の程度に応じて、食事療法が必要になる場合があります。食事療法の基本は、腎臓への負担を軽減することです。具体的な内容は個々の状態によって異なりますので、必ず医師や管理栄養士の指導を受けましょう。
食事療法の基本原則
- タンパク質の制限: 過剰なタンパク質摂取は、老廃物を増やし腎臓に負担をかけます。医師や管理栄養士の指導のもと、良質なタンパク質を適切な量に調整します。
- 塩分(ナトリウム)の制限: 塩分の摂りすぎは高血圧やむくみの原因となり、腎臓に悪影響を与えます。1日6g未満が目標とされることが多いですが、状態によって異なります。だしや香辛料を上手に使うなど、薄味に慣れる工夫が必要です。
- カリウムの制限: 腎機能が低下するとカリウムが排泄されにくくなり、血液中のカリウム濃度が高くなる「高カリウム血症」を引き起こすことがあります。これは不整脈などの原因となるため、野菜や果物の種類や調理法(茹でこぼしなど)に注意が必要です。
- 適切なエネルギー量の確保: タンパク質を制限するとエネルギー不足になりやすいため、炭水化物や脂質で十分なエネルギーを補給することが大切です。エネルギーが不足すると、体内のタンパク質が分解されてしまい、かえって老廃物が増えることがあります。
食事療法は、病気の進行度や合併症の有無によって内容が異なります。自己判断せず、必ず専門家の指導を受け、無理のない範囲で継続することが重要です。
適度な運動と休息
適度な運動は、体力維持、筋力低下の予防、ストレス解消、血圧や血糖値のコントロールにも役立ちます。ただし、腎機能の程度や合併症によっては運動が制限される場合もあるため、医師に相談の上、無理のない範囲で行いましょう。
ウォーキングや軽いジョギング、水泳、サイクリングなどの有酸素運動が推奨されることが多いです。激しい運動や息が切れるような運動は避け、体調の良い時に行うようにしましょう。
また、十分な睡眠と休息をとり、過労を避けることも大切です。規則正しい生活を心がけ、心身のバランスを整えましょう。
禁煙と節酒
喫煙は腎臓の血管を収縮させ、血流を悪化させるため、腎機能低下を促進する大きな危険因子です。また、動脈硬化を進行させ、心血管疾患のリスクも高めます。腎不全の進行を遅らせるためには、禁煙が強く推奨されます。
禁煙が難しい場合は、禁煙外来などで専門家のサポートを受けることも考えましょう。アルコールの過剰な摂取も、高血圧や肝機能障害などを介して腎臓に悪影響を与える可能性があります。
飲酒は適量を守るか、医師の指示によっては禁酒が必要です。一般的に、男性では1日あたり日本酒1合程度、女性はその半分程度が適量とされていますが、これも個人の状態によります。
生活習慣で見直したいことのまとめ
| 項目 | 具体的な行動例 | 期待される効果 |
|---|---|---|
| 食事管理 | 医師・管理栄養士の指導に基づく塩分・タンパク質制限、適切なエネルギー摂取 | 腎臓への負担軽減、血圧・血糖コントロール改善 |
| 運動習慣 | ウォーキングなどの有酸素運動を無理なく継続する | 体力維持、生活習慣病改善、ストレス解消 |
| 禁煙 | 完全に禁煙する。必要であれば禁煙補助を利用する。 | 腎血流改善、動脈硬化進行抑制、心血管リスク低減 |
これらの生活習慣の改善は、腎臓を守るだけでなく、全身の健康維持にもつながります。一つひとつ、できることから始めましょう。
よくある質問 (FAQ)
腎不全に関して、患者さんやご家族からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。ここに記載されている内容は一般的なものであり、個々の状況によって異なる場合がありますので、詳細は必ず主治医にご確認ください。
- 腎不全は治りますか?
-
急性腎不全の場合、原因を特定し早期に適切な治療を行えば、腎機能が回復する可能性があります。しかし、慢性腎不全の場合、残念ながら一度失われた腎機能を完全に元通りに治すことは現在の医療では難しいのが現状です。
慢性腎不全の治療目標は、残っている腎機能をできるだけ長持ちさせ、病気の進行を遅らせ、末期腎不全への移行をできるだけ遅らせること、そして合併症を予防・管理し、生活の質を維持することです。
早期発見と適切な治療、生活習慣の管理が非常に重要になります。
- 遺伝は関係しますか?
-
腎不全の原因となる病気の中には、遺伝が関与するものがあります。代表的なものとしては、多発性のう胞腎が挙げられます。これは遺伝性の疾患で、親からの遺伝によって発症することがあります。
また、糖尿病や高血圧なども家族歴が影響することがあり、これらの生活習慣病が原因で腎不全になるリスクも間接的に遺伝的要因が関わると言えます。
ご家族に腎臓病の方がいる場合は、定期的な腎機能検査を受けるなど、より注意を払うことが推奨されます。心配な場合は医師に相談してみましょう。
- どのような食事を心がければ良いですか?
-
腎不全の食事療法は、病気の進行度(ステージ)や合併症の有無、年齢、体格などによって異なりますので、一概に「こうすれば良い」とは言えません。
基本的には、タンパク質、塩分、カリウム、リンなどの摂取量を調整し、適切なエネルギーを確保することが中心となります。例えば、初期の段階では塩分制限が中心となることが多いですが、進行するとタンパク質やカリウムの制限も必要になってきます。
自己判断で極端な食事制限を行うと、栄養失調や体調悪化を招くこともありますので、必ず医師や管理栄養士の指導を受け、個別の食事プランを作成してもらうことが大切です。
その上で、日々の食事記録をつけるなどして、実践していくことが望ましいです。
- 薬で進行を止められますか?
-
現在のところ、腎不全の進行を完全に「止める」薬は残念ながらありません。
しかし、血圧をコントロールする薬(降圧薬、特にACE阻害薬やARB)、脂質異常症を改善する薬、貧血を改善する薬(エリスロポエチン製剤など)、尿酸値を下げる薬、そして最近では糖尿病治療薬であるSGLT2阻害薬などが、腎機能の低下を遅らせる効果が期待できる薬として用いられています。
これらの薬物療法と、食事療法や生活習慣の改善を組み合わせることで、腎不全の進行を緩やかにし、透析導入までの期間を延長することを目指します。医師の指示に従い、適切に薬物治療を継続することが重要です。
新しい治療薬も開発が進められていますので、最新の情報については主治医に確認してください。
以上
参考文献
CHEN, Teresa K.; KNICELY, Daphne H.; GRAMS, Morgan E. Chronic kidney disease diagnosis and management: a review. Jama, 2019, 322.13: 1294-1304.
WOUTERS, Olivier J., et al. Early chronic kidney disease: diagnosis, management and models of care. Nature Reviews Nephrology, 2015, 11.8: 491-502.
LOCATELLI, Francesco; VECCHIO, Lucia Del; POZZONI, Pietro. The importance of early detection of chronic kidney disease. Nephrology Dialysis Transplantation, 2002, 17.
LEVIN, Adeera; STEVENS, Paul E. Early detection of CKD: the benefits, limitations and effects on prognosis. Nature Reviews Nephrology, 2011, 7.8: 446-457.
SNYDER, Susan; PENDERGRAPH, BERNADETTE. Detection and evaluation of chronic kidney disease. American family physician, 2005, 72.9: 1723-1732.
JAMES, Matthew T.; HEMMELGARN, Brenda R.; TONELLI, Marcello. Early recognition and prevention of chronic kidney disease. The Lancet, 2010, 375.9722: 1296-1309.
WEBSTER, Angela C., et al. Chronic kidney disease. The lancet, 2017, 389.10075: 1238-1252.
ROMAGNANI, Paola, et al. Chronic kidney disease. Nature reviews Disease primers, 2017, 3.1: 1-24.
LEVEY, Andrew S.; CORESH, Josef. Chronic kidney disease. The lancet, 2012, 379.9811: 165-180.
TANGRI, Navdeep, et al. A predictive model for progression of chronic kidney disease to kidney failure. Jama, 2011, 305.15: 1553-1559.