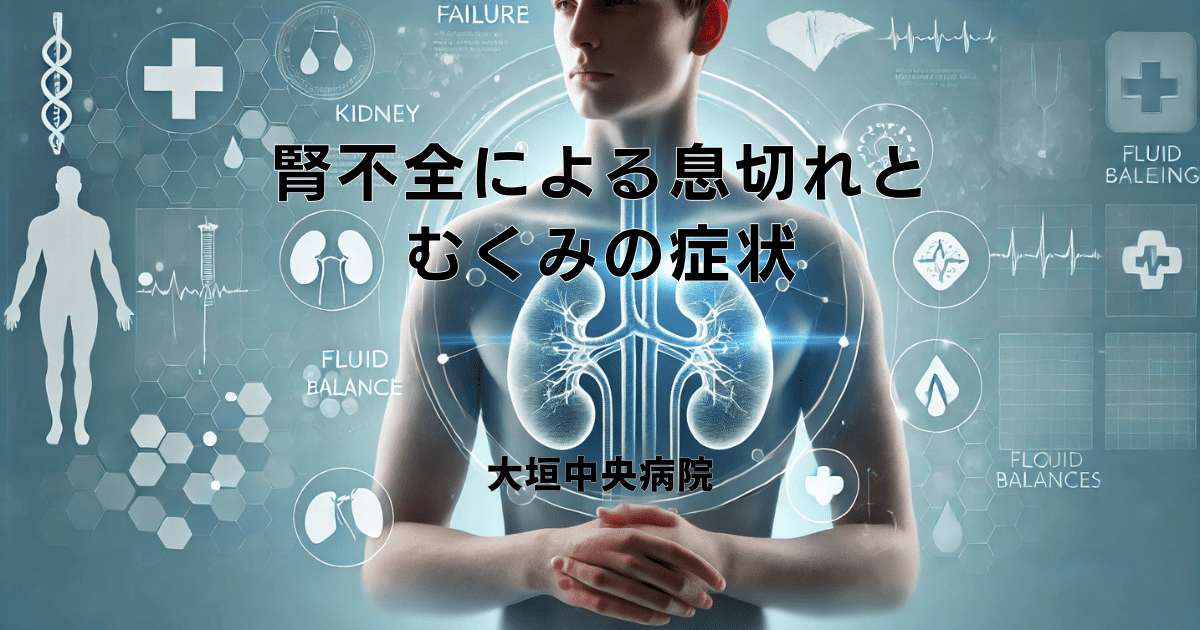腎臓が十分に機能しない状態では、体内に水分や老廃物が過剰に溜まり、息切れやむくみといった症状が起こりやすくなります。
特に腎不全むくみや腎不全呼吸困難などの状態は放置すると深刻な合併症を引き起こす可能性があります。
本記事では、腎臓の役割から腎不全の原因、息切れやむくみが起こるメカニズム、治療法までを詳しく解説します。
腎臓が担う役割と腎不全とは
体内の恒常性を維持するうえで、腎臓が果たす働きは非常に重要です。血液をろ過し、老廃物や余分な水分を体外へ排泄するほか、血圧調節やホルモン分泌など、多岐にわたる機能を持ちます。この機能が損なわれる状態が腎不全です。
腎臓が果たす重要な機能
腎臓は血液をろ過して、必要な成分は体内に戻し、不必要な成分を尿として排出します。それだけでなく、電解質や体液量のバランスを整える働きも担います。
- 老廃物の排出
- 水分バランスの調節
- 血圧の調整
- ホルモン生成(赤血球産生を促進するエリスロポエチンなど)
腎臓機能を支える要素
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 血液ろ過機能 | 血中の老廃物や余分な水分を濾過し、尿として排出する。 |
| 電解質調整 | ナトリウムやカリウムなどの量を調整する。 |
| ホルモン分泌 | 血圧調整や赤血球産生に関与するホルモンをつくる。 |
| 酸塩基平衡 | pHのバランスを維持する。 |
腎不全とはどのような状態か
腎機能が大幅に低下すると、血液中の老廃物や水分を十分に排出できなくなります。その結果、体内に不要物が溜まり、さまざまな合併症が生じる状態を腎不全と呼びます。
急激に進行する「急性腎不全」と、慢性的に悪化していく「慢性腎不全」に大きく分けられます。
腎不全による身体への主な影響
血液ろ過が十分に行えないため、毒素が蓄積しやすくなります。また、体液量の調節がうまくいかず、むくみや血圧上昇などが起こることがあります。長期的には全身の臓器機能に影響を及ぼします。
息切れとむくみが起こるメカニズム
腎不全むくみは、水分とナトリウムが過剰に残りやすくなることが原因です。さらに、腎不全呼吸困難は余分な水分が肺などにまで溜まり、酸素交換を阻害することで起こります。
腎不全肺水腫という状態になると、呼吸困難が急激に悪化する恐れがあります。
腎不全むくみが起こる背景
むくみは血液中の水分が組織内へ移動し、排出されにくい状態で生じます。腎機能が低下すると、体内の水と塩分をうまく排泄できず、水分が停滞しやすくなるため、足や顔がはれぼったく見えることが多いです。
むくみの主な発症要因
| 要因 | 具体例 |
|---|---|
| 塩分の摂りすぎ | 食事から過剰に塩分を取り込むと、体内の水分保持量が増える。 |
| 腎臓のろ過能力低下 | 老廃物や水分が排出されにくくなり、全身に水分が溜まる。 |
| 血液タンパク低下 | 血液中のタンパク質が少ないと、血管内に水を保持できなくなる。 |
| ホルモン異常 | レニンやアルドステロンなどの分泌異常で水分バランスが乱れる。 |
腎不全呼吸困難と体内の水分バランス
腎不全で余分な水分が体に蓄積すると、血液中の水分量も増え、肺の血管内圧が高まります。これにより、肺胞内へ水分がしみ出し、呼吸しにくくなる状態が起こります。
軽度なら息が切れやすい程度ですが、重度の場合は会話も困難なほどの呼吸不全になる可能性があります。
腎不全肺水腫との関連
腎不全肺水腫とは、腎臓の機能不全が原因で体液が過剰に溜まり、肺に水分がたまってしまう病態です。初期症状としては呼吸が苦しくなり、進行すると血液中の酸素濃度低下に伴い意識障害を招く恐れがあります。
入院治療が必要になることも多いため、早めの受診が大切です。
腎不全による息切れの症状に着目
腎機能の低下による体液過剰や貧血などによって、息切れが生じることがあります。階段を上るときだけ感じていた息苦しさが、日常的な動作でも強くなっていくようなら要注意です。
息切れを自覚するタイミング
初期段階では運動時や動作時だけに息切れを感じることが多いです。しかし腎不全が進行すると、安静時にも呼吸が浅くなったり動悸を伴ったりするケースがあります。
特に夜間、横になると呼吸が苦しくて眠れない場合は危険な兆候です。
息切れを自覚しやすい場面
- 坂道や階段の昇降
- 重い物を持ったとき
- 入浴やシャワー中
- 会話をしているとき
息切れの状態を悪化させる要因
高血圧や塩分過多の食生活、さらには貧血や心不全など、腎不全を助長する病態が息切れの悪化を招くことがあります。過労やストレス、睡眠不足なども全身の代謝やホルモンバランスを乱し、呼吸機能に負担をかけることがあります。
息切れ対策の要点
| 要点 | 内容 |
|---|---|
| 塩分制限 | 水分過多や血圧上昇を防ぎ、息切れを抑える効果がある。 |
| 休息の確保 | 適度な休憩と睡眠を取り、身体の負担を軽減する。 |
| 早期受診 | 初期症状が軽いうちに医療機関で検査を受ける。 |
| 運動の見直し | 過度な運動は避け、軽いウォーキングなどで体力を保つ。 |
息切れの判断と受診の目安
普段の生活での息苦しさが増してきた場合は、腎不全による呼吸機能への影響が進んでいる可能性があります。息切れが持続的に続いたり、安静時にも呼吸が苦しいと感じたりしたら、総合病院などで早めに検査を受ける必要があります。
腎不全によるむくみの症状に着目
腎不全むくみは、余分な水分が足首や顔周りなどに集まり、皮膚を押すと跡が残ることが特徴です。体液量のコントロールが難しくなるため、見た目だけでなく生活の質にも大きな影響を与えます。
足や顔への水分貯留
重力の影響で、まず足首やふくらはぎにむくみを自覚するケースが多いです。朝起きたときにまぶたが腫れぼったいという状態も、腎機能低下に伴う水分貯留のサインのひとつです。
むくみの出やすい部位一覧
| 部位 | 特徴 |
|---|---|
| 足首~ふくらはぎ | 歩行時の靴やソックスがきつく感じることが多い。 |
| 顔(まぶた) | 起床時に腫れ、日中はやや軽減する場合もある。 |
| 手指 | 指輪がきつくなり、動かしにくさを感じる。 |
| 腹部 | お腹周りが張った感じになり、違和感が続く。 |
むくみで注意したい合併症
むくみそのものが痛みを伴わないケースも多いですが、裏には血圧上昇や心臓への負担増などが潜んでいることがあります。むくみが慢性的に続くと、皮膚の炎症や感染症リスクが高まることもあるため注意が必要です。
むくみの程度と自己チェック
立ち仕事や長時間座っているときに、むくみが生じるのはある程度は自然な生理現象です。しかし、腎不全では水分の排出能力が落ちているため、軽度の刺激でもむくみが顕在化しやすいです。
毎日、足や顔の腫れ具合を確認し、いつもより気になる場合は腎機能の低下を疑ったほうがいいかもしれません。
自己チェックの手順
- 足首やすねの骨の上を数秒押してみる
- 指を離したあと、くぼみが残るかどうか確認する
- 片足だけでなく両足を見比べる
- 顔のむくみが酷い場合は鏡を見て腫れ具合を観察する
腎不全が引き起こすその他の症状
息切れやむくみだけでなく、血圧上昇や貧血、食欲不振などの症状も腎不全では起こりやすいです。複合的な症状が日常生活の質を下げる原因となり、放置すれば全身の健康を損ねるリスクが高まります。
血圧上昇や倦怠感
腎臓は血圧を調整するホルモンを分泌するため、その機能が低下すると高血圧になりやすくなります。血圧の上昇は倦怠感や頭痛を伴い、場合によっては心臓疾患を引き起こすこともあります。
血圧コントロールの要点
- 塩分の摂取量を控える
- 適度な運動を継続する
- 血圧手帳をつけて変化を把握する
- 医師の指導を受けながら降圧薬を活用する
貧血と疲労感
腎臓がエリスロポエチンを十分につくれないと、赤血球産生が低下し貧血を起こしやすくなります。貧血は持続的な疲労感や集中力の低下を招きます。息切れにも拍車がかかり、生活の質が大きく低下します。
腎性貧血が及ぼす影響
| 影響 | 内容 |
|---|---|
| 疲労・倦怠感 | 日常的に疲れやすくなり、活動意欲が落ちる。 |
| 息切れ悪化 | 血液の酸素運搬能力が下がるため、呼吸困難感が増す。 |
| めまい・頭痛 | 脳への酸素供給が十分でなくなるため、だるさや頭痛が続く。 |
| 皮膚や粘膜の蒼白 | 血色が悪くなり、健康的な肌つやを維持しにくい。 |
食欲不振と体重増加のパターン
食欲不振になりがちな一方、体重が増加することが腎不全では珍しくありません。余分な水分が溜まることで体重が増え、実際の栄養摂取量は減っているにもかかわらず、体重計の数字だけが増えてしまうパターンが見られます。
腎不全の原因と診断
腎不全には急性と慢性がありますが、高血圧や糖尿病などの生活習慣病が長期的に腎臓に負担をかけることが大きな要因です。早期発見のためには、定期的な検査と気になる症状の見逃し防止が重要です。
原因となる主な疾患
慢性腎不全は、高血圧と糖尿病が大きな原因として挙げられます。血糖値が高い状態や、血圧が常に高い状態が続くと、腎臓の血管にダメージが蓄積していきます。また、腎炎や多発性嚢胞腎などの腎そのものの病気も原因になることがあります。
原因疾患と発症リスク
| 疾患名 | 特徴 |
|---|---|
| 高血圧 | 動脈硬化を進め、腎臓の血管を傷つける。 |
| 糖尿病 | 高血糖により細小血管が損傷しやすくなる。 |
| 糸球体腎炎 | 腎臓のろ過機能の中枢である糸球体が炎症を起こす。 |
| 多発性嚢胞腎 | 嚢胞が多数形成され、腎機能を圧迫して低下させる。 |
血液検査や画像検査でわかること
血中のクレアチニンや尿素窒素、電解質濃度などで腎臓のろ過機能の状態を把握できます。さらに、エコーやCT、MRIなどの画像検査で腎臓の形態や血流状態を詳細に評価します。
検査結果の主な指標
- 血清クレアチニン:腎機能低下の程度を推定しやすい
- eGFR:糸球体ろ過量を推定する数値で腎機能の目安
- 尿蛋白:腎臓のフィルター機能が壊れているかどうか
- 血球計算:貧血の有無をチェック
検査を受けるタイミング
血圧や血糖値が高いなど、腎不全につながる恐れがある方は定期的な血液検査を心がけるほうがいいでしょう。むくみや息切れなどの自覚症状がある場合は、速やかに総合病院で受診し、詳細な検査を受けることが推奨されます。
腎不全による息切れ・むくみへの治療法
腎不全むくみや腎不全呼吸困難が見られる場合、対処としては薬物療法や食事療法などの保存的治療から、透析などの置換療法まで多岐にわたります。患者さんの病状やライフスタイルに合わせた治療を選択することが重要です。
薬物療法と食事療法
血圧や電解質のバランスを整えるための薬物療法や、タンパク質・塩分を制限した食事療法が代表的です。むくみが強い場合は、利尿剤で体内の余分な水分を排出する方法があります。
食事管理のポイント
| 項目 | コツ |
|---|---|
| 塩分 | 1日6g未満を目指し、食材の味付けを薄めにする。 |
| タンパク質 | 動物性たんぱく質を控えめにし、植物性を適度に活用。 |
| カリウム | 果物・野菜などは茹でこぼしなどで摂取量を調整。 |
| 水分 | 医師の指示に沿って摂取量を管理。 |
透析の導入を検討するポイント
腎機能が一定以下に低下した場合、血中の老廃物や余分な水分を透析で除去する方法が選ばれます。透析には血液透析と腹膜透析があり、それぞれのメリットやデメリットを十分理解したうえで選択することが大切です。
透析導入前に考慮すべき点
- 日常生活との両立が可能か
- 週に数回の通院が負担にならないか
- 合併症の有無や患者さんの全身状態
- 生活環境(通院手段や家族のサポート状況など)
透析以外の選択肢
末期腎不全の場合は、腎移植を視野に入れることもあります。移植が可能な場合は、ドナーとのマッチングや長期的な免疫抑制剤の使用など、複雑な手続きと管理が必要になります。
また、急性腎不全の場合は一時的な透析で腎機能が回復するケースもあるため、主治医との相談が欠かせません。
生活習慣の改善と病院での受診の大切さ
腎機能は一度低下すると元に戻りにくいとされています。だからこそ、早めに病院へ相談し、適切な治療を受けながら生活習慣を整えることが重要です。
定期受診を継続し、医療スタッフと協力しながら管理を行うことで、腎不全むくみや腎不全呼吸困難のリスクを軽減できます。
食事管理や運動の工夫
過度な塩分摂取を避け、適度な有酸素運動を取り入れることが推奨されます。塩分を抑えるためには加工食品の選び方や外食時の注文方法に注意が必要です。
運動はウォーキングや軽いストレッチなど、心肺に負担をかけすぎないメニューが望ましいです。
生活習慣改善のヒント
- 塩分を抑えた料理レシピを増やす
- 飲み物もスポーツドリンクより水やお茶を中心にする
- 日々の体重と血圧を記録して変動をチェックする
- テレビやスマートフォンを見ながらでも軽い体操を実施する
定期検診で早期発見
むくみや息切れがなくても、腎機能が徐々に低下しているケースは珍しくありません。血液検査や尿検査を定期的に受けることで、腎臓の状態を把握しやすくなります。
特に高血圧や糖尿病を持つ方はこまめな検査を心がけることが重要です。
健康チェック項目
| チェック項目 | 理由 |
|---|---|
| 血液検査 | クレアチニンやeGFRで腎機能の変化を追跡できる。 |
| 尿検査 | 蛋白や潜血の有無を把握し、腎炎の有無を早期に疑える。 |
| 血圧・脈拍測定 | 高血圧の進行状況や心臓への負担を知る手がかりになる。 |
| 体重 | むくみなどによる急激な増加を見逃さないようにする。 |
総合病院で受けられるサポート
腎臓内科や循環器内科などが連携し、複合的な治療や検査が可能なのが総合病院の利点です。腎不全むくみや腎不全呼吸困難がみられる場合、複数診療科での評価が役立つ場面が多々あります。
栄養指導やリハビリプランの提案など、各専門家のサポートも受けながら治療を進めることができます。
総合病院の連携体制
| 診療科 | 担当領域 |
|---|---|
| 腎臓内科 | 腎不全の全般的な管理と透析導入の検討、合併症対策 |
| 循環器内科 | 心臓機能や血圧管理、腎不全肺水腫への対応 |
| 糖尿病内科 | 血糖値コントロールによる腎障害の進行抑制 |
| 栄養管理部門 | 食事療法の提案とカウンセリング |
| リハビリ科 | 体力維持やむくみ軽減を目的とした運動プログラム提供 |
以上
参考文献
BOUCHARD, Josée, et al. Fluid accumulation, survival and recovery of kidney function in critically ill patients with acute kidney injury. Kidney international, 2009, 76.4: 422-427.
HUSAIN-SYED, Faeq; SLUTSKY, Arthur S.; RONCO, Claudio. Lung–kidney cross-talk in the critically ill patient. American journal of respiratory and critical care medicine, 2016, 194.4: 402-414.
CLAURE-DEL GRANADO, Rolando; MEHTA, Ravindra L. Fluid overload in the ICU: evaluation and management. BMC nephrology, 2016, 17: 1-9.
COTTER, Gad, et al. Fluid overload in acute heart failure—re‐distribution and other mechanisms beyond fluid accumulation. European journal of heart failure, 2008, 10.2: 165-169.
LIU, Kathleen D., et al. Acute kidney injury in patients with acute lung injury: impact of fluid accumulation on classification of acute kidney injury and associated outcomes. Critical care medicine, 2011, 39.12: 2665-2671.
PROWLE, John R., et al. Fluid balance and acute kidney injury. Nature Reviews Nephrology, 2010, 6.2: 107-115.
SLADEN, Arnold; LAVER, Myron B.; PONTOPPIDAN, Henning. Pulmonary complications and water retention in prolonged mechanical ventilation. New England Journal of Medicine, 1968, 279.9: 448-453.
KELM, Diana J., et al. Fluid overload in patients with severe sepsis and septic shock treated with early goal-directed therapy is associated with increased acute need for fluid-related medical interventions and hospital death. Shock, 2015, 43.1: 68-73.
KELLUM, John A., et al. Acute kidney injury. Nature reviews Disease primers, 2021, 7.1: 52.
O’CONNOR, Michael E.; PROWLE, John R. Fluid overload. Critical care clinics, 2015, 31.4: 803-821.