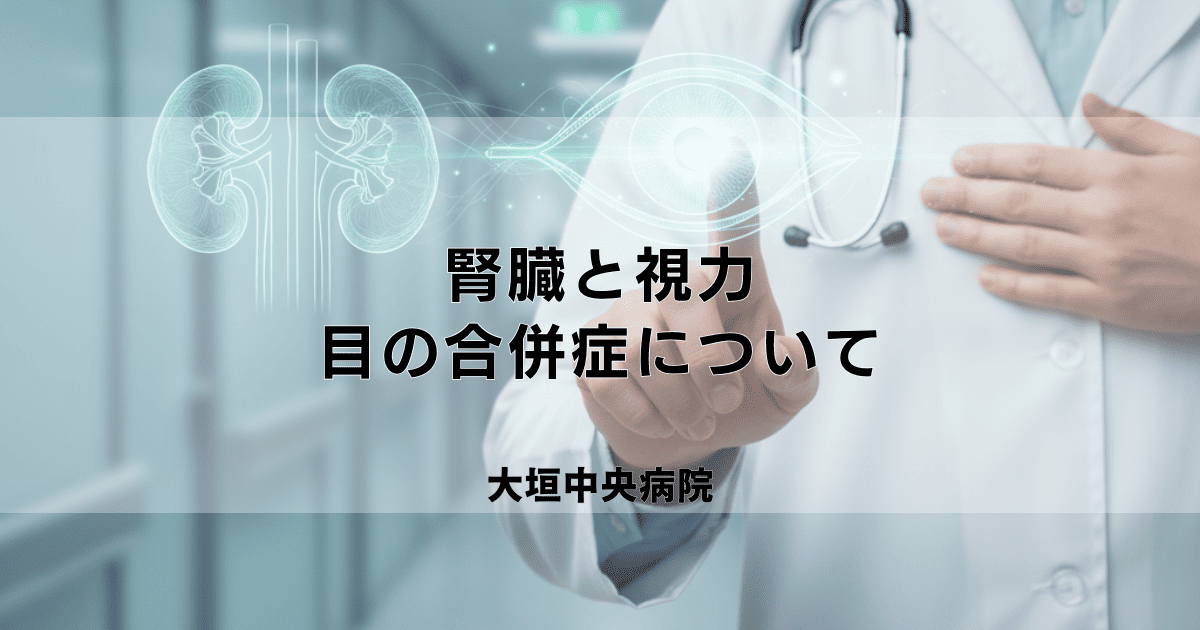「最近、腎臓の調子が良くないけれど、なんだか目の見え方も悪くなった気がする…」。このように感じている方はいませんか。
実は、腎臓と目は、体の中で深くつながっていて、腎臓の機能が低下すると、体のさまざまな部分に影響が及びますが、目は影響を受けやすい臓器の一です。
この記事では、腎臓と目の意外な関係性、腎機能の低下によって起こりうる目の病気、ご自身で確認できる注意すべきサインについて、分かりやすく解説します。
腎臓と目はなぜ関係があるの?体のつながりを解説
腎臓と目が体の離れた場所にあるにもかかわらず、密接に関係しているのはなぜでしょうか。
答えは、両方の臓器が持つ共通の構造に隠されていて、どちらも非常に細い血管が網目のように張り巡らされており、血液の状態に敏感に反応するのです。
体内のフィルターである腎臓の役割
腎臓は、血液をろ過して老廃物や余分な水分を尿として排泄する、体の高性能なフィルターで、この働きにより、血液は常にきれいに保たれ、体内の水分量やミネラルのバランスが適切に調整されています。
健康な体を維持するためには、腎臓が休むことなく働き続けることが重要です。腎臓の中には、糸球体(しきゅうたい)と呼ばれる毛細血管の塊が約100万個ずつあり、ここで血液がろ過されます。
糸球体を通過した原尿は、尿細管を通り、体に必要な水分や栄養素が再吸収された後、最終的に尿として排出されます。
腎臓が担う主な機能
| 機能 | 主な役割 | 体への影響 |
|---|---|---|
| 老廃物の排泄 | 血液中の不要な物質(尿素窒素など)を尿として捨てる | 体内に毒素が溜まる尿毒症を防ぐ |
| 水分・電解質の調整 | 体液の量やナトリウム、カリウムなどの濃度を一定に保つ | むくみや高血圧、不整脈を予防する |
| ホルモンの産生 | 血圧調整(レニン)、造血(エリスロポエチン)、骨の健康(活性型ビタミンD)に関わる | 貧血や骨粗しょう症、高血圧を防ぐ |
目と腎臓をつなぐ毛細血管
目、特に光を感じ取る網膜という部分は、無数の毛細血管から栄養や酸素を受け取っていて、腎臓の糸球体という、血液をろ過する部分の構造とよく似ています。
網膜はカメラのフィルムに相当する重要な組織で、特に視力の中心を担う黄斑部(おうはんぶ)は、体の中でも最も酸素消費量が多い場所の一つで、わずかな血流の滞りも視機能に大きな影響を与えます。
どちらも繊細な毛細血管の集まりであるため、血管にダメージを与える病気の高血圧や糖尿病の影響を同じように受けやすいのです。腎臓の血管に起きた変化は、目の血管にも起きている可能性が高いと考えられます。
腎機能低下が全身の血管に与える影響
腎臓の機能が低下すると、体内の水分や塩分の調整がうまくいかなくなり、血圧が上昇し、高血圧の状態が続くと、全身の血管、特に細い血管に常に高い圧力がかかり、血管の壁が硬くなる動脈硬化が進行します。
動脈硬化は、腎臓自体の血管をさらに傷つけ、腎機能を悪化させる悪循環を生むだけでなく、目の網膜にある細い血管にも損傷を与え、視力に影響を及ぼす原因となります。
さらに、腎機能が低下すると尿毒症性物質(ウレミックトキシン)が体内に蓄積し、このような物質は、血管の内側を覆う内皮細胞を傷つけ、酸化ストレスや炎症を起こすことで、動脈硬化を一層促進させることが分かっています。
腎機能低下は「高血圧」と「尿毒症性物質」という二つの側面から、全身の血管、ひいては目の血管にダメージを与え続けるのです。
腎臓の機能低下が引き起こす目の主な病気(合併症)
腎臓の機能が悪化すると、その影響は目の病気として現れることがあり、単なる視力の低下ではなく、治療が必要な専門的な疾患で、早期発見と適切な対応が、視力を守る鍵です。
高血圧が原因となる腎性網膜症
腎性網膜症は、腎機能の低下による高血圧が主な原因で、網膜の血管に異常が生じる病気です。
高血圧によって網膜の血管が収縮したり、壁が厚くなったりして血流が悪化し、進行すると、血管から血液の成分が漏れ出して網膜にむくみ(浮腫)や出血を起こしたり、血管が詰まって栄養が届かなくなり、網膜の機能が低下したりします。
眼底検査では、網膜の細い動脈がけいれんしたように細くなる「狭細化」や、動脈と静脈が交差する部分で動脈が静脈を圧迫する「交叉現象」が見られます。
さらに進行すると、血流が途絶えた部分に神経線維のむくみである「綿花様白斑(めんかようはくはん)」や、血液中の脂質が沈着した「硬性白斑(こうせいはくはん)」が出現します。
最も重篤な状態では、視神経の付け根である視神経乳頭がむくむ「乳頭浮腫」に至り、頭蓋内の圧力が亢進している可能性も示す危険なサインです。初期は自覚症状がほとんどありませんが、放置すると視力が著しく低下する危険があります。
腎性網膜症の進行度と主な所見
| 進行度(分類) | 主な眼底所見 | 自覚症状の目安 |
|---|---|---|
| 軽度 | 網膜動脈の狭細化、交叉現象 | ほとんどない |
| 中等度 | 網膜出血、綿花様白斑、硬性白斑 | かすみ目などを感じることがある |
| 重度 | 網膜浮腫、視神経乳頭浮腫 | 著しい視力低下、視野の異常 |
糖尿病と深く関わる糖尿病網膜症
糖尿病網膜症は、糖尿病の三大合併症の一つであり、日本の成人における失明原因の上位を占める深刻な病気で、高血糖の状態が続くことで、網膜の毛細血管が傷つき、変形したり詰まったりします。
腎臓病の中でも、糖尿病が原因で発症する糖尿病性腎症の患者さんは、糖尿病網膜症を合併していることが非常に多いです。腎症と網膜症は、どちらも糖尿病による血管障害が根本原因であるため、並行して進行する傾向があります。
網膜症は、血管が詰まって血流が途絶える「増殖前網膜症」へと進行し、さらに酸素不足を補うために「新生血管」という非常にもろく異常な血管が生えてくる「増殖網膜症」へと進みます。
新生血管は容易に出血(硝子体出血)を起こしたり、増殖膜という膜を形成して網膜を引っ張り、網膜剥離を引き起こしたりする失明の直接的な原因となります。
糖尿病網膜症の主な段階
- 単純網膜症
- 増殖前網膜症
- 増殖網膜症
動脈硬化が網膜に及ぼす影響
腎機能が低下している方は、動脈硬化が進行しやすい状態にあり、動脈硬化は全身の血管に影響を与えますが、目の奥にある網膜の血管も例外ではありません。
網膜の動脈が硬くなると、静脈との交差部分で動脈が静脈を圧迫し、血流を妨げることがあり、網膜静脈閉塞症という病気を起こし、網膜の広範囲に出血やむくみが生じ、急激な視力低下を招くことがあります。
また、まれではありますが、動脈硬化によってできた血栓などが網膜の動脈に詰まる網膜動脈閉塞症を発症することもあります。
これは網膜の神経細胞に栄養が届かなくなるため、突然の無痛性の高度な視力障害が生じる、非常に緊急性の高い病気です。
その他の関連する目の病気
腎臓病の治療では、ステロイド薬や免疫抑制剤を使用することがあり、ステロイド薬の長期使用は、眼圧を上昇させ緑内障のリスクを高めたり、水晶体が濁る白内障を進行させたりする副作用が知られています。
また、透析治療を受けている方は、体内の水分量が急激に変動するため眼圧が不安定になりやすく、注意が必要です。
さらに、腎機能低下に伴うカルシウムやリンの代謝異常が、水晶体や角膜にカルシウムを沈着させ、白内障や角膜混濁の原因となることもあります。
特に注意したい腎臓と目の関係が深い病気
すべての腎臓病が同じように目に影響を与えるわけではありません。中には、特に目の合併症を起こすリスクが高い病気があり、それは、腎臓だけでなく全身の血管にダメージを与える生活習慣病です。
糖尿病性腎症と目の合併症
糖尿病性腎症は、糖尿病が原因で腎臓の機能が徐々に低下していく病気で、糖尿病は網膜の血管にも深刻なダメージを与え、糖尿病網膜症を起こします。
糖尿病性腎症が進行して透析が必要になる方の多くは、すでに網膜症もかなり進行しているケースが少なくありません。血糖コントロールは、腎臓と目の両方を守るために極めて重要です。
食後の血糖値が急上昇する「血糖スパイク」は、血管に大きなダメージを与える活性酸素を大量に発生させ、合併症の進行を早めることが知られていて、平均的な血糖値を示すHbA1cだけでなく、日々の血糖値の変動にも注意を払うことが大切です。
糖尿病の三大合併症
| 合併症 | 障害される部位 | 主な症状 |
|---|---|---|
| 糖尿病網膜症 | 目の網膜(毛細血管) | 視力低下、飛蚊症、失明 |
| 糖尿病性腎症 | 腎臓(糸球体) | むくみ、タンパク尿、腎不全 |
| 糖尿病神経障害 | 末梢神経 | 手足のしびれ、痛み、感覚麻痺 |
腎硬化症と高血圧網膜症
腎硬化症は、長期間にわたる高血圧や加齢によって腎臓の動脈硬化が進行し、腎機能が低下する病気で、根本原因である高血圧と動脈硬化は、そのまま目の網膜にも影響を及ぼします。
高血圧によって網膜の血管が傷つく状態は高血圧網膜症と呼ばれ、これは腎性網膜症とほぼ同じ病態で、血圧の管理は、腎硬化症の進行を抑えるだけでなく、目の健康を守る上でも非常に大切です。
特に、夜間や早朝に血圧が高くなる「夜間高血圧」「早朝高血圧」は、日中の血圧が正常でも腎臓や心臓、目の血管に大きな負担をかけることが分かっています。
診察室での血圧測定だけでなく、家庭で血圧を測定し、自分の血圧パターンを把握することが重要です。
慢性糸球体腎炎と目の関係
慢性糸球体腎炎は、血液をろ過する糸球体に慢性的な炎症が起こる病気の総称で、代表的なものがIgA腎症などです。
この病気自体が直接的に目の病気を引き起こすことは少ないですが、病気が進行して腎機能が低下したり、高血圧を合併したりすると、腎性網膜症などを発症するリスクが高まります。
また、ネフローゼ症候群を呈するようなタイプでは、血液が固まりやすくなるため、網膜の血管が詰まる網膜静脈閉塞症などのリスクが上昇する可能性も指摘されています。
治療にステロイド薬などを用いる場合、副作用として緑内障や白内障に注意が必要です。
自分で気づける?目の異常を示すサイン
目の病気の多くは、初期段階では自覚症状が現れにくいのが特徴であるものの、注意深く観察すれば、体からの小さなSOSサインに気づくことができます。
腎臓の治療を受けている方は、これから挙げるような症状に特に注意を払い、少しでも変化を感じたら放置しないことが重要です。
初期段階で見られる目の症状
腎臓病に関連する目の合併症は、静かに進行しますが、以下のような症状が初期サインとして現れることがあります。一時的なものと感じて見過ごしてしまいがちですが、重要な警告かもしれません。
小さな虫のようなものが見える飛蚊症は、加齢による生理的なものがほとんどですが、急に数が増えたり、大きな影が見えたりした場合は、網膜の出血や網膜裂孔のサインである可能性があり、注意が必要です。
注意すべき初期の目のサイン
- 目がかすむ(特に朝方)
- 視力が落ちたように感じる
- 小さな虫やゴミのようなものが飛んで見える(飛蚊症)
- 物がゆがんで見える(変視症)
症状が進行した場合のサイン
病状がさらに進行すると、よりはっきりとした症状が現れるようになり、症状は、網膜の出血やむくみが悪化している可能性を示唆しています。
糖尿病網膜症で硝子体出血が起こると、突然視界にインクを垂らしたような影や、カーテンがかかったような影が現れ、網膜の中心である黄斑部にむくみが生じると、物がゆがんで見える変視症や、中心部が暗く見える中心暗点が現れます。
この段階になると、日常生活に支障をきたすことも多く、早急な対応が必要です。
進行期に見られる目のサイン
| 症状 | 考えられる原因 | 危険度 |
|---|---|---|
| 急激な視力低下 | 網膜中心部の浮腫(黄斑浮腫)、硝子体出血 | 高い |
| 視野の一部が欠ける・カーテンがかかる | 網膜の血流障害、網膜剥離、硝子体出血 | 高い |
| 目の痛み、充血、頭痛 | 血管新生緑内障による急激な眼圧上昇 | 非常に高い |
自覚症状がない場合でも安心は禁物
最も注意すべき点は、かなりの程度まで病気が進行するまで、全く自覚症状がない場合も多いということです。特に、片方の目の視力が良好な場合、もう片方の目に異常があっても脳が情報を補ってしまうため、気づきにくいことがあります。
症状がないからといって安心せず、腎臓の治療と並行して、定期的に目の検査を受ける習慣が、視力を守るためには何よりも大切です。
日常生活の中で、方眼紙やタイルの目地など、直線的なものを見て、線がゆがんだり途切れたりして見えないかを確認するのも有効で、これはアムスラーチャートと呼ばれる検査を簡略化したもので、黄斑部の異常を早期に発見するのに役立ちます。
セルフチェックのポイント
日常生活の中で、簡単にできるセルフチェックがあります。片方の目を手で隠し、カレンダーの数字や遠くの景色が左右の目で見え方に違いがないかを確認してみましょう。
少しでも「見え方が違うな」「ゆがんで見えるな」と感じたら、専門医に相談するきっかけになります。
目の健康を守るために腎臓のためにできること
目の合併症を防ぐための特別な方法はなく、最も効果的な対策は、原因となっている腎臓病の進行を抑えることです。腎臓の状態を安定させることが、結果的に目の健康を守ることにつながります。
すべての基本となる原因疾患の管理
目の合併症の根本原因は、腎臓病を起こしている高血圧や糖尿病にあり、原因疾患をしっかりと管理することが、何よりも優先されます。
医師の指示に従って、降圧薬や血糖降下薬を正しく服用し、血圧と血糖値を目標範囲内にコントロールすることが治療の基本です。
薬は、効果と副作用のバランスを見ながら調整していくもので、自己判断で薬の量を減らしたり、服用を中止したりすることは、病状の急激な悪化を招く可能性があり、非常に危険です。疑問や不安があれば、必ず医師や薬剤師に相談しましょう。
血圧と血糖値の管理目標(一般的な例)
| 項目 | 管理目標値 | ポイント |
|---|---|---|
| 診察室血圧 | 130/80 mmHg未満 | 家庭血圧も記録し医師に伝える(特に早朝血圧) |
| HbA1c(ヘモグロビンA1c) | 7.0%未満 | 合併症予防のための目標値。年齢や状態により個別設定。 |
食事療法による体内環境の改善
食事療法は、腎臓病治療の重要な柱です。腎臓への負担を減らし、血圧や血糖をコントロールすることで、血管へのダメージを軽減します。
塩分の過剰摂取は体液量を増やし血圧を上げる最大の要因であるため、減塩(1日6g未満目標)は非常に重要で、また、タンパク質の過剰摂取は、腎臓の糸球体に負担をかけ、腎機能の低下を早めるため、病状に応じて摂取制限が必要です。
食事療法は、腎臓の負担を直接的に減らすだけでなく、血圧を安定させ、動脈硬化の進行を抑制する効果があり、間接的に目の血管を守ることにもつながります。
管理栄養士と相談しながら、ご自身の病状に合った食事プランを立て、継続することが大切です。
食事療法の主なポイント
- 減塩(出汁の活用、香辛料の利用など工夫する)
- タンパク質の摂取制限(医師・管理栄養士の指示量を守る)
- カリウム、リンの制限(腎機能に応じて)
- 適切なエネルギー量の確保(エネルギー不足は筋肉の分解を招き、腎臓に負担をかける)
生活習慣の見直しと改善
日々の生活習慣を見直すことも、腎臓と目を守る上で大きな力となり、ウォーキングなどの有酸素運動は、血圧や血糖値の改善に役立ち、血流を促進する効果が期待できます。
ただし、腎機能や心臓の状態によっては運動が制限される場合もあるため、必ず医師に相談してから始めましょう。
また、喫煙は血管を収縮させて血流を悪化させ、酸化ストレスを増大させることで動脈硬化を著しく促進し、腎臓と目の健康にとって百害あって一利なしですので、禁煙は必須です。
十分な睡眠やストレス管理も、自律神経やホルモンバランスを整え、血圧の安定につながるため、全身の健康状態を良好に保つために役立ちます。
目の異常に気づいたら何科を受診するべきか
「もしかして目の調子が悪いかも…」と感じたとき、すぐに相談できる場所を知っておくことは大きな安心につながります。
腎臓病の治療を受けている方の場合、自己判断で眼科に行くだけでなく、まずはかかりつけの医師と情報を共有することが非常に重要です。
まずはかかりつけの腎臓内科医に相談
目の異常に気づいたら、最初に相談すべきは、ご自身の腎臓の状態を最もよく理解しているかかりつけの腎臓内科医です。
なぜなら、目の症状が全身状態、特に血圧や血糖、貧血、体液量のコントロール状況と密接に関連している可能性があるからです。
腎臓内科医はこれらの情報を踏まえ、どのような目の病気が考えられるか、どのタイミングで眼科を受診すべきかを的確に判断してくれます。
また、必要であれば、腎臓病患者の診療経験が豊富な眼科医や、連携している信頼できる眼科医を紹介してもらうこともできます。
腎臓内科と眼科の連携の重要性
腎臓病に関連する目の病気の治療は、腎臓内科と眼科が密に連携して進めることが大切です。眼科医は目の状態を専門的に診断し、レーザー治療や薬物治療などを行いますが、効果を最大限に引き出すには、腎臓内科での全身管理が欠かせません。
眼科で黄斑浮腫の治療を行っても、腎臓内科での血圧や血糖のコントロールが不良であれば、すぐに再発してしまいます。
また、眼科で使用する造影剤や一部の点眼薬が腎臓や全身に影響を及ぼすこともあるため、両方の医師が患者さんの情報を共有し、治療方針をすり合わせることで、安全で効果的な治療が可能になります。
診療科の役割分担
| 診療科 | 主な役割 | 検査・治療の例 |
|---|---|---|
| 腎臓内科 | 全身状態の管理、原因疾患(高血圧・糖尿病など)の治療 | 血液検査、尿検査、血圧・血糖管理、食事指導、薬物療法 |
| 眼科 | 目の状態の専門的な診断と治療 | 視力検査、眼圧検査、眼底検査、光干渉断層計、レーザー治療、硝子体注射 |
定期的な眼科検診のすすめ
腎臓病、特に糖尿病性腎症や腎硬化症と診断されたら、自覚症状がなくても定期的に眼科を受診することが強く推奨されます。
目の合併症は、かなり進行するまで症状が出ないことが多いため、眼底検査などで網膜の状態を定期的にチェックすることで、異常を早期に発見し、深刻な視力障害に至る前に対処を始めることができます。
推奨される検診頻度は病状によって異なりますが、一般的に糖尿病で腎症を合併している場合は年に数回、高血圧の場合は少なくとも年に1回は、眼科での詳しい検査を受けるように心がけましょう。
受診時に伝えるべき情報
- 診断されている腎臓病名(例:糖尿病性腎症、腎硬化症など)
- 最近の血液検査(eGFR、HbA1cなど)や尿検査の結果
- 血圧や血糖値の普段の値(家庭血圧手帳などがあれば持参)
- 服用しているすべての薬(お薬手帳を持参)
よくある質問
最後に、腎臓と目の関係について、患者さんからよく寄せられる質問と回答をまとめました。
- 透析を始めれば目の症状は改善しますか
-
透析療法は、低下した腎臓の機能の一部を代替し、体内の老廃物や余分な水分を取り除く治療法です。
腎性網膜症の原因である高血圧や体液過剰の状態が改善され、網膜のむくみが軽減し、症状の進行が緩やかになることは期待できますが、一度傷ついてしまった網膜の血管が完全に元に戻るわけではありません。
糖尿病網膜症が進行している場合、透析導入による急激な血糖値の改善や血圧の変動が、一時的に網膜症を悪化させることもあり注意が必要です。透析を始めた後も、眼科での定期的な検査と治療を継続することが重要です。
- 腎臓移植をすれば視力は回復しますか
-
腎臓移植が成功し、腎機能が正常化すれば、高血圧や体内の環境は大きく改善し、腎性網膜症の進行を食い止め、さらなる悪化を防ぐ効果は期待できます。
しかし、透析と同様に、すでに網膜に生じてしまった不可逆的なダメージ(血管の閉塞や神経の損傷など)を元に戻すことは困難です。視力がどの程度回復するかは、移植前の網膜の状態によります。
また、移植後は感染症などを防ぐために免疫抑制剤を服用しますが、副作用で感染症にかかりやすくなったり、糖尿病や白内障を発症したりすることもあるため、移植後も眼科での定期的なフォローアップは必要です。
- 目の検査ではどのようなことをするのですか
-
腎臓病に関連する目の合併症を調べるために、眼科ではいくつかの重要な検査を行い、最も基本的なものは、視力検査と眼圧検査です。それに加えて、最も重要なのが眼底検査です。
これは、点眼薬で瞳孔を開き(散瞳)、検眼鏡や眼底カメラを使って網膜の血管や視神経の状態を直接観察する検査です。
散瞳薬を点眼すると、4〜5時間ほど光がまぶしく感じたり、ピントが合いにくくなったりするため、検査当日は車の運転はできません。
この検査により、網膜の出血、むくみ、白斑などの有無や程度が分かり、病気の診断や進行度の評価に役立ちます。
必要に応じて、網膜の断面を撮影してむくみの状態を詳しく調べる光干渉断層計(OCT)や、腕の静脈から造影剤を注入して網膜の血流を調べる蛍光眼底造影を行うこともあります。
- 食生活で特に目に良い食べ物はありますか
-
特定の食品を食べれば目の病気が治る、というものはありませんが、目の健康維持に役立つとされる栄養素はいくつかあります。
ホウレンソウやブロッコリーなどの緑黄色野菜に多く含まれるルテインや、ブルーベリーに含まれるアントシアニンなどは、抗酸化作用があり、網膜を保護する働きが期待されています。
ただし、腎臓病で食事療法を行っている方は注意が必要です。
これらの野菜や果物にはカリウムが多く含まれている場合があり、腎機能によっては摂取が制限され、目のためによかれと思って食べたものが、腎臓に負担をかけてしまうこともあり得ます。
どのような食品がご自身の状態に適しているか、必ずかかりつけの医師や管理栄養士に相談してから取り入れてください。
以上
参考文献
Fukuoka H, Nagaya M, Toba K. The occurrence of visual and cognitive impairment, and eye diseases in the super-elderly in Japan: a cross-sectional single-center study. BMC research notes. 2015 Oct 29;8(1):619.
Wakasugi M, Yokoseki A, Wada M, Yoshino T, Momotsu T, Sato K, Kawashima H, Nakamura K, Fukuchi T, Onodera O, Narita I. Cataract Surgery and Chronic Kidney Disease: A Hospital-based Prospective Cohort Study. Internal Medicine. 2024 May 1;63(9):1207-16.
Wong CW, Lamoureux EL, Cheng CY, Cheung GC, Tai ES, Wong TY, Sabanayagam C. Increased burden of vision impairment and eye diseases in persons with chronic kidney disease—a population-based study. EBioMedicine. 2016 Mar 1;5:193-7.
Kimura M, Toyoda M, Saito N, Abe M, Kato E, Sugihara A, Ishida N, Fukagawa M. A Survey on the Current Status of Ophthalmological Consultations in Patients With Diabetes Undergoing Maintenance Hemodialysis and the Effectiveness of Education on Consultation Behavior–Experience of a Single Hemodialysis Clinic in Japan. Frontiers in Clinical Diabetes and Healthcare. 2022 Jan 26;2:827718.
Mullaem G, Rosner MH. Ocular problems in the patient with end‐stage renal disease. InSeminars in dialysis 2012 Jul (Vol. 25, No. 4, pp. 403-407). Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd.
Nusinovici S, Sabanayagam C, Teo BW, Tan GS, Wong TY. Vision impairment in CKD patients: epidemiology, mechanisms, differential diagnoses, and prevention. American journal of kidney diseases. 2019 Jun 1;73(6):846-57.
Zhu Z, Liao H, Wang W, Scheetz J, Zhang J, He M. Visual impairment and major eye diseases in chronic kidney disease: the National Health and Nutrition Examination Survey, 2005-2008. American journal of ophthalmology. 2020 May 1;213:24-33.
Jonas JB, Wang YX, Wei WB, Xu J, You QS, Xu L. Chronic kidney disease and eye diseases: The Beijing eye study. Ophthalmology. 2017 Oct 1;124(10):1566-9.
Chen H, Zhang X, Shen X. Ocular changes during hemodialysis in patients with end-stage renal disease. BMC ophthalmology. 2018 Aug 23;18(1):208.
Okolo OE, Omoti AE. Ocular manifestations of chronic kidney disease among adult patients receiving hemodialysis. Expert Review of Ophthalmology. 2012 Dec 1;7(6):517-28.