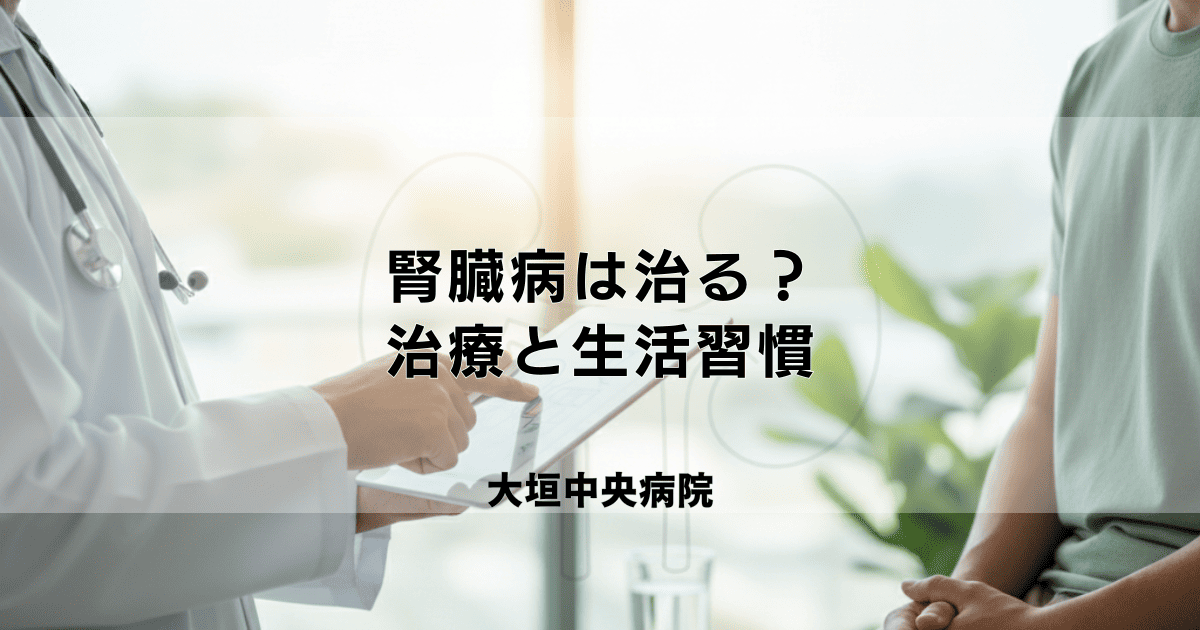健康診断で腎臓の数値を指摘されたり、ご家族が腎臓病と診断されたりしたとき、腎臓病は治るのだろうかという大きな不安を抱えることでしょう。腎臓は一度悪くなると回復しないという話を耳にしたことがあるかもしれません。
進行してしまった慢性腎臓病を完全に元の状態に戻すことは現代の医療でも難しいのが現実ですが、すべての腎臓病が治らないわけではありません。
この記事では、腎臓病の回復の可能性、進行を抑えるための治療法、日常生活で実践できることについて、分かりやすく解説していきます。
そもそも腎臓病とは?沈黙の臓器が発するサイン
腎臓は体の健康を維持するために、休むことなく働き続ける重要な臓器です。機能が静かに低下していく腎臓病の全体像を掴むことから始めましょう。
腎臓の働きと重要性
腎臓は、腰のあたりに左右一つずつある、そら豆のような形をした臓器で、主な働きは、血液をろ過して体内の老廃物や余分な水分、塩分を尿として排出することです。
ろ過機能は、体内の水分量やミネラルのバランスを一定に保つために極めて重要です。
それだけでなく、腎臓は血圧を調整するホルモンや、赤血球を作ることを促すホルモンを分泌したり、骨を丈夫にするビタミンDを活性化させたりと、多彩な役割を担っています。
腎臓の主な役割
| 役割 | 内容 | 機能が低下した場合の影響 |
|---|---|---|
| 老廃物の排出 | 血液中の不要な物質を尿として体外に出す | 尿毒症(だるさ、吐き気、食欲不振など) |
| 水分・電解質の調整 | 体内の水分量やミネラルバランスを保つ | むくみ、高血圧、不整脈 |
| ホルモンの分泌 | 血圧調整や造血に関わるホルモンを作り出す | 高血圧、貧血 |
急性腎障害と慢性腎臓病の違い
腎臓病は、発症の仕方によって大きく二つに分けられ、一つは数時間から数日の間に急激に腎機能が低下する急性腎障害(AKI)で、もう一つは数か月から数年かけてゆっくりと腎機能が低下していく慢性腎臓病(CKD)です。
急性腎障害は、脱水や薬剤、急な血圧低下などが原因で起こることが多く、原因を速やかに取り除くことで腎機能の回復が見込める場合があります。
慢性腎臓病は、糖尿病や高血圧などの生活習慣病が原因となることが多く、残念ながら一度失われた腎機能が元に戻ることはほとんどありません。治療の目標は、残された腎機能をできるだけ長く維持し、病気の進行を遅らせることです。
なぜ腎臓病は気づきにくいのか
腎臓は沈黙の臓器とも呼ばれ、機能がかなり低下するまで自覚症状がほとんど現れず、これは、腎臓が持つ予備能力の高さによるものです。
腎機能が正常の半分程度まで低下しても、残りの部分が懸命に働くため、体調の変化を感じにくく、症状がないからといって安心はできません。
気づかないうちに病状は静かに進行し、むくみや貧血、だるさといった症状が現れたときには、すでに腎機能が大幅に低下しているケースが少なくありません。
腎機能が低下すると現れる症状
初期の段階ではほとんど無症状ですが、病状が進むにつれて以下のような症状が見られるようになります。
症状は他の病気でも見られるものですが、複数が当てはまる場合は注意が必要です。もし気になる症状があれば、医療機関を受診してください。
- 尿の変化(夜間の頻尿、泡立ち)
- むくみ(足、まぶた)
- 貧血(めまい、立ちくらみ、動悸)
- 体のだるさ、疲れやすさ
- 食欲不振、吐き気
腎臓病は治る?治らない?病状による回復の見込み
腎臓病には急激に発症するものと、ゆっくり進行するものがあり、回復の見込みも異なります。ここでは、それぞれの病状について、回復の可能性を詳しくみていきます。
回復が見込める急性腎障害
急性腎障害は、何らかの原因によって腎臓への血流が急に減少したり、腎臓そのものがダメージを受けたりすることで発症します。
原因は様々ですが、代表的なものには、激しい下痢や嘔吐による脱水、特定の薬剤の副作用、心不全による血圧低下などがあります。
急性腎障害の大きな特徴は、原因となった問題を迅速に治療すれば、腎機能が回復する可能性がある点です。脱水が原因であれば点滴で水分を補給し、薬剤が原因であればその使用を中止します。
初期対応が早ければ早いほど、腎機能が元の状態に戻る可能性は高まります。ただし、治療が遅れたり、腎臓へのダメージが大きすぎたりした場合には、機能が完全には回復せず、慢性腎臓病へ移行することもあるため油断は禁物です。
急性腎障害の主な原因
| 分類 | 原因の例 | 対応 |
|---|---|---|
| 腎前性 | 脱水、出血、心不全、ショック | 輸液、輸血、原因疾患の治療 |
| 腎性 | 薬剤性、急性糸球体腎炎、血管炎 | 原因薬剤の中止、ステロイド治療 |
| 腎後性 | 尿路結石、前立腺肥大症、がん | 尿路の閉塞解除 |
残念ながら完治が難しい慢性腎臓病
慢性腎臓病(CKD)は、腎臓の障害が3か月以上持続している状態を指し、多くの場合、ゆっくりと進行し、高血圧や糖尿病、脂質異常症といった生活習慣病や、慢性糸球体腎炎などが主な原因です。
慢性腎臓病では、腎臓の組織が徐々に硬くなり、ろ過機能を持つ糸球体が壊れていきます。一度壊れてしまった組織は再生しないため、失われた腎機能を元に戻すことは現在の医療では困難です。
しかし、治療を継続し、生活習慣を改善することで、腎機能の低下速度を緩やかにし、健康な人と変わらない生活を長く続けることができます。
慢性腎臓病でも早期発見が重要な理由
慢性腎臓病の治療は、残された腎機能を守り、末期腎不全への進行を遅らせるために非常に重要で、腎機能が低下すればするほど、進行を食い止めるのは難しいです。
早期の段階で発見し治療を開始すれば、腎臓への負担を減らし、機能低下のスピードを格段に遅らせることができます。また、慢性腎臓病は心筋梗塞や脳卒中といった心血管疾患の大きなリスク要因です。
腎臓を守る治療は、同時に命に関わる病気を予防することにもつながり、自覚症状のない早い段階で病気を見つけるために、定期的な健康診断が大きな意味を持ちます。
自分の腎臓の状態を知るための検査とステージ分類
腎臓病の治療方針を立てる上で、現在の腎機能がどの程度保たれているのかを正確に把握することが第一歩です。腎臓の状態は、主に尿検査と血液検査によって評価します。
腎機能を確認する主な検査
腎臓の状態を調べる検査は、体への負担が少ないものが中心で、健康診断でも行われる基本的な検査で、多くの情報が得られます。
尿検査
尿検査では、尿中にタンパク質や血液が漏れ出ていないかを調べます。
健康な腎臓では、血液中のタンパク質のような大きな物質はろ過されずに体内にとどまりますが、腎臓に障害があると、網の目が壊れてタンパク質が尿中に漏れ出してしまいます。
尿タンパクは、腎臓がダメージを受けていることを示す重要なサインです。
血液検査(eGFR)
血液検査では、血中のクレアチニン(Cr)という老廃物の値を測定します。
クレアチニンは筋肉で作られる老廃物で、通常は腎臓でろ過され尿中に排出されますが、腎機能が低下すると、クレアチニンを十分に排出できなくなり、血液中に溜まっていきます。
血清クレアチニン値と年齢、性別から算出されるのが、推算糸球体ろ過量(eGFR)です。
eGFRは、腎臓が1分間にどれくらいの血液をろ過できるかを示しており、腎機能の指標として広く用いられていて、数値が低いほど、腎機能が低下していることを意味します。
慢性腎臓病(CKD)のステージとは
慢性腎臓病は、腎機能の指標であるeGFRの値によって、ステージG1からG5までの5段階に分類され、ステージ分類により、病状の進行度を客観的に評価し、それぞれの段階に応じた治療目標を設定することができます。
CKD重症度分類(GFR区分)
| ステージ | eGFR (mL/分/1.73㎡) | 腎機能の状態 |
|---|---|---|
| G1 | 90以上 | 正常または高値 |
| G2 | 60~89 | 正常または軽度低下 |
| G3a | 45~59 | 軽度~中等度低下 |
| G3b | 30~44 | 中等度~高度低下 |
| G4 | 15~29 | 高度低下 |
| G5 | 15未満 | 末期腎不全(ESKD) |
※G1、G2であっても、尿タンパクなどの腎障害を示す所見があれば慢性腎臓病と診断されます。
ステージごとの特徴と治療目標
ステージが軽度(G1、G2)の場合は、腎機能低下の原因となっている生活習慣病(高血圧、糖尿病など)の管理や生活習慣の改善が治療の中心で、ステージG3以降は、腎臓専門医による治療が必要となる段階です。
G3a、G3bでは、食事療法や薬物療法を本格的に開始し、腎機能低下を抑制するとともに、貧血やミネラル異常といった合併症の管理も行います。
G4になると、腎機能の低下がさらに進み、将来的な腎代替療法(透析や腎移植)の準備も視野に入れた治療計画が必要になります。
G5は末期腎不全と呼ばれ、自身の腎臓だけでは生命を維持することが困難になるため、腎代替療法が必要となる段階です。
慢性腎臓病の進行を遅らせるための基本的な治療
慢性腎臓病の治療は、病気を完治させることではなく、残っている腎機能を大切に使い、できるだけ長く維持することに主眼が置かれます。
薬物療法、食事療法、運動療法を三つの柱として、総合的に取り組んでいくことが大切で、また、腎臓病の原因となっている疾患があれば、その治療も並行して行います。
薬物療法によるアプローチ
腎臓を守るための薬物療法は多岐にわたり、最も重要なものの一つが、血圧の管理です。高血圧は腎臓に大きな負担をかけるため、降圧薬を用いて血圧を厳格にコントロールします。
アンジオテンシン変換酵素(ACE)阻害薬やアンジオテンシンII受容体拮抗薬(ARB)は、血圧を下げる作用に加えて腎臓を保護する作用も期待できるため、よく用いられます。
また、近年ではSGLT2阻害薬という種類の糖尿病治療薬にも、強力な腎保護効果があることが分かり、糖尿病の有無にかかわらず使用されるようになっています。
その他、貧血を改善するための造血ホルモン製剤や、血液中のリンを吸着して排出を促す薬、体内の酸性度を調整する薬など、病状に応じて様々な薬が使われます。
食事療法による腎臓への負担軽減
食事療法は、薬物療法と並ぶ慢性腎臓病治療の重要な柱で、食事の内容を工夫することで、腎臓への負担を直接的に減らすことができ、主なポイントは、塩分、タンパク質、カリウム、リンの制限です。
特に塩分の制限は、血圧をコントロールし、むくみを改善するために非常に重要で、タンパク質の制限は、体内で老廃物(尿毒素)が作られるのを抑え、腎臓の負担を軽くします。
ただし、制限の度合いは、病気のステージや個人の状態によって大きく異なり、自己流で極端な食事制限を行うと、栄養失調を招きかねません。必ず医師や管理栄養士の指導のもとで行うことが大事です。
運動療法で目指す体づくり
かつては腎臓病の患者さんは安静第一と考えられていましたが、現在では適度な運動が推奨されています。ウォーキングや軽いジョギングなどの有酸素運動は、血圧や血糖値の改善、体重管理に役立ち、心血管疾患の予防にもつながります。
また、筋力を維持することは、日常生活の質(QOL)を保つ上で重要です。ただし、過度な運動はかえって腎臓に負担をかける可能性もあるので、運動を始める前には必ず主治医に相談し、自分に合った運動の種類や強度を決めましょう。
運動療法の注意点
- 始める前に必ず主治医に相談する
- 体調の良い日に行う
- 準備運動と整理運動を忘れない
- 無理のない範囲で継続する
原因となる疾患の治療(高血圧・糖尿病など)
慢性腎臓病の進行を抑えるためには、原因となっている病気の治療が不可欠です。日本人に最も多い原因は糖尿病(糖尿病性腎症)で、次いで高血圧(腎硬化症)が挙げられます。
糖尿病が原因の場合は、血糖値を良好にコントロールすることが腎症の進行を防ぐ最も有効な手段で、食事療法、運動療法、薬物療法を組み合わせて、目標とする血糖管理を目指します。
高血圧が原因の場合は、降圧薬と減塩を中心とした生活習慣の改善で、厳格な血圧管理を行います。
腎臓病の主な原因疾患
| 原因疾患 | 主な治療法 | 目標 |
|---|---|---|
| 糖尿病 | 食事療法、運動療法、薬物療法 | 血糖コントロール(HbA1cなど) |
| 高血圧 | 減塩、運動、降圧薬 | 厳格な血圧コントロール |
| 慢性糸球体腎炎 | ステロイド、免疫抑制薬など | 腎炎の活動性を抑える |
腎臓をいたわる生活習慣のポイント
慢性腎臓病の進行を抑制し、残された腎機能を長持ちさせるためには、日々の生活習慣を見直すことが治療と同じくらい重要です。ここでは、腎臓をいたわるために特に意識したい生活習慣のポイントを紹介します。
適正な血圧の維持
高血圧は、腎臓の細い血管に常に高い圧力をかけ、動脈硬化を促進させることで腎機能を悪化させる最大の要因の一つです。
腎臓病の治療では、家庭で測定する血圧を125/75mmHg未満(高齢者の場合は135/85mmHg未満など、目標値は個別に設定)に保つことが推奨されています。
血圧を管理するためには、医師から処方された降圧薬をきちんと服用することに加え、食事での減塩が欠かせません。また、肥満の解消、適度な運動、ストレス管理なども血圧の安定に役立ちます。
毎日決まった時間に家庭で血圧を測定し、記録する習慣をつけることが、良好なコントロールへの第一歩です。
血糖値のコントロール
糖尿病は慢性腎臓病の最大の原因で、高血糖の状態が続くと、腎臓のフィルター役である糸球体がダメージを受け、ろ過機能が徐々に低下していきます。
糖尿病性腎症の進行を防ぐためには、血糖値をできるだけ正常に近い範囲で安定させることが最も重要です。食事療法や運動療法を基本とし、必要に応じて経口血糖降下薬やインスリン注射などの薬物療法を行います。
定期的に医療機関を受診し、血糖値やヘモグロビンA1c(過去1〜2か月の血糖値の平均を反映する指標)の推移を確認しながら、治療方針を調整していきます。
禁煙と節度ある飲酒
喫煙は、血管を収縮させて血圧を上昇させるだけでなく、血管の内壁を傷つけて動脈硬化を進行させます。このことは腎臓の血管にも当てはまり、喫煙は腎機能低下の独立した危険因子であることが知られています。
腎臓を守るためには、禁煙が強く推奨され、自力での禁煙が難しい場合は、禁煙外来などを利用するのも一つの方法です。
また、過度の飲酒は高血圧や肥満の原因となり、間接的に腎臓に負担をかけるので、飲酒は節度ある量にとどめるように心がけましょう。
生活習慣改善のチェックリスト
- 毎日、血圧を測定し記録しているか
- 塩分を控えた食事を心がけているか
- タバコを吸っていないか
- 適度な運動を習慣にできているか
- 体重が増えすぎていないか
体重管理と定期的な運動
肥満、特に内臓脂肪が増えると、血圧や血糖値、脂質の値が悪化しやすくなり、腎臓に負担がかかるので、適正な体重を維持することは、危険因子をまとめて改善する効果が期待できます。
体重管理の基本は、食事で摂取するエネルギー量と、運動で消費するエネルギー量のバランスを整えることです。
ウォーキングや水泳などの有酸素運動を週に3〜5日、1回30分程度行うのがおすすめで、運動は気分転換やストレス解消にもなり、治療を継続していく上でのモチベーション維持にもつながります。
腎臓病の食事療法で押さえておきたいこと
腎臓病の治療において、食事療法は非常に重要な役割を担い、食事の内容を管理することで、腎臓の負担を減らし、病気の進行を遅らせることができます。
塩分制限でむくみと高血圧を改善
塩分(ナトリウム)の摂り過ぎは、体内に水分を溜め込み、むくみや高血圧の大きな原因となります。腎機能が低下すると、余分な塩分を尿として排出する能力が落ちるため、より厳格な管理が必要です。
慢性腎臓病の食事療法では、1日の塩分摂取量を6g未満に抑えることが目標とされ、加工食品や外食には多くの塩分が含まれているため、注意してください。
香辛料や香味野菜、だしなどを上手に活用して、薄味でも美味しく食べられる工夫をすることが、減塩を長続きさせるコツです。
減塩の工夫
| ポイント | 具体例 |
|---|---|
| 香りを活かす | ハーブ、スパイス、ごま、しそ、みょうがなどを利用する |
| 酸味を活かす | 酢、レモン、すだちなどの柑橘類の酸味で味を引き締める |
| うま味を活かす | 昆布やきのこ、鰹節などで取っただしを基本にする |
タンパク質制限で老廃物を減らす
タンパク質は体を作る上で大切な栄養素ですが、体内で利用された後に老廃物(尿素窒素など)となって腎臓から排出されます。
腎機能が低下している状態でタンパク質を摂り過ぎると、老廃物が体内に蓄積し、尿毒症の症状を起こす原因となるため、腎機能の低下が進んだステージ(主にG3以降)では、タンパク質の摂取量を制限することがあります。
1日あたりの目標量は、標準体重あたり0.6〜0.8gなど、病状に応じて細かく設定されます。
肉や魚、卵、大豆製品などのタンパク質を多く含む食品の量を調整する一方で、エネルギー不足にならないよう、ご飯やパン、油などでしっかりとカロリーを確保することが重要です。
カリウムやリンの摂取量に注意
カリウムやリンは、体に必要なミネラルですが、腎機能が低下すると体外へうまく排出できなくなり、血液中に溜まりやすくなります。
血中のカリウム値が高くなりすぎると、不整脈など命に関わる状態を起こすことがあり、また、リンの値が高い状態が続くと、骨がもろくなったり、血管の石灰化を進めて動脈硬化を悪化させたりします。
腎機能の低下が進むと、カリウムやリンの摂取制限も必要です。カリウムは生の野菜や果物、いも類に、リンは乳製品や加工食品、魚卵などに多く含まれます。
カリウムを減らす調理のコツ
- 食材を細かく切る
- 水にさらす
- 茹でこぼす
水分摂取の考え方
腎臓が悪いと水分を控えるべき、というイメージがあるかもしれませんが、一概には言えません。腎機能がまだ比較的保たれている初期の段階では、脱水を防ぐために適度な水分摂取が勧められることもあります。
腎機能の低下が進行し、尿量が減ってきたり、むくみや心不全の症状が出たりした場合には、水分の摂取制限が必要です。1日の水分摂取量は、前日の尿量に発汗などを考慮した量を加えるなど、個々の状態に応じて決められます。
末期腎不全と診断された場合の治療法
様々な治療にもかかわらず、残念ながら腎機能の低下が進行し、eGFRが15未満になると末期腎不全と呼ばれる状態になります。
この段階では、自身の腎臓の働きだけでは体内の老廃物や余分な水分を十分に排出できなくなり、生命を維持することが困難になるため、失われた腎臓の機能を代替する治療、すなわち腎代替療法が必要です。
腎代替療法とは
腎代替療法には、大きく分けて血液透析、腹膜透析、そして腎移植の三つの選択肢があります。
どの治療法を選択するかは、医学的な状態はもちろんのこと、患者さん自身のライフスタイルや価値観、家族のサポート体制などを総合的に考慮して、医師や医療スタッフと十分に話し合って決定します。
それぞれの治療法にメリットとデメリットがあるため、内容をよく理解することが大切です。
腎代替療法の選択肢
| 治療法 | 場所 | 頻度・時間 |
|---|---|---|
| 血液透析 | 主に医療機関 | 週3回、1回4〜5時間 |
| 腹膜透析 | 主に自宅 | 毎日(終日または就寝中) |
| 腎移植 | – | – |
血液透析と腹膜透析
透析療法は、機械や特殊な膜を使って、腎臓の代わりに血液をきれいにする治療法です。
血液透析は、腕の血管にシャントと呼ばれる血液の出口・入口を作り、そこから血液を体外に取り出してダイアライザー(人工腎臓)という機械に通し老廃物を除去し、きれいになった血液を体内に戻す方法です。
通常、週に3回、専門の医療機関に通院して行います。一方、腹膜透析は、自分のお腹の中にある腹膜を利用する方法で、お腹にカテーテルという細い管を埋め込み、そこから透析液を注入します。
透析液がお腹の中にある間に、腹膜を介して血液中の老廃物や余分な水分が透析液に移動し、その液を体外に排出することで血液をきれいにし、主に自宅で行うことができ、通院は月に1〜2回程度です。
腎移植という選択
腎移植は、ドナー(臓器提供者)から提供された健康な腎臓を手術によって移植する方法で、腎機能を根本的に回復させることができる唯一の治療法です。
移植には、亡くなった方から腎臓の提供を受ける献腎移植と、親族などから提供を受ける生体腎移植があります。移植が成功すれば、透析療法から離脱でき、食事制限も大幅に緩和されるなど、生活の質が大きく向上します。
ただし、移植後も拒絶反応を抑えるために免疫抑制薬を生涯にわたって服用し続ける必要があり、また、ドナーが見つかるまでには長い待機期間が必要な場合があるなど、課題もあります。
腎臓病に関するよくある質問
最後に、腎臓病に関して多くの方が抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。
- 腎臓病は遺伝するのでしょうか?
-
一部の腎臓病、例えば多発性のう胞腎などは遺伝性がはっきりしています。ご家族に腎臓病の方がいる場合は医師に伝え、定期的に腎臓の検査を受けてください。
糖尿病や高血圧が原因となる腎臓病は、病気そのものが直接遺伝するわけではありませんが、病気になりやすい体質(生活習慣病のリスク)が家族内で似る傾向があるため、家族に腎臓病の人が集まることがあります。
血縁者に腎臓病の方がいる場合は、より一層、健康的な生活習慣を心がけることが大切です。
- 市販の痛み止めを飲んでも大丈夫ですか?
-
非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)と呼ばれる種類の痛み止め(解熱鎮痛薬)は、腎臓への血流を減少させ、腎機能を悪化させる可能性があります。
腎機能がすでに低下している方が長期間または大量に服用すると、急性腎障害を引き起こすこともあるため注意が必要です。
頭痛や関節痛などで痛み止めが必要な場合は、自己判断で市販薬を使用せず、必ず主治医やかかりつけの薬剤師に相談してください。
- サプリメントや健康食品は腎臓に影響しますか?
-
体に良いとされるサプリメントや健康食品、漢方薬などが、かえって腎臓に負担をかけることがあり、海外から個人輸入したものなど、成分が不明確な製品は危険を伴う場合があります。
また、プロテイン(タンパク質)のサプリメントの過剰摂取は、タンパク質制限が必要な方にとっては腎臓の負担を増大させます。
カリウムが多く含まれている青汁なども、腎機能が低下している方には高カリウム血症のリスクです。
- 定期的な検診はどのくらいの頻度で受けるべきですか?
-
慢性腎臓病の初期段階で状態が安定している場合は、3か月から半年に1回程度の通院となることが多いでしょう。病状が進行したり、治療内容を変更したりした場合は、より短い間隔での通院が必要になります。
定期検診は、腎機能の推移を把握し、合併症を早期に発見し、治療方針を適宜見直すために非常に重要です。自覚症状がないからといって自己判断で通院を中断することなく、医師の指示に従って定期的に受診を続けてください。
以上
参考文献
Yamagata K, Hoshino J, Sugiyama H, Hanafusa N, Shibagaki Y, Komatsu Y, Konta T, Fujii N, Kanda E, Sofue T, Ishizuka K. Clinical practice guideline for renal rehabilitation: systematic reviews and recommendations of exercise therapies in patients with kidney diseases. Renal Replacement Therapy. 2019 Dec;5(1):1-9.
Yamamoto H, Nishi S, Tomo T, Masakane I, Saito K, Nangaku M, Hattori M, Suzuki T, Morita S, Ashida A, Ito Y. 2015 Japanese Society for Dialysis Therapy: guidelines for renal anemia in chronic kidney disease. Renal Replacement Therapy. 2017 Jun 8;3(1):36.
Imai E, Yamagata K, Iseki K, Iso H, Horio M, Mkino H, Hishida A, Matsuo S. Kidney disease screening program in Japan: history, outcome, and perspectives. Clinical journal of the American Society of Nephrology. 2007 Nov 1;2(6):1360-6.
Travers K, Martin A, Khankhel Z, Boye KS, Lee LJ. Burden and management of chronic kidney disease in Japan: systematic review of the literature. International journal of nephrology and renovascular disease. 2013 Jan 3:1-3.
Fukagawa M, Yokoyama K, Koiwa F, Taniguchi M, Shoji T, Kazama JJ, Komaba H, Ando R, Kakuta T, Fujii H, Nakayama M. Clinical practice guideline for the management of chronic kidney disease‐mineral and bone disorder. Therapeutic Apheresis and Dialysis. 2013 Jun;17(3):247-88.
Saeki T, Kawano M, Mizushima I, Yamamoto M, Wada Y, Ubara Y, Nakashima H, Ito T, Yamazaki H, Narita I, Saito T. Recovery of renal function after glucocorticoid therapy for IgG4-related kidney disease with renal dysfunction. Clinical and Experimental Nephrology. 2016 Feb;20(1):87-93.
Kawamura N, Yokoyama M, Fujii Y, Ishioka J, Numao N, Matsuoka Y, Saito K, Arisawa C, Okuno T, Noro A, Morimoto S. Recovery of renal function after radical nephrectomy and risk factors for postoperative severe renal impairment: a Japanese multicenter longitudinal study. International Journal of Urology. 2016 Mar;23(3):219-23.
Takagi T, Kondo T, Iizuka J, Omae K, Kobayashi H, Hashimoto Y, Yoshida K, Tanabe K. Better recovery of kidney function in patients with de novo chronic kidney disease after partial nephrectomy compared with those with pre‐existing chronic kidney disease. International journal of urology. 2014 Jun;21(6):613-6.
Okamura M, Inoue T, Ogawa M, Shirado K, Shirai N, Yagi T, Momosaki R, Kokura Y. Rehabilitation nutrition in patients with chronic kidney disease and cachexia. Nutrients. 2022 Nov 9;14(22):4722.
Nagata K, Horino T, Hatakeyama Y, Matsumoto T, Terada Y, Okuhara Y. Effects of transient acute kidney injury, persistent acute kidney injury and acute kidney disease on the long‐term renal prognosis after an initial acute kidney injury event. Nephrology. 2021 Apr;26(4):312-8.