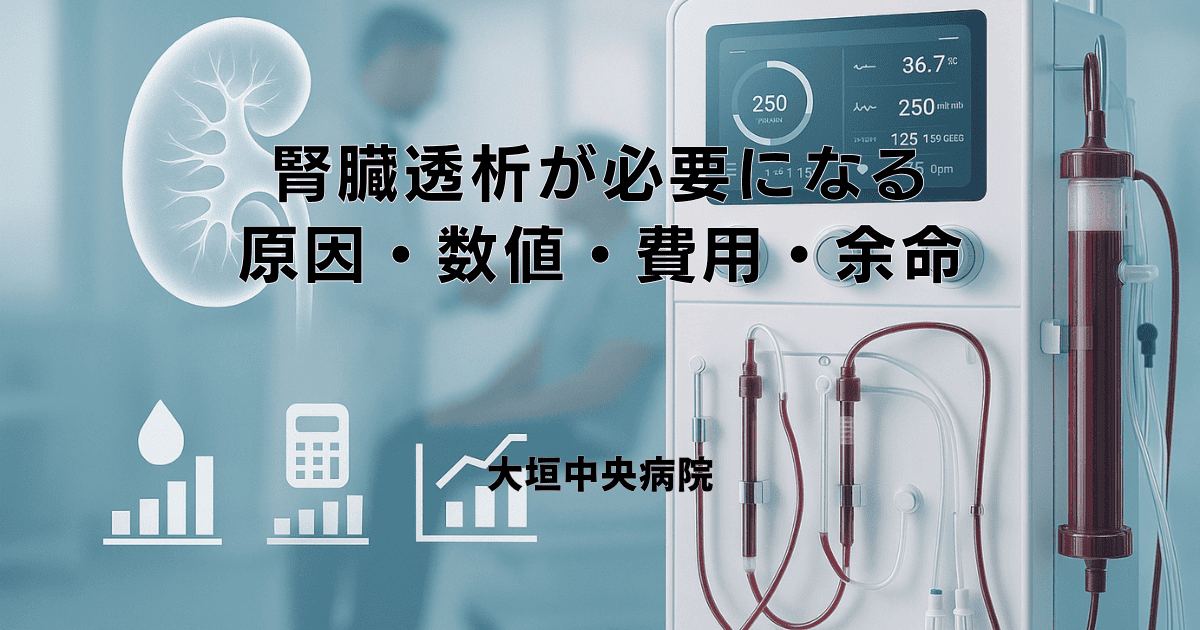腎臓の機能が低下し、透析治療を検討する際、多くの方がさまざまな疑問や不安を抱えることでしょう。
この記事では、腎臓透析が必要になる主な原因疾患、治療開始の目安となる検査数値、透析治療にかかる費用と利用できる医療費助成制度、そして透析を受けながらの生活や余命に関する情報について、基本的な知識を分かりやすく解説します。
腎臓の役割と機能低下
私たちの体にとって、腎臓は生命維持に欠かせない重要な臓器です。腎臓の働きが著しく低下すると、体内にさまざまな問題が生じ、透析治療が必要になることがあります。
まずは、腎臓がどのような役割を担っているのか、そして機能が低下するとはどういうことなのかを理解しましょう。
腎臓の主な働き
腎臓は、そら豆のような形をした握りこぶし程度の大きさの臓器で、腰のあたりに左右一つずつあります。小さいながらも、非常に多くの重要な働きをしています。
- 老廃物の排泄
- 体液量の調節
- 電解質バランスの維持
- ホルモンの産生
これらの働きを通じて、腎臓は体内の環境を常に一定に保つ役割を担っています。例えば、血液をろ過して不要な老廃物や余分な水分を尿として体外に排泄します。
また、体内の水分量やナトリウム、カリウムといった電解質のバランスを適切に保ちます。さらに、血圧を調整するホルモンや、赤血球を作るホルモンなどを産生し、分泌しています。
腎機能が低下するとは
腎機能が低下するとは、これらの腎臓の働きが悪くなる状態を指します。初期の段階では自覚症状がほとんどないことが多いですが、進行するとさまざまな症状が現れます。老廃物が体内に蓄積すると、だるさや吐き気、食欲不振などが起こります。
水分がうまく排泄できなくなると、むくみ(浮腫)が生じたり、血圧が上昇したりします。電解質のバランスが崩れると、不整脈などの心臓の問題を引き起こすこともあります。
腎機能の低下がさらに進むと、末期腎不全という状態に至り、自分の腎臓だけでは生命を維持できなくなります。この段階になると、腎代替療法である透析治療や腎移植が必要となります。
慢性腎臓病(CKD)について
慢性腎臓病(CKD: Chronic Kidney Disease)とは、腎臓の障害や、腎機能の低下が慢性的に続く状態の総称です。自覚症状が出にくいまま進行することが多く、早期発見と早期治療が重要です。
CKDの診断は、尿検査でのタンパク尿の有無や、血液検査でのeGFR(推算糸球体濾過量)の値などに基づいて行います。
CKDの主な原因
CKDの主な原因には、糖尿病や高血圧といった生活習慣病のほか、慢性糸球体腎炎などがあります。これらの病気は、腎臓のフィルター機能を担う糸球体や尿細管にダメージを与え、徐々に腎機能を低下させます。
CKDが進行すると末期腎不全に至り、透析治療が必要となるため、原因となる病気の管理とCKDの進行を抑える治療が大切です。定期的な健康診断を受け、腎臓の状態をチェックすることが、CKDの早期発見につながります。
透析治療が必要になる原因疾患
腎臓の機能が著しく低下し、透析治療が必要になる背景には、さまざまな原因疾患があります。日本透析医学会の調査によると、透析導入の原因として最も多いのは糖尿病性腎症で、次いで慢性糸球体腎炎、腎硬化症と続きます。
これらの疾患がどのように腎機能に影響を与えるのかを理解することは、予防や早期対応のためにも重要です。
最も多い原因 糖尿病性腎症
糖尿病性腎症は、糖尿病の三大合併症の一つであり、透析導入の最大の原因疾患です。長期間にわたる高血糖状態が続くことで、腎臓の糸球体という血液をろ過する部分の毛細血管が傷つき、徐々に腎機能が低下していきます。
初期には自覚症状がほとんどなく、尿検査で微量のアルブミン尿が検出されることで発見されることが多いです。
糖尿病性腎症の進行段階
糖尿病性腎症は、病気の進行度によっていくつかの段階に分けられます。早期の段階では、血糖コントロールや血圧管理、食事療法などを徹底することで、進行を遅らせることが可能です。
しかし、適切な治療が行われずに進行すると、タンパク尿の増加、むくみ、高血圧などが現れ、最終的には末期腎不全に至り、透析治療が必要となります。
糖尿病性腎症の進行度と主な症状
| 病期 | 主な特徴・症状 | 腎機能(eGFR)の目安 |
|---|---|---|
| 第1期(腎症前期) | 自覚症状なし | 正常または軽度低下 |
| 第2期(早期腎症期) | 微量アルブミン尿 | 正常または軽度低下 |
| 第3期(顕性腎症期) | 持続性タンパク尿、むくみ、高血圧 | 低下 |
| 第4期(腎不全期) | 高度タンパク尿、腎機能著明低下、尿毒症症状 | 高度低下 |
| 第5期(透析療法期) | 末期腎不全 | 著しく低下 |
糖尿病と診断された場合は、定期的に腎機能検査を受け、早期発見・早期治療に努めることが何よりも大切です。
次に多い原因 慢性糸球体腎炎
慢性糸球体腎炎は、腎臓の糸球体に慢性的な炎症が起こる病気の総称です。さまざまな種類があり、代表的なものにIgA腎症があります。炎症によって糸球体が傷つき、ろ過機能が低下することで、タンパク尿や血尿が現れます。
初期には自覚症状が乏しいことが多いですが、進行するとむくみや高血圧、腎機能低下が見られるようになります。原因が特定できない場合や、免疫異常が関与していると考えられる場合もあります。
治療は、病型や進行度に応じて、食事療法、薬物療法(ステロイドや免疫抑制薬など)が行われますが、進行を完全に止めることが難しい場合もあり、徐々に腎機能が悪化して透析治療が必要になることがあります。
その他の原因疾患
糖尿病性腎症や慢性糸球体腎炎以外にも、腎臓透析の原因となる疾患はいくつかあります。
腎硬化症
腎硬化症は、主に加齢や長期間の高血圧が原因で、腎臓の血管が動脈硬化を起こし、腎機能が徐々に低下する病気です。高齢化に伴い、腎硬化症による透析導入患者は増加傾向にあります。
血圧のコントロールが非常に重要で、降圧薬による治療や生活習慣の改善を行います。
多発性のう胞腎
多発性のう胞腎は、遺伝性の疾患で、腎臓に多数の「のう胞」(液体がたまった袋)ができ、それらが徐々に大きくなることで正常な腎組織を圧迫し、腎機能が低下していく病気です。のう胞は肝臓など他の臓器にもできることがあります。
根本的な治療法はまだ確立されていませんが、のう胞の増大を抑える薬物療法や、合併症(高血圧、のう胞感染、脳動脈瘤など)の管理が行われます。進行すると末期腎不全に至り、透析治療や腎移植が必要になります。
その他の腎疾患
- 急速進行性糸球体腎炎
- ループス腎炎(全身性エリテマトーデスに伴う腎炎)
- 薬剤性腎障害
これらの疾患も、腎機能に大きな影響を与え、透析治療が必要となることがあります。いずれの原因疾患においても、早期発見と適切な治療、そして腎機能の悪化を防ぐための継続的な管理が重要です。
定期的な健康診断や、気になる症状がある場合の医療機関受診を心がけましょう。
透析導入の目安となる数値
腎臓の機能がどの程度低下したら透析治療を開始するのか、その判断はいくつかの検査数値や患者さんの状態を総合的に評価して行います。
特に重要な指標となるのが、eGFR(推算糸球体濾過量)や血清クレアチニン値、尿素窒素(BUN)などの血液検査の数値です。これらの数値が示す意味と、透析導入の一般的な目安について解説します。
eGFR(推算糸球体濾過量)の重要性
eGFRは、腎臓が1分間にどれくらいの血液をろ過できるかを示す値で、腎機能の評価に広く用いられています。血清クレアチニン値、年齢、性別から計算され、数値が低いほど腎機能が低下していることを意味します。
健康な人のeGFRは90mL/分/1.73m²以上ですが、これが60mL/分/1.73m²未満の状態が3ヶ月以上続くと慢性腎臓病(CKD)と診断されます。
eGFRのステージ分類
CKDは、eGFRの値によって重症度がステージ分類されます。透析導入が検討されるのは、一般的にeGFRが15mL/分/1.73m²未満のG5(末期腎不全)の段階です。
ただし、eGFRの値だけで透析開始が決まるわけではありません。
CKDの重症度分類(eGFR値に基づく)
| ステージ | eGFR (mL/分/1.73m²) | 腎機能の状態 |
|---|---|---|
| G1 | 90以上 | 正常または高値 |
| G2 | 60~89 | 正常または軽度低下 |
| G3a | 45~59 | 軽度~中等度低下 |
| G3b | 30~44 | 中等度~高度低下 |
| G4 | 15~29 | 高度低下 |
| G5 | 15未満 | 末期腎不全(ESKD) |
eGFRが低下すると、体内に老廃物が蓄積しやすくなり、さまざまな尿毒症症状が現れる可能性があります。
血清クレアチニン値と尿素窒素(BUN)
血清クレアチニン値は、筋肉で作られる老廃物であるクレアチニンの血中濃度を示す値です。腎機能が低下すると、クレアチニンが尿中に十分に排泄されなくなるため、血清クレアチニン値が上昇します。
一般的に、男性よりも筋肉量の少ない女性の方が基準値は低くなります。尿素窒素(BUN)は、タンパク質が体内で分解された後にできる老廃物で、これも腎機能が低下すると血中濃度が上昇します。
ただし、BUNは食事内容(タンパク質の摂取量)や消化管出血、脱水などによっても変動するため、クレアチニン値と合わせて評価することが重要です。
腎機能低下時の一般的な検査数値の変動
| 検査項目 | 腎機能低下時の変動 | 主な影響 |
|---|---|---|
| 血清クレアチニン | 上昇 | 老廃物蓄積 |
| 尿素窒素(BUN) | 上昇 | 老廃物蓄積、尿毒症症状 |
| カリウム | 上昇(高カリウム血症) | 不整脈、心停止リスク |
これらの数値が基準値を超えて高くなってきた場合は、腎機能が低下しているサインと考えられます。
その他の検査数値(カリウム・リンなど)
腎機能が低下すると、カリウムやリンといった電解質の排泄も滞り、血中濃度が上昇します。高カリウム血症は、致死的な不整脈を引き起こす危険性があるため、厳重な管理が必要です。
高リン血症は、長期間続くと骨がもろくなったり、血管の石灰化を招いたりする原因となります。これらの電解質異常も、透析導入を検討する上での重要な判断材料となります。
また、貧血(腎性貧血)や代謝性アシドーシス(体が酸性に傾く状態)なども、腎機能低下に伴って現れる異常であり、治療の必要性を判断する上で考慮されます。
医師が総合的に判断する透析導入
透析導入のタイミングは、eGFRや血清クレアチニン値、BUNといった検査数値だけで一律に決まるものではありません。
これらの数値はあくまで目安であり、最終的には医師が患者さんの自覚症状(全身倦怠感、食欲不振、吐き気、呼吸困難、むくみなど)、合併症の有無、栄養状態、日常生活への支障の程度などを総合的に評価して判断します。
例えば、検査数値が透析導入の目安に達していなくても、尿毒症による症状が強く、生活の質(QOL)が著しく低下している場合には、早期の透析導入が検討されることもあります。
逆に、数値が悪くても自覚症状が軽微で、食事療法などでコントロールできている場合は、透析開始を少し遅らせることもあります。医師とよく相談し、納得のいく形で治療方針を決定することが大切です。
腎臓透析の種類と特徴
腎臓の機能が著しく低下した末期腎不全の治療法として行われる腎代替療法には、主に血液透析(HD: Hemodialysis)と腹膜透析(PD: Peritoneal Dialysis)の2種類の透析治療があります。
それぞれの治療法には異なる特徴があり、患者さんの病状やライフスタイル、価値観などを考慮して選択します。ここでは、血液透析と腹膜透析の基本的な仕組みや違いについて解説します。
血液透析(HD)
血液透析は、体から血液を取り出し、ダイアライザー(人工腎臓)という透析器を通して血液中の老廃物や余分な水分を除去し、浄化された血液を再び体内に戻す治療法です。
一般的に、週に2~3回、医療機関に通院して行い、1回の治療時間は4~5時間程度です。
血液透析の仕組み
血液透析を行うためには、腕の血管にシャントと呼ばれる、動脈と静脈をつなぎ合わせた太い血管を作成する手術が必要です。治療の際には、このシャントに2本の針を刺し、一方の針から血液を体外に取り出し、ダイアライザーへ送ります。
ダイアライザーの中では、血液と透析液が半透膜を介して接し、拡散と限外ろ過という原理によって老廃物や余分な水分が除去され、電解質バランスが調整されます。浄化された血液は、もう一方の針から体内に戻されます。
血液透析の頻度と時間
血液透析の頻度と時間は、患者さんの体格や残存腎機能(自分の腎臓がまだ持っている機能の度合い)などによって異なりますが、標準的には週3回、1回あたり4時間が基本です。
十分な透析時間を確保することで、老廃物を効率よく除去し、合併症のリスクを減らすことができます。医療スタッフが治療を管理するため、安心して治療を受けられる一方、通院の負担や時間的な制約があります。
腹膜透析(PD)
腹膜透析は、患者さん自身の腹腔内にある腹膜を利用して血液を浄化する治療法です。お腹にカテーテルを留置する手術を行い、そのカテーテルから透析液を腹腔内に注入します。
一定時間透析液を貯留させておくことで、腹膜を介して血液中の老廃物や余分な水分が透析液側に移動します。その後、老廃物を含んだ透析液を排出し、新しい透析液と交換します。この操作を1日に数回、自宅や職場などで行います。
腹膜透析の仕組み
腹膜は、お腹の内側を覆っている薄い膜で、毛細血管が豊富に分布しています。この腹膜が、血液透析におけるダイアライザーの半透膜のような役割を果たします。
腹腔内に注入された透析液と血液との間で、濃度勾配を利用して老廃物が移動し(拡散)、浸透圧差を利用して余分な水分が除去されます(浸透)。
腹膜透析の種類
腹膜透析には、主にCAPD(連続携行式腹膜透析)とAPD(自動腹膜透析)の2つの方法があります。
- CAPD: 日中、患者さん自身が手動で透析液の交換を1日数回(通常3~5回)行います。
- APD: 夜間、就寝中に専用の装置(サイクラー)が自動的に透析液の交換を行います。
APDは日中の透析液交換が不要または回数を減らせるため、社会生活との両立がしやすいという利点があります。ライフスタイルに合わせて選択できます。
血液透析と腹膜透析の比較
血液透析と腹膜透析は、それぞれに利点と注意点があります。どちらの治療法が適しているかは、医学的な側面だけでなく、患者さんの生活状況や希望によっても異なります。
医師と十分に話し合い、自分に合った治療法を選択することが重要です。
主な相違点の概要
| 項目 | 血液透析(HD) | 腹膜透析(PD) |
|---|---|---|
| 治療場所 | 医療機関 | 自宅、職場など |
| 治療頻度・時間 | 週2~3回、1回4~5時間程度 | 毎日(CAPD: 1日数回交換、APD: 夜間自動交換) |
| 自己管理 | シャント管理、食事・水分管理 | カテーテル管理、透析液交換操作、食事・水分管理 |
| 残存腎機能 | 比較的急速に低下しやすい | 比較的長く保たれやすい |
| 食事制限 | 水分、カリウム、リンなどの制限が比較的厳しい | 血液透析よりは比較的緩やかだが、塩分・水分管理は重要 |
| 主な合併症 | シャントトラブル、不均衡症候群、血圧変動 | 腹膜炎、カテーテル出口部感染、被嚢性腹膜硬化症(EPS) |
また、長期間腹膜透析を続けると腹膜の機能が低下することがあるため、将来的には血液透析への移行が必要になる場合もあります。両方の治療法を経験する「ハイブリッド療法」という考え方もあります。
腎臓透析にかかる費用と医療費助成制度
腎臓透析は長期間にわたる治療であり、その費用について心配される方も少なくありません。しかし、日本では透析治療を受ける患者さんの経済的負担を軽減するためのさまざまな公的医療費助成制度が整備されています。
ここでは、透析治療にかかる一般的な費用と、利用できる主な助成制度について解説します。
透析治療の一般的な費用
透析治療にかかる費用は、医療機関や治療内容によって異なりますが、非常に高額です。
例えば、血液透析の場合、医療費の総額は1ヶ月あたり約40万円から50万円程度、腹膜透析の場合は1ヶ月あたり約30万円から50万円程度かかるといわれています。
これには、透析治療そのものの費用に加え、検査費用や薬代などが含まれます。しかし、実際に患者さんが窓口で支払う自己負担額は、後述する医療費助成制度を利用することで大幅に軽減されます。
血液透析の月額費用目安(医療費総額)
血液透析では、週3回の通院と1回4~5時間の治療が一般的です。これに加えて、定期的な検査やエリスロポエチン製剤などの薬剤費も発生します。これらの費用を合計すると、月額で40万円を超えることが一般的です。
腹膜透析の月額費用目安(医療費総額)
腹膜透析では、透析液や関連する医療材料費が主な費用となります。また、定期的な通院による診察や検査も必要です。
CAPDかAPDか、使用する透析液の種類や量によっても費用は変動しますが、月額で30万円から50万円程度が目安となります。
自己負担を軽減する公的医療保険制度
高額な透析治療費ですが、日本の公的医療保険制度には、患者さんの負担を軽減するための仕組みがあります。主に「高額療養費制度」と「特定疾病療養受療制度」が適用されます。
高額療養費制度
高額療養費制度は、医療機関や薬局の窓口で支払った医療費が、1ヶ月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額が支給される制度です。上限額は、年齢や所得水準によって異なります。
透析治療のように医療費が高額になる場合、この制度を利用することで自己負担額を一定の範囲に抑えることができます。
特定疾病療養受療制度
人工腎臓(透析)を実施している慢性腎不全の患者さんは、「特定疾病療養受療制度」の対象となります。
この制度を利用するには、加入している公的医療保険(健康保険組合、協会けんぽ、国民健康保険など)に申請し、「特定疾病療養受療証」の交付を受ける必要があります。
この受療証を医療機関の窓口に提示することで、透析治療にかかる自己負担限度額が、原則として1ヶ月1万円(70歳未満の上位所得者は2万円)となります。
多くの透析患者さんがこの制度を利用しており、経済的な負担が大幅に軽減されます。
特定疾病療養受療制度の自己負担限度額
| 対象者 | 自己負担限度額(月額) |
|---|---|
| 70歳未満(標準報酬月額53万円未満など) | 1万円 |
| 70歳未満(標準報酬月額53万円以上など上位所得者) | 2万円 |
| 70歳以上75歳未満 | 1万円 |
※所得区分や制度の詳細は、加入している医療保険者やお住まいの自治体にご確認ください。
身体障害者手帳と受けられる支援
腎機能障害が一定の基準に該当する場合、身体障害者手帳の交付を受けることができます。腎機能障害による身体障害者手帳の等級は、1級、3級、4級があります。一般的に、透析療法を行っている患者さんは1級に該当します。
身体障害者手帳を取得すると、さまざまな福祉サービスや助成制度を利用できるようになります。
身体障害者手帳で受けられる主な支援の例
- 医療費の助成(自治体によって内容が異なります)
- 税金の控除・減免(所得税、住民税、自動車税など)
- 公共交通機関の運賃割引
- 福祉手当の支給(自治体による)
これらの支援内容は、お住まいの自治体によって異なるため、市区町村の福祉担当窓口や医療機関のソーシャルワーカーなどに相談し、確認することが大切です。
透析治療を始めるにあたっては、これらの医療費助成制度や福祉サービスを積極的に活用し、経済的な不安を少しでも軽減できるようにしましょう。
腎臓透析と日常生活
腎臓透析を開始すると、生活にいくつかの変化が生じますが、多くの方が治療を受けながら仕事や趣味を続け、自分らしい生活を送っています。特に重要なのは、食事療法、水分管理、そして血液透析の場合はシャントの管理です。
ここでは、透析治療を受けながら質の高い日常生活を送るためのポイントを解説します。
食事療法のポイント
透析患者さんの食事療法は、体内に老廃物や余分な水分を溜め込まないようにし、良好な栄養状態を維持することを目的とします。制限が必要な栄養素と、しっかり摂取すべき栄養素があります。
管理栄養士や医師の指導のもと、個々の状態に合わせた食事療法を実践することが重要です。
水分・塩分管理
透析患者さんは尿量が減少または消失するため、水分の摂取量を適切に管理する必要があります。水分を摂りすぎると、むくみや高血圧、心不全の原因となります。
1日の水分摂取量の目安は、前日の尿量に500~700mL程度を加えた量とされることが多いですが、医師の指示に従ってください。塩分(ナトリウム)の摂りすぎも水分摂取量の増加につながるため、減塩が基本です。
1日の塩分摂取目標量は6g未満が一般的です。
タンパク質・カリウム・リンの制限
タンパク質は体に必要な栄養素ですが、摂取しすぎると老廃物である尿素窒素が増加します。ただし、制限しすぎると栄養状態が悪化するため、良質なタンパク質を適量摂取することが大切です。
カリウムは、野菜や果物、いも類などに多く含まれ、血中濃度が高くなると高カリウム血症を引き起こし、不整脈や心停止のリスクがあります。
リンは、乳製品や肉、魚、加工食品などに多く含まれ、高リン血症は骨の病気や血管の石灰化を進行させます。これらの栄養素は、医師や管理栄養士の指導に基づき、摂取量をコントロールします。
食事療法の主な注意点
| 栄養素 | 管理のポイント | 多く含む食品例 |
|---|---|---|
| 水分 | 摂取量制限、体重増加の管理 | 飲み物全般、汁物、果物 |
| 塩分 | 1日6g未満目標、加工食品や外食に注意 | 漬物、干物、インスタント食品 |
| カリウム | 摂取量制限、調理法(茹でこぼしなど)の工夫 | 生野菜、果物、いも類、豆類 |
| リン | 摂取量制限、リン吸着薬の服用 | 乳製品、レバー、魚卵、加工食品 |
| タンパク質 | 適量摂取、良質なものを選ぶ | 肉、魚、卵、大豆製品 |
一方で、エネルギーは十分に摂取する必要があります。エネルギーが不足すると、体内のタンパク質が分解されてしまい、栄養状態が悪化する可能性があります。
食事療法は厳格に感じるかもしれませんが、工夫次第で食事を楽しむことは可能です。
運動や社会生活について
適度な運動は、体力維持、筋力向上、ストレス解消、さらには心血管疾患のリスク低減にもつながるため、透析患者さんにとっても推奨されます。
ただし、運動の種類や強度は、個々の状態や合併症の有無によって異なるため、必ず医師に相談してから行いましょう。ウォーキングや軽い体操など、無理のない範囲で継続することが大切です。
仕事については、体調管理をしながら継続している方が多くいます。勤務時間や内容について職場と相談し、理解を得ることが重要です。腹膜透析の場合は、比較的社会復帰がしやすいといわれています。
シャント管理の重要性(血液透析の場合)
血液透析を受けている患者さんにとって、シャントは「命綱」ともいえる非常に大切なものです。シャントを長持ちさせるためには、日頃の管理が重要です。
シャント管理の日常的な注意点
- シャント側の腕で重い物を持たない、ぶつけない
- シャント側の腕で血圧測定や採血をしない
- シャント側の腕を圧迫しない(腕時計、きつい衣類など)
- 毎日シャント音(スリル)を確認し、異常があればすぐに医療機関に連絡する
- シャント部位を清潔に保つ
シャントに閉塞や感染などのトラブルが起こると、透析治療が困難になるため、些細な変化にも気を配り、異常を感じたら速やかに医師や看護師に相談しましょう。
旅行や災害時の備え
透析治療を受けていても、旅行を楽しむことは可能です。事前に主治医に相談し、旅行先の透析施設(臨時透析)を予約するなどの準備が必要です。また、災害時にも透析治療を継続できるよう、日頃から備えておくことが大切です。
緊急連絡先、服用している薬のリスト、透析条件などをまとめたカードを携帯し、数日分の非常食や飲料水、必要な薬などを準備しておくと安心です。加入している透析施設や自治体の指示に従い、冷静に行動できるようにしておきましょう。
腎臓透析と余命に関する考え方
腎臓透析が必要と診断された際、多くの方が「余命はどのくらいなのか」という不安を抱くことでしょう。透析技術や医療の進歩により、透析患者さんの生命予後は大きく改善していますが、いくつかの要因が影響することも事実です。
ここでは、腎臓透析と余命に関する現在の状況や、QOL(生活の質)を維持するために大切なことについて解説します。
透析患者の平均余命
日本透析医学会の統計調査によると、透析患者さんの平均余命は年々延びています。これは、透析療法の質の向上、合併症管理の進歩、栄養状態の改善などが寄与していると考えられます。
ただし、透析患者さんの平均余命は、一般人口の平均余命と比較すると依然として短い傾向にあります。
これは、透析導入の原因となる糖尿病や高血圧などの基礎疾患が影響していることや、透析治療そのものが身体にある程度の負担をかけることなどが関係しています。
年齢別のデータについて
透析患者さんの余命は、透析を開始した年齢によっても大きく異なります。一般的に、若い年齢で透析を導入した方の方が、高齢で導入した方よりも平均余命は長くなる傾向があります。
しかし、これはあくまで統計的なデータであり、個々の患者さんの状態や治療への取り組み方によって大きく変わってきます。
透析導入年齢と平均余命の目安(概算)
以下の表は、あくまで一般的な傾向を示すものであり、個々の患者さんの状況を正確に反映するものではありません。
| 透析導入時の年齢 | その後の平均余命(概算) |
|---|---|
| 40~44歳 | 約20~25年 |
| 60~64歳 | 約10~15年 |
| 80~84歳 | 約3~5年 |
これらの数値は、あくまで過去のデータに基づく統計的な平均値であり、個々の患者さんの余命を予測するものではありません。近年では、より長期にわたり元気に過ごされる方も増えています。
余命に影響を与える要因
透析患者さんの余命には、さまざまな要因が関わってきます。これらの要因を適切に管理することが、より長く、より質の高い生活を送るために重要です。
合併症の有無と管理
透析患者さんにとって最も注意すべきなのは、心血管疾患(心筋梗塞、脳卒中など)や感染症といった合併症です。これらの合併症は、生命予後に大きな影響を与えます。
基礎疾患である糖尿病や高血圧の管理を徹底し、定期的な検査を受けて合併症の早期発見・早期治療に努めることが大切です。また、シャントトラブルや腹膜炎(腹膜透析の場合)なども、適切に管理する必要があります。
全身状態と栄養状態
患者さん自身の全身状態や栄養状態も、余命に影響する重要な要素です。適切な食事療法によって良好な栄養状態を維持し、適度な運動によって体力を保つことが、合併症の予防や免疫力の維持につながります。
貧血やミネラルバランスの異常なども、適切に治療することが求められます。
その他の影響因子
- 透析導入時の年齢
- 原疾患(透析導入の原因となった病気)
- 透析療法の種類と質
- 喫煙習慣の有無
- 治療への積極的な参加(アドヒアランス)
これらの因子が複雑に絡み合い、個々の患者さんの予後に影響します。
QOL(生活の質)を維持するために大切なこと
透析治療の目的は、単に生命を維持するだけでなく、患者さんができる限り自分らしい生活を送り、QOL(生活の質)を高く保つことです。そのためには、医療者と患者さんが協力し、治療に積極的に取り組む姿勢が重要です。
食事療法や水分管理、服薬などをきちんと守り、定期的な通院や検査を欠かさず受けることが基本となります。また、精神的なサポートも大切です。
不安や悩みを抱え込まず、医師や看護師、臨床心理士、ソーシャルワーカーなどに相談し、支援を受けることも考えましょう。趣味や社会活動への参加など、生きがいを見つけることも、QOLの向上につながります。
透析治療を受けながらも、前向きに人生を送るための工夫が求められます。
よくある質問 (FAQ)
腎臓透析に関して、多くの方が抱く疑問や不安について、Q&A形式で解説します。ここに記載されている情報が、少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。
- 透析を始めたら一生続けなければならないのか
-
一般的に、一度透析治療を開始すると、生涯にわたって継続する必要があります。これは、透析治療が失われた腎機能を代替するものであり、腎機能そのものを回復させる治療ではないためです。
ただし、例外的に腎機能がある程度回復し、一時的に透析治療を離脱できるケースもごく稀にありますが、多くの場合、透析は継続的な治療となります。腎移植を受ければ、透析治療から離脱することが可能です。
腎移植は、健康な腎臓を他者から提供してもらう治療法で、成功すれば透析の必要がなくなります。
- 透析治療中に痛みはあるのか
-
血液透析の場合、治療の開始時と終了時にシャントへ針を刺すため、その際に若干の痛みを伴います。痛みの感じ方には個人差がありますが、多くの場合、慣れてくると軽減します。
痛みが強い場合は、麻酔テープやクリームを使用することで和らげることができます。透析治療中そのものには、通常痛みはありません。もし治療中に痛みや不快感を感じた場合は、すぐに医療スタッフに伝えることが大切です。
腹膜透析の場合は、カテーテル挿入部の違和感や、透析液を腹腔内に出し入れする際に軽い圧迫感や張りを感じることがありますが、通常は強い痛みはありません。
腹痛がある場合は腹膜炎などの可能性もあるため、速やかに医療機関に連絡する必要があります。
- 透析をしていても妊娠・出産は可能か
-
透析治療を受けている女性が妊娠・出産することは、以前は非常に困難とされていましたが、近年の周産期医療と透析医療の進歩により、不可能ではなくなってきています。
ただし、妊娠・出産には多くのリスクを伴うため、計画段階から腎臓内科医と産科医が連携し、厳重な管理のもとで行う必要があります。
妊娠中は、より頻回で長時間の透析(強化透析)が必要になることが多く、血圧管理や貧血管理、栄養管理なども通常より厳密に行います。母体および胎児の安全を最優先に考え、慎重な判断と準備が求められます。
希望される場合は、まず主治医に相談し、専門的な知識と経験を持つ医療機関でサポートを受けることが重要です。
- 腎移植という選択肢について
-
腎移植は、末期腎不全の根本的な治療法の一つで、健康な腎臓を他者(ドナー)から提供してもらい、体内に移植する手術です。腎移植には、亡くなった方から腎臓の提供を受ける「献腎移植」と、健康な親族などから腎臓の提供を受ける「生体腎移植」があります。
腎移植が成功すると、透析治療から離脱でき、食事制限も大幅に緩和され、より自由な生活を送ることが期待できます。ただし、移植後は免疫抑制薬を生涯服用し続ける必要があり、定期的な通院と検査も欠かせません。
また、ドナーの確保や手術のリスク、拒絶反応の可能性など、考慮すべき点も多くあります。透析治療と腎移植は、それぞれに利点と欠点があるため、医師と十分に話し合い、自身の病状やライフスタイル、価値観に合った治療法を選択することが大切です。
腎移植の主なメリット・デメリット
区分 内容 メリット 透析治療からの離脱 食事・水分制限の大幅な緩和 生活の質の向上、社会復帰の促進 デメリット・注意点 免疫抑制薬の生涯服用と副作用のリスク 手術のリスク(ドナー・レシピエント双方) 拒絶反応や感染症のリスク 献腎移植の待機期間が長い場合がある
以上
透析センター(人工透析) | 大垣中央病院(医療法人社団豊正会 )
参考文献
WANG, Virginia, et al. The economic burden of chronic kidney disease and end-stage renal disease. In: Seminars in nephrology. WB Saunders, 2016. p. 319-330.
KONTODIMOPOULOS, Nick; NIAKAS, Dimitris. An estimate of lifelong costs and QALYs in renal replacement therapy based on patients’ life expectancy. Health Policy, 2008, 86.1: 85-96.
VANHOLDER, Raymond, et al. Reducing the costs of chronic kidney disease while delivering quality health care: a call to action. Nature Reviews Nephrology, 2017, 13.7: 393-409.
SPINOWITZ, Bruce, et al. Economic and quality of life burden of anemia on patients with CKD on dialysis: a systematic review. Journal of medical economics, 2019, 22.6: 593-604.
ELSHAHAT, Sarah, et al. The impact of chronic kidney disease on developed countries from a health economics perspective: a systematic scoping review. PloS one, 2020, 15.3: e0230512.
SHIH, Chia-Jen, et al. The impact of dialysis therapy on older patients with advanced chronic kidney disease: a nationwide population-based study. BMC medicine, 2014, 12: 1-10.
CHESNAYE, Nicholas C., et al. The impact of population ageing on the burden of chronic kidney disease. Nature Reviews Nephrology, 2024, 20.9: 569-585.
SALDARRIAGA, E. M., et al. Cost-effectiveness analysis of a strategy to delay progression to dialysis and death among chronic kidney disease patients in Lima, Peru. Cost Effectiveness and Resource Allocation, 2021, 19: 1-9.
SHAIKH, Maaz, et al. Utilization, costs, and outcomes for patients receiving publicly funded hemodialysis in India. Kidney International, 2018, 94.3: 440-445.
SUGRUE, Daniel M., et al. Economic modelling of chronic kidney disease: a systematic literature review to inform conceptual model design. Pharmacoeconomics, 2019, 37: 1451-1468.