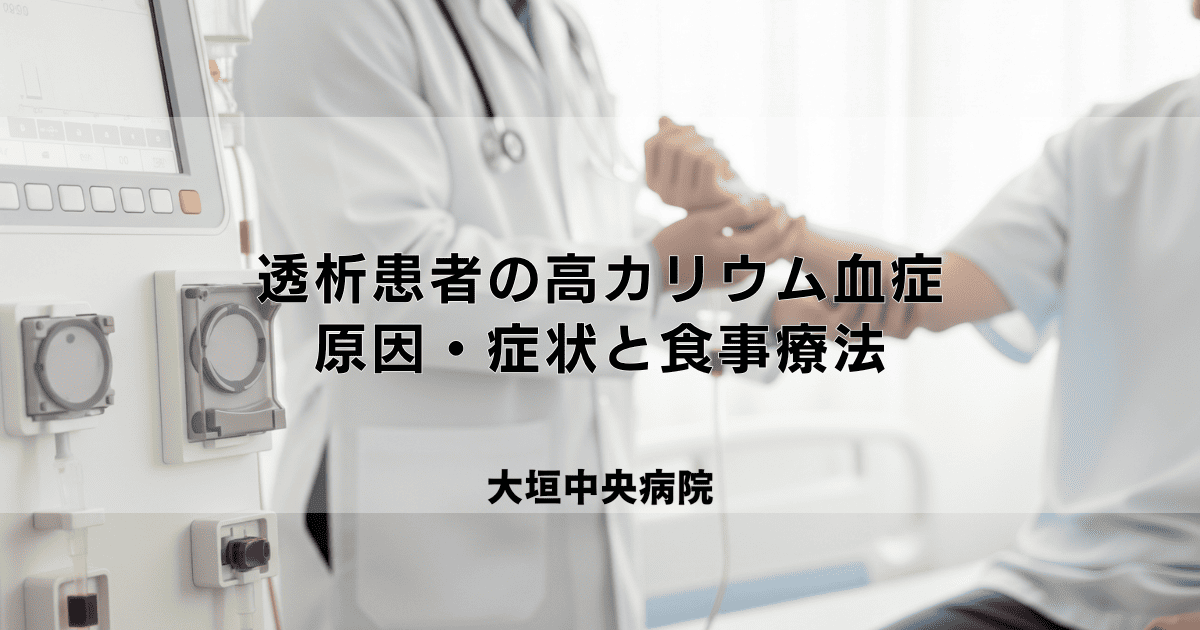透析治療を受けている方にとって、高カリウム血症は常に注意が必要な合併症の一つです。腎臓の機能が低下すると、体内のカリウムを十分に排出できなくなり、血液中のカリウム濃度が危険なレベルまで上昇することがあります。
この状態は、体にさまざまな不調を引き起こすだけでなく、時には心臓の動きに深刻な影響を及ぼし、命にかかわる事態を招くこともあります。
ここでは、透析患者様とそのご家族が、高カリウム血症について正しく理解し、日々の生活の中で適切にカリウムを管理していくための情報を提供します。
高カリウム血症とは何か
私たちの体にとって重要なミネラルであるカリウムですが、バランスが崩れると体に不調をきたします。特に透析を受けている方の場合、カリウムの管理は健康を維持する上で非常に重要な課題です。
カリウムの役割と正常値
カリウムは、生命活動を維持するために必要不可欠なミネラルです。98%は細胞の中に存在し、残りの2%が血液などの細胞の外にあります。細胞内外のわずかなバランスが、体の機能を正常に保つために極めて重要です。
主な役割は、細胞の浸透圧を調整したり、筋肉の収縮、特に心筋の正常な働きをサポートしたりすることで、また、神経細胞が興奮し、脳からの指令を体の隅々に伝える際にも、カリウムはナトリウムと共に重要な働きを担います。
健康な人の場合、腎臓が食事から摂取したカリウムの量を敏感に察知し、不要な分を尿として排出し、血液中のカリウム濃度を常に一定の範囲に保っています。
血液中のカリウム濃度の基準値は、3.5~5.0mEq/Lという非常に狭い範囲に厳密にコントロールされています。
カリウムの主な働き
| 働き | 内容 | 重要性 |
|---|---|---|
| 筋肉の収縮 | 心臓を含む全身の筋肉が正常に動き、弛緩するために必要 | 心機能の維持に直結し、不整脈を予防する |
| 神経伝達 | 脳からの指令を体の各部位にスムーズに伝える役割を担う | 体の感覚や運動機能を正常に保つ |
| 体液バランスの維持 | 細胞内外の水分量や浸透圧をナトリウムと共に調整する | 体の恒常性を保ち、血圧の安定にも寄与する |
高カリウム血症の定義
高カリウム血症とは、何らかの原因で腎臓からのカリウム排泄がうまくいかず、血液中のカリウム濃度が正常値の上限である5.0mEq/Lを超えた状態です。
透析患者の場合、腎臓の機能が著しく低下しているため、この状態に陥りやすい傾向があります。
血清カリウム値が5.5mEq/Lを超えると軽度、6.0mEq/Lを超えると中等度、そして6.5mEq/L以上になると重度と分類され、濃度が高くなるにつれて体に現れる症状も重篤になり、迅速な対応が求められます。
透析と次の透析の間は、食事からのカリウム摂取により、徐々に血中濃度が上昇していく時間帯であり、特に注意が必要です。
血清カリウム値による重症度の目安
| 重症度 | 血清カリウム値 (mEq/L) | 主なリスク |
|---|---|---|
| 軽度 | 5.5 ~ 5.9 | 自覚症状はほとんどないが、食事内容の見直しが必要 |
| 中等度 | 6.0 ~ 6.4 | しびれや脱力感が出現し始め、心電図に変化が見られる可能性 |
| 重度 | 6.5以上 | 致死的な不整脈(心室細動など)のリスクが非常に高く、緊急の治療が必要 |
透析患者がなりやすい理由
透析治療を受けている方が高カリウム血症になりやすい最大の理由は、腎臓の機能低下です。
健康な腎臓は、食事から摂取したカリウムのうち、不要な分を尿として体外に排出しますが、透析が必要な段階まで腎機能が低下すると、排出能力が著しく、あるいはほとんど失われてしまいます。
透析によって定期的に体内のカリウムを除去する必要がありますが、次の透析までの間に食事などから摂取したカリウムが体内に蓄積し、血中濃度が上昇しやすくなるのです。
食事管理が不十分であったり、予定通りに透析を受けられなかったりすると、そのリスクはさらに高まります。血液透析と腹膜透析ではカリウム除去の仕組みが異なりますが、いずれの治療法においても食事からのカリウム制限は等しく重要です。
高カリウム血症が引き起こす症状
高カリウム血症は、自覚症状が乏しいまま進行することがあり、気づいた時には危険な状態になっていることも少なくありません。どのような症状が現れる可能性があるのかを知ると、早期発見につながります。
初期症状を見逃さない
血清カリウム値が軽度に上昇している段階では、はっきりとした症状が現れないことがほとんどです。
人によっては初期のサインとして、手足の指先や唇の周りがピリピリとしびれる感覚や、何となく力が入らない、体がだるいといった脱力感や倦怠感を感じることがあり、また、胃がむかむかするような吐き気を感じることもあります。
注意したい初期症状
- 手足のしびれ(ピリピリ、ジンジンする感じ)
- 唇の周りのしびれ
- 脱力感・倦怠感(体に力が入らない、重だるい)
- 吐き気・嘔吐
進行した場合の危険な症状
カリウム値がさらに上昇し、中等度から重度の高カリウム血症になると、症状はより明確です。
筋肉の麻痺が進行し、手足が動かしにくくなったり、力が入らなくなったりし、これは四肢麻痺と呼ばれ、立ち上がれなくなることがあり、さらに、ろれつが回りにくくなったり、食べ物が飲み込みにくくなったりすることもあります。
この状態は、体の自由を奪うだけでなく、呼吸に必要な筋肉(横隔膜など)に影響が及ぶと呼吸困難に陥る危険性も伴います。
心臓への影響と不整脈
高カリウム血症で最も警戒すべきは、心臓への影響です。カリウムは心臓の筋肉が規則正しく拍動するために重要な役割を担っていますが、濃度が異常に高くなると心臓の電気的な活動が乱れ、致死的な不整脈を起こすことがあります。
心電図では、テント状T波と呼ばれる特徴的な波形が現れ始め、進行するとQRS幅の増大などが見られ、最終的には心室細動や心停止に至る恐れもある、非常に危険な状態です。
胸の不快感や動悸を感じた場合は、すぐに医療機関に連絡する必要があります。
症状が出ないこともあるサイレントキラー
高カリウム血症の怖いところは、血清カリウム値がかなり高いレベルになるまで、全く自覚症状がない場合も多い点です。高血圧と同様に、症状がないからといって問題がないわけではありません。
症状がないからと油断していると、ある日突然、重篤な不整脈を起こす可能性があるため、サイレントキラー(静かなる暗殺者)とも呼ばれます。
症状の有無にかかわらず、定期的な血液検査で自身のカリウム値を確認し、日々の食事管理を徹底することが、命を守る上で極めて重要です。
高カリウム血症の主な原因
高カリウム血症を引き起こす原因は一つではありません。透析患者様の場合、日々の食事内容が最も大きな要因となりますが、それ以外にもいくつかの原因が考えられます。
食事からのカリウム過剰摂取
最大の原因は、食事からのカリウム摂取です。カリウムは多くの食品、特に生の野菜や果物、いも類、豆類、海藻類に豊富に含まれています。
健康な人であれば問題にならない量でも、腎機能が低下している透析患者にとっては過剰摂取となり、体内に蓄積してしまいます。
知らず知らずのうちにカリウムの多い食品を摂り続けていることが、高カリウム血症の直接的な引き金になるケースが最も多いです。
果物や野菜ジュース、ドライフルーツなどは、手軽に摂取できる反面、カリウムを大量に摂取しやすいため特に注意が必要です。
カリウム摂取源となりやすい食品群
| 食品群 | 具体例 | 注意点 |
|---|---|---|
| 野菜類 | ほうれん草、かぼちゃ、アボカド、切り干し大根 | 生食やジュースは特に注意。調理法を工夫する |
| 果物類 | バナナ、メロン、キウイフルーツ、干し柿 | ドライフルーツはカリウムが凝縮されており非常に危険 |
| いも類 | さつまいも、じゃがいも、里いも、長いも | 主食の代わりにする際は量に注意し、調理法を工夫する |
透析不足による影響
透析治療は、体内に溜まった老廃物や余分な水分、そしてカリウムを排出するための重要な手段です。決められた透析時間や回数を守らないと、体内のカリウムを十分に除去できません。
自己判断で透析を早めに切り上げたり、予定通りに通院しなかったりすると、次の透析までの間にカリウム値が危険なレベルまで上昇するリスクが非常に高くなります。
十分な透析量(Kt/Vなどで評価します)を確保することが、カリウム管理の基本であり、生命を維持する上で不可欠です。
薬の影響や便秘
服用している薬が原因で高カリウム血症になることもあります。一部の降圧薬(ACE阻害薬やARB、カリウム保持性利尿薬など)や非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)、免疫抑制剤などは、カリウム値を上昇させる作用を持つものがあります。
また、便秘もカリウム値を上げる一因です。カリウムは尿だけでなく便からも一部排泄されるため、便秘が続くとその分、体内にカリウムが留まりやすくなります。
食物繊維の摂取は重要ですが、カリウムの多い食品を避ける必要があるため、食事のバランスには工夫が求められます。
その他の要因
怪我や手術、感染症などによって体内の組織(細胞)が壊れると、細胞内に豊富に含まれていたカリウムが血液中に放出され、一時的にカリウム値が上昇することがあります。
また、血糖値のコントロールが悪い場合、インスリンの働きが不足し、カリウムが細胞内へ移動しにくくなるため血中濃度が上がります。
体が酸性に傾くアシドーシスという状態でも、細胞内からカリウムが血液中へ移動し、カリウム値は上がりやすいです。
食事療法の基本と考え方
透析患者のカリウム管理において、食事療法は治療の根幹をなす非常に重要な要素です。日々の食事をどのようにコントロールするかが、高カリウム血症の予防に直結します。
なぜ食事療法が重要なのか
この状況は、蛇口から水が注がれる浴槽に例えることができます。浴槽があなたの体、注がれる水が食事からのカリウム、そして浴槽の栓が透析によるカリウム除去です。
透析患者の体では、栓が小さく、水の抜けが悪いため、蛇口をひねって水をたくさん注ぎ続ける(カリウムを多く摂取する)と、浴槽の水はあっという間に溢れてしまいます(高カリウム血症)。
透析で除去できるカリウムの量には限界があるため、蛇口を絞り、注ぐ水の量を調整する(食事からのカリウム摂取量を制限する)ことが必要です。
カリウム制限の目標値
透析患者における1日のカリウム摂取量の目標は、一般的に2,000mg以下、場合によっては1,500mg以下に設定することが多いです。
ただし、この目標値は個々の患者様の体格や残存する腎機能、透析の条件、血液検査の結果などによって異なります。必ず主治医や管理栄養士と相談の上、ご自身の適切な目標値を確認してください。
食事記録をつけるメリット
日々の食事内容を記録する食事記録(食事日誌)をつけることは、カリウム管理を成功させるための有効な手段です。
自分が何をどれだけ食べたかを客観的に把握することで、カリウムを摂りすぎていないか、どの食品から多く摂取しているかが見えてきます。
記録をもとに管理栄養士から具体的なアドバイスを受けることで、より効果的な食事改善につなげることができます。
食事記録の簡単な記入例
| 時間 | 食べたもの | 量 |
|---|---|---|
| 朝食 (7:30) | 食パン、目玉焼き、牛乳 | 6枚切り1枚、卵1個、100ml |
| 昼食 (12:00) | おにぎり(梅)、鶏の唐揚げ | 1個、2個 |
| 夕食 (19:00) | ごはん、焼き魚(鮭)、ほうれん草のおひたし | 茶碗1杯、1切れ、小鉢1杯 |
カリウムを多く含む食品と避けるべきもの
カリウム管理を実践する上で、どの食品にカリウムが多く含まれているかを知ることは第一歩です。ここでは、特に注意が必要な食品群について、解説します。
特に注意が必要な食品群
カリウムは多くの食品に含まれていますが、含有量が多いのは野菜、果物、いも類、豆類、海藻類で、肉や魚にも含まれているため、食べ過ぎには注意が必要です。
食品を完全に食事から排除するのではなく、量を管理し、調理法を工夫することが求められます。カリウムは水に溶けやすい性質を持つため、調理法で含有量を減らせる野菜類と、調理による削減が難しい果物類では、付き合い方が異なります。
カリウム制限で特に注意する食品
- 生の野菜、野菜ジュース、青汁
- 生の果物、ドライフルーツ、果物ジュース
- いも類、豆類、ナッツ類、種実類
- 海藻類(昆布、わかめ)、きのこ類
- 肉・魚の加工品(ハム、ソーセージ)
野菜・いも類のカリウム管理
野菜やいも類はビタミンや食物繊維が豊富ですが、カリウムも多く含みます。特にほうれん草、かぼちゃ、アボカド、さつまいも、じゃがいもなどは含有量が多い代表的な食品で、調理の工夫によってカリウムを減らすことが大切です。
また、生野菜サラダや野菜ジュースはカリウムを直接摂取することになるため、避けましょう。いも類は主食代わりにもなりますが、その際はごはんの量を減らすなど、全体のバランスを考える必要があります。
カリウム含有量の多い野菜の例(100gあたり)
| 食品名 | カリウム量(mg) | 調理のポイント |
|---|---|---|
| ほうれん草(生) | 690 | 必ず細かく刻んでからゆでこぼす |
| かぼちゃ(西洋) | 450 | 小さく切ってゆでるか、水にさらす |
| アボカド | 720 | 摂取はごく少量(一切れ程度)に留める |
果物・ジュースの選び方
果物もカリウムの供給源として注意が必要で、バナナ、メロン、キウイフルーツ、柿などはカリウムが豊富です。
また、水分が抜けて成分が凝縮されているドライフルーツ(干し柿、レーズンなど)は、少量でも多くのカリウムを摂取してしまうため、原則として避けてください。
果物を食べる際は、缶詰を選ぶとシロップにカリウムが溶け出しているため、生の果物よりは摂取量を抑えられます(シロップは飲まないようにします)。りんごや梨、ぶどう、缶詰の桃などは比較的カリウムが少ない果物です。
カリウム含有量の多い果物の例(100gあたり)
| 食品名 | カリウム量(mg) | 代替案(比較的少ないもの) |
|---|---|---|
| バナナ | 360 | りんご (120mg) |
| メロン(赤肉種) | 350 | 缶詰の桃 (70mg) |
| キウイフルーツ | 290 | ぶどう (130mg) |
肉・魚・乳製品の注意点
肉や魚は重要なたんぱく源ですが、カリウムも含まれています。透析患者は十分なたんぱく質を摂る必要があるので、制限しすぎるのはよくありません。適量を守ることが大切です。
特に、ハムやソーセージなどの加工品は、食品添加物としてカリウムが使われていることがあるため注意が必要です。牛乳やヨーグルト、チーズなどの乳製品もカリウムの供給源となります。
1日の摂取量を守り、摂りすぎないように心がけ、牛乳なら1日に100ml程度を目安にします。
カリウムを減らす調理の工夫
カリウムは水に溶けやすい性質を持っているので、この性質を利用すれば、調理の工夫によって食品に含まれるカリウムの量を減らすことが可能です。
食材の選び方と下ごしらえ
調理の第一歩は、食材選びから始まります。できるだけカリウムの少ない食品を選ぶことが基本で、さらに、調理前の下ごしらえが非常に重要です。
野菜やいも類は、皮をむき、細かく切ることで、水に触れる表面積が広がり、カリウムが溶け出しやすくなります。厚く切るよりも薄切りに、乱切りにするよりも千切りにする方が、より効果的にカリウムを減らせます。
ゆでこぼし・水さらしの効果
カリウムを減らす最も効果的な調理法がゆでこぼしです。食材をたっぷりの湯(食材の5~10倍量)でゆで、ゆで汁を捨てることで、カリウムを30~50%程度減らすことができます。
炒め物や煮物にする場合でも、一度下ゆでしてから調理すると良いでしょう。また、細かく切った食材を水にさらすことでも、カリウムをある程度除去できます。
ただし、長時間さらしすぎると水溶性のビタミンなども失われるため、時間は調整が必要です。ゆでるお湯の量が多いほど、カリウムは溶け出しやすくなります。
調理法によるカリウム減少効果の目安
| 調理法 | カリウム減少率 | ポイント |
|---|---|---|
| 水さらし | 約10~20% | 食材を細かく切ってから、流水または数回水を替えて行う |
| ゆでこぼし | 約30~50% | たっぷりの湯でゆで、ゆで汁は必ず捨てる。煮汁は飲まない |
| 電子レンジ加熱 | ほぼ減らない | カリウムを減らす目的では不向き。手軽だが注意が必要 |
調味料の選び方と使い方
調味料にも注意が必要です。しょうゆやソース類の中でも、減塩タイプやだし入りのものは、塩分(塩化ナトリウム)を減らす代わりに、うま味成分として塩化カリウムを使っている場合があります。
購入時には必ず成分表示を確認し、カリウムの少ない調味料を選ぶようにしましょう。また、煮物の煮汁や麺類のつゆ、鍋物のスープは、食材から溶け出したカリウムが多く含まれているので、汁は飲まずに残すことが大切です。
日常生活でできるカリウム管理
カリウム管理は、食事療法だけでなく、日々の生活習慣全体で取り組むことが成功の鍵です。外食時の注意点や便秘の予防など、日常生活の中で意識できるポイントをいくつか紹介します。
外食や加工食品との付き合い方
外食や市販の惣菜、加工食品は、どのような食材がどれだけ使われているか分かりにくく、味付けも濃いためカリウムの量も多くなりがちです。
外食する際は、生野菜や果物が多いメニュー(サラダバーなど)は避け、丼ものよりは主菜と副菜が分かれている定食を選び、小鉢の内容を確認してカリウムの多そうなものは残すといった工夫が有効です。
ラーメンやうどんのスープは飲まない、カレーライスはルーを少なめにするなど、意識的な行動が重要で、加工食品を利用する際は、栄養成分表示を確認する習慣をつけましょう。
外食時のメニュー選びの注意点
| メニュー例 | 注意すべき点 | 対策 |
|---|---|---|
| ラーメン・うどん | スープにカリウムが多く溶け出している | 麺だけを食べ、スープは必ず残す |
| カレーライス | じゃがいも、にんじんなどカリウムの多い野菜が多い | ご飯の量を調整し、ルーは少なめにする。福神漬けも注意 |
| 定食 | 小鉢の煮物(ひじき、切り干し大根)や漬物 | 生野菜やいも類の小鉢は避ける。内容を確認して選ぶ |
便秘を予防する生活習慣
便通を整えることは、カリウムの排泄を助ける上で大切ですが、透析患者は水分制限がある上、カリウムの多い野菜や果物を控えなければならないため、便秘になりやすい傾向があります。
適度な運動(散歩など)を習慣づけて腸の動きを活発にしたり、医師や管理栄養士に相談の上でカリウムの少ない食物繊維(きのこ類をゆでこぼしたものなど)を上手に取り入れたりするなど、便秘を予防する工夫が必要です。
自己判断で下剤や便秘薬を使うのではなく、必ず処方された薬を指示通りに服用してください。
定期的な血液検査の重要性
どれだけ食事管理や生活習慣に気をつけていても、実際にカリウム値がコントロールできているかは、血液検査を受けなければ分かりません。定期的に血液検査を受け、自身のカリウム値の推移を把握することが、管理の基本です。
検査結果が良いからと油断せず、悪いからと落ち込みすぎず、客観的なデータとして受け止めましょう。
検査結果をもとに、主治医や管理栄養士と共にこれまでの食生活を振り返り、必要に応じて計画を修正していくことが、高カリウム血症の予防と改善につながります。
よくある質問(Q&A)
最後に、高カリウム血症の管理に関して、患者さんからよく寄せられる質問と回答をまとめました。
- カリウム制限はいつまで続ければよいですか
-
透析治療を受けている限り、腎臓の機能が回復することは基本的にないため、カリウム制限は生涯にわたって続ける必要があります。食事療法は、透析治療と両輪で進めていく、体を守るための大切な習慣です。
管理栄養士と相談しながら、食べられる範囲で食事を楽しめる工夫を見つけていきましょう。
- カリウムの低い食品ばかり食べていれば安全ですか
-
カリウムが低いとされる食品でも、食べる量が多ければ、結果的にカリウムの摂取量は多くなってしまいます。例えば、白米もカリウムはゼロではありませんので、食べ過ぎれば影響が出ます。
また、特定の食品に偏るのではなく、様々な食品をバランス良く、かつ適量食べることが、栄養状態を良好に保つ上でも大切です。
- 「食塩不使用」の塩は使ってもいいですか
-
「減塩」や「食塩不使用」をうたった塩の代替品の多くは、塩化ナトリウムの代わりに塩化カリウムを使用しています。塩分を控える代わりに大量のカリウムを摂取してしまい、非常に危険です。
調味料を選ぶ際は、必ず原材料名を確認し、「塩化カリウム」の記載がないかチェックする習慣をつけてください。
- サプリメントや健康食品は摂取しても大丈夫ですか
-
自己判断でサプリメントや健康食品、青汁などを摂取することは絶対に避けてください。製品には、カリウムが豊富に含まれているものが多くあります。特に「野菜不足を補う」といった製品は注意が必要です。
何か使用したいものがある場合は、必ず事前に主治医や薬剤師、管理栄養士に相談し、成分を確認してもらいましょう。
以上
透析センター(人工透析) | 大垣中央病院(医療法人社団豊正会 )
参考文献
Kashihara N, Kohsaka S, Kanda E, Okami S, Yajima T. Hyperkalemia in real-world patients under continuous medical care in Japan. Kidney international reports. 2019 Sep 1;4(9):1248-60.
Iwagami M, Kanemura Y, Morita N, Yajima T, Fukagawa M, Kobayashi S. Association of hyperkalemia and hypokalemia with patient characteristics and clinical outcomes in Japanese hemodialysis (HD) patients. Journal of Clinical Medicine. 2023 Mar 8;12(6):2115.
Kohsaka S, Okami S, Kanda E, Kashihara N, Yajima T. Cardiovascular and renal outcomes associated with hyperkalemia in chronic kidney disease: a hospital-based cohort study. Mayo Clinic Proceedings: Innovations, Quality & Outcomes. 2021 Apr 1;5(2):274-85.
Saito Y, Yamamoto H, Nakajima H, Takahashi O, Komatsu Y. Incidence of and risk factors for newly diagnosed hyperkalemia after hospital discharge in non-dialysis-dependent CKD patients treated with RAS inhibitors. PLoS One. 2017 Sep 6;12(9):e0184402.
Sofue T, Nakagawa N, Kanda E, Nagasu H, Matsushita K, Nangaku M, Maruyama S, Wada T, Terada Y, Yamagata K, Narita I. Prevalences of hyperuricemia and electrolyte abnormalities in patients with chronic kidney disease in Japan: A nationwide, cross-sectional cohort study using data from the Japan Chronic Kidney Disease Database (J-CKD-DB). PLoS One. 2020 Oct 15;15(10):e0240402.
Shibata S, Uchida S. Hyperkalemia in patients undergoing hemodialysis: Its pathophysiology and management. Therapeutic Apheresis and Dialysis. 2022 Feb;26(1):3-14.
Takaichi K, Takemoto F, Ubara Y, Mori Y. Analysis of factors causing hyperkalemia. Internal medicine. 2007;46(12):823-9.
Kitai T, Maruyama S, Kuwahara K, Tamura K, Kinugawa K, Kashihara N. Establishing Cross-Specialty Expert Consensus on the Optimal Management of Hyperkalemia in Patients With Heart Failure and Chronic Kidney Disease. Circulation Journal. 2025 Mar 25;89(4):470-8.
Morimoto N, Shioji S, Akagi Y, Fujiki T, Mandai S, Ando F, Mori T, Susa K, Naito S, Sohara E, Anzai T. Associations between dietary potassium intake from different food sources and hyperkalemia in patients with chronic kidney disease. Journal of Renal Nutrition. 2024 Nov 1;34(6):519-29.
Fujimaru T, Hirose K, Yazawa M, Nagahama M, Kovesdy CP. Management of hyperkalemia: strategic clinical actions in real-world practice. Clinical and Experimental Nephrology. 2025 Jul 24:1-3.