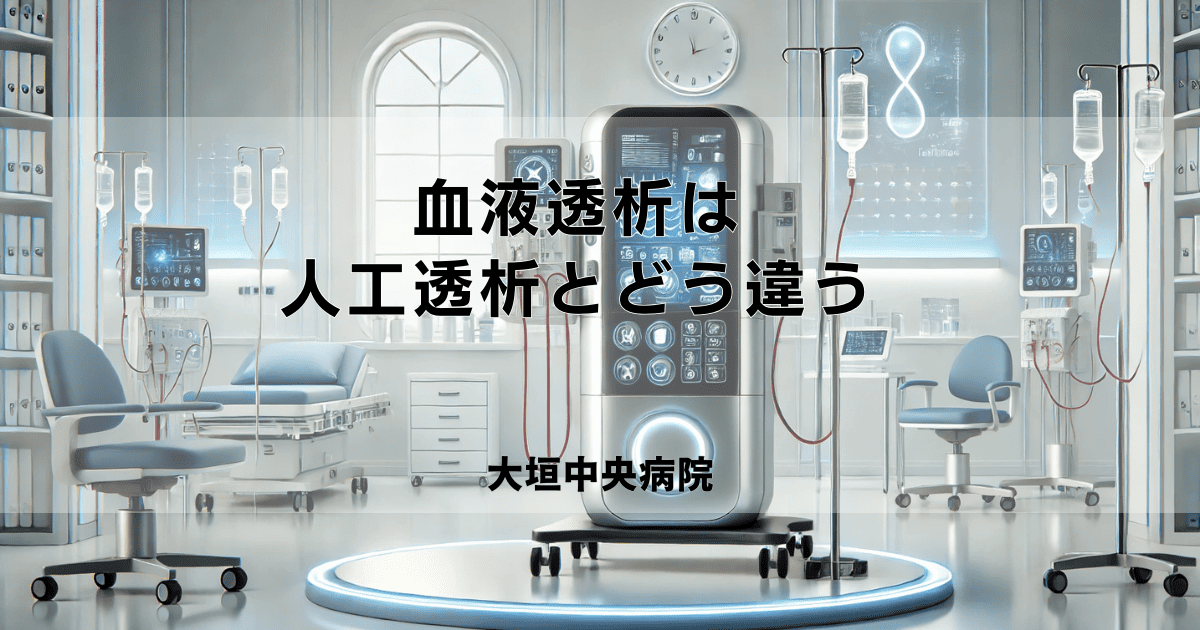腎臓の働きが低下すると、体内の老廃物や余分な水分が十分に排出されず、日常生活に支障をきたす可能性があります。そのような場合に選択肢に挙がるのが、血液透析という治療法を含む透析です。
人工透析という言葉は広い意味で用いられ、血液透析や腹膜透析を含みます。
これから透析が必要になるかもしれないといわれた方や、既に治療を始めることを検討している方に向けて、血液透析と腹膜透析の特徴、通院と在宅での違い、食事や生活習慣で意識したい点などをまとめました。
腎臓の役割と透析が必要となる理由
腎臓は老廃物や水分を排出し、体内の状態を調整する大切な臓器です。しかし腎臓の機能が著しく落ち込み、通常の方法では排出が難しくなると、透析を検討する段階に至ります。
こうした経緯や、腎機能低下に伴う体内の変化について理解しておくと、今後の治療選択がしやすくなります。
腎臓の基礎的な働き
腎臓は左右に1つずつ存在し、主に以下のような重要な役割を担っています。
- 血液中の老廃物をろ過し、尿として排出する
- 体内の水分量や電解質(ナトリウムやカリウムなど)を調節する
- 血圧を調整するホルモンを分泌する
- 赤血球をつくるホルモン(エリスロポエチン)を分泌する
これらがうまく機能しなくなると、むくみや高血圧、貧血など多様な症状が現れます。
腎不全とは何か
腎不全とは、腎臓の機能が大きく低下して老廃物の排出などの働きがうまくいかなくなる状態です。慢性腎不全の場合は腎臓の機能が徐々に落ちていき、最終的に透析を必要とする段階へ進行することもあります。
急性腎不全の場合は短期間で急激に機能が低下し、適切な治療により回復する可能性もありますが、進行すればやはり透析を考えなければならない状況が出てきます。
透析が求められる時期
腎機能の低下度合いは主にeGFR(推算糸球体ろ過量)などの数値で判断します。医師は患者さんの状態や血液検査、尿検査の結果などを総合的に見て、透析治療の開始時期を提案します。
一般的には腎機能が重度まで低下し、体内の老廃物を十分に排出できない段階が透析開始の目安です。症状としては尿量の減少や血圧上昇、倦怠感などがみられ、検査ではクレアチニンや尿素窒素の数値が高くなります。
透析導入の前に行う検査
透析を始める前には、血液検査や尿検査、画像診断などで腎臓の状態を詳しく確認します。同時に心臓や血管の状態を把握し、透析が行える身体的準備が整っているかを評価します。
糖尿病や高血圧などの基礎疾患がある場合には、その治療状況についてもあらためて点検し、透析へのスムーズな移行を目指します。
腎機能低下に伴う主な症状と合併症をまとめた表
| 症状・合併症 | 具体的な例 | 関連する臓器や原因 |
|---|---|---|
| 体液貯留 | むくみ、心不全 | 水分や塩分の排出不十分 |
| 高血圧 | 血圧上昇 | レニン・アンジオテンシン系の異常 |
| 電解質異常 | 高カリウム血症 | カリウム排出不十分 |
| 貧血 | 倦怠感、息切れ | エリスロポエチン分泌低下 |
| 骨代謝異常 | 骨粗鬆症、痛み | カルシウムやリンの代謝障害 |
血液透析という治療法の基礎
血液透析という治療法とは、身体から血液を取り出し、透析器(ダイアライザ)で老廃物や水分をろ過した上で、再び体内に戻す方法を指します。
主に透析施設や総合病院などで実施し、医療スタッフの管理のもとで行うことが多い治療です。
血液透析という名称の由来
「血液透析」という名称は、血液を直接透析器に通すことからつけられています。ダイアライザの膜を通して血液と透析液を接触させ、濃度差を利用して老廃物や余分な水分を取り除きます。
ろ過や拡散といった物理的原理を使って効率的に不純物を分離する点が大きな特徴です。
血液透析の仕組み
血液透析の基本的な流れは以下のとおりです。
- 体内から血液を取り出すためにバスキュラーアクセス(内シャントなど)を確保する
- ダイアライザに血液を通し、老廃物や過剰な水分を透析液に移動させる
- 浄化された血液を再び体内に戻す
この一連の流れを、医師や看護師などの専門スタッフがモニターで観察しながら管理します。
血液透析の流れを整理した表
| 手順 | 概要 | ポイント |
|---|---|---|
| 血液の取り出し | バスキュラーアクセスを使用 | 血流量を確保するための針刺しが重要 |
| ダイアライザでのろ過 | 半透膜を通じて不要物をろ過 | 透析液との濃度差を活用 |
| 血液の返血 | ろ過された血液を体内へ戻す | 返血時の血圧変動や体調変化に注意 |
血液透析を行う頻度と時間
多くの場合、週に3回、1回あたり4時間程度の透析を行います。患者さんの症状や体格、残存腎機能などによって微調整されることもありますが、規則的に透析を行うことで体内のバランスを保ちやすくなります。
一方で通院が必要になるため、スケジュール管理をしっかり行うことが求められます。
血液透析のメリットと留意点
血液透析の利点は、医療スタッフの管理下で安定した治療を受けられる点と、効率的に老廃物や水分を除去できる点です。しかし通院回数が増える、食事や水分摂取を制限する必要があるなどの負担も伴います。
体調や生活スタイルに合わせながら治療計画を立てることが肝要です。
血液透析中に配慮したいリスト
- 透析前後の体重管理
- 血圧の安定
- 透析中の血行動態変化(めまいや吐き気)
- 血液検査での栄養状態チェック
- 透析施設やスタッフとのコミュニケーション
人工透析に含まれる治療法の概念
人工透析という言葉は、腎臓の代わりに体外や腹腔内でろ過を行う治療を総称する用語として使われます。一般的に血液透析と腹膜透析が含まれますが、ほかにも特殊な方法が存在します。
人工透析という言葉の背景
人工透析という呼称は、腎臓の機能を人工的に代替するという意味合いで広まっています。
臨床の場では主に血液透析と腹膜透析が実施されるため、患者さん自身が「人工透析=血液透析」と捉えがちですが、実際には腹膜透析も重要な選択肢です。
血液透析の位置づけ
人工透析の中でも血液透析は広く普及し、施設数や医療スタッフの数が充実しているため、多くの患者さんが選択する治療です。一方で在宅で行う腹膜透析に比べると、通院や治療時間などの負担が生じる場合があります。
医師や医療チームは、患者さんの生活背景や希望を踏まえながら、血液透析をすすめるかどうか検討します。
腹膜透析という選択肢
腹膜透析では、患者さん自身の腹膜を透析膜として利用します。透析液を腹腔内に注入し、一定時間留置してから排液することで老廃物を除去します。
自宅や職場などで行えるため通院頻度を減らしやすいという利点がありますが、毎日継続して行う必要があり、管理上の注意点もあります。
その他の透析法
特殊なケースや合併症を抱える患者さんのために、持続血液透析や夜間透析など、さらに細かく分けられた治療法があります。
いずれも患者さんの症状や生活リズムに合わせて検討されるものであり、血液透析と腹膜透析を基本としながら多様な選択肢があると理解しておくとよいでしょう。
腹膜透析と血液透析を含む人工透析の比較表
| 項目 | 腹膜透析 | 血液透析 |
|---|---|---|
| 治療場所 | 自宅中心 | 医療施設中心 |
| 通院頻度 | 月に数回の検診 | 週に3回程度 |
| 治療時間 | 1回あたり30分ほどの交換×複数回/日 | 1回あたり4時間前後 |
| 機器の操作 | 自分や家族が行う | 医療スタッフが行う |
| 費用面 | 在宅医療関連費用が含まれる | 通院費や治療費が含まれる |
血液透析と腹膜透析の違い
血液透析と腹膜透析は、どちらも人工透析の一種です。原理や治療場所が異なるため、患者さんのライフスタイルや希望に応じた選択が大切です。この章では具体的な違いをいくつか挙げて解説します。
原理の違い
血液透析はダイアライザという装置を使って血液を体外に導き、不要物を取り除きます。腹膜透析は腹膜を透析膜として利用し、透析液と血液が直接触れ合わない形で不要物をろ過します。
前者は拡散とろ過を組み合わせた効率の良い方法ですが、通院が必要です。後者は自宅で行うことが多く、柔軟性が高い反面、自己管理が求められます。
治療場所の違い
血液透析は、ほとんどの場合が病院や透析クリニックで行われます。透析装置が大がかりであり、医療スタッフによる管理が欠かせないためです。一方で腹膜透析は、在宅での治療が可能です。
医療者による指導を受けた上で、自分や家族が透析液の交換を行います。
治療場所の違いによる利点と課題をまとめた表
| 観点 | 血液透析 | 腹膜透析 |
|---|---|---|
| 安心感 | 医療スタッフの常時サポート | 自宅で落ち着いて治療できる |
| 身体的負担 | 定期的な通院が必要 | 自己管理と穿刺リスクが少ない |
| 精神的負担 | 通院スケジュールの調整が必要 | 自宅管理の責任感が大きい |
| 生活リズム | 他者の手を借りやすい | 柔軟に時間を組めるが毎日の作業が必要 |
日常生活への影響
血液透析の場合は週3回程度の通院が必要であり、勤務形態や家族の協力体制を調整する必要があります。その代わり、透析の時間帯以外は制限が少なくなる傾向があります。
腹膜透析の場合は毎日の交換作業を自分で行いますが、外出先でも行いやすい携帯型の装置や方法が開発されているため、日常生活への自由度は比較的高いと考えられます。
費用面や通院頻度
両者ともに公的医療保険の対象になりますが、血液透析は通院回数が多いため、交通費や時間的なコストがかかりがちです。一方で腹膜透析では、在宅での医療費や関連消耗品の管理が必要です。
費用と時間の双方を考慮しながら、自身に合った方法を選んでいく姿勢が大切です。
日常生活の観点から考えるリスト
- 通院や在宅管理に必要な時間
- 仕事や学業との両立
- 家族や介助者のサポート
- 休日や夜間の対応
- 緊急時の連絡先・体制
血液透析を始める際の心構えと準備
血液透析という治療法を導入する際は、身体的準備はもちろん、生活習慣や精神面でのサポート体制も考慮したほうがよいです。ここでは血液透析の準備から日常的なケアまでを段階的に紹介します。
バスキュラーアクセスの種類
血液透析を行う場合、血液を取り出すためのバスキュラーアクセスが必要です。
最も一般的なのは「内シャント(AVF)」と呼ばれる動脈と静脈をつなぎ合わせる方法で、安定した血流量が得られやすく、長期的に利用できます。そのほかに人工血管(AVG)やカテーテルなども状況に応じて利用されます。
アクセスがうまく機能しないと、透析の効果に影響が出るため、早めに作製し、成熟を待つことが重要です。
主なバスキュラーアクセスの特徴を整理した表
| アクセス名 | 方法 | 特徴 |
|---|---|---|
| 内シャント(AVF) | 自己の動脈と静脈を直につなぐ | 長期使用に向くが成熟に時間がかかる |
| 人工血管(AVG) | 合成血管を使って動脈と静脈をつなぐ | 比較的早く使用可能だが感染リスクに注意 |
| カテーテル | 外科的に血管内に挿入 | 緊急時に役立つが長期使用はリスクあり |
食事と水分制限
血液透析中は尿量が減少しやすいため、水分や塩分を過剰に摂ると体内に余分な負荷をかけます。また、カリウムやリンなど電解質のバランスが崩れやすく、心臓や骨に影響を及ぼすこともあります。
主治医や管理栄養士と相談しながら以下の点を意識するとよいでしょう。
- 水分制限:1日の摂取量を決め、むやみに水やお茶を飲みすぎない
- 塩分制限:加工食品や外食の塩分を確認し、可能な限り控える
- カリウムやリン:野菜や果物、乳製品などを制限する必要がある場合もある
- タンパク質:不足しないように量と質を選んで摂取する
透析のスケジュールと仕事の両立
血液透析は週に3回ほど行うことが多く、1回あたり約4時間かかります。就業中の方は、職場と相談してシフトを調整したり、在宅ワークを取り入れるなどの工夫が求められます。
また、通院時間も含めると1日の大半が透析関連に費やされる日があるため、余裕のあるスケジューリングが必要です。
心理的なサポートと情報収集
透析導入時は、精神的にも不安が大きいものです。家族や友人、医療スタッフとのコミュニケーションを図り、自分の状態を理解してもらうことが大切です。
患者会やSNSなどで同じ経験を持つ人の意見を聞く機会をつくると、実生活での対処法が見えてきます。
透析を円滑に行うためのリスト
- 透析施設や病院との連絡体制の確認
- バスキュラーアクセスのセルフケア(洗浄や観察など)
- 毎日の血圧や体重測定の習慣化
- 体調不良時の早期受診
- 家族や職場への理解促進
総合病院で受ける透析治療のメリット
総合病院で血液透析を受ける場合、単に透析だけでなく、さまざまな診療科との連携が期待できます。腎臓の病気以外にも合併症を抱えるケースでは、総合的な治療が受けられる点が大きな魅力です。
急変時の対応と緊急治療
腎臓病は心臓や血管、糖尿病などと関連が深いケースが多く、透析中や透析後に体調が大きく変化することがあります。総合病院であれば、救急科や心臓内科、循環器内科などの診療科がすぐに連携し、緊急事態に迅速に対応できる利点があります。
透析患者さんに起こりやすい合併症や急性変化にも専門家が揃っているため、安心感が高まります。
専門医との連携
総合病院では、腎臓内科以外にも栄養士や薬剤師、リハビリスタッフなどが常勤していることが多く、チーム医療による総合的サポートを受けやすい環境が整っています。
定期的な検査や治療方針の見直しを迅速に行え、患者さんの体調変化やライフイベントに合わせた対応が可能です。
総合病院で受けられる主なサポート体制表
| 専門スタッフ | 役割 | 連携のポイント |
|---|---|---|
| 腎臓内科医 | 透析管理と腎臓病の治療 | 合併症の早期発見と対策 |
| 栄養士 | 食事指導 | 個々の制限量に応じた献立作成 |
| 薬剤師 | 内服薬の調整 | 投薬管理と相互作用の確認 |
| リハビリスタッフ | 運動指導 | 体力維持とQOL向上へのアドバイス |
定期的な検査と評価
総合病院では、血液検査や画像検査などを定期的に受けやすい体制が整っています。透析を受ける患者さんは血液検査をはじめ、心臓や血管の状態を確認するためのエコー検査、X線検査なども必要に応じて行います。
合併症の早期発見や、透析の効果判定を的確に行いやすいメリットがあります。
チーム医療でのサポート
多職種連携によるチーム医療では、医師や看護師だけでなく、管理栄養士やメディカルソーシャルワーカー、理学療法士などが関わります。たとえば、自宅での過ごし方や福祉制度の活用など、幅広い視点からアドバイスを受け取れます。
総合病院だからこそ、個別の事情に合わせた相談が行いやすいです。
総合病院ならではのリスト
- 一度の受診で複数科の予約調整が可能
- 精密検査の機器やスタッフが充実
- 救急対応が整っている
- 医療ソーシャルワーカーによる相談窓口
- 退院後の在宅支援との連携
血液透析と人工透析の将来展望
医療技術は日々進歩し、人工透析の方法や機材、アフターケアなどの選択肢も増えています。患者さんのニーズや生活背景に応じて、多様な治療モデルが広がりつつあります。
透析技術の進歩
血液透析の分野では、ダイアライザの性能向上や透析液の品質管理技術が高まり、効率的に老廃物を除去できる傾向があります。また、血管アクセスの術式も改良され、合併症リスクを下げる工夫が行われています。
腹膜透析においても、透析液の種類や自動化装置の導入など、患者さんの負担を軽減する取り組みが進められています。
現在一般的に用いられているダイアライザの特徴を示す表
| ダイアライザ型 | 膜素材 | 除去性能 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 低通透過型 | セルロース系 | 中分子除去は限定的 | 安価で扱いやすい |
| 高通透過型 | 合成高分子系 | 中・大分子も除去しやすい | 透析効率が高い |
| オンラインHDF用 | 特殊膜とオンラインシステム | 幅広い分子量の老廃物除去 | 血行動態を安定させやすい |
在宅透析の可能性
血液透析においても在宅透析を導入できるケースがあり、腹膜透析の在宅治療と併せて「自宅で治療」という選択肢が徐々に広がっています。
自宅での血液透析には、高性能の小型装置や厳密な水質管理などの条件が必要ですが、通院の負担が軽減されるメリットがあります。
将来的には、より多くの患者さんが自分のライフスタイルに合わせた治療を選べるようになることが期待されます。
生活の質を高める支援策
人工透析を受ける患者さんが仕事や家庭を両立しやすいように、医療機関や行政がさまざまな支援策を整えています。たとえば、フレックスタイム制度を導入している企業への就職や、障害者手帳の取得による医療費控除などが挙げられます。
自分にあった支援制度を知ることで、社会的な活動範囲を広げることができます。
移植との比較検討
透析に代わる腎移植という選択肢も存在し、ドナーが見つかれば手術を受けることで腎機能が回復する可能性があります。ただし、免疫抑制剤の服用やドナー提供の問題など、事前に慎重な検討が欠かせません。
透析を続けながら移植を待つ、あるいは移植を目指すかどうかは、患者さんと医療チームの十分な話し合いに委ねられています。
移植と透析の比較ポイントをまとめたリスト
- 待機期間:ドナーが見つかるまでの時間
- 免疫抑制剤:移植後の服用と副作用のリスク
- 生活の自由度:移植が成功すれば透析不要となる
- 医療費:透析と移植手術の費用比較
- ドナーとの関係:生体腎移植か献腎移植か
透析を検討している方へのメッセージ
透析を導入するかどうかは、多くの方にとって大きな決断です。生活や仕事への影響、家族のサポート体制など考えるべき要素がたくさんあります。
しかし、医療チームと協力しながら情報を集め、自分に合った方法を見いだすことで、より快適な生活を維持できる可能性があります。
早期からの情報収集の大切さ
腎臓の状態や病状の進行度を把握するためには、定期的な検査と専門医のフォローが欠かせません。主治医や透析センターのスタッフに積極的に質問し、自分の腎機能や生活スタイルに合わせた提案を受けることが重要です。
早い段階から情報を集めると、透析を始める時期に慌てず対処しやすくなります。
自分に合った治療法の選択
血液透析だけでなく、腹膜透析や在宅血液透析など、複数の選択肢があることを理解してください。一人ひとりの生活背景や好みによって適した治療法が異なるため、医療スタッフと相談しながら最善の方法を見つけることが大切です。
ときには変更や調整が必要になることもありますが、柔軟に対応できるように準備しておくと安心です。
治療法選択に際して考慮したい表
| 観点 | 血液透析 | 腹膜透析 | 在宅血液透析 |
|---|---|---|---|
| 通院・在宅 | 通院型 | 在宅型 | 在宅型 |
| 医療スタッフの関与 | 直接指導・管理 | 指導後は自己管理が中心 | 定期フォローあり |
| 導入難易度 | 比較的確立 | 自己交換技術が必要 | 機器操作スキルが必要 |
| 生活の自由度 | 通院日以外は自由 | 日々の交換が必要 | 自宅の環境整備が大切 |
病院スタッフとのコミュニケーション
医療チームと良好な関係を築くことは、透析治療の成功につながります。気になることや困ったことは小さなことでも医師や看護師、技士、薬剤師に相談してみましょう。
彼らは医療の専門知識だけでなく、患者さんが生活の中で感じる不安や疑問にも寄り添い、解決策を一緒に考えてくれます。
前向きな姿勢と支援の活用
透析は長期にわたる治療になるケースが多いです。身体的にも精神的にも負担を感じることがあるかもしれませんが、適切な支援や情報を得ることで生活の質を維持できます。
リハビリや栄養指導、社会福祉制度を活用し、より前向きに日常を過ごせるよう医療スタッフと連携してください。
前向きな治療生活のためのリスト
- セルフケアの方法を習得する(体重管理や食事内容など)
- 定期的にカウンセリングや相談を受ける
- 家族や友人とのコミュニケーションを大切にする
- 社会福祉制度や支援グループを活用する
- 疑問や不安をそのままにせず、早めに相談する
以上


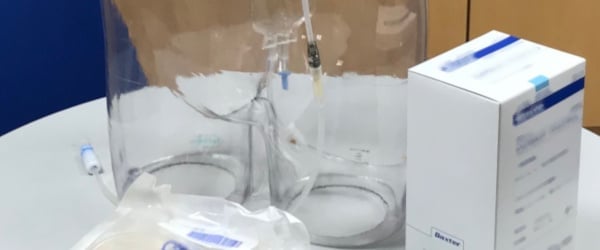
透析センター(人工透析) | 大垣中央病院(医療法人社団豊正会 )
参考文献
TERMORSHUIZEN, Fabian, et al. Hemodialysis and peritoneal dialysis: comparison of adjusted mortality rates according to the duration of dialysis: analysis of The Netherlands Cooperative Study on the Adequacy of Dialysis 2. Journal of the American Society of Nephrology, 2003, 14.11: 2851-2860.
VONESH, E. F., et al. Mortality studies comparing peritoneal dialysis and hemodialysis: what do they tell us?. Kidney International, 2006, 70: S3-S11.
ZAZZERONI, Luca, et al. Comparison of quality of life in patients undergoing hemodialysis and peritoneal dialysis: a systematic review and meta-analysis. Kidney and Blood Pressure Research, 2017, 42.4: 717-727.
FENTON, Stanley SA, et al. Hemodialysis versus peritoneal dialysis: a comparison of adjusted mortality rates. American Journal of Kidney Diseases, 1997, 30.3: 334-342.
LIEM, Ylian Serina, et al. Comparison of hemodialysis and peritoneal dialysis survival in The Netherlands. Kidney international, 2007, 71.2: 153-158.
BLOEMBERGEN, Wendy E., et al. A comparison of mortality between patients treated with hemodialysis and peritoneal dialysis. Journal of the American Society of Nephrology, 1995, 6.2: 177-183.
JAAR, Bernard G., et al. Comparing the risk for death with peritoneal dialysis and hemodialysis in a national cohort of patients with chronic kidney disease. Annals of internal medicine, 2005, 143.3: 174-183.
MEHROTRA, Rajnish, et al. Serum albumin as a predictor of mortality in peritoneal dialysis: comparisons with hemodialysis. American journal of kidney diseases, 2011, 58.3: 418-428.
BLOEMBERGEN, Wendy E., et al. A comparison of cause of death between patients treated with hemodialysis and peritoneal dialysis. Journal of the American Society of Nephrology, 1995, 6.2: 184-191.
SNYDER, Jon J., et al. A comparison of transplant outcomes in peritoneal and hemodialysis patients. Kidney international, 2002, 62.4: 1423-1430.