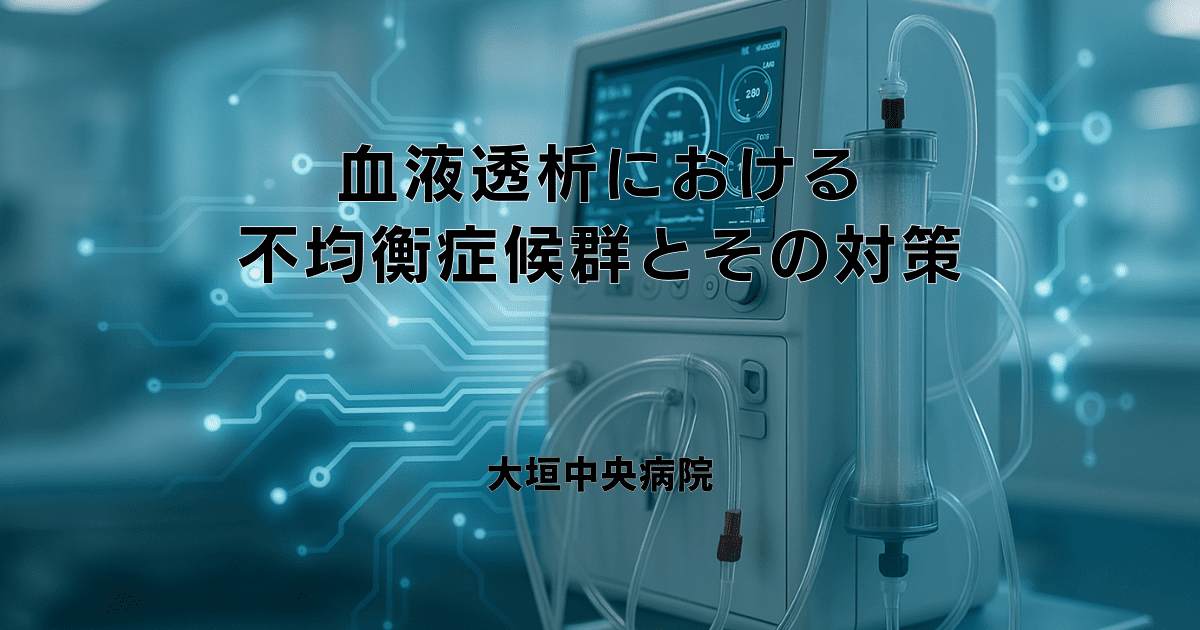血液透析の治療を行う方や、腎機能の低下が進行して透析を検討している方にとって、体への負担を軽減するための知識は重要です。
血液透析不均衡症候群は、その名のとおり血液透析による急激な体液・電解質バランスの変化によって起こる症状の総称です。頭痛や吐き気などの不快症状から重い神経障害に至るまで、さまざまな影響が出る場合があります。
この記事では、その原因や症状、予防の方法について、患者の方やご家族が理解しやすいように整理しました。透析治療中の体調管理をより安心して行えるよう、正しい情報を確認してください。
血液透析不均衡症候群とは
透析治療を始めたばかりの方や、透析条件が大きく変わった方が経験しやすい不均衡症候群は、治療中や治療後しばらくしてから発症します。適切な知識を身につけることで、自分や周囲の方が注意深く見守ることにつながります。
その定義と背景
血液透析不均衡症候群は、体内に溜まった老廃物や余分な水分を透析で短時間に除去する際、脳内および血中の浸透圧の急激な変化によって起こります。
腎臓の働きが正常に保たれている状態では、体内の水分や電解質バランスを一定に調整できますが、人工的な透析では急な変動が生じることがあります。
これが頭痛や吐き気、倦怠感などの症状を引き起こす要因になります。背景としては、透析回数や時間、個々の患者の生理学的特性といった複合的な要素が絡み合っています。
発生の仕組み
体内と透析装置の間で血液を循環させる際、老廃物や余計な水分を除去していきます。この過程で血清ナトリウムなどの電解質濃度が急激に変わり、それに引きずられる形で脳の細胞に一時的な浸透圧差が発生します。
脳内では水分が細胞内へ過剰に移動しやすくなり、脳浮腫のような状態になる可能性があります。これが頭痛、吐き気、めまいなどの不快感につながり、重症になると痙攣や意識障害を起こすケースもあります。
症状の特徴
症状の出かたは人によって差がありますが、初期段階では頭痛や吐き気、全身の倦怠感が代表的です。その後、ひどい時は目のかすみや集中力の低下、極端な場合には意識障害が生じることもあります。
発症は透析中だけでなく、透析終了後数時間たってからあらわれるケースもあるので、治療後の休憩中や帰宅後の体調にも注意が必要です。
不均衡症候群が起こりやすいタイミング
| 時間帯 | 具体的な状態例 | 注意点 |
|---|---|---|
| 透析開始から中盤 | 血液量の調整が急に進むことで頭痛や吐き気が強まる | 透析速度や除水量の設定に対するこまめなチェックが重要 |
| 透析終盤 | 電解質の変化による意識障害のリスク | 透析条件を急に変更しないよう慎重に行う必要がある |
| 透析終了後 | 頭痛や倦怠感が長引く、めまいなどの症状 | 帰宅後も体調を観察し、異常を感じたらすぐ医療機関に連絡 |
血液透析不均衡症候群のリスク要因
原因を知ることで、事前に予防する対策が立てやすくなります。自分自身の体や日頃の生活習慣を見直し、どんな点に気をつける必要があるのかを確認すると、透析治療との付き合い方が変わります。
体内水分と電解質バランス
透析によって除去できる水分量は限られているため、普段からの水分摂取量のコントロールが大切です。塩分を過剰摂取すると、体内に余計な水分が溜まりやすくなり、除水量の増加によって血圧が急激に変化します。
適量の食塩相当量と水分管理を行うことで、体内の電解質バランスが崩れにくくなります。
電解質バランスを保つために考えるポイント
- カリウムが高くならないよう、野菜や果物の下処理を工夫する
- ナトリウム摂取過多を防ぐため、味の濃い調味料を控える
- カルシウムやリンの値を把握し、主治医の指示に応じてサプリや薬を調整する
透析スケジュールと強度
週に3回の透析が一般的ですが、患者の病状や生活背景によっては透析時間や回数が変わる場合があります。除水量を一気に増やして短時間で多くの水分を抜き取ると、血液透析不均衡症候群が起こるリスクが高くなります。
人によっては透析回数を増やして1回あたりの除水量を少なくしたほうが身体への負担が軽くなることもあります。
持病と薬剤の影響
高血圧や糖尿病などの合併症がある場合、血圧調整薬やインスリン製剤などを使用していることが多く、これらの薬は血液透析の影響を受けたり、逆に透析そのものが薬剤の血中濃度に影響を及ぼしたりします。
うまく調整できないと電解質異常が生じやすくなり、結果的に不均衡症候群を誘発しやすくなることがあります。
持病がある人の注意点一覧
| 持病・疾患 | 具体的な注意 | 主な調整の例 |
|---|---|---|
| 高血圧 | 血圧降下薬の投与タイミングを透析日と照らし合わせる | 除水量を急に増やさず緩やかに設定する |
| 糖尿病 | インスリンや経口血糖降下薬の効き方を考慮する | 透析日の食事時間と服薬タイミングを検討する |
| 骨粗鬆症やカルシウム異常 | リン吸着薬や活性化ビタミンDの投与管理を見直す | 定期検査でミネラルバランスを常にチェックする |
具体的な症状と注意すべきサイン
症状を早めに察知し、必要な場合には主治医や看護スタッフに相談することが大切です。異変を感じても我慢して放置すると、症状が深刻化して救急対応が必要になるケースもあります。
頭痛や吐き気のメカニズム
血液透析不均衡症候群では、脳脊髄液の浸透圧差が急に変動し、脳の浮腫を引き起こしやすくなることが主な原因の1つです。その結果、頭蓋内圧が上昇して頭痛や吐き気、視覚障害などを感じる可能性があります。
こうした症状があらわれた際は、透析スピードの調整や水分の除去量を見直すことが効果的な対処の一つです。
血圧変動によるリスク
急激な血圧の上下動は、意識障害や心臓への負担を増大させます。除水量が多いと、透析中に急激に血圧が低下する場合があり、めまいや倦怠感、場合によっては転倒リスクが高まります。
一方、高血圧が持続する場合は、脳出血など重篤な合併症を招くおそれもあるため、透析治療中は適切なモニタリングが必要です。
血圧の変動パターンと危険度
| 血圧変化の傾向 | 体への影響 | 対策 |
|---|---|---|
| 透析中の急激な低血圧 | 立ちくらみやショック状態に陥る | 透析スピードを調整し、補液などを検討する |
| 高血圧の持続 | 心不全や脳出血リスクが高まる | 塩分制限や降圧薬のタイミングを再検討する |
| 透析後の血圧上昇 | 頭痛やめまい、循環器系への負担 | 透析終了後もしばらく安静を保ち、こまめに観察 |
意識障害と神経症状
脳の浮腫が進行すると、軽度のぼんやり感から重度の意識障害まで発展する可能性があります。手足のしびれやけいれん、さらには言語障害が出現することもあります。
重度の症状があらわれた場合は、ただちに医療スタッフに申告して適切な治療を受ける必要があります。
血液透析不均衡症候群の予防策
対策を講じることで、血液透析不均衡症候群を起こす確率が低くなります。事前に自分の生活習慣や体調傾向を理解することが重要です。
透析時間と回数の調整
従来は週3回、1回4時間程度の透析が標準的でしたが、ライフスタイルや体調に合わせて柔軟に検討することが推奨されています。
たとえば、1回あたりの時間を少し長くして除水量を緩やかに行う方法や、逆に短時間透析を週4~5回実施する方法など、人によって選択肢があります。
自身の体調と透析後の疲労度合いを踏まえ、主治医やスタッフと相談して、自分に合った設定を探すことが大切です。
透析回数・時間と体への負担例
| 透析方法 | 回数と時間 | 長所 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 週3回標準的透析 | 1回約4時間 | 日程がシンプルで継続しやすい | 1回あたりの除水量が多く、症状が出やすい可能性 |
| 長時間透析 | 1回約5~6時間 | 除水速度がゆるやかで身体への負担が軽い | 時間的拘束が増え、社会生活との両立に工夫が必要 |
| 高頻度短時間透析 | 週4~5回、1回2~3時間 | 1回の除水量が少なく、症状が出にくい | 回数が多く通院負担が大きい場合がある |
食事制限と水分管理のポイント
血液透析不均衡症候群の予防には、普段の食生活が大きく影響します。特に塩分を含む食品やカリウム、リンを多く含む食品は注意が必要です。
塩分過多は高血圧やむくみを招き、透析で無理に除水しようとすると不均衡症候群が起こりやすくなります。水分摂取では「のどの渇き」に左右されず、計画的に飲む量を決めるとよいでしょう。
担当医と連携した管理
予防の観点で重要なのは、症状が出る前に主治医や看護スタッフと情報を共有し、早めに対策を講じることです。血液検査の結果や、日頃感じている体調の変化を正直に伝えることで、透析条件や薬物処方の微調整が可能になります。
医療チームにこまめに相談する習慣をつくると、より安心して治療に臨めるようになります。
不均衡症候群への初期対処
症状を少しでも感じたら、無理をせず周囲のサポートを得ることが大切です。初期段階で適切なケアを行えば、重症化を防ぎやすくなります。
症状が軽度な場合の工夫
頭痛や吐き気、倦怠感がある程度軽い段階であれば、透析スピードの一時的な変更や除水量の調整が有効な場合があります。身体を温めて血行を促し、ゆっくりと深呼吸することで症状が和らぐこともあります。
ただし症状が悪化し始めた場合は、自己判断で対処しようとせず、迅速にスタッフへ申し出ることが重要です。
医療スタッフによるサポート
医療機関には透析中の症状に対応するための医療スタッフが常駐しています。ベッドの角度調整や、生理食塩水の追加投与、必要に応じた薬剤投与など、症状に合わせた対応を行います。
場合によっては透析を一時中断して様子を見ることも考えられます。
透析中に起こりやすい症状とスタッフ対応
| 症状 | スタッフの主な対応 | 患者側での対策 |
|---|---|---|
| 急な頭痛・吐き気 | 透析速度や除水量の再調整、投薬の検討 | 深呼吸や安静、看護師に声をかける |
| 血圧低下 | ベッドの角度を下げ、補液、酸素投与などの検討 | 無理に立ち上がらず、安静を保つ |
| 足のけいれん | 透析条件の調整、温める、軽いマッサージなど | 痛みが軽減しない場合は早めに申告する |
家族が見守る際の注意点
透析を受ける方の付き添いをする家族も、症状を見逃さないことが大切です。本人が痛みや不調を訴えにくい性格であれば、表情や呼吸の乱れなどから体調不良を察する努力が必要です。
また、透析後は疲労が強く出ることが多いため、移動の補助や車いすの手配などを検討して転倒事故を防ぐと安心です。
透析治療の質を高める取り組み
治療を単に「受ける」だけでなく、積極的に情報を得て、日々の習慣を整えることが血液透析不均衡症候群の軽減にも役立ちます。
定期的なモニタリングと検査
血液検査や心電図、血圧測定などを定期的に行うことで、体調の変化を把握しやすくなります。カリウムやリン、ナトリウムなどの値が急に上昇・下降していないかをチェックすることが、長期的な合併症の予防にもつながります。
検査結果を自分でも確認する習慣をつけると、医療者とのコミュニケーションが円滑になります。
リハビリテーションの活用
安静が必要だと考える方も多いですが、適度なリハビリや運動療法は筋力の維持や血行促進に役立ちます。透析中に行える軽い運動もあり、ふくらはぎのポンプ作用をサポートすることで血圧の安定に寄与します。
主治医やリハビリスタッフと相談しながら、自分に合った運動内容を選択すると、透析への耐性が高まる可能性があります。
透析中や透析前後に行える簡単な運動例
- 足首や手首を回す軽いストレッチ
- 呼吸法を意識したゆったりとした深呼吸
- 椅子に座ったままの上半身のひねり運動
メンタルケアとサポート体制
血液透析不均衡症候群の心身への負担は、体調だけでなく精神面にも影響することがあります。長期にわたる治療に対する不安や、生活の制限から生じるストレスなど、悩みを抱えこむと体調管理が難しくなります。
院内で心理カウンセラーやソーシャルワーカーを活用したり、患者同士のコミュニティで情報交換を行うことは、気持ちを楽にするきっかけとなるでしょう。
血液透析不均衡症候群に関する正しい知識の深め方
インターネットや書籍など、情報源は豊富ですが、中には誤情報も少なくありません。自分に必要な情報をしっかりと選んで理解を深めることが大切です。
さまざまな情報源の活用
医療機関が発信するWebサイトや、学会・公的機関の発行物など、信頼度の高い媒体をまず確認すると、基本的な知識が得やすいです。
専門書は専門用語が多いため、初めての方はややとっつきにくいかもしれませんが、最新の研究動向を把握したい場合や深く学びたい場合に役立ちます。
逆に、個人のブログやSNSは経験談が中心であり、必ずしも一般化できない情報が混在しやすいので、参考程度に留めるほうが無難です。
情報源の特徴と活用方法
| 情報源 | 特徴 | 活用のヒント |
|---|---|---|
| 医療機関のサイト | 専門家の監修が多く、正確性が高い | まず疑問点があれば確認する場所として役立つ |
| 学会・公的機関の発行物 | 科学的根拠にもとづく標準的な情報が得やすい | 根拠に基づいた記述を調べたい時に有効 |
| 個人ブログ・SNS | 生の体験談が多く、共感しやすい | あくまで体験談として参考にとどめる |
| 専門書 | 詳細かつ幅広い知識を得られる | 用語や研究データを深く確認したい時に便利 |
自己学習と主治医への相談
情報収集の基礎としては、自ら学ぶ意欲を維持することが重要です。
日々の透析をこなしながら、自分の体の変化や透析後の疲れ具合を観察し、疑問に思ったことや不安を感じた点をリスト化しておくと、主治医や看護スタッフに効率よく相談できます。
自分で問題を認識しない限り、医療スタッフも的確なフォローが難しくなるため、積極的に情報を整理しておくとよいです。
間違った情報に左右されないための工夫
強い表現を用いた民間療法の宣伝や、科学的な根拠が不十分なメソッドに惑わされると、透析治療の妨げになる可能性があります。ネット上の情報が医療専門家の意見と対立する場合には、主治医に根拠を確認し、冷静に判断してください。
患者自身が意識的に情報の裏付けを探す習慣を持つことが、誤った治療法に流されず、血液透析不均衡症候群の予防と管理を的確に行うための土台となります。
よくある質問
血液透析不均衡症候群への不安を少しでも解消できるよう、患者の方から寄せられやすい疑問について整理しました。頭痛や吐き気などの身体的症状だけでなく、生活上の注意や気持ちの持ち方など、多角的に捉えることがポイントです。
- 不均衡症候群を防ぐ具体策
-
透析時の除水量を減らす工夫や、塩分の取りすぎを控える食事管理が基本です。体調に合わせて透析時間や回数を調整できるなら、症状のリスクが軽減しやすくなります。また、水分管理では「のどが渇く前に少しずつ飲む」ことがコツです。
過度に水分を制限すると血液の粘度が高まり、逆に不均衡症候群を誘発する可能性があるため、主治医と相談してバランスよく決めてください。
- 症状が出たときの相談先
-
頭痛や吐き気、めまいなど、軽い症状であっても透析後に気になる症状があれば、通院先の透析室や主治医に連絡すると安心です。
夜間や休日など、すぐに受診できない時間帯に重い症状が出た場合は、近隣の救急病院を利用することも視野に入れておきましょう。特に意識障害やけいれんなど重度の症状が出現した場合は、すぐに救急車を呼ぶことが重要です。
- 相談先と受診のポイント
-
状況 連絡先 ポイント 軽度の頭痛・吐き気 透析室や主治医 症状の経過や強さを具体的に伝える 休日・夜間の不調 救急外来 症状の開始時刻や透析の最終日を伝える 重篤な意識障害やけいれん 救急車を呼ぶ ためらわず迅速に行動する - 透析治療を続けるうえでの心構え
-
血液透析は長期治療のため、身体面だけでなく精神面のケアも不可欠です。治療日程や食事制限が続くとストレスを抱えがちですが、周囲の家族や医療スタッフと話し合いながら、小さな工夫を積み重ねることで生活の質は向上します。
自分の体調が安定すると、外出や趣味を楽しむことも可能になります。焦らずに少しずつ前向きに取り組みましょう。
以上
透析センター(人工透析) | 大垣中央病院(医療法人社団豊正会 )
参考文献
MISTRY, Kirtida. Dialysis disequilibrium syndrome prevention and management. International journal of nephrology and renovascular disease, 2019, 69-77.
ZEPEDA-OROZCO, Diana; QUIGLEY, Raymond. Dialysis disequilibrium syndrome. Pediatric nephrology, 2012, 27: 2205-2211.
SETHI, Sidharth Kumar, et al. Prevention of dialysis disequilibrium syndrome in children with advanced uremia with a structured hemodialysis protocol: A quality improvement initiative study. Hemodialysis International, 2024, 28.2: 216-224.
BRAR, Gurpreet; SAINI, Hemant Kumar; SOIN, Divya. Assessing the knowledge and practices of staff nurses regarding nursing management of dialysis induced disequilibrium syndrome in chronic renal failure patients. Nursing & Midwifery Research Journal, 2016, 12.2: 70-79.
NOOKAEW, Budsarawadee, et al. Exploring Prevalence and Predictors of Clinically Suspected Dialysis Disequilibrium Syndrome in End-Stage Kidney Disease Patients Initiating Hemodialysis. Journal of Health Science and Medical Research, 2025, 43.3: 20241120.
KANNIKAKAMALI, D.; PARIMALA, L.; KALABARATHI, S. A Study to Assess the Risk Factors and Symptoms of DDS (Dialysis Disequilibrium Syndrome) Among Patient Undergoing Hemodialysis. Cardiometry, 2023, 26: 719-724.
SAHA, Manish; ALLON, Michael. Diagnosis, treatment, and prevention of hemodialysis emergencies. Clinical Journal of the American Society of Nephrology, 2017, 12.2: 357-369.
RAINA, Rupesh, et al. Dialysis disequilibrium syndrome (DDS) in pediatric patients on dialysis: systematic review and clinical practice recommendations. Pediatric Nephrology, 2022, 1-12.
HIDAYATI, Hanik Badriyah, et al. Dialysis disequilibrium syndrome: A case report. Anaesthesia, Pain & Intensive Care, 2024, 28.1: 191-195.
BUNCHMAN, Timothy E., et al. Prevention of dialysis disequilibrium by use of CVVH. 2007.