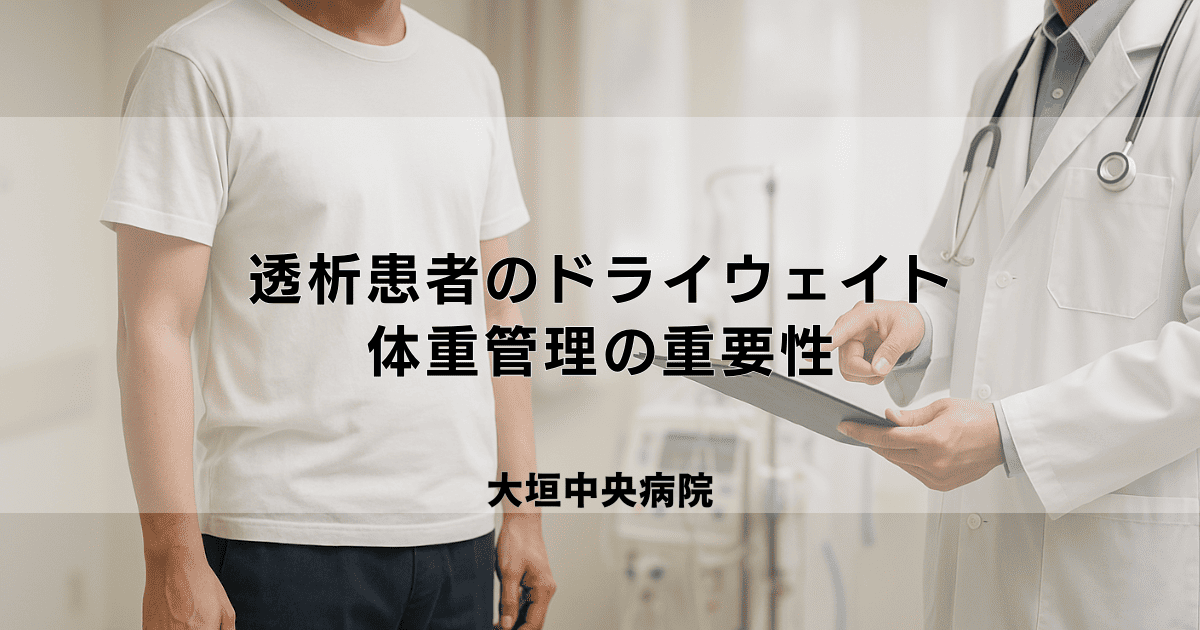透析治療を受けている方にとって、体重管理は治療そのものと同じくらい大切な自己管理の一つで、ドライウェイトという言葉を耳にする機会もあるかと思います。
これは透析治療における目標体重のことで、体内の水分量が適正に保たれている状態の体重で、ドライウェイトを正しく設定し、維持することは、心臓への負担を減らし、透析中のつらい症状を防ぐためにとても重要です。
この記事では、ドライウェイトとは何かという基本的な知識から、決め方、日々の体重管理や水分管理を上手に行うための方法まで、詳しく解説していきます。
そもそも透析患者のドライウェイト(目標体重)とは
透析治療を続けていく上で、ドライウェイトは常に意識するべき重要な指標ですが、なぜこの体重を目指す必要があるのでしょうか。まずはドライウェイトの基本的な考え方と、それが一人ひとり異なる理由について理解を深めていきましょう。
体内の余分な水分がない状態の体重
ドライウェイトとは、透析によって体内の余分な水分や老廃物を十分に取り除いた後の、最も安定した状態の体重のことです。腎臓の機能が低下すると、尿として水分を十分に排泄できなくなり、体内に水分が溜まりやすくなります。
溜まった余分な水分が、むくみや高血圧、心臓への負担の原因となり、透析治療の大きな目的の一つは、余分な水分を取り除くこと(除水)です。
ドライウェイトは、除水の目標となる体重であり、透析後の体重がこの値になるように調整します。
ドライウェイトと適正体重の違い
一般的に使われる適正体重(標準体重)と、透析治療におけるドライウェイトは意味合いが異なります。適正体重は、身長に対して病気になりにくいとされる統計上の理想的な体重(BMIなどから算出)を指します。
一方、ドライウェイトは、その時々の体の状態に基づいた、医学的な観点からの目標体重です。筋肉量や脂肪量、栄養状態によって変動するため、必ずしも適正体重と一致するわけではありません。
筋肉質でがっちりした体型の方と、華奢な体型の方とでは、同じ身長でもドライウェイトは異なります。
透析患者さんにとっての目標は、あくまでも現在の体格や健康状態に応じたドライウェイトであり、一般的な適正体重の数値にこだわる必要はありません。
ドライウェイトと適正体重の考え方の比較
| 項目 | ドライウェイト | 適正体重(標準体重) |
|---|---|---|
| 基準 | 個々の体内の水分バランス | 身長に対する統計的な理想値 |
| 目的 | 心血管系への負担軽減、血圧安定 | 生活習慣病のリスク低減 |
| 変動 | 体調、栄養状態、筋肉量の変化で変動 | 身長が変わらなければほぼ一定 |
なぜ一人ひとりドライウェイトが異なるのか
ドライウェイトは、個人の体格、筋肉量、脂肪量、そして栄養状態によって大きく左右されるため、画一的な基準で決めることはできません。
筋肉は脂肪よりも多くの水分を保持する性質があるため、同じ身長や体重であっても、筋肉量の多い人はドライウェイトが高めに設定されることがあります。
また、食事から摂取する塩分量や、発汗量などの生活習慣も体内の水分量に影響を与え、年齢や性別、合併している病気なども考慮する大事な要素です。
ドライウェイトはどのようにして決めるのか
ドライウェイトは、透析治療の効果と安全性を左右する重要な数値です。医師や医療スタッフは様々な情報を基に、慎重に値を決定します。
身体所見からの評価
最も基本的で重要なのが、医師による身体の診察で、特にむくみの状態は、体内の水分量を判断する上で分かりやすい指標となります。足のすねなどを指で押して、へこみが残るかどうかを確認し、また、血圧の変動も大切な情報です。
透析後に血圧が下がりすぎる場合は、水分を引きすぎている可能性を考え、反対に、常に血圧が高い状態が続く場合は、体内に水分が残っている、つまりドライウェイトが高い可能性が疑われます。
その他、首の血管(頸静脈)の張り具合や、聴診器で心臓や肺の音を聞き、心不全の兆候がないかなども確認します。
検査データを用いた評価
血液検査のデータもドライウェイトを評価するための客観的な指標で、心臓に負担がかかると分泌されるホルモンであるヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド(hANP)や脳性ナトリウム利尿ペプチド(BNP)の数値を測定します。
数値が高い場合、体内の水分量が多く、心臓に負担がかかっている状態であると推測でき、また、透析前後の血液中の尿素窒素(BUN)の濃度などから、体液量の変化を推測することもあります。
数値を定期的に追跡することで、ドライウェイトが適正範囲にあるかどうかを判断する助けとします。
ドライウェイト評価で参考にする主な検査項目
| 評価項目 | どのような情報が得られるか | ドライウェイトとの関連 |
|---|---|---|
| 血圧 | 循環血液量の過不足 | 高い場合は水分過剰、低い場合は水分不足の可能性 |
| 心胸郭比(CTR) | 心臓の大きさ、心臓への負担 | 大きい場合は水分過剰による心拡大の可能性 |
| 血液検査(hANP, BNP) | 心臓への負担の度合い | 数値が高い場合は水分過剰の可能性 |
胸部レントゲンや心胸郭比(CTR)の活用
胸部のレントゲン撮影も、ドライウェイトを設定する上で非常に有用な情報源で、レントゲン写真では、心臓の大きさを評価できます。
体内の水分量が多い状態が続くと、心臓は多くの血液を送り出そうとして拡大し、心臓の大きさを客観的な数値で示したものが心胸郭比(CTR)です。一般的に、CTRが50%以下であることが一つの目安とされます。
また、肺に水が溜まっていないか(肺うっ血)の有無も確認します。画像所見を定期的に評価し、身体所見や検査データと照らし合わせることで、より正確なドライウェイトの評価が可能です。
医療スタッフとの協力で設定する
最終的なドライウェイトは、客観的なデータに加えて、患者さん本人の自覚症状も考慮して総合的に決定します。透析後のだるさ、足のつり、めまいといった症状の有無は、ドライウェイトが適正かどうかを判断する上で非常に重要な情報です。
透析中に不快な症状がなく、透析後も過度な疲労感を感じずに過ごせる体重が、その時点での理想的なドライウェイトと言えます。
そのためには、日頃からご自身の体調の変化をよく観察し、些細なことでも医師や看護師、臨床工学技士といった医療スタッフに伝えることが大事です。
透析治療におけるドライウェイト管理の重要性
ドライウェイトを適正に保つことは、単に透析後の体重を目標値に合わせるというだけではなく、日々の体調を良好に保ち、長期的に健康な生活を送るための基盤となります。
心臓や血管への負担を軽減する
体内に余分な水分が溜まると、血液の全体量が増加し、血液量が増えると、全身に送り出すために心臓はより強く、より頻繁に拍動しなければならず、大きな負担がかかります。
この状態が長く続くと、心臓の筋肉が厚くなったり(心肥大)、心臓の機能そのものが低下したりする心不全という状態を起こす原因となり、また、血液量の増加は血管の壁にかかる圧力を高め、高血圧を招きます。
高血圧は動脈硬化を進行させ、心筋梗塞や脳卒中といった深刻な合併症のリスクを高めます。ドライウェイトを適切に管理し、余分な水分を溜めない生活を送ることは、心臓や血管を守り、生命予後を改善するために極めて重要です。
透析中の不快な症状を予防する
次の透析までの間に体重が増えすぎると、1回の透析で大量の水分を除去(除水)する必要が出てきます。
短時間で急激に多くの水分を体から引き抜くと、血圧が急低下し、めまい、吐き気、冷や汗、足のつり(こむら返り)といった様々な不快な症状を起こしやすいです。
症状は患者さんにとって大きな苦痛となるだけでなく、心臓にも負担をかけます。
日頃から体重増加をコントロールし、ドライウェイトとの差を小さく保つことで、1回あたりの除水量を緩やかにでき、このような透析中の症状を予防し、安定した治療を受けることにつながります。
体重増加量と透析中の症状
| 体重増加 | 除水量 | 起こりやすい症状 |
|---|---|---|
| 少ない | 緩やか | 症状が出にくく、安定しやすい |
| 多い | 急激 | 血圧低下、足のつり、吐き気など |
長期的な健康維持につながる
適切なドライウェイト管理は、血圧の安定、心臓への負担軽減、透析中の症状予防といった短期的なメリットだけでなく、長期的な健康維持にも直結します。
良好な体調を維持できると、食事を美味しく食べることができ、栄養状態の改善につながり、また、体力が維持されることで、仕事や趣味、社会活動などにも意欲的に取り組むことができ、生活の質(QOL)の向上に結びつくのです。
ドライウェイトが適正でない場合の身体のサイン
ドライウェイトは常に一定ではなく、体調の変化によって変動します。設定したドライウェイトが現在の体の状態と合わなくなると、体は様々なサインを発するので、サインにいち早く気づき対処することが大切です。
ドライウェイトが低すぎる場合(引きすぎ)の症状
ドライウェイトの設定が低すぎる、つまり水分を除去しすぎている状態では、体の水分が不足気味になり、様々な不快な症状が現れることがあります。透析の後半や終了直後に血圧が著しく低下するのは、典型的な症状の一つです。
血圧が下がると、めまいや立ちくらみ、強いだるさや倦怠感を感じやすくなります。また、筋肉への血流も不足しがちになるため、足がつりやすくなる(こむら返り)のも特徴です。
このようn症状が頻繁に起こる場合は、ドライウェイトが低すぎる可能性があるので、医療スタッフに相談しましょう。
ドライウェイトが低い場合の主なサイン
- 透析後の著しい血圧低下
- 足のつり(こむら返り)
- 強い倦怠感・疲労感
- めまい・立ちくらみ
- 食欲不振
ドライウェイトが高すぎる場合(残しすぎ)の症状
ドライウェイトの設定が高すぎる、体内に余分な水分が常に残っている状態では、慢性的な水分過剰となり、最も分かりやすいサインは、むくみ(浮腫)です。
特に足の甲やすねに現れやすく、靴下の跡がくっきりと残る、指で押すとへこむ、といった症状が見られ、また、体内の血液量が増えるため、血圧が高くなる傾向があります。
さらに水分が溜まると、肺に水が溜まって(肺水腫)、息切れや呼吸困難感、横になると咳き込むといった症状が現れることもあります。体重がなかなか減らない、常に体が重だるい、といった場合も注意が必要です。
ドライウェイトが高い場合の主なサイン
| 症状 | 具体的な状態 |
|---|---|
| むくみ(浮腫) | 顔、手、足の甲やすねが腫れぼったい |
| 高血圧 | 透析前後ともに血圧が高い状態が続く |
| 息切れ・呼吸困難感 | 階段を上るなど少し動いただけでも息が苦しい |
| 体重増加 | 食事に気をつけていても体重が減りにくい |
自宅でできる体重管理と水分コントロールの工夫
ドライウェイトを維持するためには、医療機関での透析だけでなく、ご自宅での自己管理が鍵を握り、次の透析までの体重増加をいかにコントロールするかがポイントです。
毎日の体重測定を習慣にする
体重管理の基本は、毎日決まった時間に体重を測定し、記録することです。
測定のタイミングは、朝起きてトイレを済ませた後など、毎日同じ条件で行うと、食事や活動による一時的な体重の変動の影響を受けにくく、純粋な体重の変化を把握しやすくなります。
体重計は、できれば100g単位で測定できるデジタル式のものを用意しましょう。測定した体重は、専用のノートやアプリなどに記録し、透析日に持参して医療スタッフに見せることで、治療計画の参考にしてもらえます。
体重測定と記録のポイント
| 項目 | 具体的な方法 | なぜ大切か |
|---|---|---|
| タイミング | 毎日、朝食前・排尿後など決まった時間に | 測定条件を一定にし、正確な変化を把握するため |
| 服装 | パジャマなど、いつも同じ服装で | 衣服の重さによる誤差をなくすため |
| 記録 | 測定した体重、日付、体調などを記録する | 体重の推移を客観的に把握し、透析治療に役立てるため |
水分摂取量の目安と記録
透析患者さんの場合、水分は飲み水だけでなく、お茶やジュース、味噌汁やスープなどの汁物、さらにはご飯やおかずに含まれる水分もすべて摂取量としてカウントする必要があります。
1日の水分摂取量の目安は、尿量や体格などによって個人差があるため、医師や管理栄養士の指示に従ってください。水分をどのくらい摂ったか正確に把握するために、計量カップ付きのコップや水筒を使うと便利です。
飲んだり食べたりしたものの量と時間を記録する習慣をつけると、一日の合計量が分かりやすくなります。特に夏場や運動後など、汗をかいて喉が渇きやすい場面では、水分を摂りすぎないように注意が必要です。
水分摂取の記録例
- 朝食:味噌汁 150ml
- 10時:お茶 100ml
- 昼食:うどんの汁 200ml
- 15時:ゼリー 80ml
- 夕食:煮物(汁を含む) 100ml
塩分を控える食生活のポイント
水分管理と密接に関わっているのが、塩分管理です。塩分を多く摂ると、喉が渇いて水分が欲しくなるだけでなく、体内に水分を溜め込みやすくなります。
体重増加を抑えるためには、水分摂取を我慢するだけでなく、塩分摂取量をコントロールすることが根本的な対策です。加工食品やインスタント食品、漬物や干物などは塩分が多い傾向にあるため、なるべく控えましょう。
調理の際は、香辛料や香味野菜(ショウガ、ニンニク、シソなど)、酸味(酢、レモン汁)を上手に活用すると、薄味でも美味しく感じられます。
醤油やソースは、かけるのではなく、小皿に入れてつけて食べるようにすると、使用量を減らすことができます。
喉の渇きを和らげるアイデア
水分の摂取が制限されていると、喉の渇きがつらく感じられることがあります。そういう時は、一度にたくさんの水を飲むのではなく、少量の冷たい水や氷を口に含み、ゆっくりと溶かすようにすると、渇きが癒えやすくなります。
うがいをするのも効果的で、また、レモンやライムを絞った炭酸水は、爽快感があって少量でも満足感を得やすく、ガムを噛んだり、酸味のあるキャンディーをなめたりして唾液の分泌を促すのも一つの方法です。
喉が渇いてから水分を摂るのではなく、計画的に少量ずつ摂取することで、つらい渇きを予防しましょう。
食事療法とドライウェイト維持の深い関係
ドライウェイトを良好に維持するためには、日々の食事が非常に大きな役割を果たします。単に食べる量を減らすのではなく、何をどのように食べるかを工夫することが、無理のない体重管理につながります。
塩分制限が水分管理の鍵
前述の通り、水分摂取量をコントロールするためには、原因となる塩分摂取量を制限することが最も効果的です。
塩辛いものを食べると、血液の塩分濃度(ナトリウム濃度)が上がると、体はそれを薄めようとして喉の渇きを感じさせ、水分を補給するように指令を出します。
この体の自然な反応を考えると、塩分を控えることがいかに水分管理の基本であるかが分かります。まずは、調味料の使い方を見直してみましょう。
減塩タイプの調味料を選んだり、だし(昆布やかつお節)のうま味を活かして風味を補ったりするのがお勧めです。外食や市販の惣菜は塩分が多いことが多いので、成分表示を確認する習慣をつけましょう。
塩分を減らす調理の工夫
| 工夫の種類 | 具体的な方法 |
|---|---|
| 味付け | 香辛料、香味野菜、酸味(酢・柑橘類)を利用する |
| 素材の味を活かす | 焼く、蒸す、揚げるといった調理法で香ばしさや食感を出す |
| 調味料の使い方 | 表面に味をつける、食べる直前にかける、つけて食べる |
カリウムやリンの管理も大切
透析患者さんの食事療法では、塩分や水分だけでなく、カリウムやリンの制限も必要になることがほとんどです。
カリウムは、野菜や果物、イモ類に多く含まれており、摂りすぎると不整脈などの原因で、リンは、乳製品、魚卵、肉や魚の加工品、インスタント食品などに多く含まれ、骨がもろくなったり、血管の石灰化を進めたりする原因となります。
栄養素の管理は直接ドライウェイトに関わるわけではありませんが、食事全体のバランスを考える上で無視できません。カリウムを減らすために野菜を茹でこぼしたり、水にさらしたりするといった下ごしらえの工夫は、透析食の基本です。
注意が必要な栄養素と多く含まれる食品
- カリウム:生の果物(バナナ、メロン)、生の野菜、イモ類、豆類
- リン:乳製品(チーズ、ヨーグルト)、レバー、魚卵、加工食品
- 塩分:漬物、干物、練り製品、ハム・ソーセージ、インスタント麺
栄養状態を良好に保つ食事の工夫
体重を増やさないようにと意識するあまり、食事量全体が減ってしまうと、必要なエネルギーやたんぱく質が不足し、栄養状態が悪化してしまうことがあります。
特にたんぱく質は、筋肉や血液を作るための重要な栄養素であり、透析で失われる分もあるため、しっかりと摂取することが必要です。
栄養状態が悪化して筋肉量が減ると、基礎代謝が落ちるだけでなく、体力が低下して感染症にかかりやすくなるなど、様々な問題が生じます。
体重管理は大切ですが、あくまでも余分な水分を溜めないためのものであり、食事を抜くこととは違います。
良質なたんぱく質(肉、魚、卵、大豆製品)を中心に、必要なエネルギーを確保できるような、バランスの取れた食事を三食きちんと摂ることを心がけましょう。
定期的なドライウェイトの見直しと調整
一度設定したドライウェイトも、永遠に同じというわけではありません。人の体は常に変化しており、変化に合わせてドライウェイトも定期的に見直し、調整していく必要があります。
なぜドライウェイトは変動するのか
ドライウェイトが変動する最も大きな要因は、筋肉量や脂肪量の変化、つまり栄養状態の変化です。夏バテなどで食欲が落ち、体重が減少した場合、それは単に水分が減ったのではなく、筋肉や脂肪が落ちている可能性があります。
この状態で以前と同じドライウェイトのまま水分を除去し続けると、脱水状態になってしまいます。
逆に、しっかりと食事が摂れるようになり、運動もして筋肉量が増えた場合は、体内に保持できる水分量が増えるため、ドライウェイトを増やす調整が必要になることがあります。
ドライウェイトは体重の増減だけでなく、中身の変化に応じて変動するものなのです。
ドライウェイトが変動する主な要因
- 栄養状態の変化(食事量の増減)
- 筋肉量・脂肪量の変化
- 長期的な体重の増減
- 心臓の機能の変化
- 炎症や感染症の有無
見直しのタイミングと頻度
ドライウェイトの見直しは、定期的に行われ、多くの施設では月に1回程度、レントゲン撮影や血液検査の結果などを基に総合的な評価を行っています。
しかし、それ以外にも、患者さんの体調に大きな変化があった場合は、その都度見直しを検討します。
風邪をひいて食事が摂れなかった後、血圧が下がりやすくなった、透析後のだるさが強くなった、といった自覚症状がある場合は、ドライウェイトが合っていない可能性があります。
また、むくみがひどくなったり、息切れがしたりする場合も同様です。定期的な評価を待つだけでなく、体調の変化を感じたら早めに医療スタッフに伝えることが、適切なドライウェイトを維持する上で大切です。
ドライウェイト見直しを相談するタイミングの例
| タイミング | 具体的な状況 |
|---|---|
| 定期評価 | 月1回程度の定期的な検査結果に基づく評価 |
| 体調変化時 | 風邪、食欲不振、下痢などで体重が大きく変動した時 |
| 症状出現時 | 透析後の血圧低下や足のつりが頻繁に起こる時 |
| 症状悪化時 | むくみや息切れが悪化した時 |
ドライウェイトに関するよくある質問
最後に、透析患者さんからよく寄せられるドライウェイトに関する質問と回答をまとめました。
- ドライウェイトは一度決めたら変わりませんか?
-
ドライウェイトは、その時の体調や栄養状態、筋肉量などによって変動します。
夏場に食欲が落ちて体重が減った場合や、リハビリなどで筋肉量が増えた場合など、体の状態が変化すれば、それに合わせてドライウェイトも見直す必要があります。
定期的にレントゲン検査や血液検査、身体の診察などを行い、その時点での最適なドライウェイトを評価し、必要に応じて調整していきます。体の変化を感じた場合は、医療スタッフに相談することが大切です。
- 体重が増えすぎた場合、次回の透析で多く水分を引いてもらえますか?
-
理論上は可能ですが、推奨されません。短時間で大量の水分を体にから除去すると、血圧の急激な低下や足のつり、吐き気などのつらい症状を起こしやすくなり、また、心臓にも大きな負担がかかります。
透析治療は、安全に安定して継続することが最も重要で、1回の透析での除水量は、無理のない範囲で設定します。
体重が増えすぎた場合は、数回の透析に分けて、少しずつ時間をかけて目標のドライウェイトに戻していくのが一般的です。日頃から体重が増えすぎないように、水分や塩分の管理を心がけることが基本となります。
- 食事をすると体重が増えますが、どう考えればよいですか?
-
食事をすれば、食べたものの重さの分だけ体重が増えるのは当然のことで、透析治療で管理するのは、主に体内に溜まった余分な水分の増加です。食事による体重増加と、水分による体重増加を混同しないようにしましょう。
大切なのは、透析と透析の間の体重増加(中1日、中2日)を、医師から指示された範囲内に抑えることで、この体重増加は、ほとんどが水分と塩分の摂取によるものです。
食事は栄養を摂るために重要ですので、必要なエネルギーやたんぱく質はしっかり摂取し、その上で水分と塩分を上手にコントロールしていくことが求められます。
- 夏場など汗をかく時期の注意点はありますか?
-
夏は汗をかくため、喉が渇きやすく、冷たい飲み物を摂りすぎてしまいがちです。汗として体から水分は出ていきますが、尿が出ない透析患者さんの場合、飲んだ水分はそのまま体内に溜まってしまいます。
汗で失われるのは水分だけでなく塩分も含まれるため、体の塩分濃度はあまり変わらず、思ったほど体重は減らないことが多いです。
喉の渇きに対して、安易に水分摂取で対応するのではなく、冷たいおしぼりで体を拭いたり、うがいをしたり、氷を口に含んだりする工夫をしましょう。
また、汗をかいたからといって自己判断でドライウェイトを下げたりせず、必ず医療スタッフに相談してください。
以上
参考文献
Ohashi Y, Sakai K, Hase H, Joki N. Dry weight targeting: the art and science of conventional hemodialysis. InSeminars in Dialysis 2018 Nov (Vol. 31, No. 6, pp. 551-556).
Tamaura Y, Nishitani M, Akamatsu R, Tsunoda N, Iwasawa F, Fujiwara K, Kinoshita T, Sakai M, Sakai T. Association between interdialytic weight gain, perception about dry weight, and dietary and fluid behaviors based on body mass index among patients on hemodialysis. Journal of Renal Nutrition. 2019 Jan 1;29(1):24-32.
Sato Y, Toida T, Nakagawa H, Iwakiri T, Nishizono R, Kikuchi M, Fujimoto S. Diminishing dry weight is strongly associated with all-cause mortality among long-term maintenance prevalent dialysis patients. Plos one. 2018 Aug 27;13(8):e0203060.
Inoue H, Oya M, Aizawa M, Wagatsuma K, Kamimae M, Kashiwagi Y, Ishii M, Wakabayashi H, Fujii T, Suzuki S, Hattori N. Predicting dry weight change in Hemodialysis patients using machine learning. BMC nephrology. 2023 Jun 29;24(1):196.
Sunagawa D, Imamura Y, Matsumura S, Inoue H, Wakabayashi H, Hayashi T, Takahashi Y, Joki N. Lower dry weight is associated with post‐hemodialysis hypokalemia. Therapeutic Apheresis and Dialysis. 2025 Jun;29(3):365-74.
Kanno Y, Kanda E, Kato A. Methods and nutritional interventions to improve the nutritional status of dialysis patients in JAPAN—a narrative review. Nutrients. 2021 Apr 21;13(5):1390.
Chazot C. Managing dry weight and hypertension in dialysis patients: still a challenge for the nephrologist in 2009. J Nephrol. 2009 Sep 1;22(5):587-97.
Sakai A, Hamada H, Hara K, Mori K, Uchida T, Mizuguchi T, Minaguchi J, Shima K, Kawashima S, Hamada Y, Nikawa T. Nutritional counseling regulates interdialytic weight gain and blood pressure in outpatients receiving maintenance hemodialysis. The Journal of Medical Investigation. 2017;64(1.2):129-35.
Kurita N, Hayashino Y, Yamazaki S, Akizawa T, Akiba T, Saito A, Fukuhara S. Revisiting interdialytic weight gain and mortality association with serum albumin interactions: the Japanese dialysis outcomes and practice pattern study. Journal of Renal Nutrition. 2017 Nov 1;27(6):421-9.
Nakatani H, Shoji H, Shibata M, Yoshida M, Tadokoro Y, Ogura N, Inoue Y, Hanazaki K, Hamada S, Kawamura A. Control of dry weight and tube feeding improved the general condition of a hemodialysis patient: report of a case. Hiroshima Journal of Medical Sciences. 2011;60(2):37-9.