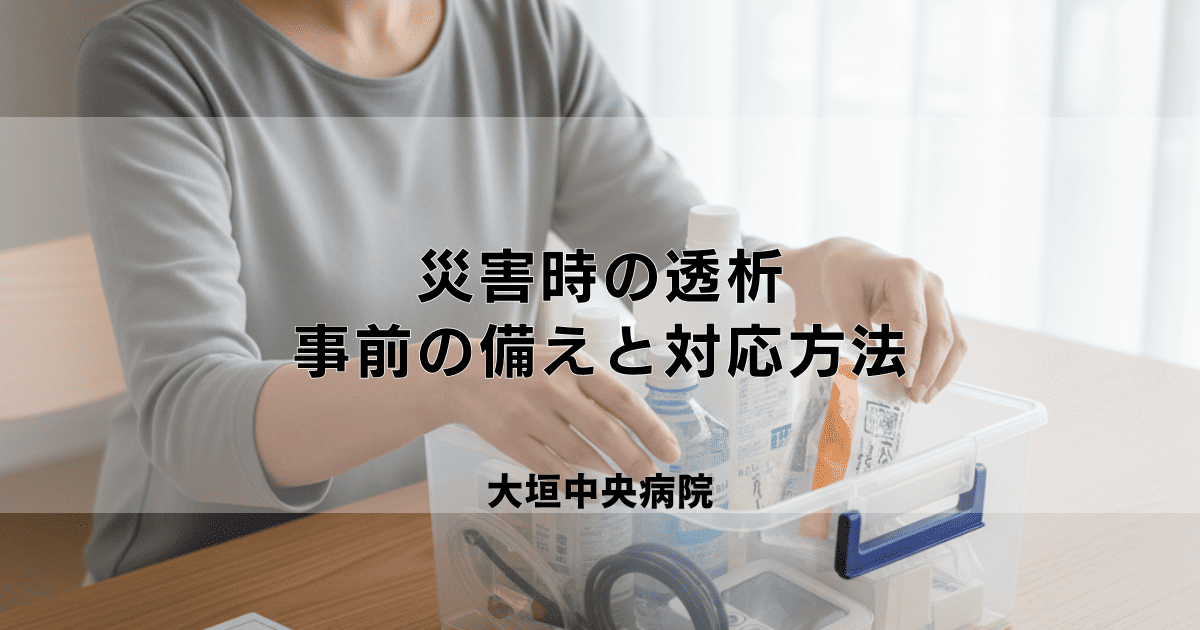日本は地震や台風、豪雨など、さまざまな自然災害が発生しやすい国です。もしもの災害時、定期的な治療を必要とする透析患者さんやご家族は、大きな不安を感じるかもしれません。
ライフラインが止まり、交通網が乱れ、医療機関が通常通り機能しなくなった状況で、どのように透析治療を続ければ良いのでしょうか。
この記事では、透析を受けている方々が災害という緊急事態に直面した際に、ご自身の安全と健康を守るための事前の備えと、災害発生後の具体的な対応方法について、詳しく解説します。
なぜ災害時の透析に備えが必要なのか
災害は、私たちの日常を突然大きく変えてしまいます。定期的な透析治療を受けている方にとって、影響は計り知れません。普段当たり前のように受けている治療が、災害時には困難になる可能性があります。
ライフラインの停止と透析治療への影響
透析治療は、大量の電力と水を必要とする医療です。大規模な災害が発生すると、停電や断水といったライフラインの停止が起こる可能性が非常に高く、透析装置を動かすための電気がなければ、治療そのものを行うことができません。
また、透析液の作成や装置の洗浄には清浄な水が大量に必要であり、断水は透析治療の継続を困難にします。多くの医療機関では自家発電装置や貯水タンクを備えていますが、能力には限りがあります。
燃料や水の供給が途絶えれば、長時間にわたるライフラインの停止には対応しきれない場合も考えられるため、災害の規模によっては、いつも通りの透析が受けられなくなるという事態を想定しておくことが大事です。
ライフライン停止による透析治療への具体的な影響
| ライフライン | 透析治療への影響 | 考えられる事態 |
|---|---|---|
| 電力 | 透析装置の稼働停止、院内照明・空調の停止 | 治療の中断、医療環境の悪化 |
| 水道 | 透析用水の不足、衛生環境の悪化 | 透析回数の減少、感染症リスクの増大 |
| ガス | 暖房や給湯の停止、調理設備の停止 | 低体温リスク、温かい食事の提供困難 |
交通網の寸断と通院困難のリスク
地震による道路の損壊や、豪雨による冠水、公共交通機関の運行停止など、災害は交通網に深刻なダメージを与え、透析施設までの通院が極めて困難になる可能性があります。
自家用車や送迎サービスを利用して通院している方にとって、道路の寸断は致命的です。また、電車やバスなどの公共交通機関も、復旧には時間がかかることが多く、代替手段をすぐに見つけるのは容易ではありません。
通院できなければ、当然ながら透析治療は受けらず、治療の間隔が空いてしまうと、体内に水分や老廃物が溜まり、心不全や高カリウム血症など、命に関わる状態を起こす危険性が高まります。
災害時の通院手段を複数想定し、避難経路と合わせて確認しておくことは、治療を継続するための重要な備えです。
医療機関の機能低下と受け入れ制限
災害時には、通院している透析施設自体が被災する可能性も考えなければなりません。建物の損傷、医療機器の故障、スタッフの不足など、さまざまな要因で医療機関の機能は著しく低下します。
また、災害拠点病院に指定されている施設では、多くの負傷者が搬送されてくるため、通常業務が圧迫されることもあります。
このような状況では、すべての透析患者さんを通常通りに受け入れることが難しくなり、透析時間や回数を短縮したり、一時的に受け入れを制限したりする場合があり、他の地域からの患者さんを受け入れる余裕もなくなるかもしれません。
自分の通う施設が被災した場合に、どこで透析を受けられるのか、地域の他の透析施設や災害時の連携体制について、あらかじめ情報を得ておくことが、万が一の事態への備えです。
情報の混乱と安否確認の重要性
災害発生直後は、電話回線が輻輳し、インターネットも繋がりにくくなるなど、情報が錯綜しがちです。
どの情報が正しいのか見極めるのが難しくなり、不安な気持ちが増大し、透析施設からの連絡が届かない、施設の状況が分からないといった事態も十分に起こりえるので、家族や支援者との安否確認は非常に重要です。
無事を知らせ、必要な助けを求めるためにも、災害用伝言ダイヤル(171)やSNSなど、複数の連絡手段を事前に家族と話し合っておくことが大切になります。
また、透析患者さん自身の情報(氏名、血液型、透析条件など)を記したカードを常に携帯することも、万が一の際に適切な医療を受けるための重要な備えです。
災害発生前に行うべき準備
災害はいつ起こるかわからないので、日頃からの備えが何よりも大切です。ここでは、透析患者さんが災害発生前に行っておくべき準備について、項目ごとに詳しく解説します。
非常用持ち出し袋の準備と中身
災害が発生し、避難が必要になった場合に備えて、非常用持ち出し袋を準備しておくことは基本中の基本です。透析患者さんの場合は、一般的な防災グッズに加えて、ご自身の治療に関わるものを忘れずに入れる必要があります。
持ち出し袋は、すぐに持ち出せる場所に保管しておきましょう。また、定期的に中身を確認し、使用期限が切れているものはないか、薬は最新のものになっているかなどをチェックする習慣をつけることが重要です。
透析患者さんのための非常用持ち出し袋チェックリスト
| 分類 | 品目例 | 確認事項 |
|---|---|---|
| 医療情報 | お薬手帳、透析条件の記録、保険証・診察券のコピー | いつでも最新の情報に更新しておく |
| 医薬品 | 常備薬(降圧薬、リン吸着薬など)最低7日分 | 予備の薬を別途準備しておく |
| 衛生用品 | ウェットティッシュ、消毒液、マスク、ビニール袋 | 感染症対策は特に重要 |
持ち出し袋には、最低3日分、できれば7日分程度の薬や衛生用品を入れておくと安心です。特に、毎日服用が必要な降圧薬やリン吸着薬、血糖降下薬などは、絶対に忘れないようにしましょう。
お薬手帳は、万が一かかりつけ以外の医療機関にかかる際に、ご自身の情報を正確に伝えるための命綱となります。
家族や関係者との連絡方法の確認
災害時には、電話が繋がりにくくなることが予想されるため、家族や親しい友人、勤務先など、大切な人たちと安否確認をするための方法を、あらかじめ複数決めておくことが大切です。
災害用伝言ダイヤル(171)や災害用伝言板(web171)の利用方法を事前に確認し、一度試してみるのも良いでしょう。また、SNSやメッセージアプリなども有効な連絡手段となりえます。
どの手段を使うか、どこに避難するか、集合場所などを話し合っておくことで、災害時の混乱の中でも落ち着いて行動することに繋がります。
- 災害用伝言ダイヤル(171)
- 災害用伝言板(web171)
- SNS(X、Facebookなど)
- メッセージアプリ
- 遠方の親戚を中継点にする
かかりつけ医や透析施設との情報共有
普段から、かかりつけの透析施設と良好な関係を築いておくことも、災害への備えです。災害時の連絡方法や、施設が被災した場合の対応方針などを、事前に確認しておきましょう。
多くの施設では、災害時の対応マニュアルを作成しているので、内容を理解し、疑問点があれば質問しておくことが重要です。
また、ご自身の緊急連絡先や避難場所の候補などを施設側に伝えておくことで、いざという時に施設からの連絡が受けやすくなります。
透析条件やシャントの状態などを記録した「透析カード」や「災害時連絡カード」を施設で発行してもらい、常に携帯する習慣をつけましょう。
災害時連絡カードの主な項目
| 項目 | 記載内容の例 |
|---|---|
| 個人情報 | 氏名、生年月日、血液型、住所、緊急連絡先 |
| 医療情報 | 透析施設名と連絡先、主治医名、透析条件、シャント情報、既往歴、アレルギー |
| 服用中の薬剤 | 薬剤名、用法、用量 |
自宅の安全対策と避難経路の確認
災害は、自宅にいる時に発生するとは限りませんが、在宅時の安全を確保することは非常に重要です。特に地震に備えて、家具の固定は必ず行い、タンスや本棚、食器棚などが倒れてこないように、転倒防止器具で壁に固定します。
また、寝室には大きな家具を置かない、または配置を工夫するなどの配慮も大切で、ガラスの飛散を防ぐフィルムを窓に貼るのも有効な対策です。あわせて、自宅から避難場所までの避難経路を実際に歩いて確認しておくことも忘れないでください。
透析患者のための食料と水分備蓄
災害時には、食料の確保が困難になることが予想されます。透析患者さんは食事制限があるため、普段の食事療法を可能な限り維持し、体調を悪化させないために、食料と水分の備蓄は極めて重要です。
災害時の食事療法の基本原則
災害時の食事は、生き延びるためのエネルギー確保が最優先ですが、透析患者さんの場合は、それに加えて体内の水分や電解質のバランスを崩さないための配慮が必要です。
基本は、普段の食事療法と同じく、水分、塩分、カリウム、リンの制限ですが、透析の間隔が通常よりも空いてしまう可能性を考慮すると、普段以上に厳格な管理が求められます。
特に、カリウムは不整脈など命に関わる合併症を起こす可能性があるため、摂取量には細心の注意を払う必要があります。
エネルギー不足になると、体内のたんぱく質が分解されてカリウム値が上昇することがあるため、炭水化物を中心に、しっかりとエネルギーを摂取することが大切です。
備蓄すべき食品の選び方
透析患者さんが備蓄する食品は、長期保存が可能で、調理の手間が少なく、栄養管理がしやすいものを選ぶのが基本です。缶詰やレトルト食品、乾物などを中心に準備しましょう。
エネルギー源となる炭水化物を多く含む、ごはん(アルファ米やレトルト粥)、もち、乾パン、クラッカーなどは多めに備蓄しておくと安心です。たんぱく質の摂取は、災害時には普段より控えめにする必要があります。
リンやカリウムが比較的少ない魚の缶詰(水煮)などを少量備蓄する程度が良いでしょう。野菜は、カリウムを多く含むものが多いため、缶詰やフリーズドライ製品を選ぶ際には成分表示をよく確認することが重要です。
備蓄に適した食品の例
| 食品分類 | 具体例 | 選び方のポイント |
|---|---|---|
| 主食(エネルギー源) | アルファ米、レトルト粥、もち、乾パン、クラッカー | 水分をあまり使わずに食べられるものが便利 |
| 主菜(たんぱく質源) | 魚の水煮缶、コンビーフ缶(少量) | 塩分、リンが少ないものを選ぶ |
| その他 | 栄養補助食品(ゼリー飲料など)、飴、はちみつ | 手軽にエネルギー補給ができるもの |
水分摂取の管理と注意点
断水に備えて、飲料水の備蓄は必須です。1人1日2リットルを目安に、最低3日分、できれば7日分を備蓄しておきましょう。ただし、透析患者さんは水分の摂取制限があるため、ただ備蓄すれば良いというわけではありません。
災害時であっても、普段の水分管理の基本を守ることが大切で、1日の飲水量は、主治医から指示されている範囲を厳守してください。
汗をかく夏場や、力仕事をした後など、のどが渇きやすくなりますが、一気に飲むのではなく、少しずつ口に含んで潤すようにし、氷をなめるのも一つの方法です。スープや味噌汁などの汁物も水分に含まれるため、食事の際にも注意しましょう。
カリウム・リン・塩分を抑える工夫
災害時の限られた食材の中で、カリウム、リン、塩分をコントロールするには、いくつかの工夫が必要です。
カリウムは水に溶けやすい性質があるため、野菜やいも類は、細かく切ってから水にさらしたり、ゆでこぼしたりすることで、含有量を減らすことができます。
ただし、災害時には貴重な水を使うことになるため、カリウムの少ない食品をあらかじめ選んで備蓄しておくことが現実的です。
リンは、たんぱく質を多く含む食品や乳製品、加工食品に多く含まれているので、摂取を控えめにすることが基本です。
塩分については、調味料の使用を極力減らし、香辛料や酸味(酢、レモン汁など)をうまく利用して味付けを工夫すると、薄味でもおいしく食べられます。缶詰などを利用する際は、汁を捨てるだけでも減塩に繋がります。
カリウムを多く含むため注意が必要な食品
- 生の果物(バナナ、メロン、キウイなど)
- 生の野菜(ほうれん草、かぼちゃなど)
- いも類(さつまいも、じゃがいも)
- 海藻類、きのこ類
- 豆類、ナッツ類
もしもの時の透析中断リスクと自己管理
災害の規模や状況によっては、残念ながら予定通りに透析が受けられない事態も起こりえますが、そのような状況でも、適切な自己管理を行うことで、体調の悪化を最小限に抑えることは可能です。
透析が受けられない場合の身体への影響
透析治療が中断すると、体内に水分と老廃物が急速に蓄積していき、まず現れるのが、体重の増加と血圧の上昇です。
身体がむくみ、息苦しさや動悸を感じるようになり、これは、余分な水分が肺や心臓に負担をかけているサイン(心不全、肺水腫)であり、非常に危険な状態です。
また、老廃物である尿毒素が溜まると、吐き気や食欲不振、頭痛、倦怠感といった尿毒症の症状が現れます。さらに深刻なのが、カリウムの蓄積による高カリウム血症です。
体内のカリウム濃度が異常に高くなると、致死的な不整脈を引き起こし、心停止に至る危険性があります。
透析中断時の体調変化チェックリスト
| 注意すべき症状 | 考えられる状態 | 緊急度 |
|---|---|---|
| 息苦しさ、横になると咳が出る | 肺水腫、心不全 | 高 |
| 手足のしびれ、脱力感、不整脈 | 高カリウム血症 | 高 |
| 強いむくみ、急激な体重増加 | 水分過剰 | 中〜高 |
緊急時の食事と水分コントロール
透析が受けられないかもしれない、という状況になったら、直ちに食事と水分の管理を普段以上に厳しくする必要があります。
まず、水分は極限まで制限し、飲水だけでなく、食事に含まれる水分も考慮し、1日の摂取量を厳密に管理してください。食事は、エネルギーを確保しつつ、カリウム、リン、塩分、たんぱく質を最大限に抑えることが目標です。
主食であるごはんやパン、めん類でエネルギーを確保し、おかずはほとんど食べないくらいの意識が必要です。特に、カリウムを多く含む生野菜、果物、いも類は絶対に避けてください。
塩分も極力摂取しないようにし、味付けのないおにぎりや、飴、氷砂糖などで空腹をしのぎ、エネルギーを補給するのが現実的な方法です。
体調変化のチェックポイント
透析が中断している間は、毎日決まった時間に自身の体調をチェックする習慣をつけましょう。まず、体重と血圧の測定が基本で、可能であれば1日2回測定し、記録しておきます。
急激な体重増加や血圧の上昇は、危険なサインで、また、尿量の変化にも注意します。尿が全く出なくなる、あるいは極端に少なくなる場合は、水分が体内に溜まっている証拠です。
息苦しさ、むくみ、手足のしびれなど、前述した危険な症状がないかどうかも、常に意識してください。少しでも異常を感じたら、ためらわずに近くの医療機関や救護所に相談することが重要です。
処方薬の管理と服用方法
災害時であっても、処方されている薬は自己判断で中断してはいけません。血圧を下げる薬(降圧薬)や、リンを吸着する薬、血糖値をコントロールする薬などは、指示通りに服用を続けることが重要です。
ただし、食事の量が極端に少ない場合には、薬の効き方が変わることがあります。食事がとれない時のリン吸着薬の服用や、血糖降下薬の調整については、可能であれば医師や薬剤師に相談するのが望ましいです。
それが難しい状況では、低血糖や副作用に注意しながら、慎重に服用してください。非常用持ち出し袋に入れた薬は、計画的に使用し、残りの日数を確認しながら、早めに補給できる手立てを探すことも大切です。
災害時透析医療ネットワークの役割と活用
大規模な災害が発生した際、個々の医療機関だけで対応するには限界があるため、透析医療の分野でも、地域や国レベルでの連携体制が整備されています。
災害派遣医療チーム(DMAT)とは
DMAT(Disaster Medical Assistance Team)は、医師、看護師、業務調整員などで構成され、大規模な災害や事故の現場に迅速に駆けつけ、救命医療を行う専門的な訓練を受けた医療チームです。
DMATの主な任務は、被災地でのトリアージ(治療の優先順位付け)や応急治療ですが、現地の医療機関の支援も行います。
透析医療に関しても、被災した透析施設の状況を調査したり、患者さんの搬送を調整したりと、重要な役割を担うことがあります。
地域における透析施設の連携体制
各都道府県や地域ブロック単位で、災害時に透析医療を継続するための連携体制が構築されていて、災害拠点病院を中心に、地域の透析施設が互いに協力し合う仕組みです。
ある施設が被災して透析を行えなくなった場合、近隣の施設が患者さんを一時的に受け入れたり、スタッフや医療物資を融通し合ったりし、連携を円滑に行うため、多くの地域では災害時の情報共有システムが導入されています。
透析カードや災害時連絡カードの重要性
災害時に、いつもと違う施設で透析を受ける可能性は十分にあり、その際、ご自身の医療情報を正確に伝えるために不可欠なのが、透析カードや災害時連絡カードです。
カードには、氏名や連絡先といった基本情報に加え、透析条件(ドライウェイト、使用ダイアライザー、血液流量など)、シャントの状態、既往歴、アレルギー情報、服用中の薬剤といった、治療に必要な情報が網羅されています。
カードを提示することで、初めての医療スタッフでも迅速かつ安全に透析治療を開始でき、災害時における「カルテ」の代わりとなる重要なツールです。常に財布や保険証ケースなどに入れて携帯しましょう。
透析センター(人工透析) | 大垣中央病院(医療法人社団豊正会 )
よくある質問(Q&A)
災害と透析治療に関して、多くの方が抱く疑問や不安について、Q&A形式でお答えします。
- 停電しても透析は受けられますか?
-
多くの透析施設では、非常用の自家発電装置を備えているため、短時間の停電であれば、透析治療を継続できる場合が多いです。
しかし、自家発電装置を動かすための燃料には限りがあり、長期間の停電に対応できるわけではありません。
また、装置があっても、災害の規模によっては施設の他の部分が損傷し、安全に治療を行えないと判断されることもあります。
停電したからといって、すぐに透析が不可能になるわけではありませんが、状況によっては時間短縮や回数制限などの措置がとられる可能性があることを理解しておきましょう。
- 薬がなくなってしまったらどうすれば良いですか?
-
まずは、最低でも7日分程度の予備の薬を非常用持ち出し袋に入れておくことが大原則です。それでも薬が尽きてしまった場合は、避難所の救護所や、診療を行っている最寄りの医療機関に相談してください。
お薬手帳があれば、どのような薬が必要かを正確に伝えることができ、災害時には、処方箋がなくても、医師の判断で薬を処方してもらえる特例措置がとられることがあります。
自己判断で服用を中断する前に、必ず医療専門家に相談してください。
- 避難所で透析患者であることを伝えるべきですか?
-
避難所には、さまざまな事情を抱えた方が大勢いるので、ご自身が透析患者であり、食事や水分に制限があること、定期的な治療が必要であることを、避難所の運営スタッフや保健師に明確に伝えることが重要です。
食事の配慮や体調悪化時の迅速な対応、透析施設からの連絡の取り次ぎなど、必要な支援を受けやすくなります。また、周囲の避難者にも事情を理解してもらうことで、無用なトラブルを避けることにも繋がります。
- 災害時に旅行先で被災したらどうなりますか?
-
旅行や出張などで、かかりつけの施設から遠く離れた場所で被災する可能性もゼロではありません。このような事態に備え、旅行の際には必ずお薬手帳と透析カード、そして多めの常備薬を携帯しましょう。
被災した場合は、まず現地の自治体が発信する災害情報に従い、安全な場所に避難します。
その後、滞在先の地域の災害拠点病院や、日本透析医会などが発信する災害時情報ネットワークを通じて、透析が受けられる施設を探すことになります。
かかりつけの施設に連絡が取れれば、情報提供などの支援を受けられる場合もあります。旅行前には、滞在先の地域の透析施設をいくつか調べておくと、より安心です。
以上
参考文献
Masakane I, Akatsuka T, Yamakawa T, Tsubakihara Y, Ando R, Akizawa T, Minakuchi J, Nitta K. Survey of dialysis therapy during the Great East Japan Earthquake Disaster and recommendations for dialysis therapy preparation in case of future disasters. Renal Replacement Therapy. 2016 Aug 25;2(1):48.
Sugisawa H, Shinoda T, Shimizu Y, Kumagai T. Cognition and implementation of disaster preparedness among Japanese dialysis facilities. International Journal of Nephrology. 2021;2021(1):6691350.
Takamatsu K, Ozaki A, Kotera Y, Sawano T, Sonoda Y, Nonaka S, Ito N, Zhao T, Tsubokura M, Kawaguchi H, Shimmura H. What facilitated the successful evacuations of patients on dialysis after the Great East Japan Earthquake and Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant accident? A qualitative analysis of facility staff experiences and perspectives. International Journal of Disaster Risk Reduction. 2025 Feb 1;117:105135.
Tamura H, Kuraoka S, Hidaka Y, Nagata H, Nakazato H. Pediatric peritoneal dialysis during the recent earthquakes in Japan and recommendations for future disaster preparation. Kidney International Reports. 2020 Jul 1;5(7):1061-5.
Sugisawa H, Shimizu Y, Kumagai T, Sugisaki H, Ohira S, Shinoda T. Earthquake preparedness among Japanese hemodialysis patients in prefectures heavily damaged by the 2011 Great East Japan Earthquake. Therapeutic Apheresis and Dialysis. 2017 Aug;21(4):334-44.
Shimizu, Y., Kumagai, T., Sugisawa, H., Shinoda, T., Shishido, K. and Magami, K., 2021. Factors promoting disaster preparedness in dialysis facilities: qualitative analyses of advanced preparedness.
Tomio J, Sato H. Emergency and disaster preparedness for chronically ill patients: a review of recommendations. Open Access Emergency Medicine. 2014 Dec 12:69-79.
Takeda T, Yamakawa T, Shin J, Sugisaki H, Yoshida T, Yamazaki C, Uchino J, Morigami T, Kawasaki T. Information-sharing system for disaster recovery of dialysis therapy in Japan. Biomedical Instrumentation & Technology. 2009 Jan 1;43(1):70-2.
Ikegaya N, Seki G, Ohta N. How should disaster base hospitals prepare for dialysis therapy after earthquakes? Introduction of double water piping circuits provided by well water system. BioMed Research International. 2016;2016(1):9647156.
Sahutoglu T, Kazancioglu R. Enhancing disaster preparedness in peritoneal dialysis care. Kidney international reports. 2024 Jul 1;9(7):1945-6.