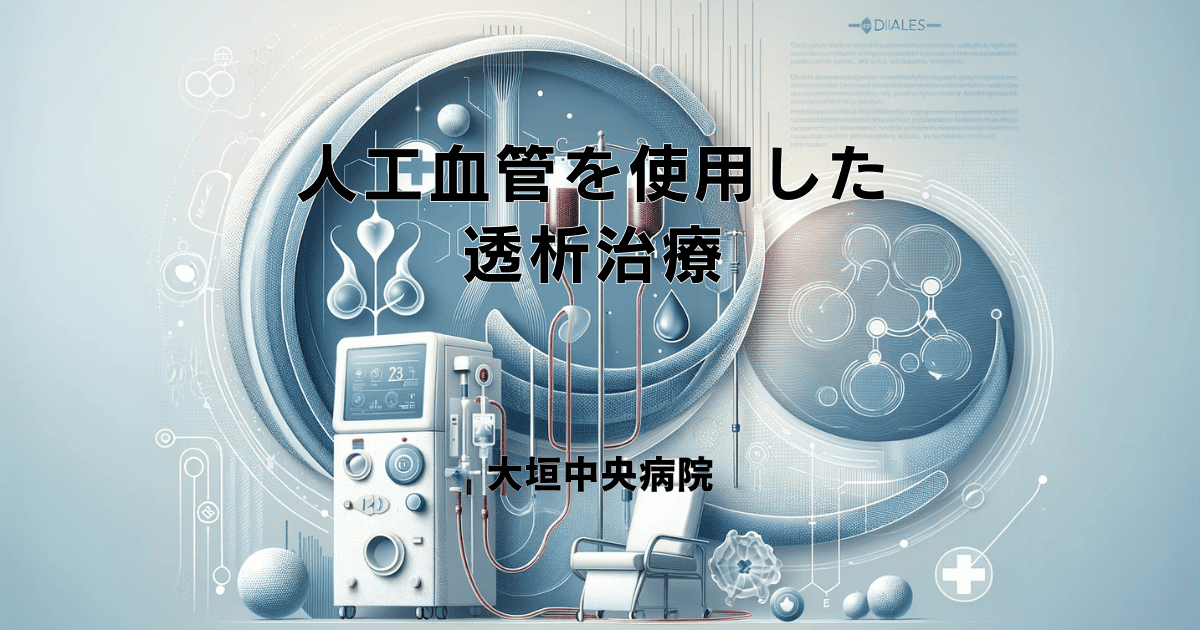透析治療の血管アクセスとして人工血管を利用する方法は、内シャントだけでは十分な血流を確保できない場合などに有効だと考えられています。
血管の状態やライフスタイルを踏まえて医師が治療方針を提案し、患者と相談しながら決定する過程は大切です。本記事では人工血管を使った透析治療の概要や手術前後の注意点、日常的な管理の方法などを解説します。
合併症のリスクを下げるポイントや長期にわたる維持のための取り組みを知ることで、人工血管を使ったシャントを安心して管理できるようになると考えています。
透析治療における血管アクセスの重要性
透析では血液を体外に導き、老廃物や余分な水分を除去してから体内に戻す必要があります。十分な血液量を安定して取り出すために血管アクセスが欠かせません。
通常は自前の血管をつないだ内シャントが候補になりますが、血管の太さや硬さなどに問題がある場合、人工血管内シャントや人工血管シャントが選ばれるケースもあります。
血管アクセスの基本
血管アクセスは透析治療を円滑に行うための出入口です。自前の血管を直接使う内シャントと、人工血管を使用するシャントがあり、それぞれに特徴があります。
内シャントは患者自身の血管をつなぐことで自然な血流を得やすい反面、血管が脆化していたり狭窄していると適用が難しいです。人工血管内シャントや人工血管シャントは合う血管が確保できない場合に考慮します。
血管アクセスが機能しなくなると透析自体が難しくなるため、医師は定期的に血管状態を調べ、適切なタイミングで新たなアクセスを構築したり修正を検討したりします。血管アクセスは透析治療の核となる存在です。
人工血管シャントの特徴
人工血管シャントは、既存の血管と人工血管をつなぎ、一定の太さと血流量を確保しやすい特徴があります。血管の状態が悪く内シャントが難しい人でも、人工素材を用いることで安定した透析が期待できます。
人工血管素材にはさまざまな種類があり、血管と素材の相性や術後の管理方法などを医師が検討します。
人工血管シャントは通常、上肢や下肢など比較的太い血管がある部位に作ることが多いです。ただし手術には全身状態の把握や、感染リスク低減など細心の注意が求められます。
術後は血管の狭窄や血栓形成に気を配りながら、長期的なメンテナンスを続けることが重要です。
人工血管内シャントが必要になる理由
内シャントが難しい理由には、血管が極端に細い、硬化が進んでいる、過去に何度もシャント手術を行い使用できる血管が乏しくなったなどの状況が挙げられます。
こうした場合、透析で十分な血流を得るために人工血管内シャントの造設を検討します。
必要性の判断は血管造影検査や超音波検査など複数の手法を用い、医師が総合的に判断します。
すでに長く透析を受けている方にとっては、人工血管内シャントへの移行がその後の人生の質を左右する大切な選択となるため、医療チームとの話し合いが欠かせません。
血管アクセスの種類一覧
| 種類 | 特徴 | 適用が難しい例 |
|---|---|---|
| 内シャント | 自身の血管を直接吻合する | 血管が細い・硬化が進んでいる |
| 人工血管内シャント | 人工素材を血管内に挿入する | 血管径が不均一・高度狭窄 |
| 人工血管シャント | 人工素材を血管と血管の間に挿入 | 感染リスクが高い状態 |
| 中心静脈カテーテル | 大きな静脈にカテーテルを留置 | 緊急透析や一時的使用 |
人工血管を使用した透析治療とは
人工血管を使った透析治療は、血管の状態が悪い方や複数回の手術で内シャントが作りにくくなった方に検討されます。人工素材による血管アクセスは一定の血管径を確保でき、血流量の安定が見込めます。
一方で感染などのリスクも存在するため、日々の管理が大切です。
概要と仕組み
人工血管を手術で移植し、動脈と静脈を接続して血液を流れやすくする方法です。透析時は人工血管の表面近くに穿刺し、体外循環を行います。
人工血管内シャントや人工血管シャントはいずれも血流量を確保しやすい反面、自身の血管を利用する内シャントよりも感染や血栓が起きやすい傾向があります。
仕組みとしては、動脈圧で血液を人工血管へ流し、そのまま静脈へ戻すルートを外科的に作る形です。導入前には患者の全身状態を把握し、血管の走行や皮膚状態などを細かく調べます。
選択のポイント
人工血管を利用したシャントの適応を判断する際は、以下の点を考慮します。
- 自前の血管で内シャントが作れないかどうか
- 身体全体の血管状態や他の基礎疾患
- 日常生活の動作や職業上の負担
- 過去のシャント手術回数や失敗例
患者の血管が太く柔軟性が残っている場合は、内シャントのほうが合併症のリスクを抑えやすいです。しかし血管が細く何度もシャント造設を試みた結果、利用可能な血管が乏しくなっている場合は人工血管シャントが候補になります。
メリットとデメリット
人工血管による透析は、以下のようなメリットとデメリットがあります。
メリット一覧
| メリット | 解説 |
|---|---|
| 安定した血流量の確保 | 人工素材の管径が一定なので必要な血流を得やすい |
| 幅広い適応 | 内シャントが難しい患者でも透析が実施できる |
| 血管の早期使用が可能 | 手術後の待機期間が比較的短めで透析を始めやすい |
デメリット一覧
| デメリット | 解説 |
|---|---|
| 感染リスクの増加 | 人工素材が細菌の温床になる場合があり、管理が重要 |
| 血栓や閉塞の可能性 | 表面が人工素材ゆえ血小板が付着しやすく閉塞の恐れがある |
| 長期使用で再手術が必要 | 人工血管が劣化した場合に交換などの追加処置が必要 |
シャント造設前に知っておきたいこと
人工血管を使ったシャントを造設する前には、体調の把握や他の選択肢の検討、実際に手術を受けたあとの生活イメージなどを総合的に検討します。
造設を急ぐほどリスクが増えるわけではありませんが、透析が必要なタイミングを逃さないよう計画的に進めることが重要です。
身体検査や血管評価
手術前には血液検査や画像検査を行い、心臓機能や血管の太さ・血流状態を確かめます。血管造影検査、超音波ドップラー検査などで血管の走行や狭窄部位の有無を調べ、術式の選定に役立てます。
患者自身が見落としている体調不良や合併症の有無も手術の安全性に影響するため、十分な検査が求められます。
術前に確認する主な項目
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 血液検査 | 貧血や感染症の有無、凝固能の評価 |
| 超音波検査 | 血管の走行や太さ、動脈壁・静脈壁の状態 |
| 心エコー | 心臓の機能評価、シャント造設による負荷確認 |
| 血管造影 | 血流量や分岐、狭窄・閉塞部位の詳細把握 |
医師との相談の進め方
患者が自分の希望をきちんと伝え、医療チームの見解を正しく理解することで、納得のいく治療方針を決められます。
特に人工血管内シャントや人工血管シャントの適応は、医師が血管状態や合併症リスクなどを総合的に考えて提案する形になりますが、患者にとって大切な情報は次のようなポイントになります。
- 手術の具体的な流れと合併症リスク
- 透析を開始した後の通院回数や注意点
- 日常生活への影響(運動や仕事、趣味など)
医師からは難しい医学用語が出ることもありますが、疑問や不安は遠慮なく尋ねることが大切です。看護師や臨床工学技士もシャント管理に精通しているため、チーム全体でサポートを依頼すると、より充実した対応を期待できます。
期待できる効果
人工血管を利用するシャントによって、透析時の血流量をしっかり確保しやすくなります。動脈圧と静脈圧の差を人工素材が支えるため、血管状態が悪くても血行動態を安定させる効果が見込めます。
透析の効率が高まりやすい利点もあり、体内の老廃物や余分な水分をスムーズに除去できるチャンスが増えます。
その結果、生活の質が向上する可能性があります。倦怠感の軽減や血圧コントロールの改善などが挙げられ、透析後の疲労が少し軽く感じられる患者もいます。ただし個人差があるため、期待しすぎないことも大切です。
人工血管シャント造設の流れ
人工血管シャントの手術は外科的処置となるため、全身状態の安定と局所の無菌管理が欠かせません。造設する血管の場所や手術の規模によって入院期間や術後の過ごし方が異なります。
事前に看護師から必要な手続きや物品の準備などの説明を受け、スムーズに手術を迎えるように備えましょう。
麻酔や術中の対応
人工血管シャントの手術では局所麻酔や全身麻酔を使う場合があります。局所麻酔であれば意識がある状態で腕や脚の感覚だけを麻痺させる方法が多いです。全身麻酔を選ぶ場合は、呼吸や循環動態を安定させるための管理が必要です。
麻酔科医や手術チームが連携して対応します。
術中は血管の位置を正確に把握し、適切な長さに人工血管をカットして動脈と静脈をバイパスする形で接合します。
血流がスムーズに流れるかどうか、その場で確認しながら吻合するため、手術にかかる時間は個々の血管状態によって異なります。
手術後の過ごし方
手術直後はシャントが正常に機能しているかどうか医師や看護師が頻繁に確認します。手術部位の感染徴候や出血がないかどうかも重要です。患部には圧迫固定用の包帯が巻かれる場合があり、数日間は安静が望ましいことが多いです。
手術後は透析の準備を進めながら、血液の凝固能や創部の回復状況を観察します。
シャント音(ブライト・スリルとも呼ばれる脈動の音や振動)のチェックや脈の触知具合などを自分でも確認し、異常があればすぐに医療スタッフに伝える習慣が必要です。
退院前の確認事項
退院前には手術創の状態やシャントの血流を再度チェックし、問題がなければ退院となります。ただし、自宅に帰った後も日々のケアが求められます。次の点を退院前に十分確認してください。
- シャント音を確認する方法
- 腕や脚の腫れ、熱感、痛みなどの観察ポイント
- 消毒のタイミングや方法
- 通院日のスケジュールと相談先(診療科、緊急連絡先)
退院後は定期的に病院でフォローアップを受ける必要があります。シャント機能の低下は徐々に進行する場合もあるため、初期段階での発見が重要です。
退院前に配布される書類例
| 書類名 | 主な記載内容 |
|---|---|
| 透析治療計画書 | 透析のスケジュールや具体的な治療目標 |
| 術後の過ごし方の説明書 | 創部のケア方法や日常生活で気をつける点 |
| 緊急連絡先一覧 | 休日・夜間対応の電話番号や緊急受診のめやす |
| 処方薬の説明書 | 抗生物質や止血剤などの使用方法と副作用の注意点 |
シャントの管理と日常生活
人工血管シャントを長く使うには、日常的なケアと観察が欠かせません。たとえ人工素材であっても血管と同様にトラブルが起きる場合があります。普段から異常の早期発見と軽減を意識して生活することで、透析の効率を保ちやすくなります。
シャント部位の観察とケア
シャント部位の皮膚や触感を毎日確認して、以下のような異常が起きていないかチェックします。
- 腫れや発赤
- 触ったときの熱感
- シャント音が弱くなった、あるいは消失している
- しびれや痛みが増強している
手指で触れて振動を感じるかどうかを確かめると、血流の状態を大まかに把握できます。皮膚の清潔を保つことも大切です。入浴時やシャワー時に石鹸で優しく洗い流し、傷がある場合は保護して刺激を避けます。
シャント部位日常点検のまとめ
| 点検項目 | 観察のポイント | 対応策 |
|---|---|---|
| 皮膚の状態 | 腫れ、発赤、ただれ、傷などの有無 | 速やかに清潔を保ち、異常が続く場合は受診 |
| シャント音 | 振動や音が弱い、消失しているかどうか | 病院に連絡し、受診や検査を早めに行う |
| しびれ・痛み | シャント周辺に違和感や痛みがあるか | 痛みが強い場合は主治医と相談し、原因を探る |
運動や入浴時の注意点
過度な重さの物を持ち上げたり、激しい運動をしたりするとシャント部位に過度な圧がかかり、血栓や断裂のリスクが高まる恐れがあります。医師や理学療法士などと相談しながら、身体を動かす方法を工夫すると安心です。
入浴時はシャント部位に直接強い水流を当てたり、長時間の入浴でふやける状態を続けたりしないほうがいい場合があります。透析後の止血をした部分は特に敏感なので、むやみにこすらず、清潔を保ちつつやさしく洗うことを心がけます。
感染予防の方法
シャントに細菌が侵入すると感染症につながる可能性があります。人工血管シャントや人工血管内シャントは素材に細菌が付着しやすい特性があり、周囲の組織に炎症が広がると重篤な合併症につながりかねません。
感染予防には次のような対策が重要です。
- 手洗い・手指消毒をこまめに行う
- シャント部位を傷つけるような行為を避ける
- 医療機関で処方された軟膏や抗菌剤を適切に使用する
皮膚が乾燥していると小さな傷から菌が入りやすくなるため、保湿や保護クリームの使用を検討するとよいでしょう。日頃から周囲の人と触れ合う場面でも、衛生意識を高く持つと感染リスクを下げやすくなります。
シャントの合併症と対応策
人工血管シャントを利用していると、血管自体が劣化したり体調の変化により思わぬトラブルが起きたりします。合併症を早期に発見し、医療者との連携をスムーズに行うことが、シャントの寿命を延ばすポイントです。
血栓や閉塞
シャント内で血栓が形成されると血流が悪化し、透析の効率が下がります。完全に血流が途絶えれば緊急処置が必要です。血栓は高凝固状態や血管内皮の損傷などが引き金になります。
抗凝固薬の処方や適度な運動で血流を維持して、血栓を防ぐ方法を医師と相談します。
血管内の閉塞が起きた場合、原因となる血栓や狭窄部位に対して再手術やバルーン拡張などの処置を行うことがあります。早期発見には、日頃のシャント音確認や腕や脚の腫れの把握が欠かせません。
血栓予防を考える上での留意点
- 水分補給を適度に行い、血液の粘度を上げすぎない
- 定期的にストレッチや軽い運動をして血流を促す
- 薬を服用している場合は医師の指示を守り、自己判断で中断しない
感染症の兆候
人工血管シャントは皮膚を貫通しない形で体内に埋め込むため、直接外部と交通しないように見えます。しかし、穿刺のたびに針を刺す行為や、皮膚周辺のトラブルなどをきっかけに感染が起こる場合があります。
発熱や患部の腫脹、皮膚の色調変化などが見られたら、すぐに医師の診察を受けるほうがよいでしょう。
感染が進むと人工血管が周囲組織から浮き上がり、皮膚から露出しかねません。その状態は重篤な合併症に発展する恐れがあります。自己判断で抗生物質を変更したり、未処方の薬を使用したりするのは避け、必ず医療スタッフに相談してください。
出血や痛みのケア
人工血管シャント周辺は穿刺部位でもあるため、出血が止まりにくい時期や痛みが生じることがあります。透析後に針を抜いた部分から滲出液が続く場合は、適切な圧迫と止血用パッドの活用が必要です。
無理に患部を触ったりこすったりするとかえって傷を悪化させる可能性があります。
強い痛みが持続する場合は、穿刺時の針の太さや角度、皮膚の状態に原因があるかもしれません。シャントの位置が深いときは特に注意が必要です。痛みを我慢するより、透析スタッフに相談して原因や対策を検討する姿勢が大事です。
定期検査とメンテナンス
人工血管シャントを適切に維持するために、定期検査と必要なメンテナンスが欠かせません。シャント機能の低下は少しずつ進行する場合があるため、こまめな検査がトラブル防止につながります。
血流量測定
透析を行う際に、実際にどの程度の血液量を体外へ導入できているかを測定する方法があります。シャント音や視診・触診だけではわからない軽度の狭窄や血栓が見つかることもあるため、定期的な血流量測定は重要です。
医療機関によっては超音波ドップラーで流速をチェックするなど、非侵襲的な手段を活用します。異常が確認されたら、状況に応じて透析治療前後のケアや抗凝固薬の調整などを実施します。
血流量の急激な変化は大きな異常のサインかもしれないので、見逃さないようにします。
シャント音の確認
日常生活でもシャント音や振動を確認することが奨励されていますが、医療機関で専門的に聴診すると、わずかな変化も捉えやすいです。
医師や看護師がシャントスコープなどを使って内部の流れを評価し、必要に応じて画像検査へ進みます。
シャント不良の兆候
| 兆候 | 考えられる原因 |
|---|---|
| シャント音の急な弱まり | 血栓や狭窄 |
| 触ったときの振動が弱くなる | 血管壁の硬化や閉塞 |
| 透析中の圧力上昇 | 血液の流れが阻害されている可能性 |
| 透析効率の低下(KT/Vの低下など) | 血流量不足による老廃物除去不足 |
トラブル予防に向けた連携
透析室や外来診療での検査だけでなく、血管外科や内科とも連携して定期的に状態を確認すると、トラブルを早期に発見しやすくなります。合併症が発生したときも、他科の医師や看護師と連携をとることで、迅速な対応が期待できます。
医療スタッフとのコミュニケーションを積極的に行い、些細な変化でも伝える姿勢がシャント維持には有益です。患者自身が異常や不調を感じたときにすぐ相談できる環境づくりが、長期的にみて透析生活を支える基盤となります。
チーム連携を円滑に進めるためのポイント
- 診察や透析後に疑問点をメモしておき、医師や看護師に尋ねる
- 血管外科、内科、透析室スタッフとの情報共有を積極的に行う
- 緊急時にすぐ連絡できる窓口を把握しておく
Q&A
人工血管シャントや人工血管内シャントを利用した透析に関しては、多くの疑問や不安があると思われます。いくつか代表的な質問を取り上げ、回答を示します。
- シャント造設の痛みはどのくらいですか?
-
手術に伴う痛みは局所麻酔や全身麻酔で和らげます。術後に多少の鈍痛や違和感を感じることがありますが、鎮痛薬で対応できます。痛みが強い場合は医師へ相談するとよいでしょう。
- シャントは何年くらい使えますか?
-
個人差がありますが、人工血管シャントや人工血管内シャントは複数年にわたって利用できるケースが多いです。血管の狭窄や劣化が進んだときは再手術を検討する場合もあります。定期的な検査とケアが長期使用の鍵です。
- 透析日の他にどれくらい通院が必要ですか?
-
基本的な透析スケジュールに加え、シャントの状態を確認するための定期検診が年に数回行われます。異常が見られる場合は臨時での受診が増える可能性があります。
透析中の不安への対処
透析は週に数回受ける治療で、時間もかかるため精神的な負担を感じる方が多いです。リラックスできる音楽を聴いたり、医療スタッフと会話したり、家族や友人と連絡を取り合ったりすることで不安を和らげる方もいます。
透析中に眠気やだるさがひどいときは、事前に水分や栄養状態を見直したり、血圧管理を調整したりする必要があります。普段から体調の変化を記録し、医師に相談するなど自分の状態を把握することが大切です。
長期維持のためのヒント
人工血管シャントや人工血管内シャントを長く維持するためには、以下のような点を心がけます。
- 日々のシャント音チェックと皮膚観察
- 無理のない運動と適度な体重管理
- 不安や疑問をためこまず医療チームに相談
- 透析前後の体調や血圧の管理に留意
シャントは繊細な血管アクセスです。患者自身が少しの変化も見逃さないよう努めることが、透析の効率を落とさずに良い状態を保つ近道になるでしょう。
医師、看護師、臨床工学技士など、それぞれの専門知識を活用しながら総合的に管理する姿勢が大切です。
以上
参考文献
SCHILD, A. Frederick. Maintaining vascular access: the management of hemodialysis arteriovenous grafts. The Journal of Vascular Access, 2010, 11.2: 92-99.
LOK, Charmaine E., et al. Arteriovenous access for hemodialysis: a review. Jama, 2024, 331.15: 1307-1317.
PADBERG JR, Frank T.; CALLIGARO, Keith D.; SIDAWY, Anton N. Complications of arteriovenous hemodialysis access: recognition and management. Journal of vascular surgery, 2008, 48.5: S55-S80.
ALLON, Michael. Vascular access for hemodialysis patients: new data should guide decision making. Clinical Journal of the American Society of Nephrology, 2019, 14.6: 954-961.
RYAN, Sean V., et al. Management of infected prosthetic dialysis arteriovenous grafts. Journal of vascular surgery, 2004, 39.1: 73-78.
THOMAS, Matthew, et al. Maintenance of hemodialysis vascular access and prevention of access dysfunction: a review. Annals of vascular surgery, 2017, 43: 318-327.
DHINGRA, Rajnish K., et al. Type of vascular access and mortality in US hemodialysis patients. Kidney international, 2001, 60.4: 1443-1451.
SIDAWY, Anton N., et al. The Society for Vascular Surgery: clinical practice guidelines for the surgical placement and maintenance of arteriovenous hemodialysis access. Journal of vascular surgery, 2008, 48.5: S2-S25.
KONNER, Klaus, et al. Tailoring the initial vascular access for dialysis patients. Kidney international, 2002, 62.1: 329-338.