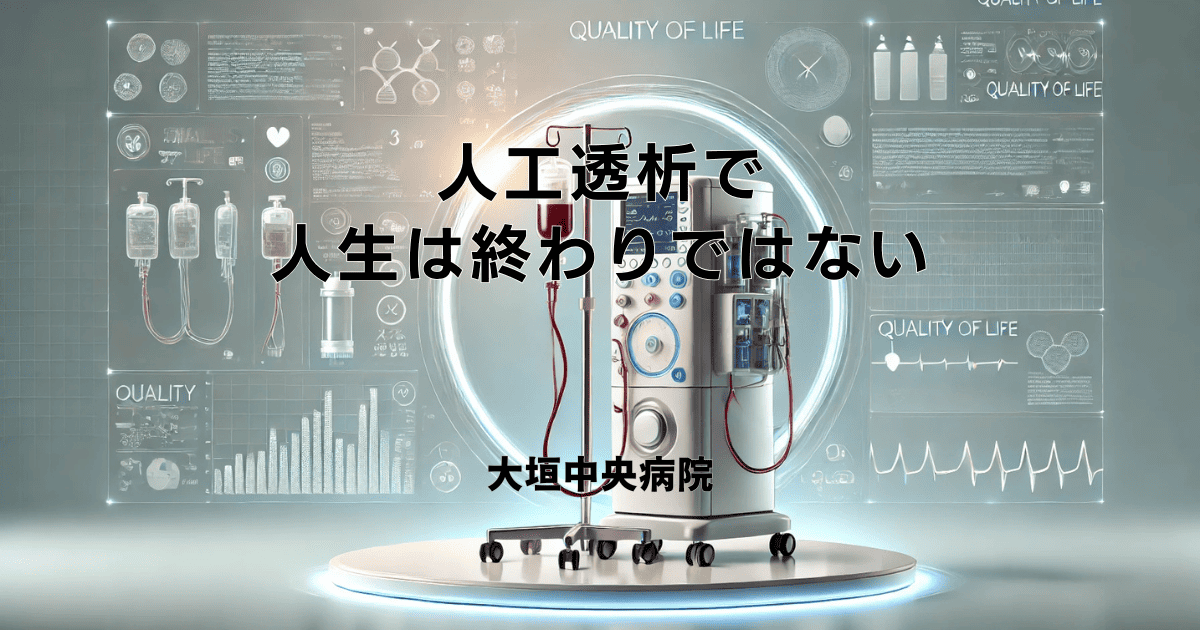人工透析を受けると聞くと、人生を大きく制限されてしまうのではないかと不安になる方が少なくありません。腎臓の機能低下によって治療を検討する段階になると、通院の負担や食事制限など、生活の質に関する悩みが増えることが多いです。
しかし、人工透析人生終わりと捉える必要はなく、適切な治療とサポートを受けながら生活を続ける方がたくさんいます。体調の安定や社会生活との両立をめざして、一歩ずつできることから始めていきましょう。
人工透析の基本を知る
腎臓の機能低下が進行すると、体内に老廃物や余分な水分が蓄積しやすくなります。体調不良を引き起こす要因となるため、人工透析によって血液をろ過する治療を行うのが一般的です。
人工透析には大きく分けて血液透析と腹膜透析があり、それぞれに特徴があります。まずは人工透析の大まかな仕組みや目的を理解し、治療を身近に感じることが大切です。
人工透析の定義と腎臓の働き
腎臓は1日約180Lの血液をろ過し、不要な物質や余分な水分を尿として排出します。塩分やミネラルなど体内のバランスを整える点でも重要です。
腎機能が大幅に低下し、老廃物の排出が困難になる段階になると、人工透析で体外に老廃物を取り除く必要が出てきます。人工透析は腎臓の働きを代替し、血液をきれいに保つことで健康状態を維持する手段です。
人工透析の背景と歴史
血液透析は1度に大量の血液をろ過できる点で注目を集め、1960年代以降に急速に広まりました。機械の性能が向上し、医療スタッフの知識も深まるとともに、透析患者の治療成績やQOL(QualityOfLife)も改善してきています。
腹膜透析は自宅で行いやすい方法として採用が進み、通院の時間や負担を減らす選択肢として根付いてきました。
人工透析が果たす役割
人工透析の主な役割は、体内に蓄積した老廃物や余分な水分を体外に排出して血液を浄化することです。腎臓自体の機能を回復させるものではありませんが、体調の安定と合併症の予防をめざします。
治療に伴う生活調整は必要になりますが、長期にわたって日常生活を維持する要となる治療法です。
人工透析に関する基礎的なポイント
- 血液浄化によって体内環境を整える
- 腎臓の代わりに不要物を排出する
- 通院回数や透析時間を調整しながら生活を続ける
- 食事や水分制限も必要になる
腎機能低下がもたらす影響
腎臓の機能低下が進むと、血圧上昇や体内の老廃物蓄積など多彩な症状が生じます。初期段階では自覚症状が少ない場合もありますが、ある程度進行すると日常生活に大きな影響が出ることがあります。
治療を受けるタイミングを見極めるためにも、腎機能低下が及ぼす影響を把握することが必要です。
腎臓の機能低下による症状
腎機能が低下すると、尿量の減少や体液バランスの崩れによるむくみ、倦怠感、吐き気などが現れやすくなります。
また、タンパク質由来の老廃物や電解質が排出されにくくなるため、高カリウム血症や高リン血症による心臓や骨のトラブルリスクが高まります。血圧調節機能も低下し、高血圧が慢性化するケースも少なくありません。
日常生活への影響
体調不良が続くと、仕事や家事の継続が難しくなったり、外出が困難になる場合があります。疲労感やめまいが重なると動作が緩慢になり、自宅での生活すら支障をきたす恐れが出てきます。
そうした状況を軽減するために、人工透析を導入することで症状の緩和を期待できる場面があるのです。
合併症への注意
腎不全が進行すると、心血管系への負担が増大するほか、透析治療を開始してからも骨や関節、貧血などの問題に注意する必要があります。これらの合併症は治療計画と日常生活の工夫によってリスクを下げることが可能です。
医療スタッフと密に相談し、こまめに検査を受けることが大切です。
腎機能低下による代表的な合併症
| 合併症名 | 主な症状 | 注意点 |
|---|---|---|
| 高血圧 | めまい、動悸 | 血圧管理が重要になる |
| 高カリウム血症 | 筋力低下、不整脈 | 食事でカリウムを調整する |
| 骨・関節障害 | 骨がもろくなる、関節痛 | カルシウムとリンのバランス |
| 貧血 | 疲労感、動悸、息切れ | エリスロポエチン投与の検討 |
どのように生活の質を保つか
人工透析人生を終わりと感じる必要はなく、適切な生活調整によって心身の負担を軽減し、より元気に暮らすことをめざすことができます。食事の見直しや軽度な運動、医療スタッフとの連携など、生活全般にわたる取り組みが大切です。
食事管理と栄養バランス
食事管理は透析患者にとって非常に重要なテーマです。塩分やカリウム、リンなどのミネラルを過度に摂りすぎないように注意しながら、必要な栄養素をバランスよく摂取する必要があります。
また、過剰な水分摂取は体に余分な負担をかけるため、1日の水分量を一定に保つ工夫が求められます。
栄養管理上のチェック項目
| 項目 | 推奨される管理法 | 具体例 |
|---|---|---|
| 塩分 | 1日6g未満を目安に抑える | 減塩調味料を活用する |
| 水分 | 適切な尿量や透析スケジュールに合わせる | スープや果物の摂取量を考慮する |
| カリウム | 野菜や果物の下茹でなど調理法を工夫 | トマト、バナナの過剰摂取を控える |
| リン | 加工食品や乳製品の摂取量に注意 | 加工肉やチーズの量を調整する |
| タンパク質 | 良質なタンパク質を適量摂取 | 魚や大豆製品を上手く取り入れる |
運動やリハビリテーション
過度の運動は負担になりますが、適度なリハビリや散歩などは血行を良くし、筋力低下を防ぐ上で役に立ちます。体調を観察しながら無理のない範囲で継続すると、心肺機能の維持やメンタル面の安定にもつながります。
医療スタッフとの連携と相談
透析を円滑に進めるには、医師や看護師、管理栄養士、臨床工学技士など多職種のサポートが重要です。疑問や不安をそのままにせず、感じたタイミングですぐに相談する習慣を持つことが、生活の質維持につながります。
社会活動への取り組み
透析日のスケジュール調整や、疲労感による制限はあるかもしれませんが、可能な範囲で趣味や交流の機会を設けることで、心の健康を保ちやすくなります。仕事を継続する場合は、職場の理解を得るための情報共有も大切です。
生活の質を高めるためのヒント
- 毎日の体重や血圧を記録して変化を把握する
- 透析後の疲労に合わせて休養を十分に取る
- 自分に合った息抜き方法を見つける
- 医療者とコミュニケーションをこまめに取る
通院透析と在宅透析の違い
人工透析には大きく分けて通院で行う血液透析と、自宅などで行う腹膜透析が挙げられます。ライフスタイルや体調、家庭環境に合わせた治療法を選ぶことが、より良いQOLの維持につながります。
通院でのメリットもあれば、在宅での自由度の高さも魅力です。
通院透析のメリットとデメリット
通院透析(血液透析)は週3回ほど病院や透析施設へ行き、1回あたり4時間程度の治療を受けることが一般的です。
専門スタッフに囲まれて治療を進める安心感がある一方、通院時間や移動にかかる負担、決まったスケジュールに合わせる必要が生じます。
通院透析の特徴
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 専門スタッフのサポートが手厚い | 通院の時間的・体力的負担 |
| 機器のメンテナンスが不要 | 治療スケジュールの融通が利きにくい |
| 血液データを綿密にチェックできる | 待ち時間が発生する可能性がある |
在宅透析のメリットとデメリット
在宅透析には主に腹膜透析や自宅血液透析があります。自宅で行う場合、通院回数が減り、治療の時間帯をある程度自由に組み立てられる利点があります。
ただし、機械の管理や衛生面の徹底が必要であり、トラブルが起きた際には医療機関との連絡体制が欠かせません。
在宅透析の特徴
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 時間的な柔軟性がある | 衛生管理や機器管理の責任が増える |
| 通院負担が少ない | 自宅のスペースと設備が必要になる |
| 体調に合わせて透析が調整しやすい | 問題発生時の対応を素早く行う必要がある |
自分に合った透析方法を選ぶ
治療方法の決定は、主治医や看護師、家族の意見を交えて慎重に行うことをおすすめします。
どちらが優れているかではなく、自分の生活全般に対してどのような影響があるかを考慮し、必要に応じて変更や見直しも視野に入れると、治療負担を軽減しやすくなります。
心のケアとサポート
人工透析人生終わりと感じてしまう背景には、治療への漠然とした不安や「自由が奪われる」という思い込みがあるかもしれません。実際には、十分に外出や仕事を続けている方も多くいます。
定期的な治療にかかる時間や制限はあるものの、気持ちを安定させるための心のケアも大切です。
不安や落ち込みと向き合う
人工透析を始めた当初は、生活の変化に戸惑いやすく、不安や落ち込みを感じるのは自然なことです。自分の気持ちを誰かに伝えたり、専門のカウンセリングを利用したりすることで、過度なストレスを軽減できます。
精神面のセルフケアの例
| 対処方法 | 具体的な取り組み |
|---|---|
| 気分転換 | 軽い運動や趣味活動、深呼吸でリラックスする |
| 情報収集 | 医療者の話を聞く、正確な情報に触れる |
| 自己肯定感を高める | 小さな成功体験を積み重ねて自信をつける |
家族や周囲の支援を得る
家族に病気や治療について理解してもらい、一緒に食事管理をしたり日常の役割分担を見直したりすることで負担が軽減しやすくなります。家族からの声かけだけでなく、友人や職場仲間との情報共有も心強い味方になります。
透析患者同士の情報交換
同じ立場の人と話す機会を得ると、日々の困りごとや工夫を共有できて視野が広がります。医療機関が主催する教室や患者会、オンラインコミュニティなど、さまざまな方法でつながりを持つ人が増えています。
人工透析患者と仕事・学業の両立
透析を受けながら仕事を続けたり学業に励む方は多くいます。周囲の理解や協力を得つつ、スケジュールを調整しながら自分のペースで活動することがポイントです。
就労中の方に必要な配慮
通院透析を行う場合、週3回程度の治療時間を確保する必要があります。勤務時間の変更や、リモートワークなどの柔軟な働き方を企業に交渉するケースもあります。
体調がすぐれない日は早退や休暇を取得できる環境があると望ましいです。
職場との調整が必要な項目
- 透析日のスケジュールを伝える
- 定期健診や診察日に休暇が取れるようにする
- 業務量や業務時間を調整する
- 人事担当や上司に体調の変化を相談する
学生生活への対応
学校に通いながら透析を受ける場合は、授業や実習のスケジュールと治療日をうまく組み合わせる必要があります。
欠席や遅刻が増える可能性があるため、担任や教授、クラスメイトへの情報共有を丁寧に行い、必要に応じてフォローを受けると安心です。
キャリア継続のための工夫
人工透析を開始してもキャリアを諦める必要はありません。長い目で見て、自分の体力と仕事のバランスを探りながら、必要に応じて転職や職種変更を考える方もいます。
病院のソーシャルワーカーに相談し、福祉制度や障害者雇用などの制度を活用することで、より安定した環境を得やすくなります。
ワークライフバランスを考える上での視点
| 視点 | 内容 |
|---|---|
| 時間管理 | 透析時間と休養時間を踏まえたスケジュール |
| 体力面の評価 | 疲労度を把握しながら業務量を調整 |
| 周囲の理解 | 職場や学校の協力体制を事前に整える |
| 将来の選択肢 | 転職や進学など多角的に検討してみる |
病院で行う定期的な検査とフォローアップ
人工透析を行う場合、腎臓に関連した数値だけでなく、全身状態を定期的に確認することが欠かせません。血液検査や画像検査で異変を早期に見つけ、治療計画を修正する機会を設けることで、合併症予防に努めることができます。
血液検査と身体計測
血液検査では、血清クレアチニンや尿素窒素だけでなく、電解質やヘモグロビンなど多方面にわたる数値を評価します。また、体重や血圧の測定、心電図やレントゲン撮影などを定期的に行い、透析効果や身体状態の経時的な変化を把握します。
定期検査で注目する主な項目
| 検査項目 | 意味 |
|---|---|
| 血清クレアチニン | 腎機能の指標 |
| 尿素窒素 | 老廃物の排出状況を確認 |
| カリウム | 心臓や筋肉に影響を及ぼす電解質 |
| リン | 骨や血管に影響し合併症リスクを高める |
| ヘモグロビン | 貧血の有無を判断 |
治療計画の見直し
血液検査や身体計測の結果を踏まえ、透析時間や頻度、使用する透析液の成分、食事管理の指導内容などを細かく調整します。これにより、常に状態に合った治療を受けられるようになります。
合併症予防のための定期確認
心不全や脳卒中をはじめとする大きなトラブルを防ぐためにも、心臓や脳、血管の状態をチェックする機会を設けることが重要です。腎臓以外の科とも連携を取り、複数の角度から健康管理を行うと安心です。
透析以外で受けることが多い検査の例
| 検査種類 | 対象疾患や目的 | 実施頻度の目安 |
|---|---|---|
| 心エコー | 心機能評価、心不全や弁膜症の確認 | 年1回程度 |
| 頸動脈エコー | 動脈硬化の進行度を確認 | 年1回または2年に1回 |
| 骨密度検査 | 骨粗鬆症予防、リンやカルシウムバランス | 年1回程度 |
Q&A
人工透析を始める前後や、透析を継続している中で、多くの方が抱く質問をまとめました。
いずれも一般的な傾向を示すものであり、個々の病状やライフスタイルにより最適な対応は変わります。治療方針や具体的な相談は主治医や医療スタッフに尋ねるのが大切です。
- 人工透析を始めたらすぐに仕事を辞めるべき?
-
透析日と勤務日の調整や、通院先の立地条件を考慮する必要はありますが、すぐに仕事を辞める必要はありません。
実際、週3回の透析を続けながらフルタイムで働く方もいます。主治医や職場と相談し、働き方を柔軟に見直してみてください。
- 通院が大変なのですが在宅透析へ切り替えられますか?
-
病状や家庭環境によっては切り替えを検討することも可能です。自宅環境の整備や機材の取り扱い、衛生面の管理など事前にクリアする条件があります。
メリット・デメリットを把握した上で、医療スタッフと相談するとスムーズです。
- 人工透析中の食事はどれくらい厳しく制限されますか?
-
カリウムやリン、塩分、水分制限など多岐にわたりますが、管理栄養士の助言に沿ってコツを覚えると少しずつ慣れていけます。完全に禁止する食品ばかりではなく、量や調理法を工夫することで楽しみを保つことも可能です。
- 人工透析人生終わりというイメージが消えません
-
人工透析を受けている人の中には、趣味を楽しみ、旅行に出かけ、仕事や家庭を両立させている方がたくさんいます。医療の進歩や社会の理解も進みつつあり、決して人生の可能性が閉ざされるわけではありません。
心配が大きい場合は、カウンセリングや患者会などを活用してみると安心感が得られます。
以上
透析センター(人工透析) | 大垣中央病院(医療法人社団豊正会 )
参考文献
D’ONOFRIO, Giuseppina, et al. Quality of life, clinical outcome, personality and coping in chronic hemodialysis patients. Renal failure, 2017, 39.1: 45-53.
PRETTO, Carolina Renz, et al. Quality of life of chronic kidney patients on hemodialysis and related factors. Revista latino-americana de enfermagem, 2020, 28: e3327.
MARTINS DO VALLE, Felipe, et al. Effects of intradialytic resistance training on physical activity in daily life, muscle strength, physical capacity and quality of life in hemodialysis patients: a randomized clinical trial. Disability and rehabilitation, 2020, 42.25: 3638-3644.
GARCÍA-MARTÍNEZ, Pedro, et al. Perceived stress in relation to quality of life and resilience in patients with advanced chronic kidney disease undergoing hemodialysis. International journal of environmental research and public health, 2021, 18.2: 536.
MATLABI, Hossein; AHMADZADEH, Sharareh. Evaluation of individual quality of life among hemodialysis patients: nominated themes using SEIQoL-adapted. Patient preference and adherence, 2016, 1-9.
ELLIOTT, Barbara A., et al. Shifting responses in quality of life: People living with dialysis. Quality of Life Research, 2014, 23: 1497-1504.
DĄBROWSKA-BENDER, Marta, et al. The impact on quality of life of dialysis patients with renal insufficiency. Patient preference and adherence, 2018, 577-583.
MOLLAOĞLU, Mukadder. Quality of life in patients undergoing hemodialysis. In: Hemodialysis. IntechOpen, 2013.
IYASERE, Osasuyi U., et al. Quality of life and physical function in older patients on dialysis: a comparison of assisted peritoneal dialysis with hemodialysis. Clinical Journal of the American Society of Nephrology, 2016, 11.3: 423-430.
BOATENG, Edward Appiah; EAST, Linda. The impact of dialysis modality on quality of life: a systematic review. Journal of renal care, 2011, 37.4: 190-200.