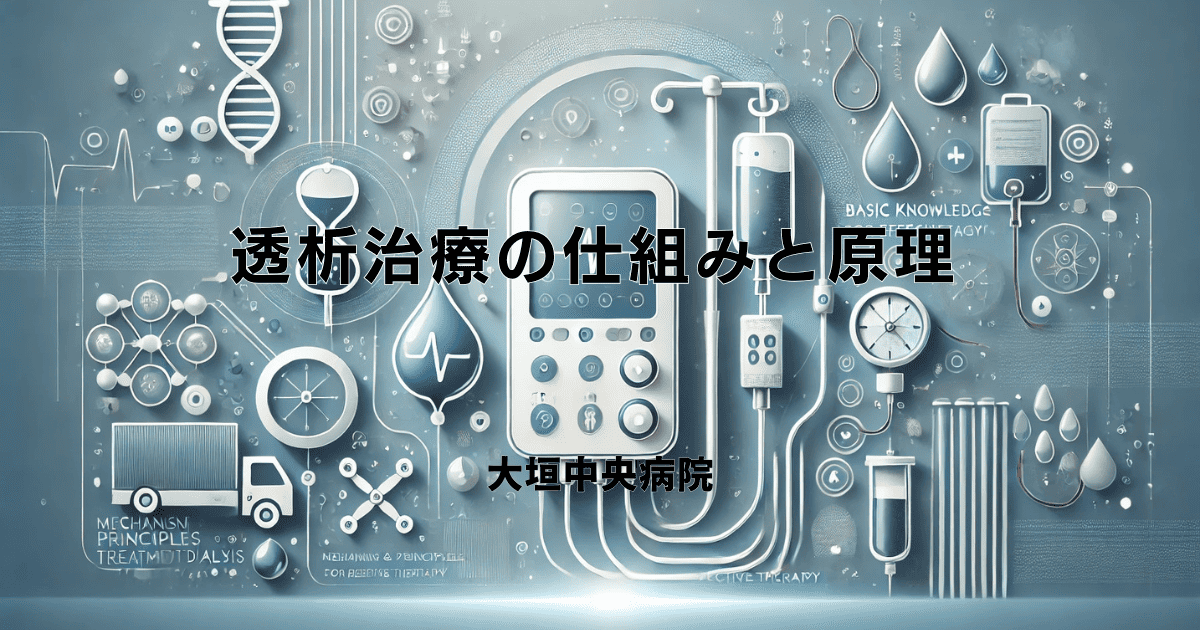腎臓の働きが十分でないと体内の老廃物や余分な水分を排出しにくくなり、さまざまな不調につながります。腎機能低下が進んだ状態では透析治療を考える人も多いです。
この治療は血液を浄化する手段として広く行っていますが、「どんな仕組みで血液をきれいにしているのか」「どのように実践するのか」など、その基本を理解することが重要です。
本記事では透析治療の基本から具体的な透析仕組み、さらに透析原理を中心に、患者さんが安心して取り組むための情報を詳しく解説します。
透析治療とは何か
腎機能が低下すると血液中に老廃物がたまり、健康を維持するのが難しくなります。こうした状態を補う方法として、透析治療が広く用いられています。
透析治療の概要
透析治療は腎臓の働きが大きく損なわれた場合に、人工的に血液中の老廃物や余分な水分を取り除く手段です。
食事管理や運動療法だけでは対応が難しい段階で導入することが多く、その方法は血液を体外に取り出してフィルターを通す血液透析や、お腹の中に専用の液体を入れて老廃物を除去する腹膜透析などに分かれます。
どちらも腎臓の代わりに老廃物を減らす働きを担い、体調をできる限り安定させるために重要な役割を果たしています。
人工的に血液を浄化する行為は複雑に感じるかもしれませんが、主治医や看護師などの専門家が安全を考慮しながら準備を進めるため、治療中に必要以上の負担を感じないよう配慮します。
治療を始めた直後は慣れないこともあるかもしれませんが、多くの場合は徐々に慣れて日常の生活リズムに組み込みやすくなります。
透析治療を受けるタイミング
腎臓機能がある程度低下しても、すぐに透析治療を始めるわけではありません。血液検査や尿検査の結果を踏まえて、腎臓がどの程度働いているかを主治医が判断しながら必要に応じて治療開始の判断を行います。
具体的には、糸球体濾過量(GFR)やクレアチニンなどの数値が一定以下になり、体にむくみや疲労感が強く出てくると、透析治療の導入を検討するケースが増えます。
腎機能の評価指標
| 指標 | 意味 | 特徴 |
|---|---|---|
| GFR | 腎臓のろ過能力を数値化 | 数値が低いほど腎機能が低下している |
| クレアチニン | 筋肉代謝物の濃度を測定 | 筋肉量の影響を受けるため基準値に幅がある |
| BUN | 血中尿素窒素を測定 | タンパク質代謝状態の影響を受けやすい |
| 尿蛋白 | 尿中のタンパク質量を測定 | 腎臓のろ過障害が進むと数値が増加する |
医師は上記のような指標と患者さんの自覚症状をあわせて考慮し、時期を見極めます。腎臓の働きがある程度残っている間は生活習慣の改善や投薬で進行を抑えることも可能ですが、限界を超えた場合には透析治療が大切です。
透析治療の目的
透析治療は単に老廃物を取り除くだけでなく、体内の電解質や水分バランスを整える意義があります。
腎機能が大きく落ちている状態ではカリウムやリン、ナトリウムなどの調節が乱れやすく、心臓や神経の働きに影響を及ぼすリスクが高まります。
透析によって過剰なカリウムを排出し、適切な電解質バランスを維持することは健康維持に欠かせません。
また、過剰な水分が体内に蓄積すると血圧が上がりやすくなり、心不全や息苦しさの原因になりやすいです。
透析治療は血液から余分な水分を取り除く役割も担っており、これにより浮腫(むくみ)や高血圧などの症状を軽減し、心臓への負担を軽くすることが期待できます。
人体における腎臓の役割と機能低下の影響
血液を浄化する透析仕組みを理解するためには、まず腎臓が果たしている働きを知ることが大切です。腎臓の機能低下が進むと、からだ全体でさまざまな問題が起こりやすくなります。
老廃物の排泄と体内バランス調整
腎臓は血液中の老廃物をろ過し、尿として排出する役割を担っています。食事から摂取した栄養素の代謝産物や薬の成分など、体に不要な物質を排泄する器官です。さらに、水分や電解質の調整を行う機能もあり、血中のナトリウムやカリウム、カルシウムなどの濃度を一定範囲に保つ重要な働きがあります。
腎臓が正常に働いているときは、体の内部環境がスムーズに保たれます。しかし、腎臓の機能が大幅に落ちると、余分な老廃物や水分を処理しきれずに血液が汚れ、全身に悪影響が及びやすくなります。
この状態が長引くと、心臓や血管にも大きな負担がかかり、生活の質も低下しがちです。
ホルモンの分泌と血圧調整
腎臓は老廃物の排泄だけでなく、さまざまなホルモンの分泌に関わっています。具体的には、赤血球をつくるのを促すエリスロポエチンや、血圧調整に関与するレニンなどが知られています。
これらのホルモンは体内の状態を整えるうえで重要なため、腎機能が低下すると貧血や血圧の乱れといった症状が生じやすいです。
腎臓が分泌する主なホルモン
| ホルモン名 | 役割 | 影響 |
|---|---|---|
| エリスロポエチン | 骨髄での赤血球生成を促す | 腎機能低下時は貧血になりやすい |
| レニン | 血圧調整に関わるレニン-アンギオテンシン系 | 高血圧や低血圧のリスクに影響 |
| 活性型ビタミンD | カルシウム吸収を助ける | 骨の強度維持に関与 |
腎臓の働きが落ちると、赤血球が作られにくくなり貧血が進んだり、血圧のコントロールが崩れたりして、疲労感やめまいなどの症状が出やすくなります。
透析治療は血液を浄化する主な目的に加え、こうした二次的な症状の悪化を防ぐためにも行われています。
機能低下が進んだ場合のリスク
腎臓の機能低下が進むと、老廃物が蓄積することだけでなく、電解質バランスの乱れや血圧の著しい変動など多くの合併症を招きやすいです。例えば高カリウム血症は心臓のリズムに影響を与え、重症化すると生命に関わる場合もあります。
また、高血圧を誘発しやすくなり、心臓への負担が増して心不全を引き起こすリスクも高まります。
腎機能低下と関連する主な合併症
| 合併症 | 主な症状・影響 | 対処方法 |
|---|---|---|
| 高カリウム血症 | 不整脈や心停止の危険性が高まる | 食事制限・透析治療の適切な導入 |
| 高血圧 | 動脈硬化・心臓病のリスク増大 | 減塩・適切な透析回数の検討 |
| 貧血 | 疲れやすさ・めまい・倦怠感の増加 | エリスロポエチン投与・食事管理 |
| 骨代謝異常(骨粗鬆症) | 骨折リスク増大 | 活性型ビタミンD補充・リン制限など |
上記の合併症を避けるためにも、腎機能が著しく低下した場合は透析治療の導入が大切です。血液を人工的に浄化することで老廃物や水分を減らし、体全体の負担を軽くします。
透析仕組みの基本
透析治療を導入する際には、透析仕組みを理解しておくと安心感が高まります。血液をどのように浄化するのかを知ると、治療の意味をより深く把握できるでしょう。
血液浄化の考え方
血液浄化の基本は、血液の中に含まれる老廃物や不要物質を選択的に取り除くことです。腎臓が果たすろ過機能を人工的に再現する仕組みが透析の核心であり、特殊なフィルターや透析液を用いて血液を浄化します。
血液透析の場合は血液を直接体外に導き、機械を通して老廃物を除去します。腹膜透析の場合はお腹の中(腹腔)を利用して老廃物を吸着・排出させる点が特徴です。
血液浄化の基本プロセス
| 項目 | 内容 | 意義 |
|---|---|---|
| 血液と透析液の接触 | フィルター内や腹腔内で血液と透析液が接触する | 不要物質を透析液側に移動させる |
| 拡散 | 老廃物などが高濃度から低濃度へ移行 | 血液中の有害物質を透析液に移し出しやすくする |
| 限外ろ過 | 水分や溶質を圧力差などを利用して除去 | 余分な水分を効率的に排出し、浮腫を防ぐ |
上表のように拡散や限外ろ過などの原理を活用し、血液から目的の物質を外へ出す手順を踏んでいます。透析装置と透析液、そして血液の流れをコントロールすることが透析治療のカギです。
血液透析に必要な血管アクセス
血液透析を受ける場合は、血管に針を刺して体外に血液を導く必要があります。安定した血流量を確保するため、上腕部や前腕部などに内シャント(動脈と静脈を直接つなぐ)や人工血管を作る方法が一般的です。
内シャントを作って血流を増やすことで、血液透析装置に血液を十分送り込みやすくなります。
シャントがない場合は中心静脈カテーテルを挿入して透析を行うこともありますが、感染症のリスクや血流量の確保が難しい面があります。
そのため、多くの場合は内シャントを作って長期的に使用する方法が選ばれます。内シャントを日常生活で守るためには、圧迫やけがに気をつけることが大切です。
透析施設での流れ
血液透析を実施する場合、病院や透析施設に定期的に通って治療を行います。週に3回前後、1回あたり4時間程度かけて血液を浄化するのが一般的です。
施設内では担当の医療スタッフや看護師が透析機器を操作し、患者さんの体調を確認しながら進めます。透析中は椅子やベッドで横になって過ごし、読書やテレビ鑑賞、仮眠をとる方もいます。
透析施設での1回の流れ
| 手順 | 概要 | 重要な点 |
|---|---|---|
| 受付・体重測定 | 施設に到着したら体重測定を実施 | 過剰な水分貯留を把握するために必要 |
| バイタルチェック | 血圧や脈拍、体温の確認を行う | 安全に透析を進めるための基礎データ |
| 針の穿刺 | 内シャントや人工血管に透析針を接続 | 感染に注意しながら確実に行う |
| 透析開始 | 血液透析装置を作動させ、血液をろ過する | 血圧や体調を随時確認する |
| 透析終了 | 時間が経過したら透析針を抜去し止血する | 出血やトラブルを防ぐため慎重に行う |
| 体重測定 | 透析後の体重を確認し、水分除去量を把握する | 血圧の変化や脱水症状に注意する |
血液透析を安定的に続けるためには、通院日程やスケジュールをしっかり調整し、生活習慣との両立を図ることが重要です。
透析原理3つと治療効果のメカニズム
透析原理は大まかに拡散、限外ろ過、対流の3要素に分かれます。これらを組み合わせることで血液から老廃物や水分、電解質などを除去し、体内環境を整えています。
透析原理3つの概要
1つ目の拡散は、高濃度から低濃度への物質移動を利用する方法です。血液中にある老廃物は透析液に比べて濃度が高く、自然に移動が起きる性質を利用して不要物質を取り去ります。
2つ目の限外ろ過は、圧力差や濃度差を活用して水分や溶質を膜を通過させる仕組みです。3つ目の対流は、大量の溶液移動によって溶質をまとめて押し流すように移動させる原理を指します。
血液透析でも腹膜透析でも、これら3要素を応用することで効果的な治療を実現しています。
拡散と限外ろ過の働き
拡散は分子やイオンが自然に動く性質で、分子量が小さい老廃物に効果を発揮します。尿素やクレアチニンなどは血液内と透析液の濃度差によって透析液側へ移動しやすいです。
一方、限外ろ過は透析膜に圧力をかけることで、水分とともに溶質を絞り出すようにして除去します。これによって余分な水分が血液から引き抜かれ、水分過多によるむくみや高血圧リスクを軽減できます。
老廃物除去と水分調整の仕組み
| 原理 | 主な除去対象 | 主なメリット |
|---|---|---|
| 拡散 | 尿素・クレアチニンなど | 小さい分子量の不要物質を低負担で除去 |
| 限外ろ過 | 余分な水分全般 | 血圧や心臓の負担を緩和 |
| 対流 | 一定量の中分子物質 | 物質をまとめて押し流す効果が期待できる |
対流は拡散と似ているようで異なり、圧力や体液移動の仕組みをさらに活用して中分子量の物質も効果的に除去します。近年は対流の要素を高めたろ過技術の活用も進んでおり、症状に応じて適切な透析方法を選ぶことが大切です。
透析原理を理解するメリット
透析原理を理解すると、自分が受けている治療の効果をより実感しやすくなります。老廃物がどのように除去されているのかを知っておくと、食事で摂取したタンパク質や水分の管理にも意識が高まります。
たとえば高カリウム食を過剰に摂れば、拡散で除去しきれないほどのカリウムが血中にたまる可能性もあります。こうした知識を活かして治療と生活のバランスを保つことが透析を安定して継続する鍵になります。
管理のヒント
- 拡散による除去が得意なものは血中濃度上昇に気をつける
- 大量の水分摂取は限外ろ過の負担を高める恐れがある
- 中分子量物質への対策として医師の指示に従った治療方法を選ぶ
透析の効果を最大限に引き出すためには、血液浄化の原理だけでなく、栄養や水分コントロールなどの日常生活の管理も大切です。
血液透析と腹膜透析の特徴
透析治療には血液透析と腹膜透析がありますが、それぞれの方法には特徴や留意点があります。主治医は患者さんのライフスタイルや合併症、血管の状態などを踏まえて治療方法を一緒に検討します。
血液透析は週3回程度、病院やクリニックなどの施設で機械を使って集中的に血液を浄化する方法です。腹膜透析は自宅でも実施でき、腹膜をフィルターとして活用して老廃物を排出します。
どちらも治療効果が期待できますが、体への負担や日常の管理方法が異なります。
血液透析のメリットとデメリット
血液透析は透析液のクオリティを医療スタッフが集中管理できるため、一定の治療効果を見込みやすいです。1回あたり4時間前後の治療を週3回程度実施することで老廃物や余分な水分を効率的に除去し、体調を整えることができます。
一方で施設への通院が必要になるため、通院が難しい状況にある方にとってはスケジュール管理が難しい面もあります。また、シャントを作って血管に針を刺すため、血管トラブルや感染症に注意が必要です。
腹膜透析のメリットとデメリット
腹膜透析は自宅などで行えるという利点があります。通院回数を減らしやすく、患者さんの生活リズムに合わせて実施できるため、職業生活や家事育児との両立をしやすい場合があります。
腹腔内にカテーテルを留置し、そこから透析液を注入・排液する方法で、血管への穿刺が不要です。ただし腹腔内で行うため、カテーテル出口部の感染防止に注意が必要です。
腹膜透析は身体への負担が比較的少ないと感じる方もいますが、腹膜機能が低下すると治療効果が下がる可能性があります。
血液透析と腹膜透析の違い
| 項目 | 血液透析 | 腹膜透析 |
|---|---|---|
| 実施場所 | 透析施設や病院 | 自宅や職場などでも実施可能 |
| 治療頻度 | 週3回ほど、1回あたり4時間前後 | 連続携行型(CAPD)や夜間交換型(APD)など多様 |
| 血管アクセス | 内シャントや人工血管などが必要 | 腹腔カテーテルを使用 |
| 身体への負担 | 通院による移動負担やシャント管理が必要 | 腹腔内の感染対策が大切、腹膜機能の保持が重要 |
| ライフスタイル | 通院スケジュールに合わせる必要がある | 交換スケジュールを自分で管理しやすい |
どちらの方法を選択するにしても、生活習慣や合併症の有無、患者さんの希望を総合的に検討して決定します。
ライフスタイルを重視するなら腹膜透析を選ぶこともありますし、医療スタッフのサポートを常に受けやすい環境を望む方は血液透析を選ぶ場合が多いです。
選択時に知っておきたい点
血液透析と腹膜透析のどちらを選ぶかは、単に通院のしやすさや治療頻度だけでなく、合併症の種類や患者さんの年齢、腹膜機能などさまざまな要因が関わってきます。
たとえば糖尿病を伴う慢性腎不全の方は、腹膜透析中に血糖値が変動しやすい場合があるため、主治医と相談しながら血液透析を選ぶケースもあります。自分に合う治療を知るためには、医療スタッフとのコミュニケーションが大切です。
透析中に気をつけたい日常生活
透析治療を行う場合、通院や在宅ケアだけでなく、日々の生活全般で注意点が生じます。食事・水分の管理や運動、仕事との両立など、多岐にわたる項目をバランスよく取り入れることが大切です。
食事療法のポイント
食事療法は腎機能を補ううえで非常に重要です。腎臓がうまく老廃物を排出できない状況では、食品から摂取するカリウムやリン、ナトリウムをコントロールしないと血中濃度が急上昇し、体調を崩す恐れがあります。
主治医や栄養士の指導を受けながら、以下のような事項を意識すると治療効果が保ちやすいです。
意識して摂取をコントロールしたい栄養素
| 栄養素 | 過剰時のリスク | 主な食品例 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 尿素窒素の増加・腎臓への負担 | 肉類・魚類・卵・大豆製品 |
| カリウム | 不整脈や心停止のリスク | 果物・野菜・芋類 |
| リン | 骨粗鬆症や血管石灰化のリスク | 乳製品・小魚・豆類 |
| 食塩 | 血圧上昇・むくみの原因 | 漬物・干物・加工食品など |
塩分を抑えた食事は高血圧を防ぐためにも必要です。味付けを工夫して薄味でも満足感を得られるようにすることが大切になります。また、カリウムを下げるために野菜を下茹でするなど、調理法にも工夫が求められます。
水分摂取の注意点
透析治療を受ける人にとって、水分管理は重要な課題です。腎機能が低下していると体内に水分がたまりやすくなり、体重増加やむくみ、血圧上昇を招きやすいです。
適切な透析回数で除去できる水分量には限りがあるため、日常的に摂取量をコントロールしないと体調不良につながります。
特に夏場の脱水症状も警戒が必要なので、水分を控えすぎて体調を崩さないよう、主治医や看護師の助言を得ながらバランスを図ります。
適度な運動とリハビリ
体力が落ちると日常生活に支障が出てくるため、透析中でも可能な範囲で運動やリハビリに取り組むことが推奨されています。散歩や軽い筋力トレーニングなどは血行促進や心肺機能の維持に役立ちます。
無理をしない範囲で続けることが大切なので、体調に合わせて運動の種類や強度を調整しましょう。リハビリ専門スタッフからの指導を受けることで、安全に体を動かす習慣を取り入れやすくなります。
取り入れやすい運動の例
- ウォーキング(自分のペースで距離や時間を調整)
- 片足立ちや軽いスクワット(筋力維持を目的とする)
- 呼吸法を意識したストレッチ
透析治療で通院中の場合は、医療施設内での待ち時間に軽い体操を行うなど、日常の中で取り入れる工夫も大切です。
仕事や社会生活への配慮
透析治療を受けながら仕事や社会活動を続ける方も増えています。勤務時間を調整し、通院日には休みやすい職場環境を整えるなど、事前の相談と準備が必要です。
職業の種類によっては肉体労働や不規則な勤務形態が負担になる場合もありますので、主治医や職場の上司と話し合って対応します。
週3回の血液透析を受けるなら、夜間透析を行う施設を選んだり、早朝や深夜のシフトをずらすなどの柔軟な働き方を模索するケースがあります。
腹膜透析の場合も交換時間をどのように確保するかが重要なので、家族の協力体制なども含めて総合的に計画を立てるとよいでしょう。
透析治療に関わる医療スタッフと役割
透析治療においては、複数の専門スタッフが連携しながら患者さんのケアを行っています。それぞれの専門家が得意分野を活かして、治療の質や患者さんの生活の質を高める役割を担います。
医師
医師は治療方針を決定し、患者さんの全身状態を評価しながら透析条件を調整します。血液検査や画像検査などの情報をもとに、透析の時間や透析液の濃度、薬剤の処方などを判断します。
合併症の有無や患者さんのライフスタイルを考慮し、血液透析と腹膜透析の選択を含む総合的な治療計画を立てます。
看護師・臨床工学技士
看護師は針の穿刺やバイタルサインのチェック、体調管理など患者さんとの接点が多い職種です。透析中に異変を感じた際、最初に相談できる相手でもあります。
臨床工学技士は透析機器の管理や保守点検を行い、機械トラブルが起きないようにサポートします。血液透析の条件設定やトラブル対応を担当し、安心して透析を続けられるよう機器の面から支援します。
チームで支える透析治療
| スタッフ | 主な役割 |
|---|---|
| 医師 | 治療方針の決定、透析条件や合併症の管理 |
| 看護師 | 透析前後のケア、バイタルチェック、穿刺、患者さんの相談窓口 |
| 臨床工学技士 | 透析装置の操作・メンテナンス、機械的トラブルの対処 |
| 管理栄養士 | 栄養指導、食事計画のアドバイス |
| 薬剤師 | 処方薬の説明、副作用や飲み合わせのチェック |
| ソーシャルワーカー | 生活支援、制度利用のサポート、心理的ケア |
これらのスタッフが定期的に情報交換を行いながら、患者さん一人ひとりに合ったケアを提供します。患者さん自身も、わからないことや不安がある場合は遠慮なく相談することが大切です。
管理栄養士・薬剤師
管理栄養士は患者さんの日常食や栄養バランスを考慮しながら、具体的な食事内容を提案します。腎臓に負担をかけにくい献立づくりのアドバイスや、カリウム、リン、塩分などを管理するコツを相談できます。
薬剤師は処方されている薬の飲み合わせや副作用を監視し、必要があれば医師に提案しながら薬の種類や量を調整します。特に透析治療中は薬物の体内滞留が変化しやすいため、薬剤師との連携が欠かせません。
ソーシャルワーカーや心理職
透析治療を長期にわたって続けると、経済的な負担や精神的なストレスが大きくなることがあります。ソーシャルワーカーは医療費に関わる公的支援制度の利用や、職場への復帰支援などについてアドバイスを行います。
心理職によるカウンセリングやメンタルサポートを受け、生活の質の維持や向上を図ることもできます。こうした専門スタッフとの連携を深めることで、より良い治療生活を送る助けとなります。
よくある質問
透析治療については、不安や疑問を抱く方が少なくありません。よく寄せられる質問を紹介しますので、治療の理解を深める際の参考にしてください。
- 透析治療を始めるタイミングはどのように決まるのですか?
-
主治医が血液検査や尿検査などの結果と、患者さんの自覚症状、生活面の状況などを総合的に判断し、導入時期を決めることが多いです。
糸球体濾過量(GFR)の低下が著しく、体にむくみや倦怠感などが出始めた場合に開始を検討します。
- 血液透析と腹膜透析のどちらが向いているのか迷っています
-
どちらの治療法にもメリットとデメリットがあります。通院の頻度を抑えたい、在宅での管理を重視したい場合は腹膜透析が向いているケースがあります。
一方、医療スタッフのケアを継続的に受けながら、安定した治療効果を得たい方は血液透析を選ぶことが多いです。主治医との相談が重要です。
- 透析中に旅行や外出をしても大丈夫ですか?
-
事前に透析先の医療機関やスケジュールを調整すれば、旅行や外出を行う方もいます。血液透析の場合、旅先の透析施設を手配する必要があります。
腹膜透析なら在宅透析の延長で続けられますが、透析液やカテーテルの管理に注意が必要です。
- 透析に通うために仕事を辞めなければならないですか?
-
職場と相談しながら通院日程を調整し、働きながら透析を受けている人も多いです。夜間や早朝透析を行う施設も増えており、治療と仕事の両立に取り組む方はいます。
難しい場合はソーシャルワーカーや上司と話し合い、制度を活用して働き方を見直す道もあります。
- 感染症が心配ですが、何か対策はありますか?
-
血液透析ではシャントへの穿刺、腹膜透析ではカテーテル出口部に細心の注意を払います。専門スタッフが清潔操作を徹底し、感染のサインを見逃さない体制を整えています。
自宅でも手洗いや器具の消毒を丁寧に行い、異常を感じた場合はすぐに主治医に相談しましょう。
以上
透析センター(人工透析) | 大垣中央病院(医療法人社団豊正会 )
参考文献
HENRICH, William L. Principles and practice of dialysis. Lippincott Williams & Wilkins, 2012.
MAHER, John F. Principles of dialysis and dialysis of drugs. The American journal of medicine, 1977, 62.4: 475-481.
MACLEOD, Alison, et al. Effectiveness and efficiency of methods of dialysis therapy for end-stage renal disease: a review. Health Technology Assessment, 1998.
DAUGIRDAS, John T.; BLAKE, Peter G.; ING, Todd S. Handbook of dialysis. Lippincott Williams & Wilkins, 2012.
FISCHBACH, Michel; WARADY, Bradley A. Peritoneal dialysis prescription in children: bedside principles for optimal practice. Pediatric nephrology, 2009, 24: 1633-1642.
TEITELBAUM, Isaac; BURKART, John. Peritoneal dialysis. American journal of kidney diseases, 2003, 42.5: 1082-1096.
MEHROTRA, Rajnish, et al. The current state of peritoneal dialysis. Journal of the American Society of Nephrology, 2016, 27.11: 3238-3252.
LEVY, Jeremy, et al. Oxford handbook of dialysis. OUP Oxford, 2009.LEVY, Jeremy, et al. Oxford handbook of dialysis. OUP Oxford, 2009.
REDDENNA, Languluri; BASHA, Shaik Ayub; REDDY, Kanala Siva Kumar. Dialysis treatment: a comprehensive description. International Journal of Pharmaceutical Research & Allied Sciences, 2014, 3.1.
GOKAL, Ram. Peritoneal dialysis in the 21st century: an analysis of current problems and future developments. Journal of the American Society of Nephrology, 2002, 13.suppl_1: S104-S115.