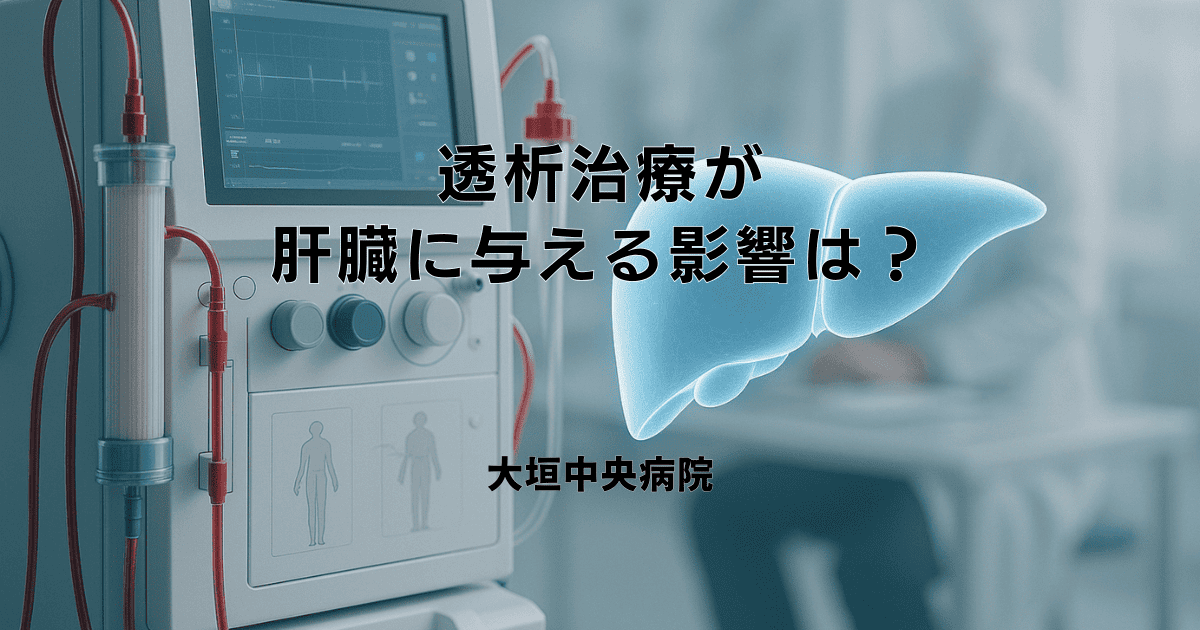腎臓の機能が低下した際に選択される透析治療は、生命を維持するために重要な役割を果たします。しかし、透析治療を受ける中で、肝臓への影響や肝機能の変化について不安を感じる方もいらっしゃるかもしれません。
この記事では、透析治療と肝臓・肝機能との関連性について、さまざまな側面から詳しく解説し、透析患者さんが知っておくべき情報を提供します。
透析治療と肝臓の基本的な関係
私たちの体内で重要な役割を担う腎臓と肝臓は、互いに密接に関連しながら機能しています。透析治療は腎臓の機能を代替するものですが、この治療が肝臓にどのような影響を与えるのか、基本的な関係性を理解することが大切です。
腎臓と肝臓の役割の連携
腎臓は血液をろ過して老廃物や余分な水分を尿として排泄する臓器ですが、肝臓もまた、体内の化学工場とも呼ばれるほど多岐にわたる重要な働きを担っています。例えば、栄養素の代謝、有害物質の解毒、血液凝固因子の生成などが挙げられます。
腎機能が低下すると、腎臓で処理しきれない物質が体内に蓄積し、肝臓の負担が増加することがあります。逆に、肝機能が低下すると、腎臓への血流や機能に影響が出ることがあり、両者は相互に影響し合う関係にあります。
腎臓と肝臓の主な機能比較
| 機能 | 腎臓 | 肝臓 |
|---|---|---|
| 老廃物の排泄 | 尿素、クレアチニンなど | ビリルビン、薬物代謝物など |
| 水分・電解質調節 | 体液量、ナトリウム、カリウムなど | アルブミン生成による膠質浸透圧維持 |
| ホルモン産生・活性化 | エリスロポエチン、活性型ビタミンD | アンジオテンシノーゲン、IGF-1 |
透析治療が始まる背景
透析治療は、慢性腎不全が進行し、腎臓の機能が著しく低下した場合(一般的にeGFRが15mL/min/1.73m²未満が目安の一つ)に、体内に溜まった老廃物や余分な水分を取り除くために導入されます。
腎機能の低下は、糖尿病性腎症、慢性糸球体腎炎、腎硬化症など、さまざまな原因によって引き起こされます。透析治療を開始することで、尿毒症症状の改善や生命予後の向上が期待できます。
なぜ透析患者さんにとって肝機能が重要なのか
透析患者さんにとって肝機能の維持は非常に重要です。肝臓は、栄養状態の維持に必要なタンパク質の合成、薬物の代謝、免疫機能など、生命維持に欠かせない多くの働きを担っています。
透析治療を受けていると、感染症のリスクや、使用する薬剤の種類が増えることなどから、肝臓への負担がかかりやすくなる場合があります。そのため、定期的な肝機能検査と適切な管理が求められます。
肝臓の主な機能のおさらい
肝臓は「沈黙の臓器」とも呼ばれ、障害があっても初期には自覚症状が現れにくい特徴があります。主な機能には以下のようなものがあります。
- 代謝機能(糖質、脂質、タンパク質の代謝)
- 解毒機能(アルコールや薬物、老廃物の分解)
- 胆汁の生成・分泌(脂肪の消化吸収を助ける)
- 血液凝固因子の生成
- 免疫機能(体内に侵入した異物を処理)
これらの機能が低下すると、全身にさまざまな影響が及びます。透析患者さんは、これらの肝機能を良好に保つことが、治療を継続し、生活の質を維持する上で大切です。
透析治療が肝機能に及ぼす直接的な影響
透析治療そのものが肝機能に直接的な影響を与える可能性も考慮する必要があります。透析療法は血液を体外循環させるため、使用する物質や血行動態の変化が肝臓に影響を及ぼすことがあります。
透析膜と生体適合性
血液透析では、ダイアライザー(透析器)の中にある透析膜を介して血液と透析液の間で物質交換を行います。
近年の透析膜は生体適合性が向上していますが、それでも血液が人工物に触れることで、微細な炎症反応や補体の活性化などが起こる可能性があります。
これらの反応が長期的に肝臓に影響を与える可能性はゼロではありませんが、通常は臨床的に問題となることは少ないと考えられています。
透析液の組成と肝臓への配慮
透析液は、血液中の電解質濃度やpHを正常に保つために、その組成が厳密に調整されています。例えば、酢酸を含まない透析液(無酢酸透析液)は、酢酸代謝に伴う血行動態の不安定化や肝臓への負担を軽減する目的で使用されることがあります。
また、透析液の清浄化も重要で、エンドトキシンなどの不純物が体内に侵入すると炎症を引き起こし、肝臓に影響を与える可能性があります。
透析の種類と特徴
| 透析の種類 | 原理 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 血液透析 (HD) | 拡散と限外ろ過 | 週2~3回、1回4~5時間程度、医療機関で実施 |
| 腹膜透析 (PD) | 腹膜を利用した拡散と浸透 | 在宅で可能、持続的または間欠的に実施 |
| 血液ろ過透析 (HDF) | 拡散、限外ろ過、補充液 | より多くの老廃物除去が期待できる |
血液浄化に伴う血行動態の変動
血液透析では、体外循環によって一時的に血圧が変動することがあります。特に除水によって循環血液量が減少すると、血圧が低下しやすくなります。このような血行動態の変動は、肝臓への血流量にも影響を与える可能性があります。
急激な血圧低下は肝虚血を引き起こすリスクがあるため、適切なドライウェイトの設定と慎重な除水管理が重要です。
薬物代謝の変化と肝臓の負担
腎機能が低下すると、多くの薬物の排泄が遅延するため、投与量の調整が必要になります。透析患者さんは複数の薬剤を服用していることが多く、これらの薬物の中には肝臓で代謝されるものも少なくありません。
腎機能低下に加えて、透析治療による影響も考慮し、薬物性肝障害を予防するためには、薬剤の選択や投与量に細心の注意を払う必要があります。特に、肝代謝型の薬剤を長期間使用する場合には、定期的な肝機能検査が大切です。
透析患者さんに見られる肝臓の合併症
透析患者さんは、一般の方と比較して特定の肝臓疾患を発症しやすい傾向があることが知られています。これらの合併症を早期に発見し、適切に対処することが、QOL(生活の質)の維持につながります。
ウイルス性肝炎(B型肝炎・C型肝炎)のリスクと現状
かつては、輸血や透析施設での集団感染により、透析患者さんにおけるB型肝炎ウイルス(HBV)やC型肝炎ウイルス(HCV)の感染率が高い時期がありました。
しかし、献血血液のスクリーニング検査の導入、透析機器の消毒・滅菌の徹底、HCVに対する有効な治療薬の開発などにより、新規の感染は大幅に減少しています。
それでも、既感染者やキャリアの方は存在するため、定期的なウイルスマーカーの検査と、必要に応じた抗ウイルス療法が重要です。
ウイルス性肝炎の種類と感染経路
| 肝炎ウイルスの種類 | 主な感染経路 | 慢性化のリスク |
|---|---|---|
| B型肝炎ウイルス (HBV) | 血液・体液(母子感染、性交渉、医療行為など) | 感染時期による(成人では低い) |
| C型肝炎ウイルス (HCV) | 血液(主に注射針の共有、過去の輸血など) | 高い(約70%) |
非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD/NASH)
非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)は、飲酒歴がないか少量にもかかわらず、肝臓に脂肪が蓄積する疾患です。そのうち、肝炎や線維化を伴うものを非アルコール性脂肪肝炎(NASH)と呼び、肝硬変や肝がんへ進行する可能性があります。
透析患者さんでは、糖尿病、脂質異常症、肥満などの合併が多く、これらがNAFLD/NASHの発症リスクを高めます。食事療法や運動療法による生活習慣の改善が予防と治療の基本となります。
NAFLD/NASHのリスク因子
| リスク因子 | 説明 |
|---|---|
| 肥満(特に内臓脂肪型) | インスリン抵抗性を介して脂肪肝を促進 |
| 糖尿病(2型) | 高血糖やインスリン抵抗性が肝臓への脂肪蓄積を助長 |
| 脂質異常症 | 血中のコレステロールや中性脂肪が高い状態 |
鉄過剰症と肝臓
透析患者さんでは、腎性貧血の治療のために鉄剤の投与や赤血球造血刺激因子製剤(ESA)と併用して鉄剤を使用することがあります。また、頻回の輸血も鉄過剰の原因となり得ます。
体内に過剰な鉄が蓄積すると、肝臓をはじめとするさまざまな臓器に沈着し、機能障害を引き起こす可能性があります(ヘモクロマトーシス)。
定期的な血清フェリチン値やトランスフェリン飽和率(TSAT)の測定により鉄の状態を評価し、適切な鉄管理を行うことが重要です。
薬剤性肝障害の注意点
透析患者さんは多くの薬剤を服用する機会があり、薬剤性肝障害のリスクも考慮しなければなりません。腎機能が低下しているため、薬物の排泄が遅れがちで、肝臓で代謝される薬物の場合は特に注意が必要です。
原因となる薬剤は多岐にわたりますが、抗菌薬、解熱鎮痛薬、抗てんかん薬、脂質異常症治療薬などが挙げられます。
新たな薬剤を開始する際や、長期にわたり薬剤を服用する際には、定期的な肝機能検査を行い、異常が見られた場合は速やかに原因薬剤を特定し、中止または変更を検討します。
肝機能低下が透析治療に与える影響
肝機能の低下は、透析治療そのものや患者さんの全身状態にさまざまな影響を及ぼします。肝臓の機能が損なわれると、透析管理がより複雑になることがあります。
栄養状態の悪化とアルブミン値
肝臓は、血清タンパク質の主要な成分であるアルブミンを合成する場所です。肝機能が低下するとアルブミンの合成能力が低下し、低アルブミン血症をきたすことがあります。
アルブミンは栄養状態の指標であると同時に、血液の浸透圧を維持する役割も担っています。
低アルブミン血症は、透析中の血圧低下(除水困難)、浮腫、免疫力低下、生命予後の悪化などと関連するため、適切な栄養管理がより一層重要になります。
易出血性と凝固因子の産生低下
肝臓は、血液凝固に必要な多くの凝固因子を産生しています。肝硬変などで肝機能が著しく低下すると、これらの凝固因子の産生が不足し、出血しやすい状態(易出血性)になることがあります。
透析治療では、血液が固まらないように抗凝固薬を使用しますが、肝機能低下による易出血傾向がある場合は、抗凝固薬の量の調整が難しくなり、シャント穿刺部位からの止血困難や、消化管出血などのリスクが高まる可能性があります。
肝機能低下時の主な症状
- 全身倦怠感、易疲労感
- 黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)
- 浮腫、腹水
- 食欲不振、体重減少
- 出血傾向(鼻血、歯肉出血、皮下出血)
腹水の管理と透析の難しさ
肝硬変が進行すると、門脈圧亢進や低アルブミン血症などにより腹水が貯留することがあります。腹水が大量に貯留すると、呼吸困難や食欲不振を引き起こし、生活の質を著しく低下させます。
透析患者さんで腹水がある場合、除水による循環動態の不安定化を招きやすく、透析中の血圧維持が困難になることがあります。また、腹水穿刺排液や腹膜透析カテーテルからの感染リスクも考慮する必要があります。
薬物療法の調整の必要性
肝機能が低下すると、薬物の代謝や排泄が変化するため、多くの薬剤で投与量の調整が必要になります。特に肝代謝型の薬剤や肝毒性のある薬剤の使用は慎重に行うべきです。
腎機能障害に加えて肝機能障害も合併している場合は、薬物動態がさらに複雑になるため、血中濃度モニタリングなどを参考にしながら、個々の患者さんの状態に合わせてきめ細かく薬物療法を調整することが求められます。
透析患者さんの肝機能を守るためのポイント
透析治療を受けながら肝機能を良好に保つためには、日頃からの注意と定期的な管理が重要です。いくつかの重要なポイントを解説します。
定期的な肝機能検査の重要性
肝臓は「沈黙の臓器」と言われるように、初期には自覚症状が出にくいことがあります。そのため、定期的な血液検査による肝機能のチェック(AST、ALT、γ-GTP、ビリルビン、アルブミンなど)が非常に重要です。
これにより、肝障害の早期発見、原因の特定、そして適切な対応へとつなげることができます。検査結果に異常が見られた場合は、原因を詳しく調べるために追加の検査(腹部超音波検査、ウイルスマーカー検査など)を行うこともあります。
肝機能検査の主な項目
| 検査項目 | 何を示しているか | 基準値の目安(施設により異なる) |
|---|---|---|
| AST (GOT) | 肝細胞の障害の程度 | 10~40 IU/L |
| ALT (GPT) | 肝細胞の障害の程度 (より肝特異的) | 5~45 IU/L |
| γ-GTP | 肝・胆道系の障害、アルコール性肝障害 | 男性: 80 IU/L以下, 女性: 30 IU/L以下 |
栄養管理と食事療法の工夫
透析患者さんの食事療法は、カリウム、リン、水分、塩分の制限が基本となりますが、肝機能が低下している場合は、これに加えてタンパク質の量や質、総エネルギー量なども考慮する必要があります。
低栄養は肝機能にも悪影響を及ぼすため、適切なエネルギーとタンパク質を摂取することが大切です。特に肝硬変が進行している場合は、分岐鎖アミノ酸(BCAA)製剤の利用や、アンモニアの産生を抑える食事などが考慮されることもあります。
管理栄養士と相談しながら、個々の状態に合わせた食事計画を立てることが望ましいです。
透析患者さんの食事療法のポイント(肝臓への配慮)
| 栄養素 | 配慮する点 | 具体的な食品例(注意点) |
|---|---|---|
| タンパク質 | 良質なタンパク質を適量摂取。肝硬変進行時は制限も。 | 魚、肉、卵、大豆製品(リン含有量に注意) |
| エネルギー | 低栄養を避けるため、十分なエネルギーを確保。 | 炭水化物(ごはん、パン、麺類)、油脂類(適量) |
| ビタミン・ミネラル | 水溶性ビタミンは透析で失われやすい。肝機能低下時は脂溶性ビタミンの蓄積にも注意。 | 医師の指示に基づきサプリメントも検討 |
適切な体重管理(ドライウェイト設定)
ドライウェイト(透析後の目標体重)の適切な設定と維持は、心血管系への負担を軽減するだけでなく、肝臓への血流を安定させる上でも重要です。過度な除水は血圧低下を招き、肝虚血のリスクを高める可能性があります。
逆に、水分過多の状態が続くと心不全を悪化させ、うっ血肝を引き起こすこともあります。定期的なドライウェイトの見直しと、日々の体重測定による自己管理が大切です。
感染症予防とワクチン接種
透析患者さんは免疫機能が低下している場合があり、感染症にかかりやすい状態にあります。肝炎ウイルス(特にB型肝炎)はワクチンで予防可能なものもあります。
医療従事者との相談の上、B型肝炎ワクチンの接種を検討することが推奨されます。また、インフルエンザワクチンや肺炎球菌ワクチンなど、他の感染症に対する予防接種も重要です。
日常生活においては、手洗いやうがいを励行し、感染経路を遮断する意識を持つことが肝臓を守ることにもつながります。
感染症予防のための基本的な対策
- 手洗い、うがいの励行
- 人混みを避ける
- 十分な睡眠と休息
- バランスの取れた食事
- 予防接種の検討
肝機能障害を持つ透析患者さんの日常生活の注意点
肝機能に何らかの障害を抱えながら透析治療を続ける場合、日常生活においてもいくつかの注意点があります。これらを守ることで、肝機能の悪化を防ぎ、より良い状態を維持することを目指します。
服薬管理の徹底
処方された薬剤は、指示通りに正しく服用することが基本です。特に肝機能が低下している場合は、薬物の代謝や排泄が通常と異なるため、自己判断で薬の量を変更したり、中止したりすることは危険です。
市販薬や健康食品を利用する際も、必ず事前に医師や薬剤師に相談し、肝臓への影響がないか確認するようにしましょう。
肝臓に負担をかける可能性のある薬剤の例
以下はあくまで一般例であり、個々の状況によって異なります。必ず医師・薬剤師にご相談ください。
| 薬剤の種類 | 注意点 |
|---|---|
| 一部の解熱鎮痛薬(アセトアミノフェンなど) | 過量投与で肝障害のリスク。 |
| 一部の抗菌薬 | 薬剤の種類により肝障害の報告あり。 |
| 一部の抗真菌薬 | 定期的な肝機能検査が必要な場合あり。 |
食事制限と栄養バランス
前述の通り、肝機能の状態に応じた食事療法が重要です。塩分、水分、カリウム、リンの制限に加え、タンパク質の量や質、総エネルギー量などを医師や管理栄養士の指導のもとで調整します。
特に肝硬変がある場合は、アンモニアの生成を抑えるためにタンパク質の種類を選んだり、便秘を避ける工夫(食物繊維の摂取など)も大切になります。バランスの取れた食事を心がけ、低栄養にならないように注意しましょう。
過度な安静を避け、適度な活動を
体調が良い範囲で、適度な身体活動を維持することは、全身の血行を促進し、筋力の維持にもつながります。ただし、肝機能が著しく低下している場合や、黄疸、腹水などの症状が強い場合は、安静が必要なこともあります。
どのような運動が適切か、どの程度の活動が許容されるかについては、必ず主治医に相談し、指示に従ってください。無理のない範囲で、散歩などの軽い運動から始めるのが良いでしょう。
定期受診と医師との連携
定期的な受診は、肝機能を含む全身状態のチェック、検査結果の評価、治療方針の確認・調整のために非常に重要です。体調の変化や気になる症状があれば、些細なことでも遠慮なく医師や医療スタッフに伝えましょう。
早期発見・早期対応が、合併症の進行を防ぎ、より良い透析生活を送るための鍵となります。また、複数の医療機関にかかっている場合は、情報共有がスムーズに行えるよう、お薬手帳などを活用することも大切です。
よくある質問 (FAQ)
透析治療と肝機能に関して、患者さんやご家族からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
- 透析をしていると必ず肝臓が悪くなりますか?
-
透析治療を受けているからといって、必ずしも肝臓が悪くなるわけではありません。
確かに、透析患者さんは肝臓に影響を及ぼす可能性のある要因(薬剤、感染症リスク、血行動態の変動など)にさらされる機会が多いのは事実です。
しかし、定期的な肝機能検査を受け、異常があれば早期に原因を特定し対処すること、適切な栄養管理や服薬管理を行うこと、感染予防策を講じることなどで、肝機能の維持は十分に可能です。
多くの透析患者さんが、良好な肝機能を保ちながら治療を継続しています。
- 肝機能が悪いと透析治療は受けられませんか?
-
肝機能が低下している場合でも、多くの場合、透析治療を受けることは可能です。実際、肝硬変などの肝疾患を合併している透析患者さんもいらっしゃいます。
ただし、肝機能の程度によっては、透析方法の選択(例えば、腹膜透析を考慮する、血液透析の条件を調整するなど)、使用する薬剤の調整、栄養管理の強化など、特別な配慮が必要になることがあります。
主治医が肝臓の状態を正確に把握し、最も安全かつ効果的な透析治療計画を立てることが重要です。
- 肝臓を守るために自分でできることはありますか?
-
はい、いくつかあります。まず、医師から指示された食事療法(塩分、水分、タンパク質、カリウム、リンなどの制限やバランス)をしっかり守ることが基本です。
処方された薬は正しく服用し、市販薬やサプリメントを使用する前には必ず医師に相談してください。B型肝炎などのワクチン接種も有効な予防策です。また、過度な飲酒は避け(透析患者さんは原則禁酒が望ましい場合が多いです)、禁煙を心がけましょう。
適度な運動や十分な睡眠、ストレスを溜めない生活も、間接的に肝臓を守ることにつながります。そして何よりも、定期的な検査を受け、体調の変化に気付いたらすぐに相談することが大切です。
- 肝炎ウイルスに感染していても透析は続けられますか?
-
はい、B型肝炎ウイルスやC型肝炎ウイルスに感染している場合でも、適切な治療と感染管理のもとで透析治療を続けることは可能です。
C型肝炎については、近年、副作用が少なく効果の高い経口抗ウイルス薬が登場し、多くの患者さんでウイルスの排除が可能になっています。B型肝炎についても、核酸アナログ製剤などによる治療でウイルスの増殖を抑えることができます。
透析施設では、感染対策が徹底されており、他の患者さんへの感染拡大を防ぐための措置が講じられています。肝炎治療と透析治療の両方を専門医とよく相談しながら進めていくことが重要です。
以上
透析センター(人工透析) | 大垣中央病院(医療法人社団豊正会 )
参考文献
CHAUDHARY, Kunal; KHANNA, Ramesh. Renal replacement therapy in end-stage renal disease patients with chronic liver disease and ascites: role of peritoneal dialysis. Peritoneal dialysis international, 2008, 28.2: 113-117.
QURESHI, Muhammad Omar, et al. Renal failure in patients with end stage liver disease and its impact on clinical outcome. Journal of the College of Physicians and Surgeons–Pakistan, 2014, 24: 628-631.
FRALEY, Donald S., et al. Impact of acute renal failure on mortality in end-stage liver disease with or without transplantation. Kidney international, 1998, 54.2: 518-524.
LIM, Young-Suk, et al. Serum sodium, renal function, and survival of patients with end-stage liver disease. Journal of hepatology, 2010, 52.4: 523-528.
SETHI, Aastha, et al. Kidney function and mortality post-liver transplant in the Model for End-Stage Liver Disease era. International journal of nephrology and renovascular disease, 2011, 139-144.
PARAJULI, Sandesh, et al. Renal function and transplantation in liver disease. Transplantation, 2015, 99.9: 1756-1764.
THORAT, Ashok; JENG, Long-Bin. Management of renal dysfunction in patients with liver cirrhosis: role of pretransplantation hemodialysis and outcomes after liver transplantation. In: Seminars in Vascular Surgery. WB Saunders, 2016. p. 227-235.
KOVVURU, Karthik; VELEZ, Juan Carlos Q. Kidney replacement therapy in patients with acute liver failure and end-stage cirrhosis awaiting liver transplantation. Clinics in Liver Disease, 2022, 26.2: 245-253.
CHENG, Xingxing S.; TAN, Jane C.; KIM, W. Ray. Management of renal failure in end‐stage liver disease: a critical appraisal. Liver Transplantation, 2016, 22.12: 1710-1719.
DAVENPORT, Andrew. Is there a role for continuous renal replacement therapies in patients with liver and renal failure?. Kidney International, 1999, 56: S62-S66.