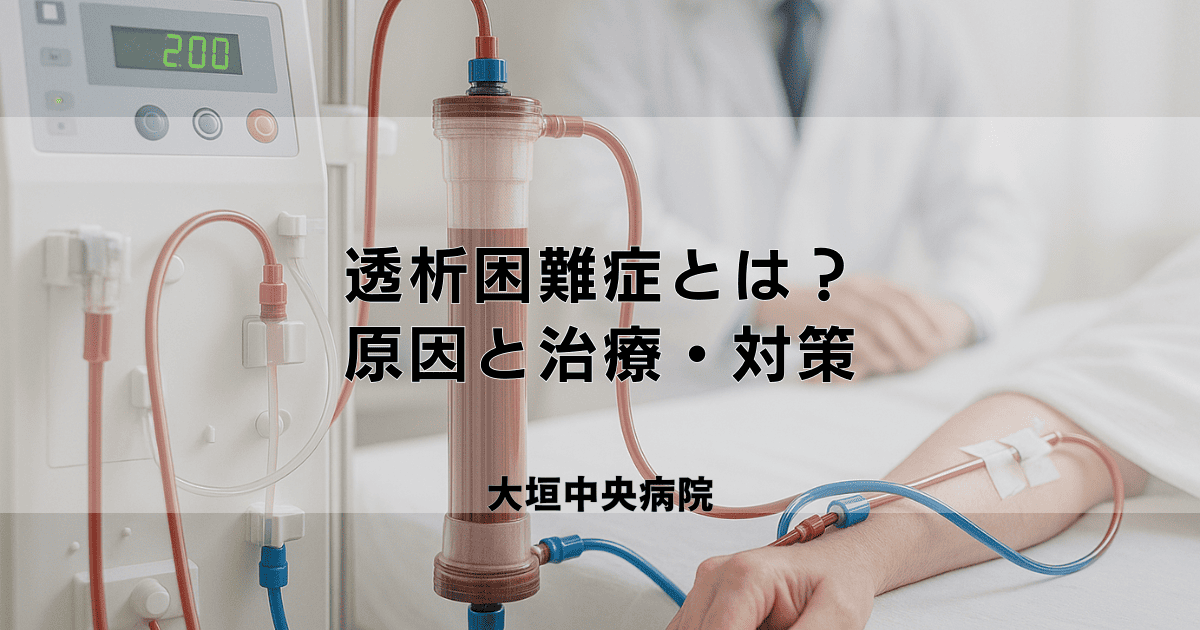血液透析は、腎臓の機能を代替する重要な治療法ですが、一部の患者さんにとっては、治療を安定的かつ安全に継続することが難しい場合があります。このような状態は透析困難症と呼ばれ、原因は一つではありません。
バスキュラーアクセスのトラブル、透析中の体調不良、精神的な負担など、さまざまな要因が複雑に絡み合って生じます。
この記事では、透析困難症とは何か、主な原因であるバスキュラーアクセス不全や血圧低下、さらには心理的な問題に焦点を当て、それぞれの治療法や対策について、解説していきます。
透析困難症の全体像を理解する
透析困難症という言葉を聞いたことがあるでしょうか。これは単一の病気を指すものではなく、さまざまな原因によって安定した透析治療の継続が難しくなる状態の総称です。
患者さん一人ひとりが抱える問題は異なり、解決には多角的な視点が必要です。
透析困難症の定義と概念
透析困難症は、医学的に明確に定義された単一の疾患名ではありません。
バスキュラーアクセスの問題、透析中の血圧変動、アレルギー反応、心理的要因など、何らかの理由で計画通りに血液透析を完了できない、あるいは治療中に著しい苦痛を伴う状態全般を指します。
身体的な問題だけでなく、精神的、社会的な要因が複雑に絡み合って、治療の継続を妨げているケースも少なくありません。
なぜ透析が困難になるのか
透析が困難になる原因は多岐にわたり、最も一般的なのは、血液の出入り口であるバスキュラーアクセスの機能不全で、また、透析による急激な体液の移動に伴う血圧の低下も、多くの患者さんを悩ませる問題です。
その他、透析膜に対するアレルギー、筋肉のけいれん、穿刺への恐怖心や長期治療に対する抑うつ気分など、身体的な要因と心理的な要因も相互に影響し合います。
透析困難症に該当する主な症状
透析困難症は、さまざまな症状として現れます。症状は、透析治療の効果を低下させるだけでなく、患者さんの生活の質(QOL)を著しく損なう可能性があります。
透析困難症の主な症状分類
| 分類 | 具体的な症状の例 | 主な原因 |
|---|---|---|
| アクセス関連 | 穿刺が難しい、十分な血流がとれない、シャントの閉塞 | バスキュラーアクセスの狭窄・閉塞 |
| 循環器関連 | 血圧低下、めまい、吐き気、意識消失、胸痛 | 急激な除水、心機能低下、自律神経障害 |
| アレルギー関連 | かゆみ、じんましん、呼吸困難、血圧低下 | ダイアライザ(透析膜)などへの反応 |
透析困難症がもたらす影響
透析困難症を放置すると、さまざまな悪影響が生じます。
まず、計画通りの除水や毒素の除去ができないため、透析不足の状態になり、体内に余分な水分や老廃物が蓄積し、心臓への負担増加や尿毒症症状の悪化を招きます。
また、毎回の透析が苦痛であると、治療に対する意欲が低下し、精神的にも追い詰められてしまうなど、生活の質そのものが大きく低下する危険性があります。
バスキュラーアクセス不全とその対策
安定した透析治療の生命線ともいえるのが、血液を体外に取り出し、きれいにして戻すための出入り口であるバスキュラーアクセスです。このアクセスに問題が生じると、透析そのものが困難になります。
バスキュラーアクセスの種類と役割
バスキュラーアクセスには主に3つの種類があり、患者さんの血管の状態や全身状態を考慮して、最も適した方法が選択されます。
バスキュラーアクセスの種類と特徴
| 種類 | 概要 | 長所・短所 |
|---|---|---|
| 自己血管内シャント(AVF) | 自身の動脈と静脈を手術でつなぎ合わせ、静脈を発達させたもの。 | 長所:長持ちしやすく、感染に強い。短所:作成に時間がかかり、血管の状態によっては作成困難。 |
| 人工血管内シャント(AVG) | 人工の管を動脈と静脈の間に埋め込み、つなぎ合わせたもの。 | 長所:比較的早期に使用可能。短所:AVFに比べ閉塞や感染のリスクが高い。 |
| 長期留置カテーテル | 首や胸、足の付け根の太い静脈にカテーテルを留置するもの。 | 長所:すぐに使用可能。短所:感染リスクが非常に高く、入浴などに制限がある。 |
アクセス不全の主な原因
長年透析を続けていると、バスキュラーアクセスにはさまざまな問題が生じやすくなります。
最も多いのは、血管の内側が狭くなる狭窄や、完全に詰まってしまう閉塞で、これは、繰り返される穿刺や血流の変化による血管への負担が主な原因です。
その他、細菌が侵入することによる感染や、血の塊(血栓)ができて流れを妨げることもあります。
アクセス不全の兆候と自己管理
バスキュラーアクセスのトラブルは、早期に発見し対処することがアクセスを長持ちさせる鍵で、そのためには、患者さん自身による日々の観察がとても重要です。異常をいち早く察知するために、以下の点に注意しましょう。
日常で確認すべきシャントのチェックポイント
- 見て:シャント部分に赤みや腫れ、傷がないか
- 聞いて:シャント音(ザーザーという血流の音)がいつも通りか、弱くなっていないか
- 触れて:スリル(血流による微細な振動)を感じるか、弱まったり消えたりしていないか
医療機関での治療法
アクセス不全が疑われた場合、医療機関では超音波検査や血管造影検査で状態を詳しく評価し、結果に基づき、治療法を決定します。狭窄している場合には、風船のついたカテーテルで血管を内側から広げる経皮的血管形成術(PTA)が一般的です。
閉塞してしまった場合は、血栓を溶かしたり、外科的に除去したりする治療が行われます。治療で改善しない場合は、シャントを新しく作り直す手術(再建術)が必要になることもあります。
透析中の血圧低下(透析低血圧)の原因と対処法
透析中に気分が悪くなったり、意識が遠のくような感覚を覚えたりする原因の多くは、血圧の低下にあります。これは多くの透析患者さんが経験する症状であり、透析困難症の主要な原因の一つです。
なぜ透析中に血圧が低下するのか
透析中に血圧が低下する最大の理由は、短時間で体から水分(除水)と血液を取り出すことによる循環血液量の減少です。
健康な人であれば、自律神経が働いて血管を収縮させ、血圧を維持しようとしますが、長期の透析患者さんではこの調節機能がうまく働かないことがあります。
また、心臓の機能が低下している場合や、透析液の温度が体温より高い場合なども、血圧が下がりやすくなる要因です。
透析低血圧の症状
透析低血圧は、さまざまな症状を起こし、初期症状は、あくび、吐き気、冷や汗、倦怠感などです。
症状が進行すると、めまいや頭痛、腹痛、筋肉のけいれんなどが起こり、重度の場合には意識を失ったり、けいれん発作を起こしたりすることもあります。
医療機関で行う対策
医療機関では、透析低血圧を防ぐためにさまざまな対策を講じます。最も基本となるのは、患者さん一人ひとりに合った適正体重(ドライウェイト)を正確に設定し、過度な除水を避けることです。
また、除水速度を一定にするのではなく、透析の経過に合わせて変化させるプログラム除水や、透析液の温度・ナトリウム濃度を調整する方法も有効です。
それでも血圧が下がってしまう場合には、血圧を上げる薬(昇圧剤)を使用することもあります。
透析低血圧に対する医療機関での主な対策
| 対策 | 内容 | 目的 |
|---|---|---|
| ドライウェイトの見直し | 心胸郭比や体組成などを参考に、適正な目標体重を再設定する。 | 過剰な除水を防ぎ、循環血液量の減少を緩やかにする。 |
| 除水・透析液の調整 | 除水速度のパターンを変更したり、透析液の温度やNa濃度を調整する。 | 血圧の変動を抑制し、末梢血管の収縮を助ける。 |
| 薬物療法 | 透析中に昇圧剤を使用したり、食間の降圧薬の調整を検討する。 | 直接的に血圧を維持し、急激な低下を防ぐ。 |
患者自身ができる予防策
透析低血圧の予防には、患者さん自身の自己管理も非常に重要で、最も大切なのは、水分や塩分の摂取量を守り、透析間の体重増加をコントロールすることです。
体重増加が多いと、その分だけ短時間で多くの除水が必要になり、血圧低下のリスクが高まります。また、透析直前の食事は消化のために胃腸に血液が集まり、血圧が下がりやすくなるため、軽めにするなどの工夫も有効です。
降圧薬を内服している場合は、服薬のタイミングについて主治医と相談することも大事です。
その他の身体的要因による透析困難
バスキュラーアクセスや血圧の問題以外にも、透析を困難にする身体的な要因があります。透析膜に対するアレルギー反応や、透析中の筋肉のけいれんなど、比較的多くの患者さんが経験する問題について、原因と対策を解説します。
アレルギー反応と不均衡症候群
透析治療では、ダイアライザ(透析膜)や血液回路、薬剤などに対してアレルギー反応が起こることがあります。症状はかゆみやじんましんといった軽いものから、呼吸困難や血圧低下といった重篤なものまでさまざまです。
また、特に透析導入期には、体内の尿毒素が急激に除去されることで、脳と血液の間に濃度差が生じ、頭痛や吐き気、意識障害などを引き起こす不均衡症候群が生じることがあります。
アレルギー反応のタイプと主な症状
| タイプ | 発症時期 | 主な症状 |
|---|---|---|
| Ⅰa型 | 透析開始直後(数分以内) | 胸部不快感、呼吸困難、灼熱感 |
| Ⅰb型 | 透析開始後15~30分 | かゆみ、じんましん、咳、発熱 |
筋肉のけいれん(こむら返り)
透析中に足がつる、いわゆる「こむら返り」も頻度の高い症状です。
急激な除水によって循環血液量が減少し、筋肉への血流が不足することや、体内の電解質(ナトリウム、カリウムなど)のバランスが崩れることが主な原因と考えられています。
血圧低下に伴って起こることも多く、強い痛みを伴うため、患者さんにとっては大きな苦痛となり、予防としては、適切なドライウェイトの設定と体重管理が基本です。症状が出た際には、透析スタッフがマッサージや補液などの対処を行います。
かゆみや不眠
透析患者さんの多くが、全身の強いかゆみに悩まされます。かゆみは、皮膚の乾燥、リンや尿毒素物質の蓄積、アレルギー反応など、複数の要因が絡み合って生じます。
また、レストレスレッグス症候群(むずむず脚症候群)と呼ばれる、じっとしていると足がむずむずして動かさずにはいられない症状も、不眠の大きな原因です。
症状に対しては、保湿剤によるスキンケア、食事療法、薬物療法などを組み合わせて対処します。
透析に伴うかゆみの対策
- スキンケア:保湿剤を十分に塗り、皮膚の乾燥を防ぐ
- 食事療法:リンの摂取を制限する
- 薬物療法:抗ヒスタミン薬、かゆみを抑える特殊な内服薬など
- 十分な透析:尿毒素をしっかりと除去する
精神的・心理的要因とケア
長期間にわたる透析治療は、身体だけでなく心にも大きな負担をかけます。週3回の通院、食事や水分の制限、穿刺の痛み、そして将来への不安などが積み重なり、心が疲弊してしまうことも少なくありません。
治療への意欲喪失や抑うつ気分が、透析を困難に感じさせることもあります。
透析治療に伴う心理的ストレス
透析患者さんが抱えるストレスは多岐にわたり、治療による時間的な拘束は、仕事や社会活動への参加を難しくすることがあります。
食事や水分制限は、生活の楽しみを奪いかねず、毎回のシャント穿刺への恐怖や痛みは、透析室へ向かう足を重くさせます。
また、病気と共に生きることへの不安や、いつまで治療が続くのかという絶望感が、抑うつ状態を起こすこともあります。
不安や抑うつへの対処法
つらい気持ちを一人で抱え込まず、まずは、医師や看護師、臨床工学技士といった医療スタッフに、自分の気持ちを話してみることが大切です。専門家としてのアドバイスだけでなく、話を聞いてもらうだけでも気持ちが楽になることがあります。
また、同じ病気を抱える患者会などに参加し、悩みを分かち合うことも有効で、趣味や運動など治療以外のことに目を向け、生きがいを見つけることも、心の健康を保つ上で重要です。
心理的負担を軽減するためのヒント
- 信頼できる医療スタッフに気持ちを話す
- 家族や友人に理解を求める
- 患者会などで仲間を見つける
- 治療以外の楽しみや目標を持つ
- 必要であれば専門家の助けを借りる
専門家によるカウンセリングや精神科医療
不安や抑うつが強く、日常生活に支障をきたすような場合には、専門家の助けを借りることも一つの選択肢です。多くの透析施設では、臨床心理士や精神保健福祉士、医療ソーシャルワーカーなどが相談に応じています。
また、必要に応じて精神科や心療内科と連携し、カウンセリングや薬物療法(抗不安薬、抗うつ薬など)を行うこともあります。心のケアも、透析治療の重要な一環です。
透析困難症に対する包括的な治療戦略
透析困難症は、一つの原因を解決すれば良いというものではなく、多角的な視点からのアプローチが必要です。
医師、看護師、臨床工学技士などから成る医療チームが、患者さん一人ひとりの状況を総合的に評価し、個別化された治療計画を立てていくことが求められます。
多職種チームによるアプローチ
透析困難症の治療は、一人の医師だけで完結するものではありません。医師、看護師、臨床工学技士、管理栄養士、薬剤師、医療ソーシャルワーカーといった多くの専門職が、それぞれの専門性を活かして患者さんを支えるチーム医療が基本です。
定期的にカンファレンスを開き、患者さんの情報を共有し、治療方針について議論することで、最善の治療を目指します。
透析チームの各専門職の役割
| 専門職 | 主な役割 |
|---|---|
| 医師 | 治療方針の決定、合併症の管理、全体的な医学的管理 |
| 看護師 | 全身状態の観察、穿刺、精神的ケア、自己管理の指導 |
| 臨床工学技士 | 透析装置の操作・保守、バスキュラーアクセスの管理、水質管理 |
個別化された治療計画の立案
治療は、まず透析困難に陥っている原因を正確に特定することから始まります。詳細な問診や診察、各種検査を通じて原因を探り、それに基づいて個別化された治療計画を立案します。
その際には、医学的な正しさだけでなく、患者さんの年齢、合併症、生活背景、そして何を大切にしたいかという価値観を尊重することが重要です。
代替療法や新しい治療法の検討
現在の血液透析がどうしても困難な場合には、他の腎代替療法を検討することもあります。自宅で行う在宅血液透析(HHD)や、お腹に透析液を入れて行う腹膜透析(PD)は、通院の負担を軽減できる可能性があります。
また、条件が合えば腎移植という選択肢もあります。それぞれの治療法には利点と欠点があるため、十分に情報提供を受けた上で、自分に合った治療法を選択することが大切です。
血液透析以外の腎代替療法
| 治療法 | 概要 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 腹膜透析 (PD) | 自身の腹膜を利用して、自宅で透析液の交換を行う。 | 通院は月1~2回。残存腎機能が保たれやすい。自己管理が重要。 |
| 在宅血液透析 (HHD) | 自宅に透析装置を設置し、自分や家族が操作して透析を行う。 | 時間や頻度を自由に設定でき、十分な透析量を確保しやすい。介助者が必要。 |
| 腎移植 | 亡くなった方や親族から提供された腎臓を移植する外科手術。 | 成功すれば透析から離脱できる。免疫抑制剤の生涯服用が必要。 |
患者自身の治療への積極的な参加
透析困難症を克服するためには、患者さん自身が治療の主役であるという意識を持つことが何よりも重要です。自分の体の変化や、治療中に感じたことを、遠慮せずに医療スタッフに伝えることが、問題の早期発見につながります。
また、提示された治療の選択肢について、目的や内容をよく理解し、自分の希望を伝え、方針決定に主体的に関わっていくことが、納得のいく治療を受けるための鍵です。
治療に積極的に参加するためのポイント
- 自分の状態や気持ちを正確に伝える
- 分からないことは遠慮せずに質問する
- 治療の目標をスタッフと共有する
- 日々の体重測定や食事管理を継続する
よくある質問(Q&A)
最後に、透析困難症に関して多くの方が抱く疑問について、Q&A形式で分かりやすくお答えします。
- 透析が辛いときは休んでも良いですか
-
透析治療が辛いと感じるお気持ちはよく分かりますが、自己判断で透析を休むことは絶対に避けてください。
透析を1回休むだけでも、体内に余分な水分や老廃物が溜まり、心不全や高カリウム血症といった命に関わる状態を引き起こす危険があります。どうしても辛い場合は、治療を中断する前に、必ず医師や看護師に相談してください。
- シャントが使えなくなったらどうなりますか
-
シャントが完全に閉塞して使えなくなった場合でも、治療を諦める必要はありません。まずはPTAや外科手術による修復を試み、それが難しい場合でも、腕の別の場所や足などに、新たなシャントを作成することが可能です。
また、次のシャントが使えるようになるまでの間や、シャント作成が困難な場合には、長期留置カテーテルを用いて透析を継続します。シャントを長持ちさせるためにも、日々の自己管理と定期的なメンテナンスが重要です。
- ドライウェイトはどのように決めるのですか
-
ドライウェイト(透析後の目標体重)は、透析治療における最も重要な指標の一つです。これは、体内に余分な水分がない、いわば「からだの一番軽い状態」の体重を指します。
胸部レントゲン写真での心臓の大きさ(心胸郭比)、心エコー検査での血管内の水分量、体組成分析装置による体水分量の測定結果、血圧やむくみの有無などを評価して、個々の患者さんに合ったドライウェイトを決定します。
これは固定的なものではなく、体調や食事内容によって変動するため、定期的に見直しを行います。
- 治療法を変更することは可能ですか
-
現在の血液透析で解決が難しい問題がある場合や、ご自身のライフスタイルの変化に合わせて、他の治療法へ変更することを検討できます。
通院が負担であれば腹膜透析や在宅血液透析、より良い生命予後や生活の質を望むのであれば腎移植といった選択肢があります。ただし、どの治療法にも利点と欠点があり、医学的な適応(その治療法が可能かどうか)もあります。
治療法の変更を希望する場合は、まずは主治医に相談し、それぞれの選択肢について詳しい説明を受け、ご家族とも十分に話し合った上で決定することが大切です。
以上
透析センター(人工透析) | 大垣中央病院(医療法人社団豊正会 )
参考文献
Sato T, Sakurai H, Okubo K, Kusuta R, Onogi T, Tsuboi M. Current state of dialysis treatment and vascular access management in Japan. The journal of vascular access. 2019 May;20(1_suppl):10-4.
Ozeki T, Shimizu H, Fujita Y, Inaguma D, Maruyama S, Ohyama Y, Minatoguchi S, Murai Y, Terashita M, Tagaya T. The type of vascular access and the incidence of mortality in Japanese dialysis patients. Internal Medicine. 2017 Mar 1;56(5):481-5.
Murakami M, Fujii N, Kanda E, Kikuchi K, Wada A, Hamano T, Masakane I. Association of four types of vascular access including arterial superficialization with mortality in maintenance hemodialysis patients: a nationwide cohort study in Japan. American journal of nephrology. 2023 Jul 11;54(3-4):83-94.
Nakagawa Y, Ota K, Sato Y, Fuchinoue S, Teraoka S, Agishi T. Complications in blood access for hemodialysis. Artificial Organs. 1994 Apr;18(4):283-8.
Yoshida M, Doi S, Nakashima A, Kyuden Y, Kawai T, Kawaoka K, Takahashi S, Ueno T, Nishizawa Y, Masaki T. Different risk factors are associated with vascular access patency after construction and percutaneous transluminal angioplasty in patients starting hemodialysis. The Journal of Vascular Access. 2021 Sep;22(5):707-15.
Rayner HC, Besarab A, Brown WW, Disney A, Saito A, Pisoni RL. Vascular access results from the dialysis outcomes and practice patterns study (DOPPS): performance against kidney disease outcomes quality initiative (K/DOQI) clinical practice guidelines. American journal of kidney diseases. 2004 Nov 1;44:22-6.
Ethier J, Mendelssohn DC, Elder SJ, Hasegawa T, Akizawa T, Akiba T, Canaud BJ, Pisoni RL. Vascular access use and outcomes: an international perspective from the Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study. Nephrology Dialysis Transplantation. 2008 Oct 1;23(10):3219-26.
Kuramochi G, Ohara N, Hasegawa S, Moro H. Femoral arteriovenous fistula: a complication of temporary hemodialysis catheter placement. Journal of Artificial Organs. 2006 Jun;9(2):114-7.
Asano M, Thumma J, Oguchi K, Pisoni RL, Akizawa T, Akiba T, Fukuhara S, Kurokawa K, Ethier J, Saran R, Saito A. Vascular access care and treatment practices associated with outcomes of arteriovenous fistula: international comparisons from the Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study. Nephron Clinical Practice. 2013 Sep 12;124(1-2):23-30.
Furukawa H. Surgical management of vascular access related aneurysms to salvage dialysis access: case report and a systematic review of the literature. The journal of vascular access. 2015 Mar;16(2):120-5.