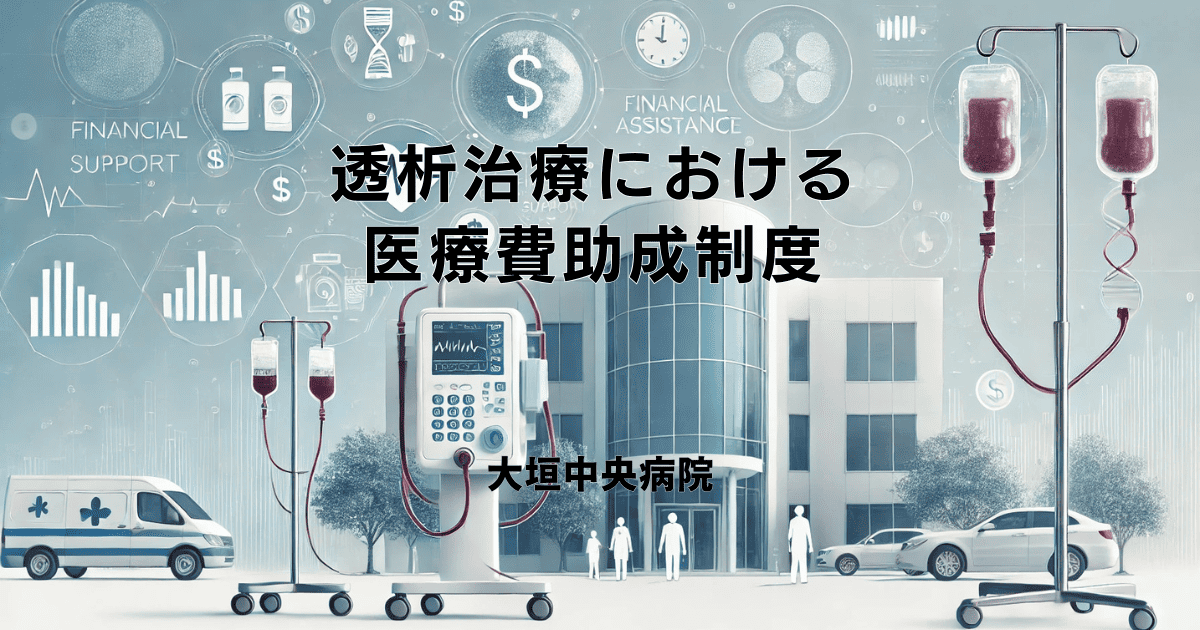慢性腎臓病から移行する透析治療は、患者さんの身体的・経済的な負担が大きい治療のひとつです。高齢の方は、病状の変化や生活環境の事情によって通院が難しくなるなどの事情が加わり、医療費も膨らむ傾向があります。
そのため医療費助成制度や公的支援を活用することが大切です。
本稿では、各年齢層への透析治療の影響や医療費負担の軽減策、人工透析費用65歳以上・人工透析費用70歳以上・人工透析費用75歳以上の方にも適用できる助成制度、公費15透析などの制度活用ポイントをまとめ、透析治療に臨む高齢者の方が利用しやすい仕組みを詳しく解説します。
透析治療の概要と高齢者への影響
人工腎臓機器を用いる透析治療は、腎臓の機能が著しく低下したときに導入する方法です。高齢者の場合は複数の持病を抱えることが多く、透析治療が生活の大半を占めるリスクがあります。
そこで医療費助成制度を知り、必要な準備を進めておくことが重要です。
透析治療が必要になる原因と過程
慢性腎臓病が悪化し、体内の老廃物を排泄できなくなると、症状進行に応じて人工透析を考慮する段階に至ります。日本においては糖尿病性腎症や高血圧性腎硬化症などが透析導入の主な原因とされています。
特に高齢になると、循環器疾患や他の臓器の合併症が重なる可能性が高く、経過中にさまざまな治療が必要です。
週に複数回必要となる透析の負担
透析治療は週に数回受ける必要があり、それぞれ数時間程度を要します。高齢者の方は通院や移動自体が負担になりやすく、自宅・施設からの送迎サービスの利用を考慮するケースも多いです。
医療保険の枠組みで負担する通院交通費は制度上の支援が受けにくいため、透析に伴う医療費とあわせてしっかりと計画を立てることが必要です。
高齢者における身体面・精神面の注意点
高齢になるほど、下記のように治療へ影響を与える要素が増えてきます。
- 複数の合併症による体力の低下
- 食事・運動制限の遵守が難しくなる場合
- 家族の介助が必要な場面が増える
- 精神的な負担が大きくなる
特に透析治療は長期間継続する可能性が高く、高齢者にとって生活全体の見直しを迫られる場合もあります。このような負担を和らげるために、公的助成制度を適切に利用することが欠かせません。
高齢者への影響を踏まえた受診タイミング
高齢になると、病状の進行が緩やかでも生活機能への影響は顕著になることがあります。腎臓専門医による定期的なチェックを怠らず、重症化を防ぐ工夫がポイントです。
人工透析費用65歳以上や人工透析費用70歳以上の方は家計負担が増えやすいため、症状の早期発見・治療の選択肢を検討するタイミングが早い段階で必要になるケースも珍しくありません。
高齢者に多い透析治療導入のきっかけ
| きっかけ | 内容 |
|---|---|
| 糖尿病性腎症 | 高齢者でも糖尿病が長引くと腎機能が悪化しやすい |
| 高血圧性腎硬化症 | 長年の高血圧が原因で腎臓の血管が硬化し機能低下 |
| 動脈硬化による血流障害 | 腎臓への血流不足による組織ダメージが蓄積 |
| 蛋白尿のコントロール不良 | 蛋白尿が続くと慢性腎臓病が重症化しやすい |
| 薬剤性腎障害 | 高齢者は複数の薬を飲む機会が多く、相互作用による腎機能低下に注意が必要 |
公費助成制度の基本
医療保険制度のもとで受けられる透析治療は、公的助成制度を組み合わせることで経済的負担を大きく減らすことができます。特に腎不全に対する透析は長期化することが多いため、負担軽減策の理解がカギになります。
健康保険と高額療養費制度
透析治療では健康保険による給付が基本です。自己負担割合は年齢や収入状況に応じて変わります。医療費が高額になった場合、一定額以上の自己負担を減らす高額療養費制度を利用するケースが多いです。
高齢の方ほど通院回数が多くなりがちなので、医療費上限が設定されるこの仕組みを把握しておくことが大切です。
自治体単位の医療費助成
自治体ごとに運営される医療費助成制度は、収入や重症度などの条件によって支給要件が異なります。透析治療は慢性的な通院と医薬品費用がかかるため、自治体が行う独自の助成を活用できると家計負担を大きく下げることにつながります。
例えば交通費補助や介護保険との連携支援などが代表的です。
障害年金との併用
人工透析は障害者手帳の交付や障害年金給付の対象になり得ます。透析導入時点で身体障害者手帳を取得できれば、経済的支援だけでなく社会福祉サービスの活用も検討できます。
申請手続きには医師の診断書や複数の書類が必要であり、時間がかかる場合もあるので早めに準備を進めることが望ましいです。
慢性腎不全患者が知っておきたい手続き
透析導入に際し、初回から公費助成を活用するために必要な手続きが複数あります。支給要件に合致するかを確認し、主治医と相談しながら申請書類を作成することが一般的です。
手帳や制度の枠組みを使った医療費軽減策は、事前の準備でスムーズに進められます。
公費助成にまつわる基本項目まとめ
| 項目 | 概要 | 備考 |
|---|---|---|
| 高額療養費制度 | 月々の自己負担上限を設け、超過分を払い戻す | 所得区分や年齢で上限額が変動 |
| 自治体独自の助成 | 交通費補助や医療費減免など | お住まいの地域で条件が異なる |
| 障害者手帳・障害年金 | 身体障害者として認定されることで経済的支援が拡充 | 人工透析導入で対象になるケース多 |
| 医療費控除 | 医療費の自己負担分を所得税から控除 | 年末調整や確定申告で手続き |
各年齢層における助成制度
年齢によって保険制度上の負担割合が異なるため、人工透析費用65歳以上や人工透析費用70歳以上の方を含む各年代で活用できる助成制度の特徴を確認することが重要です。
年齢ごとの制度の違いを理解しておくと、負担を最小限に抑えられる可能性が高まります。
65歳未満との違い
65歳未満の方は一般的に現役世代として扱われ、健康保険での自己負担割合は3割が中心です。高額療養費制度を使う場合、所得により月の自己負担上限が大きく変わります。
一方で65歳を超えると、段階的に制度の取り扱いが変化します。
人工透析費用65歳以上の助成
65歳を超えてから透析治療を導入する場合、病状や障害認定の程度に応じて公的な支援の幅が広がります。
人工透析費用65歳以上の方は、健康保険の自己負担割合や各種補助が拡充されるケースが多く、要介護認定や障害者手帳との併用も考えられます。
人工透析費用70歳以上になると拡がる選択肢
70歳を超えると医療保険は後期高齢者医療制度へ移行するか、各種公費助成をさらに活用できるタイミングが訪れます。
人工透析費用70歳以上の方は、後期高齢者医療への切り替えが発生したときの負担割合や、別途利用可能な自治体助成の有無などを確認する必要があります。
人工透析費用75歳以上での留意点
75歳になると後期高齢者医療制度の対象となります。
人工透析費用75歳以上の方にとって後期高齢者医療制度は、自己負担割合の軽減効果が大きい仕組みですが、加入時期の手続きや保険料の負担など、年齢到達のタイミングに合わせて見直す点が増えます。
年齢別の自己負担割合と注意点
| 年齢帯 | 主な医療保険 | 自己負担割合 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 65歳未満 | 健康保険 (国保/社保) | 原則3割 | 所得によって高額療養費制度の上限が変動 |
| 65歳以上~70歳未満 | 健康保険または退職者医療 | 原則2割~3割 | 退職後の保険切り替えや障害認定の取得によって負担軽減が可能 |
| 70歳以上~75歳未満 | 後期高齢者医療への移行時期 | 原則2割 | 所得が一定額以上の方は3割負担になる場合もある |
| 75歳以上 | 後期高齢者医療 | 原則1割 (2割) | 所得に応じて負担割合が変わる。公費助成との併用でさらに負担軽減可能 |
後期高齢者の助成制度
人工透析費用後期高齢者の方は、既に複数の慢性疾患を抱えていることが多く、医療費の増大につながりやすい状況です。
後期高齢者医療制度には自己負担割合を抑える仕組みがあり、さらに自治体独自の助成と組み合わせることで経済的負担を低減できます。
後期高齢者医療制度の特徴
75歳以上になると原則として後期高齢者医療制度に加入し、自己負担は1割または2割になります。ただし一定以上の所得がある場合は3割負担となるため、収入状況により差が出る点に注意が必要です。
透析など長期間にわたる医療費がかかる治療を受けるときは、高額療養費制度をあわせて確認してください。
自己負担額が軽減される仕組み
後期高齢者医療制度の自己負担額が低く設定されている一方、高額療養費制度や各種公費助成によってさらに支出を抑えられます。
通院交通費を支援する制度がある自治体もあるので、重い通院負担が想定される方は対応可能なサービスを探してみるとよいでしょう。
要介護認定・障害者手帳と合わせた活用
後期高齢者の場合、要介護認定が降りているケースも少なくありません。その場合、介護保険サービスとの連携によって通院支援が受けられる可能性があります。
また透析治療で障害者手帳を取得すれば、各種手当や税制上の優遇を受けることも考えられます。
後期高齢者における支援制度の具体例
| 制度・支援名 | 内容 | 手続き上のポイント |
|---|---|---|
| 後期高齢者医療制度 | 医療費負担割合が1割または2割 | 所得状況により3割負担になる場合あり |
| 介護保険サービス | デイサービスやヘルパー利用など | 要介護認定が必要 |
| 身体障害者手帳 | 交通機関や税制の優遇などがある | 透析導入で取得できるか医師と相談が必要 |
| 自治体独自の助成 | 交通費など間接的負担の軽減 | 自治体窓口での申請に書類が必要になること多い |
公費15透析の活用
慢性腎不全での人工透析治療を受ける方は、公費15透析という制度を聞いたことがあるかもしれません。これは特定疾患医療費助成制度の中で認められるもので、経済的負担の軽減を狙う上で知っておきたい内容です。
公費15透析とは
公費15透析は、いわゆる特定疾患(特定医療費助成)の対象疾病に該当する場合に、自己負担を一定額に抑える制度です。
都道府県や政令指定都市などの自治体によって細かい要件が設定され、年齢や所得に応じて適用範囲や負担限度額が異なることがあります。
申請条件と必要書類
公費15透析を申請する際は、医師の診断書や本人の所得証明を含む複数の書類が必要になります。提出窓口は自治体の担当部署ですが、申請時期や更新手続きの締め切りが設定されていることも多いので注意が必要です。
治療開始の時点で主治医やソーシャルワーカーに相談するとスムーズです。
他の助成制度との併用
公費15透析は高額療養費制度や後期高齢者医療制度などと併用が可能です。公的支援をフル活用することで自己負担を大幅に軽減できる場合があります。
ただし併用の際には、主治医の意見書や自治体の審査が必要になることもあるので、余裕をもって手続きを行うと安心です。
公費15透析に向けた注意点
公費15透析は大きな経済的メリットがありますが、受給対象となるのは指定されている疾患に限られます。対象外の場合は他の制度を検討する必要があります。
また年齢や所得額の変化により負担割合が変動するため、状況に応じて継続的に見直すことが望ましいです。
公費15透析と他制度の併用パターン
| 制度名 | 併用の有無 | ポイント |
|---|---|---|
| 高額療養費制度 | 併用可能 | 月々の自己負担上限をさらに抑えられる |
| 後期高齢者医療制度 | 併用可能 | 後期高齢者の自己負担割合を基礎に負担軽減が効く |
| 自治体独自の交通費助成 | 併用可能 | 通院負担の軽減に役立つ |
| 身体障害者手帳の取得 | 併用可能 | 税制上の優遇や公共料金の減免などが期待できる |
| 障害年金 | 併用には要確認 | 障害等級など条件を満たす必要がある |
負担軽減のためのポイント
透析治療は長期にわたることが多く、高齢になるほど治療に伴う経済的・身体的負担が増えやすいです。医療費助成制度を含めた多角的な対策を考え、負担を減らす工夫が大切です。
後回しにしない書類準備
助成制度の申請は複数の書類が必要なことが多く、取得に時間がかかる場合があります。主治医やソーシャルワーカーと相談しながら早めに準備を始めると、導入直後から負担軽減を受けられます。
制度を複数組み合わせるメリット
後期高齢者医療制度と高額療養費制度、公費15透析などをうまく組み合わせると、自己負担を最小限に抑えることが可能です。高齢の方ほど介護保険サービスや障害者手帳の活用といった選択肢も広がり、生活全体の負担軽減が実現しやすくなります。
助成制度を上手に併用する要点
- 申請に必要な書類を整理しておく
- 主治医や自治体担当者との連携をこまめにとる
- 更新や申請時期をカレンダーにメモしておく
- 所得や家族状況の変化に応じて再度手続きを検討する
負担を増やさない生活習慣
透析治療の負担を軽くするうえで、病状の進行を抑える日頃のケアも欠かせません。適切な食事管理や運動、検査スケジュールの遵守によって、合併症リスクを下げられる場合があります。
経済的な面でも、病状悪化に伴う入院回数を減らせると、トータルの支出を抑えられる可能性があります。
家族・周囲とのコミュニケーション
高齢者は自己判断だけでは対応しきれない場面が出てきます。家族や介護者、主治医とのコミュニケーションによって、日常生活のサポートを得られれば治療継続が楽になるでしょう。
金銭面でも、家族が情報収集や申請書類の取り寄せを代行してくれると、スムーズに手続きを進められます。
維持期に意識したい生活管理
| 項目 | 留意点 | 効果 |
|---|---|---|
| 食事療法 | 塩分・たんぱく質・カリウムのバランスを保つ | 合併症の予防、電解質異常のコントロール |
| 適度な運動 | 血流改善や筋力維持 | 透析効率の向上、日常生活動作の維持 |
| 体重管理 | 過度な肥満や過度な痩せを防ぐ | 心血管系リスク軽減、感染症リスクの低下 |
| 定期受診と検査 | 透析効率や血液データを確かめ治療方針を確認 | 病状の悪化を防ぎ、緊急入院リスクを下げられる |
受診・手続きの流れ
実際に透析治療を受けるまでには、医療機関の選定から書類申請まで複数の手順があります。高齢者の場合は手続きが複雑になりがちなので、一連の流れを把握しておくと安心です。
腎臓専門医の診断と治療方針
透析が必要かどうかの判断は腎臓専門医による診断が基準になります。定期的な血液検査やエコー検査などによって腎機能を確認し、透析の導入が必要と判断された段階で治療方針が具体化されます。
高齢者は合併症を考慮しながら治療計画を立てることが大切です。
病院選びと通院体制
透析に対応している病院・クリニックの設備やスタッフの専門性を確認し、通院のしやすさや送迎の有無などを考慮して医療機関を選びます。
自宅近くや施設近くで受診できるかどうかは、日常生活への影響を左右する重要な要素です。
病院・クリニックを探す際の観点
- 自宅や施設からの距離
- 送迎サービスの提供の有無
- 透析室の設備(ベッド数や看護体制など)
- ソーシャルワーカーや医療相談員の配置
医療費助成制度の申請と受給
透析導入が決まったら、健康保険の確認や高額療養費制度・公費15透析などの適用可能性を検討します。申請書類の作成や医師の診断書の取得が必要になり、手続きにはある程度の日数を要する場合もあります。
後期高齢者医療制度への切り替え時期にも注意が必要です。
透析開始後の定期フォロー
透析治療を開始した後は、週に複数回の通院で血液浄化を行います。治療の合間に医師や看護師と相談して、病状の変化や助成制度の更新手続きが必要かどうかを確認してください。
高齢者の場合は、身体機能の維持のためにリハビリや栄養指導なども受けることが多くあります。
受診・手続きでつまずきやすい点
| 項目 | よくある状況 | 対応策 |
|---|---|---|
| 健康保険の変更時期 | 退職後の国保切り替えや後期高齢者移行 | 保険証の期限や更新手続きを早めに把握して準備 |
| 障害認定のタイミング | 診断書取得に時間がかかる | 主治医やソーシャルワーカーと相談し、早めに書類作成に取り掛かる |
| 公費助成の申請忘れ | 制度を知らないまま自己負担を続ける | 必要書類のリストを作成し、段取りよく申請 |
| 通院や送迎手段の確保 | 移動手段がない、費用が嵩む | デイケアや介護保険の訪問系サービスなども視野に入れる |
よくある質問
透析治療を検討する際や受け始めてからは、多くの疑問が生じます。高齢者やそのご家族が気になる代表的な質問をまとめます。
- 申請書類が多くて混乱しそうだがどうすればよいか
-
医療機関のソーシャルワーカーや各自治体の担当窓口に相談すると、必要書類や申請の進め方を整理できます。
診断書の作成には時間がかかる場合があるため、受診や治療方針が決まった段階で早めに準備を始めることをおすすめします。
- 障害者手帳を取得するメリットは大きいのか
-
障害者手帳を取得すると、多彩な福祉サービスの対象になったり、税の減免や交通費の割引が受けられたりします。人工透析の導入が決まった時点で、医師と相談しながら取得の可能性を検討してください。
所得状況や家族構成によって適用範囲が違う点に注意が必要です。
- 後期高齢者医療制度に移行すると、どれくらい負担が減るのか
-
後期高齢者医療制度の自己負担割合は原則1割または2割で、一定以上の所得がある場合のみ3割になります。併せて高額療養費制度や公費15透析などを利用することで自己負担を抑えられるケースが多いです。
ただし保険料や各種要件もあるため、移行時期に詳細を確認すると安心です。
- 一度導入した公的助成制度はずっと使えるのか
-
公的助成制度は年齢や所得、病状の変化などに伴い、更新手続きが求められる場合があります。
更新を怠ると助成が打ち切られる可能性があるので、提出期限や必要書類を把握し、計画的に準備を進める必要があります。
以上
透析センター(人工透析) | 大垣中央病院(医療法人社団豊正会 )
参考文献
VANHOLDER, Raymond, et al. Reducing the costs of chronic kidney disease while delivering quality health care: a call to action. Nature Reviews Nephrology, 2017, 13.7: 393-409.
LAMPING, Donna L., et al. Clinical outcomes, quality of life, and costs in the North Thames Dialysis Study of elderly people on dialysis: a prospective cohort study. The Lancet, 2000, 356.9241: 1543-1550.
BLACK, C., et al. Early referral strategies for management of people with markers of renal disease: a systematic review of the evidence of clinical effectiveness, costeffectiveness and economic analysis. Health Technology Assessment, 2010, 14.21: 1-184.
HIMMELFARB, Jonathan, et al. The current and future landscape of dialysis. Nature Reviews Nephrology, 2020, 16.10: 573-585.
WONG, Susan PY; KREUTER, William; O’HARE, Ann M. Treatment intensity at the end of life in older adults receiving long-term dialysis. Archives of internal medicine, 2012, 172.8: 661-663.
MORTON, Rachael L., et al. Factors influencing patient choice of dialysis versus conservative care to treat end-stage kidney disease. Cmaj, 2012, 184.5: E277-E283.
WANG, Virginia, et al. The economic burden of chronic kidney disease and end-stage renal disease. In: Seminars in nephrology. WB Saunders, 2016. p. 319-330.
LIU, Frank Xiaoqing, et al. A global overview of the impact of peritoneal dialysis first or favored policies: an opinion. Peritoneal Dialysis International, 2015, 35.4: 406-420.
MOHNEN, Sigrid M., et al. Healthcare costs of patients on different renal replacement modalities–analysis of Dutch health insurance claims data. PLoS One, 2019, 14.8: e0220800.
COOK, Wendy L., et al. Falls and fall-related injuries in older dialysis patients. Clinical journal of the American Society of Nephrology, 2006, 1.6: 1197-1204.