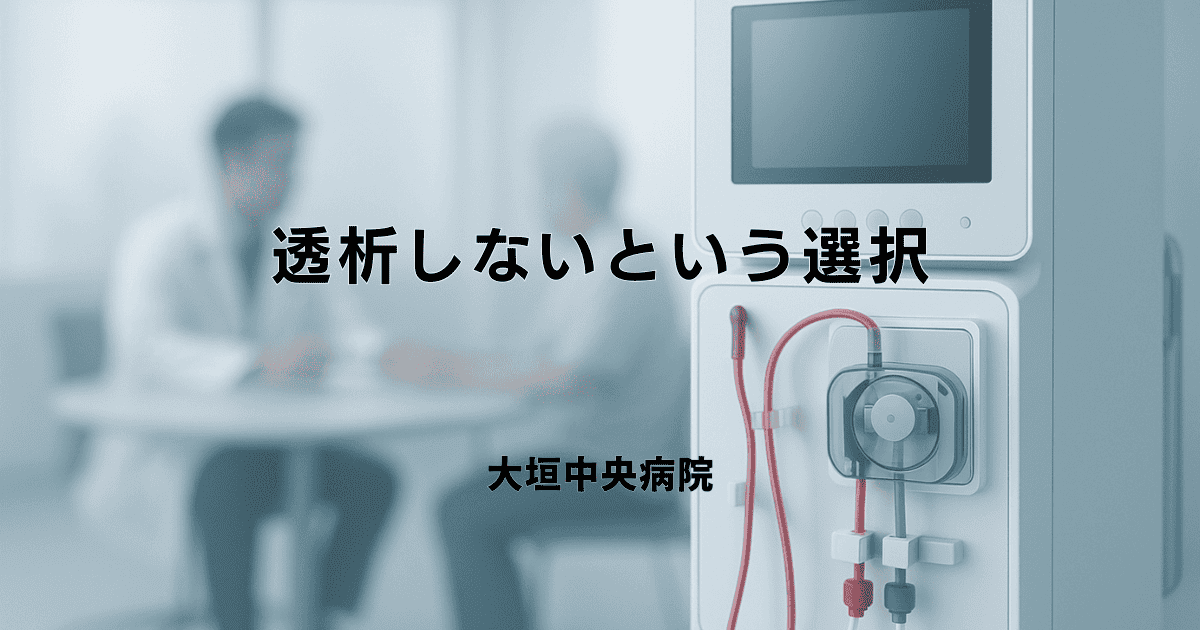腎臓の機能が著しく低下した末期腎不全の治療法として、透析療法は広く知られています。しかし、さまざまな理由から「透析をしない」という選択を考える方や、そのご家族もいらっしゃいます。
この記事では、透析をしないという選択肢について、その理由、透析をしなかった場合にどのような経過をたどるのか、そしてその過程で考えられることや大切なことについて、できる限り分かりやすく解説します。
透析治療の基本
まず、「透析しない」という選択を考える上で、透析治療そのものについて正しく理解することが大切です。ここでは、腎臓の働きから透析治療の目的、種類、開始の目安について解説します。
腎臓の重要な役割と機能が低下するとどうなるか
腎臓は、私たちの体の中で生命維持に必要ないくつかの重要な働きを担っています。主な役割は、血液をろ過して老廃物や余分な水分を尿として排泄することです。
また、体内の水分量や電解質(ナトリウム、カリウム、カルシウムなど)のバランスを調整したり、血圧をコントロールするホルモンや、赤血球を作るホルモンを分泌したりもします。
さまざまな原因で腎臓の機能が低下し、これらの働きが十分にできなくなると、体内に老廃物や余分な水分が溜まり、尿毒症と呼ばれる状態になります。
尿毒症が進行すると、吐き気、食欲不振、全身の倦怠感、むくみ、呼吸困難、意識障害など、さまざまな症状が現れ、生命に危険が及ぶこともあります。
腎臓の主な働き
| 働き | 内容 | 機能低下時の影響例 |
|---|---|---|
| 老廃物の排泄 | 血液中の不要物を尿として捨てる | 尿毒症(吐き気、倦怠感) |
| 水分・電解質の調整 | 体内の水分量やミネラルバランスを保つ | むくみ、高カリウム血症 |
| ホルモンの産生 | 血圧調整、造血に関わるホルモンを作る | 高血圧、貧血 |
透析治療の目的と主な種類
透析治療は、機能しなくなった腎臓の代わりに、血液中の老廃物や余分な水分を取り除き、電解質のバランスを整える治療法です。これにより、尿毒症の症状を改善し、生命を維持することを目指します。
透析治療には、主に「血液透析」と「腹膜透析」の2つの種類があります。
血液透析は、腕の血管に針を刺し、血液を体外に取り出して透析器(ダイアライザー)に通し、浄化した血液を再び体内に戻す方法です。通常、週に2~3回、1回あたり4~5時間程度、医療機関に通院して行います。
一方、腹膜透析は、お腹の中にカテーテルという管を埋め込み、その管を通して透析液を腹腔内に入れ、一定時間溜めておくことで、自身の腹膜を利用して血液を浄化する方法です。
透析液の交換は、自宅や職場などで患者さん自身やご家族が行います。
血液透析と腹膜透析の比較
| 項目 | 血液透析 | 腹膜透析 |
|---|---|---|
| 治療場所 | 主に医療機関 | 主に自宅 |
| 治療頻度・時間 | 週2~3回、1回4~5時間程度 | 毎日、1日数回の透析液交換 |
| 生活への影響 | 通院が必要、食事・水分管理が比較的厳しい | 通院は月1~2回程度、比較的自由度が高い |
透析治療を開始する一般的な目安
透析治療を開始する時期は、腎機能の低下の程度、尿毒症の症状、全身状態などを総合的に判断して決定します。
一般的には、腎機能の指標であるeGFR(推算糸球体ろ過量)が15 mL/min/1.73m²未満になると末期腎不全と診断され、透析導入が検討され始めます。eGFRが6 mL/min/1.73m²未満になると、多くの場合で透析治療が必要と判断されます。
ただし、これらの数値はあくまで目安であり、症状の強さや合併症の有無、患者さんの生活状況や希望なども考慮して、医師と患者さんが十分に話し合って開始時期を決定します。
例えば、eGFRがまだそれほど低くなくても、尿毒症による強い症状(重度のむくみ、呼吸困難、コントロールできない高カリウム血症など)がある場合には、早期に透析を開始することもあります。
透析治療の一般的な効果と限界
透析治療は、末期腎不全の患者さんにとって生命を維持するための重要な治療法です。適切に行うことで、尿毒症の症状を軽減し、体調を改善させ、社会生活を送ることも可能になります。
しかし、透析治療は失われた腎機能を完全に代替するものではありません。健康な腎臓が24時間休まず働いているのに対し、血液透析は週に十数時間程度しか行われません。
そのため、食事制限や水分制限が必要になることが多く、合併症(心血管疾患、感染症、骨の病気など)のリスクも依然として残ります。また、治療に伴う時間的拘束や身体的負担、精神的なストレスを感じる方も少なくありません。
透析治療のメリットとデメリットをよく理解することが大切です。
「透析しない」という選択肢が考えられる背景
透析治療は生命維持に貢献する一方で、さまざまな理由から「透析をしない」という選択を考える方もいます。ここでは、その背景にある主な理由や状況について説明します。
患者さんご自身の価値観や人生観
最も大きな理由の一つは、患者さんご自身の価値観や人生観です。
「できる限り自然な形で最期を迎えたい」「延命よりも残された時間の質を重視したい」「これ以上つらい治療は受けたくない」といった思いから、透析を希望しないことがあります。
特に高齢の患者さんの中には、これまでの人生に満足し、積極的な延命治療よりも穏やかな終末期を望む方がいらっしゃいます。ご自身の死生観や、どのように生きたいかという主体的な意思が、この選択の根底にあることが多いです。
高齢や多くの併存疾患による影響
高齢であることや、心臓病、糖尿病、がんなど、腎不全以外にも多くの病気(併存疾患)を抱えている場合、透析治療そのものが体に大きな負担となることがあります。
透析治療によって体調が改善するよりも、むしろ合併症のリスクが高まったり、生活の質(QOL)が低下したりする可能性が懸念される場合です。
また、認知症が進行している場合、透析治療の必要性を理解したり、自己管理を行ったりすることが難しく、治療の継続が困難になることもあります。
高齢者における透析導入の検討事項
| 検討事項 | 内容 |
|---|---|
| 全身状態・予後 | 透析による生命予後の改善が見込めるか |
| 認知機能 | 治療の理解や自己管理が可能か |
| 生活の質(QOL) | 透析によってQOLが維持・向上するか |
治療に伴う身体的・精神的負担
血液透析の場合、週に数回の通院が必要であり、1回数時間の治療中はじっとしていなければなりません。
シャント(透析を行うための血管)の管理や、透析中の血圧低下、不均衡症候群(頭痛、吐き気など)といった身体的な苦痛を伴うこともあります。
腹膜透析の場合でも、毎日の透析液交換の手間や、カテーテル管理、腹膜炎のリスクなどがあります。これらの身体的負担に加えて、食事制限や水分制限、将来への不安などから、精神的に大きなストレスを感じる方も少なくありません。
こうした負担が耐え難いと感じ、透析をしない選択を考えることがあります。
ご家族の状況やサポート体制
透析治療を続けるためには、ご家族の理解とサポートが重要になる場合があります。特に、通院の送迎や、在宅での腹膜透析の介助、食事管理の協力などが必要になることがあります。
しかし、ご家族が高齢であったり、遠方に住んでいたり、仕事で忙しかったりすると、十分なサポートが得られないこともあります。また、経済的な負担も考慮すべき点です。
こうしたご家族の状況やサポート体制の限界から、透析治療の継続が難しいと判断し、透析をしないという選択に至るケースもあります。
透析をしない場合に考えられること 医学的な側面
透析治療を受けないという選択をした場合、腎機能の低下は進行し、体にさまざまな変化が現れます。ここでは、医学的な観点から、透析をしない場合にどのようなことが起こりうるのかを説明します。
尿毒症の進行と現れる主な症状
腎臓の機能が低下すると、体内に老廃物や毒素が蓄積し、尿毒症という状態になります。透析をしない場合、この尿毒症は進行し続けます。初期には、食欲不振、吐き気、嘔吐、全身の倦怠感、皮膚のかゆみなどが現れます。
進行すると、意識障害(ぼんやりする、眠りがちになる)、けいれん、呼吸困難、出血傾向(鼻血が出やすい、あざができやすい)など、より重篤な症状が現れるようになります。最終的には、昏睡状態に至ることもあります。
尿毒症の進行に伴う症状の変化
| 進行度 | 主な症状 |
|---|---|
| 初期 | 食欲不振、吐き気、倦怠感、かゆみ |
| 中期 | むくみ、息切れ、貧血、集中力低下 |
| 末期 | 意識障害、けいれん、呼吸困難、出血傾向 |
体液貯留による影響(むくみ、呼吸困難など)
腎臓の重要な働きのひとつに、体内の余分な水分を尿として排泄することがあります。腎機能が低下し、尿量が減ってくると、体内に水分が溜まりやすくなります。これにより、手足や顔にむくみ(浮腫)が現れます。
さらに水分が溜まると、肺に水が溜まる肺水腫という状態になり、息苦しさや呼吸困難を引き起こします。横になると呼吸が苦しくなり、座っている方が楽になる「起座呼吸」という特徴的な症状が見られることもあります。
心臓にも負担がかかり、心不全が悪化することもあります。
電解質異常のリスクと症状
腎臓は、血液中の電解質(ナトリウム、カリウム、カルシウム、リンなど)のバランスを調整する役割も担っています。透析をしない場合、これらの電解質のバランスが崩れやすくなります。
特に危険なのは、カリウム値の上昇(高カリウム血症)です。カリウムは筋肉や神経の働きに重要なミネラルですが、血中の濃度が高くなりすぎると、不整脈や心停止を引き起こす可能性があります。
また、カルシウムやリンのバランスが崩れると、骨がもろくなったり、血管が石灰化したりする原因にもなります。
- 高カリウム血症:不整脈、心停止のリスク
- 低ナトリウム血症:意識障害、けいれんのリスク
- 高リン血症・低カルシウム血症:骨のもろさ、血管石灰化のリスク
貧血や骨の病気の進行
腎臓は、赤血球を作るために必要なホルモン(エリスロポエチン)を分泌しています。腎機能が低下すると、このホルモンの分泌が減少し、貧血(腎性貧血)が進行します。貧血になると、動悸、息切れ、めまい、倦怠感などの症状が現れます。
また、腎臓はビタミンDを活性化する働きも持っており、これはカルシウムの吸収に重要です。
腎機能が低下するとビタミンDの活性化がうまくいかず、カルシウムの吸収が悪くなり、骨が弱くなる腎性骨症(骨粗しょう症や線維性骨炎など)が進行し、骨折しやすくなることがあります。
透析をしない場合の余命について
「透析をしない」という選択を考えるとき、多くの方が気になるのが「余命はどのくらいなのか」ということだと思います。これは非常に個人差が大きく、一概には言えない難しい問題です。
ここでは、余命に影響する要因や、緩和ケアの重要性について説明します。
余命に影響を与えるさまざまな要因
透析をしない場合の余命は、患者さんの年齢、腎機能がどの程度残っているか、腎不全の原因となった病気、心臓病や糖尿病などの併存疾患の有無や重症度、全身状態、栄養状態など、多くの要因によって大きく異なります。
一般的に、高齢であるほど、また併存疾患が多いほど、余命は短くなる傾向があります。また、尿毒症の進行速度や、高カリウム血症などの危険な合併症がいつ起こるかによっても左右されます。
一部の研究では、透析を導入しなかった高齢の末期腎不全患者さんの平均余命は数ヶ月から1年程度という報告もありますが、これはあくまで平均であり、数週間で亡くなる方もいれば、数年にわたって比較的穏やかに過ごされる方もいます。
個々の状況によって大きく異なるため、担当医とよく話し合い、見通しを確認することが大切です。
余命に影響しうる主な因子
| 因子 | 内容 |
|---|---|
| 年齢 | 高齢であるほど予後が短い傾向 |
| 残存腎機能 | 尿量が保たれているか、eGFRの値 |
| 併存疾患 | 心疾患、糖尿病、悪性腫瘍などの有無と重症度 |
| 栄養状態 | 低栄養は予後不良因子となりうる |
個別性が非常に高いことの理解
前述の通り、透析をしない場合の余命は、統計的なデータや平均値で語ることが非常に難しい領域です。インターネット上にはさまざまな情報がありますが、それらが必ずしもご自身の状況に当てはまるとは限りません。
大切なのは、ご自身の体の状態を最もよく理解している担当医と密に連携を取り、個別具体的な見通しや、今後起こりうる変化について説明を受けることです。不安や疑問点は遠慮なく質問し、納得のいくまで話し合うことが重要です。
症状緩和を目的としたケア(緩和ケア)の重要性
透析をしないという選択をした場合、病気を治すことではなく、つらい症状を和らげ、残された時間をできるだけ穏やかに、その人らしく過ごせるようにするためのケア(緩和ケア、または保存的腎臓療法とも呼ばれます)が中心となります。
痛み、吐き気、呼吸困難、倦怠感、不安など、さまざまな身体的・精神的な苦痛を軽減するための治療やケアを行います。緩和ケアは、終末期だけでなく、比較的早い段階から始めることで、生活の質を維持・向上させるのに役立ちます。
医師、看護師、薬剤師、栄養士、ソーシャルワーカーなど、多職種のチームで患者さんとご家族を支えます。
統計データと個人の違いについて
透析をしない場合の余命に関する統計データは、あくまで集団を対象としたものであり、個々の患者さんにそのまま当てはまるわけではありません。
統計は傾向を示すものであり、個人の経過を正確に予測するものではないことを理解しておく必要があります。
例えば、「平均余命が6ヶ月」というデータがあったとしても、それは3ヶ月で亡くなる方もいれば、1年以上穏やかに過ごされる方もいるということを意味します。
ご自身の状態や希望を医療チームと共有し、個別化されたケアプランを立てることが何よりも大切です。
透析をしない場合の生活と必要なケア
透析をしないという選択をした場合、生活の中心は延命治療ではなく、症状をコントロールし、生活の質をできる限り維持することに移ります。これを「保存的腎臓療法(Conservative Kidney Management: CKM)」と呼ぶこともあります。
ここでは、その具体的な内容について説明します。
症状緩和を中心とした医療ケア(保存的腎臓療法)
保存的腎臓療法では、尿毒症によるさまざまな症状や、腎機能低下に伴う合併症(貧血、高血圧、電解質異常など)をできる限り和らげるための医療ケアを行います。具体的には、以下のような治療や管理が含まれます。
- 薬物療法:吐き気止め、痛み止め、利尿剤、降圧剤、リン吸着薬、カリウム降下薬、貧血改善薬(エリスロポエチン製剤など)の使用
- 輸液管理:脱水を防ぎつつ、過剰な水分負荷を避けるための調整
- 酸素療法:呼吸困難がある場合の対応
これらのケアは、患者さんの状態や希望に応じて、外来通院、訪問診療、または入院という形で行われます。定期的に医師の診察を受け、症状の変化に合わせて治療内容を調整していくことが重要です。
保存的腎臓療法における主なケア内容
| ケアの対象 | 具体的な内容例 |
|---|---|
| 尿毒症症状 | 吐き気止め、かゆみ止め、便秘薬など |
| 水分・電解質管理 | 利尿剤、カリウム降下薬、食事指導 |
| 貧血 | 造血ホルモン注射、鉄剤 |
| 精神的苦痛 | カウンセリング、精神安定剤の処方 |
食事療法や水分管理の継続的な重要性
透析をしない場合でも、食事療法と水分管理は、症状をコントロールし、体調を維持するために非常に重要です。腎臓への負担を軽減し、尿毒症の進行を遅らせることを目指します。
具体的には、タンパク質の摂取量を適切に制限すること、塩分を控えること、カリウムを多く含む食品(生野菜、果物、いも類など)の摂取に注意することが基本となります。
水分摂取量も、尿量やむくみの状態に応じて調整が必要です。管理栄養士と相談しながら、個々の状態に合わせた食事計画を立て、無理なく続けられるように工夫することが大切です。
ただし、終末期に近づき、食欲が著しく低下してきた場合には、厳格な食事制限よりも、患者さんが食べたいものを少量でも口にできることを優先する場合もあります。この点も医療チームとよく相談しましょう。
日常生活での注意点と快適に過ごすための工夫
体力の低下やさまざまな症状が現れる中で、日常生活をできるだけ快適に送るためには、いくつかの注意点と工夫があります。まず、無理のない範囲で体を動かすことは、筋力の維持や気分の転換にもつながります。
感染症は体力を消耗させ、全身状態を悪化させる可能性があるため、手洗いやうがいを励行し、人混みを避けるなど、感染予防を心がけることが大切です。
皮膚の乾燥やかゆみに対しては、保湿剤を使用したり、刺激の少ない衣類を選んだりするなどのケアが有効です。また、便秘も体調を悪化させる要因となるため、食事や適度な運動、必要に応じて下剤を使用するなどして、排便コントロールを心がけましょう。
口腔ケアも、食欲維持や感染予防の観点から重要です。
精神的なサポートと心のケアの必要性
透析をしないという選択は、患者さんご自身だけでなく、ご家族にとっても大きな決断であり、不安や悲しみ、葛藤など、さまざまな感情を抱えることがあります。
このような精神的な負担を軽減するためには、適切なサポートと心のケアが必要です。医療従事者(医師、看護師、臨床心理士、医療ソーシャルワーカーなど)に、自分の気持ちや不安を率直に話すことが大切です。
また、同じような経験を持つ患者さんやご家族との交流(患者会など)が支えになることもあります。ご家族も、患者さんの気持ちに寄り添いながら、自分自身の心の健康も大切にする必要があります。
必要であれば、専門家のサポートを受けることをためらわないでください。
「透析しない」選択を考える上で大切なこと
「透析しない」という選択は、ご自身の人生に関わる非常に重い決定です。後悔のない選択をするために、そしてその選択をした後に穏やかに過ごすために、事前に考えておくべきこと、行うべきことがあります。
医療チームとの十分な話し合いと情報共有
最も重要なのは、担当医をはじめとする医療チームと十分に話し合い、正確な情報を得ることです。
ご自身の病状、透析治療のメリット・デメリット、透析をしなかった場合の医学的な見通し(起こりうる症状、余命など)、そして利用できる緩和ケアやサポートについて、納得いくまで説明を受けましょう。
疑問や不安な点は遠慮なく質問し、ご自身の希望や価値観を医療チームに伝えることが大切です。医療チームは、患者さんの意思を尊重し、最善の選択ができるように支援する役割を担っています。
ご家族との意思疎通と理解の促進
透析をしないという選択は、ご家族にも大きな影響を与えます。ご自身の考えや気持ちを率直にご家族に伝え、十分に話し合う時間を持つことが重要です。
ご家族が病状や治療について正しく理解し、患者さんの意思を尊重できるよう、医療チームも交えて話し合いの場を設けることも有効です。
ご家族の不安や疑問にも耳を傾け、お互いの気持ちを理解し合うことで、より良いサポート体制を築くことができます。意思決定のプロセスにご家族が関わることで、後々の後悔を減らすことにもつながります。
家族との話し合いで伝えるべきこと
| 項目 | 具体例 |
|---|---|
| 自分の病状の理解 | 医師から受けた説明、現在の状態 |
| 透析しない理由 | 価値観、生活の質、身体的負担など |
| 今後の希望 | どのように過ごしたいか、どこで過ごしたいか |
| 家族への想い | 感謝の気持ち、心配なこと |
アドバンス・ケア・プランニング(ACP)の活用
アドバンス・ケア・プランニング(ACP)とは、将来の意思決定能力の低下に備えて、ご自身が望む医療やケアについて、事前に家族や医療関係者と話し合い、共有する取り組みのことです。「人生会議」とも呼ばれます。
もしもの時に備えて、どのような治療を受けたいか、または受けたくないか、どこで最期を迎えたいか、延命措置についての考えなどを具体的に話し合い、書面に残しておくこともできます。
ACPを通じて、ご自身の価値観や希望を明確にし、それを周囲と共有することで、将来的にご自身で意思表示ができなくなった場合でも、その意思が尊重されやすくなります。
- 自分の価値観や希望を明確にする
- 信頼できる人(家族、医療者など)と話し合う
- 話し合った内容を記録に残す(任意)
- 状況の変化に応じて見直す
セカンドオピニオンの検討も選択肢の一つ
透析をしないという重大な決断をするにあたり、現在の担当医以外の医師の意見を聞くこと(セカンドオピニオン)も有効な選択肢です。
異なる専門分野の医師や、経験豊富な別の医師の意見を聞くことで、より多角的な視点から病状や治療法について理解を深めることができます。
セカンドオピニオンは、現在の治療方針に疑問がある場合だけでなく、より納得して治療方針を決定したい場合にも役立ちます。セカンドオピニオンを希望する場合は、まず担当医に相談し、紹介状や検査データなどの提供を依頼しましょう。
透析をやめるという選択について
既に透析治療を受けている方が、さまざまな理由から透析治療を中止する(やめる)という選択を考えることもあります。これは「透析離脱」とも呼ばれ、非常に慎重な判断が求められる選択です。
透析中止(離脱)が検討される状況
透析中止が検討されるのは、主に以下のような状況です。
- 患者さん本人が、回復の見込みがない重篤な合併症(末期がん、重度の認知症、重度の脳血管障害など)を併発し、透析継続が苦痛を長引かせるだけと判断した場合
- 透析治療を継続しても、生命の質の著しい低下が避けられず、患者さん本人がこれ以上の透析を望まない場合
- 患者さんの意思決定能力が失われている場合で、事前に示された意思(リビングウィルなど)や、ご家族が患者さんの意思を推定して中止を希望する場合
これらの状況において、患者さんの意思を最大限に尊重し、医療チームとご家族が十分に話し合い、倫理的な側面も考慮した上で慎重に判断します。
透析中止後の経過と必要なケア
透析を中止すると、数日から数週間以内に尿毒症が進行し、多くの場合、死に至ります。
その間の経過は、残存する腎機能や全身状態によって異なりますが、一般的には、倦怠感、食欲不振、吐き気、意識レベルの低下などが徐々に現れます。
透析中止後のケアは、苦痛をできる限り和らげることを目的とした緩和ケアが中心となります。呼吸困難や痛み、不穏などの症状に対して、薬物療法や精神的なサポートを行います。
患者さんが穏やかに最期を迎えられるよう、医療チームとご家族が協力してケアにあたります。
透析中止後の主な症状とケア
| 症状 | ケアの例 |
|---|---|
| 呼吸困難 | 酸素投与、体位の工夫、医療用麻薬の使用 |
| 倦怠感・傾眠 | 安楽な環境整備、無理強いしないケア |
| 精神的苦痛・不穏 | 声かけ、鎮静薬の使用、家族の付き添い |
倫理的な側面と多職種による意思決定支援
透析中止は生命に直結する決定であるため、倫理的な側面からの十分な検討が必要です。医療チームは、患者さんの自己決定権を尊重しつつ、医学的な妥当性、患者さんにとっての最善の利益、そして社会的な公正性などを考慮します。
多くの医療機関では、倫理委員会や多職種カンファレンス(医師、看護師、ソーシャルワーカー、臨床心理士、倫理の専門家などが参加)を開催し、透析中止の妥当性について慎重に議論します。
このプロセスを通じて、患者さんとご家族の意思決定を支援し、関係者全員が納得できる結論に至るよう努めます。
ご家族の心のケアとグリーフケア
透析中止という決断は、ご家族にとっても非常につらい経験となります。患者さんの意思を尊重しつつも、大切な人を失うことへの悲しみや罪悪感、無力感などを抱えることがあります。
医療チームは、患者さんだけでなく、ご家族の精神的なサポートも行います。気持ちを表現できる場を提供したり、必要に応じて専門家(臨床心理士や精神科医)のサポートを紹介したりします。
また、患者さんが亡くなられた後も、ご家族が悲嘆(グリーフ)から立ち直れるように支援するグリーフケアも重要です。悲しみを乗り越えるには時間がかかりますが、一人で抱え込まず、周囲のサポートを求めることが大切です。
よくある質問
ここでは、「透析しない」という選択に関して、患者さんやご家族からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
- 透析をしないと、どれくらい生きられますか?
-
これは非常によく聞かれる質問ですが、一概にお答えすることはできません。
透析をしない場合の余命は、その方の年齢、腎機能がどの程度残っているか、他にどのような病気(心臓病や糖尿病など)をお持ちか、全身状態、栄養状態など、多くの要因によって大きく異なります。
数週間から数ヶ月という場合もあれば、1年以上穏やかに過ごされる方もいらっしゃいます。大切なのは、ご自身の状態を最もよく把握している担当医とよく話し合い、個別具体的な見通しについて説明を受けることです。
- 透析をしない場合、どのような症状が出ますか?
-
透析をしないと、腎臓の機能低下に伴い、体内に老廃物や余分な水分が溜まることで「尿毒症」という状態が進行します。初期には、食欲不振、吐き気、だるさ、皮膚のかゆみなどが現れることが多いです。
進行すると、むくみ、息切れ、貧血、意識がぼんやりする、けいれんなどが起こりえます。これらの症状を和らげるために、緩和ケア(保存的腎臓療法)を行います。
症状の出方や強さには個人差がありますので、担当医や看護師に都度相談し、適切な対応をとることが重要です。
透析しない場合に起こりうる主な症状
分類 症状例 全身症状 倦怠感、食欲不振、体重減少、発熱 消化器症状 吐き気、嘔吐、便秘、下痢 循環器・呼吸器症状 むくみ、息切れ、呼吸困難、胸痛 精神・神経症状 不眠、不安、うつ状態、意識障害、けいれん 皮膚症状 かゆみ、乾燥、皮膚の色素沈着 - 家族として、本人の「透析しない」という選択をどう支えれば良いですか?
-
ご本人が「透析しない」という重い決断をされたとき、ご家族のサポートは非常に重要です。まずは、ご本人の気持ちや考えをじっくりと聞き、なぜそのような選択をしたのかを理解しようと努めることが大切です。
その上で、ご本人の意思を尊重し、寄り添う姿勢を示しましょう。病状や今後の経過、必要なケアについて医療チームから一緒に説明を受け、情報を共有することも助けになります。
ご本人が穏やかに過ごせるように、身の回りの世話や精神的な支えとなること、そしてご家族自身も無理をしすぎず、必要なサポートを外部に求めることも考えてください。
医療ソーシャルワーカーやケアマネージャーなどに相談することも有効です。
- 保存的腎臓療法とは具体的にどのようなものですか?
-
保存的腎臓療法(CKM: Conservative Kidney Management)とは、透析や腎移植といった腎代替療法を選択せず、現在の腎機能をできるだけ維持しながら、症状緩和を中心とした医療とケアを行うアプローチです。
具体的には、食事療法(タンパク質、塩分、カリウムなどの制限)、薬物療法(尿毒症症状の緩和、貧血治療、血圧管理、電解質補正など)、精神的・社会的なサポートなどが含まれます。
目的は、病気を治すことではなく、患者さんが最期までその人らしく、できる限り苦痛なく穏やかに過ごせるように支援することです。患者さんの状態や希望に応じて、多職種の医療チームが連携してケアプランを作成し、実践します。
以上
透析センター(人工透析) | 大垣中央病院(医療法人社団豊正会 )
参考文献
O’CONNOR, Nina R.; KUMAR, Pallavi. Conservative management of end-stage renal disease without dialysis: a systematic review. Journal of palliative medicine, 2012, 15.2: 228-235.
VOOREND, Carlijn GN, et al. Survival of patients who opt for dialysis versus conservative care: a systematic review and meta-analysis. Nephrology Dialysis Transplantation, 2022, 37.8: 1529-1544.
TONKIN-CRINE, Sarah, et al. Understanding by older patients of dialysis and conservative management for chronic kidney failure. American Journal of Kidney Diseases, 2015, 65.3: 443-450.
MORTON, Rachael L., et al. Factors influencing patient choice of dialysis versus conservative care to treat end-stage kidney disease. Cmaj, 2012, 184.5: E277-E283.
SAEED, Fahad; ADAMS, Hugh; EPSTEIN, Ronald M. Matters of life and death: why do older patients choose conservative management?. American journal of nephrology, 2020, 51.1: 35-42.
TERUEL, José Luis, et al. Choosing conservative therapy in chronic kidney disease. Nefrología (English Edition), 2015, 35.3: 273-279.
SEAH, Angeline ST, et al. Opting out of dialysis–Exploring patients’ decisions to forego dialysis in favour of conservative non‐dialytic management for end‐stage renal disease. Health Expectations, 2015, 18.5: 1018-1029.
NOBLE, Helen, et al. Clinician views of patient decisional conflict when deciding between dialysis and conservative management: qualitative findings from the PAlliative Care in chronic Kidney diSease (PACKS) study. Palliative Medicine, 2017, 31.10: 921-931.
VERBERNE, Wouter R., et al. Value-based evaluation of dialysis versus conservative care in older patients with advanced chronic kidney disease: a cohort study. BMC nephrology, 2018, 19: 1-11.
CASTRO, Manuel Carlos Martins. Conservative management for patients with chronic kidney disease refusing dialysis. Brazilian Journal of Nephrology, 2018, 41: 95-102.