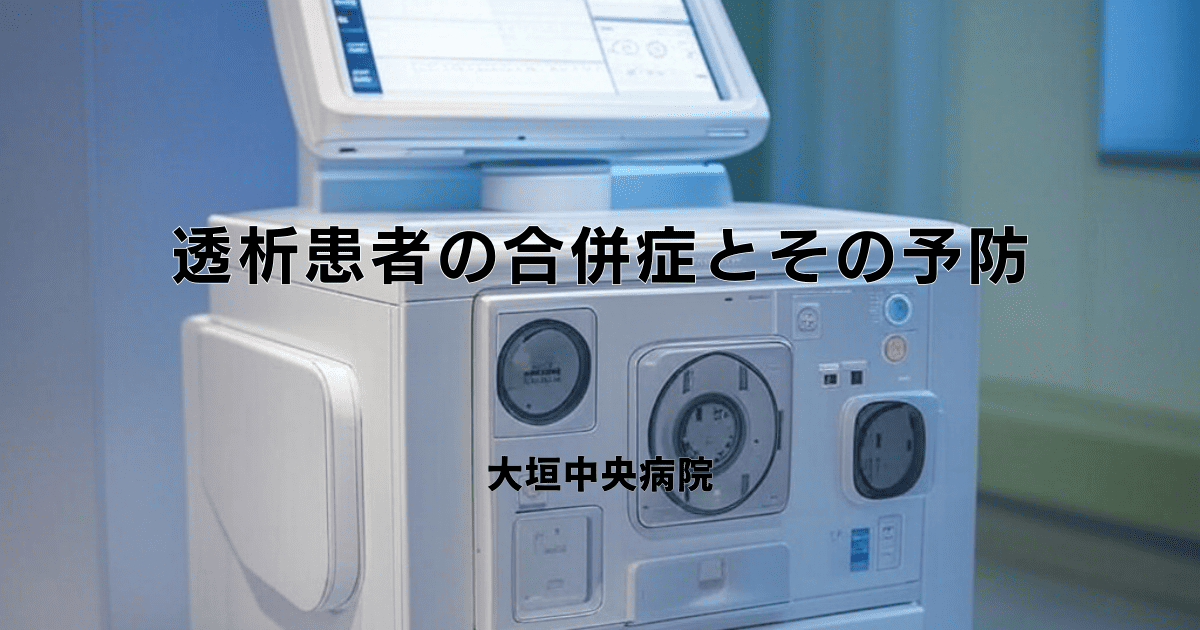透析治療を受けている方や、将来的に透析の可能性を指摘されている方にとって、合併症の早期発見と予防策を意識することはとても大切です。
長期にわたる透析では、心血管系や免疫機能など体内のさまざまな部分に影響を与える可能性がありますが、適切な知識を身につけることで健康状態を保ちやすくなります。
病気や治療に対する理解を深め、毎日の生活習慣や医療者との連携を積極的に取り入れてみてください。以下では、透析の基本からよく起こる合併症、そして予防や対処法までを詳しく解説します。
透析の基本知識
透析とは、腎機能が著しく低下または失われた状態の方を対象に、血液中の老廃物や余分な水分を除去し、体内の環境を整える治療法です。
腎臓は体内のバランスを保つ重要な役割を担っているため、腎臓が十分に働かなくなると、血液中に毒素や水分が過度に蓄積し、体調が悪化しやすくなります。以下では、透析の役割や種類、治療が必要となる主な原因などを紹介します。
透析の役割と目的
透析治療では、血液中の老廃物や余分な水分を取り除き、電解質バランスを調整します。健康な腎臓が担う浄化機能を代替することで、身体のコンディションを整え、合併症のリスクを軽減することが主な目的です。
透析の有無によって生活の質が大きく左右されるため、必要に応じた通院や在宅での管理を行うことが大切です。
定期的な透析を受けることで得られるメリットは以下のようにまとめられます。
透析治療による身体的メリット一覧
| 項目 | メリット |
|---|---|
| 血液浄化 | 老廃物や毒素を排除する |
| 電解質バランス調整 | カリウムやナトリウムなどの過剰・不足を予防する |
| 余分な水分の除去 | むくみや血圧の乱れを抑えやすくする |
| 生活の質向上 | 倦怠感や呼吸困難などを緩和しやすくする |
こうした透析の目的を正しく理解すると、自身の治療計画に前向きに取り組みやすくなります。
透析の種類
代表的な透析には、血液透析と腹膜透析があります。血液透析は血管に針を刺して体外に血液を取り出し、機械的に老廃物をろ過する方法です。
腹膜透析は、お腹の中にある腹膜をフィルターの役割とし、透析液を注入することで血液中の毒素や水分を取り除きます。それぞれにメリットとデメリットがあり、患者さんの生活スタイルや身体状況、医師の判断などを踏まえて選択します。
医療機関で行う血液透析では、週に複数回通う必要があり、比較的長時間の透析を行います。一方、自宅で行いやすい腹膜透析は通院の手間が減る一方で、毎日透析液の交換を行う負担も伴います。
いずれの方法も専門的知識が必要となるため、医療スタッフとの連携と学習が重要です。
透析が必要になる主な原因
透析が必要となる背景には、さまざまな腎臓病があります。慢性腎臓病や糖尿病性腎症、高血圧による腎障害、糸球体腎炎などが主な原因として挙げられます。
とくに糖尿病や高血圧を長年放置すると、腎臓の機能が徐々に損なわれ、最終的に透析が避けられなくなる場合があります。生活習慣の改善や早期の医療介入によって、透析導入を遅らせることも可能です。
自覚症状が出にくい初期段階では見過ごしやすいため、定期的な健診や血液検査が予防に役立ちます。血圧が高めの方や血糖コントロールに課題を感じる方は、早めに専門医の診察を受けることが大切です。
通院透析と在宅透析の違い
通院透析では、病院や透析専門のクリニックに週数回通って医療スタッフの管理下で治療を受けます。血液透析を中心に行うことが多く、安全面での確保やトラブル時の即時対応がしやすいといった利点があります。
ただし、決められた曜日や時間に通う必要があるため、仕事や家事などとの両立が難しくなるケースもあります。
在宅透析には、腹膜透析や在宅血液透析が含まれます。腹膜透析では自宅で透析液を交換する方法を取るため、医療機関へ足を運ぶ頻度を減らせます。
しかし、自身や家族が正しく交換手技を習得する必要があるうえ、清潔環境の維持が重要になります。生活スタイルや病状に応じて適切な方法を選ぶことで、より安定した治療生活を送りやすくなります。
透析合併症の概念
透析合併症は、長期的な透析治療を行う過程で起こりやすい健康上のトラブルを指します。心臓や血管、骨などさまざまな部位に影響を与え、生活の質を下げる要因になりやすいです。
正しい知識を身につけ、早い段階で異変に気づくことが大切になります。
透析中に起こりやすい身体的変化
透析中には、血圧低下や筋けいれん、頭痛などが生じることがあります。透析装置によって血液から急激に水分や老廃物が除去されるため、血液量や血圧のコントロールが難しくなる場面があるからです。
また、特定の電解質が急に変動することで、不整脈やけいれんなどの症状が出現しやすくなります。
医療スタッフは透析の設定や透析液の調整を行い、患者さんの血圧測定や症状の確認をこまめに実施します。患者さん自身も透析前後の体重や血圧を日常的にチェックし、違和感があれば早めに報告することがポイントです。
患者の生活の質への影響
透析を定期的に受ける必要がある方の生活リズムは、通院日程や食事制限などによって大きく変化します。通院透析の場合、週に複数回の長時間治療が必要になり、仕事や家庭との両立をどうするか悩む方も多いです。
さらに、身体的にも貧血や疲労感が続き、活動量が下がることで社会参加の機会を制限しやすくなります。
生活の質に関わる要素は多岐にわたるため、一人ひとりの事情を踏まえたケアやサポート体制を整えることが大切です。患者さん自身の主体的な工夫に加え、医療スタッフや家族との協力が欠かせません。
生活の質に影響を与えやすい要素一覧
| 要素 | 具体例 |
|---|---|
| 身体的負担 | 低血圧、疲労感、貧血 |
| 社会的要因 | 通院による就労制限、外出機会の減少 |
| 心理的要因 | 治療への不安、うつ傾向 |
| 経済的負担 | 医療費、交通費、介護費用 |
上記のような要素が相互に影響し合い、生活全体に変化をもたらします。
透析の長期化に伴うリスク
透析を長期間継続することで蓄積されるリスクとして、心血管系のトラブルや骨・関節の変性、皮膚障害などが挙げられます。慢性的な体液コントロールの乱れが原因となり、高血圧や心不全、動脈硬化の進行が進むことがあります。
また、透析アミロイドーシスによって骨や関節が侵され、痛みや動きにくさを感じるケースもあります。
こうしたトラブルは早期の検査や日常的な観察で把握しやすくなります。長期にわたって透析を受ける方ほど、定期健診の重要性は増すといえます。
透析合併症看護の重要性
透析合併症看護は、合併症の予防や早期発見、症状の緩和に大きく貢献します。看護師が中心となって血圧や体重、検査データの変化を把握し、治療チームへ迅速に情報を共有することで適切な処置を実施しやすくなります。
患者さんとのコミュニケーションを通じて、生活スタイルや食事管理の継続に関する相談相手にもなります。
医療スタッフだけでなく、患者さん自身も看護の視点を取り入れて日々のケアに取り組む意識が大切です。身体の小さな異変や気になる症状を見過ごさず、積極的に報告していくことが合併症の早期発見に直結します。
よく見られる合併症の種類
透析合併症には、心血管系や血液管理に関わる問題、骨や関節への影響、感染症リスクなど、さまざまな種類があります。一つひとつの合併症に適した対策を講じ、症状の悪化を防ぐことが大切です。
心血管系のトラブル(心不全・狭心症など)
透析中や透析歴の長期化に伴って、心臓や血管系のトラブルが起こりやすくなります。具体的には動脈硬化や心不全、狭心症などが代表的です。
特に、長期間の高血圧状態や体液バランスの乱れが心臓や血管に負担をかけ、症状を進行させる原因になります。胸の痛みや動悸、息切れなどが持続的にみられた場合は、医療機関で詳細な検査を受けることが重要です。
生活習慣の調整や適度な運動、血圧コントロールなどによって、心血管系への負担を軽減することができます。病院での定期検査では心エコーや心電図などを受け、状態を把握しながら治療方針を立てると安心です。
血液管理に関わるトラブル(貧血・出血傾向など)
腎臓の機能が低下すると、赤血球をつくるエリスロポエチンの産生量が減り、貧血が起こりやすくなります。透析自体も血液中の成分が流出する可能性があり、貧血状態のコントロールが必要となります。
ヘモグロビン値やフェリチン値などを定期的に測定し、必要に応じて注射や内服薬で赤血球の産生を促します。
もう一つ注意が必要なのは、出血傾向です。透析の度に抗凝固薬を使用する場合があり、血小板機能が変化しやすくなります。鼻血や皮下出血が増えた場合は速やかに医療者へ相談するとよいでしょう。
血液管理の指標を把握しながら、薬剤調整や生活面の注意を行うことでリスクを軽減できます。
血液関連の数値と意義一覧
| 指標 | 正常範囲(目安) | 異常が疑われる状態 |
|---|---|---|
| ヘモグロビン | 約12~16g/dL(成人女性), 約13~17g/dL(成人男性) | 10g/dL以下で貧血の可能性が高い |
| フェリチン | 30~300ng/mL程度 | 低値の場合は鉄欠乏 |
| 血小板数 | 15万~40万/µL程度 | 10万/µL以下で出血リスク上昇 |
| CRP | 0.30mg/dL以下(施設による) | 高値では炎症・感染を疑う |
血液データを定期的に確認すると、貧血や感染リスクを見極めやすくなります。
骨や関節への影響(透析アミロイドーシスなど)
長年の透析治療では、骨や関節への負担が大きくなることがあります。代表的なものとして、透析アミロイドーシスが挙げられます。
これは、β2-ミクログロブリンというタンパク質が体内に蓄積し、関節や骨などに影響を及ぼし、関節痛や骨折リスクを高めます。症状が進行すると、日常生活に支障をきたすような痛みや変形が生じる場合があります。
骨に関係するミネラルバランス(カルシウムやリン)の乱れも、骨密度の低下を招く要因になります。
検査でリン値やパラトルモン値(PTH)を確認し、薬剤によるコントロールを行うとともに、食事管理や運動を取り入れることで骨折リスクを低減させやすくなります。
感染症リスクと免疫低下
透析患者は免疫力が下がりやすく、感染症リスクが高まります。特に、シャント部(血液透析で用いる血管吻合部)や腹膜透析カテーテル挿入部などの創部感染には注意が必要です。
皮膚トラブルを放置すると細菌が入り込み、重篤な状態につながる恐れもあります。日々の清潔管理を徹底し、少しでも腫れや痛み、発赤を感じたら早めに受診してください。
一般的な風邪やインフルエンザ、肺炎なども重症化しやすいため、予防接種や適度な休養を心がけることが大切です。体調の変化に気づきやすいよう、平時から体温や呼吸状態を確認する習慣を持つと安心です。
合併症を早期に発見するためのポイント
合併症の多くは、初期の段階で軽度の症状が現れることが少なくありません。小さな異常や体調の変化に注目し、検査を受けることで早期発見につなげやすくなります。
予防の視点を持ちながら、定期的な診察やセルフチェックの習慣を育むことが重要です。
定期的な検査の活用
定期的に採血や心電図、画像検査などを行い、現在の身体状態を把握することは合併症予防の要です。血圧や体重、血液データの推移を見比べることで、以前との違いにいち早く気づく機会が増えます。
透析日にはルーチンで検査する項目が多いですが、必要に応じて追加の検査を依頼できるよう、医療スタッフとのコミュニケーションを活発にとってください。
検査内容と主な目的一覧
| 検査内容 | 主な目的 |
|---|---|
| 血液検査(生化学) | 腎機能、電解質、貧血の程度などを把握 |
| 心電図 | 不整脈や心臓負担の有無を確認 |
| X線・CT・MRI | 骨や内臓の異常、合併症の進展度を確認 |
| シャントエコー | 血液透析で用いる血管の状態を評価 |
定期的に検査を行うことで、合併症の発症リスクを早期に捉えやすくなります。
日常生活でのセルフチェック
毎日の生活の中でも、自分の体調や症状をこまめに確認する習慣が大切です。透析前後の体重や血圧、尿量(残存尿量がある場合)をメモに取り、変化が大きいと感じたら医療者に相談するのが望ましいです。
疲労感やむくみ、食欲の低下などは単なる体調不良と見落としがちですが、合併症のサインである可能性もあります。
- 起床時と就寝前の血圧測定
- 透析後の体重増減チェック
- 皮膚トラブル(かゆみや赤み、傷など)の観察
- 立ちくらみや頭痛の頻度の記録
こういった行為は手間に感じるかもしれませんが、合併症の予防や早期発見には効果的です。
かかりつけ医との密な連携
腎臓内科や透析専門の医師だけでなく、ほかの合併症に対応する診療科と連携を図ることもポイントです。糖尿病や高血圧を抱えている方は、内科や循環器科など複数の科で並行して治療を進めるケースが一般的です。
情報を共有しながら一元的に管理してもらうことで、重複する薬剤や検査の見落としを防ぎやすくなります。
かかりつけ医を中心に、必要に応じて専門医を紹介してもらう形で連携体制を築くと、症状の変化に対して柔軟に対応できるでしょう。医療機関を受診する際には、普段測定しているデータや症状のメモを持参するとスムーズです。
透析合併症看護の視点とサポート
透析合併症看護では、患者さんの身体的な変化はもちろん、精神面や社会的背景を含めたケアを重視します。日常的に体調観察を行い、不安を聞き取ることで気になる症状の早期発見につながります。
医療スタッフによる定期的な相談や、教育プログラムを通じた情報提供も行われます。
患者さんが主体的に取り組む意欲を育むため、無理のない範囲で目標設定をしていく流れがよくとられます。小さな成功体験の積み重ねでセルフケア能力を高め、合併症に対する抵抗力や自信を持ちやすくなります。
透析中の食事や水分管理の重要性
食事や水分管理は透析合併症の予防や体調管理に大きく影響します。腎臓の機能が十分でない場合は、体内に不要な物質や水分が蓄積しやすく、合併症のリスクを高める要因となります。
医師や管理栄養士と相談しながら、個々の状況に合った食生活を続けることが大切です。
透析を受けている方の栄養バランス
体内の老廃物を効率よく排出するためには、適度なエネルギーとたんぱく質の摂取が必要になります。しかし過剰摂取すると尿素やクレアチニンなどの老廃物が増え、透析で除去しきれない分が体に残ってしまう可能性があります。
カロリーやたんぱく質の摂取量をバランスよく調整しながら、ビタミンやミネラルも過不足なく取り入れることがポイントです。
透析患者が意識したい栄養素と役割一覧
| 栄養素 | 役割 | 注意点 |
|---|---|---|
| たんぱく質 | 組織修復、免疫維持 | 過剰摂取で老廃物増加 |
| 炭水化物 | 主なエネルギー源 | 過度な制限は疲労を招きやすい |
| 脂質 | エネルギー源、ホルモン合成 | 質の良い油脂を選ぶ |
| ビタミン | 代謝サポート | 水溶性ビタミン不足に注意 |
| ミネラル(鉄・亜鉛など) | 血液や骨の健康維持 | 過剰・不足の両面に留意 |
管理栄養士による指導を受ける場合は、自身の食習慣を具体的に伝えることが有効です。日々の食事を振り返るために食事日記をつける方もいます。
塩分・カリウム・リンのコントロール
腎臓が十分に機能していない場合、塩分やカリウム、リンなどが体内に溜まりやすくなります。特にカリウムは心臓の働きに深く関わるため、透析患者にとっては重大なコントロール項目になります。
またリンが過剰に蓄積すると、カルシウムとのバランスが乱れ、骨の健康が損なわれやすくなります。塩分の摂りすぎも血圧上昇を招き、心血管系の合併症を進行させる要因となります。
- 加工食品や外食は塩分が多い傾向
- 果物やジュースに含まれるカリウム量に注意
- リンは乳製品や加工食品にも含まれやすい
すべてを厳しく制限するとストレスにつながるため、医療者と相談しながら上手に取り入れることが大切です。
水分制限の実践方法
腎臓機能が低下している方は、余分な水分を排出しにくくなり、むくみや高血圧、心不全などを引き起こしやすいです。そのため、透析を受けている方には水分制限が求められます。といっても、まったく水分を摂らないのは体に良くありません。
必要最低限の量を確保しながら、過剰摂取を防ぐ工夫が必要になります。
少しずつ口に含むように飲む、一口ごとに飲む量を小さめにする、食事の塩分を減らして喉の渇きを抑えるなど、日々の生活の中でできる対策があります。
夏場や発熱時は脱水リスクも考慮し、決められた範囲内で柔軟な水分補給を行うとよいでしょう。
日々の献立と体調管理
栄養バランスとともに、食生活では味付けや調理方法も重要です。煮物や汁物の味付けを薄味にしたり、だしを効かせて満足度を上げるなどの工夫が有効です。塩分やカリウム量が多い食材は下茹でや水にさらす方法で減らすことができます。
食材の調理による成分調整例
| 食材 | 調理法 | 調整される成分 |
|---|---|---|
| ほうれん草 | 湯がいて水にさらす | カリウム量を減らす |
| レンコン | 茹でこぼしを行う | アクやカリウム除去 |
| じゃがいも | 水に長めに浸す | 糖分やカリウムをやや低減 |
| 肉類(豚・牛) | 脂肪分を茹でて落とす | カロリーをコントロール |
透析合併症看護における栄養指導では、こうした具体例を使いながら日々の献立を考えます。自己流で制限しすぎると栄養不足になる恐れがあるため、必ず医療スタッフに相談しながら実践することが大切です。
合併症の具体的な予防対策
透析合併症を予防するには、毎日の生活習慣と医療的ケアの両面からアプローチすることが求められます。小さな努力の積み重ねが大きな違いを生み、合併症の発症リスクを減らす助けとなります。
自分に合った方法を継続し、定期的に見直しを行っていきましょう。
運動習慣の確立とメリット
運動は血液循環を促進し、筋力維持や心肺機能の向上に役立ちます。過度な運動は体への負担になりますが、軽いウォーキングやストレッチなど、自分の体力に合わせた運動を継続することで、合併症のリスクを下げられる可能性があります。
関節の可動域を保つために軽い体操を行うと、透析アミロイドーシスによる関節のこわばりを軽減しやすくなります。
医師や理学療法士に相談しながら運動プログラムを組むと、安全に続けやすいです。透析後の疲労感が強い方は、無理せず体調の良いタイミングを見計らって少しずつ行うとよいでしょう。
運動の種類と期待できる効果一覧
| 運動方法 | 期待できる効果 | 注意点 |
|---|---|---|
| ウォーキング | 血行促進、体力維持 | 転倒に注意し、地面が平坦な場所を選ぶ |
| ストレッチ | 関節可動域維持 | 痛みやしびれがあれば中断する |
| 軽い筋トレ | 筋力維持・向上 | 重度の貧血や心不全がある場合は要注意 |
| 水中運動 | 関節への負荷軽減 | 透析患者は感染リスクに配慮が必要 |
リスクを伴う運動を始める場合は、主治医の確認を得ると安全です。
透析前後の体調管理と記録
透析前後で体重や血圧、症状をこまめに記録する習慣は、合併症の早期発見に直結します。透析によって除去する水分量を適切に設定するためには、こまめなデータ収集が重要です。
体重増加が大きすぎると透析時に血圧低下や心負荷がかかりやすくなり、合併症リスクを高める原因となります。
- 透析前の体重・血圧を記録
- 透析後の脱水症状やめまいの有無を確認
- 血圧の変動傾向を医療者と共有
- 体重増加分が多い時の食事内容や水分摂取量の振り返り
こうした取り組みを継続することで、自分の身体をより深く理解しながら治療を進められます。
投薬管理と自己注射の取り組み
透析を受けている方は、複数の薬剤を使用することが多いです。血圧を調整する降圧薬や、リンを抑える薬、貧血に対するエリスロポエチン製剤など、複数の処方がある場合は、飲み忘れや重複摂取を防ぐ工夫が必要です。
薬の種類や服用時間を整理するために、1週間分を専用のケースに小分けしたり、カレンダーに書き込んだりすると管理しやすくなります。
エリスロポエチン製剤の自己注射を行う場合は、医療スタッフの指導をしっかり受け、注射部位の清潔保持に努める必要があります。注射後に腫れや出血がひどい場合は、すみやかに診察を受けてください。
透析合併症看護で意識したいケア
透析合併症看護の実践では、患者さんの日常生活を支えるさまざまなサポートが行われます。血圧や血液検査の管理のみならず、心理面へのケアや家族サポートも含まれます。
特に長期透析では、鬱屈した気持ちが起こりやすくなり、治療意欲が低下してしまうこともあります。
看護師やソーシャルワーカー、臨床心理士など多職種が連携し、生活背景や経済面、社会復帰の課題などを含めて支援を提供します。患者さん自身も、遠慮せずに不安や悩みを発信し、必要な相談につなげる姿勢が大切です。
トラブルが起こった時の対処方法
透析患者は、体調の急変やトラブルに備えて常に柔軟な対応を意識する必要があります。急な痛みや不調があったとき、どのような行動を取るべきかをあらかじめ考えておくことで、慌てずに対応しやすくなります。
突然の症状悪化への初動
透析中や日常生活の中で、急に胸の痛みや息切れ、めまいなどが生じた場合は、まず安全な場所で安静を保ち、深呼吸して落ち着きましょう。呼吸困難や意識障害の兆候があるときは、すぐに救急車を呼ぶなど、迅速な行動が必要です。
症状が軽度であっても、持続する場合やいつもと違う感覚がある場合は、早めに医療者に連絡すると安心です。
急変時に意識したい行動の例
| 行動 | ポイント |
|---|---|
| 安静にする | 座ったり横になったりして転倒を防ぐ |
| 周囲に声をかける | 一人で対応しようとせず、支援を求める |
| バイタルサインを確認 | 血圧・脈拍を測れる場合は測定する |
| 症状の詳細を記録 | 痛みの強さ、部位、発症時刻などをメモする |
自宅や職場で症状が出たときも、焦らずに初動対応を行い、必要であれば救急搬送を依頼してください。
担当医や医療スタッフへの連絡手順
気になる症状が出たときは、どのタイミングで医療スタッフに連絡すべきか悩む方もいるでしょう。
明らかに緊急性を伴う場合は救急車の手配が第一ですが、緊急ではないものの不安な症状が続く場合は、病院や透析クリニックに電話をして状況を説明します。
言葉だけでは伝わりにくい場合には、普段の体重や血圧、症状の日誌を手元に用意するとスムーズです。
事前に連絡先や診療時間、緊急時の受け入れ体制などを確認し、連絡先をメモしておくと心強いです。症状の経過を詳細に伝えると適切なアドバイスをもらいやすくなります。
入院治療が必要となるケース
合併症が進行し、内服薬や外来での透析だけでは十分に対処できない場合は、入院治療を検討することがあります。心不全や重度の感染症、出血リスクが高いと判断された場合など、医師の判断のもとで早期に入院して集中的な治療を受ける形です。
入院になると、より詳細な検査や専門的な治療(心臓カテーテル検査や外科的処置など)を受けられます。
体調が落ち着けば退院後の通院透析に戻ることが多いですが、入院中から退院後までのケア計画を多職種で話し合い、再発防止に取り組む姿勢が重要です。
自分や家族の心構え
トラブル時には、本人だけでなく家族の協力体制も大切です。万一の急変時に医療スタッフへ正確に状況を伝えたり、透析スケジュールや薬剤の管理を補助したりすることで、安心感が増します。
家族同士で役割分担を決めておき、緊急時の連絡先やかかりつけ医の情報を共有しておくと慌てずに済みます。
患者さんが不安や痛みを訴えているときは、その気持ちを受け止める姿勢が大切です。本人の意見に耳を傾けながら、医療スタッフとのコミュニケーションをつなげていくことで、より良い対処策を見つけやすくなります。
よくある質問
透析と合併症に関しては、多くの方が不安や疑問を抱いています。ここでは、患者さんや家族からよく寄せられる質問や相談内容を取り上げ、考え方を紹介します。
- 合併症の症状が軽い場合はどうしたらいいのか
-
軽微な症状であっても、透析合併症の初期サインである可能性があります。痛みやむくみ、倦怠感など気になる症状を感じたら、まずは治療施設のスタッフに相談しましょう。
状況に応じて追加の検査を実施することが早期発見につながります。もし大きな異常がなかった場合でも、日常的なチェックを継続していくと安心です。
- 定期的な検査はどれぐらいの頻度で行うのがよいか
-
基本的に透析を受けるたびに、ある程度の検査は行われていますが、詳細な検査を実施する頻度は個人差があります。
心臓や血管の状態確認のためのエコー検査やCT検査は、症状や既往歴に応じて数か月~1年に1回ほど行うことが多いです。医師と相談しながら、必要なタイミングで検査を受けるよう調整してください。
- 病院で相談すべきタイミング
-
に該当する場合は、早めに医療スタッフに連絡すると適切な対処を得られやすいです。
- 透析後も強い倦怠感が続き、日常生活が困難
- 持続的な発熱や原因不明の痛みがある
- 体重や血圧の変動が大きく、むくみが悪化した
- 皮膚にただれや発赤、強い痛みが出現
症状が軽快しないときや緊急度の判断に迷うときは、受診を先延ばしにせず連絡してみてください。
- 家族が気をつけるべき点
-
患者さんの通院スケジュールや服薬内容を大まかに把握しておき、困ったことがあればすぐに医療スタッフに相談できるようにしておくと役立ちます。
特に体調不良時に患者さん自身がうまく状況を説明できないとき、家族が代わりに伝えることが重要です。家族も無理をせず、地域の介護サービスやソーシャルワークを活用するなど、協力体制を整えておくと安心につながります。
以上
透析センター(人工透析) | 大垣中央病院(医療法人社団豊正会 )
参考文献
KHALIL, Abdalrahim; ABDALRAHIM, M. Knowledge, attitudes, and practices towards prevention and early detection of chronic kidney disease. International nursing review, 2014, 61.2: 237-245.
JOHNSON, David W., et al. KHA-CARI guideline: Early chronic kidney disease: detection, prevention and management. Nephrology, 2013, 18.5.
JAMES, Matthew T.; HEMMELGARN, Brenda R.; TONELLI, Marcello. Early recognition and prevention of chronic kidney disease. The Lancet, 2010, 375.9722: 1296-1309.
LOCATELLI, Francesco; VECCHIO, Lucia Del; POZZONI, Pietro. The importance of early detection of chronic kidney disease. Nephrology Dialysis Transplantation, 2002, 17.
WOUTERS, Olivier J., et al. Early chronic kidney disease: diagnosis, management and models of care. Nature Reviews Nephrology, 2015, 11.8: 491-502.
BASTOS, Marcus Gomes; KIRSZTAJN, Gianna Mastroianni. Chronic kidney disease: importance of early diagnosis, immediate referral and structured interdisciplinary approach to improve outcomes in patients not yet on dialysis. Brazilian Journal of Nephrology, 2011, 33: 93-108.
CHEN, Teresa K.; KNICELY, Daphne H.; GRAMS, Morgan E. Chronic kidney disease diagnosis and management: a review. Jama, 2019, 322.13: 1294-1304.
TZANAKAKI, Eleftheria, et al. Causes and complications of chronic kidney disease in patients on dialysis. Health science journal, 2014, 8.3: 343.
DEBONE, Mayara Cristina, et al. Nursing diagnosis in older adults with chronic kidney disease on hemodialysis. Revista brasileira de enfermagem, 2017, 70: 800-805.
LOPEZ‐VARGAS, Pamela A., et al. Prevention, detection and management of early chronic kidney disease: a systematic review of clinical practice guidelines. Nephrology, 2013, 18.9: 592-604.