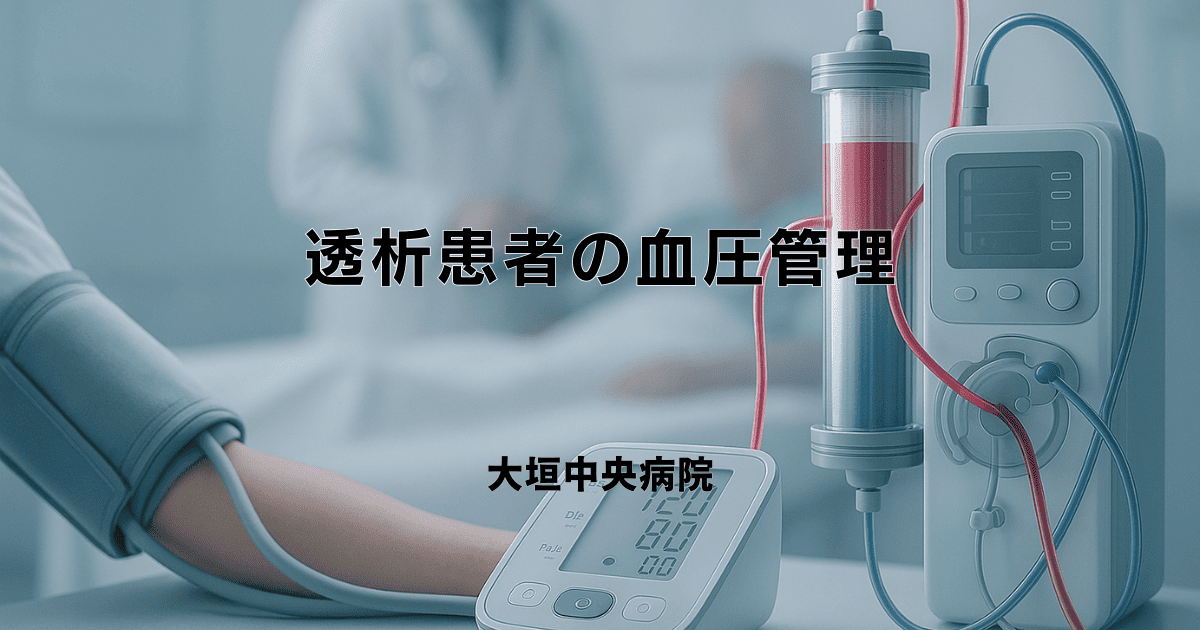透析治療を受ける方にとって、血圧の管理は合併症を予防し、健やかな毎日を送るために非常に重要です。透析患者の血圧は、体内の水分量や自律神経の働きなど、様々な要因で変動しやすいため、高すぎても低すぎても体に負担をかけます。
この記事では、透析と血圧の基本的な関係から、血圧が変動する原因、適切な目標値、そしてご家庭でできる血圧管理の具体的な方法や日常生活での注意点まで、網羅的に解説します。
透析患者の血圧が不安定になる理由
透析治療を受けている方の血圧は、健常な人と比べて変動しやすい傾向があります。その背景には、透析治療そのものが体に与える影響や、腎臓機能の低下に伴う体の変化が関係しています。
なぜ血圧が不安定になるのか、その主な理由を理解することが、適切な血圧管理の第一歩です。
体液量の変動
透析治療では、体内に溜まった余分な水分(体液)を短時間で除去します。これにより、透析の前後で体液量が大きく変動します。体液量は血管内の血液量に直結し、血液量が多ければ血圧は上がり、少なければ下がります。
透析によって水分が除去されると血圧は下がり、次の透析までの間に水分や塩分を摂取すると体液量が増え、血圧が上昇する、というサイクルを繰り返すことが、血圧を不安定にする最も大きな原因です。
自律神経の乱れ
自律神経は、血圧を一定に保つために血管の収縮や拡張をコントロールしています。しかし、透析患者では、尿毒素の影響や体液量の急激な変化などにより、この自律神経の働きが乱れやすくなります。
特に、透析中に急速に除水を行うと、体が対応しきれずに血圧が下がりすぎてしまうことがあります。自律神経の調節機能がうまく働かないことが、血圧の不安定さにつながります。
昇圧物質の影響
腎臓は、血圧を上げる働きを持つ「レニン」というホルモンを分泌します。腎機能が低下すると、このレニンの分泌が過剰になったり、逆にうまくコントロールできなくなったりします。
レニンはアンジオテンシンという強力な昇圧物質を生成するため、その活動が過剰になると高血圧の原因となります。また、血管を収縮させるエンドセリンなどの物質の影響も、血圧を上昇させる一因です。
体液量と血圧の関係
| 状態 | 体液量 | 血圧への影響 |
|---|---|---|
| 非透析日(水分摂取後) | 増加傾向 | 上昇しやすい |
| 透析直後 | 減少 | 低下しやすい |
| ドライウェイト達成時 | 適正 | 安定しやすい |
透析中の高血圧(高血圧)の原因とリスク
透析患者における高血圧は、心臓や血管に大きな負担をかけ、様々な合併症を引き起こす危険な状態です。透析治療を受けている方の高血圧には、特有の原因が存在します。原因を正しく理解し、リスクを認識することが重要です。
ドライウェイト設定の問題
ドライウェイト(DW)とは、透析後に体内の余分な水分が除去され、最も安定した血圧を保てる目標体重のことです。このドライウェイトの設定が高すぎると、透析後も体内に余分な水分が残っている状態(体液過剰)になります。
これが、血管内の血液量を増やし、血圧を上昇させる大きな原因となります。ドライウェイトは定期的に見直すことが大切です。
塩分・水分摂取過多
塩分を摂りすぎると、喉が渇いて水分を多く摂取してしまいます。摂取された水分は体内に溜まり、体液量を増加させ、血圧を上昇させます。特に透析と透析の間(中1日、中2日)の塩分・水分管理は、血圧コントロールに直結します。
日頃の食生活が、透析中の血圧に大きく影響を与えることを意識する必要があります。
降圧薬の調整不足
高血圧の治療には降圧薬を用いますが、透析患者の場合、薬の選択や量の調整が難しい側面があります。透析によって薬の成分が除去されてしまうことや、体液量の変動によって薬の効き方が変わることがあるためです。
医師と相談し、自身の血圧の状態に合わせて降圧薬を適切に調整することが必要です。
高血圧が引き起こす主な合併症
| 臓器 | 主な合併症 | 説明 |
|---|---|---|
| 心臓 | 心不全・心肥大 | 高い圧力に抵抗して血液を送るため心臓に負担がかかる |
| 脳 | 脳卒中(脳出血・脳梗塞) | 高い圧力で脳の血管が破れたり、詰まったりする |
| 血管 | 動脈硬化 | 血管が硬く、もろくなり、様々な臓器の障害につながる |
透析中の低血圧の原因とリスク
高血圧とは逆に、透析中に血圧が下がりすぎる「透析時低血圧」も、患者さんにとってつらい症状を引き起こし、長期的には体に悪影響を及ぼす可能性があります。
透析中に気分が悪くなるなどの症状がある場合、この低血圧が原因かもしれません。
急激な除水
透析間の体重増加が多いと、短時間で多くの水分を除去(除水)しなくてはなりません。血管内の水分が急激に減少すると、体が対応できずに血圧が低下します。
特に、心臓の機能が低下している方や、自律神経の調節がうまくいかない方では、透析時低血圧が起こりやすくなります。
食事摂取のタイミング
透析直前や透析中に食事をすると、消化のために血液が胃や腸に集まります。その結果、心臓に戻る血液量が減少し、血圧が下がりやすくなります。透析中の食事は、血圧の変動に注意しながら、少量にするなどの工夫が必要です。
降圧薬の効果
透析の前に服用した降圧薬が、透析中に効きすぎてしまうことも低血圧の原因の一つです。特に、作用時間の長い薬や、透析で除去されにくい薬を服用している場合は注意が必要です。
透析日の降圧薬の服用については、自己判断で中止せず、必ず主治医の指示に従ってください。
透析時低血圧の主な症状
- 倦怠感・あくび
- 吐き気・嘔吐
- 冷や汗・動悸
- 意識が遠のく感じ
透析患者の血圧管理における目標値
透析患者の血圧は、健常者とは異なる基準で管理します。心血管系の合併症を予防するため、透析施設での血圧だけでなく、家庭での血圧も参考にして、個々の患者さんに合った目標値を設定することが重要です。
なぜ厳格な目標値が必要か
透析患者は、動脈硬化が進行しやすく、心筋梗塞や脳卒中などの心血管イベントのリスクが非常に高い状態にあります。血圧が高い状態が続くと、血管や心臓への負担がさらに増大し、これらのリスクを高めます。
血圧を適切な範囲にコントロールすることは、生命予後を改善し、QOL(生活の質)を維持するために極めて重要です。
透析前後の血圧目標
透析室での血圧は、治療の安全性と効果を判断する上で重要な指標です。一般的な目標値はありますが、年齢や合併症の有無によって調整します。
透析室での血圧目標(目安)
| 測定タイミング | 収縮期血圧(上の血圧) | 拡張期血圧(下の血圧) |
|---|---|---|
| 透析前 | 140 mmHg 未満 | 90 mmHg 未満 |
| 透析後 | 100 mmHg 以上 | – |
家庭血圧の目標値
透析室での血圧は一時的なものであるため、普段の血圧の状態を把握するには家庭での血圧測定が非常に大切です。家庭血圧は、透析の影響が少ない状態で測定できるため、より実態に近い血圧を反映します。
家庭血圧の降圧目標
| 対象 | 収縮期血圧(上の血圧) | 拡張期血圧(下の血圧) |
|---|---|---|
| 75歳未満の成人 | 130 mmHg 未満 | 80 mmHg 未満 |
| 75歳以上の高齢者 | 140 mmHg 未満 | 90 mmHg 未満 |
家庭での血圧測定の重要性と正しい方法
透析患者の血圧管理において、家庭での血圧測定は不可欠な要素です。毎日の血圧を記録することで、医師はより適切な治療方針を立てることができます。正確な血圧を測定するためには、正しい方法で測定することが大切です。
家庭血圧が示す本当の血圧
病院や透析施設で測定すると、緊張などから普段より血圧が高くなる「白衣高血圧」という現象が起こることがあります。家庭ではリラックスした状態で測定できるため、日常生活における真の血圧値を把握できます。
この家庭血圧のデータが、降圧薬の調整やドライウェイトの評価に役立ちます。
正しい血圧測定の手順
正確な値を測るために、測定時の環境や手順を守りましょう。血圧計は、腕にカフを巻く「上腕式」のものが推奨されます。
血圧測定時の注意点
| 項目 | 正しい方法 | 避けるべきこと |
|---|---|---|
| タイミング | 朝(起床後1時間以内、排尿後、朝食・服薬前)、夜(就寝前)の2回 | 入浴直後、食事直後、運動直後、喫煙・飲酒直後 |
| 環境・姿勢 | 静かな部屋で、椅子に座り1~2分安静にしてから測定。腕は心臓の高さに。 | 会話しながらの測定、寒い部屋での測定、脚を組んだ姿勢 |
| その他 | 毎日同じ時間帯に測定する。シャントのある腕では測定しない。 | 複数回続けて測定する(測定後は少し時間を空ける) |
測定結果の記録と共有
測定した血圧値(収縮期血圧、拡張期血圧)と脈拍数は、必ず血圧手帳などに記録してください。測定した日付と時間も一緒に記録します。体調の変化や気になったことがあれば、メモしておくと良いでしょう。
この記録は、透析施設を受診する際に必ず持参し、医師やスタッフに見せてください。貴重な情報源となります。
血圧を安定させる日常生活の注意点
薬物療法や食事療法に加え、日々の生活習慣を見直すことも血圧管理には重要です。心身ともに健やかな状態を保つことが、血圧の安定につながります。
適度な運動のすすめ
体調が良い日には、無理のない範囲で体を動かすことを心がけましょう。運動には、血圧を下げ、心肺機能を高め、ストレスを解消する効果が期待できます。
透析患者に適した運動としては、ウォーキングや軽い体操などがあります。
推奨される運動の例
| 運動の種類 | ポイント |
|---|---|
| ウォーキング | 少し汗ばむ程度で、会話ができるくらいの速さで。1回15~30分程度。 |
| ストレッチ・体操 | 血行を促進し、筋肉の緊張をほぐす。非透析日に行うのが良い。 |
運動を始める前には、必ず主治医に相談し、どの程度の運動が適切か指導を受けてください。
ストレス管理と十分な睡眠
精神的なストレスは、交感神経を刺激し、血圧を上昇させる原因になります。趣味の時間を持つ、リラックスできる環境を作るなど、自分なりのストレス解消法を見つけることが大切です。
また、睡眠不足も血圧に悪影響を及ぼします。規則正しい生活を送り、十分な睡眠時間を確保するよう努めましょう。
禁煙と節酒の徹底
喫煙は血管を収縮させて血圧を上昇させるだけでなく、動脈硬化を強力に促進します。透析患者にとって喫煙は百害あって一利なしです。禁煙は血圧管理の基本です。
喫煙がもたらす悪影響
- 血管収縮による血圧上昇
- 動脈硬化の促進
- 心筋梗塞・脳卒中リスクの増大
- シャントの閉塞リスク上昇
アルコールも適量を超えると血圧を上昇させます。飲酒については、必ず主治医に許可される量を確認し、それを厳守してください。
食事療法による血圧管理
透析患者の血圧管理において、食事療法は薬物療法と並んで最も重要な柱の一つです。特に「塩分」のコントロールは、血圧に直接影響します。
減塩の具体的な方法
目標とする塩分摂取量は、1日6g未満が推奨されています。加工食品や外食には多くの塩分が含まれているため、注意が必要です。自炊を基本とし、薄味に慣れる工夫をしましょう。
減塩のための調理の工夫
| 工夫 | 具体例 |
|---|---|
| 香辛料や香味野菜を利用する | コショウ、カレー粉、ショウガ、ニンニク、シソ、ネギなどを活用する |
| 酸味を利用する | 酢やレモン汁などを使い、味にアクセントをつける |
| だしを効かせる | 昆布やかつお節でしっかりだしを取り、素材の味を活かす |
カリウム・リンの管理
血圧管理とは直接的な関係が薄いように思えるかもしれませんが、カリウムやリンの管理も透析患者には重要です。これらの値が乱れると、不整脈や骨・血管の石灰化などを引き起こし、結果的に心血管系に負担をかけることになります。
カリウムは野菜や果物に、リンは乳製品や加工食品、タンパク質の多い食品に多く含まれます。医師や管理栄養士の指導のもと、適切な摂取量を守りましょう。
適切なエネルギーとタンパク質の摂取
食事制限が厳しいイメージのある透析治療ですが、生命維持に必要なエネルギーや体を作るタンパク質は十分に摂取する必要があります。エネルギーが不足すると、筋肉が分解されて体力が低下し、かえって体調を崩す原因になります。
タンパク質も制限が必要な場合がありますが、良質なタンパク質を適量摂ることが大切です。食事管理は自己判断で行わず、必ず専門家の指導に従ってください。
食事管理の基本ポイント
| 栄養素 | 管理のポイント |
|---|---|
| 塩分 | 厳格に制限する(6g/日未満が目標) |
| 水分 | 透析間の体重増加量を基準に管理する |
| カリウム・リン | 血液検査のデータに基づき、医師・管理栄養士の指導に従う |
| エネルギー・タンパク質 | 不足しないように、適量をしっかり摂取する |
よくある質問
最後に、透析患者さんの血圧管理に関するよくあるご質問にお答えします。
- 透析の日は降圧薬を飲みますか?
-
自己判断で中止したり、量を変更したりしないでください。透析日は血圧が下がりやすいため、朝の降圧薬を中止する指示が出ることが多いですが、これは患者さん一人ひとりの状態によって異なります。
必ず主治医や施設のスタッフの指示に従ってください。不明な点があれば、事前に確認しておくことが大切です。
- 血圧が低い日はどうすればよいですか?
-
まずは安静にして、めまいやふらつきがある場合は横になってください。家庭で血圧を測定し、普段より著しく低い場合や、体調がすぐれない場合は、かかりつけの透析施設に連絡して指示を仰いでください。
特に、透析のない日に血圧が低いからといって、自己判断で塩分を多く摂ることは避けてください。
- 家庭用血圧計はどれを選べばよいですか?
-
手首式よりも測定値が安定しやすい「上腕式」の血圧計を選んでください。国際的な精度基準を満たしていると認証された製品を選ぶと、より安心です。
シャントのない腕の太さに合った、適切なサイズのカフ(腕帯)を使用することも正確な測定のために重要です。
- 体重管理と血圧にはどんな関係がありますか?
-
透析患者の体重管理、特に透析と透析の間の体重増加の管理は、血圧管理とほぼ同義です。体重増加が大きいということは、それだけ体内に水分が溜まっていることを意味し、これが直接的に血圧を上昇させます。
日々の体重測定と塩分・水分管理を徹底し、体重増加を抑えることが、高血圧を防ぐ最も効果的な方法の一つです。
以上
透析センター(人工透析) | 大垣中央病院(医療法人社団豊正会 )
参考文献
JINDAL, Kailash, et al. Management of blood pressure in hemodialysis patients. Journal of the American Society of Nephrology, 2006, 17.3_suppl_1: S8-S10.
MISKULIN, Dana C.; WEINER, Daniel E. Blood pressure management in hemodialysis patients: what we know and what questions remain. In: Seminars in dialysis. 2017. p. 203-212.
AGARWAL, Rajiv. Management of hypertension in hemodialysis patients. Hemodialysis International, 2006, 10.3: 241-248.
MAZZUCHI, Nelson; CARBONELL, Enriqueta; FERNÁNDEZ-CEAN, Juan. Importance of blood pressure control in hemodialysis patient survival. Kidney international, 2000, 58.5: 2147-2154.
SANTORO, Antonio, et al. Blood volume controlled hemodialysis in hypotension-prone patients: a randomized, multicenter controlled trial. Kidney international, 2002, 62.3: 1034-1045.
DAUL, Anton E., et al. Arterial hypotension in chronic hemodialyzed patients. Kidney international, 1987, 32.5: 728-735.
RAM, C. Venkata S.; FENVES, Andrew Z. Management of hypertension in hemodialysis patients. Current hypertension reports, 2009, 11.4: 292-298.
RAHMAN, Mahboob, et al. Factors associated with inadequate blood pressure control in hypertensive hemodialysis patients. American journal of kidney diseases, 1999, 33.3: 498-506.
AGARWAL, Rajiv. Blood pressure and mortality among hemodialysis patients. Hypertension, 2010, 55.3: 762-768.
AGARWAL, Rajiv, et al. Prevalence, treatment, and control of hypertension in chronic hemodialysis patients in the United States. The American journal of medicine, 2003, 115.4: 291-297.