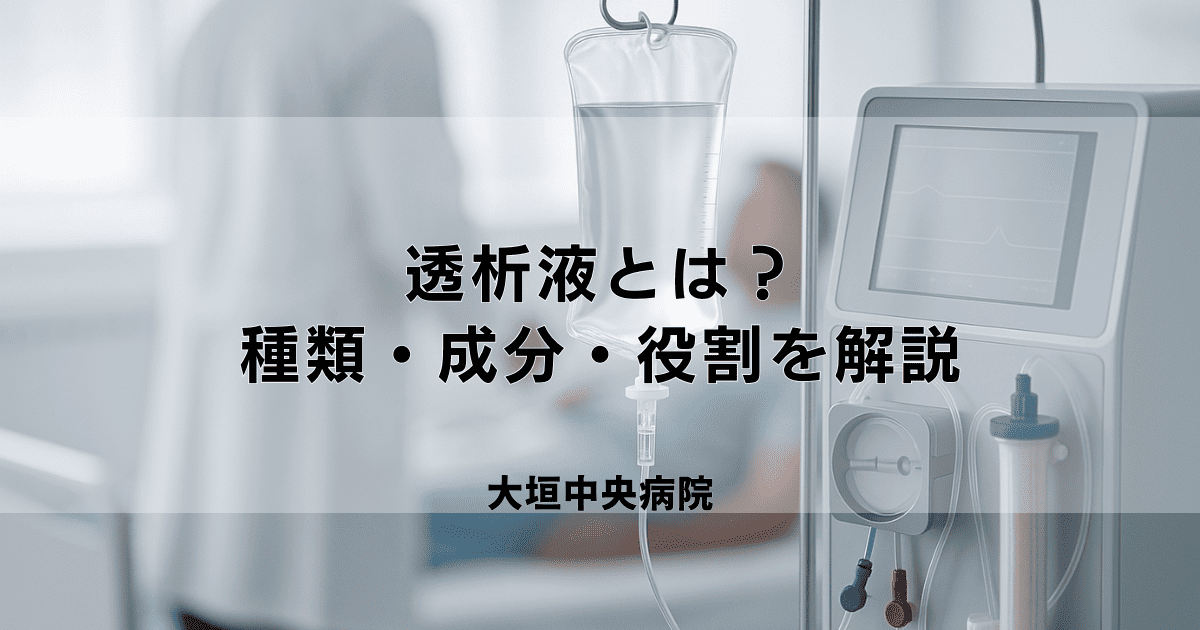血液透析治療を受けるにあたり、血液をきれいにするために使われる透析液がどのようなもので、なぜ重要なのでしょうか。
この記事では、透析治療の要ともいえる透析液について、その基本的な役割から、含まれている成分、知っておきたい種類と特徴、そして安全性を保つための基準まで、専門的な内容を詳しく解説します。
そもそも透析液とは?生命維持に欠かせない正体
血液透析の中心的な役割を担う透析液は、単なるきれいな水ではありません。患者さんの体を健やかな状態に近づけるため、精密に調整された特別な液体です。
透析治療における透析液の位置づけ
血液透析は、機能が低下した腎臓に代わって、血液中の老廃物や余分な水分を取り除く治療法です。治療は、ダイアライザー(透析器)と呼ばれる特殊なフィルターを通して血液を循環させることで行います。
ダイアライザーの内部では、血液が通る極めて細い管の外側を透析液が流れていて、この時、血液と透析液は直接混じり合うことはありません。半透膜という非常に薄い膜を隔てて接しており、この膜を介して物質のやり取りが行われます。
つまり、透析液は血液をきれいにするための洗浄液のような働きを担っており、透析治療の成果を左右する極めて重要な要素です。
透析液はきれいな水と薬剤を混ぜて作られる
透析液は、透析用水と呼ばれる非常に清浄な水と、電解質やブドウ糖などを含む濃縮された薬剤(透析原液)を、透析装置で正確に混合して作られます。水道水をそのまま使うことは決してありません。
水道水に含まれる微量の金属や塩素、細菌などは、透析を受ける患者さんにとって有害となる可能性があるため、何段階ものフィルターや処理を経て、厳格な基準をクリアした透析用水が作られます。
超純水に近い水に、体の状態を整えるための成分が含まれた原液を混ぜ合わせることで、安全で効果的な透析液が完成するのです。
透析原液のA液とB液
透析原液は、一般的にA液とB液の2種類に分かれています。これは、特定の成分を一緒に濃縮すると、化学反応を起こして沈殿物を作ってしまうためです。
A液には主にブドウ糖、ナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウムなどが、B液にはアルカリ化剤である炭酸水素ナトリウムが含まれています。
治療の直前に、これら2つの原液と透析用水を装置内で混合することで、常に新鮮な透析液が供給される仕組みになっています。
なぜ一人ひとりに合わせた透析液が必要なのか
人の体格や食事内容、合併症の有無が一人ひとり違うように、血液の状態も患者さんによって様々です。ある患者さんにとっては適切な透析液の成分濃度が、別の患者さんにとっては不適切である場合があります。
血液中のカリウム値が高い患者さんにはカリウム濃度が低い透析液を、低い患者さんには逆に高い透析液を使用する必要があります。
個々の患者さんの血液検査データや体調に合わせて透析液の成分を微調整する、いわばオーダーメイドの治療が、安全で快適な透析ライフには大切です。
透析液が果たす3つの重要な役割
透析液は、ダイアライザー内で血液と接することで、主に3つの重要な役割を果たします。これらの働きは、物理的な原理に基づいており、機能が低下した腎臓の仕事を代行するために精密に設計されています。
体内の老廃物を取り除く(拡散)
健康な腎臓は、尿素やクレアチニン、尿酸といったタンパク質の燃えカス(老廃物)を尿として体外に排出しますが、腎機能が低下すると、これらの老廃物が血液中に溜まり、尿毒症という危険な状態を起こします。
透析液の最も重要な役割の一つが、この溜まった老廃物を効率的に取り除くことです。
拡散の原理
この老廃物の除去は、拡散という物理現象を利用して行われ、拡散とは、濃度の高い方から低い方へ物質が自然に移動する性質のことです。
透析液には老廃物が一切含まれていないため、老廃物の濃度は血液中が非常に高く、透析液中がゼロになります。この濃度差によって、老廃物は半透膜を通過して血液側から透析液側へと移動していきます。
電解質のバランスを整える(拡散)
電解質とは、ナトリウム、カリウム、カルシウムなど、体液に溶けて電気を帯びるミネラルのことで、神経の伝達や筋肉の収縮など、生命活動の根幹を支える重要な働きをしています。
腎機能が低下すると、これらの電解質のバランスが崩れやすくなります。
電解質異常が引き起こす問題
カリウムが過剰になると不整脈や心停止の危険があり、カルシウムやリンのバランスが崩れると骨がもろくなるなどの問題が生じます。透析液には、電解質が正常な血液に近い濃度で含まれています。
老廃物と同じく拡散の原理によって、血液中の濃度が高い電解質は透析液側へ移動し、逆に濃度が低い電解質は透析液側から血液側へ補充されます。相互作用により、体内の電解質バランスが適切な状態に調整されるのです。
透析液と血液の電解質バランス調整
| 電解質 | 血液中の濃度が高い場合 | 血液中の濃度が低い場合 |
|---|---|---|
| カリウム(K) | 血液 → 透析液へ移動 | 透析液 → 血液へ移動 |
| カルシウム(Ca) | 血液 → 透析液へ移動 | 透析液 → 血液へ移動 |
| リン(P) | 血液 → 透析液へ移動 | (透析液には含まれない) |
余分な水分を除去する(限外ろ過)
腎機能が低下すると尿量が減るため、体内に水分が溜まりやすくなります。余分な水分は、むくみや高血圧、心不全の原因となるため、透析治療で適切に取り除く必要があり、水分除去の働きを限外ろ過と呼びます。
限外ろ過の原理
限外ろ過では、透析装置で透析液側に圧力をかけて、血液側から水分を物理的に引き抜きます。コーヒーフィルターでコーヒーを淹れる際に、お湯がコーヒーの粉を通って下に落ちる様子をイメージすると分かりやすいかもしれません。
透析治療では、治療時間や目標とする体重(ドライウェイト)に合わせて、除去する水分量を正確に設定します。
透析液の基本となる成分と働き
透析液は、体の内部環境を整えるために、様々な成分が絶妙なバランスで配合されています。ここでは、代表的な成分である電解質、アルカリ化剤、そしてブドウ糖の役割について、一つひとつ詳しく見ていきましょう。
電解質(ナトリウム・カリウム・カルシウムなど)
電解質は、体の水分量を調整したり、神経や筋肉の働きを正常に保ったりするために重要な成分です。透析液に含まれる電解質は、患者さんの血液中の濃度を正常範囲に近づけるよう調整されています。
ナトリウム(Na)
ナトリウムは、体内の水分バランスや血圧の調整に深く関わっています。
透析液のナトリウム濃度は、血圧の安定化や透析中の不快な症状の軽減を目的として、患者さんごとに調整され、正常な血清ナトリウム値に近い濃度に設定することが一般的です。
カリウム(K)
カリウムは、心臓の筋肉をはじめとする全身の筋肉の働きに重要な役割を果たし、腎機能が低下すると体外への排出が滞り、高カリウム血症になりやすい傾向があります。
高カリウム血症は命に関わる不整脈を起こす可能性があるため、透析でしっかりと除去する必要があるため、多くの患者さんでは、血液よりも低いカリウム濃度の透析液を使用します。
カルシウム(Ca)
カルシウムは、骨の健康を維持するほか、血液凝固や筋肉の収縮にも関与しています。透析患者さんはカルシウムやリンの代謝異常を起こしやすく、骨がもろくなったり、血管に石灰化が起きたりすることがあります。
透析液のカルシウム濃度は、これらの合併症を予防・改善するために、薬物療法と合わせて慎重に調整することが重要です。
主な電解質の役割と調整目的
| 電解質 | 主な役割 | 透析液での調整目的 |
|---|---|---|
| ナトリウム (Na) | 体液量、血圧の調整 | 血圧の安定、循環動態の維持 |
| カリウム (K) | 神経・筋肉の働き、心機能 | 高/低カリウム血症の是正 |
| カルシウム (Ca) | 骨の形成、血液凝固 | 骨代謝異常の管理、心血管石灰化の抑制 |
体を弱アルカリ性に保つアルカリ化剤
健康な人の血液は、pH7.4前後の弱アルカリ性に保たれていますが、腎機能が低下すると、体内で作られる酸を十分に排出できなくなり、血液が酸性に傾く代謝性アシドーシスという状態になります。
アシドーシスは、倦怠感や吐き気、骨がもろくなるなどの原因です。
なぜアルカリ化剤が必要か
酸性に傾いた血液を正常な弱アルカリ性に戻すために、透析液にはアルカリ化剤が含まれています。
アルカリ化剤が透析液から血液中へ補充されることで、体内の酸が中和されアシドーシスが是正され、全身の様々な機能が正常に働くための土台が整えられます。
炭酸水素ナトリウムの役割
現在、日本の透析医療で主に使用されているアルカリ化剤は、炭酸水素ナトリウム(重曹)です。これは、もともと体内に存在する物質であり、安全性が高いと考えられています。
透析液のアルカリ化剤濃度は、患者さんのアシドーシスの程度に応じて調整されます。
浸透圧を調整するブドウ糖(グルコース)
透析液には、エネルギー源としても知られるブドウ糖(グルコース)も含まれていますが、透析液におけるブドウ糖の主な役割はエネルギー補給ではなく、浸透圧の調整です。
ブドウ糖の濃度と役割
浸透圧とは、膜を介して水分を引き寄せようとする力のことです。透析液の浸透圧を血液に近づけることで、急激な水分移動による血圧低下などを防ぎ、治療を安定して行うことができます。
通常、透析液のブドウ糖濃度は、正常な血糖値に近い100mg/dL前後に設定されます。ただし、糖尿病の患者さんなど、血糖値の管理が必要な場合には、より高い濃度のブドウ糖を含む透析液を使用することもあります。
透析液のブドウ糖濃度と主な目的
| ブドウ糖濃度 (mg/dL) | 主な対象 | 目的 |
|---|---|---|
| 100~125 | 多くの患者さん | 浸透圧の維持、低血糖の予防 |
| 150~175 | 糖尿病患者さんなど | 血糖値の安定、透析中の低血糖予防 |
| 0(無糖) | 特殊な場合 | 高血糖の是正 |
透析液の主な種類とそれぞれの特徴
透析液は、含まれる成分の違いによっていくつかの種類に分けられます。現在、日本で主に使用されているのは、酢酸を含む透析液と含まない透析液です。
酢酸を含む透析液(酢酸透析液)
古くから広く使われている標準的な透析液です。ごく微量の酢酸が含まれていて、透析液のpHを安定させ、カルシウムやマグネシウムが沈殿するのを防ぐという重要な役割があります。
酢酸の役割とメリット
酢酸は、透析液の品質を保ちやすく、安定した治療を可能にするというメリットがあり、また、体内で代謝されてエネルギー源になるという側面もあります。長年の使用実績があり、多くの施設で基本的な透析液として採用されています。
酢酸による体への影響
一方で、一部の患者さんでは、透析液に含まれる酢酸が原因で、透析中に血圧が低下したり、気分が悪くなったりすることがあります。これは、酢酸が血管を拡張させる作用を持つためです。
特に、心臓の機能が低下している方や、血圧が不安定な方にとっては、酢酸の影響が問題となる場合があります。
酢酸を含まない透析液(無酢酸透析液)
酢酸透析液が体に合わない患者さんのために開発されたのが、酢酸を一切含まない透析液です。代表的なものにカーボスターがあり、酢酸の代わりにクエン酸などを少量加えることで、pHの安定化を実現しています。
無酢酸透析液が開発された背景
より体に優しく、循環動態が不安定な患者さんでも安心して治療を受けられるようにすることを目指して開発されました。酢酸による血圧低下などの副作用が起こりにくいため、透析中の体調をより安定させることが期待できます。
カーボスター®︎の特徴と利点
無酢酸透析液であるカーボスターは、酢酸を含まないため、透析中の血圧低下が起こりにくいとされています。また、栄養状態の改善や、体内の炎症を抑える効果も報告されており、より質の高い透析治療の選択肢として注目されています。
- 血圧の安定化
- 心臓への負担軽減
- 栄養状態の改善
酢酸透析液と無酢酸透析液の比較
| 項目 | 酢酸透析液 | 無酢酸透析液(カーボスター®︎) |
|---|---|---|
| 安定化剤 | 酢酸 | クエン酸など |
| 利点 | 安定性が高い、安価 | 血圧が安定しやすい、体に優しい |
| 考慮点 | 血圧低下、不快症状の可能性 | コストが比較的高め |
オンラインHDFで使われる補充液
近年、より多くの老廃物を除去できる治療法として、オンライン血液透析ろ過(オンラインHDF)が普及しています。この治療法では、通常の透析液に加えて、補充液という液体が重要です。
オンラインHDFとは
オンラインHDFは、通常の血液透析(HD)の拡散に加えて、ろ過という原理を大量に利用して水分を多めに除去し、その分を補充液で補いながら治療を行う方法です。
この方法により、通常の透析では除去しにくい、少し大きめの老廃物まで取り除くことができ、関節痛やかゆみ、貧血の改善などが期待できます。
補充液としての透析液
オンラインHDFで使われる補充液は、実は透析液そのものです。治療に使用している透析液を、さらに厳格な基準で清浄化したものを、直接血管内に補充します。
そのため、オンラインHDFを行う施設では、極めて高いレベルでの透析液の水質管理が求められ、超純粋透析液を補充液として使用することで、安全かつ効果的な治療が可能となるのです。
患者さんの状態に合わせた透析液の調整
透析液は既製品をそのまま使うだけでなく、患者さん一人ひとりの体の状態に合わせて、成分濃度を細かく調整し、これを透析液の処方と呼びます。適切な処方を行うことが、長期的に良好な健康状態を維持する鍵です。
なぜ透析液の調整(処方)を行うのか
透析治療の目的は、ただ老廃物を除去するだけではありません。乱れた体内の環境を、できるだけ正常な状態に近づけることも同じくらい重要です。
そのためには、画一的な透析液ではなく、個々の状態に最適化された透析液を用いることが大事になります。
血液検査データに基づく判断
医師や医療スタッフは、毎月の定期的な血液検査の結果を注意深く確認し、血液中のカリウム、カルシウム、リン、アルブミンなどの値を見て、現在の透析液の処方が適切かどうかを評価します。
数値に異常が見られる場合、食事指導と合わせて透析液の成分濃度を見直すことがあります。
体調や合併症の考慮
血液データだけでなく、患者さんの日々の体調も重要な判断材料です。透析中の血圧変動、足のつり、倦怠感などの症状や、糖尿病、心疾患、骨粗しょう症といった合併症の有無や進行度も考慮に入れて、総合的に透析液の処方を決定します。
具体的にどの成分濃度を調整するのか
透析液の処方では、主に電解質やブドウ糖の濃度が調整の対象となり、ここでは代表的な調整例を紹介します。
カリウム濃度の調整
高カリウム血症の傾向がある患者さんには、カリウム濃度が低い透析液(例 2.0mEq/L)を、逆に食事が十分に摂れず低カリウム血症のリスクがある患者さんには、高めの濃度の透析液(例 3.0mEq/L)を使用することがあります。
カルシウム濃度の調整
骨代謝の薬物治療の内容に応じて、透析液のカルシウム濃度を調整します。
活性型ビタミンD製剤を使用している場合は、高カルシウム血症を防ぐために低めの濃度(例 2.5mEq/L)に、カルシウム値が低い場合は高めの濃度(例 3.0mEq/L)に設定することがあります。
ブドウ糖濃度の調整
糖尿病を合併している患者さんで、透析中に血糖値が下がりやすい場合には、ブドウ糖濃度が高い透析液(例 150mg/dL)を使用することで、低血糖の発作を予防します。
透析液の成分調整例
| 調整する成分 | 患者さんの状態 | 調整の方向性 |
|---|---|---|
| カリウム(K) | 高カリウム血症 | 透析液のK濃度を低くする |
| カルシウム(Ca) | 骨代謝異常、薬物療法の内容 | 透析液のCa濃度を高く、または低くする |
| ブドウ糖 | 糖尿病、低血糖のリスク | 透析液のブドウ糖濃度を高くする |
透析液の温度管理も重要
成分濃度だけでなく、透析液の温度も治療の快適性や安定性に影響を与える要素です。一般的には体温に近い36℃前後に設定しますが、患者さんによっては少し低めの温度に設定することで、透析中の血圧低下を予防する効果が期待できます。
透析液の安全性を保つための基準と管理
透析液は、治療中に広大な面積の半透膜を介して血液と接するため、品質は極めて清浄でなければなりません。透析液の安全性を確保することは、安全な透析治療の絶対条件です。
透析液の清浄化が極めて重要な理由
透析液が細菌やその毒素で汚染されていると、それらが透析膜を通過して血液中に入り込み、様々な健康被害を起こす可能性があります。特に問題となるのが、エンドトキシンと呼ばれる物質です。
エンドトキシンとは何か
エンドトキシンは、グラム陰性菌という種類の細菌の細胞壁に含まれる毒素です。この物質が血液中に入ると、発熱や炎症反応を起こします。
長期間にわたって微量のエンドトキシンにさらされ続けると、慢性的な炎症状態となり、動脈硬化の進行、栄養状態の悪化、アミロイドーシスといった長期合併症のリスクを高めることが知られています。
清浄化されていないリスク
透析液の清浄度が低いと、以下のようなリスクが高まります。
- 発熱、悪寒などの急性炎症反応
- 慢性的な微小炎症による合併症(動脈硬化、心血管疾患)
- 透析アミロイドーシスの進行
- 貧血の悪化(エリスロポエチン製剤の効果減弱)
リスクを避けるため、透析液の清浄化は徹底して行われます。
日本透析医学会が定める水質基準
日本では、安全な透析治療を担保するために、日本透析医学会が透析液に関する厳格な水質基準を定めていて、すべての透析施設は、この基準を遵守することが義務付けられています。
エンドトキシン濃度の基準値
基準では、透析液中のエンドトキシン濃度が厳しく定められています。特に、オンラインHDFのように透析液を補充液として体内に直接注入する治療では、注射用水と同等の極めて清浄なレベル(超純粋透析液)が必要です。
生菌数の基準値
エンドトキシンの元となる細菌そのものの数(生菌数)についても、厳しい基準が設けられています。細菌が繁殖しないよう、透析液の供給システム全体を清潔に保つことが重要です。
透析液の水質基準(日本透析医学会)
| 項目 | 標準的な透析液 | 超純粋透析液(オンラインHDF用) |
|---|---|---|
| エンドトキシン濃度 | 0.05 EU/mL 未満 | 0.001 EU/mL 未満 |
| 生菌数 | 100 CFU/mL 未満 | 0.1 CFU/mL 未満 |
※EU: エンドトキシンユニット, CFU: コロニー形成単位
医療施設における厳格な管理体制
この厳しい水質基準を維持するために、透析施設では様々な取り組みを行っています。透析液の安全性は、目に見えない部分での地道な努力によって支えられています。
定期的な水質検査
透析液供給システムの末端(透析装置への接続部)で定期的に透析液を採取し、エンドトキシン濃度と生菌数の測定を行い、常に基準をクリアしていることを確認しています。
透析関連機器のメンテナンス
透析用水を作成する装置や透析液を供給する配管、そして各透析装置に対して、定期的な洗浄・消毒・部品交換といったメンテナンスを計画的に実施します。特に、細菌が繁殖しやすい箇所は入念な管理が必要です。
透析液に関するよくある質問(FAQ)
最後に、患者さんから寄せられることの多い、透析液に関する質問と回答をまとめました。
- 透析液が体の中に入ることはありますか?
-
通常の血液透析(HD)では、主に拡散の原理で物質のやり取りが行われますが、水分の移動に伴い、一部の電解質などが透析液から血液側へ移動します。
また、オンライン血液透析ろ過(オンラインHDF)という治療法では、老廃物をより効率的に除去するために、清浄化された透析液(補充液)を意図的に血液中に補充します。
いずれの場合も、体に入ることを前提とした極めて安全な液体が使用されているため、心配は要りません。
- 透析液の種類は自分で選べますか?
-
透析液の種類の選択は、医師が患者さん一人ひとりの血液検査データ、体調、合併症、透析中の血圧などを総合的に評価して決定する医療行為です。そのため、患者さんが自由に選ぶことは基本的にはできません。
しかし、現在の治療で何か気になる症状(血圧低下、不快感など)がある場合は、遠慮なく医師やスタッフに相談してください。
- 透析液の味がすることはありますか?
-
通常、透析液の味がすることはありません。透析液と血液は直接混ざるわけではなく、半透膜を介して物質が移動するためです。
もし治療中に口の中で何か異常な味を感じるようなことがあれば、それは別の原因が考えられるため、すぐに医療スタッフに伝えてください。
- 自宅での腹膜透析で使う透析液も同じものですか?
-
腹膜透析(PD)で使う透析液は、血液透析(HD)のものとは成分や目的が少し違います。
腹膜透析液は、患者さん自身がお腹に入れたカテーテルから腹腔内に注入し、ブドウ糖濃度を高くすることで浸透圧を高め、腹膜を介して体から余分な水分や老廃物を除去します。
血液透析液のように機械で循環させるのではなく、一定時間お腹の中に貯留させて使用する、滅菌済みのバッグに入った製品です。
以上
透析センター(人工透析) | 大垣中央病院(医療法人社団豊正会 )
参考文献
Rippe B, Venturoli D. Optimum electrolyte composition of a dialysis solution. Peritoneal Dialysis International. 2008 Jun;28(3_suppl):131-6.
Hoenich NA, Levin R, Ronco C. How do changes in water quality and dialysate composition affect clinical outcomes?. Blood purification. 2009 Jan 23;27(1):11-5.
Locatelli F, Covic A, Chazot C, Leunissen K, Luno J, Yaqoob M. Optimal composition of the dialysate, with emphasis on its influence on blood pressure. Nephrology Dialysis Transplantation. 2004 Apr 1;19(4):785-96.
Sam R, Vaseemuddin M, Leong WH, Rogers BE, Kjellstrand CM, Ing TS. Composition and clinical use of hemodialysates. Hemodialysis International. 2006 Jan;10(1):15-28.
Abdulla JE, Shakor JK, Shallal AF, Kheder R. Effect of dialysis on some Hematological and Electrolyte parameters in chronic kidney patients. Annals of Tropical Medicine and Public Health. 2020;23(11):9-13.
Liberek T, Topley N, Jörres A, Coles GA, Gahl GM, Williams JD. Peritoneal dialysis fluid inhibition of phagocyte function: effects of osmolality and glucose concentration. Journal of the American Society of Nephrology. 1993 Feb 1;3(8):1508-15.
Tzamaloukas AH, Ing TS, Siamopoulos KC, Raj DS, Elisaf MS, Rohrscheib M, Murata GH. Pathophysiology and management of fluid and electrolyte disturbances in patients on chronic dialysis with severe hyperglycemia. InSeminars in Dialysis 2008 Sep (Vol. 21, No. 5, pp. 431-439). Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd.
GAULT MH, Ferguson EL, Sidhu JS, Corbin RP. Fluid and electrolyte complications of peritoneal dialysis: choice of dialysis solutions. Annals of Internal Medicine. 1971 Aug 1;75(2):253-62.
Aucella F, Di Paolo S, Gesualdo L. Dialysate and replacement fluid composition for CRRT. Contributions to Nephrology. 2007 Jan 1;156(R):287.
Ramirez G, Bercaw BL, Butcher DE, Mathis HL, Brueggemeyer C, Newton JL. The role of glucose in hemodialysis: the effects of glucose-free dialysate. American Journal of Kidney Diseases. 1986 May 1;7(5):413-20.