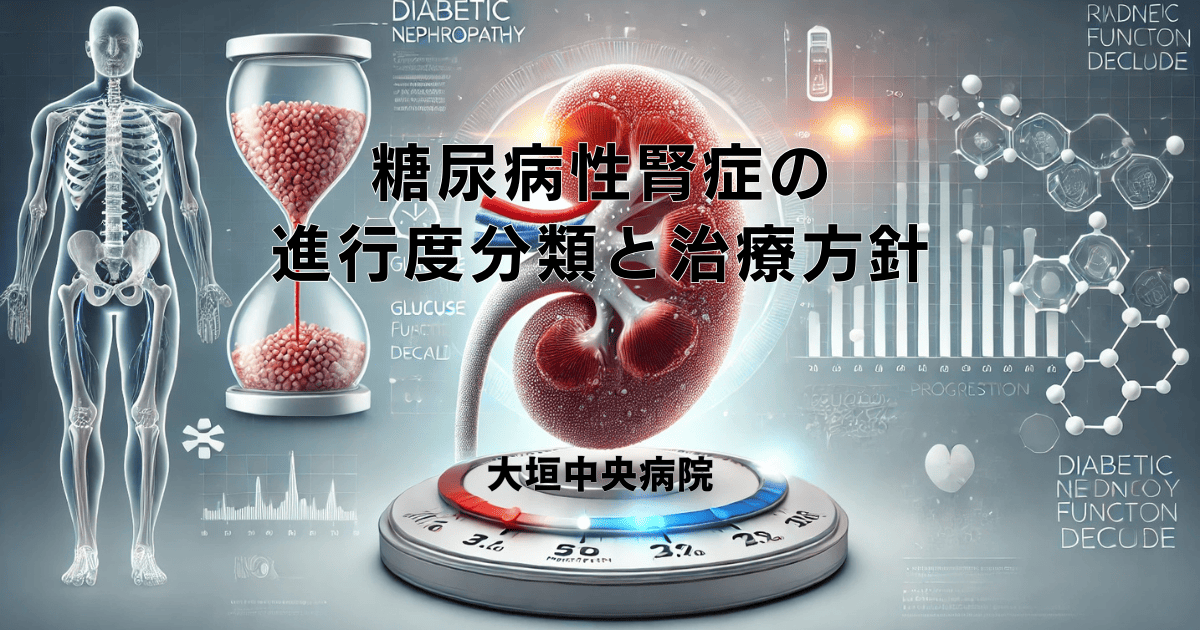糖尿病を長く患っていると、腎臓の機能に少しずつ負担がかかり、やがては腎症へと進行しやすくなります。特に糖尿病性の腎症は、初期の段階では自覚症状に乏しいものの、症状が進行すると透析が必要となるケースも見られます。
そのため、腎症2期や腎症3期の段階でどのような兆候があるかを把握し、適切に治療や生活管理を行うことが大切です。
この記事では、糖尿病性腎症の進行度分類や症状、腎症2期や腎症3期における具体的な治療方針について詳しく解説いたします。
糖尿病性腎症とは
糖尿病からくる腎症は、血液中の糖分が高い状態(高血糖)が長く続くことによって腎臓の微小血管が傷つき、機能低下を引き起こす病気です。血管障害が進むと、やがて腎臓のろ過機能が低下し、老廃物を十分に排出できなくなります。
重症化すると、人工的に老廃物を取り除く透析の導入を検討する必要が出てきます。
病気の概要
糖尿病性の腎トラブルは、尿中へのタンパク質漏出や浮腫(むくみ)、血圧上昇などを伴います。初期段階では「尿アルブミン」の微量な増加から始まり、腎症2期、腎症3期などへ進行していくほど尿蛋白やクレアチニン値が顕著に変化します。
生活習慣の改善や内服薬の調整で進行を遅らせることが可能ですが、適切な治療を開始するタイミングを逃すと、腎機能が大幅に低下してしまうおそれがあります。
病態の特徴
糖尿病性の腎症は、おもに血管内皮の障害によって起こります。血糖値の上昇が慢性的に続くと、毛細血管が硬くなり、ろ過機能を担う糸球体がダメージを受けやすくなります。
さらに血圧の上昇や脂質異常などの併存疾患があると、症状が一層進みやすい傾向があります。
早期発見の意義
症状が軽い段階で腎症を発見できれば、薬物療法や食事療法、日常生活上の注意によって腎機能の低下を緩やかにすることが期待できます。
逆に、糖尿病と診断されてから長い間放置してしまうと、気づいたときにはすでに腎症3期やそれ以降の段階に達しており、透析を検討しなければならないこともあります。医師の管理のもと、定期的な尿検査と血液検査を受けることが重要です。
糖尿病性腎症の主な特徴一覧
| 特徴 | 内容 |
|---|---|
| 血糖コントロール不良 | 慢性の高血糖が腎機能を損なう要因となる |
| 尿アルブミン増加 | 腎症2期以降で顕著に増加しやすい |
| 血圧上昇 | 高血圧が腎障害をさらに悪化させる |
| 透析のリスク | 進行すると腎代替療法が必要となる |
腎症2期と3期に至る背景
糖尿病性の腎機能低下は段階的に進み、やがて腎症2期や腎症3期という段階に差しかかります。どのようなメカニズムを経て腎症2期・腎症3期に至るのかを把握することは、透析を回避するためにも意義があります。
腎症というと「いきなり腎臓が悪くなる」とイメージしがちですが、実際には血管障害や尿中タンパクの増加など、いくつもの背景要因が重なり合っています。
糖尿病による血管障害
糖尿病では血糖値が高い状態が続くことで、血管の壁が傷つきやすくなります。特に腎臓内の微小血管が硬化すると、糸球体の機能が徐々に低下します。
腎症2期に入るころには、微量アルブミン尿が明確になり始め、これが進むと腎症3期ではタンパク尿として捉えられるようになります。
尿中アルブミンの変化
腎臓のろ過機能が下がると、本来は血液中に留まるべきアルブミンなどのタンパク質が尿中へ漏れ出します。微量アルブミン尿から顕性アルブミン尿へと変化するにしたがって、腎症はより進行した段階へ移行していると判断できます。
eGFR低下のメカニズム
血液検査で腎機能を見る指標にeGFR(推算糸球体ろ過量)があります。これは年齢や性別、血清クレアチニン値などをもとに算出される数値で、低下すると腎臓が不要物を排出する能力が落ちていることを意味します。
腎症2期ではまだeGFRの急激な低下は少ないものの、腎症3期に至ると明確に数値の下がり方が進む傾向にあります。
腎症の主な進行過程
| 段階 | 尿アルブミン量 | eGFRの傾向 | 主な臨床所見 |
|---|---|---|---|
| 腎症2期 | 微量アルブミン尿 | わずかな低下 | 血圧や浮腫の軽度変化 |
| 腎症3期 | 顕性アルブミン尿 | 目立った低下 | 明確なタンパク尿 |
| 腎症4期以降 | 大量蛋白尿 | さらに低下が加速 | 腎不全や透析検討 |
腎症2期の症状と治療
腎症2期になると、微量アルブミン尿が確認され始めるため、糖尿病の合併症検査でこの変化を捉えることが治療のスタート地点になります。自覚症状はまだ少ない段階ですが、腎臓の負担は徐々に増大します。
腎症2期という比較的初期の段階からコントロールを始めると、腎症3期やそれ以降に至るスピードを大幅に緩やかにすることができます。
症状のあらわれ方
腎症2期は軽度から中等度の尿アルブミン増加が特徴ですが、尿量や排尿の色の変化など、はっきりとした自覚症状はほとんどありません。
血圧がやや上昇したり、軽度のむくみが出ることがありますが、慢性の糖尿病患者では日常的な症状として見過ごされる可能性もあります。
生活指導と薬物療法
食事面では糖質の管理に加えて、塩分摂取を控えめにすることやたんぱく質の過剰摂取を避ける工夫が必要です。運動療法も無理のない範囲で続けると血糖値や血圧の改善に寄与します。
薬物療法としては、血圧を管理する目的でARB(アンジオテンシンII受容体拮抗薬)やACE阻害薬などが用いられます。糖尿病治療薬も血糖コントロールの強化を図るために調整します。
腎症2期の治療ポイント一覧
- 血圧を管理する(上は130mmHg未満を目指す場合が多い)
- 適正な体重管理を行う(BMIが過剰に高くならないように注意)
- 塩分摂取量を減らし、血圧コントロールを補助する
- 血糖コントロールの目標値を医師と相談しながら設定する
検査頻度の目安
腎症2期では、尿中アルブミン量と血清クレアチニン値、eGFRを定期的にチェックします。個人差はありますが、3か月〜6か月ごとの検査で経過を追う方法が一般的です。
異常が認められれば早めに受診し、薬の調整や生活指導の見直しを行います。
腎症2期で確認したい主な検査項目
| 検査項目 | 意味 | 参考頻度 |
|---|---|---|
| 尿中アルブミン | 微量アルブミン尿の有無や増加度合い | 3か月ごと〜6か月ごと |
| 血清クレアチニン | 腎ろ過機能の目安 | 3か月ごと〜6か月ごと |
| eGFR | 腎機能全般の把握 | 3か月ごと〜6か月ごと |
| 血圧 | 腎臓への負担を予測 | 毎日または随時 |
腎症3期の症状と治療
腎症3期では、尿中のアルブミンが顕著に増え、検査データでも腎機能の低下が明確になります。自覚症状としては、むくみや倦怠感、夜間頻尿などが目立ち始める場合があります。
糖尿病の治療も一段と厳密なコントロールが求められ、同時に透析の準備を視野に入れるタイミングが近づきます。
自覚症状と注意点
腎症3期になると血圧がさらに上昇し、タンパク尿も顕著になります。むくみは下肢だけでなく、全身に及ぶ場合もあり、朝起きたときの顔のむくみが気になる方もいます。
疲れがとれにくくなる、貧血が進むなど、日常生活における体調管理が一段と難しくなる面があります。
透析を視野に入れるタイミング
腎症3期の時点ですぐに透析に入るわけではありませんが、ここから腎症4期へ進むかどうかは治療や生活習慣の管理にかかっています。
尿毒症の症状が顕在化する前に腎代替療法の準備を始めるかどうか、患者さんや家族と相談しながら方針を決めることが大切です。
透析開始の主な検討基準
| 要素 | 主な基準 |
|---|---|
| eGFR値 | 15〜30mL/min/1.73m²前後で要相談 |
| 血液所見 | BUNやクレアチニンの急上昇 |
| 臨床症状 | むくみ、倦怠感、食欲不振、貧血など |
| 心血管リスク | 高血圧や心不全の合併がある場合は早期判断 |
治療に関する選択肢
糖尿病薬に加えて、ARBやACE阻害薬で血圧管理を強化し、腎臓への負担を軽減します。食事療法では塩分制限だけでなく、たんぱく質摂取量にも注意する必要があります。
必要に応じて腎臓内科の専門医と相談しながら利尿薬などを活用し、浮腫や血圧をコントロールする場合もあります。
合併症への対処
腎症3期で注意したい合併症としては、心不全や脳卒中などの心血管疾患リスクが挙げられます。コレステロールの管理や、糖尿病網膜症の進行チェックなど、多方面にわたる合併症を同時に考慮することが重要です。
特に透析が近づくほど、体内の老廃物排出が不十分になるため、全身状態をこまめに観察することが望ましいでしょう。
血液透析と腹膜透析の基礎知識
腎症3期を越え、腎機能がさらに低下した場合は、腎臓の代わりに老廃物や余分な水分を取り除く方法として透析を検討します。大きく分けると、血液透析と腹膜透析の2種類があります。
それぞれに異なる利点と注意点があり、患者さん自身の生活スタイルや健康状態によって選択肢が変わることがあります。
血液透析の特徴
血液透析は、血液を体外に導いてダイアライザーと呼ばれる装置で老廃物や余分な水分を取り除く方法です。週に3回程度の通院を要する場合が多く、1回あたり4時間ほどかけて透析を行います。
メリットとしては、高いろ過効率が挙げられますが、時間的拘束や血管への負担、通院の手間がかかります。
血液透析に関する主なメリットと注意点
| メリット | 注意点 |
|---|---|
| 老廃物除去率が高い | 定期的な通院が必要 |
| 医療スタッフによる管理 | 針の穿刺に伴う痛みや血管障害 |
| 緊急時の対応がしやすい | 体外循環による疲労や低血圧 |
腹膜透析の特徴
腹膜透析は、自分の腹膜を利用して老廃物の除去を行う方法です。体内に透析液を一定時間留め、老廃物などが移行した透析液を交換します。自宅で行えるため自由度が高い一方で、自己管理の徹底が必要になります。
腹膜の炎症(腹膜炎)などのリスク管理にも注意が欠かせません。
どちらを選ぶか考える視点
血液透析か腹膜透析か、あるいはその両方を組み合わせるかは、患者さんの年齢、合併症の有無、通院環境などを総合的に勘案して決定します。たとえば、仕事や家事の都合で週3回の通院が難しい方は腹膜透析を選択することが多いです。
逆に医療スタッフによる管理を重視する方は血液透析を選びやすい傾向があります。
食事療法と日常生活の管理
腎症2期や腎症3期の段階から食事や生活習慣に配慮すると、透析の導入を遅らせたり、腎機能の残存率をできるだけ維持したりする助けになります。糖尿病性腎症では特に塩分とたんぱく質の管理が重要です。
適度な運動や休養を意識し、血圧や体重をコントロールすることも欠かせません。
食事のポイント
腎症2期や腎症3期の方の場合、1日の塩分摂取を6g前後に抑えることを目標とすることが多いです(個人差あり)。また、たんぱく質摂取量も体重1kgあたり0.8~1.0g程度(腎機能に応じて変動)を目安にするケースがよく見られます。
野菜や果物にはカリウムが豊富なものが多く、摂取の際には主治医や管理栄養士の指示に従って量や調理法を考慮してください。
1日の塩分量とたんぱく質摂取目安
| 項目 | 目安量 | 備考 |
|---|---|---|
| 塩分 | 6g前後 | 高血圧傾向や浮腫が強い場合にはさらに制限 |
| たんぱく質 | 体重1kgあたり0.8〜1.0g | 過度な制限は低栄養を招くため、医師の指示を仰ぐ |
運動と休養のバランス
過度な運動は腎臓への負担がかかる可能性があるため、ウォーキングや軽い筋力トレーニングなど、無理のない範囲で実践することが大切です。
生活が不規則にならないように睡眠リズムを整え、体力を温存することも腎機能を保つ上で意義があります。
禁煙・節酒の大切さ
喫煙は血管を収縮させ、腎臓を含む全身の臓器へ血液が行き渡りにくくなります。腎症だけでなく、心血管疾患や末梢血管障害を悪化させる原因にもなります。
アルコールの摂取量が過度になると高血圧につながり、腎臓への負担が増すことにも注意が必要です。
生活上気をつけたいポイントのまとめ
- 水分摂取量は過不足に注意し、医師の指示に沿う
- 長時間の立ち仕事や重労働は体に負担がかかる
- 喫煙習慣があれば早めの禁煙を目指す
- 飲酒量は適度を心がけ、血圧や肝機能にも配慮する
当院での総合的アプローチ
糖尿病性の腎症は、内科や腎臓内科だけでなく、栄養管理科やリハビリテーション科など、多職種が一体となって診療にあたる必要があります。
当院では、糖尿病そのものの治療だけでなく、腎症2期や腎症3期の段階ごとに適切な検査と生活指導を行い、患者さんの状態に応じてスムーズな治療連携を目指しています。
チーム医療の体制
医師、看護師、管理栄養士、薬剤師、理学療法士など、複数の専門スタッフが連携して患者さんをサポートします。
それぞれの視点から、食事制限や運動の仕方、薬の正しい服用方法などをアドバイスし、一人ひとりのライフスタイルに合った治療プランを立案します。
当院の連携体制概要
| スタッフ | 主な役割 |
|---|---|
| 医師 | 診断、治療方針の決定 |
| 看護師 | 日常のケアや健康相談、診療補助 |
| 管理栄養士 | 食事療法の提案、栄養評価 |
| 薬剤師 | 内服薬の選択と服用指導、副作用のチェック |
| 理学療法士 | 運動療法のプログラム作成とリハビリサポート |
早期介入と継続的フォロー
糖尿病性腎症は早期発見と早期治療が大切です。当院では、糖尿病と診断された方には定期的な腎機能検査を推奨しています。腎症2期や腎症3期と判断された場合は、頻度を高めて経過を観察し、必要に応じて投薬や生活指導の見直しをします。
患者さん自身にも検査結果を共有しながら、疑問点をその都度解消する体制を整えています。
定期検査の活用
血液検査や尿検査、超音波検査(エコー)などを組み合わせて腎臓の状態を総合的に評価します。特に血清クレアチニンやeGFRの変化を継続的に追うことで、腎症が進んでいるかどうかを判断します。
一定の基準を満たした時点で、透析の準備を始めるかどうかを主治医と患者さんが話し合いながら決めます。
当院で実施している主な検査スケジュール
| 検査名 | 実施頻度 | 特徴 |
|---|---|---|
| 尿検査(蛋白、アルブミン) | 1〜3か月に1回 | 腎機能変化の早期発見に有用 |
| 血清クレアチニン | 1〜3か月に1回 | 腎ろ過機能の動向を把握 |
| eGFR | 1〜3か月に1回 | 腎症2期・腎症3期の進行度合いを確認 |
| エコー検査 | 必要に応じて | 腎臓の形態異常や大きさをチェック |
よくある質問
- 腎症は改善できる?
-
腎症が進みきってしまうと回復は難しい場合が多いですが、腎症2期や腎症3期の段階なら腎機能の温存や進行を遅らせることは期待できます。
血糖管理や血圧管理、適切な食事制限などを続けることで、透析の開始を後ろ倒しにできる可能性があります。
- 透析は必須なの?
-
腎症3期でただちに透析を受けなければならないわけではありません。腎機能がさらに低下して腎症4期や5期になると透析や腎移植を検討する必要性が高まります。
ただし、腎症3期の段階であっても個々の症状や検査結果によっては早めの準備が望ましいケースもあるので、主治医と相談してください。
- 食事制限のコツは?
-
塩分やたんぱく質の制限が中心ですが、全体のカロリーを落としすぎると低栄養になるリスクがあります。管理栄養士と相談しながら、食材選びや調理法を工夫することが大切です。
味付けは香辛料や酸味を活用するなど、工夫すると無理なく続けやすくなります。
- 病院の受診タイミングは?
-
糖尿病と診断された段階で定期的に腎機能の検査を受けておくのが望ましいです。
腎症2期や腎症3期になってから症状がはっきり現れる場合もありますが、検査によって先回りして変化を捉え、適切な治療を始めたほうが負担を軽減できます。
自覚症状がなくても、定期検査の結果に注目しながら、体の変化を感じたら早めに受診してください。
以上
参考文献
SELBY, Nicholas M.; TAAL, Maarten W. An updated overview of diabetic nephropathy: Diagnosis, prognosis, treatment goals and latest guidelines. Diabetes, Obesity and Metabolism, 2020, 22: 3-15.
UMANATH, Kausik; LEWIS, Julia B. Update on diabetic nephropathy: core curriculum 2018. American journal of kidney diseases, 2018, 71.6: 884-895.
GROSS, Jorge L., et al. Diabetic nephropathy: diagnosis, prevention, and treatment. Diabetes care, 2005, 28.1: 164-176.
DOSHI, Simit M.; FRIEDMAN, Allon N. Diagnosis and management of type 2 diabetic kidney disease. Clinical Journal of the American Society of Nephrology, 2017, 12.8: 1366-1373.
DASGUPTA, Indranil, et al. Current management of chronic kidney disease in type‐2 diabetes—A tiered approach: An overview of the joint Association of British Clinical Diabetologists and UK Kidney Association (ABCD‐UKKA) guidelines. Diabetic medicine, 2025, 42.2: e15450.
AMERICAN DIABETES ASSOCIATION PROFESSIONAL PRACTICE COMMITTEE; AMERICAN DIABETES ASSOCIATION PROFESSIONAL PRACTICE COMMITTEE:. 11. Chronic kidney disease and risk management: Standards of Medical Care in Diabetes—2022. Diabetes care, 2022, 45.Supplement_1: S175-S184.
NAVANEETHAN, Sankar D., et al. Diabetes management in chronic kidney disease: synopsis of the 2020 KDIGO clinical practice guideline. Annals of internal medicine, 2021, 174.3: 385-394.
LIN, Yi-Chih, et al. Update of pathophysiology and management of diabetic kidney disease. Journal of the formosan Medical Association, 2018, 117.8: 662-675.
QASEEM, Amir, et al. Screening, monitoring, and treatment of stage 1 to 3 chronic kidney disease: a clinical practice guideline from the American College of Physicians. Annals of internal medicine, 2013, 159.12: 835-847.
HOVIND, Peter, et al. Progression of diabetic nephropathy. Kidney international, 2001, 59.2: 702-709.