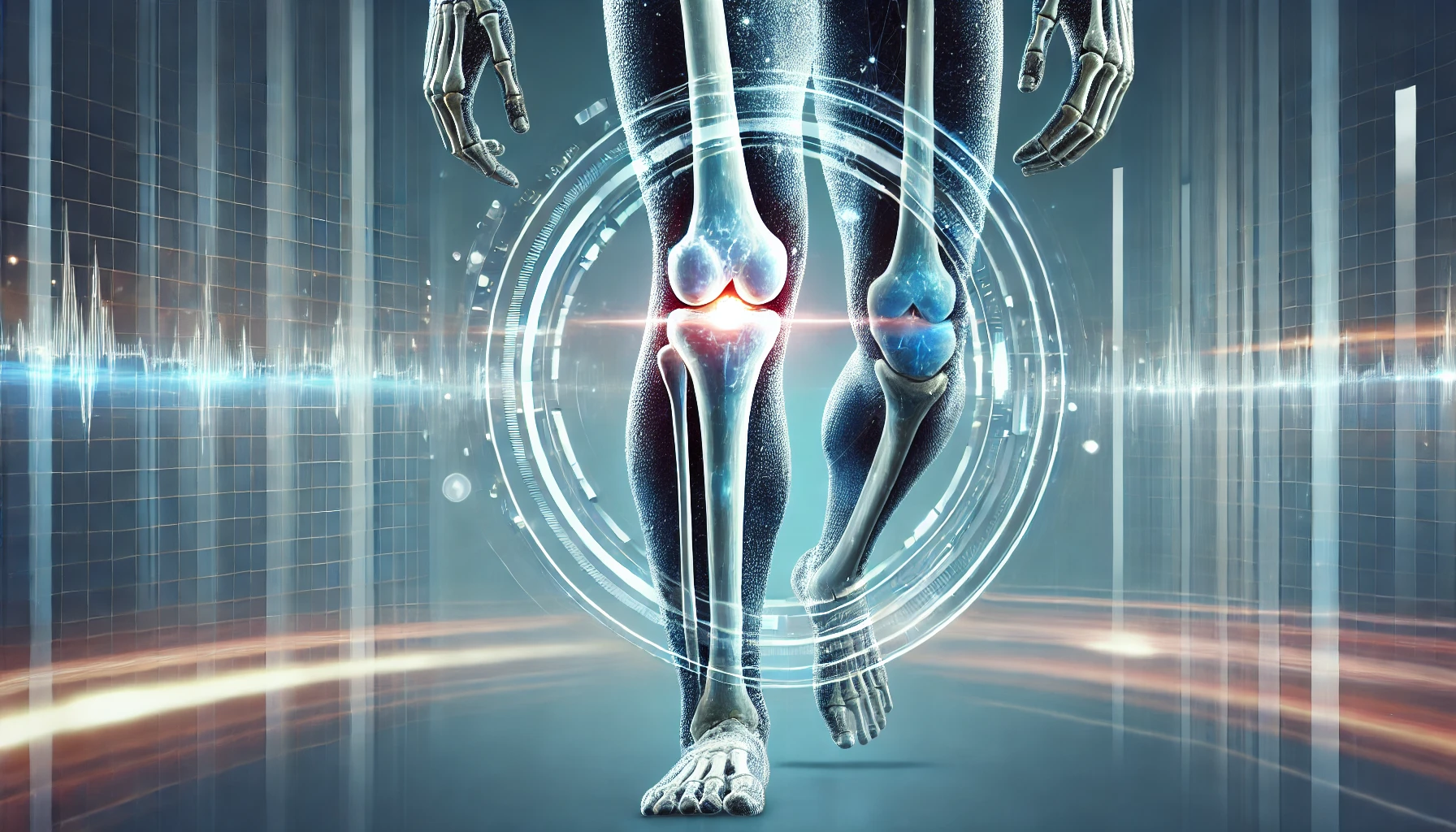交通事故で膝を強打すると、体重を支える膝関節に大きなダメージが加わり、半月板が傷つく場合があります。痛みが軽度でも放置すると、のちに歩行障害や慢性的な違和感につながる可能性があり、早めの対応が重要です。
この記事では、交通事故による膝関節・半月板損傷の原因や症状から治療・リハビリに至るまでを整理し、より適切な受診やケアのきっかけとなる情報をお伝えします。
この記事の執筆者

臼井 大記(うすい だいき)
日本整形外科学会認定専門医
医療社団法人豊正会大垣中央病院 整形外科・麻酔科 担当医師
2009年に帝京大学医学部医学科卒業後、厚生中央病院に勤務。東京医大病院麻酔科に入局後、カンボジアSun International Clinicに従事し、ノースウェスタン大学にて学位取得(修士)。帰国後、岐阜大学附属病院、高山赤十字病院、岐阜総合医療センター、岐阜赤十字病院で整形外科医として勤務。2023年4月より大垣中央病院に入職、整形外科・麻酔科の担当医を務める。
交通事故が起こす膝関節の損傷: 全体像
交通事故による衝撃は思わぬ方向から膝に加わり、靭帯や半月板、軟骨など複数の組織を同時に傷めることがあります。とくに膝関節は歩行や立位で大きな負荷を支える部分であり、少しのダメージでも症状が長引くことが多いです。
ここでは膝の構造と、交通事故が引き起こす膝関節損傷の全体像を把握するための情報をまとめます。
膝関節とは
膝関節は大腿骨(太ももの骨)、脛骨(すねの骨)、膝蓋骨(膝のお皿)から構成され、関節軟骨や半月板などがクッションの役割を果たしています。
日常生活での歩行や階段の上り下りだけでなく、スポーツでも大きな負荷を担う部分です。
曲げ伸ばしという単純な動作に見えて、実際には複雑な動きが連動しており、わずかなズレが大きなトラブルにつながります。
膝関節を構成する主な組織
| 組織名 | 役割 | 交通事故時のリスク |
|---|---|---|
| 大腿骨 | 体重を支える大きな骨 | 衝撃で骨折や軟骨損傷を起こす可能性あり |
| 脛骨 | 大腿骨とともに膝関節を形成 | 圧迫やずれにより損傷が発生しやすい |
| 膝蓋骨 | 膝のお皿。大腿四頭筋との連携が重要 | 正面からの衝突で骨折が生じることも |
| 半月板 | 衝撃の吸収と関節の安定性を維持 | 捻転や圧迫により断裂しやすい |
| 靭帯 | 骨同士をつなぎ、関節を安定させる | 衝撃で伸展・断裂を起こすリスクがある |
膝を構成する組織は互いに関連し合っています。1つのパーツが傷つくと膝全体の動きが乱れ、二次的な負担がかかり、症状が長引くことがあります。
交通事故で膝を痛めるメカニズム
交通事故は歩行中や自転車乗車時の転倒、車の運転中や同乗中の急激な衝撃など、さまざまな状況で発生します。
転倒や衝突により膝をひねる、ハンドルに膝を強打するなど、普段は想定していない方向への力が加わるため、大きなけがにつながりやすいです。
- 車との接触で膝を強打する
- 突然のブレーキやハンドル操作で膝がねじれる
- 外力が膝の横から入って靭帯や半月板が損傷する
- バイクや自転車での転倒時に膝を路面に打ち付ける
多彩なシチュエーションが存在する分、負傷の程度も幅広いです。見た目の腫れが少なくても痛みや違和感が続くなら、早めに専門医へ相談したほうがよいでしょう。
半月板の役割と損傷しやすい理由
半月板は膝関節の内側と外側に存在し、主に衝撃吸収や関節の動きを安定させる役割を担っています。半月板の繊維には弾力性がありますが、血行が乏しい部位が多く、一度傷つくと自然治癒が進みにくい特徴があります。
また、交通事故の衝撃は膝に大きな回旋力を及ぼすことがあり、半月板の繊維が断裂しやすくなります。
交通事故特有の衝撃
交通事故では瞬間的に大きな力が加わるため、単なるねんざでは終わらないケースが多いです。
自分で体を守ろうとする防御姿勢がとれず、さらに車両や地面との強い接触が加わることで、通常のスポーツや日常生活とは異なる傷め方をする場合があります。
あまり自覚症状がないまま深部が損傷していることもあるため、事故後はしばらく様子を見ながら膝に注意を向けることが必要です。
交通事故による半月板損傷の症状と特徴
膝関節の中でも半月板が傷つくと、膝の屈伸時に痛みや引っかかり感が生じやすくなります。
交通事故特有のねじれや圧迫で半月板が断裂すると、急性期の強い痛みだけでなく、時間の経過とともに症状が変化する点も特徴です。
ここでは交通事故後にみられやすい半月板損傷の症状と、その特徴的なサインを確認します。
急性期にみられる症状
受傷直後は激しい痛みや膝の腫れ、熱感などが代表的です。関節内で出血が起こっているケースもあり、痛みで膝を曲げ伸ばしできない状態になることがあります。
痛みが強い間は歩行が困難になり、安静が必要となる場面が多いです。一時的に症状が落ち着いても、数日後から再び痛みが増すことも珍しくありません。
代表的な急性期症状
- 強い痛みと膝の腫れ
- 曲げ伸ばしの制限
- 階段昇降時の激痛
- 歩行が困難になるほどの不安定感
膝関節内の状態は外からはわかりにくく、腫れや出血があってもあまり表面化しないことがあります。我慢できる程度の痛みでも、内部で組織が裂けている場合もあるため、専門的な検査が大切です。
時間が経過した後の症状
交通事故の数週間後や数か月後に半月板損傷が疑われるケースもあります。急性期の痛みが落ち着いて日常生活に戻ったあと、膝の違和感やロッキング(膝が突然引っかかって動かなくなる状態)を訴える人が少なくありません。
歩行時にカクンと膝が崩れるような感じが出る場合もあり、早期の治療を見送ってしまうと日常動作全般に支障が生じます。
損傷の程度の分類
半月板損傷は部位や程度によって分類されます。一般的に縦断裂、横断裂、放射状断裂などのパターンに分かれ、断裂の仕方によって症状や治療方針が異なります。
交通事故の衝撃で複雑に裂けることもあり、画像検査や関節鏡検査で正確な把握が必要です。
半月板断裂パターンと特徴
| 断裂パターン | 特徴 | 治療の考え方 |
|---|---|---|
| 縦断裂 | 半月板を縦方向に裂く | 縫合が有効なことが多い |
| 横断裂 | 外周から内側に向かって横方向に裂く | 症状が軽度なら保存的治療も可能 |
| 放射状断裂 | 半月板の中心部に向かって放射状に裂く | 損傷範囲が大きい場合は手術検討 |
| 変性断裂 | 加齢や繰り返しの負担で生じる不規則な断裂 | 交通事故で悪化しやすい場合あり |
多くの場合、交通事故で強い負荷がかかると1種類の断裂に限らず、複数のパターンが混在することもあります。複合的な損傷は痛みが慢性化しやすい傾向があります。
痛み以外に気をつけたいサイン
半月板損傷で注目されがちなのは痛みですが、その他にも以下のようなサインが現れることがあります。
- 膝からゴリゴリ音がする
- 膝に水(関節液)がたまる
- 座った姿勢から立ち上がるときに強い違和感がある
- 長時間同じ姿勢でいると膝が固まるような感じがする
こうした症状がある場合、早めにMRI検査などで半月板を詳しく調べたほうがよいでしょう。
正しい診断の重要性
交通事故後の膝痛や腫れは、骨折や靭帯損傷も疑われるため、早い段階で正確な診断を受ける必要があります。痛み止めや湿布だけでやり過ごしてしまうと、誤ったセルフケアでかえって症状を悪化させることもあります。
ここでは半月板損傷を正確に見極めるための検査や、専門医の役割について解説します。
レントゲンとMRIの役割
膝の検査で最初に行うことが多いのはレントゲン撮影です。骨折や骨の変形の有無が確認できるため、骨に関する大まかな状況を把握するのに有効です。
しかし、半月板や軟骨などの軟部組織はレントゲンでははっきり映りません。そこでMRIが重要になります。MRIは軟部組織を詳細に映し出すので、半月板の断裂部位や程度を把握するのに欠かせない検査です。
レントゲンとMRIの比較
| 検査方法 | 主にわかること | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| レントゲン | 骨折や骨の変形、関節の隙間の狭まりなど | 撮影時間が短く費用も比較的安い | 軟部組織の情報が不足する |
| MRI | 半月板や軟骨、靭帯の状態 | 軟部組織の損傷を正確に把握できる | 機器や撮影費用が高い場合がある |
レントゲンだけで「骨に異常がないから大丈夫」と思い込むのは危険です。
痛みの原因が半月板や靭帯、軟骨の損傷にあるケースが多く、MRIでより詳しい情報を得ることが治療方針の決定に繋がります。
関節鏡検査の実際
画像検査だけでは判断が難しい場合、関節鏡検査を行うことがあります。小さなカメラ(関節鏡)を関節内に挿入し、実際に目視で半月板の状態を確認しながら治療することも可能です。
切開が小さく、入院期間の短縮にも役立ちますが、手術という形になるため負担がかかります。医師とよく相談して進めることが望ましいです。
- 半月板の断裂部位を直接観察できる
- その場で縫合や切除などの処置を行える
- リスクや費用を考慮して必要性を検討する
見逃しが起きやすいケース
膝の痛みがそこまで強くない場合や、事故直後のショックで痛みがあいまいになるケースでは半月板損傷が見逃されることがあります。
また、他の部位のけがが重度でそちらの治療が優先されると、膝の詳細な検査が遅れることもあります。
早期に気付けないと状態が悪化し、より大きな治療が必要になる可能性があるので注意が必要です。
専門医に相談する意義
交通事故による膝関節損傷は、一般的なねんざや肉離れとは異なるメカニズムや後遺症が考えられます。専門医は交通事故関連の膝トラブルに精通している場合が多く、症状や画像所見から的確な診断を下しやすいです。
適切な検査や治療方針を早期に決定するために、整形外科専門医への受診を検討することが大切です。
専門医選びのポイント
- 交通事故による治療の経験が豊富
- MRIや関節鏡検査などの検査環境が整っている
- リハビリスタッフとの連携がスムーズ
- 保険手続きや後遺障害の書類作成などに理解がある
信頼できる医療機関を選ぶことは、長期的な回復に大きく関わってきます。自宅や職場から通いやすい場所かどうかも含めて検討するとよいでしょう。
半月板損傷における治療の流れ
交通事故で半月板を傷めた場合、症状や断裂部位、患者さんの年齢や活動レベルに応じて治療方法が変わります。保存療法から手術療法、リハビリまで、治療の流れを把握することが回復を早める近道になります。
ここでは治療の具体的な選択肢と流れを解説します。
保存療法と手術療法の違い
保存療法では膝にかかる負荷をコントロールし、装具の使用やリハビリを通じて回復を目指します。
一方、断裂が大きい場合や痛みが強い場合は手術療法が選択肢に入ります。手術では、縫合して半月板を修復する方法と、傷んだ部分を切除する方法があります。
保存療法と手術療法の比較
| 治療法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 保存療法 | 手術の負担がなく、リハビリ中心で体への負荷が少ない | 治療期間が長引くことがある |
| 手術療法 | 損傷部位を直接修復または切除するので改善が早いことも | 入院やリスク、費用面の検討が必要 |
保存療法が適するか、手術が適するかは医師の診断だけでなく、患者さんの生活スタイルや仕事・スポーツの状況も含めて総合的に判断します。
損傷部位や患者背景を考えた治療選択
半月板の外側には多少の血流があるため、外側部の断裂なら自然回復が見込めることもあります。しかし、内側や中心部の断裂は血流が乏しいので、保存療法の効果が限られる場合があります。
さらに、若いアスリートと高齢者では求める運動機能のレベルが異なるため、治療方針が変わります。
- 若年層でスポーツ復帰が目標
- 中高年で日常生活に支障が少ないなら保存的に進める
- 仕事で膝を多用するなら早期回復を重視して手術を検討
手術の種類と特長
半月板の手術には、縫合と切除の2つが主な方法として挙げられます。縫合手術は断裂している部分を縫い合わせる方法で、半月板の機能を温存しやすい利点があります。
一方、切除手術は損傷が激しい部分を切り取ってしまい、痛みの軽減や早期回復が見込める反面、将来的に軟骨への負担が増える可能性があります。
主な手術方法
- 半月板縫合術:機能温存が可能だが回復期間が長め
- 半月板部分切除術:痛みの軽減が早く、リハビリも短期化しやすい
- 関節鏡視下手術:切開が小さく、回復期の負担を軽減できる
- 開放手術:関節鏡に比べて侵襲が大きいが、複雑な損傷に対応する場面も
手術を受けるタイミングや方法は医師と十分に話し合い、自身の生活プランと合わせて決定すると安心できます。
術後の経過観察
手術後は再発防止や膝の機能回復を図るため、定期的な診察やリハビリが続きます。膝に負担がかからないように、段階的に運動量や負荷を増やすことが必要です。
痛みや腫れが引いたあとも、しばらくは膝の安定性に注意し、歩行や階段昇降に違和感があれば医師に相談してください。
交通事故と保険の手続き
交通事故による治療では、自賠責保険や任意保険、健康保険など複数の保険が関わる場合があります。保険の仕組みを理解しておくことで、治療費の負担や後遺障害等級認定に関する手続きをスムーズに進められます。
ここでは保険関連の基礎を整理し、早期受診の重要性を紹介します。
自賠責保険と任意保険の違い
自賠責保険は車やバイクを所有する場合に法律で加入が義務づけられた保険で、人身事故の被害者を救済する目的があります。
一方、任意保険は加入が義務ではないものの、対物賠償や人身傷害など幅広い補償を受けるために多くの人が加入しています。
交通事故による治療費は、まず自賠責保険でカバーし、足りない分を任意保険で補うのが一般的です。
保険適用範囲の目安
| 保険の種類 | 主な補償範囲 | 加入状況 |
|---|---|---|
| 自賠責保険 | 被害者の治療費や慰謝料など | 法律で加入が義務 |
| 任意保険 | 自賠責保険でまかなえない費用など | 加入は任意だが推奨される |
| 健康保険 | 通常の疾病治療 | 交通事故でも使用可能な場合がある |
任意保険に加入していない加害者との事故や、保険金の上限を超えた費用が発生した場合はトラブルになりやすいです。保険会社や弁護士への相談を早めに行うことが大切です。
治療費の請求手順
保険会社へ連絡をしたら、担当者とのやり取りが始まります。医療機関から直接保険会社に請求書を送る場合と、患者さん自身が立て替え払いをして後から請求する場合があります。
整形外科での治療やリハビリ、検査費用のほか、交通費や雑費なども必要に応じて補償対象になることがあります。
- 事故後すぐに保険会社に連絡
- 医療機関を受診し、診断書を取得
- 受診先や治療内容を保険会社へ報告
- 立て替え払いの有無や請求方法を確認
保険会社とのやり取りが滞ると治療が受けにくくなる場合もあるため、分からないことは遠慮せず質問するとよいでしょう。
後遺障害等級認定のポイント
交通事故後、治療を続けても痛みや機能障害が残る場合には「後遺障害等級」の認定を受ける可能性があります。後遺障害等級が認定されると、損害賠償金の額などに影響を及ぼします。
膝の半月板損傷であっても、機能制限が残れば後遺障害として扱われることがあります。
後遺障害等級認定に関するチェック項目
- 痛みの度合いが日常生活に影響しているか
- 膝の可動域が著しく制限されているか
- 医療機関で定期的に治療を継続した記録があるか
- 画像検査や医師の所見が明確に示されているか
適切な診断書や通院記録の提出が重要になります。早期から医療機関に通い、症状を正確に報告することが後遺障害の認定手続きでも大切です。
早期受診のメリット
交通事故に遭った直後はアドレナリンが出て痛みを感じにくい状態になることもあります。しかし、何日か経ってから痛みが強くなるケースが多いです。
事故後すぐに受診しておくと、外力によるけがの証明がしやすくなり、保険対応が円滑になります。また、早期に診断がつくほど、よりよい治療結果を期待しやすいです。
リハビリと日常生活への復帰
交通事故で半月板を損傷した場合、治療後のリハビリは膝の機能回復に欠かせないステップです。適切な時期に適切なリハビリを行うことで、再び日常生活やスポーツに復帰しやすくなります。
ここではリハビリのポイントと、家庭で気をつけたいことについて解説します。
リハビリ開始時期と注意点
リハビリを開始するタイミングは損傷の度合いや治療方法によって変わります。手術をした場合は、術後の痛みや腫れが落ち着いたタイミングを見計らってリハビリを始めることが多いです。
早すぎる負荷は再断裂につながり、遅すぎると膝まわりの筋肉が萎縮して回復に時間がかかります。医師や理学療法士と相談しながら、適切な時期を見極めることが大切です。
リハビリプログラムの一般的な流れ
| 時期 | 主な目的 | 具体的なリハ内容 |
|---|---|---|
| 急性期 | 痛みのコントロール、患部の安静 | 患部を固定、アイシング、軽いマッサージ |
| 回復初期 | 可動域の確保と筋力の基礎回復 | 軽めのストレッチ、アイソメトリック運動 |
| 回復中期 | 本格的な筋力強化とバランス機能の回復 | スクワット、バランス訓練、チューブ運動 |
| 復帰準備期 | 日常動作やスポーツ動作の再習得 | ランニングドリル、段階的な負荷練習 |
一足飛びに重い負荷をかけるのではなく、段階を追ってリハビリを進めることで再発リスクを減らせます。
筋力トレーニングと可動域訓練
膝の安定性を高めるには、太ももの前側(大腿四頭筋)や後側(ハムストリングス)など、周囲の筋力をバランスよく養うことが重要です。
可動域が狭いままだと日常動作でも支障が生まれるため、ストレッチや軽い屈伸運動で膝を少しずつ動かし、柔軟性を回復させます。
- 大腿四頭筋の強化:レッグエクステンションやスクワットなど
- ハムストリングスの強化:レッグカールやブリッジなど
- 可動域向上:タオルギャザーや軽い屈伸運動
痛みを我慢して急にトレーニングを行うと、別の部位をかばって二次的な故障を招くリスクがあります。痛みが出たら無理をせず医療スタッフに相談してください。
生活動作の注意点
日常生活での動作もリハビリの一環です。片足に重心をかけず、両足に均等に体重を分散する意識が大切です。階段ではできるだけ手すりを使い、膝への負担を軽減しましょう。
正座やしゃがみ込みなど、膝を深く曲げる動作は痛みや違和感を誘発することがあるため、無理のない範囲で行ってください。
日常生活で気をつけたいこと
- 通勤や外出時に急ぎ足を避ける
- 長時間の座りっぱなしや立ちっぱなしを避ける
- 重い荷物を持つ場合は膝と腰を両方意識する
- 車の乗り降りで膝をひねらないように注意する
些細な心掛けの積み重ねが、膝の負担を減らし回復を後押しします。
回復を促す食事や休息
怪我の回復を早めるには、適切な栄養摂取と休息も欠かせません。たんぱく質やビタミン、ミネラルをバランス良く摂取することで、筋肉や組織の修復をスムーズに進められます。
睡眠は成長ホルモンの分泌を促すため、早寝早起きの習慣や質の良い睡眠環境を整えることも意識しましょう。
通院先の選び方と専門医との連携
交通事故後の膝の治療は、長期的に通院が必要になることもあります。治療を続けやすい通院先を選ぶことは、回復に大きく影響します。
病院やクリニックの特徴を理解し、必要に応じて専門医との連携を図ることがスムーズな治療のカギとなります。
ここでは通院先を選ぶ際の視点や、医師とのコミュニケーションのポイントをお伝えします。
病院とクリニックの違い
大きな病院ではMRIや関節鏡検査などの検査設備が充実していることが多く、重症例や複合的な損傷に対処しやすいです。一方、クリニックは待ち時間が比較的短く、医師やスタッフとの距離が近いケースがあります。
どちらも一長一短があるため、自身のけがの程度や通院のしやすさを考慮して選ぶとよいでしょう。
病院とクリニックの比較
| 施設の種類 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 総合病院 | 検査・治療設備が充実 | 待ち時間が長くなることがある |
| 専門クリニック | 通院がしやすく待ち時間が短め | 設備やスタッフ数が限られる |
事故後の膝の状態をしっかり評価したい場合、最初は大きな病院で検査を行い、その後のリハビリや通院をクリニックに移すという方法を選ぶ人もいます。
医師とのコミュニケーション
自分の症状や悩みを正確に伝えることは、適切な治療を受ける上で欠かせません。痛みの場所や強さ、いつ感じるのか、どのような動作で増すのかなど、具体的に説明すると医師は診断を立てやすくなります。
疑問点や不安な点は遠慮せずに質問し、納得したうえで治療方針を決めることが望ましいです。
- 症状をわかりやすく伝えるためにメモを取っておく
- 医師が使う専門用語はわからなければその場で尋ねる
- 治療のメリット・リスクの両面を確認する
紹介状の活用
大きな病院や大学病院での精密検査や手術が必要な場合、地域のクリニックから紹介状を書いてもらうと手続きがスムーズになります。
紹介状には診断内容やこれまでの治療経過が記載されるので、重複した検査を回避できるメリットがあります。逆に、大きな病院から地域のクリニックへ戻ってリハビリやフォローアップを続けるケースも多いです。
リハビリ施設の充実度
膝の機能回復を図るにはリハビリ施設の充実度も大きく影響します。理学療法士が常駐しているか、運動療法や物理療法など多様なリハビリプログラムを受けられるかを確認してください。
自分に必要なトレーニングや機器がそろっている環境なら、治療効果も高まりやすいです。
膝の健康を保つアフターケア
交通事故による膝関節・半月板損傷は、治療が終わったあとも再発や慢性的な痛みに悩まされるケースがあります。長期的に膝の健康を維持するためには、日常生活での予防策や定期的なケアが大切です。
ここでは、事故後も快適に生活するためのアフターケアのポイントをご紹介します。
日常生活での予防策
膝に負担をかけすぎない生活習慣を心掛けると、再発リスクを下げやすいです。適正体重を維持することで膝関節への負荷を軽減し、筋力や柔軟性を保つことで関節の動きを滑らかにできます。
急激な運動や無理なダイエットはかえって膝を痛める原因になるため、バランスを意識しましょう。
- ウォーキングなどの低負荷な有酸素運動を日常に取り入れる
- 体重増加を防ぐために食事の量と質を管理する
- 座り続ける時間を減らし、適度に立ち上がってストレッチする
- 靴選びも意識して、クッション性があるものを使う
膝を守る姿勢と動作
| シチュエーション | 推奨する姿勢・動作 |
|---|---|
| 座るとき | 両足を軽く開いて膝を自然に曲げ、深く腰をかける |
| 立ち上がるとき | 座面に手をつきながらゆっくりと立ち上がる |
| 歩行 | 軽く膝を曲げたまま足裏全体で接地し、リズミカルに歩く |
| 物を持つとき | 膝と腰を同時に曲げ、背筋を伸ばしながら持ち上げる |
何気ない日常動作でも、正しい姿勢を意識するだけで膝への負担は大幅に減らせます。
定期検診の重要性
交通事故で半月板を痛めた人は、その後も定期的に膝の状態をチェックすることが好ましいです。痛みや腫れがなくなっても、関節内で軟骨がすり減っている場合や再び半月板が損傷しかけている場合があります。
定期的に医療機関で診察を受けることで、トラブルの早期発見・早期対応が可能になります。
スポーツとの付き合い方
ランニングや球技など、膝への負荷が大きいスポーツを趣味とする人も多いでしょう。事故後に膝が完治したと思っても、急に激しい運動を再開すると再発リスクが高まります。
医師や理学療法士と相談しながら負荷をコントロールし、身体が慣れてきた段階で本格的なトレーニングを再開すると安心です。
- 準備運動とクールダウンを十分に行う
- 無理のない距離やスピードから始める
- 膝サポーターなどの装具を利用して安定性を高める
痛みや違和感が再発した場合
事故後、時間が経ってから再び痛みや違和感が出ることもあります。そのまま放っておくと、半月板損傷の再発や軟骨の摩耗が進んでしまう恐れがあります。
痛みが続くときや腫れがある場合は、できるだけ早く整形外科を受診してください。再受診が早いほど治療期間が短く済む可能性が高いです。
参考文献
TERESIŃSKI, Grzegorz; MĄDRO, Roman. Knee joint injuries as a reconstructive factors in car-to-pedestrian accidents. Forensic science international, 2001, 124.1: 74-82.
TERESIŃSKI, Grzegorz. Injuries of the thigh, knee, and ankle as reconstructive factors in road traffic accidents. In: Forensic medicine of the lower extremity: Human identification and trauma analysis of the thigh, leg, and foot. Totowa, NJ: Humana Press, 2005. p. 311-342.
ATKINSON, Theresa; ATKINSON, Patrick. Knee injuries in motor vehicle collisions: a study of the National Accident Sampling System database for the years 1979–1995. Accident Analysis & Prevention, 2000, 32.6: 779-786.
KRAUS, T., et al. The epidemiology of knee injuries in children and adolescents. Archives of orthopaedic and trauma surgery, 2012, 132: 773-779.
NAGASAKA, Kei, et al. Finite element analysis of knee injury risks in car-to-pedestrian impacts. Traffic injury prevention, 2003, 4.4: 345-354.
CHEN, Jiemin; XIA, Wentao. Assessment of the responsibility between a road traffic accident and medical defects after the traffic accident injury of knee joint. Journal of forensic and legal medicine, 2012, 19.3: 168-170.
LU, K. H.; HSIAO, Y. M.; LIN, Z. I. Arthroscopy for acute knee haemarthrosis in road traffic accident victims. Injury, 1996, 27.5: 341-343.
OTTE, Dietmar; HAASPER, Carl. Technical parameters and mechanisms for the injury risk of the knee joint of vulnerable road users impacted by cars in road traffic accidents. In: IRCOBI Conference. 2005. p. 281-298.
STEINMETZ, R. Garrett, et al. Prevalence of ligamentous knee injuries in pedestrian versus motor vehicle accidents. BMC musculoskeletal disorders, 2020, 21: 1-8.