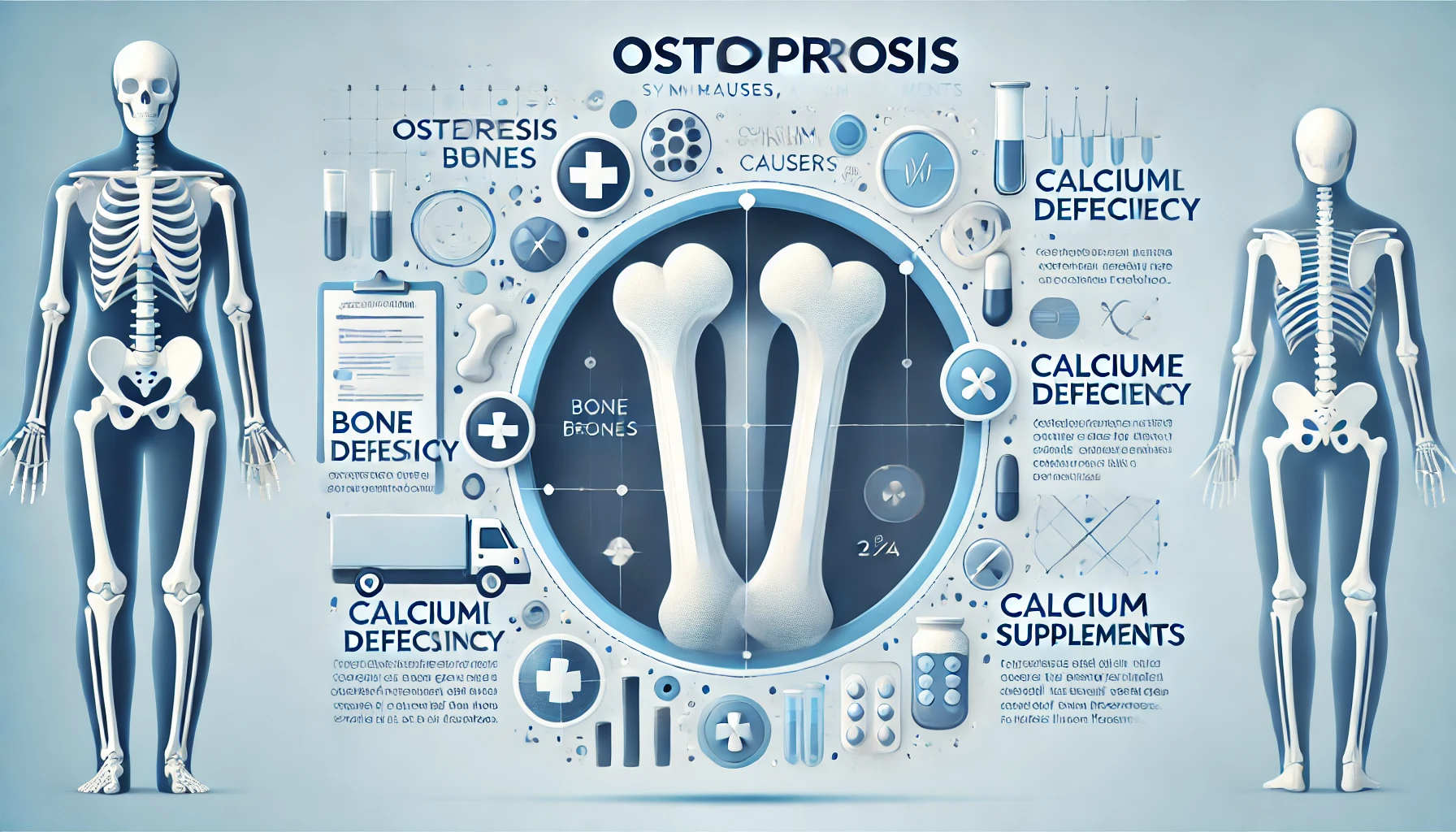骨粗鬆症は、骨の強度が低下し、骨折しやすくなる状態です。加齢とともに起こりやすい一方、生活習慣や他の病気との関連も指摘されています。
骨が弱まると痛みや姿勢の変化が生じやすくなり、日常生活に大きな支障をもたらす可能性があります。ただし、食事や運動など生活習慣を工夫し、適切な治療を受ければ、骨粗鬆症によるリスクを低減できる場合も多いです。
この記事では、骨粗鬆症の具体的な原因や症状、検査法から治療・予防までを整形外科の観点から幅広く紹介し、日常生活での留意点に触れます。骨粗鬆症について理解を深め、受診の必要があるかどうかを考えるための情報をお伝えします。
この記事の執筆者

臼井 大記(うすい だいき)
日本整形外科学会認定専門医
医療社団法人豊正会大垣中央病院 整形外科・麻酔科 担当医師
2009年に帝京大学医学部医学科卒業後、厚生中央病院に勤務。東京医大病院麻酔科に入局後、カンボジアSun International Clinicに従事し、ノースウェスタン大学にて学位取得(修士)。帰国後、岐阜大学附属病院、高山赤十字病院、岐阜総合医療センター、岐阜赤十字病院で整形外科医として勤務。2023年4月より大垣中央病院に入職、整形外科・麻酔科の担当医を務める。
骨粗鬆症とは何か
骨密度や骨強度が低下し、骨折リスクが高まる状態を指します。加齢が主な原因と考えられていますが、それだけではなく、閉経後の女性ホルモン変化や生活習慣など、多様な要素が重なることで発症リスクが上昇します。
ここでは、骨粗鬆症の基本的な定義や特徴を確認しながら、どのような人に起きやすいのかを見ていきます。
骨密度の意味
骨密度は、骨の中のミネラル(主にカルシウム)の量を示し、骨の強さをある程度推定できる指標です。若年成人期にピーク骨量を迎え、それを維持することが重要と考えられています。
骨密度が低下すると、転倒や軽い衝撃でも骨折を起こす可能性が高くなります。
骨強度と骨質
骨密度のみに注目すると見過ごしやすい要素として、骨質が挙げられます。骨質は骨の構造やコラーゲンの状態など、骨の内部構造の質的要素を指します。
骨粗鬆症では、骨密度に加えて骨質が低下しやすく、骨折につながりやすい脆弱な骨になるケースがあります。
骨粗鬆症が与える影響
骨粗鬆症になると、軽度の衝撃で骨折しやすくなるだけでなく、腰や背中の痛み、姿勢異常、身長の低下など、さまざまなトラブルが起こる可能性があります。
結果として日常生活の活動量が下がり、外出が億劫になることで筋力も低下しやすくなり、さらに骨が弱くなる悪循環が生まれやすくなります。
骨折リスクと死亡率
骨粗鬆症による骨折、とくに大腿骨近位部(股関節周辺)の骨折は、要介護状態に直結することが知られています。
また、骨粗鬆症が原因の骨折によって長期入院を余儀なくされることもあるため、結果的に寿命にも影響を与えることがあります。予防や早期治療の意義は大きいと考えられます。
骨粗鬆症の基礎知識のまとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 骨密度 | 骨のミネラル量の指標であり、骨の強さを推定するうえで重要 |
| 骨質 | 骨の構造やコラーゲンなど、骨の内部構造の質的な要素 |
| 主な症状 | 軽度の衝撃で骨折しやすい、腰・背中の痛み、姿勢の変化、身長の低下など |
| 合併症 | 大腿骨近位部骨折などによる寝たきりリスク、長期入院、QOL低下など |
| 注意すべき点 | 早期から骨密度低下を防ぐための生活習慣が大切 |
骨粗鬆症の原因とリスク要因
骨粗鬆症を引き起こす主な要因は加齢ですが、それだけにとどまりません。性別や遺伝的素因、ライフスタイル、さらには一部の疾患や薬剤など、さまざまな要因が関与すると考えられています。
ここでは、骨粗鬆症に関わる代表的なリスク要因を具体的に見ていきましょう。
加齢とホルモンバランス
年齢を重ねるとともに、骨形成と骨吸収のバランスが崩れやすくなります。特に閉経後の女性はエストロゲンの分泌が急激に低下し、骨密度低下が加速しやすくなるのが特徴です。
男性の場合も加齢とともにテストステロンなどのホルモン分泌が減少し、骨代謝に影響を与える可能性があります。
遺伝的背景
骨粗鬆症には遺伝要素があると考えられています。親や祖父母が骨粗鬆症や骨折を起こしやすい傾向にある場合、本人も骨密度が低めになる場合があります。
遺伝要素がどの程度骨粗鬆症の発症に影響するかは個人差が大きいですが、家族歴がある方は特に注意が必要です。
栄養と生活習慣
カルシウムやビタミンDなど骨形成に関わる栄養素が不足すると、骨密度が低下しやすくなります。また、喫煙や過度の飲酒は骨を弱くするリスクを高める要因です。
栄養バランスの乱れや運動不足も骨代謝に影響を与え、骨密度の維持が難しくなる場合があります。
併存疾患や薬剤
リウマチや甲状腺疾患、慢性腎臓病など、骨代謝に影響を及ぼす疾患を抱えると骨粗鬆症のリスクが高まる可能性があります。
また、長期のステロイド薬使用なども骨代謝を阻害し、骨密度の低下を促進する場合があります。
骨粗鬆症を引き起こしやすい要因
- 年齢(加齢による骨代謝バランスの崩れ)
- 性別(女性は閉経後にエストロゲンが急激に減少)
- 遺伝的素因(家族に骨粗鬆症や骨折歴がある)
- 栄養不足(カルシウム・ビタミンD・タンパク質など)
- 喫煙や過度の飲酒
- 運動不足
- ステロイド薬の長期使用
- リウマチや甲状腺疾患などの持病
骨粗鬆症に関連する主なリスク因子と対応策
| リスク因子 | 対応策 |
|---|---|
| 加齢 | 定期的な骨密度検査と必要に応じた治療 |
| 閉経やホルモン低下 | 適切なホルモン補充療法を検討し、整形外科や婦人科に相談 |
| 栄養不足 | バランスの良い食事、必要に応じたサプリメント |
| 喫煙・過度の飲酒 | 禁煙や節酒を意識したライフスタイルの見直し |
| 運動不足 | ウォーキングや筋力トレーニングの導入 |
| 長期のステロイド使用 | 可能な範囲での薬量調整、骨保護薬の併用 |
| リウマチや甲状腺疾患など | 基礎疾患のコントロールを整形外科や内科と連携して行う |
骨粗鬆症の症状と合併症
骨粗鬆症自体は無症状のことが多いです。気づかないうちに進行し、ある日突然骨折することで発見されるケースも珍しくありません。
ただし、進行に伴って起こりやすい症状や合併症は日常生活に大きな影響を与える場合があります。ここでは、骨粗鬆症によってみられやすい症状と、その延長で起こる合併症を紹介します。
無症状のまま骨折するリスク
骨の強度が徐々に落ちていくため、痛みなどの自覚症状がないまま進行することが多いです。
結果として、軽い転倒やちょっとした動作で骨折し、初めて骨粗鬆症と診断される方もいます。日常的に骨を守る行動を取ることが大切です。
慢性的な腰痛や背中の痛み
骨粗鬆症が進むと、背骨(脊椎)の圧迫骨折を引き起こしやすくなります。圧迫骨折は急性の痛みを伴うケースもありますが、慢性的な腰痛や背部痛につながる場合もあります。
さらに、脊椎がつぶれることで身長が低下したり、姿勢が変化したりすることがあります。
姿勢異常や身長の低下
骨粗鬆症の進行により、椎体の変形が複数個所に及ぶと背中が丸くなり、いわゆる「円背」と呼ばれる姿勢異常を生じやすくなります。
身長が数センチ単位で低下することもあります。生活の質が下がり、呼吸がしにくくなる場合もあるので注意が必要です。
重篤な合併症の代表:大腿骨近位部骨折
骨粗鬆症の合併症として最も恐れられるのが、大腿骨近位部(股関節周辺)の骨折です。転倒などで起こりやすく、手術が必要になる場合が多いです。
また、寝たきりを招く大きな要因でもあり、長期のリハビリテーションが必要になるケースも少なくありません。
骨粗鬆症で起こりやすい主な症状
- 骨折(手首や背骨、股関節など)
- 腰痛や背部痛
- 身長の低下
- 背骨の圧迫骨折による姿勢異常(円背)
よくみられる骨粗鬆症関連骨折の特徴
| 骨折部位 | 特徴 |
|---|---|
| 脊椎(圧迫骨折) | 姿勢の変化、腰や背中の痛み、慢性化すると身長低下 |
| 橈骨遠位端(手首付近) | 転倒時に手をついた際に骨折しやすい |
| 大腿骨近位部 | 転倒や衝撃で骨折が起こりやすく、手術や長期入院が必要になるケースが多い |
| 上腕骨近位部 | 肩周辺の骨折で、日常動作やリハビリが困難になりやすい |
骨密度検査や診断の進め方
骨粗鬆症のリスクを知るためには、骨密度検査が非常に有用です。自覚症状がない段階でも検査で骨密度が低いことが判明し、早期介入につなげることが可能です。
代表的な骨密度検査の種類や診断の流れ、検査を受けるタイミングについて紹介します。
DXA(デキサ)法
DXA(Dual-energy X-ray Absorptiometry)は、骨密度検査で最も広く用いられる方法です。
X線を使って骨密度を測定し、腰椎や大腿骨の骨密度を数値化します。検査時間も短く、精度が高いのが特徴です。
超音波法
かかと(踵部)の骨を超音波で測定する方法もあります。DXA法ほどの精密さはありませんが、簡便に検査でき、結果の目安が分かります。
ただし、診断の確定にはDXAなどのより正確な検査を行うのが一般的です。
血液検査や尿検査
骨密度検査だけではなく、骨代謝マーカーを測定する血液検査や尿検査を行うことがあります。
骨の形成や吸収の状態を把握し、骨粗鬆症の進行度や治療効果の目安を知るためにも役立ちます。
診断基準と医師の判断
骨密度がYAM(若年成人平均値)の70%未満の場合や、既に骨折歴がある場合など、複合的な要素から総合判断して骨粗鬆症と診断します。
単に骨密度が低いだけでなく、年齢や性別、他のリスク要因との兼ね合いを見ながら診断を行います。
骨密度検査の種類と特徴
| 検査方法 | 主な測定部位 | 特徴 |
|---|---|---|
| DXA法 | 腰椎・大腿骨 | 精度が高い、検査時間が短い |
| 超音波法 | 踵部 | 測定が簡易、スクリーニング向き |
| 血液・尿検査 | – | 骨代謝マーカーを計測可能 |
骨密度検査を考える際に意識したいポイント
- 家族に骨粗鬆症の人がいる
- 閉経後である(女性)
- 骨折を起こした経験がある
- 長期間ステロイド薬を使用している
- 年齢とともに腰痛や背中の痛みが増してきた
骨粗鬆症の治療法
骨粗鬆症の治療は、大きく分けて薬物治療と生活習慣の改善の2本柱です。
骨密度や骨強度を高め、骨折リスクを減らすためにさまざまな種類の薬が使われますが、一方で運動や栄養、喫煙や飲酒のコントロールなどライフスタイルの見直しも欠かせません。
ここでは骨粗鬆症に用いられる主な治療法とその概要を紹介します。
薬物治療の種類
ビスホスホネート製剤、選択的エストロゲン受容体モジュレーター(SERM)、カルシトニン製剤、骨形成促進薬(PTH製剤)など、骨粗鬆症に対応する薬は多種多様です。
骨吸収を抑制する薬や、骨形成を促進する薬などがあり、患者さんの状態や合併症の有無によって使い分けられます。
カルシウムやビタミンDの補給
食事やサプリメントでカルシウムやビタミンDを補給することは、薬物治療と併用されることが多いです。特にビタミンDは、カルシウムの吸収率を高めるために重要です。
日光浴もビタミンD合成を促進しますが、紫外線の過剰摂取には注意が必要です。
運動療法とリハビリ
運動は骨代謝を活発にし、骨密度の維持や筋力アップに役立ちます。ウォーキングや軽いジョギング、筋力トレーニングなど、骨に適度な負荷をかける運動が推奨されます。
整形外科でリハビリを行いながら、自分に合った運動メニューを継続することが大切です。
痛みや骨折への対処
すでに圧迫骨折などが起きている場合、痛みのコントロールやコルセットの活用、骨折部の安定化などを検討します。痛みが強いと運動療法が制限されるため、適切な痛みの管理が重要です。
骨折が見つかった場合は、早急に整形外科の受診を検討したほうが良いです。
骨粗鬆症治療薬の主な種類
| 種類 | 作用 |
|---|---|
| ビスホスホネート製剤 | 骨吸収抑制作用が強く、骨密度の維持や骨折リスク低減に役立つ |
| SERM(選択的エストロゲン受容体) | エストロゲンに類似した作用で骨密度を維持し、乳がんリスク低減効果もある場合がある |
| カルシトニン製剤 | 骨吸収を抑制し、痛みの緩和にも寄与する可能性がある |
| PTH製剤(副甲状腺ホルモン) | 骨形成を促進し、骨密度を上昇させる |
治療を受けるうえで意識したいポイント
- 内服薬は処方通りに飲み、自己判断で中断しない
- 定期的に骨密度を測定し、効果を確認する
- 食事や生活習慣を見直し、薬物療法をサポートする
- 副作用など異常を感じた場合はすぐに医師に報告する
予防のための生活習慣
骨粗鬆症は治療だけでなく、日常の習慣改善でリスクを大幅に減らせる可能性があります。食事や運動、嗜好品のコントロールなど、積み重ねによって骨密度の維持を後押しできます。
ここでは、予防の観点から日常的に取り組みやすいポイントを具体的に挙げていきます。
カルシウムとビタミンDを意識した食事
乳製品や小魚、豆腐、野菜などにはカルシウムが豊富に含まれています。
ビタミンDは魚やキノコ類に含まれ、カルシウムの吸収を高めます。偏食や過度なダイエットは骨に必要な栄養素を不足させる原因になるので注意が必要です。
骨を強くする食事例
| 食品グループ | 具体例 | 骨に有益な栄養素 |
|---|---|---|
| 乳製品 | 牛乳、ヨーグルト、チーズなど | カルシウム、ビタミンB群、たんぱく質 |
| 魚 | いわし、鮭、ししゃも、さんまなど | カルシウム、ビタミンD、良質なたんぱく質 |
| 大豆製品 | 豆腐、納豆、豆乳など | カルシウム、たんぱく質、イソフラボン |
| 野菜 | 小松菜、ブロッコリー、チンゲンサイなど | カルシウム、ビタミンK、その他ミネラル |
| きのこ | しいたけ、エノキ、マイタケなど | ビタミンD(干しシイタケなど) |
適度な運動と筋力維持
骨には適度な負荷をかけることでリモデリングが促進されます。
ウォーキングや軽いジョギング、筋力トレーニングを継続的に行うと、骨密度の維持とともに筋力もアップし、転倒リスクの軽減にもつながります。
禁煙・節酒
喫煙は骨密度低下を助長し、骨粗鬆症の進行を早める要因です。
過度な飲酒も骨形成に悪影響を及ぼす可能性があります。禁煙や節酒に取り組むことは、骨の健康のみならず全身の健康を守るうえでも有益です。
日常生活の転倒予防
骨粗鬆症で骨が弱い場合、転倒は大きなリスクです。
家具の配置を見直したり、足元を照らす照明を工夫したり、滑りにくい靴を選ぶなど、ちょっとした配慮で転倒リスクが下がります。筋力やバランス力を高める運動も重要です。
日常生活で取り入れやすい予防習慣
- 毎日の食事で乳製品や魚、大豆製品を意識する
- 屋外散歩や軽い運動を継続する
- 禁煙や節酒を心がける
- 家の中でつまずきやすい場所を点検する
整形外科の役割と治療の流れ
骨粗鬆症に関しては内科や婦人科など多くの診療科が関わりますが、骨や関節の疾患を専門とする整形外科は重要な役割を担います。骨折への迅速な対応やリハビリテーション、薬物治療のプランニングなど、総合的にサポートできる存在です。
整形外科が骨粗鬆症でどのような対応を行うのか、その流れを確認します。
骨折の診断と治療
整形外科では、骨折の診断を正確に行い、必要に応じて手術や保存的治療(ギプス固定・装具など)を行います。
骨粗鬆症が背景にある場合、再骨折の予防策も含めて総合的に治療計画を立てます。
リハビリテーションと運動指導
骨折してしまった場合、その後のリハビリテーションがとても大切です。痛みの緩和や筋力低下の防止、関節の可動域維持などを目的としたプログラムが組まれます。
運動療法を指導する専門スタッフとも連携を取りながら、日常生活への早期復帰を目指します。
薬物治療の管理
骨粗鬆症治療薬は飲むタイミングや副作用への注意が必要です。整形外科医は患者さんの骨密度や合併症状を見ながら、最適な薬の選択や投与を管理します。
定期的な検査を通じて治療の経過を見守り、必要に応じて薬の種類や量を変更する場合もあります。
他診療科との連携
閉経後女性のホルモンバランスに関して婦人科と連携したり、リウマチや慢性腎臓病を抱える場合には内科やリウマチ科と協力したりするなど、骨粗鬆症の背景にある病気に応じて連携が不可欠です。
複数科の視点を取り入れることで、骨粗鬆症に起因する合併リスクの軽減を図ります。
整形外科での受診から治療までの流れ
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 初診・問診 | 症状の確認、既往歴や家族歴の確認 |
| 画像検査・骨密度検査 | X線撮影やDXA測定などを行い、骨折や骨密度の程度を把握 |
| 診断と治療方針決定 | 手術の要否、薬物治療の開始、リハビリ計画の立案 |
| 治療・リハビリ | 手術・ギプス固定・リハビリ・薬物療法などを行い、効果を随時評価 |
| 経過観察 | 定期的な骨密度検査や画像診断で治療効果をチェックし、薬剤調整を検討 |
整形外科医に相談するときに準備したいこと
- 過去の骨折歴や手術歴
- 家族の骨粗鬆症や骨折の有無
- 現在服用している薬の種類と量
- 日常生活で困っていること(痛みや動きづらさなど)
- 運動習慣や食事の状態
受診を迷う方へ
骨粗鬆症は初期に症状を自覚しにくく、受診のタイミングを逃しがちです。しかし、早期に対策を講じれば将来的な骨折リスクを下げる可能性があります。
迷っている場合は、まずは身近にできるセルフチェックや簡易検査を行い、違和感があれば整形外科を受診すると良いでしょう。
セルフチェックの重要性
腰痛や背中の痛みが長引く、身長が縮んだ気がする、背中が丸くなってきたと感じる場合、骨粗鬆症が関係している可能性があります。
また、転びやすくなった、骨折歴があるなど心当たりがある場合も受診を検討してください。
かかりつけ医との相談
いきなり専門の整形外科を受診することに抵抗がある場合は、まずはかかりつけの医師に相談するのも選択肢です。
必要に応じて整形外科や専門センターを紹介してもらえるため、スムーズに専門医療機関にたどり着けます。
症状がなくても受診を検討
骨粗鬆症は症状がなくても骨密度が極端に落ちている場合があります。
特に閉経後の女性や高齢の方、家族に骨粗鬆症の人がいる場合は、定期的な骨密度検査を受けることで早期発見と予防につなげられます。
日常生活の情報をメモしておく
受診時に、普段の食生活や運動習慣、喫煙・飲酒の状況などを医師に伝えると診断や治療方針の参考になります。簡単なメモを用意しておくとスムーズです。
受診前に振り返りたい項目
- 現在の運動習慣はどの程度か
- 栄養バランスに気を遣っているか(カルシウム、ビタミンDなど)
- 家族の骨折歴や骨粗鬆症歴があるか
- 腰や背中に慢性的な痛みがあるか
- 過去に骨折を経験していないか
こんな場合は受診を検討しましょう
| 状況 | アドバイス |
|---|---|
| 転倒や骨折が増えた実感がある | 早めの整形外科受診を検討し、骨密度検査や画像検査を受ける |
| 慢性的な腰痛や背中の痛みが続いている | 圧迫骨折の可能性もあるため、医師に相談して適切な検査を受ける |
| サプリメントなどで対策しているが不安がある | 一度専門医に相談し、薬物療法やリハビリなど専門的なアプローチを検討する |
| 症状はないが家族に骨粗鬆症の人がいる | 定期的な骨密度検査を受けることで早期発見・予防を図る |
以上、骨粗鬆症の症状や原因、治療、そして日常生活での予防策について整理しました。骨粗鬆症は「気づかないうちに進行し、ある日骨折で発覚する」という方が少なくありません。
適切な検査や治療、生活習慣の見直しを早めに行うことで、骨折などの深刻な合併症を避け、長く健やかな生活を送れる可能性が高まります。
骨折リスクが高い方や加齢とともに骨の衰えを感じる方は、ぜひ整形外科での検査や治療を前向きに検討してみてください。
参考文献
KHOSLA, Sundeep; HOFBAUER, Lorenz C. Osteoporosis treatment: recent developments and ongoing challenges. The lancet Diabetes & endocrinology, 2017, 5.11: 898-907.
TU, Kristie N., et al. Osteoporosis: a review of treatment options. Pharmacy and Therapeutics, 2018, 43.2: 92.
BOLLAND, Mark J., et al. Effect of osteoporosis treatment on mortality: a meta-analysis. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2010, 95.3: 1174-1181.
DRAKE, Matthew T.; CLARKE, Bart L.; LEWIECKI, E. Michael. The pathophysiology and treatment of osteoporosis. Clinical therapeutics, 2015, 37.8: 1837-1850.
TOSTESON, Anna NA, et al. Cost-effective osteoporosis treatment thresholds: the United States perspective. Osteoporosis international, 2008, 19: 437-447.
STAFFORD, Randall S.; DRIELING, Rebecca L.; HERSH, Adam L. National trends in osteoporosis visits and osteoporosis treatment, 1988-2003. Archives of internal medicine, 2004, 164.14: 1525-1530.
RIGGS, B. Lawrence; MELTON III, L. Joseph. The prevention and treatment of osteoporosis. New England Journal of Medicine, 1992, 327.9: 620-627.
ROSSINI, Maurizio, et al. Determinants of adherence to osteoporosis treatment in clinical practice. Osteoporosis International, 2006, 17: 914-921.
BARON, Roland; HESSE, Eric. Update on bone anabolics in osteoporosis treatment: rationale, current status, and perspectives. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2012, 97.2: 311-325.
DELMAS, Pierre D. Treatment of postmenopausal osteoporosis. The Lancet, 2002, 359.9322: 2018-2026.