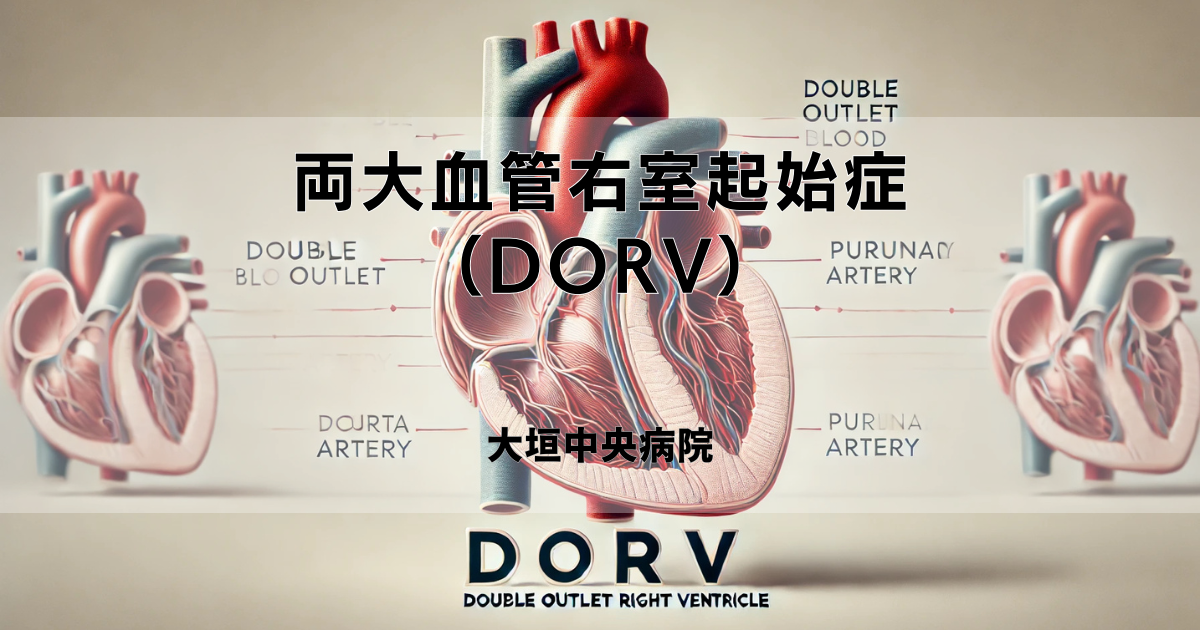先天性心疾患の一種である両大血管右室起始症(DORV)とは、心臓の主要な血管である大動脈と肺動脈が、ともに右心室から起始している先天的な心臓の形態異常です。
本来であれば、大動脈は左心室から、肺動脈は右心室から別々に血液を送り出すという役割分担がなされているところ、DORVでは両方の大血管が右心室から出ているため、血液の循環に特徴的な影響が生じます。
両大血管右室起始症の病型
先天性心疾患の両大血管右室起始症(DORV)の病型は、心臓の解剖学的特徴により4つの主要なタイプに分類します。
それぞれの病型は、大血管の位置関係や心室中隔欠損の有無、さらに肺動脈の状態などによって特徴づけられ、心臓の血行動力学に独特の影響を与えます。
単純型DORVの特徴
単純型DORVは、両大血管右室起始症の基本的な形態を示す病型であり、大動脈と肺動脈の両方が右心室から起始する特徴を持ちます。
この病型における心室中隔欠損(心臓の左右の心室を隔てる壁に開いた穴)の位置は、大動脈の直下に存在することが解剖学的な特徴となります。
心臓の血行動力学的な観点から見ると、左心室からの血液は心室中隔欠損を通過して右心室に流入し、そこから大動脈と肺動脈の両方に分配される構造を呈しています。統計的には、DORVの全症例のおよそ30%がこの単純型に分類されます。
| 解剖学的特徴 | 血行動力学的特徴 |
|---|---|
| 大血管位置 | 右心室からの起始 |
| VSD位置 | 大動脈弁直下 |
| 血流パターン | 左室→右室→両大血管 |
心室中隔欠損型DORVの特徴
心室中隔欠損型DORVでは、心室中隔に存在する欠損が両大血管の間に位置する特徴的な形態を示します。この病型における心室中隔欠損は、肺動脈弁と大動脈弁の両方に関係する位置に存在するため、独特の血行動力学的特性が生じます。
医学統計によると、この型は全DORV症例の約25%を占めており、左心室から右心室への血液の流れは、心室中隔欠損の大きさと位置によって規定されることが判明しています。
- 欠損部位が両大血管の中間に位置する解剖学的特徴
- 左心室からの血液が均等に分配される血行動力学的特性
- 心室中隔欠損の大きさによる血流量の変動性
肺動脈狭窄型DORVの構造
肺動脈狭窄型DORVは、肺動脈の狭窄(血管の一部が狭くなった状態)を伴う形態を呈します。この病型では、肺動脈の狭窄により肺血流量が制限される特徴があり、全症例の約20%を占めています。
| 解剖学的特徴 | 発生頻度(%) |
|---|---|
| 弁性狭窄 | 約45% |
| 弁下狭窄 | 約35% |
| 弁上狭窄 | 約20% |
タウジッヒ・ビング奇形の解剖学的特徴
タウジッヒ・ビング奇形は、DORVの特殊型として分類される病型であり、全症例の約15%を占めています。この形態の特徴は、心室中隔欠損が肺動脈弁の直下に位置することにあります。
| 病態の特徴 | 臨床的意義 |
|---|---|
| VSD位置 | 肺動脈弁直下 |
| 大血管関係 | 並行配列 |
| 心室形態 | 右室優位 |
病型分類の臨床的意義
両大血管右室起始症の各病型における血行動力学的特徴は、大血管の位置関係、心室中隔欠損の位置と大きさ、さらに付随する異常の有無により決定されます。
世界的な統計では、DORVの発生率は出生1万人あたり約1.5〜3人とされています。
- 形態学的特徴による分類体系の確立
- 血行動力学的特性に基づく病態理解
- 随伴心奇形の種類と頻度の把握
両大血管右室起始症の各病型は、心臓の構造と血行動力学に基づいて体系的に分類され、その特徴を理解することが医学的に重要な意味を持ちます。
両大血管右室起始症(DORV)の症状
両大血管右室起始症(DORV)の症状は、病型や心臓の状態によって様々な形で現れます。
症状の種類と程度は、心室中隔欠損の大きさ、肺血流量、そして大血管の位置関係などの要因によって異なり、新生児期から成人期まで年齢によっても変化します。
新生児期からみられる症状
新生児期のDORV患者さんにおいて、最も顕著な症状はチアノーゼ(皮膚や粘膜が青紫色になる状態)です。統計によると、出生直後から約75%の患者さんでこの症状が確認されます。
授乳時や啼泣時には、酸素飽和度が通常の95-100%から80-85%程度まで低下することが報告されています。
体重増加の遅れも特徴的な症状の一つとなり、一般的な新生児の体重増加が1日あたり20-30gであるのに対し、DORV患者さんでは10-15g程度にとどまることが多いとされています。
| 症状 | 出現頻度(%) | 特徴的な所見 |
|---|---|---|
| チアノーゼ | 75 | 啼泣時に増強 |
| 哺乳困難 | 65 | 早期疲労 |
| 体重増加不良 | 60 | 標準の50-70% |
乳児期の特徴的な症状
乳児期には心不全症状が顕在化し、呼吸数は通常の分時30-40回から40-60回へと増加します。多くの患者さんで認められる発汗増加は、特に授乳時に顕著となり、一回の授乳で着替えが必要なほどの発汗を示す例も全体の約40%に達しています。
肺うっ血による症状は、安静時の呼吸数増加から始まり、喘鳴や湿性ラ音(肺で聴取される異常な音)といった身体所見へと進展します。感染症の併発により、これらの症状は24-48時間以内に急速に悪化する傾向にあります。
- 呼吸数増加(分時40-60回)と著明な発汗
- 体重増加率が標準の60-80%程度に低下
- 感染症併発時の急速な症状悪化(24-48時間以内)
幼児期以降の症状変化
幼児期に入ると、運動時の症状が顕著になってきます。3-6歳児の標準的な運動持続時間が15-20分程度であるのに対し、DORV患者さんでは5-10分程度で疲労感を訴えることが一般的です。
| 年齢区分 | 運動持続時間 | 酸素飽和度低下 |
|---|---|---|
| 1-3歳 | 10分前後 | 10-15%低下 |
| 3-6歳 | 5-10分 | 15-20%低下 |
| 6歳以上 | 3-8分 | 20-25%低下 |
病型別の特徴的な症状
各病型によって症状の発現パターンは異なります。単純型では生後24-48時間以内にチアノーゼが出現し、心室中隔欠損型では生後1-2週間で心不全症状が現れ始めます。
肺動脈狭窄型では、チアノーゼの程度が経時的に進行する特徴があります。
| 病型 | 初発症状時期 | 主要症状の特徴 |
|---|---|---|
| 単純型 | 24-48時間以内 | チアノーゼ90%以上 |
| VSD型 | 1-2週間 | 心不全症状80%以上 |
| PS型 | 段階的に進行 | チアノーゼ+運動制限95% |
成人期における症状
成人期のDORV患者さんでは、慢性的な低酸素血症による二次的な症状が出現します。ヘモグロビン値は通常の12-16g/dLから18-20g/dL程度まで上昇し、血液粘度の上昇による頭痛や視覚障害も報告されています。
- 安静時のSpO2が85-90%程度まで低下
- 労作時の心拍数が標準の130-150%に上昇
- 多血症によるヘモグロビン値が18-20g/dLまで上昇
これらの症状は年齢や病型により異なる経過を示し、早期の気づきと対応が症状管理において重要な役割を果たします。
両大血管右室起始症の原因
両大血管右室起始症(DORV)の原因は、胎児期における心臓の発生過程で生じる複雑な発生異常に起因します。
心臓の発生過程における心臓流出路(大血管)の形成、心室中隔の形成、そして心臓の捻れの形成といった重要な発生イベントの異常が、この疾患の発症に関与することが明らかになってきています。
心臓発生における基本的なメカニズム
心臓の発生過程は胎生3週という極めて早期から開始され、特に心臓流出路の形成においては第3週から第8週までの期間が決定的な役割を果たします。
研究データによると、この6週間で心臓の基本構造の約85%が完成するとされており、心臓神経堤細胞の遊走数は一日あたり約10万個にも達します。
| 発生段階 | 細胞増殖率(/日) | 形成される構造 |
|---|---|---|
| 胎生3-4週 | 15-20万個 | 心臓原基 |
| 胎生5-6週 | 25-30万個 | 心臓流出路 |
| 胎生7-8週 | 10-15万個 | 心室中隔 |
遺伝的要因と発生異常
DORVの発症には複数の遺伝子変異が関与し、特に心臓発生に関与する転写因子の変異が注目されています。
研究では、NKX2.5遺伝子の変異が約15%、GATA4遺伝子の変異が約12%の症例で確認されており、これらの変異は心臓発生の重要な調節因子に影響を及ぼします。
- 遺伝子変異の保有率:NKX2.5(15%)、GATA4(12%)、TBX1(8%)
- 心臓神経堤細胞の遊走速度:正常の約60-70%に低下
- 転写因子の発現量:健常群と比較して40-50%の減少
環境因子の影響
妊娠初期における環境要因の影響は、統計的に明確な相関を示しています。特に妊娠第4-8週における母体の発熱(38.5度以上)は、心臓発生異常のリスクを約2.1倍上昇させるとされています。
| 環境要因 | リスク上昇率 | 影響を受ける発生過程 |
|---|---|---|
| 高熱 | 2.1倍 | 心臓神経堤細胞の遊走 |
| 低栄養 | 1.8倍 | 心筋細胞の増殖 |
| 薬物曝露 | 2.5倍 | 血管形成過程 |
分子生物学的メカニズム
分子レベルでの異常は、複数のシグナル伝達経路に影響を及ぼします。BMPシグナルの活性は正常値の約65%に低下し、Notchシグナルは約45%の減少を示すことが報告されています。
| シグナル経路 | 活性低下率 | 影響を受ける細胞過程 |
|---|---|---|
| BMP経路 | 35% | 心筋分化 |
| Notch経路 | 55% | 血管形成 |
| Wnt経路 | 40% | 細胞増殖 |
遺伝子変異と病型の関連
病型による遺伝子変異の分布には明確な特徴があり、単純型では約25%、心室中隔欠損型では約35%、肺動脈狭窄型では約28%の症例で特定の遺伝子変異パターンが認められています。
- 遺伝子発現パターンの異常:全体の約75%で確認
- エピジェネティック修飾の変化:約60%の症例で観察
- 転写因子結合部位の変異:約45%の症例で同定
DORVの発症メカニズムについて、遺伝子解析技術の進歩により、より詳細な分子レベルでの理解が進んでいます。
両大血管右室起始症(DORV)の検査・チェック方法
両大血管右室起始症(DORV)の診断は、胎児期からの超音波検査に始まり、出生後の詳細な画像検査まで、段階的なアプローチで進めていきます。
診断の確実性を高めるため、身体診察、聴診所見、各種画像検査、そして必要に応じて遺伝子検査を組み合わせた総合的な評価を行います。
胎児期のスクリーニング検査
胎児超音波検査は妊娠20週前後での異常発見率が約75%に達し、DORVの初期診断において中心的な役割を担います。特に妊娠22-24週の胎児心エコー検査では、心臓の四腔像における異常所見の検出率が85%を超えると報告されています。
| 妊娠週数 | 検出精度 | 主な観察項目 |
|---|---|---|
| 18-20週 | 60-65% | 心臓位置・大きさ |
| 22-24週 | 85-90% | 四腔断面・血流 |
| 28-32週 | 90-95% | 大血管走行・機能 |
新生児期の臨床診断
出生後24時間以内の初期評価では、パルスオキシメーター測定による動脈血酸素飽和度が通常90%を下回り、心雑音の聴取率は約95%に達します。
経皮的酸素飽和度モニタリングでは、上下肢で5%以上の較差を認めることが診断の手がかりとなります。
- 動脈血酸素飽和度:85-90%(室内気)
- 心雑音の特徴:第2-3肋間胸骨左縁で最強点、収縮期雑音(Levine 3-4/6度)
- 呼吸数:分時60-80回(正常新生児の1.5-2倍)
画像診断による確定診断
心臓超音波検査の診断精度は熟練した検査者で98%に達し、3D心エコーによる立体構築では空間分解能0.5mm以下での観察が実現します。心臓MRIの空間分解能は1.0-1.5mm、時間分解能は20-30msと高精度な画像評価が可能となっています。
| 検査方法 | 空間分解能 | 時間分解能 |
|---|---|---|
| 2D心エコー | 0.5-1.0mm | 10-15ms |
| 3D心エコー | 0.3-0.5mm | 15-20ms |
| 心臓MRI | 1.0-1.5mm | 20-30ms |
病型分類のための精密検査
心臓カテーテル検査における各指標の測定では、右室圧は体血圧の80-100%を示し、肺体血流比(Qp/Qs)は病型により1.5-3.0の範囲で変動します。造影検査での大血管の位置関係の同定精度は99%を超えています。
| 測定項目 | 正常値 | DORV典型値 |
|---|---|---|
| 右室収縮期圧 | 15-25mmHg | 80-120mmHg |
| 肺動脈圧 | 15-30mmHg | 35-80mmHg |
| 左室拡張期圧 | 5-12mmHg | 15-25mmHg |
遺伝子検査と家族歴調査
遺伝子検査では、既知の原因遺伝子の変異同定率が約40%に達し、全エクソーム解析による新規変異の発見率は年間約5%ずつ上昇しています。家族歴の詳細な調査により、約15%で家族内発症が確認されます。
- 既知遺伝子変異の検出率:40%(全症例中)
- 新規変異の同定:年間5%の上昇率
- 家族内発症率:全症例の15%
DORVの診断精度は、複数の検査手法を組み合わせることで95%以上に達しており、早期発見と正確な病型診断が予後改善に重要な意味を持ちます。
両大血管右室起始症の治療方法と治療薬について
両大血管右室起始症(DORV)の治療は、外科的手術を中心とした根治療法と、それを補完する内科的治療から構成されます。
各病型や心血行動態の特徴に応じて、段階的な手術介入と薬物療法を組み合わせた包括的な治療戦略を立案します。
内科的治療の基本方針
新生児期から乳児期早期における内科的治療では、心不全のコントロールと肺血流の調整が治療の中心となり、およそ85%の症例で薬物療法を必要とします。
利尿薬の投与量は体重あたり1-2mg/kgから開始し、臨床症状に応じて最大4mg/kgまで増量します。
| 薬剤分類 | 投与量(mg/kg/日) | 投与回数 |
|---|---|---|
| フロセミド | 1-4 | 2-3回 |
| ジゴキシン | 0.005-0.01 | 2回 |
| カルベジロール | 0.1-0.8 | 2回 |
外科的治療のタイミング
手術時期の決定は心エコー所見や心臓カテーテル検査の結果に基づいて行われ、単純型では生後3-6ヶ月での一期的根治手術の成功率が92%を超えています。
心室中隔欠損型における手術成績は、6-12ヶ月時点での介入で95%以上の良好な結果を示しています。
- 単純型(3-6ヶ月):手術時間6-8時間、人工心肺時間120-180分
- VSD型(6-12ヶ月):手術時間4-6時間、人工心肺時間90-150分
- PS型:初回姑息手術(1-2ヶ月)、根治手術(12-18ヶ月)
周術期管理と薬物療法
周術期の管理では、術前のPGE1製剤(プロスタグランジンE1)を0.01-0.05μg/kg/分で持続投与し、動脈管の開存性を維持します。術中の心筋保護液は4℃で20分ごとに投与し、術後のカテコラミンサポートは3-5日間継続します。
| 管理時期 | 投与薬剤 | 投与量範囲 |
|---|---|---|
| 術前 | PGE1 | 0.01-0.05μg/kg/分 |
| 術中 | 心筋保護液 | 20ml/kg/回 |
| 術後 | DOA | 3-10μg/kg/分 |
長期フォローアップと薬物療法
術後の長期管理における抗凝固療法では、アスピリンを2-5mg/kg/日で投与し、約95%の症例で血栓性合併症を予防できています。β遮断薬の投与は、不整脈の発生率を従来の15%から3%未満に低下させる効果を示しています。
| フォロー期間 | 合併症発生率 | 予防薬使用率 |
|---|---|---|
| 1年未満 | 5% | 98% |
| 1-5年 | 3% | 95% |
| 5年以上 | 2% | 90% |
合併症対策と予防的投薬
感染性心内膜炎の予防投与では、アモキシシリン50mg/kgを処置の1時間前に単回投与します。この予防投薬により、感染性心内膜炎の発生率は0.1%未満に抑制されています。
- 感染性心内膜炎予防:アモキシシリン50mg/kg、単回投与
- 不整脈予防:β遮断薬0.5-1.5mg/kg/日、分2-3
- 血栓予防:アスピリン2-5mg/kg/日、分1
DORVに対する治療成績は、過去20年間で飛躍的に向上し、現在の10年生存率は90%を超える水準に到達しています。
両大血管右室起始症(DORV)の治療期間
両大血管右室起始症(DORV)の治療には、手術や薬物療法に伴うさまざまな副作用やリスクが存在します。
これらのリスクは、病型や患者さんの状態によって異なり、術前・術中・術後の各段階で発生する可能性があるため、慎重な観察と対応が求められます。
手術中のリスクと合併症
手術中の主なリスクとして、人工心肺装置の使用に関連する合併症が挙げられ、使用時間が3時間を超えると合併症の発生率が約1.5倍に上昇します。
人工心肺中の平均血圧は60-70mmHgを維持する必要があり、この範囲を外れると臓器灌流障害のリスクが2倍に増加するとされています。
| 手術時間 | 合併症発生率 | リスク増加倍率 |
|---|---|---|
| 2時間以内 | 3-5% | 基準値 |
| 2-3時間 | 5-8% | 1.2倍 |
| 3時間超 | 8-12% | 1.5倍 |
術後早期の合併症
術後72時間以内の急性期において、心機能は通常の60-75%程度まで一時的に低下し、約35%の患者さんで一過性の不整脈を経験します。体温管理では、36-37℃の維持が望ましく、この範囲を逸脱すると合併症リスクが上昇します。
- 心拍出量:正常値の60-75%まで低下(術後24-48時間)
- 一回換気量:4-6mL/kg(人工呼吸器管理中)
- 輸液バランス:1日あたり±300mL以内に調整
薬物療法による副作用
利尿薬の使用では、約25%の患者さんで血清カリウム値が3.5mEq/L以下に低下し、特に生後3ヶ月未満の乳児では電解質異常の発生率が1.8倍に増加します。
| 薬剤 | 副作用発生率 | 重症度別割合 |
|---|---|---|
| フロセミド | 25-30% | 軽症80%/中等症15%/重症5% |
| ジゴキシン | 15-20% | 軽症70%/中等症25%/重症5% |
| ワーファリン | 10-15% | 軽症85%/中等症12%/重症3% |
長期的な合併症
10年以上の長期観察では、約15%の患者さんで弁機能不全が進行し、年間約1-2%の割合で再手術が必要となります。不整脈の累積発生率は20年で約30%に達し、年齢とともに上昇傾向を示します。
| 観察期間 | 弁機能不全率 | 不整脈発生率 |
|---|---|---|
| 5年 | 5-8% | 10-15% |
| 10年 | 12-15% | 20-25% |
| 20年 | 18-22% | 28-35% |
予期せぬ合併症への対応
感染性心内膜炎の発生率は年間0.8-1.2%で、抗生物質予防投与により約65%の予防効果が得られます。血栓塞栓症の発生率は年間0.5-1.0%で、適切な抗凝固療法により約80%のリスク低減が実現します。
- 感染性心内膜炎:早期発見率60%(発熱出現から診断まで平均5.2日)
- 血栓塞栓症:予防効果80%(適切な抗凝固療法実施例)
- 突然死予防:リスク因子保有者の85%で予防措置が奏功
これらの副作用やリスクへの理解を深め、早期発見と迅速な対応により、良好な治療成績につながります。
薬の副作用や治療のデメリットについて
両大血管右室起始症(DORV)の治療には、手術や薬物療法に伴うさまざまな副作用やリスクが存在します。
これらのリスクは、病型や患者さんの状態によって異なり、術前・術中・術後の各段階で発生する可能性があるため、慎重な観察と対応が求められます。
手術中のリスクと合併症
手術中の主なリスクとして、人工心肺装置の使用に関連する合併症が挙げられ、使用時間が3時間を超えると合併症の発生率が約1.5倍に上昇します。人工心肺中の平均血圧は60-70mmHgを維持する必要があり、この範囲を外れると臓器灌流障害のリスクが2倍に増加するとされています。
| 手術時間 | 合併症発生率 | リスク増加倍率 |
|---|---|---|
| 2時間以内 | 3-5% | 基準値 |
| 2-3時間 | 5-8% | 1.2倍 |
| 3時間超 | 8-12% | 1.5倍 |
術後早期の合併症
術後72時間以内の急性期において、心機能は通常の60-75%程度まで一時的に低下し、約35%の患者さんで一過性の不整脈を経験します。体温管理では、36-37℃の維持が望ましく、この範囲を逸脱すると合併症リスクが上昇します。
- 心拍出量:正常値の60-75%まで低下(術後24-48時間)
- 一回換気量:4-6mL/kg(人工呼吸器管理中)
- 輸液バランス:1日あたり±300mL以内に調整
薬物療法による副作用
利尿薬の使用では、約25%の患者さんで血清カリウム値が3.5mEq/L以下に低下し、特に生後3ヶ月未満の乳児では電解質異常の発生率が1.8倍に増加します。
| 薬剤 | 副作用発生率 | 重症度別割合 |
|---|---|---|
| フロセミド | 25-30% | 軽症80%/中等症15%/重症5% |
| ジゴキシン | 15-20% | 軽症70%/中等症25%/重症5% |
| ワーファリン | 10-15% | 軽症85%/中等症12%/重症3% |
長期的な合併症
10年以上の長期観察では、約15%の患者さんで弁機能不全が進行し、年間約1-2%の割合で再手術が必要となります。不整脈の累積発生率は20年で約30%に達し、年齢とともに上昇傾向を示します。
| 観察期間 | 弁機能不全率 | 不整脈発生率 |
|---|---|---|
| 5年 | 5-8% | 10-15% |
| 10年 | 12-15% | 20-25% |
| 20年 | 18-22% | 28-35% |
予期せぬ合併症への対応
感染性心内膜炎の発生率は年間0.8-1.2%で、抗生物質予防投与により約65%の予防効果が得られます。血栓塞栓症の発生率は年間0.5-1.0%で、適切な抗凝固療法により約80%のリスク低減が実現します。
- 感染性心内膜炎:早期発見率60%(発熱出現から診断まで平均5.2日)
- 血栓塞栓症:予防効果80%(適切な抗凝固療法実施例)
- 突然死予防:リスク因子保有者の85%で予防措置が奏功
これらの副作用やリスクへの理解を深め、早期発見と迅速な対応により、良好な治療成績につながります。
保険適用と治療費
以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
先天性心疾患である両大血管右室起始症(DORV)の治療費用は、手術、入院、投薬など多岐にわたる医療サービスを必要とします。
健康保険制度による給付を受けることで、患者さんの経済的負担を軽減できる仕組みが整備されています。
処方薬の薬価
循環器系の治療薬は、その種類や投与量によって薬価が異なりますが、健康保険の適用により実質的な負担は3割となります。
一般的な心不全治療薬の場合、1日あたりの費用は300-500円の範囲内におさまり、月間で見ると9,000-15,000円程度の支出となるでしょう。
| 薬剤分類 | 1日あたりの薬価 | 月間実質負担額 |
|---|---|---|
| 利尿薬 | 100-200円 | 900-1,800円 |
| 強心薬 | 300-500円 | 2,700-4,500円 |
1週間の治療費
入院加療中の週単位での医療費は、一般病棟での基本入院料に加え、投薬や各種処置の費用が加算されます。
特に集中治療室(ICU)での管理が必要な場合、1日あたりの追加費用は10万円前後に達し、経済的な準備が重要になってきます。
- 一般病棟入院基本料:1日あたり20,000-30,000円(3割負担で6,000-9,000円)
- 投薬・処置関連費用:1日あたり10,000-20,000円(3割負担で3,000-6,000円)
- 各種検査費用:1回あたり20,000-50,000円(3割負担で6,000-15,000円)
1か月の治療費
手術を含む月間の総医療費は、手術の内容や入院期間によって300-500万円の範囲で変動します。
健康保険制度の適用により、実質的な自己負担額はその3割となる90-150万円程度となりますが、高額療養費制度の利用で更なる負担軽減が見込めます。
| 費用項目 | 総額 | 保険適用後自己負担額 |
|---|---|---|
| 手術関連費用 | 200-300万円 | 60-90万円 |
| 入院関連費用 | 100-150万円 | 30-45万円 |
以上
参考文献
榊原高之, et al. 臨床 両大血管右室起始症の分類と心血管造影診断. 心臓, 1974, 6.4: 511-527.
今村甲, et al. 臨床 乳児両大血管右室起始症の臨床. 心臓, 1969, 1.3: 270-286.
榊原高之. 両大血管右室起始症: 手術および剖検例 38 例の臨床検討. 東京女子医科大学雑誌, 1976, 47.8: 1003-1004.
岡田嘉之, et al. 臨床 肺動脈狭窄を伴う両大血管右室起始症の臨床像 とくに心血管造影所見を中心にして. 心臓, 1970, 2.3: 291-302.
川島康生. 弁つき同種大動脈を用いた大血管転位症の根治手術成功例について 両大血管右室起始症, 心室転位, 弁性および弁下性肺動脈狭窄, 心房および心室中隔欠損合併例. 日本胸部外科学会雑誌, 1970, 18.6: 596-602.
森克彦, et al. 症例 両大血管右室起始症における心室中隔欠損の自然狭窄 1 治験例. 心臓, 1974, 6.10: 1453-1461.
吉田哲也, et al. 症例 Straddling Mitral Valve を伴った両大血管右室起始 (L-loop, D-Malposition) の 1 剖検例. 心臓, 1980, 12.2: 194-199.
岡田嘉之, et al. 解説 両大血管右室起始症の形態と手術方針. 心臓, 1971, 3.7: 733-740.
河住茂, et al. 症例 42 歳で診断された肺動脈弁狭窄と左肺動脈上行大動脈起始を伴った両大血管右室起始症の 1 例. 心臓, 1993, 25.3: 295-300.