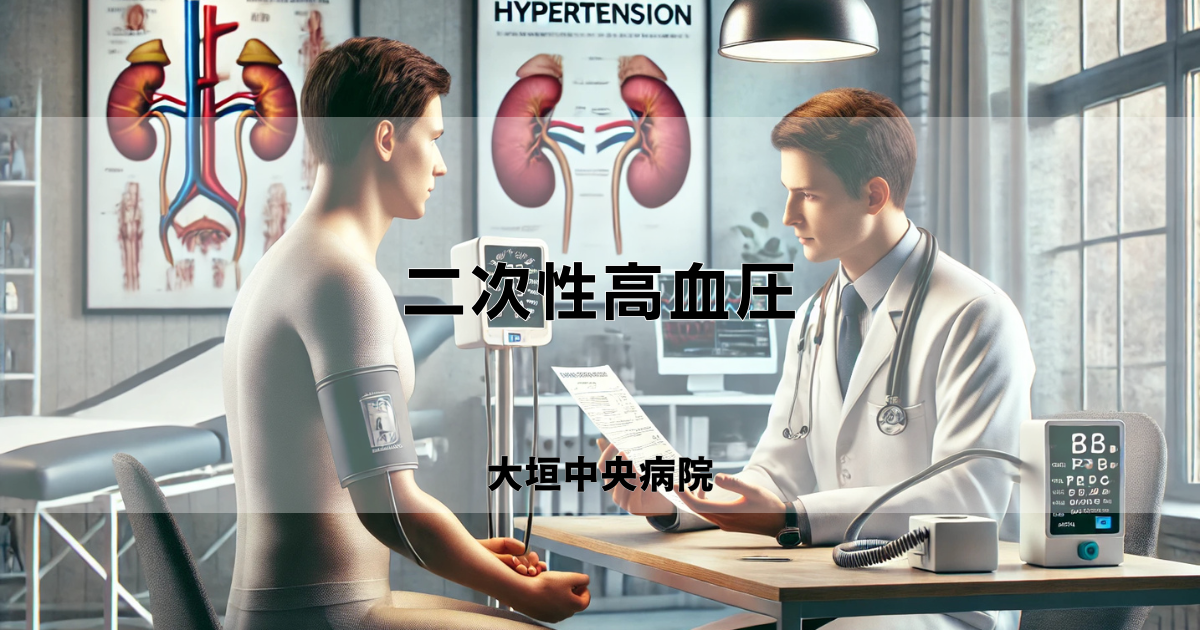二次性高血圧とは、ほかの疾患や異常が原因となって血圧が上昇する状態を指します。
原因が一次性高血圧(本態性高血圧)とは異なり、特定の要因を突き止めて取り除くことで血圧が安定する場合も多く、適切な治療が重要です。
高血圧が続くことで心筋梗塞や脳卒中、腎臓のダメージなどにつながる可能性があるため、気になる症状やリスク因子がある場合は早めに医療機関を受診して詳細を調べることが大切です。
ここでは二次性高血圧について、病型や症状、原因、検査・チェック方法、治療方法、治療にかかる期間、薬の副作用や治療上のデメリット、保険適用や費用面に至るまで詳しく解説します。
病型
二次性高血圧には、原因となる疾患や器質的異常によっていくつかのタイプがあります。ここでは代表的な病型の特徴や考えられるメカニズムについて、基本的な視点を示します。
早期発見や適切な治療を考えるためにも、全体像を把握することが大切です。
腎臓由来の二次性高血圧
腎臓の病気や血管の異常が引き起こすタイプは比較的多くみられます。特に腎動脈狭窄や慢性腎不全などが関係し、体内の水分・塩分バランスやホルモン調整が乱れやすくなります。
腎機能が低下すると血液中の老廃物をうまく排泄できず、血圧が上昇しやすい傾向があります。また、腎臓から分泌されるレニンというホルモンが高血圧に深く関与することでも知られています。
以下の表は、腎臓由来の代表的な疾患と高血圧の関係を示したものです。
| 疾患名 | 高血圧への関与の特徴 |
|---|---|
| 腎動脈狭窄 | レニン上昇による血管収縮作用で血圧が上昇しやすい |
| 慢性腎不全 | 体液量の増加やホルモン分泌の異常により血圧が上昇 |
| 糖尿病性腎症 | 糖尿病の進行に伴う腎機能の低下で血圧調整が乱れる |
| 多発性嚢胞腎 | 腎臓組織の損傷や圧迫によって高血圧が生じやすい |
さらに、腎臓が主な原因の場合、尿検査や腎機能検査、画像検査などで比較的早期に異常が見つかることもあります。
内分泌系由来の二次性高血圧
ホルモン分泌が過剰になったり、不足したりする内分泌系の異常も高血圧の原因になります。たとえば原発性アルドステロン症やクッシング症候群、甲状腺機能亢進症などが挙げられます。
これらはホルモン過剰分泌が血圧上昇の直接的な引き金となる点が特徴です。
- 原発性アルドステロン症では、アルドステロンが多く分泌されることでナトリウムと水分が体内に残り、カリウムが排泄されすぎる傾向があります。
- クッシング症候群では、コルチゾールというホルモンが過剰に分泌されて高血圧や糖代謝異常、満月様顔貌(ムーンフェイス)などが起こりやすくなります。
血管系由来の二次性高血圧
大動脈縮窄や動脈瘤などの血管の異常によっても高血圧が起こります。血管の狭窄部位以降の血流が滞ると、血液を送り出すポンプ作用が強化されてしまうため上流の血圧が上がることになります。
年齢や基礎疾患によっては見逃されるケースもあるため、動脈硬化などのリスク因子を持つ人は細心の注意が必要です。
下記の箇条書きにまとめると、血管系由来の高血圧には以下の特徴があります。
- 血管壁の狭窄や硬化に伴う血流抵抗の増加
- 先天的な血管形成異常による血圧上昇
- 動脈瘤形成による周囲組織への圧迫と血液動態の乱れ
薬剤性高血圧
一部の薬剤は血圧を上昇させる作用を持ちます。たとえば経口避妊薬やステロイド薬、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)などを長期で使用している場合、思わぬ副次的影響として高血圧が発症するケースがあります。
薬が体にもたらすメリットとデメリットを総合的に考慮しながら、必要に応じて医師と相談しつつ別の薬に切り替える判断が求められます。
二次性高血圧の症状
二次性高血圧には、原因疾患の特徴が色濃く反映されます。
一次性高血圧(本態性高血圧)のように自覚症状が乏しい場合もありますが、他の病気に起因していることが多いため、特有のサインを示すこともあります。ここでは、その多彩な症状について具体的に紹介します。
血圧以外の体調変化に注目
血圧の上昇そのものが急激に起こる場合があり、めまいや頭痛、動悸などを引き起こします。また、腎疾患が関係するケースでは以下のような症状が伴うことがあります。
- 尿の色が普段と違う、泡立ちが増える
- むくみやすくなる
- 倦怠感が続く
こうした体調変化が続く場合、生活習慣やストレスだけでなく基礎疾患の存在を疑うことが大切です。
内分泌系の異常による特徴
ホルモンが関係する二次性高血圧では、高血圧以外にも特徴的な兆候がみられます。たとえばクッシング症候群では満月様顔貌や中心性肥満、多毛などの症状が同時に起こりやすくなります。
甲状腺機能亢進症の場合には、発汗や動悸、体重減少、手の震えなどが多くみられます。
以下の表に、内分泌系疾患による症状の一例を示します。
| 疾患名 | 主な症状・サイン |
|---|---|
| 原発性アルドステロン症 | 血圧上昇、低カリウム血症、筋力低下、倦怠感など |
| クッシング症候群 | 高血圧、満月様顔貌、中心性肥満、糖代謝異常など |
| 甲状腺機能亢進症 | 頻脈、発汗過多、体重減少、手指振戦など |
| 褐色細胞腫 | 頻回の動悸発作、発汗、激しい頭痛、高血糖など |
血管異常の症状
血管性の問題から二次性高血圧が起こると、血流障害による下肢の冷えやしびれ、動脈瘤の圧迫による疼痛などが起こることがあります。
大動脈縮窄の場合、腕の血圧は高いのに下肢の血圧が著しく低いという特徴的な所見がみられることがあります。
こうした症状の裏には血流の分配不全があるため、身体のどの部位にどのような違和感があるかをしっかりと把握する必要があります。
薬剤性高血圧の症状
服用している薬の副作用が原因で血圧が上昇するケースでは、血圧以外に次のような影響が出ることもあります。
- 胃腸障害
- 体重増加傾向
- だるさや眠気
- 頭痛
もし服用中の薬を変えた時期を境に血圧が上昇し始めた場合は、薬剤性高血圧を疑って医師に相談するとよいでしょう。
二次性高血圧の原因
二次性高血圧にはさまざまな引き金がありますが、主に腎疾患、内分泌系の異常、血管の構造的問題、薬剤などに大別されます。ここではより詳細な観点でその原因を確認し、自分自身のリスク因子を考える参考にしてください。
腎疾患がもたらす要因
腎臓は血液をろ過して尿をつくるだけでなく、血圧を調整する重要なホルモンを分泌します。腎臓自体に炎症や血管の詰まり、腫瘍がある場合、血圧が不安定になりやすい傾向があります。
腎臓に負担をかける生活習慣や病気を抱えている場合は注意が必要です。
下記の箇条書きは、腎疾患に関連するリスク要因の例です。
- 塩分過多の食生活
- 慢性的な脱水や水分摂取不足
- 長期的な高血糖や糖尿病
- 喫煙や過度のアルコール摂取
ホルモン過剰分泌や分泌異常
内分泌系は体内のさまざまな機能をコントロールしています。甲状腺や副甲状腺、副腎などに異常があると、レニン-アンジオテンシン-アルドステロン系の過剰活性を引き起こし、高血圧につながるケースがあります。
特に原発性アルドステロン症は高血圧患者の中でも一定の割合を占め、近年注目されています。
以下の表で、代表的な内分泌異常とその特徴を簡潔にまとめます。
| 内分泌異常の種類 | 概要 |
|---|---|
| 原発性アルドステロン症 | アルドステロン分泌増加でナトリウムや水分が体内に滞留し血圧上昇 |
| クッシング症候群 | コルチゾール過剰分泌により高血圧や脂質代謝異常、糖代謝異常を伴う |
| 甲状腺機能亢進症 | 代謝亢進と血行動態の亢進により血圧が上がりやすくなる |
| 褐色細胞腫 | カテコールアミンの過剰放出で発作的な高血圧を引き起こす |
血管の形態的・機能的異常
大動脈の先天的な狭窄、大動脈解離、動脈瘤、動脈硬化など、血管の形態や機能に問題があると血液の流れが阻害され、血圧に偏りが生じる場合があります。
特に大動脈縮窄は若年層の高血圧の原因となることがあるため、子どものころから血圧が高いと言われていた場合には、一度は疑ってみる必要があります。
- 若年性高血圧の中には大動脈縮窄の症例が含まれる
- 動脈硬化や解離は急激に症状が進行する場合がある
- 末梢血流不足に伴うしびれや冷え、だるさが出る
薬剤、その他の原因
一部の薬剤、特にステロイドやNSAIDs、経口避妊薬などは、服用期間が長いと二次性高血圧のリスクが高まるといわれています。
また、習慣的な喫煙やアルコール乱用、コカインなどの薬物使用も血圧を上げる原因となりえます。可能な限り負担を減らす形で治療方針を考えることが大切です。
二次性高血圧の検査・チェック方法
二次性高血圧は、元となる疾患を見つけることで治療方針が明確になります。さまざまな検査を組み合わせて、隠れた疾患やホルモン異常などを探ることが重要です。ここでは主な検査・チェック方法を挙げます。
血液検査や尿検査によるスクリーニング
最初に行われることが多いのは血液検査と尿検査です。腎機能や電解質バランス、血糖値、ホルモン値など、さまざまな項目を同時に調べます。二次性高血圧を疑う際には、以下の点に注目します。
- 血清クレアチニン、尿タンパク量など腎機能の評価
- レニン・アルドステロン比やコルチゾール値による内分泌評価
- 甲状腺ホルモン値(TSH、FT4など)の異常
次の表に、代表的な検査項目とその目的をまとめました。
| 検査項目 | 目的・意義 |
|---|---|
| 血清クレアチニン | 腎機能の把握 |
| BUN(尿素窒素) | 腎臓のろ過機能を推測 |
| レニン・アルドステロン | ホルモン分泌異常の発見 |
| 甲状腺ホルモン(TSH,FT4) | 甲状腺機能の亢進や低下の有無を確認 |
| コルチゾール | クッシング症候群の可能性を探る |
| カテコールアミン | 褐色細胞腫を疑う際に評価 |
画像検査による器質的異常の確認
腎動脈狭窄や大動脈縮窄など、血管系の問題が疑われる場合には画像検査が有効です。CTやMRI、エコー検査で血管の狭窄や腫瘍の有無などを詳しく確認します。腎エコーで腎臓のサイズや構造を調べることも多いです。
- CTでは血管の形態や狭窄を確認
- MRIでは軟部組織や腫瘍性変化を捉えやすい
- エコーは放射線被ばくがないため繰り返し検査に向いている
ホルモン負荷試験や24時間蓄尿検査
クッシング症候群や原発性アルドステロン症などを疑う場合、ホルモン負荷試験を行うことがあります。また、24時間蓄尿検査で体内のホルモンや電解質がどのように変動しているかをつかむことも大切です。
複数の時間帯のデータを集めることで、通常の血液検査だけでは見落としがちな異常を発見できます。
以下の箇条書きは、ホルモン検査の特徴的なポイントです。
- 負荷試験でホルモン分泌の反応性を評価する
- 24時間蓄尿検査で日内変動を見極める
- 異常値が得られた場合、追加で画像検査などを組み合わせて確定診断へ
血圧測定のバリエーション
家庭での血圧測定やホルター血圧測定(24時間血圧測定)など、さまざまな方法を活用し、変動幅を観察するのも重要です。
診察室では高く出る「白衣高血圧」や、逆に診察室では正常なのに家庭で高くなる「仮面高血圧」が存在するため、日常的な計測が大切です。
二次性高血圧の治療方法と治療薬について
二次性高血圧の治療は、原因疾患の管理が基本になります。一次性高血圧の場合と異なり、原因を取り除くことで血圧が安定するケースも多くみられます。ここでは、原因別の治療方法や使用される薬について解説します。
腎疾患が原因の場合の治療
腎動脈狭窄の場合、血管拡張を目的としたカテーテル治療やステント留置が選択肢となります。慢性腎不全が関与している場合は、食事療法と降圧薬の併用に加えて、腎臓の機能維持を目指すための管理が重要です。
透析導入が必要になったケースでも、降圧の指標を踏まえて調整していきます。
以下の表は、腎由来の二次性高血圧に用いられる主な治療法と特徴をまとめたものです。
| 治療法 | 特徴 |
|---|---|
| 経皮的腎動脈形成術 | 腎動脈の狭窄部位を風船などで拡張して血流を改善 |
| ステント留置 | 狭窄部位を金属製のステントで支えて再び狭くなるのを防ぐ |
| 食事療法 | 塩分制限やタンパク質制限などで腎臓への負担を軽減 |
| 透析 | 腎機能が大幅に低下したときに人工的に血液をろ過して老廃物を排出する |
内分泌性高血圧の場合
ホルモン異常が原因の高血圧では、そのホルモン分泌を抑える薬や腫瘍があれば手術で切除するなど、原因に合わせた治療を行います。
原発性アルドステロン症は内服薬でアルドステロンの作用を抑制し、カリウム補給を並行して行う方法がとられます。クッシング症候群の場合は、副腎腫瘍を外科的に切除するケースが一般的です。
- ホルモン抑制薬を併用して血中ホルモン濃度のコントロール
- 腫瘍性病変がある場合は手術療法を選択
- 食事や生活習慣の見直しでホルモンバランスを保つ工夫
血管性高血圧の場合
大動脈縮窄や動脈瘤が原因であれば、外科的介入が必要となることがあります。薬物療法だけでは対応しきれない場合、外科的手法で血行を改善し、血圧を正常に保ちやすくします。
手術の適応やタイミングについては、症状の進行度や全身状態を考慮しながら慎重に判断します。
薬剤性高血圧の場合
もし服用中の薬が高血圧の原因であると判明したら、医師と相談しながら代替薬への切り替えや使用量の調節を行います。
ただし、薬剤本来の治療効果が高く、切り替えが難しい場合もあります。副作用と効能のバランスを考慮し、必要に応じて追加の降圧薬を導入するケースもあります。
治療期間
二次性高血圧の治療期間は原因疾患や患者さんの全身状態、治療効果によって変わります。ここでは、大まかな治療期間のイメージやフォローアップの必要性を解説します。
焦らずに計画的に治療することで、合併症のリスクを抑えることが大切です。
原因疾患の特定と初期治療
二次性高血圧では、まず原因をはっきりさせるための精密検査に一定の時間がかかります。検査結果をもとに原因疾患を特定し、治療方針を立てるまでに数週間から数か月を要することもあります。
その後、薬物療法や手術療法などが始まり、血圧が落ち着くまでにさらに時間がかかるケースがあります。
以下の箇条書きは、初期治療の流れの一例です。
- 検査結果に基づいて根本原因の明確化
- 内科的治療・外科的治療の方針決定
- 治療薬の開始や用量調整
- 数週間~数か月単位で効果判定
長期管理が必要な場合
慢性腎不全やホルモン異常による二次性高血圧の場合、基本的には長期的な管理が必要になります。腎機能が徐々に低下していく場合は、透析や腎移植などが視野に入ることもあります。
ホルモン異常の場合は、薬でホルモン分泌をコントロールしながら定期的に検査を行い、血圧を維持していくことになります。
| 状態 | 長期管理のポイント |
|---|---|
| 慢性腎不全 | 定期検査、食事管理、透析の導入タイミングの検討 |
| 原発性アルドステロン症 | ホルモン抑制薬の内服、電解質バランスの観察 |
| クッシング症候群 | 手術後の再発防止に向けた定期フォローアップ |
手術後の経過観察
大動脈縮窄や腫瘍など、外科的手術で原因を取り除いた場合でも、再発や別の合併症が生じるリスクをゼロにはできません。
術後しばらくは血圧が急に低下することもあるため、入院して血圧モニタリングを行うことも少なくありません。その後は退院しても定期的な検査が重要です。
ライフスタイルの見直しと継続
原因疾患を克服しても、再び血圧が上昇しないように食事療法や適度な運動、十分な睡眠などのライフスタイル面の改善を継続する必要があります。自己判断で治療を中断せず、定期的な受診で調子を確認すると安心です。
二次性高血圧薬の副作用や治療のデメリットについて
治療薬を使うことで血圧を管理し、合併症リスクを抑えられる一方、薬による副作用や治療上のデメリットが生じることがあります。ここではそれらの可能性を理解し、上手に付き合っていくためのポイントを整理します。
薬の作用と副作用のバランス
降圧薬にはさまざまな種類があり、個々の作用機序や副作用が異なります。たとえばACE阻害薬やARBは咳や高カリウム血症を引き起こす可能性があり、カルシウム拮抗薬では動悸や顔のほてりが起こることがあります。
利尿薬を使うと電解質バランスが乱れやすくなり、脱水傾向になる場合もあります。
下記の箇条書きは代表的な降圧薬の副作用例です。
- ACE阻害薬:空咳、血中カリウム上昇
- カルシウム拮抗薬:動悸、顔面紅潮、頭痛
- β遮断薬:倦怠感、徐脈、気管支ぜんそく悪化
- 利尿薬:低カリウム血症、脱水、頻尿
原因疾患に特化した薬の副作用
二次性高血圧では、原因疾患そのものを治療するための薬を使う場面が多くあります。たとえば副腎ホルモンを抑制する薬はホルモンバランスを崩しやすいため、体重増減やムーンフェイスなどが出ることもあります。
腎疾患の進行を遅らせる薬では、長期的に肝機能や胃腸障害に注意が必要なケースがあります。
治療のデメリット
降圧薬や原因疾患に対処する薬を使うことで、患者さんの生活にいくつかのデメリットが生じる場合があります。たとえば薬の服用回数が増えることで生活リズムが縛られ、医療費の負担がかさんでしまう可能性があります。
また、利尿薬を使うケースでは夜間頻尿が増え、睡眠の質が低下することも考えられます。
以下の表に、治療で考慮すべきデメリットをまとめています。
| デメリットの内容 | 対応策 |
|---|---|
| 薬の種類や服用回数の増加 | 主治医との相談により服用スケジュールを整理 |
| 医療費の負担が大きい | ジェネリック医薬品の活用や保険制度の確認 |
| 夜間頻尿などの生活上の制限 | 就寝前の水分調整や薬の服用タイミングの見直し |
副作用と上手に付き合うコツ
副作用が強く出てしまう場合、主治医に相談して薬の種類や用量の調整を検討します。絶対に自己判断で薬をやめるのではなく、不安や悩みを正直に伝えることが大切です。
医療スタッフとの連携を密にすることで、治療のデメリットをできるだけ小さく抑えながら血圧を管理できます。
保険適用と治療費
以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
二次性高血圧の治療は、通常の高血圧治療よりも精密検査や専門的な治療が必要になることが多いため、医療費がかさむ可能性があります。ここでは保険適用の範囲や治療費の考え方などについて説明します。
健康保険の適用範囲
二次性高血圧は、特定の疾患に起因する高血圧として診断がついた場合でも、公的健康保険の適用範囲に含まれます。
内科や循環器内科、腎臓内科、内分泌内科など、専門科での受診・検査が必要になりますが、保険診療で対応できるケースがほとんどです。
- 血液検査や尿検査、画像検査は保険診療内
- 手術やカテーテル治療も必要性が認められれば保険適用
- 入院費用も保険適用の対象
特定疾患や指定難病の扱い
二次性高血圧の原因疾患が特定疾患や指定難病に該当する場合、医療費助成制度が活用できる場合があります。ただし、すべての原因疾患が対象となるわけではないため、担当医や自治体の窓口に確認が必要です。
| 制度名 | 対象・特徴 |
|---|---|
| 指定難病制度 | 厚生労働省が指定した難病を対象に医療費助成が受けられる |
| 重度障害者医療費助成 | 患者さんの障害認定に応じて助成される場合がある |
| 障害年金 | 働けない状態が続くときに給付を受けられる可能性がある |
二次性高血圧とは、別の疾患や器質的異常により血圧が上昇する状態を指す。本記事では病型や症状、原因、検査、治療方法、治療期間、副作用、保険適用や費用面などを詳しく解説している。
原因を正確に把握して治療を行えば血圧が安定する可能性が高まり、合併症のリスク低減にもつながるため、適切な受診や検査を検討することが大切である。
以上
参考文献
OMURA, Masao, et al. Prospective study on the prevalence of secondary hypertension among hypertensive patients visiting a general outpatient clinic in Japan. Hypertension Research, 2004, 27.3: 193-202.
MOCHIZUKI, Seibu, et al. RETRACTED: Valsartan in a Japanese population with hypertension and other cardiovascular disease (Jikei Heart Study): a randomised, open-label, blinded endpoint morbidity-mortality study. The Lancet, 2007, 369.9571: 1431-1439.
YAGI, Shusuke, et al. High serum parathyroid hormone and calcium are risk factors for hypertension in Japanese patients. Endocrine Journal, 2014, 61.7: 727-733.
WAKI, Takashi, et al. Prevalence of hypertensive diseases and treated hypertensive patients in Japan: A nationwide administrative claims database study. Hypertension Research, 2022, 45.7: 1123-1133.
OHKUBO, Takayoshi, et al. Prognosis of “masked” hypertension and “white-coat” hypertension detected by 24-h ambulatory blood pressure monitoring: 10-year follow-up from the Ohasama study. Journal of the American College of Cardiology, 2005, 46.3: 508-515.
FUKUDA, Keiichi, et al. Guidelines for the treatment of pulmonary hypertension (JCS 2017/JPCPHS 2017). Circulation Journal, 2019, 83.4: 842-945.
RIMOLDI, Stefano F.; SCHERRER, Urs; MESSERLI, Franz H. Secondary arterial hypertension: when, who, and how to screen?. European heart journal, 2014, 35.19: 1245-1254.
HATA, Akira, et al. Angiotensinogen as a risk factor for essential hypertension in Japan. The Journal of clinical investigation, 1994, 93.3: 1285-1287.
MORIMOTO, Atsushi, et al. Sodium sensitivity and cardiovascular events in patients with essential hypertension. The Lancet, 1997, 350.9093: 1734-1737.
JATOS STUDY GROUP, et al. Principal results of the Japanese trial to assess optimal systolic blood pressure in elderly hypertensive patients (JATOS). 2008.