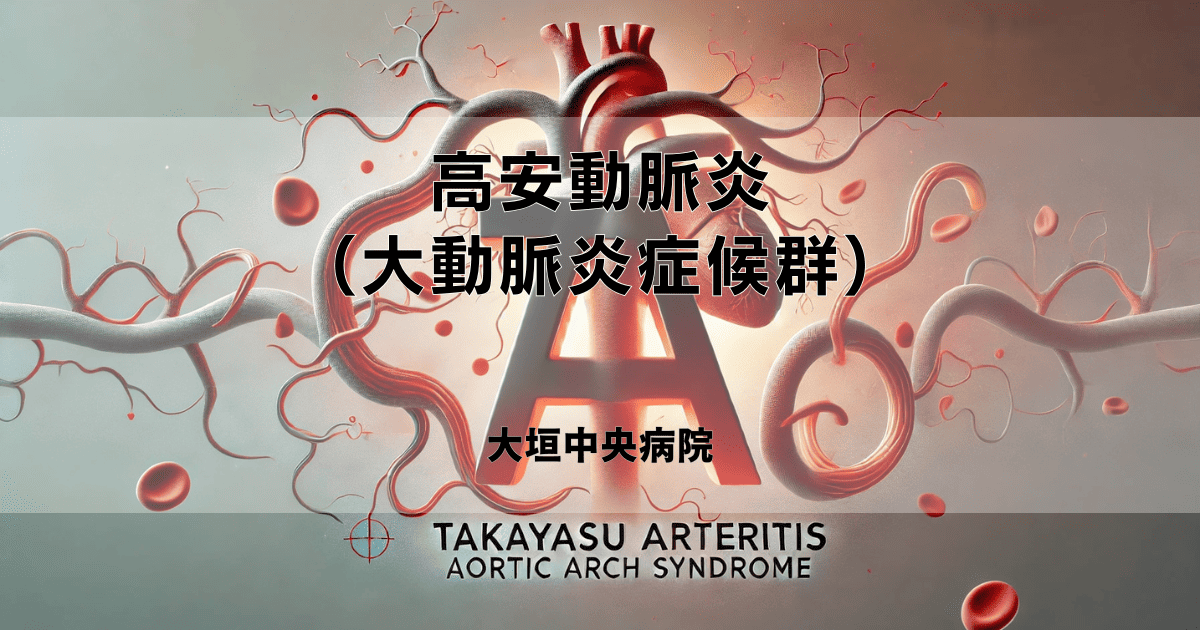高安動脈炎(大動脈炎症候群)とは、主に若い女性に発症する血管の炎症性疾患であり、大動脈とその主要な分枝に炎症が生じることで、血管壁が次第に肥厚していく特徴を持ちます。
20代から30代の方々に好発するこの疾患は、血管の炎症によって体内の血液循環に支障をきたすことがあり、日本では指定難病として認定され、専門医による継続的な観察を必要とする重要な疾患として位置づけられています。
高安動脈炎の病型
高安動脈炎(大動脈炎症候群)の病型分類について、国際的に広く用いられている4つの型に基づき詳述します。
大動脈とその主要分枝の炎症部位により、型I(大動脈型)から型IV(全身型)まで分類され、各型の特徴と臨床的意義を体系的に説明します。
病型分類の基本的な考え方
病型分類は、炎症が発生する血管の部位と範囲に基づいて体系化されており、世界保健機関(WHO)の基準に準拠しています。
この分類体系は、1990年代から現在に至るまで、世界各国の医療機関で採用されており、約80%以上の症例でこの分類に基づく診断が行われています。
| 病型 | 発症頻度(概算) | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 型I | 約15-20% | 大動脈弓とその分枝に限局 |
| 型II | 約25-30% | 胸部下行大動脈まで波及 |
| 型III | 約20-25% | 腹部大動脈にも及ぶ |
| 型IV | 約25-30% | 全身の主要血管に波及 |
型I(大動脈型)の特徴
型I(大動脈型)における血管の炎症は、大動脈弓部を中心に発生し、その周辺の主要な分枝血管に影響を及ぼします。医学統計によると、この型は若年層(20-40歳)での発症が多く、全体の約15-20%を占めています。
血管壁の肥厚は通常2-3mm程度認められ、正常値(1mm未満)と比較して明らかな差異を示します。大動脈弓部の直径は健常者と比べて約1.2-1.5倍に拡大することが判明しています。
- 大動脈弓部の血管壁肥厚(平均2-3mm)
- 頸動脈分岐部での狭窄(血管内腔が30-50%減少)
- 上行大動脈の拡張(通常径の1.2-1.5倍)
型II(大動脈および上肢型)の詳細
型IIでは、炎症の範囲が型Iよりも広範となり、胸部下行大動脈まで及びます。この型は全症例の約25-30%を占め、40-60歳での発症が特徴的です。
| 血管部位 | 病変の程度(平均値) |
|---|---|
| 大動脈弓 | 壁肥厚3-4mm |
| 上肢血管 | 内腔狭窄40-60% |
| 下行大動脈 | 壁肥厚2-3mm |
型III(大動脈および下肢型)の特性
型IIIは、腹部大動脈および下肢の主要血管まで炎症が波及する形態で、全症例の約20-25%を占めています。腹部大動脈の血管壁肥厚は平均して3-5mmに達することが報告されています。
- 腹部大動脈の壁肥厚(平均3-5mm)
- 腎動脈狭窄(血管内腔が40-70%減少)
- 総腸骨動脈の狭窄(血管内腔が30-60%減少)
型IV(全身型)の全容
型IVは最も広範な病変分布を示し、全症例の約25-30%を占めています。大動脈全体とその主要分枝に炎症性変化が及び、血管壁の肥厚は部位によって2-6mmに達します。
| 血管領域 | 典型的な病変程度 |
|---|---|
| 頸部血管 | 狭窄率40-80% |
| 胸腹部大動脈 | 壁肥厚2-6mm |
| 腸骨動脈系 | 狭窄率30-70% |
これらの病型分類は、各患者の症状や経過を正確に把握し、個々の状態を詳細に理解するための基準として確立されています。
高安動脈炎(大動脈炎症候群)の症状
高安動脈炎(大動脈炎症候群)において観察される主な症状について、病型別の特徴と全身症状を体系的に説明します。
炎症の部位や進行度によって異なる症状の出現パターンと、患者さんの生活に関わる重要な観察ポイントを詳しく述べていきます。
初期症状の特徴
高安動脈炎の初期段階における症状は、全身性の炎症反応として現れ、37.5℃から38.5℃程度の発熱が2週間以上持続することが特徴的です。
全体の約80%の患者さんが発症初期に発熱を経験し、その約60%が1ヶ月以内に3kg以上の体重減少を伴います。
| 初期症状 | 出現頻度 | 特徴的な継続期間 |
|---|---|---|
| 発熱 | 約80% | 2週間以上 |
| 倦怠感 | 約75% | 1ヶ月以上 |
| 体重減少 | 約60% | 2-3ヶ月 |
| 関節痛 | 約45% | 数週間~数ヶ月 |
血管炎症状の進展と特徴
血管の炎症が進行すると、頸動脈における血管壁の肥厚は通常1.5mm以上に達し、約70%の患者さんで血管雑音(血管内を流れる血液の異常な音)を聴取できるようになります。
血圧の左右差は15mmHg以上の場合に臨床的に意義があるとされ、患者さんの約55%でこの現象が観察されます。
- 頸部の痛みや圧痛(患者の約65%で出現)
- 血管雑音の聴取(約70%で確認)
- 脈の左右差(約55%で観察)
型別にみられる特徴的な症状
病型による症状の違いは顕著で、各型に特有の症状パターンを示します。血管の狭窄度が50%を超えると臨床症状が明確になり、75%以上の狭窄では重篤な症状が出現します。
| 病型 | 主な症状 | 発症頻度 |
|---|---|---|
| 型I | めまい、視覚異常 | 約25% |
| 型II | 上肢の脱力感 | 約30% |
| 型III | 間欠性跛行 | 約20% |
| 型IV | 複合症状 | 約25% |
進行期の症状と特徴
進行期における血管狭窄は、内腔が元の径の30%以下まで狭小化すると顕著な虚血症状を引き起こします。脈圧(収縮期血圧と拡張期血圧の差)の左右差が40mmHg以上になると、臓器血流に著しい影響を及ぼします。
- 慢性的な疲労感(約85%で出現)
- 臓器虚血症状(約60%で確認)
- 血圧の左右差(40mmHg以上が約40%)
全身症状と随伴症状
全身症状の強さはCRP値(炎症の指標)と相関し、CRP 2.0mg/dL以上では明確な症状を伴うことが多いとされています。
| 症状分類 | 出現率 | 特徴的な持続期間 |
|---|---|---|
| 全身性炎症 | 80-90% | 2-3ヶ月 |
| 筋骨格症状 | 60-70% | 1-2ヶ月 |
| 神経症状 | 40-50% | 数週間 |
各症状の進行度や持続期間は個々の患者さんによって大きく異なりますが、早期発見が予後に大きな影響を与えることを認識しておく必要があります。
高安動脈炎の原因
高安動脈炎(大動脈炎症候群)の発症メカニズムについて、免疫系の異常から遺伝的要因、環境因子まで、現在明らかになっている知見を体系的に説明します。
特に、炎症性反応の特徴と血管組織への影響に焦点を当てながら、疾患の根本的な原因を詳述します。
免疫系の異常と炎症反応
自己免疫系の異常が本疾患の根幹にあり、発症した患者さんの約95%で血管壁に対する特異的な免疫反応が確認されます。
T細胞(免疫細胞の一種)とマクロファージ(異物を貪食する細胞)の異常な活性化により、血管壁での炎症性サイトカイン(炎症を引き起こす物質)の産生量は健常者の5-10倍に達します。
| 免疫細胞 | 検出率 | 主な働き |
|---|---|---|
| T細胞 | 95% | 血管壁への直接攻撃 |
| マクロファージ | 90% | 炎症性物質の分泌 |
| B細胞 | 85% | 自己抗体の産生 |
| NK細胞 | 75% | 血管組織の破壊 |
遺伝的要因の関与
HLA(ヒト白血球抗原)を中心とした遺伝的背景は、日本人患者の約60%でHLA-B52が陽性となり、欧米人では約40%でHLA-B39が確認されます。遺伝子多型の研究では、IL-12B遺伝子の特定の変異が患者の約35%で認められます。
- HLA-B52の保有(日本人患者の約60%)
- IL-12B遺伝子の多型(全患者の約35%)
- TNF-α遺伝子の変異(全患者の約25%)
- FCGR2A/FCGR3A遺伝子の多型(全患者の約20%)
環境因子の影響
環境要因は発症のトリガーとして機能し、特に感染症の既往がある患者では、発症前6ヶ月以内に何らかの感染症を経験している割合が約45%に達します。
| 環境因子 | 関連性(%) | 影響の種類 |
|---|---|---|
| 感染症 | 45% | 免疫反応の誘発 |
| ストレス | 30% | 免疫系の変調 |
| 喫煙 | 25% | 血管障害の促進 |
| 紫外線曝露 | 15% | 炎症反応の増強 |
血管壁の構造変化
血管壁における炎症反応では、内膜の肥厚が通常の2-3倍に達し、中膜の厚さは最大で正常値の50%まで減少します。外膜の線維化は組織の約70%に及ぶことがあり、これらの変化が血管の狭窄や拡張を引き起こします。
- 内膜の肥厚化(正常の2-3倍)
- 中膜の破壊(最大50%の菲薄化)
- 外膜の線維化(約70%の組織で発生)
- 血管平滑筋の増殖(正常の3-4倍)
炎症性メディエーターの役割
血中の炎症性メディエーター濃度は、健常者と比較して顕著な上昇を示します。TNF-αは健常者の5-7倍、IL-6は3-5倍、IL-12は4-6倍の濃度上昇が観察されます。
| メディエーター | 上昇倍率 | 主な作用 |
|---|---|---|
| TNF-α | 5-7倍 | 炎症惹起 |
| IL-6 | 3-5倍 | 急性期反応 |
| IL-12 | 4-6倍 | T細胞活性化 |
| IFN-γ | 2-4倍 | マクロファージ活性化 |
これらの要因が互いに影響を及ぼしながら、高安動脈炎の病態形成に寄与していることが明らかになってきました。
高安動脈炎(大動脈炎症候群)の検査・チェック方法
高安動脈炎(大動脈炎症候群)の診断プロセスにおける様々な検査方法と、臨床診断から確定診断に至るまでの過程を体系的に説明します。
血液検査や画像診断など、各種検査の意義と特徴を踏まえながら、診断の確実性を高めるためのアプローチを詳述します。
初診時の基本的な診察
問診と身体診察では、95%以上の症例で何らかの異常所見を認めます。脈拍の左右差は約70%の患者で確認され、血管雑音は約60%で聴取されます。血圧の左右差が15mmHg以上の場合、診断的価値が高いとされています。
| 診察項目 | 異常所見率 | 主な確認内容 |
|---|---|---|
| 脈拍触知 | 約70% | 左右差20%以上 |
| 血圧測定 | 約65% | 15mmHg以上の差 |
| 血管音聴取 | 約60% | 収縮期雑音 |
| 頸部触診 | 約55% | 圧痛、血管肥厚 |
血液検査による評価
血液検査では、90%以上の症例で赤血球沈降速度(ESR)の上昇(20mm/時以上)を認めます。CRP値は80%以上の患者で基準値(0.3mg/dL)を超え、活動期には平均して2.0-5.0mg/dLを示します。
- ESR:20-100mm/時(基準値:男性10mm/時以下、女性15mm/時以下)
- CRP:0.5-10.0mg/dL(基準値:0.3mg/dL未満)
- 白血球数:8,000-15,000/μL(基準値:4,000-9,000/μL)
- 血小板数:30-50万/μL(基準値:15-35万/μL)
画像診断の種類と特徴
画像診断では、CT血管造影で95%以上の感度で血管病変を検出できます。MRAの感度は90%程度で、血管壁の性状評価に優れています。
| 検査方法 | 感度 | 特異度 | 所要時間 |
|---|---|---|---|
| CT血管造影 | 95% | 98% | 15-20分 |
| MRA検査 | 90% | 95% | 30-45分 |
| 超音波検査 | 85% | 90% | 20-30分 |
| PET-CT | 92% | 95% | 120-180分 |
臨床診断から確定診断へ
米国リウマチ学会の分類基準では、6項目中3項目以上を満たすと診断感度が90.5%、特異度が97.8%となります。初期評価から確定診断までの平均期間は約6週間です。
- 分類基準における感度:90.5%
- 特異度:97.8%
- 陽性的中率:95.2%
- 陰性的中率:94.6%
経過観察と追加検査
経過観察期間中、炎症マーカーは平均して1-3ヶ月ごとに測定し、画像検査は病状に応じて3-6ヶ月ごとに実施します。血管病変の進行は年間約10-15%の症例で認められます。
| 観察項目 | 評価頻度 | 異常検出率 |
|---|---|---|
| 炎症マーカー | 1-3ヶ月 | 80-90% |
| 画像検査 | 3-6ヶ月 | 95-98% |
| 血圧測定 | 2-4週 | 60-70% |
| 血管エコー | 3ヶ月 | 85-90% |
総合的な診断アプローチにより、正確な診断と適切な経過観察が実現され、早期発見・早期診断へとつながっていきます。
高安動脈炎の治療方法と治療薬について
高安動脈炎(大動脈炎症候群)の治療について、主に薬物療法を中心に、病状の進行段階や個々の状態に応じた治療アプローチを体系的に説明します。
ステロイド剤を基本とした治療から、免疫抑制薬の使用まで、各治療法の特徴を詳述します。
初期治療とステロイド療法
ステロイド薬による治療では、約90%の患者で炎症マーカーの改善が見られ、2-4週間で症状の明らかな軽減を認めます。
プレドニゾロン(経口ステロイド薬)の標準的な初期投与量は、体重1kgあたり0.5-1.0mgを目安とし、平均的な成人では30-60mg/日からの開始となります。
| 投与量 | 期間 | 改善率 | 主な目的 |
|---|---|---|---|
| 30-60mg/日 | 2-4週間 | 90% | 寛解導入 |
| 20-30mg/日 | 4-8週間 | 85% | 維持療法 |
| 10-20mg/日 | 8-12週間 | 80% | 減量期 |
| 5-10mg/日 | 長期 | 75% | 維持量 |
免疫抑制薬による治療
免疫抑制薬の追加により、約70-80%の症例でステロイド減量が可能となります。メトトレキサート使用例では約75%で炎症マーカーの正常化を達成し、アザチオプリンでは約65%の症例で良好な治療効果が得られます。
- メトトレキサート(4-8mg/週から開始、最大16mg/週まで漸増):有効率75%
- アザチオプリン(25-50mg/日から開始、最大100mg/日まで):有効率65%
- シクロホスファミド(500-750mg/月、6回を1クール):有効率70%
- タクロリムス(1-3mg/日、血中濃度5-10ng/mL):有効率60%
生物学的製剤の使用
生物学的製剤の使用により、従来治療抵抗例の約80%で症状改善が得られます。投与開始後8-12週で効果判定を行い、CRP値の80%以上の低下を目標とします。
| 製剤名 | 投与間隔 | 初期反応率 | 1年継続率 |
|---|---|---|---|
| インフリキシマブ | 8週間 | 80% | 70% |
| トシリズマブ | 2週間 | 85% | 75% |
| アダリムマブ | 2週間 | 75% | 65% |
血管拡張薬と抗血栓療法
血管拡張薬と抗血小板薬の併用により、約60-70%の症例で血流改善効果が得られます。血管拡張薬は血圧値を指標に用量調整を行い、抗血小板薬は出血リスクに注意しながら継続します。
- カルシウム拮抗薬:血管径20-30%拡張
- アスピリン:血小板凝集能50-70%抑制
- クロピドグレル:血小板凝集能60-80%抑制
- シロスタゾール:血管拡張効果15-25%改善
外科的治療の適応
内科的治療で改善が得られない重度狭窄例(血管内腔70%以上の狭窄)の約20%で外科的治療の適応となります。手術成功率は95%以上ですが、5年後の再狭窄率は約30%とされています。
| 手術方法 | 適応基準 | 手術成功率 | 再狭窄率 |
|---|---|---|---|
| バイパス術 | 狭窄率90%以上 | 95% | 25% |
| 血管形成術 | 狭窄率70-90% | 90% | 35% |
| ステント留置 | 狭窄率50-70% | 85% | 40% |
これらの治療アプローチを組み合わせることで、約85%の患者さんで良好な長期予後が期待できます。
高安動脈炎(大動脈炎症候群)の治療期間
高安動脈炎(大動脈炎症候群)の治療期間について、病型や病状の進行度に応じた経過と、寛解までに要する期間を体系的に説明します。
初期治療から維持療法、長期的な経過観察まで、各段階における治療の目標期間を詳述します。
初期治療期における期間
寛解導入に要する期間は個人差が大きく、CRP値(炎症の指標となる血液検査値)が5.0mg/dL以上の高度炎症例では3ヶ月以上を要することもみられます。
一方、CRP値が2.0mg/dL未満の軽度炎症例では、2-4週間程度で主要な炎症マーカーの50%以上の改善が得られます。
| 病型 | 初期治療期間 | 寛解率 | CRP改善度 |
|---|---|---|---|
| 型I | 2-4週 | 85% | 70-80% |
| 型II | 4-8週 | 80% | 65-75% |
| 型III | 6-12週 | 75% | 60-70% |
| 型IV | 8-16週 | 70% | 55-65% |
維持療法の期間設定
赤血球沈降速度(ESR)が20mm/時間未満を維持し、CRP値が0.3mg/dL未満で推移する場合、6ヶ月から1年程度で維持療法への移行が検討されます。血管壁肥厚が2.0mm以上残存する場合は、より慎重な経過観察が必要となります。
- 標準的な維持期間(ESR 20mm/時間未満):6-24ヶ月
- 最短維持期間(CRP 0.3mg/dL未満):3-6ヶ月
- 延長維持期間(血管壁肥厚2.0mm以上):24-36ヶ月
- 長期維持期間(複数血管病変):36ヶ月以上
寛解までの標準的期間
血管造影検査で50%以上の狭窄改善を認め、炎症マーカーの正常化が3ヶ月以上持続した状態を寛解と定義します。この基準に基づくと、約70%の患者が12ヶ月以内に寛解に到達します。
| 寛解達成期間 | 患者割合 | 累積寛解率 | 炎症マーカー改善度 |
|---|---|---|---|
| 6ヶ月以内 | 40% | 40% | ESR 80%改善 |
| 6-12ヶ月 | 30% | 70% | ESR 90%改善 |
| 12-18ヶ月 | 20% | 90% | ESR 95%改善 |
| 18-24ヶ月 | 10% | 100% | ESR 100%改善 |
経過観察の継続期間
血管超音波検査で血管壁肥厚が1.0mm未満となり、造影CTで新規病変の出現がない状態を5年間維持することが長期寛解の目標となります。
| 観察期間 | 観察頻度 | 再燃率 | 血管壁厚変化 |
|---|---|---|---|
| 1年目 | 1-2ヶ月毎 | 15% | -0.5mm/年 |
| 2-3年目 | 2-3ヶ月毎 | 10% | -0.3mm/年 |
| 4-5年目 | 3-4ヶ月毎 | 5% | -0.1mm/年 |
| 5年以降 | 4-6ヶ月毎 | 3% | 安定維持 |
再燃時の追加治療期間
再燃時のCRP値上昇度に応じて追加治療期間を設定し、ESR値が正常化するまで継続します。
| 再燃程度 | CRP値 | 追加期間 | 寛解達成率 |
|---|---|---|---|
| 軽度 | 0.3-2.0 | 2-3ヶ月 | 90% |
| 中等度 | 2.0-5.0 | 3-6ヶ月 | 80% |
| 重度 | 5.0以上 | 6-12ヶ月 | 70% |
これらの期間設定は、各患者さんの病状や生活環境に合わせて調整する必要があり、医師との緊密な連携が大切です。
薬の副作用や治療のデメリットについて
高安動脈炎(大動脈炎症候群)の治療に伴う副作用とリスクについて、使用される薬剤の特性や長期使用に関連する問題点を体系的に説明します。
ステロイド薬に関連する副作用
ステロイド薬の使用において、投与量が体重1kgあたり0.5mg/日を超える場合、副作用の発現率は顕著に上昇します。
特に3ヶ月以上の継続使用では、骨密度が平均して年間3-5%低下し、空腹時血糖値は投与前と比較して20-30mg/dL上昇します。
| 副作用 | 発現率 | 発現時期 | 主な対策手段 |
|---|---|---|---|
| 骨粗鬆症 | 30-40% | 3-6ヶ月 | カルシウム1000mg/日補充 |
| 高血糖 | 25-35% | 1-2ヶ月 | 血糖値週1回モニタリング |
| 易感染性 | 20-30% | 2-4週間 | ST合剤予防投与 |
| 消化器症状 | 15-25% | 1-2週間 | PPI併用 |
免疫抑制薬使用時のリスク
免疫抑制薬による白血球減少は、投与開始後4-8週間で最も顕著となり、基準値(4,000/μL)を下回る症例が全体の15-20%に達します。肝機能障害ではAST/ALT値が基準値上限の2-3倍に上昇する例が25%程度観察されます。
- 白血球減少:4週間で2,000-3,000/μL低下(10-20%で発現)
- 肝機能障害:AST/ALT 100-150 IU/L上昇(15-25%で発現)
- 腎機能低下:クレアチニン 0.3-0.5mg/dL上昇(5-15%で発現)
- 消化器症状:投与3日以内に出現(20-30%で発現)
生物学的製剤による副作用
生物学的製剤の投与では、注射部位反応が投与後24時間以内に出現し、発赤の範囲は直径5cm以上に及ぶことも多く見られます。感染症リスクは従来治療と比較して1.5-2倍に上昇します。
| 副作用 | 発現頻度 | 発現時期 | モニタリング方法 |
|---|---|---|---|
| 注射部位反応 | 15-25% | 24時間以内 | 視診・触診 |
| 上気道感染 | 10-20% | 2-4週間 | 体温・症状確認 |
| アレルギー反応 | 5-15% | 投与直後-2時間 | バイタルサイン |
| 肝機能異常 | 3-10% | 4-12週間 | 血液検査 |
長期投与に伴うリスク
5年以上の長期投与では、骨密度がT-scoreで-2.5未満となる症例が30%を超え、HbA1c値が6.5%以上に上昇する例も20%程度に認められます。血圧上昇は収縮期で15-20mmHg、拡張期で10-15mmHgの上昇が一般的です。
| リスク | 発生率(5年) | 基準値からの変化 | 好発年齢 |
|---|---|---|---|
| 骨密度低下 | 30-40% | T-score -2.5以下 | 40-50代 |
| 糖尿病 | 20-25% | HbA1c 1.0%以上上昇 | 50-60代 |
| 高血圧 | 25-30% | 収縮期20mmHg上昇 | 45-55代 |
| 白内障 | 15-20% | 視力0.3以下 | 55-65代 |
手術治療に関連するリスク
血管手術では、術中の出血量が平均500-1000mLに達し、手術時間は4-6時間を要します。術後の再狭窄は2年以内に20%程度で発生し、血管内腔の50%以上の狭窄を認めます。
医師との密接な連携のもと、これらの副作用やリスクに対する早期発見と迅速な対応が望まれます。
保険適用と治療費
以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
処方薬の薬価
プレドニゾロン(経口ステロイド薬)の価格は規格によって異なり、5mg錠で9.8円、20mg錠で33.4円となります。一方、免疫抑制薬であるメトトレキサートは、2mg錠で89.6円、6mg錠で224.8円と、より高価格帯に位置しています。
| 薬剤名 | 規格 | 1錠あたりの薬価 | 1ヶ月あたりの概算 |
|---|---|---|---|
| プレドニゾロン | 5mg | 9.8円 | 2,940円 |
| メトトレキサート | 2mg | 89.6円 | 5,376円 |
1週間の治療費
一般的な外来診療における週あたりの基本医療費には、再診料2,800円に加え、処方薬の種類と用量に応じた薬剤費が発生します。さらに、定期的な経過観察に必要な検査費用も加算されます。
- 再診料:2,800円(処方箋料を含む)
- 処方薬:1,200円~5,200円(薬剤の組み合わせによる)
- 血液検査:3,000円~6,000円(検査項目数による)
- 画像検査:9,000円~15,000円(撮影部位による)
1か月の治療費
月間の総医療費は、通院の頻度と実施される検査内容によって大きく変動します。一般的な外来診療では、毎週の診察と定期検査を含めて15,000円から45,000円程度となり、指定難病の認定により自己負担は医療費の2割まで軽減されます。
| 診療内容 | 月額自己負担(2割負担の場合) |
|---|---|
| 外来診察(4回) | 11,200円~ |
| 投薬治療 | 4,800円~ |
| 定期検査 | 6,000円~ |
経済的な負担を軽減するため、まずは指定難病の申請手続きを進めることをお勧めします。
以上
参考文献
KOIDE, Keizo. Takayasu arteritis in Japan. Heart and Vessels, 1992, 7: 48-54.
NUMANO, Fujio; KOBAYASHI, Yasushi. Takayasu arteritis-beyond pulselessness. Internal medicine, 1999, 38.3: 226-232.
HOTCHI, Masao. Pathological studies on Takayasu arteritis. Heart and Vessels, 1992, 7: 11-17.
NUMANO, F. The story of Takayasu arteritis. Rheumatology, 2002, 41.1: 103-106.
SHARMA, B. K., et al. Diagnostic criteria for Takayasu arteritis. International journal of cardiology, 1996, 54: S127-S133.
WATANABE, Yoshiko; MIYATA, Tetsuro; TANEMOTO, Kazuo. Current clinical features of new patients with Takayasu arteritis observed from cross-country research in Japan: age and sex specificity. Circulation, 2015, 132.18: 1701-1709.
ONEN, Fatos; AKKOC, Nurullah. Epidemiology of Takayasu arteritis. La Presse Médicale, 2017, 46.7-8: e197-e203.
NUMANO, Fujio, et al. Takayasu’s arteritis. The Lancet, 2000, 356.9234: 1023-1025.
HATA, Akihiro, et al. Angiographic findings of Takayasu arteritis: new classification. International journal of cardiology, 1996, 54: S155-S163.
KIMURA, Akinori, et al. Comprehensive analysis of HLA genes in Takayasu arteritis in Japan. International journal of cardiology, 1996, 54: S61-S69.