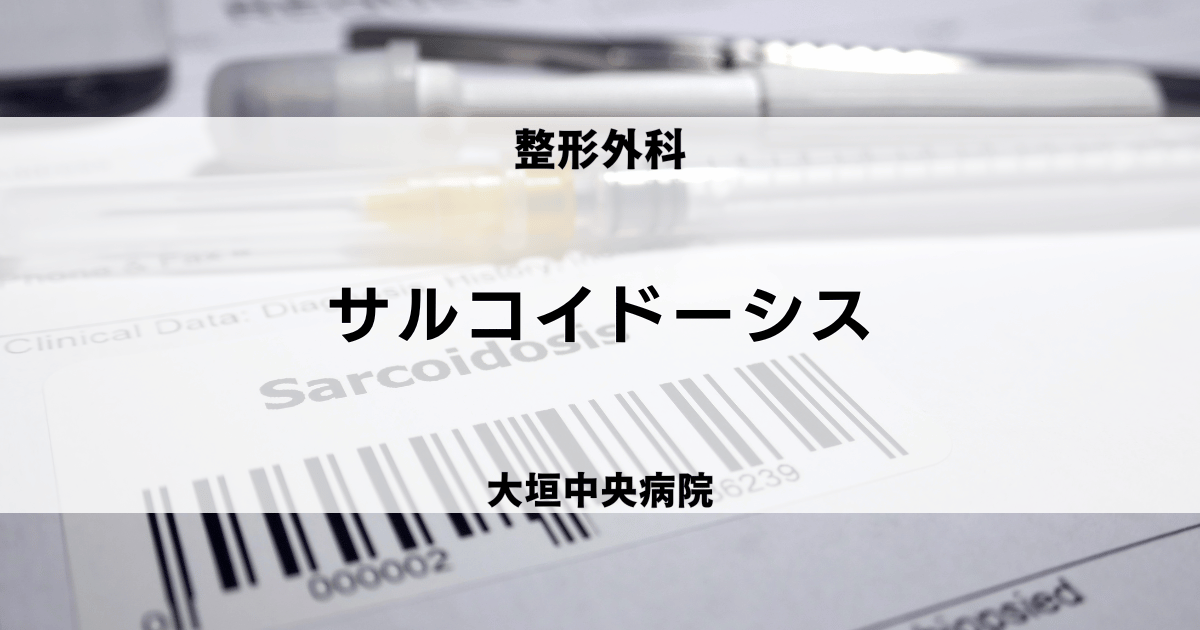サルコイドーシス(Sarcoidosis)とは、全身のさまざまな臓器や組織に、肉芽腫(にくげしゅ)と呼ばれる小さな炎症のかたまりが形成される疾患です。
原因は完全には解明されていませんが、免疫システムの異常が関与すると考えられています。
呼吸器や眼、皮膚、関節をはじめとした多彩な病型が存在し(肺や縦隔病変が多い)、症状の出方にも個人差があります。
この記事の執筆者

臼井 大記(うすい だいき)
日本整形外科学会認定専門医
医療社団法人豊正会大垣中央病院 整形外科・麻酔科 担当医師
2009年に帝京大学医学部医学科卒業後、厚生中央病院に勤務。東京医大病院麻酔科に入局後、カンボジアSun International Clinicに従事し、ノースウェスタン大学にて学位取得(修士)。帰国後、岐阜大学附属病院、高山赤十字病院、岐阜総合医療センター、岐阜赤十字病院で整形外科医として勤務。2023年4月より大垣中央病院に入職、整形外科・麻酔科の担当医を務める。
サルコイドーシスの病型
サルコイドーシスは臨床経過により急性型と慢性型に大別できます。
- 急性型:Löfgren症候群(両側肺門リンパ節腫大・結節性紅斑・足関節炎の三徴)が代表的で、患者の約5~10%にみられ予後は比較的良好。
- 慢性型:臓器障害が持続・進行しうるため長期の治療と経過観察が必要。
また臓器別分類も重要で、肺・縦隔リンパ節病変のほか、皮膚、眼、心臓、中枢神経など多彩な病変型があります。
筋骨格系サルコイドーシス(整形外科的領域の病変)はその一つで、関節・骨・筋肉への病変を含みます。
報告によれば、サルコイドーシス症例の25~33%に筋骨格系への関与がみられ、なかでも骨病変は歴史的には3~13%程度と稀と考えられてきましたが、多くが無症状で見逃されていた可能性があります。
近年ではMRIやPETなど画像診断の発達により骨髄病変の検出率が上昇し、手指・足指など四肢末端骨のみならず、脊椎や骨盤といった軸骨格への病変も頻繁に認められることが報告されました。
筋骨格系への具体的病変には、急性関節炎(前述のLöfgren症候群の関節症状など)や慢性関節炎(関節リウマチ様の経過を取ることもある)、骨内病変(手足の骨の嚢胞状透亮像や骨皮質破壊病変など)、筋病変(肉芽腫性筋炎や筋内結節)などがあります。
サルコイドーシスの症状
サルコイドーシスの症状は病型によって異なります。
一部の方は無症状のまま経過しますが、複数の臓器に影響が及ぶ場合や症状が顕著に現れる場合には、QOL(生活の質)を大きく損なうおそれがあるため注意が必要です。
| 症状 | 頻度 | 特徴 |
|---|---|---|
| 咳・息切れ(呼吸器) | 約50~60% | 肺門リンパ節の腫大や肺の炎症 |
| 皮膚症状 | 約20~40% | 結節性紅斑、皮膚の隆起病変 |
| 関節痛・筋肉痛 | 約10~30% | 関節のこわばりや筋力低下を伴う場合もある |
| 眼の炎症(ぶどう膜炎) | 約10~25% | 視力低下や目の痛み、充血など |
| 心臓症状(不整脈など) | 約5~15% | 心不全や重篤な不整脈に進展するリスク |
呼吸器症状
呼吸器症状としては乾性咳嗽(痰を伴わない咳)が最も多く、進行例では労作時の呼吸困難、喘鳴、胸痛、まれに血痰を認めます。
特に階段の昇降や軽い運動で息苦しさを感じたり、慢性的に空咳が続いたりするケースがあります。
これらの症状はほかの呼吸器疾患(喘息や慢性閉塞性肺疾患など)とも類似しており、鑑別が難しい点に注意が必要です。
皮膚症状
皮膚に赤く腫れた結節や、表面が盛り上がったような発疹が出る場合があります。
結節性紅斑では触れると痛みを伴うケースが多く、脚のすねや前腕などに出る傾向があります。
皮膚の色素沈着や乾燥などが起こる可能性もあり、外見上の変化が大きいため精神的なストレスにつながりかねません。
関節・筋肉の症状
朝起きたときに手指や足首が動かしづらい、じっとしていると関節がこわばるといった症状がある場合、サルコイドーシスによる関節炎を疑う必要があります。
筋肉の炎症により、筋力の低下や筋肉痛を訴えるケースもあります。
眼症状・全身症状
眼に生じる炎症は視力低下、目の充血、ドライアイのような症状として現れ、重症化すると失明する危険性も否定できません。
全身症状としては発熱や倦怠感、体重減少などがみられ、こうした症状が長く続く場合は注意が必要です。
サルコイドーシスの原因
サルコイドーシスの原因は完全に解明されていませんが、現在の有力な説は、遺伝的素因を有する人が何らかの環境抗原に曝露されることで異常な免疫反応が誘発されるというものです。
ただし、どの因子がどの程度影響するかは人によって大きく異なり、一概にはいえません。
| 原因 | 特徴・リスク |
|---|---|
| 遺伝的素因 | 家族内発症や人種差などが報告されており、重症化リスクにも関与 |
| 環境要因(粉塵など) | 農業・林業従事者で発症率が高いとする報告がある |
| 感染因子(ウイルスなど) | 過去の感染が免疫系の異常反応を誘発する可能性が示唆 |
| 不明な免疫反応の誘導因子 | 自己免疫疾患とは異なるが、似たような炎症メカニズムが関係 |
免疫システムの過剰反応
サルコイドーシスでは、体内の免疫細胞が過剰に反応し、炎症を引き起こすメカニズムが注目されています。
本来、免疫システムは外敵から体を守るために働きますが、何らかのトリガーによって自己組織に対しても反応し、肉芽腫と呼ばれる炎症のかたまりが生じます。
自己免疫疾患との関連が指摘される場合もありますが、サルコイドーシスは厳密には自己免疫疾患としては分類されていません。
遺伝的要因
家族内発症の報告や人種による発症率の違いが存在します。
欧米の一部の地域では日本より発症率が高く、特にアフリカ系アメリカ人など特定の人種で重症化しやすいとの研究報告もあります。
これらのデータから遺伝的要因が関係している可能性がありますが、単一の遺伝子変異だけで発症するわけではなく、複数の遺伝的因子が絡み合って発症リスクを高めると考えられています。
環境因子
農業や林業などで有機粉塵に曝露される機会が多い職業の人は、サルコイドーシスを発症しやすいといわれています。
また、モルモットや鳥などの動物由来の抗原との接触が関与すると提唱する研究者もいます。
タバコとの関連については、意外にも喫煙者より非喫煙者の発症率が高いとの報告がありますが、そのメカニズムは明確にはわかっていません。
複合的要因による発症
サルコイドーシスの発症には単一の原因ではなく、遺伝や環境、免疫の働きなど複数の要素が複雑に影響しています。
1つの要因が特定されれば対策が立てやすいですが、現時点では予防策を確立しづらい状況です。
サルコイドーシスの検査・チェック方法
サルコイドーシスの確定診断には、複数の検査を総合的に判断する必要があります。
呼吸器を中心とした症状が多いため、まず胸部X線やCT、肺機能検査などを行い、さらに血液検査や生検などで肉芽腫の存在を確認します。
症状が多様なため、必要に応じて眼科や循環器科などとの専門的な連携も大切です。
| 検査方法 | 特徴・役割 |
|---|---|
| 胸部X線・CT | 肺門リンパ節腫大や肺病変の程度を把握 |
| 血液検査(ACEなど) | 免疫異常や活動性の把握 |
| 生検(リンパ節・皮膚など) | 肉芽腫の組織学的確認 |
| 心電図・ホルター心電図 | 心臓型の不整脈やブロックの有無を評価 |
| 眼科検査(スリットランプ) | ぶどう膜炎などの眼病変を詳細に観察 |
画像検査(胸部X線・CTなど)
胸部X線検査では肺門リンパ節の腫大や肺病変を確認できます。
さらに詳細な情報を得るためにCT検査を行い、病変の部位や広がり、肉芽腫の形成状況を詳しく把握します。
呼吸器型の場合は、これらの検査が初期診断の手がかりになるケースが多いです。
血液検査
サルコイドーシスでは、血中のアンギオテンシン変換酵素(ACE)が高値を示す傾向があります。
また、免疫系の異常を示す指標として、可溶性IL-2受容体やリゾチーム値などを調べる場合があります。
ただし、これらは特異度が高いとは限らず、確定診断には生検などの病理所見が必要です。
生検(リンパ節・肺・皮膚など)
確定診断には、病変部位の組織を採取し、肉芽腫の有無を顕微鏡で確認する方法が有効です。
リンパ節の腫大がみられる場合はリンパ節生検を行い、肺病変が疑われる場合は気管支鏡を用いて肺の組織を一部採取します。
皮膚病変がある場合は皮膚生検を実施し、肉芽腫形成を確認する場合もあります。
心臓・眼・神経などの専門的検査
心サルコイドーシスが疑われる場合は、心電図やホルター心電図検査、心エコーなどで心機能をチェックします。
眼の症状がある場合は、眼科での精密検査(スリットランプ検査など)を行い、ぶどう膜炎の有無を確認します。
神経症状がある場合は、MRIや脳脊髄液検査などによる病変の評価が必要です。
サルコイドーシスの治療方法と治療薬、リハビリテーション、治療期間
サルコイドーシスの治療は、症状の程度や臓器の障害度合いによって異なります。
無症状や軽症であれば経過観察のみで自然軽快する場合もありますが、症状が強いときや臓器障害が進行するリスクがあるときには、薬物療法を行うのが一般的です。
さらに、必要に応じてリハビリテーションを組み合わせると、生活の質(QOL)向上につながります。
経過観察と薬物療法の基本方針
軽症の場合は、定期検査や画像検査を受けながら経過を観察し、症状が進まないかを確認します。
症状や臓器障害が進行したり、心臓や神経など重要な臓器に重い影響が及んだりする場合は、ステロイド薬や免疫調整薬を使用します。
薬物療法を始めるかどうかの判断は、患者さんの症状の強さや臓器機能障害の有無、炎症がどの程度進行しているかなどを総合的に考慮します。
主な治療薬の種類
| 薬剤名 | 例 | 主な効果 | 用いるケース |
|---|---|---|---|
| ステロイド薬 | プレドニゾロンなど | 強力な抗炎症作用で肉芽腫形成を抑制 | 中等度~重症例の初期治療に活用 |
| 免疫抑制薬 | メトトレキサート、アザチオプリンなど | 過剰な免疫反応を調整 | ステロイドの効果不足や副作用軽減 |
| 免疫調整薬 | TNF阻害薬など | 免疫システムの特定経路をブロック | 難治性の症例やほかの薬が効きにくい場合 |
| NSAIDs | イブプロフェンなど | 痛みや炎症を緩和 | 関節痛や軽度の炎症に使用 |
サルコイドーシスの治療で中心的な役割を担うのはステロイド薬(副腎皮質ホルモン)です。
特にプレドニゾロンなどを用いて炎症を抑え、肉芽腫の形成や臓器障害の進行を抑制します。
ステロイドに抵抗性がある場合や、副作用を軽減したい場合は、免疫抑制薬(メトトレキサート、アザチオプリンなど)との併用を検討します。
リハビリテーションと生活指導
| リハビリテーションの種類 | 主な目的 |
|---|---|
| 関節リハビリ | 可動域維持、筋力強化 |
| 呼吸リハビリ | 肺活量の維持、呼吸筋の強化、息切れの軽減 |
| 運動療法 | 全身の血行促進、体力向上、疲労感の軽減 |
| 生活指導 | バランスのよい食生活、睡眠や休息、ストレス管理など |
関節や筋肉に症状がある場合は、整形外科的なリハビリテーションを取り入れると、関節の可動域を保ち、筋力低下を予防できます。
また、肺機能が低下しているときは呼吸リハビリテーションが有効です。
日常生活では、適度な運動、バランスの取れた食事、十分な休息などを心がけることが大切です。
治療期間と予後
サルコイドーシスは自然軽快する例も多く、半年から1~2年で炎症がおさまっていくケースがあります。
一方、慢性化して長期的にステロイド療法を必要とする場合もあり、治療期間は個人差が大きいです。
特に心臓や中枢神経系を侵すタイプは重症化リスクが高く、慎重な経過観察と治療の継続が必要です。
治療の効果が見られなくても諦めず、医師と相談しながら治療方針を見直していきましょう。
薬の副作用や治療のデメリット
サルコイドーシスの治療に用いる薬剤、特にステロイド薬や免疫抑制薬には副作用が存在します。
治療効果とのバランスを見極めながら投与量や投与期間を調整しますが、人によっては副作用が強く出てしまうおそれがあります。
副作用やデメリットをよく理解したうえで、医師と相談しながら治療を進めてください。
| 副作用 | 対策 |
|---|---|
| 骨粗しょう症 | カルシウム・ビタミンD摂取、適度な運動 |
| 感染症リスクの上昇 | 手洗い、マスク着用、人混みを避ける |
| 高血糖・体重増加 | 食事制限、定期的な血糖測定 |
| 肝機能障害 | 定期的な肝機能検査、アルコール摂取の制限 |
| 精神的ストレス | カウンセリング、家族や医療スタッフとの相談 |
ステロイド薬の主な副作用
ステロイド薬は炎症を強力に抑える一方で、骨粗しょう症、高血糖、体重増加、感染症リスクの上昇などさまざまな副作用を引き起こす場合があります。
長期投与では高血圧やむくみ、胃潰瘍などが問題になるリスクもあるため、定期的な血液検査や骨密度検査などを実施しながら、投与量を徐々に減らす工夫を行います。
免疫抑制薬の主な副作用
メトトレキサートやアザチオプリンなどの免疫抑制薬は、過剰な免疫反応を抑えることで症状をコントロールします。
しかし、白血球や血小板の減少、肝機能障害、感染症への抵抗力低下などを引き起こすおそれがあります。
投与中は定期的に血液検査や肝機能検査を行い、副作用の兆候を早期に発見する必要があります。
治療継続による心理的負担
長期にわたる投薬治療では、服薬管理や定期受診の煩わしさ、費用面の負担、生活スタイルの制約など、患者さんの心理的負担が増大します。
副作用が出ると、治療へのモチベーションが低下するケースも少なくありません。
医師とのコミュニケーションを大切にしながら、必要に応じてカウンセリングやサポートを受けてください。
保険適用と治療費
以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
サルコイドーシスの診断や経過観察のために行う血液検査、画像検査などは保険が適用されます。また、ステロイド薬や免疫抑制薬などの内服薬も一般的に保険適用の対象です。
処方薬の費用は薬の種類や用量、処方日数によって異なり、3割負担で1か月あたり数千円から1万円程度です。
高血圧や糖尿病など副作用対策のための薬を併用すると、薬代が増加する可能性があります。
| 項目 | 3割負担の費用目安 | 2割負担の費用目安 |
|---|---|---|
| 外来診察料(1回) | 約500円~1,000円 | 約300円~700円 |
| 血液検査(1回) | 約2,000円~3,000円 | 約1,300円~2,000円 |
| 画像検査(レントゲン) | 約1,000円~2,000円 | 約700円~1,300円 |
| 画像検査(CT) | 約3,000円~10,000円 | 約2,000円~6,700円 |
| 薬代(1カ月) | 数千円~1万円程度(薬の種類・量による) | 数千円~1万円程度(薬の種類・量による) |
実際の金額は各医療機関や患者さんの状況によって異なるため、詳しくは担当の医療機関にお問い合わせください。
難病指定の対象と医療費助成
サルコイドーシスは厚生労働省の定める指定難病の一つです。
ただし、難病医療費助成制度を受けるには、一定の条件(重症度や臓器障害の程度など)を満たす必要があります。
対象となる方は医療費助成の申請が可能で、自己負担が軽減される可能性があります。
担当医や自治体の窓口に相談して、要件を満たすかどうかを確認してください。
以上
参考文献
COSTABEL, U. Sarcoidosis: clinical update. European respiratory journal, 2001, 18.32 suppl: 56S-68S.
UNGPRASERT, Patompong; RYU, Jay H.; MATTESON, Eric L. Clinical manifestations, diagnosis, and treatment of sarcoidosis. Mayo Clinic Proceedings: Innovations, Quality & Outcomes, 2019, 3.3: 358-375.
CHEN, Edward S.; MOLLER, David R. Etiologies of sarcoidosis. Clinical reviews in allergy & immunology, 2015, 49: 6-18.
CHEN, Edward S.; MOLLER, David R. Etiology of sarcoidosis. Clinics in chest medicine, 2008, 29.3: 365-377.
SCADDING, John Guyett; MITCHELL, Donald Norton. Sarcoidosis. Springer, 2013.
WESSENDORF, Thomas E.; BONELLA, Francesco; COSTABEL, Ulrich. Diagnosis of sarcoidosis. Clinical reviews in allergy & immunology, 2015, 49: 54-62.
BAUGHMAN, Robert P.; COSTABEL, Ulrich; DU BOIS, Ronald M. Treatment of sarcoidosis. Clinics in chest medicine, 2008, 29.3: 533-548.
SOTO-GOMEZ, Natalia; PETERS, Jay I.; NAMBIAR, Anoop M. Diagnosis and management of sarcoidosis. American family physician, 2016, 93.10: 840-850.
JUDSON, Marc A. The clinical features of sarcoidosis: a comprehensive review. Clinical reviews in allergy & immunology, 2015, 49: 63-78.
JUDSON, Marc A. The diagnosis of sarcoidosis. Clinics in chest medicine, 2008, 29.3: 415-427.