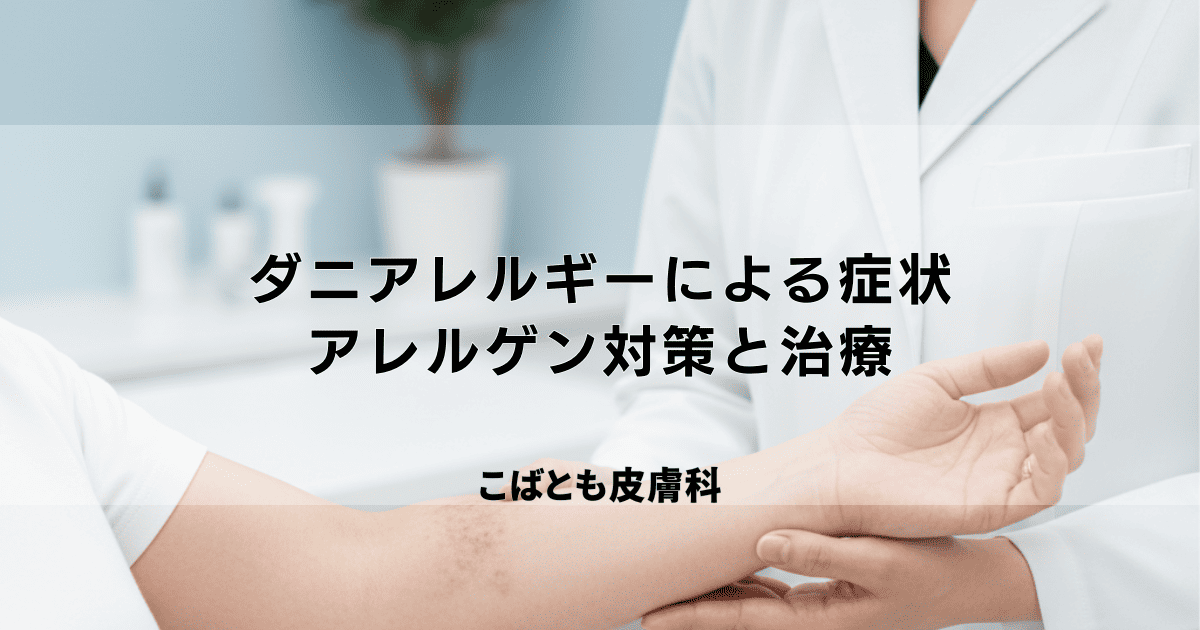突然、耐え難いかゆみと共に皮膚が赤く腫れあがる蕁麻疹や、繰り返しじくじくとかゆくなる湿疹、ご家庭に潜むダニのアレルギーが原因かもしれません。
ダニは高温多湿を好み、寝具やカーペットなどに多く生息しています。
この記事では、ダニアレルギーによって起きる湿疹や蕁麻疹の具体的な症状、原因となるアレルゲン、そして皮膚科で行う検査や治療法、さらにご家庭で今日から実践できるダニ対策まで、詳しく解説していきます。
この記事の執筆者

小林 智子(こばやし ともこ)
日本皮膚科学会認定皮膚科専門医・医学博士
こばとも皮膚科院長
2010年に日本医科大学卒業後、名古屋大学医学部皮膚科入局。同大学大学院博士課程修了後、アメリカノースウェスタン大学にて、ポストマスターフェローとして臨床研究に従事。帰国後、同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンターにて、糖化と肌について研究を行う。専門は一般皮膚科、アレルギー、抗加齢、美容皮膚科。雑誌を中心にメディアにも多数出演。著書に『皮膚科医が実践している 極上肌のつくり方』(彩図社)など。
こばとも皮膚科関連医療機関
ダニアレルギーが起こす皮膚症状
ダニが原因となるアレルギー反応は、くしゃみや鼻水といった呼吸器症状だけでなく、皮膚にも様々な症状を起こします。
突然現れる蕁麻疹
蕁麻疹は、ダニアレルゲンに接触したり、体内に取り込まれたりした直後から数時間以内に発症することが多い、即時型のアレルギー反応の一つです。
蕁麻疹によって現れる膨疹は、強いかゆみを伴い、形や大きさは様々で、数ミリ程度の小さなものから、手のひら以上に広がるものまであり、個々の膨疹が融合して大きな地図状になることもあります。
ダニが原因の場合、寝具に入った時や、カーペットの上でくつろいだ後、衣替えで出した服を着た時などに症状が出やすい傾向があります。蕁麻疹のもう一つの重要な特徴は、症状が一時的である点です。
通常、個々の膨疹は数時間から長くても24時間以内には跡形もなく消えてしまいますが、原因となるアレルゲンが身の回りにあり続ける限り、異なる場所に新たな膨疹が次々と出現し、症状が数日間続くこともあります。
繰り返し起こる湿疹
ダニアレルギーによる湿疹は、蕁麻疹とは異なり、遅れて現れる反応や、慢性的な経過をたどることが多い症状です。
ジュクジュクとした浸出液を伴う湿疹や、カサカサと乾燥して皮膚が厚くなる苔癬化(たいせんか)など、多彩な皮膚症状が見られます。
特に注目すべきは、アトピー性皮膚炎との深い関連です。アトピー性皮膚炎の患者さんの多くは、ダニをはじめとする環境アレルゲンに対してアレルギー反応を起こしやすい素因を持っています。
もともとアトピー性皮膚炎の素因がある方がダニアレルゲンに繰り返し暴露されると、皮膚のバリア機能が低下している部分からアレルゲンが侵入し、炎症が起きやすいです。
症状が出やすい体の部位
ダニアレルギーによる皮膚症状は、アレルゲンと接触しやすい部位に現れやすい傾向があり、寝具にはダニのフンや死骸が非常に多く蓄積しているため、睡眠中に無防備な皮膚が長時間触れることになります。
このため、顔、首、腕、脚など、衣類で覆われていない露出部や、寝具に直接こすれやすい部分に湿疹や蕁麻疹が出やすくなります。
また、皮膚のバリア機能がもともと弱い部位も、アレルゲンの侵入を許しやすいため症状が出やすい場所です。
肘の内側や膝の裏側、首の周りなど、皮膚が薄く柔らかい部分は、汗もかきやすく刺激を受けやすいため、アトピー性皮膚炎の好発部位とも一致します。
カーペットの上でハイハイをする乳幼児の場合、お腹や胸、手足など、床に接する面に症状が集中することもあります。
湿疹と蕁麻疹 見た目と症状の違い
ダニアレルギーによって起きる湿疹と蕁麻疹は、どちらもかゆみを伴いますが、性質は異なります。
症状の比較
| 特徴 | 湿疹(アトピー性皮膚炎の悪化など) | 蕁麻疹 |
|---|---|---|
| 見た目 | 赤いぶつぶつ、カサカサ、ジュクジュク、皮膚が厚くなる(苔癬化)など多彩。境界が不明瞭なことが多い。 | 皮膚の盛り上がり(膨疹)。赤みを伴う。境界が明瞭。 |
| 症状の持続時間 | 数日~数週間以上と慢性的に続くことが多い。 | 個々の膨疹は通常数時間~24時間以内に消える。場所を変えて繰り返すことはある。 |
| かゆみの性質 | 持続的なかゆみ。掻き壊して悪化しやすい。 | 一時的だが非常に強いかゆみ。チクチク、ムズムズする感じ。 |
なぜダニで皮膚がかゆくなるのか
ダニそのものが皮膚を刺したり咬んだりしてかゆみが出ることもありますが(ツメダニなど)、アレルギーによる湿疹や蕁麻疹の場合、原因は異なります。
主な原因アレルゲン チリダニのフンや死骸
日本国内の家屋でアレルギーの主な原因となるのは、ヒョウヒダニ(チリダニ)と呼ばれる種類のダニで、ヤケヒョウヒダニやコナヒョウヒダニが代表的です。
ダニは非常に小さく、肉眼で確認することは困難で、人を刺すことはありませんが、フケやアカ、食べこぼしなどをエサにして、布団、枕、マットレス、カーペット、ソファ、ぬいぐるみなど、生活空間のいたるところに生息しています。
問題となるアレルゲンは、ダニのフンや死骸です。特にフンは、乾燥すると細かく砕けて空気中に舞い上がりやすく、呼吸器や皮膚に容易に接触します。
ダニのフンには強力なアレルギー誘発物質(タンパク質)が含まれており、これが皮膚症状の直接的な引き金です。
アレルゲンが皮膚に侵入する流れ
健康な皮膚は、角層と呼ばれるバリアによって、外部からの刺激や異物の侵入を防いでいますが、何らかの理由でこのバリア機能が低下すると、アレルゲンが皮膚の内部に侵入しやすくなります。
乾燥、間違ったスキンケア、過度な洗浄、あるいはアトピー性皮膚炎の素因などによって皮膚がダメージを受けると、角層の隙間が広がってしまいます。
ダニのフンや死骸といったアレルゲンが皮膚に付着しただけでは、すぐに症状が出るわけではありませんが、バリア機能が低下した皮膚では、アレルゲンが容易に角層を突破し、表皮や真皮にまで到達してしまいます。
また、かゆみを感じて皮膚を掻きむしる行為は、物理的に角層を破壊し、さらにアレルゲンの侵入を助長するという悪循環を生み出します。
寝具や衣類に付着したアレルゲンが、就寝中や日常の動作で皮膚にこすり付けられることも、侵入のきっかけです。
アレルギー反応が起こる体の防御システム
皮膚の内部に侵入したダニアレルゲンは、体の防御システム、すなわち免疫細胞によって異物として認識され、このとき、アレルゲンに特異的に反応するIgE抗体というタンパク質が関与します。
ダニアレルギーを持つ人の体内では、ダニ特異的IgE抗体がすでに大量に作られていて、皮膚にあるマスト細胞(肥満細胞)の表面に結合して、アレルゲンの侵入を待ち構えています。
アレルゲンが侵入し、マスト細胞上のIgE抗体に結合すると、マスト細胞が刺激され、内部に蓄えていたヒスタミンなどの化学伝達物質を一気に放出します。
放出されたヒスタミンは、血管を拡張させて皮膚を赤くし(発赤)、血管の透過性を高めて体液を漏れ出させ、皮膚を腫れさせ(膨疹)、さらに、ヒスタミンは知覚神経を刺激し、耐え難いかゆみを起こすのです。
ダニの種類とアレルゲン
家庭内に生息するダニは一種類ではありませんが、アレルギーの観点で特に重要なのはヒョウヒダニ(チリダニ)です。
アレルギーに関連する主なダニ
| ダニの種類 | 主な生息場所 | 主なアレルゲン |
|---|---|---|
| ヒョウヒダニ(チリダニ) | 布団、マットレス、カーペット、ソファ、ぬいぐるみ | フン、死骸(人を刺さない) |
| コナダニ | 畳、食品(小麦粉、乾物など) | フン、死骸(人を刺さない) |
| ツメダニ | 畳、カーペット(ヒョウヒダニなどを捕食) | 体液(人を刺して吸血することがある) |
ダニアレルギーによる湿疹・蕁麻疹の診断
皮膚にかゆみや湿疹、蕁麻疹が出た場合、ダニアレルギーによるものなのか、あるいは他の原因(食物、金属、ストレス、感染症など)によるものなのかを特定することが治療の第一歩です。
皮膚科での問診 症状の発生状況の確認
医師による診断は、まず患者さんから詳しくお話を伺う問診から始まり、いつから症状が出たか、どのような時にかゆみや発疹が強くなるか、症状は一日中続くのか、特定の時間帯に集中するのかなどをお聞きします。
また、ご自宅の環境(畳かフローリングか、カーペットや布製ソファの有無、ペットの飼育状況)や、寝具の管理方法(布団を干す頻度、シーツの洗濯頻度)などもお伺いします。
ご自身やご家族に、アトピー性皮膚炎、気管支ぜんそく、アレルギー性鼻炎などのアレルギー疾患があるかどうかも重要な情報です。
アレルギー検査の種類
問診や診察の結果、ダニアレルギーが疑われる場合、それを裏付けるためにアレルギー検査を行います。
主なアレルギー検査
- 血液検査(特異的IgE抗体検査)
- 皮膚テスト(プリックテスト)
- パッチテスト(接触皮膚炎の鑑別)
これらの検査は、症状や疑われる原因に応じて医師が選択します。
血液検査(特異的IgE抗体検査)で分かること
現在、アレルギー検査の主流となっているのが血液検査(特異的IgE抗体検査)で、これは、採血によって血液を採取し、血液中に特定のアレルゲンに対して作られたIgE抗体がどれくらいあるかを調べる検査です。
IgE抗体はアレルギー反応に関わるタンパク質で、量が多いほど、そのアレルゲンに対してアレルギー反応を起こしやすい状態と考えられます。
検査の利点は採血が一度で済み、小さなお子さんや皮膚の状態が悪い方でも安全に行える点、抗ヒスタミン薬などを内服していても検査結果に影響が出にくい点です。
検査結果はクラス0から6までの7段階で示され、クラスが高いほどダニに対するアレルギーの程度が強いと判断されます。ただし、検査結果が陽性であっても、それが直接現在の皮膚症状の原因であるとは限りません。
皮膚テスト(プリックテストなど)の方法
皮膚テストは、アレルゲンを皮膚に直接反応させて、アレルギー反応が起こるかを確認する検査で、代表的な方法はプリックテストです。
プリックテストでは、ダニのアレルゲンエキスを腕の内側などに一滴垂らし、その上から専用の細い針で軽く皮膚を刺します。
ダニアレルギーがある場合、15分から20分後に、その部位が蚊に刺されたように赤く腫れあがり(膨疹と発赤)、膨疹の大きさを測定して陽性かどうかを判定します。
プリックテストは、血液検査よりも早く、その場で結果が分かるという利点があり、また、実際に皮膚で起こる反応を見ているため、症状との関連性が高いです。
ただし、抗ヒスタミン薬を内服していると正しい反応が出ないため、検査の数日前から服薬を中止する必要があります。
主なアレルギー検査の比較
| 検査方法 | 内容 |
|---|---|
| 血液検査(特異的IgE抗体検査) | 採血し、血液中のダニ特異的IgE抗体量を測定。服薬中でも検査可能。 |
| 皮膚テスト(プリックテスト) | 皮膚にアレルゲンエキスを垂らし、針で軽く刺して反応を見る。即時結果が分かるが、服薬制限あり。 |
家庭でできるダニアレルゲン対策の基本
ダニアレルギーによる湿疹や蕁麻疹の治療において、薬物療法と並んで非常に重要なのが、原因となるダニアレルゲンを生活環境から減らすことです。
掃除の重要性 除去すべき場所と頻度
ダニアレルゲン対策の基本は、何と言っても掃除です。ダニのフンや死骸は非常に軽く、人の動きや空気の流れで簡単に舞い上がりますが、最終的には床や家具の表面に蓄積します。
特にダニが好むのは、エサとなるフケやアカが溜まりやすく、適度な温度と湿度が保たれる場所で、寝室、リビングのカーペット、布製ソファは最重点対策エリアになります。
掃除機は、少なくとも3日に1回、できれば毎日かけるのが理想で、寝室は、起床後すぐではなく、人が活動してアレルゲンが床に落ちてくるのを待ってから、あるいは就寝前にかけると効果的です。
掃除機をかける際は、アレルゲンを舞い上げないよう、ゆっくりと(1平方メートルあたり20秒以上かけて)動かすことが大切で、さらに拭き掃除を組み合わせると、微細なアレルゲンも効率よく除去できます。
寝具(布団・枕・マットレス)の管理方法
人は一日の約3分の1を寝具で過ごすので、フケやアカというエサが豊富で、人の体温と汗で適度な温度・湿度が保たれるため、寝具はダニにとって最も快適な生息場所の一つです。
まず、シーツ、枕カバー、布団カバーはこまめに洗濯します。週に1回以上が目安で、洗濯だけではダニは死滅しにくいですが、アレルゲンの大部分(フンや死骸)は水溶性のため、洗い流すことができます。
布団本体やマットレスは、頻繁に掃除機をかけることが重要です。専用のノズルを使い、ゆっくりと時間をかけて吸引します。
天日干しは、布団の湿気を取り除く効果はありますが、ダニを殺す効果は限定的です(ダニは日光の当たらない反対側に逃げるため)。
より効果的なのは、布団乾燥機で、多くの布団乾燥機には50度以上の熱風でダニを死滅させる機能がついています。ダニを死滅させた後は、その死骸やフンを掃除機でしっかりと吸い取ることが重要です。
室内の湿度と温度のコントロール
ダニは、温度20~30度、湿度60~80%の高温多湿な環境を最も好み、逆に、湿度が50%以下になると活動が鈍り、繁殖しにくくなります。
したがって、室内の湿度をコントロールすることは、ダニ対策において非常に有効な手段です。梅雨時や夏場は、除湿機やエアコンの除湿(ドライ)機能を積極的に活用し、室内の湿度を常に60%以下、できれば50%程度に保つよう心がけましょう。
湿度計を部屋に設置し、現在の湿度を把握できるようにしておくと管理がしやすくなります。
また、換気も重要です。天気の良い日には窓を二方向開けて空気の通り道を作り、室内にこもった湿気やアレルゲンを外に排出し、浴室やキッチンなど、特に湿気が発生しやすい場所では、換気扇をこまめに回す習慣をつけましょう。
アレルゲン対策グッズの選び方
ダニ対策を補助するための様々なグッズが市販されているので、賢く利用することで、日々の負担を軽減し、対策の効果を高めることができます。
主なアレルゲン対策グッズ
- 防ダニ寝具カバー(高密度繊維使用)
- 布団乾燥機(ダニ対策機能付き)
- HEPAフィルター搭載の掃除機
- 空気清浄機(HEPAフィルター搭載)
- ダニ捕獲シート(置くタイプ)
特に有効なのが、高密度繊維を使用した防ダニ寝具カバーです。これは、繊維の隙間が非常に細かいため、ダニそのものやフン・死骸が布団やマットレスから出てくるのを物理的に防ぎます。
徹底解説 ダニアレルゲンを減らす掃除術
基本的な対策に加えて、ダニアレルゲンをより効果的に減らすための掃除のコツがあります。
掃除機のかけ方 ゆっくりと時間をかける
掃除機はダニ対策の主役ですが、使い方一つで効果は大きく変わります。
ダニやそのアレルゲンは、カーペットや畳の奥、繊維の根元にしがみついているので、掃除機をサッと動かすだけでは表面のホコリしか取れず、肝心のアレルゲンは残ってしまいます。
ポイントはゆっくりと動かすことで、畳やフローリング、カーペットなど、床材にかかわらず、1平方メートルあたり20秒以上(例:6畳間で約3~5分)かけることが目安です。
掃除機をかける方向も重要で、カーペットや畳は、縦方向、横方向、斜め方向と、多方向からかけることで、繊維の奥に入り込んだアレルゲンをかき出しやすくなります。
また、掃除機をかける時間帯は、起床直後や帰宅直後がおすすめです。人が活動していない間に床に沈殿したアレルゲンが、人の動きで舞い上がる前に除去できます。
布製品(ソファ・カーペット・ぬいぐるみ)のケア
ダニは床や寝具だけでなく、布製のソファ、カーペット、クッション、ぬいぐるみなど、ホコリが溜まりやすいあらゆる布製品に潜んでいます。
布製品のダニ対策
| 布製品 | 主な対策 |
|---|---|
| カーペット・ラグ | こまめな掃除機がけ(多方向にゆっくり)。可能であれば丸洗いできるタイプを選び、定期的に洗濯する。 |
| 布製ソファ | 掃除機で座面、背もたれ、隙間を丁寧に吸引。カバーが外せるタイプは定期的に洗濯する。 |
| ぬいぐるみ | できるだけ置かない。置く場合は、丸洗いできるものを選び、定期的に洗濯するか、ビニール袋に入れて天日干しや布団乾燥機で加熱処理後、掃除機で吸う。 |
洗濯の効果的な方法と寝具の丸洗い
ダニアレルゲンの多くは水溶性であるため、洗濯は非常に有効なアレルゲン除去手段です。シーツやカバー類は週に1回以上の洗濯が推奨されます。
ただし、ダニ本体は洗濯機の水流程度では死滅せず、繊維にしがみついて生き残ることがあり、ダニ本体を減らすには、洗濯の前に熱を加えるのが効果的です。
布団乾燥機(50度以上)をかけた後に洗濯する、あるいは、コインランドリーの大型乾燥機(高温)を利用するのも一つの方法です。
布団や枕、マットレスなど、丸洗いできない寝具本体は、布団乾燥機での加熱処理と掃除機がけが基本となります。
換気と空気清浄機の役割
掃除によって床や寝具のアレルゲンを除去しても、空気中に舞い上がった微細なアレルゲンが残っていることがあり、効率的に室外へ排出するのが換気の役割です。
換気と空気清浄機の比較
| 対策 | 目的 | ポイント |
|---|---|---|
| 換気 | 室内の湿気を排出する。空気中に浮遊するアレルゲンを室外へ出す。 | 1日数回、2方向の窓を開けて空気の通り道を作る。5~10分程度。 |
| 空気清浄機 | 室内の空気を循環させ、浮遊するアレルゲンをフィルターで捕集する。 | HEPAフィルター搭載機種を選ぶ。床面に近い場所(アレルゲンが舞い上がりやすい)に設置。24時間稼働が理想。 |
ただし、空気清浄機は、あくまで補助的な役割と考えるのがよいでしょう。
ダニアレルゲンの多くは重さがあるため、空気中に浮遊している時間は比較的短く、すぐに床に沈降するので、空気清浄機で除去できるのは、掃除や人の動きで舞い上がった直後のアレルゲンが中心です。
皮膚科で行う湿疹・蕁麻疹の治療法
アレルゲン対策と並行して、今出ているかゆみや炎症を抑え、皮膚の状態を改善するための治療を行います。
かゆみや炎症を抑える塗り薬(ステロイド外用薬など)
湿疹や蕁麻疹による炎症とかゆみを抑えるために、最も中心的な役割を果たすのが塗り薬(外用薬)で、湿疹に対しては、炎症を強力に抑えるステロイド外用薬が第一選択になります。
ステロイドと聞くと不安を感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、皮膚科専門医の指導のもと、症状の強さや部位(顔、体、手足など)に応じて適切な強さの薬を適切な期間使用すれば、非常に効果的で安全な治療薬です。
炎症を中途半端に抑えると、すぐに再発を繰り返してしまうので、医師の指示通りに、十分な量をしっかり塗ることが大切です。
顔や首などデリケートな部分には、ステロイド以外の炎症を抑える塗り薬(タクロリムス軟膏やデルゴシチニブ軟膏など)が用いられることもあります。
主な外用薬(塗り薬)
| 薬剤の種類 | 主な働き | 使用上の注意点 |
|---|---|---|
| ステロイド外用薬 | 強力な抗炎症作用。赤み、腫れ、かゆみを抑える。 | 症状と部位に応じた強さの選択が必要。医師の指示通りに使用する。 |
| 非ステロイド性抗炎症薬 | 比較的軽度の炎症を抑える。 | ステロイドに比べ効果は穏やか。かぶれを起こすことがある。 |
| 免疫抑制外用薬 | 免疫反応を局所的に抑え、炎症を鎮める。 | アトピー性皮膚炎の治療に用いる。特有の刺激感が出ることがある。 |
かゆみを和らげる飲み薬(抗ヒスタミン薬)
特に蕁麻疹や、かゆみが非常に強い湿疹の場合、塗り薬だけではかゆみをコントロールしきれないことがあり、このような場合、飲み薬(内服薬)を併用します。
中心となるのは抗ヒスタミン薬で、アレルギー反応によって放出されるヒスタミンの働きをブロックすることで、かゆみや膨疹(蕁麻疹の盛り上がり)を抑える薬です。
ダニアレルギーによる蕁麻疹や、アトピー性皮膚炎のかゆみが夜間に強くなり睡眠を妨げるような場合には、就寝前に内服することで、かゆみを抑えてぐっすり眠れるようにする目的でも処方されます。
主な内服薬(飲み薬)
| 薬剤の種類 | 主な働き | 使用上の注意点 |
|---|---|---|
| 抗ヒスタミン薬 | ヒスタミンの作用を抑え、かゆみや蕁麻疹(膨疹)を鎮める。 | 眠気が出にくいタイプが主流だが個人差あり。医師の指示通りに内服。 |
| 抗アレルギー薬(ロイコトリエン拮抗薬など) | ヒスタミン以外の化学伝達物質を抑え、アレルギー反応全体を鎮める。 | 主に鼻炎や喘息に用いるが、皮膚症状に併用することもある。 |
スキンケアと保湿の重要性
ダニアレルゲンが皮膚に侵入するのを防ぐためには、皮膚のバリア機能を正常に保つことが何よりも大切です。
炎症が治まった後も、アレルゲン対策と並行して継続的なスキンケア、特に保湿が重要となり、皮膚科では、炎症を抑える薬と同時に、保湿薬(ヘパリン類似物質、ワセリン、尿素軟膏など)を処方します。
保湿ケアのポイント
- 入浴後はなるべく早く(5~10分以内)保湿薬を塗る。
- 保湿薬は、皮膚がしっとりするくらいたっぷりと塗る。
- 症状が落ち着いていても、保湿は毎日継続する。
保湿薬は、皮膚に水分を補給し、水分の蒸発を防ぐことで、角層のバリア機能をサポートし、バリア機能が整えば、ダニアレルゲンなどの外部からの刺激が侵入しにくくなり、湿疹や蕁麻疹が再発しにくい、健康な皮膚状態を維持できます。
治療の基本的な流れ
ダニアレルギーによる皮膚症状の治療は、アレルゲン対策、薬物療法、スキンケアの三本柱で進めます。
まず、問診と検査でダニアレルギーの関与を診断し、次に、ステロイド外用薬や抗ヒスタミン薬を用いて、現在のつらいかゆみと炎症を速やかに鎮めます。
症状が改善してきたら、薬の強さや使用頻度を徐々に減らしていきますが、自己判断で急にやめず、医師の指示に従ってください。同時に、保湿ケアを徹底し、皮膚のバリア機能を回復させます。
並行して、ご家庭でのダニアレルゲン対策(掃除、寝具管理、湿度コントロール)を継続的に行い、アレルゲンに触れる量を減らします。
症状がなくなった後も、保湿ケアとアレルゲン対策を続けることが、再発を防ぐために最も重要です。
症状改善に向けた生活習慣の見直し
皮膚科での治療やアレルゲン除去の掃除と合わせて、日々の生活習慣を見直すことも、ダニアレルギーによる皮膚症状の改善と再発予防に役立ちます。
皮膚のバリア機能を守る入浴方法
毎日の入浴は重要ですが、洗い方が間違っていると、皮膚のバリア機能を支える皮脂や天然保湿因子まで奪ってしまい、かえって皮膚を乾燥させ、バリア機能を低下させる原因になります。
大切なのは、洗いすぎないことです。石鹸やボディソープは、低刺激性で弱酸性のものを選び、ナイロンタオルやスポンジでゴシゴシこするのではなく、手で優しく泡立ててなでるように洗います。
皮脂の分泌が多い胸や背中、脇、陰部、足などは丁寧に洗いますが、乾燥しやすい腕やすねは、泡でなでる程度で十分です。お湯の温度も熱すぎると皮脂を奪いすぎるため、38~40度程度のぬるめに設定しましょう。
入浴後は、タオルで優しく水分を押さえるように拭き、皮膚が乾燥する前に(5~10分以内)保湿薬を全身にたっぷりと塗布します。
入浴時のスキンケア
| 入浴のポイント | 具体的な方法 | 避けるべきこと |
|---|---|---|
| 洗浄 | 低刺激性の石鹸を使い、手で泡立てて優しく洗う。 | ナイロンタオルでのゴシゴシ洗い。 |
| お湯の温度 | 38~40度のぬるま湯。 | 42度以上の熱いお湯、長時間の入浴。 |
| 入浴後の保湿 | 入浴後5~10分以内に保湿薬を全身に塗る。 | 自然乾燥させたり、保湿を怠ったりすること。 |
食事とアレルギーの関係
ダニアレルギーと直接関係はありませんが、一般的に皮膚の健康を保つためには、バランスの取れた食事が大切です。
皮膚や粘膜の健康を保つビタミンA、抗酸化作用がありコラーゲンの生成を助けるビタミンC、血行を促進するビタミンE、皮膚の新陳代謝に関わるビタミンB群などを意識して摂るとよいでしょう。
また、特定の食品が湿疹や蕁麻疹を悪化させると感じる場合(食物アレルギー)、その食品を特定することも必要です。
ストレス管理と睡眠
精神的なストレスは、アレルギー反応を悪化させることが知られていて、ストレスを感じると、体内の免疫バランスやホルモンバランスが崩れ、かゆみを感じやすくなったり、炎症が強くなったりすることがあります。
睡眠不足も体調を崩し、皮膚のバリア機能や免疫機能に悪影響を与え、また、かゆみは夜間に強くなることが多く、睡眠が妨げられがちです。
見直したい生活習慣
日々の何気ない習慣が、ダニアレルギーの症状に影響を与えているかもしれません。
見直したい習慣
- 衣類や寝具の素材選び
- ペットの飼育環境
- 喫煙習慣
衣類は、ウールや化学繊維などチクチクしやすい素材は避け、肌触りの良い木綿(コットン)素材を選ぶと皮膚への刺激が少なくなります。
ペット(犬や猫など)を飼っている場合、ペットの毛やフケがダニのエサになったり、あるいはペット自身のアレルゲンが症状を悪化させたりする可能性があります。ペットのシャンプーをこまめに行い、寝室には入れないなどの配慮が必要です。
喫煙は、本人だけでなく受動喫煙も含め、気道や皮膚の粘膜を刺激し、アレルギー反応を悪化させる可能性があります。
ダニアレルギーに関するよくある質問
ダニアレルギーによる湿疹や蕁麻疹に関して、患者さんから寄せられることの多い質問にお答えします。
- ダニは肉眼で見えますか
-
アレルギーの主な原因となるヒョウヒダニ(チリダニ)は、体長が0.2~0.4ミリメートル程度と非常に小さく、肉眼で見ることはほぼ不可能です。
時々、布団などで見かける小さな虫は、ダニではなくチャタテムシなど他の虫であるか、あるいはアレルギーの原因とはなりにくいツメダニなど(これでも0.5~1ミリ程度)である可能性が高いです。
- 掃除をしても症状が改善しません
-
掃除機のかけ方が速すぎたり、寝具やソファなどダニの温床となる場所の対策が見落とされていたりしないか、今一度確認してみてください。また、湿疹や蕁麻疹の原因はダニだけとは限りません。
食物、花粉、カビ、ペット、金属、あるいはストレスや疲労など、様々な要因が考えられるので、症状が続く場合は、再度皮膚科を受診してください。
- 薬を使い続けることに不安があります
-
お気持ちは理解できますが、特にステロイド外用薬は、炎症をしっかり抑えるために必要な薬なので、医師の指示通りに使用してください。
中途半端に使用して炎症が残ると、かえって治療が長引き、皮膚が厚くなるなどの変化を残すこともあります。不安な点があれば、自己判断で中断せず医師に伝え、相談しましょう。
- 症状が治まれば治療をやめてもよいですか
-
症状が治まっても、すぐに対策や治療をやめるのは早計です。ダニアレルギーは体質的なものであり、環境中にダニがいる限り、再発のリスクは常につきまといます。
薬物療法(塗り薬や飲み薬)は、医師が皮膚の状態を見て、徐々に減らしていきます。また、症状がなくなった後も、アレルゲン対策(掃除や寝具管理)と保湿ケアは、再発を防ぐために継続して行うことが必要です。
以上
参考文献
Numata T, Yamamoto S, Yamura T. The role of mite, house dust and Candida allergens in chronic urticaria. The Journal of Dermatology. 1980 Jun;7(3):197-202.
Imoto Y, Sakashita M, Tokunaga T, Kanno M, Saito K, Shimizu A, Maegawa A, Fujieda S. Recent prevalence of allergic rhinitis caused by house dust mites among the pediatric population in Fukui, Japan. World Allergy Organization Journal. 2024 Jul 1;17(7):100932.
Ohshima Y, Yamada A, Hiraoka M, Katamura K, Ito S, Hirao T, Akutagawa H, Kondo N, Morikawa A, Mayumi M. Early sensitization to house dust mite is a major risk factor for subsequent development of bronchial asthma in Japanese infants with atopic dermatitis: results of a 4-year followup study. Annals of allergy, asthma & immunology. 2002 Sep 1;89(3):265-70.
Miller JD. The role of dust mites in allergy. Clinical reviews in allergy & immunology. 2019 Dec;57(3):312-29.
Nishioka K. Atopic eczema of adult type in Japan. Australasian Journal of Dermatology. 1996 May;37:S7-9.
Kojima R, Shinohara R, Kushima M, Yui H, Otawa S, Horiuchi S, Miyake K, Yokomichi H, Akiyama Y, Ooka T, Yamagata Z. The association of environmental house dust mite allergens and crustacean allergy: the Japan Environment and Children’s Study (JECS). Asia Pacific Allergy. 2025:10-5415.
Dabbaghzadeh A, Ghaffari J, Yazdani-Charati J, Kordkheyli MM, Pouresmaeil F. Sensitization to Food and Aeroallergens in Patients with Asthma, Allergic Rhinitis, Eczema and Urticaria. International Journal of Medical Laboratory. 2021 Dec 24.
Ricci G, Patrizi A, Specchia F, Massi M. Effect of house dust mite avoidance measures in children with atopic dermatitis: reply from authors. British Journal of Dermatology. 2001 Apr 1;144(4):913-.
Beltrani VS. THE ROLE OF DUST MITES IN ATOPIC DERMATITIS:: A Preliminary Report. Immunology and allergy clinics of North America. 1997 Aug 1;17(3):431-41.
Tupker RA, De Monchy JG, Coenraads PJ. House‐dust mite hypersensitivity, eczema, and other nonpulmonary manifestations of allergy. Allergy. 1998 Dec;53:92-6.