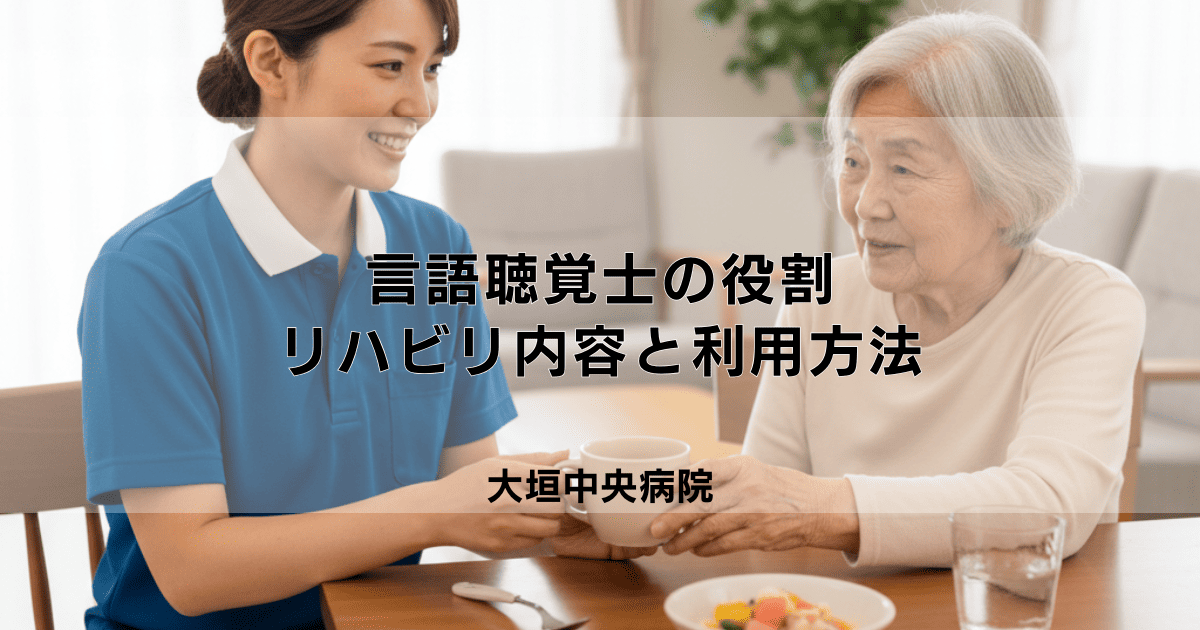病気や加齢によって、ある日突然、当たり前にできていた食事が摂りにくくなったり、家族との会話が難しくなったりすることがあります。
「食べる」「話す」「聞く」といった機能の悩みを抱えながらご自宅で療養生活を送る方々にとって、言語聴覚士(ST)による訪問看護リハビリは大きな支えです。
この記事では、訪問看護の現場で言語聴覚士(ST)がどのような専門的な役割を果たし、どのようなリハビリを提供しているのか、そしてどうすれば支援を受けられるのか、詳しく解説します。
訪問看護における言語聴覚士(ST)とは
在宅療養を支える訪問看護チームには、看護師だけでなく、リハビリテーションの専門家もいて、その中でも、言語聴覚士(ST)は「話す」「聞く」「食べる」ことに関する問題に特化した専門職です。
ST(言語聴覚士)の専門性
言語聴覚士(ST)は、音声機能、言語機能、聴覚機能、嚥下機能などに関するリハビリテーションの国家資格を持つ専門職です。英語のSpeech-Language-Hearing Therapist の頭文字をとってSTとも呼ばれます。
主な専門領域は、言葉による意思疎通の問題(失語症、構音障害など)や、食べ物の飲み込み(嚥下)に関する問題(嚥下障害)です。
病気や事故、発達上の問題により、話す、聞く、読む、書くといった言語機能や、声の出し方、発音に困難が生じた方々を支援します。
さらに、記憶や注意、判断といった高次脳機能に問題が生じた方への支援も行い、その人らしい生活を再構築するためのお手伝いをします。また、安全に食事を楽しみ、十分な栄養を摂取するための嚥下機能の評価と訓練も、STの重要な仕事です。
なぜ自宅にSTが来てくれるのか
病院を退院した後も、リハビリが必要な方は多くいますが、ご高齢の方や障害を持つ方にとって、定期的に通院すること自体がご本人やご家族の大きな身体的・精神的な負担になります。
飲み込みの問題を抱えている方や、重度の意思疎通の困難がある方にとって、外出は容易ではありません。
訪問看護の枠組みでSTがご自宅を訪問することにより、通院の負担なく、住み慣れたリラックスできる環境で専門的なリハビリを受けることが可能になります。
生活の場で実践的な訓練を行うことで、リハビリで得られた成果を、食事や家族との団らんといった実際の日常生活の質の向上に直結しやすいことが大きな利点です。
訪問看護STと病院勤務STの違い
病院(特に急性期や回復期)で勤務するSTは、主に発症直後や状態が不安定な時期の集中的な機能回復訓練や、嚥下造影検査(VF)や嚥下内視鏡検査(VE)といった検査機器を用いた詳細な評価を担当します。
訪問看護で活動するSTは、退院後の生活期にある方を主な対象とします。ご自宅の環境、普段の食事内容、ご家族の介護力、そして何よりご本人の希望や価値観を踏まえ、より日常生活に即したリハビリ計画を立てる点が大きな特徴です。
訪問STと病院STの主な役割の違い
| 項目 | 訪問看護のST | 病院勤務のST(回復期など) |
|---|---|---|
| 主な活動場所 | 利用者の自宅(生活の場) | 病院内のリハビリ室(訓練室) |
| リハビリの焦点 | 実生活での応用・維持、環境調整 | 集中的な機能回復、詳細な検査 |
| 環境 | 実際の生活環境、普段の道具を使用 | 整備された訓練環境、専門機器を使用 |
訪問STはご自宅にある食器や椅子を使ったり、ご家族が普段作っている食事の形態や調理法を一緒に確認したりするなど、実際の生活場面に密着した支援を行うので、実生活への密着度が、訪問看護STの最大の強みです。
言語聴覚士(ST)が訪問看護で対応する主な症状
訪問看護を利用する方々は、脳卒中、神経難病、認知症、あるいは加齢による機能低下など、様々な病気や障害を背景に持っています。ここでは、STが訪問看護で関わることの多い代表的な症状を紹介します。
飲み込みの問題(嚥下障害)
嚥下障害は、食べ物や飲み物をうまく認識し、口の中でまとめ、喉に送り込み、飲み込むという一連の動作がスムーズに行えない状態です。脳卒中やパーキンソン病、あるいは加齢による筋力低下(サルコペニア)など、原因は多岐にわたります。
食べ物が食道ではなく気管に入ってしまう誤嚥(ごえん)を起こしやすく、繰り返されると重篤な肺炎(誤嚥性肺炎)を発症するリスクが非常に高まります。
誤嚥性肺炎は、在宅療養中の高齢者にとって命に関わることもあるため、早期からの対応が重要です。
STは、安全に食事を摂るための飲み込みの練習や、食べやすい食事の形態(とろみ、刻み、ペーストなど)、誤嚥しにくい正しい食事の姿勢などを評価し、指導します。
ことばの問題(失語症・構音障害)
ことばの問題もSTの主要な対象で、代表的なものに失語症と構音障害、音声障害があります。
- 失語症
- 構音障害
- 音声障害
失語症は、主に脳卒中(脳梗塞や脳出血)などで脳の言語中枢が損傷し、それまで獲得していた「話す」「聞く」「読む」「書く」といったことばの機能全般が障害される状態です。
言いたい言葉が出てこない(喚語困難)、相手の言うことが理解できない(聴覚的理解の障害)といった症状が現れます。
構音障害は、脳や神経の障害により、発声発語器官(唇、舌、顎など)の麻痺や運動のぎこちなさが生じ、ろれつが回らず発音が不明瞭になる状態です。言葉そのものの機能は保たれています。
また、声帯の麻痺などで声がかすれる、小さくなるなどの音声障害も対象となります。STは、それぞれの原因や症状に合わせて、残された能力を活かしながら意思疎通を図る方法を一緒に探したり、発音や発声の練習を行ったりします。
聞こえの問題(聴覚障害)
加齢や病気により聞こえにくさ(難聴)が生じると、ご本人だけでなく、ご家族や友人との会話も減少しがちです。必要な情報が得られにくくなったり、社会的な孤立感を深めたり、認知機能の低下につながったりすることが懸念されます。
STは、聞こえの状態を評価し、補聴器の調整や適切な使い方について助言し、訪問看護では、ご自宅の生活音(テレビの音、換気扇の音など)の中で、どの程度会話が聞き取れているかを評価できる利点があります。
また、ご家族に対して、聞こえにくい方への効果的な話しかけ方(ゆっくり、はっきり、顔を見て話す、雑音を減らすなど)を指導することもあり、聴覚的なリハビリや環境調整を通じて、生活の質を保つお手伝いをします。
高次脳機能障害
高次脳機能障害は、脳の損傷によって記憶、注意、思考、判断、計画といった高度な精神機能が障害される状態です。
新しいことを覚えられない(記憶障害)、一つのことに集中力が続かない(注意障害)、計画的に物事を進められない(遂行機能障害)、感情のコントロールが難しい(社会的行動障害)といった多様な症状が見られます。
このような問題は、外見からは分かりにくいため、ご本人も周囲も気づきにくく、日常生活や社会生活を送る上で大きな障壁となります。ご家族も、ご本人の「性格が変わってしまった」と感じ、対応に苦慮することが少なくありません。
STは、こうした認知面の問題に対しても詳細に評価を行い、日常生活の困難を軽減するための工夫(メモリーノートの活用、アラームの設定、作業手順の視覚的な提示など)や、機能の回復を目指す訓練を提供します。
高次脳機能障害の主な症状例
| 障害の種類 | 主な症状の例 | 生活上の困難さ |
|---|---|---|
| 記憶障害 | 新しいことを覚えられない、さっき言ったことを忘れる | 薬の飲み忘れ、約束を忘れる、何度も同じ話をする |
| 注意障害 | 集中力が続かない、複数のことを同時にできない | 会話中にぼんやりする、作業ミスが多い、料理が焦げる |
| 遂行機能障害 | 計画的に行動できない、段取りが悪い | 料理の手順が分からない、外出準備に時間がかかる |
訪問看護での言語聴覚士(ST)によるリハビリ内容
ご自宅で行うリハビリは、病院の訓練室とは異なり、その方の生活空間そのものが訓練の場となります。
言語聴覚士(ST)は、利用者の医学的な状態や機能評価に基づくだけでなく、生活環境、ご家族の希望、ご本人の価値観に応じて、個別性の高いリハビリテーションプログラムを立案し、実践します。
嚥下(飲み込み)のリハビリ
安全に楽しく食事を続けることは、在宅療養においてご本人の楽しみであると同時に、生命維持と肺炎予防の観点からも非常に重要です。STはまず、利用者の飲み込みの状態を詳細に評価します。
実際に食事をする様子を観察し、どのタイミングでむせやすいか、食べ物が口に残りやすいか、食事に時間がかかりすぎていないかなどを確認した上で、必要なリハビリを実施します。
嚥下リハビリの主な内容
| 訓練の種類 | 目的と内容 |
|---|---|
| 間接訓練 | 食事を使わずに行う訓練。嚥下体操(口や舌の体操、首の運動)、呼吸練習、発声練習などで飲み込む力を高める。 |
| 直接訓練 | 実際に食べ物や飲み物(ゼリーやとろみ水など、安全なものから)を用いて行う訓練。安全な姿勢や食べ方、一口量を練習する。 |
また、ご家族に対して、食事介助の方法(姿勢、スプーンの運び方、声かけのタイミングなど)や、調理器具(とろみ剤やミキサーなど)の使い方、ご本人の状態に合った食べやすい食事形態(刻み食、ペースト食など)の調理法などを提案します。
発声・発話のリハビリ
声が出しにくい(音声障害)や、ろれつが回らない(構音障害)方に対しては、発声や発音の明瞭度を高めるリハビリを行います。
腹式呼吸を練習して力強い安定した声を出す練習や、口唇や舌の動きを滑らかにするための体操(「パ」「タ」「カ」「ラ」といった音を繰り返し発音する「パタカラ体操」など)を行います。
また、特定の音を繰り返し発音する練習や、ゆっくりと大きな声で話す練習などを通じて、会話における聞き取りやすさを改善します。
言語(読む・書く・聞く・話す)のリハビリ
失語症の方に対しては、残された言語機能を最大限に引き出し、意思疎通の能力を高めるためのリハビリを行います。単に単語カードや絵カードを使った訓練をご自宅で行うだけではありません。
- 単語や文の復唱
- 絵カードを用いた呼称訓練
- 文字の読み書き練習
- 日常会話の練習
ご本人が趣味で読んでいた雑誌や新聞を使ったり、ご家族との日常会話の場面にSTが同席し、実際のやり取りの中でことばの理解や表出を促したりします。
また、ことばが出にくい場合には、ジェスチャーや描画、あるいは文字盤やタブレット端末などの代替手段(AAC: 拡大・代替コミュニケーション)の導入を積極的に検討し、使い方を練習することもあります。
大切なのは、ことばの機能回復を目指すだけでなく、その人らしい実用的な意思疎通の方法を見つけ出し、社会的なつながりを維持することです。
代替手段(AAC)の例
| 種類 | 具体例 | 特徴 |
|---|---|---|
| ローテク(非電子的) | 文字盤、絵カード、ジェスチャー、描画 | 導入しやすい、電源が不要 |
| ハイテク(電子的) | 会話補助装置、タブレット端末のアプリ | 音声出力が可能、多くの語彙を登録できる |
認知機能へのアプローチ
高次脳機能障害や認知症の方に対しては、日常生活の困難さを軽減するためのアプローチが大切です。
記憶障害の方には、カレンダーやメモリーノート、スマートフォンのアラーム機能などを活用して、スケジュール管理や服薬管理がご自身で(あるいは少ない介助で)できるように環境を整え、使い方を繰り返し練習します。
注意障害の方には、テレビを消す、一度に一つのことだけ行うなど、集中しやすい環境を設定し、一つの作業に集中する練習を行います。
訪問看護でSTのリハビリを受けるメリット
病院でのリハビリとは異なり、訪問看護のSTによるご自宅でのリハビリには、在宅療養中の方ならではの多くの利点があります。
住み慣れた環境での実践的な訓練
最大のメリットは、ご本人が最もリラックスでき、かつ実際に生活している環境でリハビリを受けられることです。
病院のリハビリ室という非日常的な空間ではなく、ご自宅のいつもの食卓で、普段使っている食器や椅子を使って食事の練習ができます。
また、ご自宅のトイレまでの移動中の会話や、かかってきた電話の応対など、実際の生活場面に即した具体的な課題に対して、より実践的な訓練が可能です。
ご家族へのサポートと指導
訪問看護では、ご家族もリハビリの重要なパートナーです。STはご家族がリハビリに同席することを奨励し、ご本人の現在の状態やリハビリの目的、今後の見通しなどを共有します。
そして、ご家族が日常生活の中で行える効果的な関わり方(例えば、失語症の方へのゆっくりとした話し方)や、安全な食事介助の方法、むせにくい食事の調理法などを指導します。
- 安全な食事介助の姿勢
- むせにくい食事形態の調理法(とろみの付け方など)
- 失語症の方への効果的な話しかけ方
ご家族が正しい知識と技術を身につけることで、ご本人の状態維持や改善につながるだけでなく、介護にあたるご家族の不安や負担が軽減されるという側面も持ちます。STはご家族の悩みやストレスにも耳を傾け、精神的なサポートも行います。
ご家族への指導内容例
| 対象となる問題 | 指導内容の例 | 期待される効果 |
|---|---|---|
| 嚥下障害(むせ) | 食事の姿勢調整、一口量の調整、とろみの付け方 | 誤嚥性肺炎の予防、安全な経口摂取の継続 |
| 失語症(言葉が出にくい) | ゆっくり話す、「はい/いいえ」で答えられる質問をする、ジェスチャーを併用する | ご本人の意思疎通ストレス軽減、ご家族の関わりやすさ向上 |
医療チームとの密な連携
訪問看護のSTは、決して一人で活動しているわけではありません。
主治医や訪問看護師、ケアマネジャー、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、薬剤師、歯科医師、歯科衛生士、ヘルパーなど、在宅療養を支える多くの専門職と常に情報を共有し、連携しています。
STが嚥下機能の低下を発見した場合、すぐに訪問看護師と主治医に報告し、食事形態の変更や栄養状態の確認、場合によっては薬剤の形状変更(錠剤から粉薬へなど)を薬剤師に依頼することが大切です。
また、PTやOTと連携し、食事の際の適切な座位姿勢(車椅子やベッド上の姿勢)や、使いやすい食器(自助具)の選定を共同で行うこともあります。
訪問看護の言語聴覚士(ST)が関わる対象者
訪問看護によるSTのリハビリは、特定の疾患名だけで決まるものではなく、「食べる」「話す」「聞く」といった機能に何らかの困難があり、在宅療養中で通院によるリハビリが難しい方が主な対象です。
脳卒中(脳梗塞・脳出血)の後遺症がある方
脳卒中は、STが関わる最も代表的な疾患の一つです。損傷を受けた脳の部位によって、失語症、構音障害、嚥下障害、高次脳機能障害など、多様な後遺症が現れます。
病院での急性期・回復期リハビリを終えて退院した後も、症状が残り、ご自宅での生活に支障をきたしている場合に、訪問STが継続的なリハビリや生活指導を行うことが重要です。
パーキンソン病などの神経難病の方
パーキンソン病や筋萎縮性側索硬化症(ALS)、脊髄小などの神経難病は、病気の進行に伴って徐々に話す力や飲み込む力が低下していくことが特徴です。
訪問STは、病気の進行段階に合わせて、機能の維持・低下予防を目的としたリハビリを行います。
- パーキンソン病
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 脊髄小脳変性症
- 多系統萎縮症
パーキンソン病で声が小さくなりがちな方には、声を大きく明瞭にするための専門的な発声訓練(LSVT LOUDなど)を行います。飲み込みにくさが出てきた方には、進行に合わせた食事形態の調整を早期から行います。
また、ALSなどで病気が進行して会話が難しくなった場合には、ご本人の意思を尊重しながら、早期から文字盤や視線入力式の意思伝達装置の導入を検討し、ご本人とご家族が長く意思疎通を続けられるよう支援することが可能です。
神経難病におけるSTの主な関わり
| 疾患名例 | 主な症状 | STの支援内容 |
|---|---|---|
| パーキンソン病 | 声が小さい、話しにくい、飲み込みにくい | 専門的発声訓練、嚥下訓練、食事指導 |
| ALS | ろれつが回らない、飲み込みにくい、呼吸しにくい | 構音訓練、嚥下訓練、代替の意思伝達手段の導入・練習 |
加齢により飲み込みや会話が難しくなった方
特定の病気だけでなく、加齢に伴う全身の筋力の低下(サルコペニア)や、口腔機能の低下(オーラルフレイル)、感覚の鈍化によっても、食べる機能や話す機能は低下します。
「最近、食事中にむせやすくなった」「硬いものが食べにくくなった」「声がかすれてきた」「会話中に聞き返しが増えた」など、加齢による衰え(老衰)が背景にある場合も、訪問STの対象です。
兆候を放置すると、低栄養や脱水、誤嚥性肺炎のリスクが高まります。STが早期から関わり、嚥下体操や発声練習、食事環境の調整、補聴器の調整などを支援することで、肺炎予防や社会的な孤立を防ぎ、生活の質(QOL)を維持します。
認知症の症状がある方
認知症(アルツハイマー型、レビー小体型、脳血管性など)の方も、病状の進行に伴い、様々な問題が生じます。
食事に集中できない、食べ物を食べ物として認識できない(失認)、言葉が理解できない、うまく話せないといった問題が生じ、食事が困難になることがあります。
また、意思疎通が難しくなることで、ご本人の不安や混乱が強まり、ご家族の介護負担が増大することも少なくありません。
STは、ご本人が混乱しないような環境設定(静かな場所で食事をする、食器の色を変えて認識しやすくする等)や、ご本人のペースに合わせた食事介助、理解しやすいような単純で言葉がけの方法をご家族に助言することも、大きな役割です。
訪問看護によるSTリハビリの利用開始までの流れ
ご自宅で言語聴覚士(ST)のリハビリを受けたいと考えた場合、いくつかの手順を踏む必要があります。訪問看護サービスは医療保険または介護保険を利用して提供されるため、公的な手続きと、主治医やケアマネジャーとの連携が重要です。
必要な準備と相談先
まず、ご本人やご家族が「食べる」「話す」「聞く」ことに関して、日常生活でどのようなことに困っているのかを整理します。
例えば、「食事中にむせることが週に何度もあって心配だ」「ろれつが回らず、電話で相手に伝わらない」「言葉が出なくて、本人がイライラしている」などです。
その上で、かかりつけの主治医(病院の医師、または在宅医)、または介護保険を利用している場合は担当のケアマネジャーに相談します。
主な相談先
| 相談先 | 主な役割 |
|---|---|
| 主治医(かかりつけ医) | 医学的な必要性を判断し、「訪問看護指示書」を発行する |
| ケアマネジャー | 介護保険サービスとしてケアプランに訪問看護(STリハビリ)を位置づけ、事業所と調整する |
| 地域の訪問看護ステーション | サービス内容や利用方法、STの在籍状況について直接相談する |
主治医による指示書の重要性
訪問看護(STリハビリを含む)を開始するためには、医療保険・介護保険のどちらを利用する場合でも、主治医が医学的に判断し、訪問看護ステーション宛てに訪問看護指示書を発行することが必須条件です。
指示書に基づいて、訪問看護師やSTはご自宅を訪問し、医療的なケアやリハビリを提供するので、まずは主治医に現在の症状や生活での困りごとを正確に伝え、訪問看護の必要性を相談してください。
訪問看護ステーションとの契約
主治医の許可が得られ、ケアマネジャー(または病院の退院支援室の相談員)が調整した後、利用する訪問看護ステーションの管理者や担当者がご自宅を訪問します。
そこで、サービス内容の詳細、利用料金(保険適用の自己負担分)、緊急時の連絡方法や対応体制などについて詳しい説明があるので、内容を十分に理解し、同意した場合、ステーションと正式に利用契約を結びます。
この際に、言語聴覚士(ST)の訪問を希望していることを再度確認し、訪問可能な曜日や時間帯についても調整することが大事です。
初回訪問とリハビリ計画の作成
契約後、まず看護師が訪問して全身状態(バイタルサイン、既往歴、服薬状況など)をアセスメントし、その後STが初回訪問に伺います。STはご本人の状態(嚥下機能、言語機能、発声発語機能、認知機能など)を専門的に評価します。
加えて、ご本人やご家族の希望、生活環境、食事の状況などを詳しく伺いながら、ご本人・ご家族と目標を共有し、目標を達成するために、個別のリハビリテーション計画書を作成し、主治医の確認を得ます。
訪問看護での言語聴覚士(ST)リハビリに関するよくある質問
訪問看護でのSTリハビリについて、多くの方から寄せられる代表的な質問と回答をまとめました。
- リハビリはどれくらいの頻度で受けられますか?
-
一般的には、週に1回から2回程度、1回の訪問でリハビリを行う方が多いです。介護保険を利用する場合は、ケアマネジャーが作成するケアプランに基づいて、他のサービスとのバランスを見ながら訪問回数が決まります。
医療保険を利用する場合は、主治医の指示に基づきますが、原則として週3回までです(特定の難病など、厚生労働大臣が定める疾病等の場合はこの限りではありません)。
- リハビリの1回あたりの時間はどれくらいですか?
-
1回あたり40分から60分程度が一般的です。
この時間内で、訪問時の体調確認(血圧、脈拍、体温など)、実際のリハビリテーションの実施、ご家族への指導や助言、その日の経過やリハビリ内容の記録などを行います。
利用者のその日の体調や疲労度、集中力に応じて、リハビリ内容や時間を調整することもあります。訪問看護は医療保険または介護保険が適用されますが、制度によって1回の訪問時間が定められている場合があります。
- 家族もリハビリに同席できますか?
-
ぜひ同席をお勧めします。必須ではありませんが、多くのメリットがあります。ご家族がリハビリの様子を実際に見ることで、ご本人の現在の状態やリハビリ内容への理解が深まります。
また、STがご家族に直接、安全な食事介助の方法や、日常での効果的な関わり方を指導できるため、リハビリの効果をご家族がいない時間帯の生活場面にも広げることができます。
ご家族が抱える介助上の不安や疑問にその場でお答えすることも可能です。
- どのような準備が必要ですか?
-
訪問リハビリは、ご自宅にあるものを活用して、実際の生活環境で行うのが基本です。嚥下リハビリであれば普段お使いの食器やスプーン、練習用の食品(ゼリーやお茶、とろみ剤など)をご用意いただくことがあります。
言語リハビリであれば、新聞や雑誌、筆記用具、カレンダーなど、ご本人が関心のあるものや、生活に必要なものを使うことがあります。
以上
参考文献
Jeong S, Inoue Y, Arai Y, Ohta H, Suzuki T. What should be considered when evaluating the quality of home care? A survey of expert opinions on the evaluation of the quality of home care in Japan. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2022 Feb 18;19(4):2361.
Ashiga H, Kojima K, Omori F, Fujiu-Kurachi M. A survey on advantages and disadvantages of telerehabilitation by speech-language-hearing therapists in Japan. Preventive Medicine Research. 2025 Sep 26;3(2):84-96.
Iwata H, Matsushima M, Watanabe T, Sugiyama Y, Yokobayashi K, Son D, Satoi Y, Yoshida E, Satake S, Hinata Y, Fujinuma Y. The need for home care physicians in Japan–2020 to 2060. BMC health services research. 2020 Aug 15;20(1):752.
Kinoshita S, Abo M, Okamoto T, Miyamura K. Transitional and long-term care system in Japan and current challenges for stroke patient rehabilitation. Frontiers in Neurology. 2022 Jan 11;12:711470.
Nakamura K, Takano T, Akao C. The effectiveness of videophones in home healthcare for the elderly. Medical care. 1999 Feb 1;37(2):117-25.
Chu SY, Hara Y, Wong CH, Higashikawa M, McConnell GE, Lim A. Exploring attitudes about evidence-based practice among speech-language pathologists: a survey of Japan and Malaysia. International Journal of Speech-Language Pathology. 2021 Nov 2;23(6):662-71.
Yamaguchi K, Makihara Y, Kono M. Rehabilitation professionals for the aging society in Japan Their scopes of work and related health policies and systems. Journal of the National Institute of Public Health. 2022 Feb 28;71(1):35-44.
Sato K, Otaka E, Ozaki K, Shiramoto K, Narukawa R, Kamiya T, Kamiya M, Shimotori D, Kamizato C, Itoh N, Kagaya H. Investigating the effects of home-based rehabilitation after intensive inpatient rehabilitation on motor function, activities of daily living, and caregiver burden. PLoS One. 2024 Dec 27;19(12):e0316163.
Sakai K, Momosaki R. Real-world effectiveness of speech therapy time on cognitive recovery in older patients with acute stroke. Progress in Rehabilitation Medicine. 2016;1:20160004.
Butler J, Smith T. Community care and rehabilitation after stroke in Japan. British Journal of Occupational Therapy. 2002 Aug;65(8):363-70.