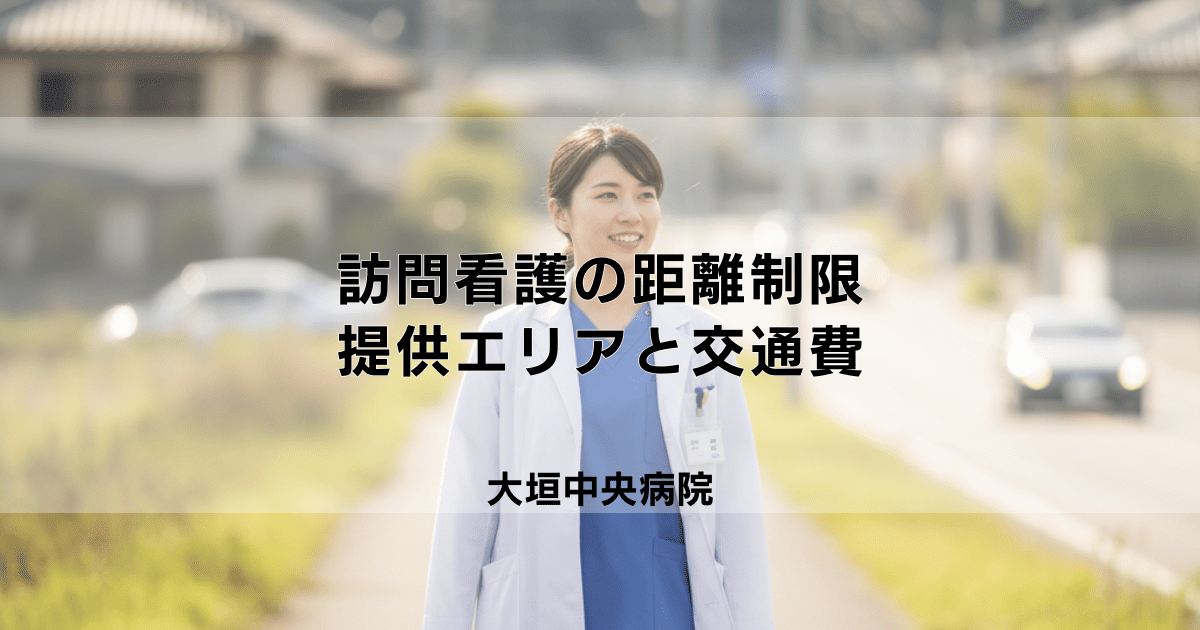訪問看護を自宅で受けたいと考えたとき、多くの方が「自宅まで来てもらえるのか」「家が遠いと料金が高くなるのではないか」という疑問を持つでしょう。
訪問看護は、看護師などが自宅を訪問してケアを提供するサービスですが、無制限にどこへでも訪問できるわけではなく、各訪問看護ステーション(事業所)がサービス提供エリアを定めています。
エリアの決め方や、エリア外の場合の対応、そして気になる交通費の仕組みについて、詳しく解説します。
訪問看護のサービス提供エリアとは
サービス提供エリアとは、訪問看護ステーション(事業所)が、サービスを安定的かつ効率的に提供できると定めた地理的な範囲のことです。
利用者の自宅がエリア内にあれば、事業所の訪問看護サービスを利用できまが、エリアは、法律で一律に決められているわけではなく、それぞれの事業所が独自に設定しています。
なぜ提供エリアが設定されるのか
提供エリアを設定する主な理由は、サービスの質を維持・確保するためです。
もしエリアが広すぎると、看護師などのスタッフは訪問先への移動に多くの時間を費やすことになり、一日に訪問できる件数が減るだけでなく、利用者一人ひとりのケアに充てる時間が圧迫される可能性があります。
また、移動距離が長くなるとスタッフの疲労も蓄積し、長期的に安定したサービスを提供することが難しくなるかもしれません。
さらに、緊急時の対応も重要な理由の一つです。訪問看護の利用者の中には、容態が急変するリスクを抱えている方もいて、事業所から近いエリアであれば、緊急の訪問要請があった場合にも迅速に駆けつけることが可能です。
提供エリアは、緊急時対応の速さを担保するためにも大事な基準となります。
提供エリアは誰が決めているのか
サービス提供エリアは、国の法律や都道府県の条例で「半径〇km」のように一律に定められているものではなく、エリアを決定しているのは、各訪問看護ステーション自身です。
事業所は、厚生労働省の基準に基づき、事業所の運営規程という内部ルールの中で通常の事業の実施地域としてサービス提供エリアを明記します。
この運営規程は、事業所が指定を受ける(開設許可を得る)際に、都道府県や市町村に届け出ることが必要です。
事業所は、地域の人口密度、地理的な特徴(山、川、大きな道路など)、交通の便、スタッフの人数、緊急時対応の体制などを総合的に考慮して、現実的に質の高いサービスを提供できる範囲を判断し、エリアとして設定します。
このため、事業所の規模や方針によって、提供エリアの広さや形状は様々です。
提供エリアの目安
多くの訪問看護ステーションでは、事業所からの移動時間を基準に提供エリアを設定していて、目安としては、「事業所から車やバイクで片道20分から30分以内に到達できる範囲」とすることが一般的です。
距離に換算すると、都市部であれば半径5km圏内、交通量が少ない地域であれば半径10km圏内といった具合になりますが、あくまで移動時間が優先されます。
また、行政区分(例:〇〇市全域、△△区と□□区の一部)を基準にすることもあり、これは、地域の医療機関やケアマネジャー、行政との連携のしやすさを考慮した結果です。
同じ市内であっても、大きな川や山を隔てている場合は、移動時間がかかるためエリア外としているケースもあります。
提供エリア設定の一般的な基準例
| 基準 | 目安 | 考慮点 |
|---|---|---|
| 移動時間 | 片道20分~30分以内 | 地域の交通事情(渋滞など) |
| 距離 | 事業所から半径5km~10km圏内 | 地理的条件(山間部、都市部) |
| 行政区分 | 〇〇市、△△区 | 地域の連携のしやすさ |
訪問看護ステーションが定める提供エリアの基準
訪問看護は、利用者が自身の住まいで安心して生活を継続できるよう支援する、非常に地域密着性の高いサービスです。
看護師は利用者の自宅での様子を直接把握できるため、その地域の特性(気候、文化、利用できる社会資源など)を理解していることが、より適切なケアの提供につながります。
効率的な訪問ルートの確保
訪問看護のスタッフは、一日に複数の利用者の自宅を順番に訪問するので、サービス提供エリアが適切に設定されていないと、訪問先が地理的に点在し、訪問と訪問の間の移動時間が長くなってしまいます。
午前中はA市の北端、午後はA市の南端、その次はB市、といった非効率なルートになれば、移動だけで多くの時間を浪費するので、提供エリアをある程度限定することで、効率的な訪問ルート(訪問順序)を組みやすくなります。
移動時間を最短にできればその分、利用者のケアや記録、他の専門職との情報共有により多くの時間を充てられ、結果としてサービス全体の質の向上につながるのです。
緊急時対応のための体制
在宅療養を支える上で、利用者の容態急変時にいかに迅速に対応できるかは極めて重要です。
多くの訪問看護ステーションでは、24時間対応の体制を整えており、夜間や休日でも利用者の電話相談に応じたり、必要に応じて緊急訪問を行ったりします。
緊急訪問が機能するためには、事業所から利用者の自宅まで、すぐに駆けつけられる物理的な距離であることが前提です。
もし事業所から非常に遠い場所に住んでいると、緊急連絡を受けてから到着までに1時間以上かかるようでは、迅速な対応とは言えません。サービス提供エリアは、この万が一の事態に備え、利用者の安全を守るための範囲でもあるのです。
エリア設定で考慮する地理的要因
- 河川や線路による分断
- 山間部や坂道の多さ
- 一方通行や狭い道路
- 公共交通機関の利便性(自動車が使えない場合)
スタッフの負担軽減
訪問看護の仕事はケアの提供だけでなく、訪問先への移動も伴い、都市部での渋滞や、悪天候(大雨、雪)、山間部での運転などは、スタッフにとって大きな身体的・精神的負担です。
訪問エリアが広すぎると、一日の大半を運転に費やすスタッフも出てくるようになり、このような状況が続けば、スタッフの疲労が蓄積し、注意力が散漫になり、医療事故や交通事故のリスクを高める可能性があります。
また、過度な負担は離職の原因ともなり得ます。経験豊富なスタッフが長く働き続けられる環境を整えることは、利用者への安定したサービス提供に直結します。
適切なサービス提供エリアの設定は、スタッフの労働環境を守り、サービスの質を維持するためにも必要な配慮です。
法律上の距離制限はあるのか
訪問看護は、介護保険または医療保険のどちらかを利用して受けるサービスですが、どちらの保険制度においても、訪問看護の距離に関して「事業所から半径〇km以内」といった数値での制限を設ける法律はありません。
事業所の運営規程による定め
法律による一律の距離制限がない代わりに、訪問看護ステーションがサービス提供を行う上での実質的な制限となっているのが運営規程です。
すべての訪問看護ステーションは、事業所を開設するにあたり、運営規程を作成し、都道府県(または政令市・中核市)に届け出る義務があります。運営規程の中に、通常の事業の実施地域という項目を設ける必要があります。
ここに記載された地域(例:「〇〇市、△△市(一部地域を除く)」など)が、事業所の正式なサービス提供エリアとなります。
事業所は、原則としてこのエリア内に住む利用者からの申し込みに応じる義務があり、逆にエリア外の利用者からの申し込みについては、正当な理由があれば断ることも可能です。
訪問看護の提供エリアに関する規定
| 規定の種類 | 主な内容 | 距離制限 |
|---|---|---|
| 法律(介護保険法など) | 訪問看護の距離に関する明確な規定はない | なし |
| 事業所の運営規程 | 「通常の事業の実施地域」を定める義務 | 実質的な制限 |
交通費に関する国の指針
距離制限そのものではありませんが、距離に関連する交通費については、国(厚生労働省)が一定の指針を示しています。
介護保険の場合、通常の事業の実施地域内であれば、交通費は利用料(介護報酬)の中に含まれているため、別途交通費を徴収することは原則として認められていません。
ただし、通常の事業の実施地域を越えてサービスを提供する場合に限り、移動にかかる実費を利用者に請求することが認められています。
この指針があるため、多くの事業所は運営規程で定めたエリア内は交通費無料、エリア外は交通費(実費)が必要、というルールを採用していて、運営規程で定めるエリアを適切に設定する動機付けにもなっているのです。
サービス提供エリア外でも利用できるケース
訪問看護ステーションが定めたサービス提供エリアの外に住んでいる場合でも、訪問看護の利用を絶対に諦めなければならないわけではありません。
エリア外の利用者がサービスを希望し、かつ、その訪問看護ステーションが対応可能と判断(同意)した場合、サービスを受けることは可能です。
事業所の判断基準
事業所がエリア外の利用者を受け入れるかどうかを判断する際、いくつかの点を検討し、最も重要なのは、利用者の自宅への訪問が、既存の訪問スケジュールやルートの中に効率的に組み込めるかという点です。
エリア外であっても、既に他の利用者がいる訪問先のすぐ近所であれば、移動の負担が少ないため受け入れやすいかもしれません。
また、緊急時対応が可能かどうかも厳しく審査され、容態が安定している利用者であれば受け入れやすく、頻繁な緊急訪問が予想される利用者であれば、距離を理由に難色を示すこともあります。
利用者のケアに必要な専門性(例:特定の医療機器の管理、精神科訪問看護など)も考慮されます。
エリア外利用の相談時に確認すべき点
| 確認項目 | 確認内容 |
|---|---|
| 訪問の可否 | エリア外だが訪問してもらえるか |
| 追加費用(交通費) | 交通費はいくらかかるか(算定方法) |
| 緊急時対応 | 緊急時の訪問体制はどうなるか |
エリアの境界付近に住んでいる場合
サービス提供エリアの境界線付近にお住まいの場合は、エリア外であっても比較的柔軟に対応してもらえる可能性が高く、提供エリアが「〇〇市」となっていても、隣接する△△市の、市境からすぐの場所にお住まいの場合などです。
この場合、距離的にはエリア内の他の利用者と変わらない、あるいはむしろ近いということもあり得ます。
行政区分でエリアを区切っている事業所も、実態としては移動時間で判断していることが多いため、地図上の線引きだけで諦めず、まずは「エリアのすぐ隣なのだが」と具体的に住所を伝えて相談してみることが大切です。
特別な事情がある場合
利用者に特別な事情がある場合、事業所が距離のハードルを越えて対応を検討することもあります。
利用者が特定の難病や障害を抱えており、専門的なケアができる訪問看護ステーションが地域に他になく、その事業所だけが対応可能な場合などです。
また、利用者の主治医(かかりつけ医)が、その訪問看護ステーションの看護師との連携を強く希望し、紹介した場合なども、エリア外であっても受け入れを前向きに検討する要因となり得ます。
利用者の療養生活にとって、事業所の訪問看護が強く必要とされる理由がある場合は、その旨を主治医やケアマネジャーを通じて伝えてもらうと良いでしょう。
訪問看護にかかる交通費の仕組み
事業所が運営規程で定めた通常の事業の実施地域(サービス提供エリア)内への訪問については、利用料(介護報酬)に含まれていると解釈されるため、別途交通費を請求できません。
エリア外への訪問については、事業所は利用者に対して交通費を請求することが認められていいて、訪問看護の基本料金とは別のその他の費用として扱われます。
交通費の算定方法
交通費を請求する場合、算定方法は事業所によって様々で、事業所は、交通費の具体的な金額と算定根拠を定め、利用者にあらかじめ説明しておくことが必要です。
主な算定方法には、実際にかかった費用をそのまま請求する実費精算と、距離や地域に応じてあらかじめ決められた額を請求する定額制があります。
医療保険を利用する場合の交通費は、介護保険のような明確なルールがなく、事業所の判断に委ねられている側面が強いですが、多くの事業所は介護保険の考え方に準じて、エリア外の場合に実費を請求するという運用をしています。
交通費の主な算定方法
| 算定方法 | 内容 | 特徴 |
|---|---|---|
| 実費精算 | 公共交通機関の運賃、ガソリン代など | 訪問ごとに変動する可能性あり |
| 距離に応じた一定額 | 例:事業所から5km毎に100円など | 金額が明確で分かりやすい |
| エリア内一律無料 | 基本料金に含む(エリア内のみ) | 利用者にとって最も分かりやすい |
利用者への事前説明の重要性
交通費は、利用者がサービスを選択する上での重要な情報の一つで、訪問看護ステーションは、交通費を徴収する可能性があるのであれば、サービス開始前の契約時に、利用者やその家族に対して必ず説明を行う義務があります。
重要事項説明書などの文書に、交通費を徴収する条件(例:エリア外の場合)、算定方法(例:実費)、おおよその金額などを明記し、口頭でも説明した上で、利用者の同意を得なければなりません。
もし、事前の説明や同意なしに、後から高額な交通費を請求された場合は、適切な手続きを踏んでいない可能性があります。契約時には交通費の項目をしっかりと確認し、疑問点があればその場で解消しておくことが大切です。
交通費が自己負担になる場合とならない場合
利用者の自宅が、訪問看護ステーションの運営規程に定められた通常の事業の実施地域(サービス提供エリア)内にある場合、交通費は自己負担にならないケースがほとんどです。
ただし、これはあくまで介護保険の原則であり、事業所によっては独自のルールを設けている場合もゼロではありません(例えば、医療保険利用者に一律で請求する、など)。
サービス提供エリア外の交通費
利用者の自宅がサービス提供エリア外にある場合、交通費は自己負担となるのが一般的です。
エリア外への訪問は、事業所にとって通常の運営コストを超える移動時間や費用(ガソリン代、高速道路料金、駐車料金など)が発生するためで、追加コスト分を、サービスを受ける利用者に実費として負担してもらいます。
この場合事業所は、事業所から利用者宅までの往復の交通費実費を請求することが認められています。
金額は距離や使用する交通手段によって大きく異なるため、契約前に「自宅までの訪問だと、1回あたりいくらになるか」を具体的に確認しておくことが大切です。
エリア内外での交通費比較(一例)
| 区分 | 交通費の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| サービス提供エリア内 | 無料(基本料金に含む) | 事業所の方針による |
| サービス提供エリア外 | 実費請求(ガソリン代、高速代など) | 事前に金額の確認が必要 |
交通費の確認方法
交通費が自己負担になるかならないか、なるとすればいくらかかるのか最も確実に確認する方法は、サービス利用の契約時に取り交わす重要事項説明書と契約書を確認することです。
書類には、利用料金の詳細が記載されており、交通費についても徴収の有無、金額、算定方法が明記されています。
もし記載があいまいだったり、口頭での説明と異なったりする場合は、必ず担当者に質問してください。「交通費はかかりません」と説明された場合は、エリア内に限った話なのか、エリア外になった場合どうなるのかまで確認しておくと安心です。
交通費の取り扱いパターン
- エリア内は無料、エリア外は実費請求
- エリア内外問わず、一律無料
- エリア内外問わず、一律〇〇円を徴収
- エリア内外問わず、実費を請求
訪問看護ステーションの選び方とエリア確認
利用したい訪問看護ステーションが見つかったら、まずはご自宅が事業所のサービス提供エリアに含まれているかを確認する必要があります。
サービス提供エリアの確認方法
確認方法はいくつかあり、最も簡単なのは事業所の公式ホームページを見ることですが、ホームページに記載がない場合や、情報が古い可能性もあるため、電話で直接問い合わせるのが確実です。
| 確認方法 | 確認できる場所・相手 |
|---|---|
| ホームページ | 各訪問看護ステーションのHP |
| 電話問い合わせ | 各訪問看護ステーションの窓口 |
| 相談 | ケアマネジャー、病院の相談員 |
複数の事業所を比較する
ご自宅が複数の訪問看護ステーションの提供エリアに入っている場合、どの事業所を選ぶか比較検討することが大切です。
事業所によって様々な特色があり、リハビリテーション(理学療法士など)に力を入れている事業所、精神科の訪問看護を専門とする事業所、小児や難病の対応経験が豊富な事業所などがあります。
ご自身の病状や必要とするケアに合わせて、強みを持つ事業所を選ぶことが、より良い在宅療養につながります。
また、24時間対応の体制が整っているか、緊急時に迅速に来てくれそうか(事業所との実際の距離感)なども、比較のポイントです。
交通費の規定を契約前に確認する
利用する事業所が決まったら、サービス開始前の契約手続きを行い、この際、必ず交通費の規定を確認してください。重要事項説明書や契約書に交通費の項目を探し、どのような場合に、いくら、どのような方法で算定されるのかをチェックします。
特に、エリア外利用になる場合は、交通費が高額になる可能性もあるので、後々のトラブルを避けるためにも、費用に関する説明は納得がいくまで受け、不明点を残さないようにすることが重要です。
事業所選びの確認リスト
- 自宅がサービス提供エリア内か
- 交通費の規定(無料か、有料か)
- 緊急時(24時間)の対応体制
- 事業所の専門性(リハビリ、精神科など)
交通費に関する確認事項(契約時)
| 確認項目 | 具体的な質問例 |
|---|---|
| 請求の有無 | 交通費は別途かかりますか? |
| 金額・算定方法 | エリア外ですが、交通費は毎回いくらですか? |
| 文書の記載 | 重要事項説明書のどこに記載がありますか? |
ケアマネジャーや医療機関との連携
どの訪問看護ステーションを選べばよいか分からない場合や、ご自身の状況(住所、病状)で利用できる事業所を探すのが難しい場合は、専門家に相談するのが一番の近道です。
すでに介護保険サービスを利用している方であれば、担当のケアマネジャーに相談してください。ケアマネジャーは地域の訪問看護ステーションの情報を熟知しており、利用者の希望や自宅の場所に適した事業所を紹介してくれます。
また、病院を退院して在宅療養に移行する場合は、病院の医療ソーシャルワーカーや退院調整看護師が、地域の事業所との調整を行ってくれることが一般的です。主治医と連携が取れている事業所を紹介してもらえることもあります。
訪問看護の距離制限に関するよくある質問
- 法律で訪問距離に決まりはありますか?
-
法律で「半径〇km以内」といった一律の距離制限は定められていません。
ただし、各訪問看護ステーションが運営規程で「通常の事業の実施地域(サービス提供エリア)」を定めており、これが実質的な訪問範囲の目安となります。
- 自宅がサービス提供エリアの境界線ギリギリです。利用できますか?
-
エリアの境界付近にお住まいの場合、多くの事業所が柔軟に対応してくれます。
行政区分上はエリア外でも、事業所からの実際の移動時間が短ければ問題ないと判断されることが多いため、まずは希望する訪問看護ステーションに直接電話などで相談してみることをお勧めします。
- エリア外ですが、どうしても利用したい事業所があります。
-
事業所が訪問可能と判断すれば、エリア外でも利用できることがあります。
ただし、その場合、通常の利用料金とは別に、事業所から自宅までの実費の交通費(ガソリン代や高速代など)を請求されることが一般的です。まずはその事業所に、エリア外だが訪問してもらえないか相談してください。
- 訪問看護の交通費は、毎回必ずかかるのですか?
-
サービス提供エリア内であれば交通費は無料(基本料金に含む)としている事業所が多いですが、事業所の方針によっては、エリア内でも一定額を請求する場合や、エリア外の場合のみ実費を請求するなど様々です。
契約前の重要事項説明書で必ず確認してください。
以上
参考文献
Ohashi K, Sato M, Fujiwara K, Tanikawa T, Morii Y, Ogasawara K. Spatial accessibility of home visiting nursing: An exploratory ecological study. Health Science Reports. 2024 Sep;7(9):e70078.
Kashiwagi M, Tamiya N, Sato M, Yano E. Factors associated with the use of home-visit nursing services covered by the long-term care insurance in rural Japan: a cross-sectional study. BMC geriatrics. 2013 Jan 2;13(1):1.
Fukui S, Yamamoto-Mitani N, Fujita J. Five types of home-visit nursing agencies in Japan based on characteristics of service delivery: cluster analysis of three nationwide surveys. BMC health services research. 2014 Dec 20;14(1):644.
Sakano T, Anzai T, Takahashi K, Fukui S. Impact of home‐visit nursing service use on costs in the last 3 months of life among older adults: A retrospective cohort study. Journal of Nursing Scholarship. 2024 Jan;56(1):191-201.
Setoya N, Aoki Y, Fukushima K, Sakaki M, Kido Y, Takasuna H, Kusachi H, Hirahara Y, Katayama S, Tachimori H, Funakoshi A. Future perspective of psychiatric home-visit nursing provided by nursing stations in Japan. Global health & medicine. 2023 Jun 30;5(3):128-35.
Iwasaki T, Yamamoto-Mitani N, Sato K, Yumoto Y, Noguchi-Watanabe M, Ogata Y. A purposeful yet nonimposing approach: how Japanese home care nurses establish relationships with older clients and their families. Journal of family Nursing. 2017 Nov;23(4):534-61.
Oda Y, Katsuki NE, Tago M, Hirata R, Kojiro O, Nishiyama M, Oda M, Yamashita SI. Effects of Caregiver’s Gender or Distance Between Caregiver and Patient’s Home on Home Discharge from Hospital in 285 Patients Aged≥ 75 Years in Japan. Medical Science Monitor: International Medical Journal of Experimental and Clinical Research. 2023 Jan 24;29:e939202-1.
Saito Y, Asakura T, Takashi K, Umazume T, Watari H, Tamakoshi A. Relationship between out‐of‐facility deliveries and distance and travel time to delivery facilities in Hokkaido, Japan: An ecological study. Journal of Obstetrics and Gynaecology Research. 2023 Mar;49(3):930-7.
Nakai H, Nakai Y, Horiike R, Itatani T. Evaluation of Spatial Accessibility of Visiting Nursing Stations in Kochi Prefecture. Journal of Japan Academy of Nursing Science. 2023 Jan 1;43.
Nakagawa Y, Kato H, Iwamoto T. A qualitative study on the current status and problems of pharmacists in home healthcare from the viewpoint of care managers in medically underpopulated areas in Japan. Journal of Pharmaceutical Health Care and Sciences. 2024 Nov 8;10(1):71.