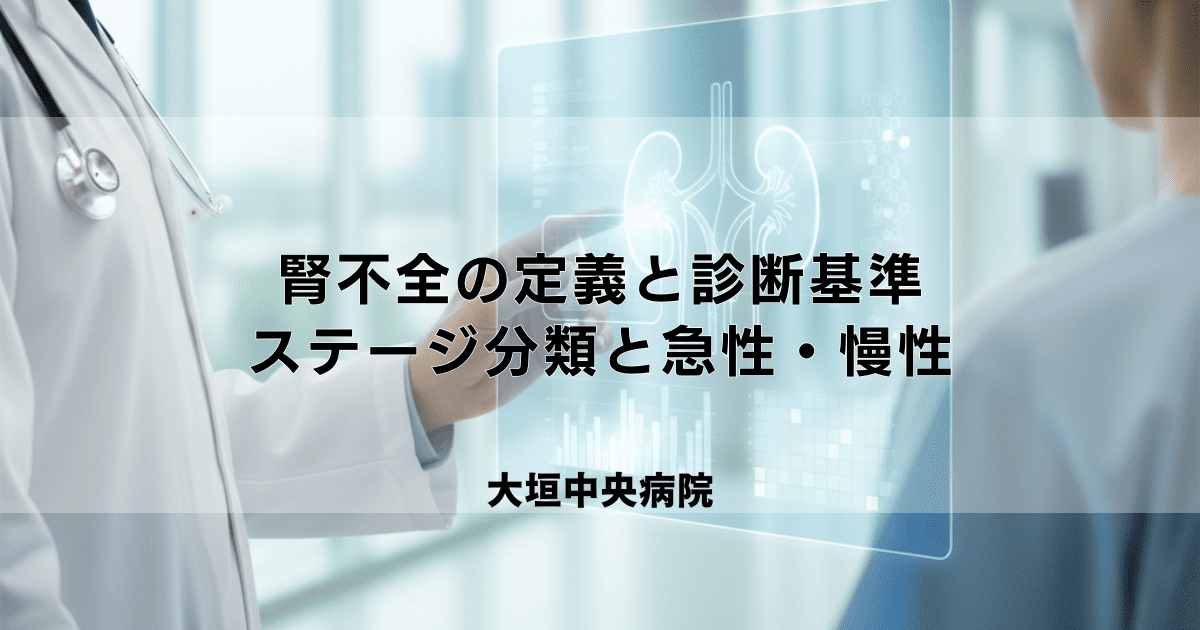腎臓は、体内で血液をろ過し、老廃物や余分な水分を尿として排出する重要な臓器で、腎臓の機能が何らかの理由で低下し、体内のバランスを正常に保てなくなった状態を腎不全と呼びます。
腎不全には、急激に機能が低下するタイプと、ゆっくりと時間をかけて低下するタイプがあります。
この記事では、腎不全の基本的な定義、診断に用いられる基準、そして腎不全の分類について、詳しく解説していきます。
腎不全とは何か?基本的な定義を理解する
腎不全という言葉を聞くと、すぐに透析をイメージするかもしれませんが、実際には腎臓の機能が低下し始めた初期の段階から、機能がほとんど失われた末期の状態までを含む広い概念です。
腎臓の主な働きと重要性
腎臓は背中側の腰骨の上に左右一対ある、そら豆のような形をした臓器で、一つが握りこぶし程度の大きさですが、生命維持に欠かせない多くの役割を担っています。最もよく知られているのは、血液をろ過して尿を作ることです。
体内で不要になった老廃物や、摂取しすぎた塩分・水分を尿として体の外に排出し、体内の水分量や電解質(ナトリウム、カリウム、カルシウムなど)のバランスを一定に保っています。
それだけでなく、血圧を調整するホルモンや、赤血球を作るのを助けるホルモンを分泌したり、ビタミンDを活性化させて骨を丈夫に保つ働きもしています。
腎臓が担う主要な役割
| 役割 | 具体的な内容 | 体が受ける恩恵 |
|---|---|---|
| 老廃物の排出 | 血液中の不要な物質(尿素窒素など)を尿として排出 | 体内に毒素が溜まるのを防ぐ |
| 水分・電解質の調節 | 体内の水分量や塩分、カリウムなどのバランスを維持 | むくみの防止、血圧の安定 |
| ホルモンの分泌 | 血圧調整(レニン)、造血(エリスロポエチン) | 血圧のコントロール、貧血の予防 |
| ビタミンDの活性化 | 食事から摂取したビタミンDを活性型に変える | 骨の健康維持 |
腎不全の定義とは
腎不全の定義とは、簡単に言えば「腎臓の働きが正常でなくなった状態」で、腎臓の機能が正常時の30%未満にまで低下した状態を指すことが多いです。
ただし、30%という数字はあくまで一つの目安であり、実際にはもっと早い段階から腎機能の低下は始まっています。腎臓は非常に予備能力が高い臓器で、機能が半分程度に低下しても自覚症状がほとんど現れないのです。
症状が出た時にはすでに腎不全がかなり進行しているケースも少なくありません。
腎不全の定義は、単に機能が低下した状態を指すだけでなく、それによって体内の水分や老廃物の調節ができなくなり、さまざまな異常(むくみ、高血圧、貧血、電解質異常など)が現れ始めた状態も含む、幅広い意味で使われます。
腎機能が低下するとどうなるか
腎臓の機能が低下すると、まず、老廃物や余分な水分を排泄する力が弱まるため、体に不要なものが溜まり始めます。
初期の段階では自覚症状はほとんどありませんが、進行すると、朝起きた時にまぶたが腫れぼったい、足がむくむ、といった症状が現れることがあり、これは、水分や塩分が体外にうまく排出されずに溜まってしまうためです。
さらに進行すると、老廃物が体に溜まることで尿毒症と呼ばれる状態になり、倦怠感、食欲不振、吐き気、息苦しさ、かゆみなど、全身にさまざまな症状が現れます。
また、血圧を調節するホルモンのバランスが崩れて高血圧になったり、造血ホルモンが不足して貧血になったり、骨がもろくなったりもします。
症状はゆっくりと現れるため、体調の変化に気づきにくいことも、腎機能低下の発見を遅らせる一因です。
急性腎不全と慢性腎不全の違い
腎不全は、腎機能が低下するスピードによって急性腎不全と慢性腎不全の二つに大きく分類され、原因や経過、回復の可能性も異なります。
急性腎不全(AKI)の特徴と原因
急性腎不全は、英語でAcute Kidney Injury (AKI)と呼ばれ、文字通り急激に腎機能が悪化する状態です。数時間から数日の間に、急に尿の量が減ったり、血液検査で腎機能を示す数値(クレアチニンなど)が急上昇したりします。
原因としては、腎臓そのものに問題がある場合だけでなく、腎臓への血流が急に減ったり、尿の通り道が詰まったりすることでも起こります。
脱水症、大出血、心不全、重い感染症(敗血症)などで腎臓に流れる血液が不足すると、腎臓はうまく働けなくなります(腎前性)。
また、薬剤や造影剤による腎臓の障害、急速進行性糸球体腎炎など腎臓自体の病気(腎性)、尿管結石や前立腺肥大症などで尿の流れがせき止められること(腎後性)も原因です。
急性腎不全(AKI)の主な原因分類
- 腎前性(腎臓への血流低下)
- 腎性(腎臓自体の障害)
- 腎後性(尿路の閉塞)
慢性腎不全(CKD)の特徴と原因
慢性腎不全は、英語でChronic Kidney Disease (CKD)と呼ばれ、数ヶ月から数年という長い時間をかけて、ゆっくりと腎機能が低下していく状態で、初期の段階ではほとんど自覚症状がありません。
健康診断などで尿タンパクや血清クレアチニン値の異常を指摘されて初めて気づくことが多い病気です。
慢性腎不全の最も多い原因は、糖尿病による糖尿病性腎症や、高血圧による腎硬化症、腎臓の糸球体に慢性的な炎症が起こる慢性糸球体腎炎です。
病気が長期間続くことで、腎臓の組織が少しずつ壊れて硬くなり(線維化)、ろ過機能が徐々に失われていきます。
一度失われた腎機能は、残念ながら元の状態に戻すことは難しいため、慢性腎不全では、いかに腎機能の低下スピードを緩やかにし、現状の機能を長く維持するかが重要です。
急性と慢性の経過と回復の見込み
急性腎不全は、発症の原因が一時的なものであれば、原因を取り除くことで腎機能が大きく回復する可能性があり、脱水が原因であれば水分補給を、薬剤が原因であればその薬剤を中止することで、腎臓は再び働き始めることができます。
しかし、対応が遅れたり、腎臓へのダメージが大きすぎたりすると、機能が完全には戻らず、慢性腎不全に移行することもあります。
慢性腎不全は、長期間かけて腎臓の組織が壊れてしまった結果であり、原則として失われた機能が回復することはありません。慢性腎不全の対応の目的は、機能の回復ではなく、残された腎機能をできるだけ長く保つことにあります。
食事療法や薬物療法によって進行を遅らせ、末期腎不全(透析が必要な状態)に至るまでの時間を稼ぐことが中心です。
急性腎不全と慢性腎不全の主な違い
| 項目 | 急性腎不全 (AKI) | 慢性腎不全 (CKD) |
|---|---|---|
| 発症スピード | 急激(数時間〜数日) | 緩徐(数ヶ月〜数年) |
| 自覚症状 | 尿量減少、むくみ、倦怠感などが急に出現 | 初期はほとんど無症状 |
| 回復の可能性 | 原因の除去により回復する可能性がある | 失われた機能の回復は困難 |
腎不全の診断基準とは?
腎不全、特に慢性腎臓病(CKD)は、特定の検査結果に基づいて診断します。ここでは、腎不全の診断に用いられる主要な検査と、数値の意味について解説します。
診断に用いられる主要な検査
血液検査では、腎臓が老廃物をどれくらい処理できているかを調べ、尿検査では、腎臓が壊れていないか、体に必要なたんぱく質などが漏れ出ていないかを調べます。
健康診断や人間ドックの基本的な項目に含まれていることが多く、腎機能低下の早期発見に役立ちます。
このほか、必要に応じて腎臓の形や大きさを調べる画像検査(超音波検査やCT検査)や、腎臓の組織を直接調べる腎生検を行うこともあります。
腎機能評価のための主な検査
| 検査の種類 | 主な検査項目 | 調べる内容 |
|---|---|---|
| 血液検査 | 血清クレアチニン (Cr)、eGFR | 腎臓の老廃物ろ過能力 |
| 尿検査 | 尿タンパク、尿潜血、尿アルブミン | 腎臓の障害(傷)の有無 |
| 画像検査 | 超音波(エコー)検査 | 腎臓の大きさ、形、結石や嚢胞の有無 |
血清クレアチニン値(Cr)とeGFR
腎不全の診断基準として最も重要なのが、血液検査による血清クレアチニン値(Cr)と、そこから計算されるeGFR(推算糸球体ろ過量)です。
クレアチニンは、筋肉を動かす時に作られる老廃物の一種で、通常は腎臓でろ過されて尿中に排出されますが、腎機能が低下すると、クレアチニンをうまく排出できなくなり、血液中に溜まっていきます。
血清クレアチニン値が高いほど、腎機能が低下していると考えられるものの、クレアチニン値は筋肉量に影響されるため、同じ腎機能でも筋肉質な人では高く、高齢者や女性では低く出る傾向があります。
そこで、クレアチニン値に年齢と性別を考慮して、より正確な腎機能の指標として計算したものがeGFRです。eGFRは、腎臓が1分間にどれくらいの血液をろ過できるか(ろ過量)を推算した値で、健康な人では90以上あります。
数値が低いほど腎機能が低下していることを示し、CKDの診断基準ではeGFRが60未満の状態が続く場合を腎機能低下と定義します。
尿検査の重要性(タンパク尿・血尿)
腎不全のもう一つの重要な診断基準が尿検査で、タンパク尿(アルブミン尿)の有無は、eGFRと並んでCKDの診断に欠かせません。
腎臓のろ過装置(糸球体)は、体に必要なタンパク質(特にアルブミン)が尿に漏れ出ないようにフィルターの役割を果たしていますが、腎臓に障害が起こるとフィルターが壊れ、尿の中にタンパク質が漏れ出てしまい、これがタンパク尿です。
タンパク尿が出ているということは、腎臓が傷ついているサインであり、さらに腎臓を傷つける原因にもなります。eGFRが正常でも、タンパク尿が陽性であれば腎障害あり、と診断されます。
また、尿に血液が混じる血尿(尿潜血)も、糸球体腎炎など、腎臓の炎症を示す重要なサインです。
尿検査でわかる腎臓のサイン
- タンパク尿(腎臓のフィルターの損傷)
- アルブミン尿(より早期の腎障害)
- 血尿(糸球体や尿路の出血・炎症)
画像診断(超音波検査など)の役割
血液検査や尿検査で腎機能の低下や腎障害が疑われた場合、原因を探るために画像診断を行い、最も一般的に行われるのが超音波(エコー)検査です。
慢性腎不全が進行すると、腎臓が小さく萎縮してくることが多いため、腎臓の大きさは急性と慢性を区別する手がかりにもなります。
また、腎臓に結石がないか、水が溜まっていないか(水腎症)、嚢胞(のうほう)や腫瘍がないかなどを確認するためにも重要です。必要に応じて、より詳細な情報を得るためにCT検査やMRI検査を行うこともあります。
慢性腎臓病(CKD)のステージ分類
慢性腎不全、すなわち慢性腎臓病(CKD)は、進行度合い(重症度)によっていくつかのステージに分類されます。ここでは、CKDの定義とステージ分類について詳しく見ていきましょう。
CKDとは何か
CKD(Chronic Kidney Disease:慢性腎臓病)は、腎臓の障害を示す所見(タンパク尿など)か、腎機能の低下(eGFR 60未満)が、3ヶ月以上続いている状態です。
初期段階では無症状であるにもかかわらず、放置すると末期腎不全(透析や腎移植が必要な状態)に進行するリスクがあります。
また、CKDは心筋梗塞や脳卒中といった心血管疾患の重大な危険因子でもあるため、CKDを早期に発見し、進行を抑えることが、腎臓だけでなく全身の健康を守るために大切です。
CKDのリスクを高める要因
- 高血圧
- 糖尿病
- 脂質異常症(コレステロールや中性脂肪が高い)
- 肥満
- 喫煙
- 家族に腎臓病の人がいる
GFR区分(G1~G5)によるステージ分類
CKDのステージ分類は、主に腎機能の指標であるeGFRの値に基づいて行われます。eGFRの値によって、ステージG1からG5までの5段階に分けられ、「G」はGFR(糸球体ろ過量)の頭文字です。
ステージG1はeGFRが90以上で正常または高値を意味しますが、タンパク尿など腎障害の所見がある場合にCKDと診断されます。ステージG2はeGFRが60~89で正常または軽度低下で、自覚症状はまずありません。
ステージG3a(45~59)およびG3b(30~44)は軽度~高度低下とされ、この段階から腎機能低下による合併症(貧血、骨の異常など)が少しずつ現れ始めます。
ステージG4はeGFRが15~29で高度低下となり、末期腎不全への進行が近づいている状態で、ステージG5はeGFRが15未満で、末期腎不全(ESKD)と呼ばれ、透析や腎移植などの腎代替療法の準備や導入が必要となる段階です。
CKDステージ分類(GFR区分)
| ステージ | eGFR (mL/min/1.73m²) | 腎機能の状態 |
|---|---|---|
| G1 | 90 以上 | 正常または高値 |
| G2 | 60 ~ 89 | 正常または軽度低下 |
| G3a | 45 ~ 59 | 軽度~中等度低下 |
| G3b | 30 ~ 44 | 中等度~高度低下 |
| G4 | 15 ~ 29 | 高度低下 |
| G5 | 15 未満 | 末期腎不全 (ESKD) |
アルブミン尿・タンパク尿区分(A1~A3)
CKDの重症度を判断する上で、eGFR(腎機能)とともにもう一つ重要なのが、尿検査によるアルブミン尿またはタンパク尿の程度(腎障害)です。
尿中に漏れ出るタンパク質の量が多いほど、腎臓の障害が強く、将来的に腎機能が低下するスピードが速いことがわかっています。
CKDの分類ではeGFRのG区分に加えて、アルブミン尿・タンパク尿のA区分(A1~A3)も組み合わせて評価します。
A1は正常または微量(アルブミン尿が30mg/gCr未満)、A2は微量アルブミン尿(30~299mg/gCr)、A3は顕性アルブミン尿(300mg/gCr以上)です。
CKDステージ分類(アルブミン尿・タンパク尿区分)
| 区分 | 尿アルブミン定量 (mg/gCr) | 状態 |
|---|---|---|
| A1 | 30 未満 | 正常または微量 |
| A2 | 30 ~ 299 | 微量アルブミン尿 |
| A3 | 300 以上 | 顕性アルブミン尿 |
CKD重症度分類(ヒートマップ)の見方
CKDの最終的な重症度は、GFR区分(G1~G5)とアルブミン尿区分(A1~A3)を組み合わせて評価します。
信号機の色(緑、黄、オレンジ、赤)を使ったヒートマップと呼ばれる図で示されることが多く、将来的な末期腎不全への進行リスクや心血管疾患の発症リスクが一目でわかるようになっています。
eGFRがG2(軽度低下)でも、アルブミン尿がA3(高度)であれば、リスクは「赤」となり、厳重な管理が必要です。
eGFRがG3a(軽度低下)でも、アルブミン尿がA1(正常)であれば、リスクは「黄」となり、中等度のリスクと判断されます。
腎不全の主な原因疾患
腎機能が慢性的に低下するCKD(慢性腎臓病)には、背景にさまざまな原因となる病気があります。ここでは、腎不全を引き起こす代表的な原因について解説します。
糖尿病性腎症
現在、日本で新たに透析を導入する患者さんの原因疾患として最も多いのが糖尿病性腎症です。糖尿病の合併症の一つで、長期間にわたって血糖値が高い状態が続くことにより、腎臓のろ過装置である糸球体がダメージを受けて発症します。
高血糖は、糸球体の血管を硬化させたり、フィルター機能を壊し、初期の段階では、まず微量アルブミン尿が出始め、この段階で血糖コントロールや血圧管理を徹底すれば、進行を遅らせたり、場合によっては改善させたりすることも可能です。
しかし、放置してタンパク尿が持続的に出るようになると、腎機能は徐々に低下し、やがて末期腎不全に至ります。
慢性糸球体腎炎(腎炎)
慢性糸球体腎炎は、以前は日本人の透析導入原因の第1位で、現在も糖尿病性腎症に次いで多い原因疾患です。腎臓の糸球体に慢性的な炎症が起こる病気の総称で、いくつかの種類があり、最も代表的なものがIgA腎症です。
IgA腎症は、免疫グロブリンAという免疫物質が糸球体に沈着することで炎症が起こり、タンパク尿や血尿が出ます。多くは若い世代で発症し、症状がないままゆっくりと進行し、数十年かけて腎不全に至ることがあります。
学校や職場の検尿でタンパク尿や血尿を指摘されたことがきっかけで見つかることも多いです。
腎硬化症(高血圧性)
腎硬化症は、長期間にわたる高血圧が原因で腎臓の血管が動脈硬化を起こし、腎機能が低下する病気です。
高血圧によって腎臓の細い動脈に常に高い圧力がかかると、血管が硬く、狭くなり、腎臓に流れる血液の量が減少し、糸球体が壊れてろ過機能が低下していきます。
腎硬化症は、高齢者に多く見られ、糖尿病性腎症や慢性糸球体腎炎に次いで、透析導入の原因として増加傾向にあります。腎硬化症の進行を防ぐためには、何よりも厳格な血圧コントロールが重要です。
腎不全の三大原因疾患
| 原因疾患 | 主な特徴 | 重要な管理ポイント |
|---|---|---|
| 糖尿病性腎症 | 高血糖による糸球体障害。微量アルブミン尿から始まる。 | 血糖コントロール、血圧管理 |
| 慢性糸球体腎炎 | IgA腎症など。免疫異常による糸球体の炎症。血尿・タンパク尿。 | 血圧管理、炎症を抑える対応 |
| 腎硬化症 | 高血圧による腎血管の動脈硬化。高齢者に多い。 | 厳格な血圧コントロール |
その他の原因(多発性嚢胞腎など)
上記の三大原因以外に代表的なものに、多発性嚢胞腎(たはつせいのうほうじん)があります。遺伝性の病気で、腎臓に嚢胞と呼ばれる水のたまった袋が多数でき、徐々に大きくなることで正常な腎臓の組織を圧迫し、腎機能を低下させます。
また、鎮痛薬などの薬剤の長期使用による薬剤性腎障害や、自己免疫の異常によって腎臓などが攻撃される膠原病(全身性エリテマトーデスなど)、尿路結石や前立腺肥大症などで尿の流れが悪い状態が長く続くことも、腎機能低下の原因です。
腎不全が進行した場合の症状
慢性腎不全(CKD)はサイレント・キラー(静かなる殺し屋」とも呼ばれ、初期の段階ではほとんど自覚症状がありませんが、腎機能の低下が一定のレベルを超えると、体にさまざまなサインが現れ始めます。
初期段階で見られる症状
CKDの初期(ステージG1~G2、あるいはG3aの一部)では、腎臓の予備能力が高いため、ほとんどの人は無症状で、この段階で気づくきっかけの多くは、健康診断の尿検査でタンパク尿や血尿を指摘されることです。
人によっては、夜間にトイレに起きる回数が増える(夜間頻尿)ことがあります。腎臓が尿を濃縮する力(尿濃縮力)が低下し、薄い尿をたくさん作ってしまうために起こりますが、加齢による変化と見過ごされがちです。
進行期に現れる症状(むくみ・倦怠感など)
腎機能がさらに低下し、ステージG3b~G4(eGFRが45未満)程度になると、腎臓の働きが追いつかなくなり、体に異常が現れ始め、最もわかりやすい症状の一つがむくみ(浮腫)です。
腎臓から塩分や水分を十分に排出できなくなり、皮下に水分が溜まることで起こり、朝起きた時にまぶたが腫れぼったい、指輪がきつい、靴下の跡がくっきり残る、足のすねを押すとへこんだまま戻らない、といった症状が出ます。
また、腎臓で作られる造血ホルモン(エリスロポエチン)の分泌が減るため、赤血球が作られなくなり腎性貧血が起こり、息切れがする、体がだるい、疲れやすい(倦怠感)、めまいがする、といった症状が現れます。
末期腎不全(尿毒症)の症状
ステージG5(eGFRが15未満)に至り、末期腎不全の状態になると、腎臓の機能が極度に低下し、老廃物や毒素が体内に蓄積した尿毒症と呼ばれる状態になり、全身に多様な症状が現れます。
消化器系では、食欲が全くなくなる、吐き気や嘔吐が続く、口の中がアンモニア臭い(尿臭)といった症状です。
神経系では、頭痛、集中力の低下、昼夜逆転、イライラする、といった精神症状や、手足のしびれ(末梢神経障害)が現れることもあり、皮膚には、老廃物が沈着することで、治りにくい強いかゆみが出ます。
さらに重篤になると、呼吸困難(心不全や肺水腫による)、けいれん、意識障害などを起こし、生命に危険が及ぶ状態となり、尿毒症症状が現れた場合は、透析療法や腎移植などの腎代替療法が必要です。
腎不全の進行度と主な自覚症状の目安
| CKDステージ | eGFR (mL/min/1.73m²) | 主な症状 |
|---|---|---|
| G1~G2 | 60 以上 | ほぼ無症状(検尿異常のみ) |
| G3 | 30 ~ 59 | 夜間頻尿、軽度の貧血、むくみ(G3b以降) |
| G4 | 15 ~ 29 | むくみ、倦怠感、息切れ(貧血)、食欲不振 |
| G5 | 15 未満 | 尿毒症症状(吐き気、かゆみ、呼吸困難など) |
腎機能低下が判明した後の対応
健康診断や病院での検査で腎機能の低下、CKD(慢性腎臓病)の疑いがあると指摘された場合、どう対応すればよいのでしょうか。
なぜ早期の対応が重要か
CKDの対応において、最も重要なのは早期発見・早期対応です。
慢性腎不全は、一度失われた腎機能を取り戻すことが困難な病気ですが、腎機能が低下し始める初期の段階(ステージG1~G3aなど)で発見し、適切な管理を行えば、腎機能が低下するスピードを大幅に遅らせることができます。
対応が早ければ早いほど、末期腎不全(透析)に至る時期を先に延ばしたり、生涯にわたって透析を必要としない状態を維持したりすることも可能です。
また、CKDは心筋梗塞や脳卒中のリスクを高めますが、早期から血圧やタンパク尿などを良好にコントロールすることで、心血管疾患を予防することにもつながります。
食事管理の基本的な考え方
CKDの進行を抑える上で、薬物療法と並んで柱となるのが食事管理です。腎機能が低下すると、体内の老廃物や塩分、カリウム、リンなどをうまく排出できなくなるため、食事から摂取する量を調整する必要があります。
特に重要なのが減塩で、塩分を摂りすぎると、体に水分が溜まってむくみや高血圧の原因となり、腎臓にさらに負担がかかります。1日の塩分摂取量を6g未満に抑えることが目標です。
また、腎機能が低下してくると(ステージG3b以降)、老廃物のもととなるタンパク質の摂取を制限することがあります。必要なエネルギーは炭水化物や脂質でしっかり確保しつつ、タンパク質の量を調整することが重要です。
さらに、カリウム(生野菜や果物に多い)やリン(加工食品や乳製品に多い)の制限が必要になる場合もあります。
食事管理で調整が必要な主な項目
- 塩分(高血圧・むくみ予防)
- タンパク質(老廃物の蓄積抑制)
- カリウム(高カリウム血症予防)
- リン(骨・血管の障害予防)
生活習慣の見直し(血圧管理など)
食事以外の生活習慣の見直しで、最も大切なのは血圧管理で、高血圧は腎硬化症の原因となるだけでなく、CKDを進行させる最大の要因の一つです。
家庭でも血圧を測定する習慣をつけ、医師から処方された降圧薬をきちんと服用し、目標血圧(130/80mmHg未満、タンパク尿陽性なら125/75mmHg未満を目指すことも)を維持します。
血糖コントロールも同様に重要で、特に糖尿病性腎症の場合は、血糖値の管理が腎機能の予後を大きく左右します。禁煙も必須です。喫煙は腎臓の血管を収縮させ、腎機能低下を加速させます。
適度な運動は血圧や血糖の改善に役立ちますが、腎機能が低下している場合は過度な運動は避け、医師に相談の上で行いましょう。
また、市販の鎮痛薬(非ステロイド性抗炎症薬:NSAIDs)の中には、腎機能に影響を与えるものがあるため、使用する際は注意が必要です。
腎不全の定義と診断基準に関するよくある質問
腎不全やCKDについて、患者さんやご家族から多く寄せられる質問にお答えします。
- 腎臓は一度悪くなると元に戻らないのですか?
-
慢性腎不全(CKD)の場合、一度壊れて機能しなくなった腎臓の組織(糸球体など)を元の状態に戻すことは、現在の医療では困難です。
CKDの対応の目的は、失われた機能を回復させることではなく、残された腎機能をできるだけ長く維持し、腎機能が低下するスピードを緩やかにすることにあります。
ただし、急性腎不全(AKI)の場合は、原因(脱水、薬剤、尿路閉塞など)を速やかに取り除くことで、腎機能が回復する可能性はあります。
- CKDステージは改善することがありますか?
-
CKDステージが良くなることは期待できません。CKDステージ分類は、腎機能が慢性的に低下した状態を示すものだからです。
ただし、急性腎不全の要素が加わって一時的にeGFRが低下していた場合、急性的な原因が解消されればeGFRが改善し、見かけ上ステージが良くなることはあります。
また、厳格な食事療法や血圧管理、原因疾患の対応によって、ステージの進行を長期間食い止める(現状維持)ことは十分に可能です。
- クレアチニン値が高いと必ず腎不全ですか?
-
必ずしもそうとは限りません。クレアチニン値は筋肉量の影響を受けるため、非常に筋肉質な人(ボディビルダーなど)では、腎機能が正常でも基準値より高くなることがあります。
また、検査前に激しい運動をしたり、肉類を大量に食べたりすると一時的に上昇することもあります。
重要なのは、クレアチニン値そのものよりも、年齢・性別を考慮したeGFRの値や、タンパク尿などの腎障害の所見があるかどうか、その状態が3ヶ月以上続いているかどうかです。
- 腎不全の診断は何科を受診すればよいですか?
-
健康診断などで腎機能の低下(eGFR低下)やタンパク尿を指摘された場合は、まずは腎臓内科の受診をお勧めします。
腎臓内科は、腎臓病全般の診断と管理を専門とする診療科で、腎臓病の原因を特定するための精密検査や、腎機能の低下を抑えるための食事指導、薬物療法などを専門的に行います。
以上
参考文献
Hasegawa T, Sakamaki K, Koiwa F, Akizawa T, Hishida A, CKD-JAC Study Investigators. Clinical prediction models for progression of chronic kidney disease to end-stage kidney failure under pre-dialysis nephrology care: results from the Chronic Kidney Disease Japan Cohort Study. Clinical and experimental nephrology. 2019 Feb 15;23(2):189-98.
Yamagata K, Yagisawa T, Nakai S, Nakayama M, Imai E, Hattori M, Iseki K, Akiba T. Prevalence and incidence of chronic kidney disease stage G5 in Japan. Clinical and experimental nephrology. 2015 Feb;19(1):54-64.
Usami T, Koyama K, Takeuchi O, Morozumi K, Kimura G. Regional variations in the incidence of end-stage renal failure in Japan. Jama. 2000 Nov 22;284(20):2622-4.
Tanaka K, Watanabe T, Takeuchi A, Ohashi Y, Nitta K, Akizawa T, Matsuo S, Imai E, Makino H, Hishida A, CKD-JAC Investigators. Cardiovascular events and death in Japanese patients with chronic kidney disease. Kidney international. 2017 Jan 1;91(1):227-34.
Hirano K, Kobayashi D, Kohtani N, Uemura Y, Ohashi Y, Komatsu Y, Yanagita M, Hishida A. Optimal follow-up intervals for different stages of chronic kidney disease: a prospective observational study. Clinical and experimental nephrology. 2019 May 1;23(5):613-20.
Travers K, Martin A, Khankhel Z, Boye KS, Lee LJ. Burden and management of chronic kidney disease in Japan: systematic review of the literature. International journal of nephrology and renovascular disease. 2013 Jan 3:1-3.
Kimura K, Hosoya T, Uchida S, Inaba M, Makino H, Maruyama S, Ito S, Yamamoto T, Tomino Y, Ohno I, Shibagaki Y. Febuxostat therapy for patients with stage 3 CKD and asymptomatic hyperuricemia: a randomized trial. American Journal of Kidney Diseases. 2018 Dec 1;72(6):798-810.
Bauer C, Melamed ML, Hostetter TH. Staging of chronic kidney disease: time for a course correction. Journal of the American Society of Nephrology. 2008 May 1;19(5):844-6.
Tangri N, Stevens LA, Griffith J, Tighiouart H, Djurdjev O, Naimark D, Levin A, Levey AS. A predictive model for progression of chronic kidney disease to kidney failure. Jama. 2011 Apr 20;305(15):1553-9.
Castner D. Understanding the stages of chronic kidney disease. Nursing2024. 2010 May 1;40(5):24-31.