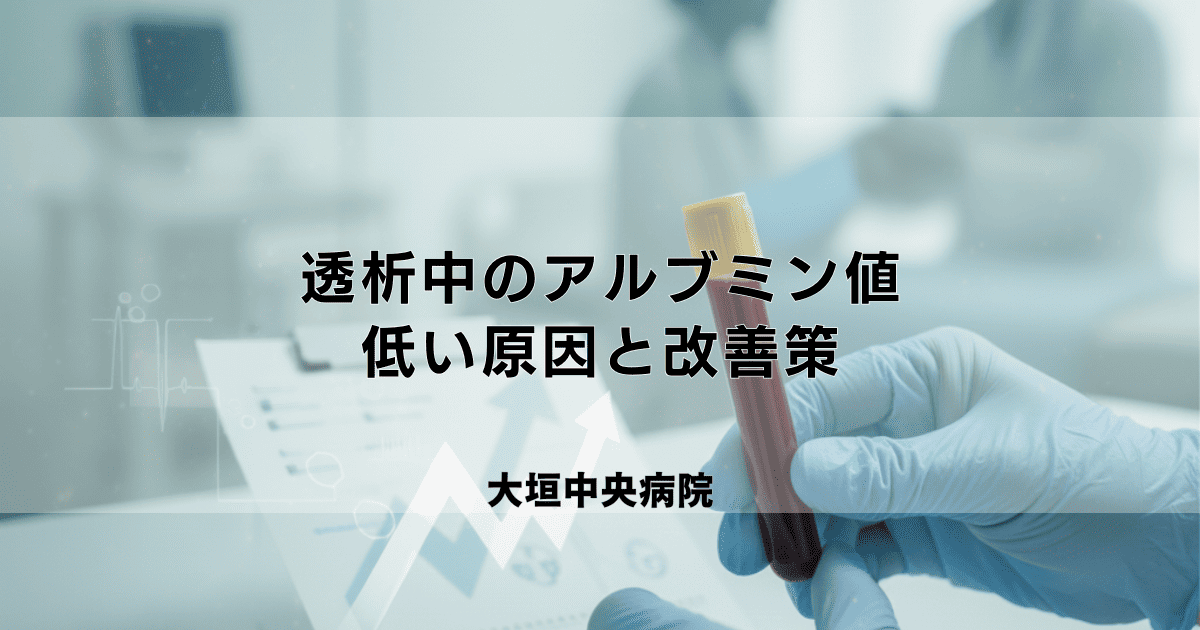透析治療を受けている方にとって、ご自身の栄養状態を把握することは、治療を続けながら日々の生活を元気に送る上で非常に重要で、栄養状態を知るための大切な指標の一つが、血液検査で測定するアルブミン値です。
この値が低いと、体の抵抗力が落ちたり、むくみが出やすくなったりするなど、様々な影響が出ることがあります。
なぜアルブミン値が透析患者さんにとってこれほど重要視されるのか、低い場合の主な原因は何か、日々の生活、特に栄養管理でどのように改善していけばよいのかを、詳しく解説します。
透析患者にとってのアルブミン値とは?
定期的な血液検査で目にするアルブミンは、栄養状態を反映する重要なバロメーターで、透析患者さんの健康維持において、アルブミン値の管理は、透析効率やリン・カリウムの管理と並んで、欠かすことのできない重要な柱の一つです。
アルブミンとは何か
アルブミンは、血液中に最も多く含まれるたんぱく質の一種で、血液に含まれる総たんぱく質のうち、約60%以上を占めています。
主に肝臓で、食事から摂取したたんぱく質(アミノ酸)を原料にして作られ、血液の流れに乗って体中を巡っていて、体内で非常に多くの役割を担っており、生命活動を支える縁の下の力持ちのような存在です。
アルブミンの主な働
- 栄養素や薬の運搬
- 血液の浸透圧の維持
- 体液のバランス調整
カルシウムや亜鉛といったミネラル、脂肪酸、さらには処方された薬の成分と結合し、必要な組織まで運ぶ「運び屋」の役割を果たします。
また、血管内に水分を引きつけておく力(膠質浸透圧)を生み出し、血液中の水分量を適切に保ち、水分が血管の外に漏れ出るのを防ぎ、全身のむくみを抑制しているのです。
なぜ透析患者で重要視するのか
透析治療を受けている方の場合、腎臓の機能が低下しているため、体内の老廃物の蓄積や体液のバランスが崩れやすくなっていて、アルブミン値は全身の健康状態や栄養状態を客観的に示す指標として特に注目されます。
アルブミン値が良好に保たれていることは、体に必要な栄養素、特にたんぱく質が充足していることを示します。
栄養状態が良いと、体力の維持、感染症への抵抗力向上、そして週に数回の透析治療そのものへの耐性(治療中の血圧低下の予防など)にもつながります。
アルブミン値が低い状態が続くと、心血管疾患(心不全や動脈硬化など)のリスクや、入院の頻度が高まるなど、様々な合併症のリスクが高いです。
栄養状態を示す指標としての役割
アルブミンは体内で作られるたんぱく質であり、その主な材料は食事から摂取するたんぱく質です。
食事からのたんぱく質摂取が不足したり、摂取したたんぱく質が体内でうまく利用できなかったりすると、アルブミンの産生量が減少し、血液中のアルブミン値が低下します。
アルブミン値は透析患者さんのたんぱく質の摂取状況や、体内の栄養状態を評価するための信頼できる指標として広く用いられています。ただし、栄養状態の評価はアルブミン値だけで行うわけではありません。
体重(特にドライウェイト)の変化、毎日の食事摂取量、筋肉量の指標となる検査(クレアチニン値や体組成測定など)と合わせて総合的に判断します。
血清アルブミン値と栄養評価
| 評価項目 | 主な役割 | 関連する栄養素 |
|---|---|---|
| 血清アルブミン値 | 長期的なたんぱく質の栄養状態を反映 | たんぱく質、エネルギー |
| 体重変化 | 短期間の栄養状態や体液量の変動を反映 | エネルギー、水分 |
| 食事摂取量 | 日々の栄養摂取状況を直接評価 | 全般 |
アルブミン値の基準と見方
検査結果で示されるアルブミン値がどのような意味を持つのか、どのくらいの値を目標にすればよいのかを知ることは、ご自身の健康管理を進める第一歩です。
透析患者における目標値
透析患者のアルブミン値は、健康な人とは異なる管理目標が設定されていて、一般的に、生命予後や合併症予防の観点から、維持すべき望ましい値が示されています。
日本透析医学会の発行するガイドラインなどでは、透析患者さん(特に血液透析)の血清アルブミン値は、3.5g/dL以上を維持することが望ましいとされています。
しかし、より良好な状態を目指す観点から、施設によっては、より高い目標値(例 3.8g/dLや4.0g/dL以上)を設定している場合もあり、これは、患者さん個々の年齢、合併症の有無、活動量などを考慮して、個別化された目標が設定されるためです。
アルブミン値の一般的な目安(透析患者)
| 数値 (g/dL) | 状態の目安 | 考えられる対応 |
|---|---|---|
| 4.0 以上 | 非常に良好 | 現在の良好な栄養管理を継続 |
| 3.5 ~ 3.9 | 維持目標範囲 | 食事内容の維持・見直しを検討 |
| 3.5 未満 | 栄養状態低下の懸念 | 積極的な栄養改善(食事指導など)が必要 |
検査結果の読み解き方
血液検査の結果表では、アルブミン(Alb)という項目で数値が示され、単位は通常 g/dL(グラム・パー・デシリットル)です。
ただし注意点があり、アルブミン値は栄養状態だけで変動するわけではなく、体内の炎症の有無や、体液量(透析間の体重増加)によっても数値が変わることがあります。
体に水分が多く溜まっている(ドライウェイトから体重が増えすぎている)状態で採血すると、血液が薄まるため、実際の栄養状態よりもアルブミン値が低く出ることがあり、脱水気味だと高く出ることがあります。
このため、採血のタイミング(透析前か後か)や、その時の体重増加量も考慮して数値を評価することが必要です。
定期的な測定の大切さ
アルブミンは体内で作られてから分解されるまでの期間(半減期)が約3週間と比較的長いため、昨日今日の短期間の食事内容の変化では数値は大きく変動せず、数週間から数ヶ月単位の長期的な栄養状態を反映します。
月に1回など、定期的にアルブミン値を測定し、推移を見守ることが重要で、単発の数値に一喜一憂するのではなく、数値が徐々に低下傾向にあるのか、あるいは維持・上昇傾向にあるのか、トレンドを把握することが大切です。
低下傾向が続く場合は、栄養不足が慢性的に続いている可能性があり、早めに原因を探り、対策を講じる必要があります。
アルブミン値が低い主な原因
目標値よりもアルブミン値が低くなってしまう背景には、いくつかの要因が考えられ、複数の要因が絡み合っていることも少なくありません。
食事からのたんぱく質不足
最も直接的で多い原因は、食事から摂取するたんぱく質の量が不足していることです。アルブミンは肝臓でたんぱく質(アミノ酸)を原料にして作られているので、原料が足りなければ、当然ながら産生量は減ってしまいます。
透析患者さんは、以前は腎臓の負担を減らすためにたんぱく質制限を行っていたことが多いですが、透析導入後は十分なたんぱく質を摂取することが重要です。
しかし、透析治療による体調の変化、味覚の変化、老廃物の蓄積による食欲不振や、リン・カリウムの制限を意識しすぎるあまり、たんぱく質源となる食品(肉、魚、卵、大豆製品など)の摂取が不十分になっていないか、見直す必要があります。
栄養摂取不足のサイン
- 食欲がない日が続く
- 食事の量が全体的に減った
- 体重(ドライウェイト)が減少傾向にある
透析によるアルブミンの損失
透析治療そのものによっても、アルブミンは体外へ失われてしまい、血液透析(HD)では、透析膜(ダイアライザ)を通して老廃物を除去する際に、アルブミンも一部が漏れ出てしまいます。
高性能な膜(HDFなど)を使用すると、老廃物の除去効率は上がりますが、アルブミンの損失も増える傾向にあると言われています。
また、腹膜透析(PD)の場合も、透析液を交換する際に腹膜を通してアルブミンが失われ、PDではこれが毎日続くため、1日あたりの損失量はHDより多いです。
透析方法とアルブミン損失
| 透析方法 | 主な損失経路 | 損失の目安 |
|---|---|---|
| 血液透析 (HD) | 透析膜からの漏出 | 1回あたり 数g程度 |
| 腹膜透析 (PD) | 腹膜からの透析液への漏出 | 1日あたり 5~10g程度 |
炎症(CRPとの関係)
栄養状態が悪くないにもかかわらずアルブミン値が低い場合、体内のどこかに炎症が隠れている可能性があり、体内で炎症が起こると、体は炎症を抑えるためのたんぱく質(CRPなどの急性期たんぱく)の産生を優先します(急性期反応)。
この状態になると、肝臓はアルブミンの産生を後回し(抑制)にしてしまうため、血液中のアルブミン値が低下します。
血液検査の CRP(C反応性たんぱく)という項目が、炎症の有無を示す代表的な指標となり、CRPが高い状態(炎症がある状態)では、いくら食事を頑張ってもアルブミン値が上がりにくいです。
シャントの感染や、カテーテルの出口部感染、歯周病、風邪や肺炎、あるいは腸内環境の悪化による微細な炎症など、原因を特定し、治療することが先決となる場合もあります。
その他の要因(年齢・合併症など)
加齢に伴い、食事量が減ったり、筋肉量が落ちたりすること(サルコペニア、さらには虚弱状態であるフレイル)も、アルブミン値の低下と深く関連します。
また、肝臓の機能が低下している場合(肝硬変、肝炎など)は、アルブミンの産生工場である肝臓そのものの能力が落ちてしまいます。
さらに、消化管からのたんぱく質の吸収が悪い場合(慢性的な下痢や便秘など)や、一部の薬剤の影響、気分の落ち込みによる食欲低下なども考えられます。
低アルブミン値が体に及ぼす影響
低アルブミン血症が続くと、体には様々な不調が現れやすくなります。栄養状態の悪化が起こす影響について見ていきましょう。
栄養状態の悪化と体力低下
アルブミン値の低下は、体内のたんぱく質が不足しているサインで、たんぱく質は筋肉や臓器を構成する主要な成分であり、不足すると筋肉量が減少しやすくなります。
この状態はPEM(たんぱく質・エネルギー欠乏状態)と呼ばれることもあり、透析患者にとって避けたい状態の一つです。
筋肉が減ると、基礎代謝が落ち、体を動かすことが億劫になる、立ち上がりや歩行が不安定になるなど、体力や活動量の低下に直結します。活動量が減ると、さらに食欲がわかなくなり、たんぱく質摂取が減る…という悪循環に陥りやすくなります。
むくみ(浮腫)の発生
アルブミンの重要な働きのひとつに、血液の浸透圧を維持し、血管内に水分を保持する役割があります。
血液中のアルブミン濃度が低くなると、この力が弱まり、水分が血管の外(細胞と細胞の間)に漏れ出しやすくなり、漏れ出た水分が、むくみ(浮腫)として現れ、足のすねや甲、顔やまぶたなどに出やすいのが特徴です。
むくみは単に不快なだけでなく、皮膚が弱くなって傷ができやすくなったり、心臓への負担が増えたりする原因にもなります。
アルブミン値低下による主な影響
| 影響 | 具体的な症状・状態 | 理由 |
|---|---|---|
| むくみ(浮腫) | 足、顔、全身のむくみ、胸水 | 血液の浸透圧が低下し、水分が血管外に漏れ出すため |
| 体力・筋力低下 | 疲れやすい、筋力が落ちる(サルコペニア) | 筋肉の材料となるたんぱく質が不足するため |
| 免疫力低下 | 感染症にかかりやすく、重症化しやすい | 免疫細胞や抗体の材料となるたんぱく質が不足するため |
免疫力の低下と感染症リスク
たんぱく質は、細菌やウイルスと戦う免疫細胞や抗体(免疫グロブリンなど)を作るための重要な材料でもあり、栄養状態が悪化し、アルブミン値が低い状態では、免疫機能も低下しがちです。
風邪や肺炎、シャント感染、腹膜炎(PDの場合)など、様々な感染症にかかりやすくなったり、かかった場合に治りにくくなったり、さらには重症化しやすくなったりするリスクが高まります。
生命予後との関連性
多くの研究により、透析患者さんの血清アルブミン値は、長期的な生命予後(病気の経過や結末の見通し)と強い関連があることが示されています。
アルブミン値が低い患者さんは、高い患者さんと比較して、入院のリスクや、特に心不全や動脈硬化といった心血管疾患による死亡率が高い傾向にあることが報告されています。
アルブミン値を改善する栄養管理の基本
アルブミン値を改善し、良好な栄養状態を維持するためには、日々の栄養管理が鍵となり、透析患者さんの場合、たんぱく質とエネルギーの摂取が二つの大きな柱です。
十分なたんぱく質を摂取する
アルブミンの材料であるたんぱく質をしっかり摂ることが、最も基本的な対策で、透析治療によって失われるたんぱく質を補い、さらに体が必要とする量を確保する必要があります。
透析導入前はたんぱく質制限があった方も、透析開始後は適切な量のたんぱく質摂取へと切り替える意識が大切です。ただし、やみくもに増やせばよいわけではありません。
たんぱく質を多く摂れば、リンや老廃物(尿素窒素)の産生も増えるため、リンの摂取量とのバランスや、十分な透析が行われているかが大事で、どのような食品から、どのくらい摂るかが重要です。
エネルギー(カロリー)を確保する
たんぱく質と同じくらい、あるいはそれ以上に重要なのが、十分なエネルギー(カロリー)を摂取することです。
もしエネルギーが不足していると、体は不足分を補うために、食事から摂ったたんぱく質や、ご自身の筋肉を分解してエネルギー源として使おうとします(糖新生)。
これでは、せっかく摂ったたんぱく質がアルブミンの材料や筋肉の維持に使われず、効率が悪くなってしまいます。
十分なエネルギーを確保することで、摂取したたんぱく質を効率よくアルブミンの合成や体の修復に使えるようになり、これを「たんぱく質の節約効果」と呼びます。
アルブミン値が低い方は、まずエネルギー摂取量が足りているかを見直すことが非常に重要です。
透析患者の栄養摂取の目安(体重60kgの場合)
| 栄養素 | 1日の推奨摂取量目安 | 体重1kgあたり |
|---|---|---|
| エネルギー | 1800~2100 kcal | 30~35 kcal |
| たんぱく質 | 60~72 g | 1.0~1.2 g |
(注:必要な量は年齢、性別、活動量、透析方法によって異なります。必ず主治医や管理栄養士の指導に従ってください。)
バランスの良い食事を心がける
たんぱく質とエネルギーを基本としつつも、食事全体のバランスが重要です。ビタミンやミネラルなども、体の調子を整え、たんぱく質の代謝を助ける働きがあります。
透析患者さんは水分やカリウム、リンなどの制限があるため、その範囲内で、主食、主菜、副菜をそろえることを目指しましょう。制限がある中でのバランスは難しく感じられるかもしれませんが、工夫次第で食事の満足度を保つことは可能です。
- 主食(ごはん、パン、麺)でエネルギーをしっかり確保
- 主菜(肉、魚、卵、大豆製品)で良質なたんぱく質を確保
- 副菜(野菜、きのこ、海藻)でビタミン・ミネラルを補給
野菜類はカリウムを多く含むため、細かく切ってから水にさらしたり、茹でこぼしたりする下ごしらえも、引き続き大切です。
たんぱく質を上手に摂取する食事の工夫
アルブミン値を上げるためには、たんぱく質の摂取が欠かせませんが、透析患者さんにとってはリンやカリウムの管理も同時に必要です。
たんぱく質を多く含む食品の選び方
たんぱく質源となる食品は、主に肉類、魚介類、卵、大豆製品、乳製品で、毎食の主菜(メインのおかず)として取り入れることが基本です。
特に、体内で作ることができない必須アミノ酸をバランスよく含む、アミノ酸スコアの高い「良質なたんぱく質」を含む食品を選ぶことが推奨されます。
良質なたんぱく質を含む主な食品
- 肉類(鶏むね肉、ささみ、豚ヒレ肉、赤身肉など)
- 魚類(アジ、サバなどの青魚、タラ、カレイなどの白身魚)
- 卵(鶏卵)
- 大豆製品(豆腐、納豆、厚揚げなど)
1日の摂取目安量
1日に必要なたんぱく質量は、標準体重(ドライウェイト)1kgあたり約1.0~1.2gが目安で、体重60kgの方なら、1日に60~72gのたんぱく質が必要で、3食で分けると1食あたり20~24gです。
食品に含まれるたんぱく質量を把握するのは難しいかもしれませんが、「卵1個(約6g)と納豆1パック(約7g)とごはん(約4g)」で約17g、「鶏もも肉80g(唐揚げ2~3個分)」で約14g、「焼きサバ一切れ(80g)」で約17g程度になります。
毎食、肉・魚・卵・大豆製品のいずれかを、ご自身の手のひらサイズ程度食べることを意識すると良いでしょう。
リンやカリウムを考慮した食品選択
たんぱく質を多く含む食品は、同時にリンも多く含む傾向があるので、リンの摂取を抑えながらたんぱく質を確保するには、食品選びと調理法に工夫が必要です。
最も重要な工夫の一つが、加工食品(ハム、ソーセージ、練り物、インスタント食品、レトルト食品など)を避けることで、リン酸塩として食品添加物が使われていることが多く、「無機リン」は体への吸収率が非常に高くなっています。
肉や魚などに含まれる「有機リン」は吸収率が比較的低く、同じたんぱく質を摂るなら、加工品ではなく、生の食材から調理したものを食べることが、リン管理の大きなポイントです。
たんぱく質量とリン含有量の比較(100gあたり)
| 食品名 | たんぱく質 (g) | リン (mg) |
|---|---|---|
| 鶏むね肉(皮なし) | 23.3 | 200 |
| プロセスチーズ | 22.7 | 730 |
| 木綿豆腐 | 7.0 | 82 |
(注:数値は目安です。食品データベースに基づきます。チーズはリンが多い代表例です。)
エネルギー摂取を増やすためのポイント
アルブミン値を改善するためには、たんぱく質だけでなく、十分なエネルギー摂取が不可欠です。エネルギーが不足すると、たんぱく質が効率よく利用されません。
エネルギー源となる食品(脂質・炭水化物)
主なエネルギー源となるのは炭水化物(糖質)と脂質で、たんぱく質もエネルギー源になりますが、主に体を作る材料として使いたいため、エネルギーは炭水化物と脂質からしっかり摂ることが理想です。
炭水化物は、ごはん、パン、麺類などの主食に多く含まれ、脂質は、植物油(サラダ油、オリーブオイルなど)や動物性脂肪(バター、肉の脂身など)、マヨネーズなどに多く含まれます。
脂質は炭水化物やたんぱく質の2倍以上のエネルギー(1gあたり9kcal)があるため、効率的なエネルギー補給源となります。
透析患者さんにとっては、脂質は重要なエネルギー源であり、過度に避ける必要はなく、植物油や魚の油(不飽和脂肪酸)は適度に活用したい食品です。
間食(おやつ)の取り入れ方
3度の食事だけでは十分なエネルギーが摂りきれない場合、間食(おやつ)を上手に取り入れ、1日の総エネルギー量を確保する手段とします。ただし、透析患者さんの場合、水分やカリウム、リンに配慮した食品を選ぶことが大切です。
カリウムの多い果物やいも類、リンの多い乳製品(アイスクリーム、ケーキなど)は控えめにし、エネルギーが高く、カリウムやリンが比較的少ないお菓子(例:飴、ゼリー、水ようかん、カステラ、一部のクッキーなど)を選ぶと良いでしょう。
また、透析患者向けのエネルギー補給用のお菓子やゼリーなども市販されており、何をどれくらい食べて良いかは、栄養士に相談すると安心です。
エネルギー補給に適した間食の例
| 種類 | 具体的な食品例 | 注意点 |
|---|---|---|
| 糖質中心のもの | 飴、グミ、水ようかん、カステラ、せんべい | 食べ過ぎに注意。水分・塩分量を確認。 |
| 脂質も補えるもの | クッキー、マドレーヌ(乳製品少なめ) | リンが多いナッツ類や乳製品が使われていないか確認。 |
| 市販の補助食品 | エネルギー補給ゼリー、ビスケット、専用飲料 | 栄養成分表示を確認し、管理栄養士に相談。 |
調理法による工夫
毎日の調理法を少し工夫するだけでも、エネルギー摂取量を増やすことができ、食欲がない時は、少ない量でエネルギーを確保する工夫が有効です。
- 炒め物や和え物に油(ごま油、オリーブオイルなど)を少量加える
- 揚げ物や天ぷらなど、油を使った料理を適度に取り入れる(油で揚げることでカリウムが減る効果も)
- マヨネーズやドレッシングを和え物やサラダに利用する
- 主食(ごはん)におかゆではなく、普通の硬さのごはんを選び、量をしっかり食べる
特に「油」は、少量で効率よくエネルギーをアップできるため、上手に活用したい食品で、「油は健康に悪い」というイメージがあるかもしれませんが、透析患者さんにとっては体を維持するための重要なエネルギー源です。
アルブミン値に関するよくある質問
- アルブミン値はすぐに改善しますか?
-
アルブミンは体内で作られてから分解されるまでの期間が比較的長いため(半減期が約3週間)、食事内容を改善しても、血液検査の数値に反映されるまでには数週間から1ヶ月以上の時間がかかることが一般的です。
また、体内に炎症があると改善が遅れることもあります。大切なのは、結果を焦らず、日々の良好な栄養管理を根気強く続けることです。
- 食事以外で気をつけることはありますか?
-
まず、体内の炎症がアルブミン値低下の原因になることがあるため、シャントの管理を清潔に行い感染を防ぐことや、毎日の歯磨きや歯周病をケアすること、風邪予防など、体調管理に気をつけることが重要です。
また、無理のない範囲での適度な運動(ウォーキング、透析中の軽い足の運動など)は、食欲増進や筋力の維持につながり、結果として栄養状態の改善に役立つことがあります。
- アルブミン値が高すぎる場合は問題ありませんか?
-
基本的には、4.0g/dL以上であれば栄養状態が良好であることを示すため、良い状態と捉えられます。
ただし、極端に高い数値が出る場合(例えば 4.5g/dLを超えるなど)、脱水状態(透析間の体重増加が少なすぎる、ドライウェイトの設定が低すぎるなど)で血液が濃縮している可能性も考えられます。
その場合は、体液量のバランスを見直す必要があるため、主治医と相談することが大切です。
- 栄養指導を受けるメリットは何ですか?
-
大きなメリットがあります。透析患者さんの栄養管理は、たんぱく質やエネルギーの確保と、水分・塩分・カリウム・リンの制限を両立させる必要があり、非常に複雑です。
管理栄養士による栄養指導(個別指導)では、ご自身の血液検査データや毎日の食事記録、生活スタイル、嗜好に合わせて、具体的で実践可能な食事の工夫や食品の選び方を一緒に考えてもらえます。
「何をどれだけ食べて良いか」が明確になり、アルブミン値の改善だけでなく、リンやカリウムの管理、塩分・水分管理の悩み解消にも役立ちます。
以上
参考文献
Kurita N, Hayashino Y, Yamazaki S, Akizawa T, Akiba T, Saito A, Fukuhara S. Revisiting interdialytic weight gain and mortality association with serum albumin interactions: the Japanese dialysis outcomes and practice pattern study. Journal of Renal Nutrition. 2017 Nov 1;27(6):421-9.
Abe T, Shono M, Kodama T, Kita Y, Fukagawa M, Akizawa T. Extracorporeal albumin dialysis. Therapeutic Apheresis and Dialysis. 2004 Jun;8(3):217-22.
Yamada S, Kawai Y, Tsuneyoshi S, Tsujikawa H, Arase H, Yoshida H, Tsuruya K, Nakano T, Kitazono T. Lower serum albumin level is associated with an increased risk for loss of residual kidney function in patients receiving peritoneal dialysis. Therapeutic Apheresis and Dialysis. 2020 Feb;24(1):72-80.
Minatoguchi S, Nomura A, Imaizumi T, Sasaki S, Ozeki T, Uchida D, Kawarazaki H, Sasai F, Tomita K, Shimizu H, Fujita Y. Low serum albumin as a risk factor for infection-related in-hospital death among hemodialysis patients hospitalized on suspicion of infectious disease: a Japanese multicenter retrospective cohort study. Renal Replacement Therapy. 2018 Aug 1;4(1):30.
Kawai Y, Masutani K, Torisu K, Katafuchi R, Tanaka S, Tsuchimoto A, Mitsuiki K, Tsuruya K, Kitazono T. Association between serum albumin level and incidence of end-stage renal disease in patients with Immunoglobulin A nephropathy: A possible role of albumin as an antioxidant agent. PLoS One. 2018 May 24;13(5):e0196655.
Yeun JY, Kaysen GA. Factors influencing serum albumin in dialysis patients. American journal of kidney diseases. 1998 Dec 1;32(6):S118-25.
Krieter DH, Canaud B. High permeability of dialysis membranes: what is the limit of albumin loss?. Nephrology Dialysis Transplantation. 2003 Apr 1;18(4):651-4.
Spiegel DM, Anderson M, Campbell U, Hall K, Kelly G, McClure E, Breyer JA. Serum albumin: a marker for morbidity in peritoneal dialysis patients. American journal of kidney diseases. 1993 Jan 1;21(1):26-30.
Kaysen GA, Don BR. Factors that affect albumin concentration in dialysis patients and their relationship to vascular disease. Kidney International. 2003 May 1;63:S94-7.
Rocco MV, Bedinger MR, Milam R, Greer JW, McClellan WM, Frankenfield DL. Duration of dialysis and its relationship to dialysis adequacy, anemia management, and serum albumin level. American journal of kidney diseases. 2001 Oct 1;38(4):813-23.