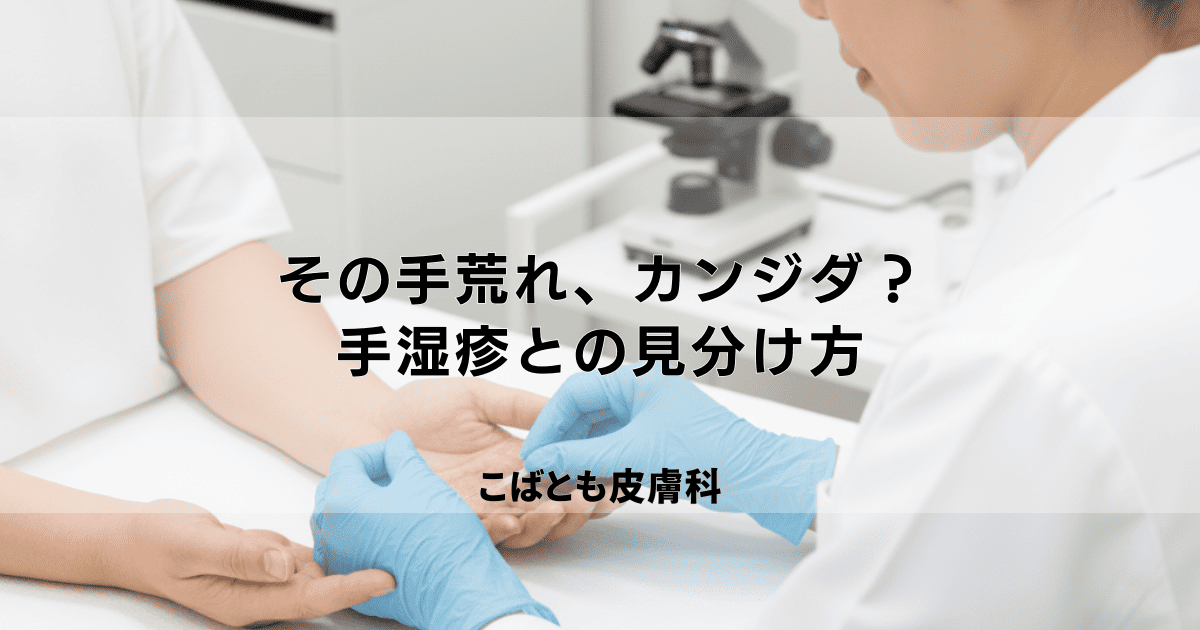長引く手荒れ、治りにくい指先のひび割れ、何を塗っても改善しないかゆみに悩まされている方は少なくありません。
多くの場合、それは手湿疹と呼ばれる皮膚の炎症ですが、中には真菌の一種であるカンジダ菌が原因となっているケースも隠れています。
手湿疹とカンジダ症は、症状が似ているため自己判断で間違ったケアを続けてしまい、かえって症状を悪化させることもあります。
この記事では、つらい手荒れの正体を見極めるために、手湿疹と手のカンジダ症の違い、見分け方のポイント、皮膚科で行われる治療法について、詳しく解説していきます。
この記事の執筆者

小林 智子(こばやし ともこ)
日本皮膚科学会認定皮膚科専門医・医学博士
こばとも皮膚科院長
2010年に日本医科大学卒業後、名古屋大学医学部皮膚科入局。同大学大学院博士課程修了後、アメリカノースウェスタン大学にて、ポストマスターフェローとして臨床研究に従事。帰国後、同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンターにて、糖化と肌について研究を行う。専門は一般皮膚科、アレルギー、抗加齢、美容皮膚科。雑誌を中心にメディアにも多数出演。著書に『皮膚科医が実践している 極上肌のつくり方』(彩図社)など。
こばとも皮膚科関連医療機関
手荒れの正体 手湿疹とカンジダ症の違いとは
つらい手荒れの症状は、日常生活にも大きな影響を及ぼし、原因として最も一般的なのは手湿疹ですが、よく似た症状を起こすカンジダ症という病気の可能性も考える必要があります。
一般的な手荒れ、手湿疹とは
手湿疹は、一般的に手荒れとして知られる皮膚の炎症で、水や洗剤、化学物質、物理的な摩擦など、外部からのさまざまな刺激が繰り返しかかることで、皮膚のバリア機能が低下して発症します。
特に、美容師、調理師、医療従事者など、水仕事や手洗いの頻度が高い職業の方に多く見られ、また、アトピー性皮膚炎の素因を持つ方は、皮膚のバリア機能がもともと弱いため、手湿疹を発症しやすい傾向があります。
主な症状は、乾燥、赤み、ひび割れ、かゆみ、小さな水ぶくれなどで、利き手の指先から症状が出始めることが多いです。悪化すると、皮膚が硬くなったり、深い亀裂が生じて痛みを感じたりすることもあります。
カンジダ症とは何か
カンジダ症は、カンジダという真菌(カビの一種)が異常増殖することによって起こされる感染症です。カンジダ菌は、もともと私たちの皮膚や口の中、消化管などに存在する常在菌で、普段は特に害を及ぼすことはありません。
しかし、体の抵抗力が落ちたり、皮膚が長時間湿った状態が続いたりすると、菌が異常に増殖して皮膚に炎症を起こします。
手や指に発症するものを手指カンジダ症と呼び、特に指の間の皮膚が白くふやけて、じゅくじゅくしたり、赤くただれたりする症状が特徴的です。爪の周囲に感染が及ぶと、爪囲炎を起こし、赤く腫れて痛みを伴うこともあります。
なぜ手湿疹とカンジダ症は間違われやすいのか
手湿疹とカンジダ症が間違われやすい最大の理由は、どちらも赤み、かゆみ、皮膚のめくれといった共通の症状を示す点にあり、初期段階では、見た目だけで判断するのは非常に困難です。
指の間にできた手湿疹は、カンジダ症のようにじゅくじゅくすることがありますし、乾燥してカサカサすることもあります。
自己判断で手湿疹用の市販薬(ステロイド外用薬など)をカンジダ症に使用してしまうと、カンジダ菌の増殖を助長してしまい、症状が劇的に悪化する危険性があります。
手湿疹とカンジダ症の基本的な違い
| 項目 | 手湿疹 | 手指カンジダ症 |
|---|---|---|
| 原因 | 外的刺激、アレルギーなど | カンジダ菌(真菌)の増殖 |
| 主な症状 | 乾燥、ひび割れ、赤み | 白いただれ、赤み、膿疱 |
| 好発部位 | 指先、手のひら、手の甲 | 指の間、爪の周り |
指や手のカンジダ症 なぜ発症するのか
身近に存在するカンジダ菌が、なぜ特定の条件下で手荒れの原因となるのでしょうか。カンジダ症の発症には、菌そのものの性質と、体の状態や生活環境が深く関わっています。
原因となるカンジダ菌について
カンジダ菌は酵母様真菌に分類され、数百種類がありますが、皮膚感染症の原因として最も多いのはカンジダ・アルビカンスという菌種です。
この菌は、健康な人の皮膚や粘膜にも少数ながら存在しており、普段は他の常在菌とのバランスが保たれており、問題を起こすことはありません。しかし、菌の増殖に適した環境が整うと、その数を増やし、病原性を示し始めます。
カンジダ菌は、特に高温多湿な環境を好む性質があるため、皮膚が蒸れやすい場所は、菌の温床となりやすいのです。
カンジダ菌が増殖しやすい環境
- 高温
- 多湿
- アルカリ性の環境
カンジダ症を起こす主な要因
カンジダ症の発症は、単に菌が存在するだけでは起こらず、菌の増殖を許してしまう、何らかの誘因があり、体の内側からの要因と、外側からの要因に大別できます。
内的な要因としては、糖尿病や免疫不全疾患などの基礎疾患、あるいはステロイド薬や免疫抑制薬、広域抗菌薬の長期使用などが挙げられ、全身の免疫力を低下させ、カンジダ菌が優勢になる状況を作り出します。
外的な要因としては、長時間ゴム手袋を着用する、指輪をつけっぱなしにする、手を洗った後にしっかり乾かさないなど、手が湿った状態が長く続くことが直接的な引き金です。
カンジダ症のリスクを高める要因
| 分類 | 具体的な要因 | 内容 |
|---|---|---|
| 内的要因 | 免疫力の低下 | 糖尿病、ステロイド薬の内服、疲労、ストレスなど |
| 外的要因 | 湿潤環境 | 長時間の水仕事、ゴム手袋の着用、多汗など |
| その他 | 皮膚の損傷 | 小さな傷、他の皮膚疾患によるバリア機能の低下 |
特に注意が必要な人とは
特定の職業や生活習慣を持つ人は、手指カンジダ症のリスクが高まるため、注意が必要です。
調理師、パン職人、清涼飲料水工場で働く人などは、日常的に手が水や糖分に触れ、湿った状態になりやすいため、カンジダ菌が増殖しやすい環境にあります。また、乳幼児のおむつ交換を頻繁に行う育児中の方や、介護の現場で働く方も同様です。
さらに、基礎疾患として糖尿病を抱えている方は、血糖コントロールが悪いと皮膚の免疫機能が低下し、感染症全般にかかりやすくなるため、手指カンジダ症のリスクも高まります。
これってカンジダ?手湿疹と見分けるためのチェックポイント
なかなか治らない手荒れが、手湿疹なのかカンジダ症なのかを見分けることは、適切な治療を選択する上で非常に重要です。ここでは、ご自身の症状を客観的に観察するための具体的なチェックポイントをいくつか紹介します。
症状が現れる場所の特徴
まず注目すべきは、症状がどこに現れているかです。
手湿疹は、刺激を受けやすい指先や手のひら、手の甲など、手のあらゆる場所に起こり、手指カンジダ症は、指と指の間(指間びらん)や、爪の生え際(爪囲炎)に好発する傾向があります。
指の間が白くふやけてじゅくじゅくしたり、皮がむけたりしている場合は、カンジダ症の可能性を考えます。
手袋などで密閉され、湿気がこもりやすい薬指と中指の間に最も多く見られ、これは、カンジダ菌が高温多湿な環境を好むという性質を反映しています。
見た目でわかる皮膚の変化
皮膚の見た目にも、特徴的な違いが現れることがあります。
手湿疹の場合、皮膚が乾燥してカサカサしたり、硬くなってひび割れたりすることが多く、典型的な手指カンジダ症では、病変部が赤くただれ、境界がはっきりしていることが特徴です。
また、病変部の周囲に、小さな水ぶくれや膿を持ったぶつぶつ(膿疱)が衛星のように点在して見られることがあります。これは手湿疹ではあまり見られない、カンジダ症に特徴的な所見の一つです。
爪の周りが赤く腫れ、少し押しただけで膿が出てくるような場合も、カンジダ性の爪囲炎が疑われます。
カンジダ症と手湿疹の見た目の違い
| 観察ポイント | 手指カンジダ症で多い所見 | 手湿疹で多い所見 |
|---|---|---|
| 境界 | 比較的はっきりしている | 比較的ぼやけている |
| 色 | 鮮やかな赤み、白いふやけ | くすんだ赤み、茶色っぽい色素沈着 |
| 表面の状態 | じゅくじゅく、膿疱、鱗屑 | カサカサ、ひび割れ、苔癬化 |
かゆみや痛みの感覚の違い
自覚症状であるかゆみや痛みの性質にも、若干の違いが見られます。
手湿疹は、強いかゆみを伴うことが多く、思わず掻きむしってしまうことでさらに悪化する悪循環に陥りがちですが、手指カンジダ症のかゆみは、手湿疹ほど強くない場合もありますが、ピリピリとした刺激感や痛みを伴うことが多いです。
指の間の皮膚が裂けてしまうと、強い痛みを感じ、爪囲炎を起こしている場合は、指先にズキズキとした拍動性の痛みを感じることもあります。
症状の感じ方には個人差があるため一概には言えませんが、かゆみよりも痛みが強い場合は、カンジダ症を含む感染症の可能性を考慮することが必要です。
進行したときに見られる症状
症状が進行すると、両者の違いはさらに顕著になることがあります。手湿疹が慢性化すると、皮膚がゴワゴワと硬く厚くなる苔癬化(たいせんか)という状態になり、長期間にわたる炎症と掻破によって起こされる変化です。
カンジダ症が進行したり、不適切な治療(ステロイド外用など)が続けられたりすると、感染範囲が拡大し、手のひら全体や手の甲にまで赤いぶつぶつが広がることがあります。
また、カンジダ性の爪囲炎を放置すると、爪の変形や変色を起こし、爪が正常に生えてこなくなることもあります。症状が長引いたり、悪化したりしている場合は、早めに皮膚科を受診することが重要です。
カンジダ症と間違いやすい他の皮膚疾患
手や指の症状は、カンジダ症や手湿疹以外にも、さまざまな皮膚疾患によって起こされることがあります。正確な診断のためには、違いを理解しておくことも役立ちます。
汗疱(かんぽう)との違い
汗疱は、手のひらや足の裏、指の側面に、かゆみを伴う小さな水ぶくれ(小水疱)がたくさんできる病気です。特に季節の変わり目や、夏場に悪化する傾向があります。
汗の排出がうまくいかないことが一因と考えられていますが、はっきりとした原因は不明な点も多いです。
小さな水ぶくれが多発するという点で、カンジダ症の膿疱と見間違えることがありますが、汗疱の水ぶくれは通常、透明な液体を含んでいます。
カンジダ症の膿疱は白や黄色っぽい膿を含んでいることが多く、また、汗疱は指の間よりも指の側面にできやすいという違いもあります。
白癬菌(はくせんきん)による感染症との違い
白癬菌は、水虫の原因となる真菌で、足に感染することが圧倒的に多いですが、まれに手に感染して手白癬(てはくせん)を起こすことがあります。
手白癬は、手のひら全体の皮膚が厚く硬くなり、カサカサと皮がむける症状が特徴で、かゆみはあまりないことが多く、カンジダ症のように指の間がじゅくじゅくすることは比較的まれです。
片方の手だけに症状が見られ、同じ側の足に水虫を合併しているケースがほとんどで、原因菌は同じ真菌ですが、カンジダ菌と白癬菌では治療に使う抗真菌薬の種類が異なる場合があるため、菌の種類を特定することが重要になります。
カンジダ症と他の皮膚疾患の比較
| 疾患名 | 主な症状 | 好発部位 |
|---|---|---|
| 手指カンジダ症 | 指間のびらん、爪囲の腫れ、膿疱 | 指の間、爪の周り |
| 汗疱 | 透明な小水疱、強いかゆみ | 手のひら、指の側面 |
| 手白癬 | 手のひらの角化、鱗屑、かゆみは軽度 | 手のひら全体(主に片手) |
細菌感染症との違い
ひび割れや掻き傷などから黄色ブドウ球菌などの細菌が侵入し、二次的な細菌感染を起こすことがあり、伝染性膿痂疹(とびひ)などと呼びます。この場合、黄色っぽいかさぶたを伴うじゅくじゅくした病変が急速に広がります。
また、蜂窩織炎(ほうかしきえん)という、より深い組織での細菌感染を起こすと、皮膚が広範囲にわたって赤く硬く腫れあがり、熱感や強い痛みを伴います。発熱などの全身症状が出ることもあります。
カンジダ症でも膿疱や痛みを伴いますが、細菌感染症は進行が早く、より強い炎症症状を示し、細菌感染症の場合は、抗真菌薬ではなく抗菌薬による治療が絶対に必要です。
専門医による診断の重要性
手荒れの症状はさまざまな原因によって起こり、見分けは専門家でも難しい場合があります。適切な治療を行い、症状を速やかに改善させるためには、自己判断に頼らず、皮膚科専門医による正確な診断を受けることが何よりも大切です。
自己判断が危険な理由
自己判断で市販薬を使用することには、大きなリスクが伴います。最も注意すべきは、カンジダ症に対して手湿疹用のステロイド外用薬を使用してしまうケースです。
ステロイド薬は炎症を抑える効果が非常に高いですが、同時に皮膚の免疫反応も抑制するため、真菌感染症であるカンジダ症に使うと、菌の増殖をかえって促進してしまい、症状が爆発的に悪化することがあります。
最初は少し良くなったように感じても、すぐにこれまで以上の範囲に症状が広がってしまうのです。逆に、手湿疹に対して抗真菌薬を使用しても、全く効果は期待できません。
皮膚科受診を推奨する症状
- 市販薬を1週間使っても改善しない、または悪化した
- 指の間が白くふやけている
- 爪の周りが赤く腫れて痛い
- 症状が急速に広がっている
- 強い痛みを伴う
皮膚科で行われる検査方法
皮膚科では、まず問診と視診で詳しく症状を確認し、いつからどのような症状があるのか、どのような仕事や生活習慣があるのか、既往歴などを聞き取ります。
その上で、カンジダ症などの真菌感染症が疑われる場合には、確定診断のために検査を行い、最も一般的に行われるのが、直接鏡検(直接検鏡検査)です。
これは、症状が出ている部分の皮膚の表面や膿などを少量採取し、顕微鏡で直接観察して、カンジダ菌の菌体や仮性菌糸を確認する検査で、その場で真菌の有無を判断することができます。
必要に応じて、採取した検体を培地で培養し、菌の種類を特定する培養検査を行うこともあります。
皮膚科での主な検査
| 検査名 | 方法 | わかること |
|---|---|---|
| 直接鏡検 | 病変部をこすり取り顕微鏡で観察 | 真菌(カンジダ、白癬菌など)の有無 |
| 培養検査 | 検体を培地で育てて菌を同定 | 菌の種類、薬剤感受性など |
正確な診断がもたらすメリット
皮膚科で正確な診断を受けることには、多くのメリットがあります。第一に、原因に応じた最も効果的な治療を速やかに開始できることで、無駄な治療による症状の悪化を防ぎ、早期の改善が期待できます。
第二に、症状の根本的な原因や悪化要因について、専門家からアドバイスを受けられることです。日常生活での注意点やスキンケアの方法など、再発予防につながる指導を受けることで、長期的に良好な状態を維持しやすくなります。
そして第三に、似たような症状を示す他の重篤な病気の可能性を除外できるという安心感を得られることです。不安を抱えながら過ごすよりも、専門医に相談することで、精神的な負担も大きく軽減されるでしょう。
手のカンジダ症に対する効果的な治療法
皮膚科で手指カンジダ症と診断された場合、原因であるカンジダ菌を抑えるための治療が始まり、治療の主役は抗真菌薬と呼ばれる薬です。
治療の基本となる抗真菌薬
カンジダ症の治療には、真菌の細胞膜に作用して増殖を抑えたり、殺菌的に働いたりする抗真菌薬を使用し、手指カンジダ症のように、皮膚の表面に限局した感染症の場合は、主に塗り薬(外用薬)が用いられます。
抗真菌外用薬には、さまざまな種類がありますが、カンジダ菌に効果のある成分が含まれたものが処方されます。
代表的なものに、イミダゾール系やアリルアミン系などと呼ばれるグループの薬があり、医師の指示通りに適切な期間使用し続けることが非常に重要です。
症状が軽くなったからといって自己判断で中断してしまうと、生き残った菌が再び増殖し、再発の原因となります。
代表的な抗真菌薬(外用薬)の系統
| 系統 | 特徴 | 主な対象真菌 |
|---|---|---|
| イミダゾール系 | 幅広い真菌に効果を示す | カンジダ、白癬菌など |
| アリルアミン系 | 白癬菌に強い効果を示す | 白癬菌、一部のカンジダ |
| ベンジルアミン系 | イミダゾール系と似た作用を持つ | カンジダ、白癬菌など |
塗り薬(外用薬)の正しい使い方
抗真菌薬の効果を最大限に引き出すためには、薬を正しく塗ることが大切です。まず、塗る前には石鹸で手を優しく洗い、清潔なタオルで水分をしっかりと拭き取り、薬は、症状が出ている部分よりも少し広めの範囲に塗るのがポイントです。
これは、目に見えない部分にも菌が潜んでいる可能性があるためで、指の間などの細かい部分にも、忘れずに丁寧に塗り込みます。一般的には1日1回または2回、入浴後などの清潔な皮膚に塗ることが多いです。
抗真菌薬の塗り方のポイント
- 塗布前に患部を清潔にする
- 症状のある部位より広めに塗る
- すり込まず、優しくのせるように塗る
- 医師の指示した期間、毎日続ける
症状が重い場合の治療選択
外用薬だけでは改善が見られない場合や、症状の範囲が非常に広い場合、爪の変形を伴う爪囲炎を繰り返す場合、あるいは免疫力が著しく低下している患者さんなどでは、飲み薬(内服薬)による治療が検討されることがあります。
抗真菌薬の内服薬は、血流に乗って体の内側から皮膚や爪に作用するため、外用薬が届きにくい場所にも効果を発揮します。
ただし、内服薬は肝臓への負担など、副作用のリスクも考慮する必要があるため、使用前には血液検査などが行われることもあります。
治療期間の目安
手指カンジダ症の治療期間は、症状の重症度や範囲によって異なりますが、一般的には外用薬による治療を始めてから2週間から4週間程度で症状の改善が見られます。
ただし、見た目がきれいになったからといって、菌が完全にいなくなったわけではありません。再発を防ぐためには、医師の指示に従い、症状が消えた後もしばらくの間は治療を続けることが大切です。
特に爪囲炎の場合は、爪の構造上、薬が浸透しにくく、治療が長引くこともあり、根気強く治療を続けることが、完治への近道です。
日常生活で気をつけるべき予防とセルフケア
手指カンジダ症の治療を成功させ、再発を防ぐためには、薬による治療と並行して、日々の生活習慣を見直すことがとても大事です。カンジダ菌が増殖しにくい環境を整え、皮膚の健康を保つためのセルフケアについて解説します。
手を清潔で乾燥した状態に保つ
カンジダ菌は湿った環境を好むため、手を常に清潔で乾燥した状態に保つことが予防の基本です。手を洗った後や水仕事の後には、清潔なタオルで指の間まで丁寧に水分を拭き取りましょう。
特に、指輪をしていると、その下に湿気がたまりやすくなるため、水仕事の際には外すか、外した後に指輪の内側と指をしっかり乾かす習慣をつけることが重要です。また、汗をかきやすい人は、こまめに汗を拭き取ることを心がけてください。
吸湿性の良い綿の手袋を下着代わりにつけるのも一つの方法です。
水仕事の際の注意点
- 長時間の水仕事は避ける
- ゴム手袋の下に綿の手袋を着用する
- 作業後は手袋を裏返して乾かす
- 手を洗った後はすぐに保湿する
水仕事での工夫と保護
水仕事が多い方は、皮膚のバリア機能を守るための工夫が必要です。食器洗いや掃除の際には、必ずゴム手袋を着用しましょう。ただし、ゴム手袋を長時間つけていると、内部が汗で蒸れてしまい、かえってカンジダ菌の温床になることがあります。
対策として、ゴム手袋の下に、汗を吸収してくれる綿の手袋をはめ、二重の手袋は、皮膚への刺激を和らげる効果もあります。水仕事が終わった後は、すぐに手を洗い、保湿剤を塗って皮膚のバリア機能を補いましょう。
保湿剤は、皮膚を保護し、外部からの刺激や乾燥を防ぐ上で非常に有効です。
手の保護に役立つアイテム
| アイテム | 選び方のポイント | 使用のコツ |
|---|---|---|
| 保湿剤 | 低刺激で保湿力が高いもの(ワセリン、ヘパリン類似物質など) | 手を洗うたび、こまめに塗り直す |
| 綿の手袋 | 通気性・吸湿性の良い天然素材 | ゴム手袋の下に着用、就寝時に保湿剤を塗った上から着用 |
| ゴム手袋 | 自分の手に合ったサイズを選ぶ | 長時間の連続使用は避け、こまめに着脱する |
免疫力を維持するための生活習慣
カンジダ症は、体の抵抗力が落ちたときに発症しやすくなる日和見感染症で、皮膚のケアだけでなく、全身の免疫力を高く維持するような生活習慣を心がけることも、根本的な予防につながります。
バランスの取れた食事、十分な睡眠、適度な運動は、免疫システムを正常に機能させるために必要です。過度のストレスや疲労は免疫力を低下させる大きな要因となるため、自分なりのリフレッシュ方法を見つけ、心身の健康を保つよう努めましょう。
また、糖尿病などの基礎疾患がある方は、主治医の指導のもとで病状を良好にコントロールすることが、カンジダ症を含むさまざまな感染症の予防に直結します。
免疫力維持につながる生活習慣
| 習慣 | ポイント | 具体例 |
|---|---|---|
| 食事 | 栄養バランスを整える | 野菜、タンパク質、発酵食品を意識して摂取する |
| 睡眠 | 質と量を確保する | 毎日決まった時間に就寝・起床する、寝る前のスマホを控える |
| 運動 | 血行を促進し、体力をつける | ウォーキングなどの有酸素運動を週に2〜3回行う |
手のカンジダ症に関するよくある質問
最後に、患者さんからよく寄せられる、手のカンジダ症に関する質問と回答をまとめました。
- 市販薬を使っても大丈夫ですか
-
自己判断での市販薬の使用は推奨しません。手荒れの原因がカンジダ症か手湿疹か、あるいは他の疾患かによって使うべき薬が全く異なるからです。
もしカンジダ症に手湿疹用のステロイド薬を使うと、症状が悪化する危険性があります。まずは皮膚科を受診し、正確な診断を受けてから、症状に合った薬を処方してもらうことが、最も早い改善につながります。
- 家族にうつることはありますか
-
過度に心配する必要はありません。カンジダ菌はもともと多くの人の皮膚に存在する常在菌であり、接触したからといって必ずしも感染が成立するわけではありません。
健康な皮膚にはバリア機能があるため、菌が付着しても通常は洗い流されます。
ただし、家族内に皮膚が弱い乳幼児や、免疫力が低下している高齢者などがいる場合は、タオルや爪切りの共用を避けるなどの配慮をすると、より安心です。
- 一度治っても再発しますか
-
再発する可能性はあります。カンジダ症は、菌を完全に取り除くというよりも、異常増殖した菌を抑え、常在菌としてのバランスを取り戻す治療です。
治療後に再び手が高温多湿な環境に長時間さらされたり、体の抵抗力が落ちたりすると、菌が再度増殖して再発することがあります。
治療後も、手を乾燥させる、保湿を心がける、体調管理に気をつけるといった予防策を継続することが重要です。
- 食事で気をつけることはありますか
-
直接的に特定の食べ物がカンジダ症を悪化させるという科学的根拠は確立されていませんが、全身の健康状態を良好に保つという観点から、バランスの取れた食生活が大切です。
特に、糖質の過剰な摂取は、糖尿病のリスクを高めたり、腸内環境の乱れにつながったりする可能性が指摘されることがあります。
日々の食事では、極端な偏食を避け、野菜やタンパク質、ビタミン、ミネラルを豊富に含む食品をまんべんなく摂ることを心がけ、健やかな体を維持することが、免疫力の維持と感染症予防につながります。
以上
参考文献
Kajihara T, Yahara K, Nagi M, Kitamura N, Hirabayashi A, Hosaka Y, Abe M, Miyazaki Y, Sugai M. Distribution, trends, and antifungal susceptibility of Candida species causing candidemia in Japan, 2010–2019: a retrospective observational study based on national surveillance data. Medical Mycology. 2022 Sep;60(9):myac071.
Iguchi S, Itakura Y, Yoshida A, Kamada K, Mizushima R, Arai Y, Uzawa Y, Kikuchi K. Candida auris: a pathogen difficult to identify, treat, and eradicate and its characteristics in Japanese strains. Journal of Infection and Chemotherapy. 2019 Oct 1;25(10):743-9.
Watanabe SI, Seki Y, Shimozuma M, Takizawa K. Nail candidiasis. The Journal of Dermatology. 1983 Jun;10(3):189-203.
Pfaller MA. Epidemiology of candidiasis. Journal of Hospital Infection. 1995 Jun 1;30:329-38.
Bonassoli LA, Bertoli M, Svidzinski TI. High frequency of Candida parapsilosis on the hands of healthy hosts. Journal of Hospital Infection. 2005 Feb 1;59(2):159-62.
Y1ıld1ır1ım M, Sahin I, Kucukbayrak A, Ozdemir D, Tevfik Yavuz M, Oksuz S, Cakir S. Hand carriage of Candida species and risk factors in hospital personnel. Mycoses. 2007 May;50(3):189-92.
Meunier F. Candidiasis. European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. 1989 May;8(5):438-47.
Vazquez JA, Sobel JD. Candidiasis. InEssentials of clinical mycology 2010 Nov 27 (pp. 167-206). New York, NY: Springer New York.
Khullar G, Vignesh P, Lau YL, Rudramurthy SM, Rawat A, De D, Handa S, Singh S. Chronic mucocutaneous candidiasis. The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice. 2017 Jul 1;5(4):1119-21.
Sakita KM, Faria DR, da Silva EM, Tobaldini-Valério FK, Kioshima ES, Svidzinski TI, de Souza Bonfim-Mendonça P. Healthcare workers’ hands as a vehicle for the transmission of virulent strains of Candida spp.: A virulence factor approach. Microbial pathogenesis. 2017 Dec 1;113:225-32.