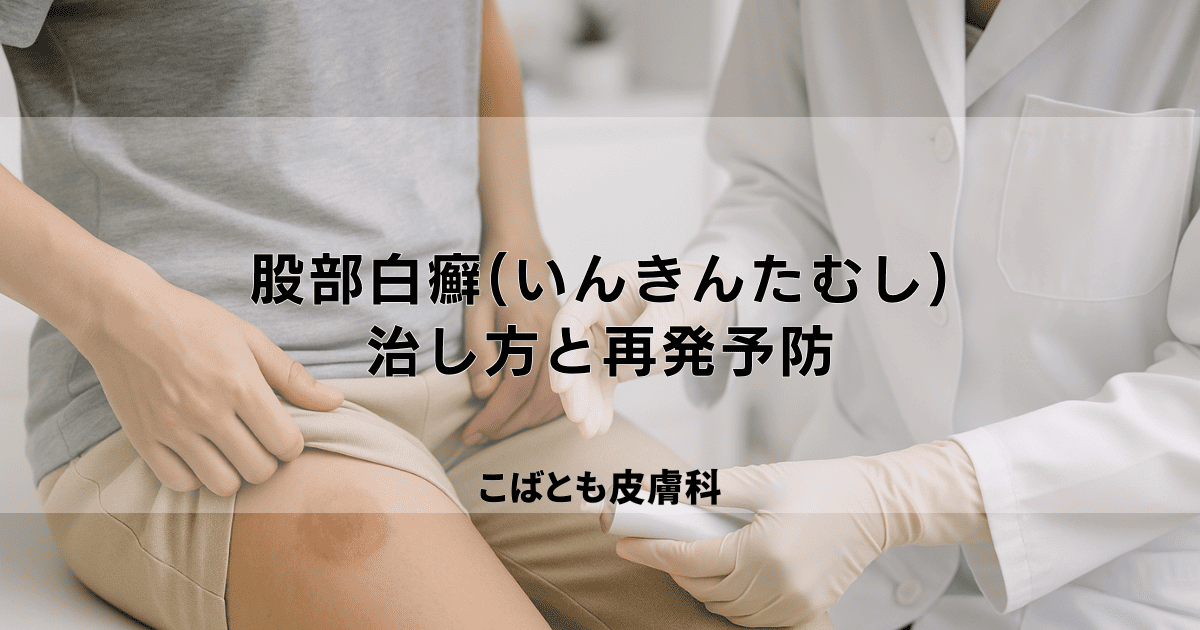股部白癬、一般的にいんきんたむしとして知られるこの皮膚の症状は、多くの人が悩む一方で、場所が場所だけに相談しにくいと感じるかもしれませんが、強いかゆみや不快感は日常生活の質を大きく低下させます。
原因は白癬菌というカビの一種であり、決して不潔だから発症するわけではありません。正しい知識を持ち、治療と予防を行えば、症状を改善し、快適な毎日を取り戻すことが可能です。
この記事では、股部白癬の原因から、皮膚科で行う正確な診断、効果的な治療法、そして何よりも重要な再発を防ぐための対策まで、詳しく解説します。
この記事の執筆者

小林 智子(こばやし ともこ)
日本皮膚科学会認定皮膚科専門医・医学博士
こばとも皮膚科院長
2010年に日本医科大学卒業後、名古屋大学医学部皮膚科入局。同大学大学院博士課程修了後、アメリカノースウェスタン大学にて、ポストマスターフェローとして臨床研究に従事。帰国後、同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンターにて、糖化と肌について研究を行う。専門は一般皮膚科、アレルギー、抗加齢、美容皮膚科。雑誌を中心にメディアにも多数出演。著書に『皮膚科医が実践している 極上肌のつくり方』(彩図社)など。
こばとも皮膚科関連医療機関
股部白癬(いんきんたむし)の正体と原因
股部周辺に現れるかゆみや赤い発疹は、単なるかぶれや湿疹ではなく、股部白癬かもしれません。なぜ股部周辺に発症しやすいのか、背景にある要因を探っていきましょう。
そのかゆみ、カビが原因?股部白癬とは何か
股部白癬は、皮膚糸状菌(ひふしじょうきん)というカビ(真菌)が、股部、足の付け根周辺の皮膚に感染して起こる皮膚感染症です。一般的にいんきんたむしという通称で広く知られています。
菌は皮膚の最も外側にある角層に寄生し、ケラチンというタンパク質を栄養源にして増殖し、増殖する過程で炎症反応が起こされ、強いかゆみや赤み、輪郭がはっきりした円形または半円形の発疹といった特徴的な症状が現れます。
性別を問わず発症しますが、構造的に蒸れやすい男性に多く見られる傾向があります。
原因菌は白癬菌(はくせんきん)
股部白癬を起こす主な原因菌は、トリコフィトン属に分類される白癬菌で、トリコフィトン・ルブルムやトリコフィトン・メンタグロフィテスが原因となる場合が多いです。
菌は、足白癬(水虫)の原因菌と同一であり、水虫を患っている人が無意識のうちに患部を触った手で股部を掻いてしまうことで、菌が運ばれて感染するケースが非常によく見られます。
股部白癬の治療を考える際には、足白癬の有無を確認し、もしあれば同時に治療することが重要です。
感染の主な原因菌
| 菌の種類 | 主な特徴 | 関連する他の疾患 |
|---|---|---|
| トリコフィトン・ルブルム | 最も一般的な原因菌。慢性化しやすい。 | 足白癬(水虫)、爪白癬(爪水虫) |
| トリコフィトン・メンタグロフィテス | 強い炎症やかゆみを伴うことが多い。 | 足白癬(水虫) |
高温多湿な環境が菌の温床に
白癬菌は、高温多湿な環境を非常に好み、股部は、下着や衣類によって常に覆われており、汗をかきやすく、熱がこもりやすい場所です。特に夏場やスポーツ後、通気性の悪い下着を着用していると、菌が増殖するのに絶好の環境が生まれます。
また、身体の構造上、皮膚がこすれやすいことも、角層に微細な傷を作り、菌が侵入しやすくなる一因で、環境要因が、股部白癬の発症リスクを高めています。
人から人へうつる?感染経路を知る
股部白癬は感染症であり、人から人へうつる可能性があり、感染者の皮膚から剥がれ落ちた角層(鱗屑:りんせつ)には白癬菌が含まれており、これが他人の皮膚に付着することで感染が成立します。
ただし、菌が付着したからといってすぐに発症するわけではありません。付着後、洗い流されずに高温多湿の環境が保たれると、菌が増殖を始めて発症に至ります。
直接的な皮膚の接触だけでなく、タオルやバスマット、下着の共用なども感染経路となり得て、また、自身の足白癬から感染する自家感染が最も多いパターンです。
これって股部白癬?見分けるための症状
股部白癬の症状は特徴的で、それを知ることが早期発見と適切な対処につながります。かゆみや赤みといった一般的な皮膚トラブルとの違いを理解し、自身の症状と照らし合わせてみましょう。
典型的な症状は強いかゆみと発疹
股部白癬の最も代表的な症状は、股部、太ももの内側、臀部(おしり)にかけて生じる強いかゆみです。かゆみは、じっとしている時よりも、温まったり汗をかいたりすると強くなる傾向があります。
皮膚には、境界がはっきりとした半円状またはリング状の赤い発疹が現れ、中心部が治ったように薄い色に見える一方、縁の部分が盛り上がって赤みが強く、小さな水ぶくれや皮むけを伴うことが特徴です。
この見た目から輪癬(りんせん)とも呼ばれます。
初期症状のチェックポイント
- 股間や太ももの内側のかゆみ
- 赤く、少し盛り上がった発疹
- 発疹の輪郭がはっきりしている
症状が広がる様子
発疹は、中心部が治癒していくように見えながら、縁の部分が遠心状、つまり外側に向かって徐々に拡大していき、放置すると、太ももの内側から臀部、下腹部へと広範囲に及ぶことがあります。
陰嚢(いんのう)にまで症状が広がることは比較的まれですが、重症化すると色素沈着を起こして皮膚が黒ずんだり、慢性化して皮膚が厚くゴワゴワになったりすることもあります。
かゆみが強いからといって掻き壊すと、そこから細菌が侵入して二次感染を起こし、痛みや腫れを伴うこともあるため注意が必要です。
他の皮膚疾患との見分け方
股部のかゆみや赤みを起こす病気は、股部白癬だけではなく、自己判断で誤った市販薬を使うと、症状を悪化させる危険があります。皮膚科では、症状や見た目から鑑別診断を行います。
股部白癬と間違えやすい皮膚疾患
| 疾患名 | 症状の特徴 | 股部白癬との主な違い |
|---|---|---|
| カンジダ性間擦疹 | 赤み、じゅくじゅくしたびらん、小さな膿疱 | 発疹の境界が不明瞭で、周辺に小さな発疹が散在する。 |
| 接触皮膚炎(かぶれ) | 原因物質に触れた部分に一致した赤み、かゆみ | 発疹の境界が比較的はっきりしているが、リング状にはならない。 |
| 脂漏性皮膚炎 | 黄色がかったフケのような皮むけ、軽度のかゆみ | 赤みは軽度で、境界がはっきりしないことが多い。 |
皮膚科を受診すべきタイミング
股部に上記のような症状が現れ、市販のかゆみ止めを数日間使用しても改善しない場合、または症状が悪化する場合には、速やかに皮膚科専門医の診察を受けてください。
足白癬(水虫)を患っている場合や、発疹がリング状に広がっている場合は股部白癬の可能性が高いです。正確な診断を受け、適切な治療を早期に開始することが、完治への近道になります。
自己判断による治療の危険性
「ただのかぶれだろう」「市販の薬で治るはず」といった自己判断は、股部白癬の治療において大きな落とし穴となります。手軽に手に入る薬が、かえって症状を複雑にし、治療を長引かせる原因になることも少なくありません。
なぜ自己判断が危険なのか、その理由を具体的に見ていきましょう。
安易な判断が招く症状の悪化
股部白癬を単なる湿疹やかぶれと勘違いしてしまうことが、問題の始まりです。
見た目が似ているため、多くの人がドラッグストアで湿疹用の塗り薬を購入してしまいますが、このような薬には股部白癬の原因である白癬菌を殺す成分が含まれていないため、根本的な解決にはなりません。
一時的にかゆみが和らぐことがあっても、菌は皮膚の内部で増殖を続け、気づいた時には症状が広範囲に広がっているという事態を招くのです。
ステロイド外用薬が菌を増殖させる
特に注意が必要なのが、ステロイド成分を含む外用薬の使用です。ステロイドには優れた抗炎症作用があり、湿疹やかぶれによる赤みやかゆみを抑える効果があるものの、同時に免疫を抑制する働きも持っています。
股部白癬の原因である白癬菌に対してステロイドを使用すると、皮膚の免疫力が低下し、菌の増殖をかえって助長してしまいます。
一時的にかゆみが引いたように感じても、薬の使用を中止すると以前よりひどい症状で再燃したり、発疹の典型的な特徴が失われて診断が困難になったりし、これが菌交代現象と呼ばれるものです。
誤った自己治療のリスク
| 誤った対処法 | 起こりうる結果 | 解説 |
|---|---|---|
| 湿疹用の市販薬を使用 | 症状が改善しない、または悪化する | 原因菌である白癬菌に効果がないため。 |
| ステロイド配合の薬を使用 | 菌の増殖、症状の悪化・長期化 | 皮膚の免疫を抑え、白癬菌を増殖させてしまう。 |
| かゆみを我慢できず掻く | 二次感染、色素沈着 | 掻き傷から細菌が侵入したり、皮膚が黒ずんだりする。 |
市販の抗真菌薬の限界
最近では、白癬菌に効果のある抗真菌成分を配合した市販薬も販売されていますが、万能ではありません。まず、自身の症状が本当に股部白癬であるかどうかの正確な診断が前提です。
もし他の皮膚疾患であった場合、効果がないばかりか、薬の成分によるかぶれを起こす可能性もあります。また、市販薬を使い始めて症状が少し良くなると、自己判断で塗布を中止してしまう人が多いのも問題です。
白癬菌は症状が消えても角層の奥に潜んでいるため、中途半端な治療は再発の大きな原因となります。
感染拡大のリスク
不適切な治療を続けている間にも、白癬菌は増殖を続け、自身の体で感染範囲が広がるだけでなく、家族や同居人にうつしてしまうリスクも高まります。タオルやバスマットなどを介して、家庭内に感染が広がるケースは珍しくありません。
自分一人の問題と軽視せず、周囲への影響も考えて、早期に適切な対応をとることがそれぞれの責任です。
皮膚科で行う検査と診断
皮膚科では、専門医が視診や問診に加え、科学的な根拠に基づいた検査を行うことで、症状の原因を特定し、他の類似した皮膚疾患と明確に区別し、最も効果的な治療方針を立てることが可能です。
問診と視診による初期評価
診察室では、まず医師が患者さんから詳しい話を聞き、いつから症状があるのか、どのようなかゆみか、どのような状況で悪化するのか、自分でどのような薬を使ったか、足白癬(水虫)の既往はないか、といった情報が診断の重要な手がかりです。
続いて、患部の状態を直接目で見て確認し、発疹の色や形、広がり方、皮むけの有無、境界の明瞭さなど、股部白癬に特徴的な所見があるかどうかを詳細に観察します。
診断を確定させる顕微鏡検査(直接鏡検)
視診で股部白癬が疑われた場合、診断を確定するために顕微鏡検査(直接鏡検、KOH法とも呼ばれます)を行います。
まず、発疹の縁の部分の皮膚の表面を、ピンセットやメスで軽くこすって、角層を少量採取しますが、痛みはほとんどありません。採取した角層をスライドガラスに乗せ、水酸化カリウム(KOH)溶液を滴下して角層を溶かし、顕微鏡で観察します。
もし白癬菌がいれば、糸状の菌糸や分節構造を持つ胞子としてはっきりと確認でき、白癬菌の存在を直接証明できるため、最も確実な診断方法です。
顕微鏡検査の流れ
| 手順 | 内容 | 所要時間 |
|---|---|---|
| 1. 角層の採取 | 患部の縁から、皮むけなどを少量採取します。 | 約1分 |
| 2. プレパラート作成 | 採取した角層をKOH溶液で溶かします。 | 約5~10分 |
| 3. 顕微鏡での観察 | 顕微鏡で白癬菌の有無を確認します。 | 約2~3分 |
他の皮膚疾患の可能性を排除
顕微鏡検査で白癬菌が見つからなかった場合、股部白癬以外の疾患の可能性を考えます。
問診や視診の情報とあわせて、カンジダ性間擦疹、接触皮膚炎、脂漏性皮膚炎、尋常性乾癬(じんじょうせいかんせん)といった、股部に症状が現れやすい他の皮膚疾患との鑑別を進めます。
場合によっては、診断をより確実にするために、皮膚の一部を採取して病理組織検査を行ったり、細菌や真菌の培養検査を追加したりすることもあります。
皮膚科で行う正しい治療法
股部白癬の診断が確定したら、治療が始まります。治療の主役は、白癬菌を直接退治する抗真菌薬ですが、ただ薬を塗るだけでは十分な効果は得られません。正しい種類の薬を、正しい方法で、正しい期間使い続けることが完治の鍵です。
治療の基本は抗真菌薬の塗り薬
股部白癬の治療の第一選択は、抗真菌作用を持つ外用薬(塗り薬)で、白癬菌の細胞膜の合成を阻害するなどして、菌の増殖を抑え、最終的に死滅させます。
現在、さまざまな種類の抗真菌外用薬があり、医師は患者さんの症状の程度や皮膚の状態、ライフスタイルに合わせて、クリーム、軟膏、ローション、スプレーといった剤形の中から最も適したものを選びます。
抗真菌薬は原因菌に直接作用するため、高い治療効果が期待できます。
主な抗真菌外用薬の種類
- イミダゾール系
- アリルアミン系
- ベンジルアミン系
- チオカルバミン酸系
薬の正しい塗り方と範囲
薬の効果を最大限に引き出すためには、正しい塗り方を実践することが非常に重要で、まず、入浴などで患部を清潔にし、よく乾燥させてから薬を塗布します。
薬を塗る範囲は、発疹が出ている部分よりも一回り広く、指2本分くらい外側まで塗るのがポイントで、これは、症状が出ていないように見える部分にも菌が潜んでいる可能性があるためです。
また、薬は擦り込むのではなく、優しくなでるように均一に塗布します。ゴシゴシ擦ると皮膚への刺激となり、かえって炎症を悪化させることがあります。
塗り方のポイント
| ポイント | 理由 | 具体的な方法 |
|---|---|---|
| 清潔な状態で塗る | 薬の浸透を良くし、他の細菌感染を防ぐため。 | 入浴後、タオルで優しく押さえるように水分を拭き取る。 |
| 広めに塗る | 目に見えない菌も退治するため。 | 発疹の縁から指2本分くらい外側まで塗る。 |
| 毎日続ける | 菌の増殖サイクルを断ち切るため。 | 医師の指示通り、1日1回または2回、決まった時間に塗る。 |
症状が消えても治療を続ける理由
治療を開始して1~2週間もすると、かゆみや赤みが引き、見た目はすっかり良くなったように感じることがありますが、ここで治療をやめてしまうのは絶対に禁物です。症状が消えても、皮膚の角層の奥深くには白癬菌がまだ生き残っています。
菌を完全に死滅させるためには、症状が消えてから、さらに最低でも1ヶ月以上は根気よく薬の塗布を続ける必要で、この期間を守れるかどうかが、再発を防ぐ上で最も重要な分かれ道です。
塗り薬で改善しない場合の飲み薬
通常は外用薬で治療可能ですが、症状が非常に広範囲に及んでいる場合、炎症が強く外用薬だけでは抑えきれない場合、あるいは皮膚が厚くなっていて外用薬の浸透が悪い場合には、抗真菌薬の内服薬(飲み薬)が処方されることがあります。
内服薬は、血液を介して体の中から皮膚に作用するため、外用薬が届きにくい角層の深部にも効果を発揮します。ただし、肝機能への影響など副作用の可能性も考慮し、定期的な血液検査を行いながら慎重に投与することが大切です。
内服薬の使用は、必ず医師の判断と管理のもとで行います。
再発させないための日常生活の注意点
股部白癬の治療を成功させ、二度と繰り返さないためには、薬物治療と並行して日常生活の習慣を見直すことが極めて重要です。白癬菌が好む環境を自ら作らないように心がけることで、再発のリスクを大幅に減らすことができます。
患部を清潔・乾燥に保つ
再発予防の基本中の基本は、股部を常に清潔で乾燥した状態に保つことで、汗をかいたら、そのままにせず、こまめにシャワーを浴びるか、濡れたタオルで優しく拭き取りましょう。特に運動後は速やかに汗を流すことが大切です。
入浴時には、石鹸やボディソープをよく泡立て、ナイロンタオルなどでゴシゴシ擦らず、手で優しく洗うように心がけてください。洗浄後は、水分が残らないようにタオルでしっかりと、優しく押さえるように拭き取ります。
ドライヤーの冷風を軽くあてるのも効果的です。
下着選びのポイント
毎日身につける下着は、股部の環境に直接影響を与え、再発予防のためには、下着の素材と形状に注意を払うことが重要です。締め付けの強い窮屈な下着は、通気性を妨げ、摩擦による刺激も起こすため避けましょう。
ゆとりのあるサイズで、通気性と吸湿性に優れた素材を選ぶのが理想です。
下着選びの比較
| 推奨される素材・形状 | 避けるべき素材・形状 |
|---|---|
| 綿(コットン)、絹(シルク)などの天然素材 | ポリエステル、ナイロンなどの化学繊維 |
| トランクス、ゆったりしたボクサーパンツ | ブリーフ、ガードルなど締め付けの強いもの |
衣類やタオルの洗濯・管理
白癬菌は、衣類やタオルに付着して生き残ることがあるので、下着やズボン、タオルは毎日交換し、こまめに洗濯しましょう。洗濯自体で菌を完全に死滅させることは難しいですが、他の衣類への菌の拡散を防ぐ効果はあります。
家族に股部白癬や足白癬の人がいる場合は、タオルやバスマットの共用は避けてください。
白癬菌は乾燥に弱いため、洗濯物は天日干しでしっかりと乾かし、また、浴室の足ふきマットも菌の温床になりやすいため、頻繁に洗濯し、乾燥させることが大事です。
足白癬(水虫)も同時に治療する
股部白癬の患者さんの多くが、足白癬(水虫)を合併しています。足の水虫を放置していると、そこが感染源となり、いくら股部の治療をしても、再び自分の手などを介して菌が運ばれ、再発を繰り返すことになります。
悪循環を断ち切るためには、足の指の間、足の裏、かかとなどをチェックし、もし水虫の症状があれば、股部と同時に治療を開始することが絶対に必要です。
両方を根気よく治療し、完治させることが、股部白癬の再発を防ぐための重要な鍵となります。
注意すべき体の部位
- 足の指の間
- 足の裏
- かかと
- 爪
再発予防を強化する生活習慣の改善
治療によって症状が改善した後も、油断は禁物で、股部白癬の再発を防ぐためには、日々の生活の中に潜むリスク要因を理解し、それを排除していく意識が大切です。
菌が再び増殖する隙を与えないための、一歩進んだ生活習慣改善について考えてみましょう。
運動後や入浴後のケア
運動で汗をかいた後は、白癬菌にとって最高の繁殖環境が整います。トレーニングウェアは通気性の良いものを選び、運動後はできるだけ早くシャワーを浴びて汗を流しましょう。
すぐにシャワーを浴びられない場合は、汗を拭き取るボディシートなどを活用するのも一つの方法です。
また、入浴後も注意が必要で、体を拭いた後は、すぐに下着や衣服を身につけず、少し時間をおいて股部を自然乾燥させることで、湿気がこもるのを防げます。
入浴方法の見直し
体を清潔に保つための入浴ですが、洗い方によっては皮膚のバリア機能を損ない、かえって菌の侵入を許す原因になることがあります。体を洗う際は、殺菌作用の強い石鹸を使いすぎたり、ナイロンタオルで力任せに擦ったりするのは避けましょう。
過度な洗浄は、皮膚を守るために必要な皮脂まで奪い去ってしまいます。弱酸性のボディソープをよく泡立て、なでるように優しく洗い、すすぎ残しがないようにしっかりと洗い流すのが正しい入浴方法です。
入浴時の注意点
| 項目 | 良い例 | 避けるべき例 |
|---|---|---|
| 洗浄剤 | 弱酸性で保湿成分のあるもの | 強い殺菌・脱脂作用のあるもの |
| 洗い方 | 手や柔らかい綿のタオルで優しく洗う | ナイロンタオルでゴシゴシ擦る |
| 湯温 | 38~40度程度のぬるま湯 | 42度以上の熱いお湯 |
生活全般と免疫力
皮膚の健康は、体全体の健康状態と密接に関連していて、不規則な生活や睡眠不足、栄養バランスの偏った食事、過度なストレスなどは、体の免疫力を低下させ、感染症にかかりやすい状態を招きます。
白癬菌も例外ではなく、免疫力が低下していると、少量の菌が付着しただけでも発症しやすくなったり、治りにくくなったりします。
バランスの取れた食事、十分な睡眠、適度な運動を心がけ、ストレスを上手に発散するなど、日頃から自己の免疫力を高く維持することが、根本的な再発予防策です。
免疫力を維持するための生活習慣
- バランスの取れた食事
- 十分な睡眠時間の確保
- 定期的な運動
- ストレス管理
股部白癬に関するよくある質問
ここでは、患者さんから特によく寄せられる股部白癬に関する質問と回答をまとめました。治療や日常生活における疑問や不安の解消にお役立てください。
- 治療にはどのくらいの期間がかかりますか
-
治療期間は、症状の重症度や範囲によって異なりますが、一般的には塗り薬による治療で最低でも1ヶ月から2ヶ月は必要です。
かゆみや赤みなどの自覚症状は、治療開始後1~2週間で軽快することが多いですが、それは表面上の菌が減っただけで、角層の奥深くにはまだ菌が残っているので、ここで治療を中断すると、ほぼ確実に再発します。
見た目がきれいになっても、医師の指示があるまで根気強く治療を続けることが完治のために最も重要です。飲み薬を使用する場合は、さらに長い期間が必要になることもあります。
- 治った後に跡は残りますか
-
通常、適切に治療を行えば、跡が残ることはほとんどありません。
しかし、炎症が非常に強かった場合や、かゆみのために強く掻き壊してしまった場合には、一時的に炎症後色素沈着という形で皮膚が茶色っぽく黒ずむことがあります。
色素沈着は、皮膚の炎症が治まった後にメラニン色素が沈着することによるもので、病気自体が治れば、数ヶ月から半年ほどの時間をかけて徐々に薄くなっていきます。
掻き壊して二次感染を起こした場合は、稀に小さな傷跡として残る可能性もあります。跡を残さないためにも、かゆくても掻かないこと、そして早期に治療を開始することが重要です。
- 自然に治ることはありますか
-
自然に治ることはありません。股部白癬は、白癬菌という真菌が原因の感染症であり、放置しても自然に治癒することはなく、治療せずにいると症状は徐々に悪化し、発疹の範囲が広がっていきます。
かゆみが強いために掻き壊してしまい、そこから細菌が侵入して二次感染を起こすリスクもあり、また、治療が遅れるほど、皮膚の色素沈着が残りやすくなる可能性も高まります。
症状に気づいたら、自然治癒を期待せずに、できるだけ早く皮膚科を受診し治療を開始してください。
- 薬を塗ったら、かぶれたり刺激を感じたりします。どうすればよいですか
-
すぐに薬の使用を中止し、処方を受けた医師に相談しましょう。
処方された抗真菌薬によって、かぶれ(接触皮膚炎)や刺激感が出ることがあり、その場合は、自己判断で使い続けずに、速やかに医療機関に連絡することが大切です。
医師は、症状を診察した上で、別の種類の抗真菌薬に変更したり、かぶれを抑えるための薬を併用したりするなどを判断します。薬が合わないと感じた場合は、我慢は禁物です。
以上
参考文献
Toyama S, Tominaga M, Takamori K. Treatment options for troublesome itch. Pharmaceuticals. 2022 Aug 19;15(8):1022.
Hiruma J, Ogawa Y, Hiruma M. T richophyton tonsurans infection in Japan: Epidemiology, clinical features, diagnosis and infection control. The Journal of Dermatology. 2015 Mar;42(3):245-9.
Mandal S, Tyagi P, Jain AV, Yadav P. Advanced formulation and comprehensive pharmacological evaluation of a novel topical drug delivery system for the management and therapeutic intervention of Tinea Cruris (Jock Itch). Journal of Nursing. 2024;71(03).
Shiraki Y, Hiruma M, Inoue A, Matsushita A, Ogawa H. A short-term treatment of tinea corporis and tinea cruris with oral terbinafine. Nippon Ishinkin Gakkai Zasshi. 2003 Apr 30;44(2):121-5.
El‐Gohary M, van Zuuren EJ, Fedorowicz Z, Burgess H, Doney L, Stuart B, Moore M, Little P. Topical antifungal treatments for tinea cruris and tinea corporis. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2014(8).
Van Zuuren EJ, Fedorowicz Z, El‐Gohary M. Evidence‐based topical treatments for tinea cruris and tinea corporis: a summary of a Cochrane systematic review. British Journal of Dermatology. 2015 Mar 1;172(3):616-41.
Weinstein A, Berman B. Topical treatment of common superficial tinea infections. American family physician. 2002 May 15;65(10):2095-103.
Smith EB. Topical antifungal drugs in the treatment of tinea pedis, tinea cruris, and tinea corporis. Journal of the American Academy of Dermatology. 1993 May 1;28(5):S24-8.
Boonk W, De Geer D, De Kreek E, Remme J, Van Huystee B. Itraconazole in the treatment of tinea corporis and tinea cruris: comparison of two treatment schedules: Itraconazol bei der Behandlung der Tinea corporis und Tinea cruris: Vergleich zweier Behandlungsschemata. Mycoses. 1998 Dec;41(11‐12):509-14.
Katsambas A, Antoniou CH, Frangouli E, Rigopoulos D, Vlachou M, Michailidis D, Stratigos J. Itraconazole in the treatment of tinea corporis and tinea cruris. Clinical and experimental dermatology. 1993 Jul;18(4):322-5.