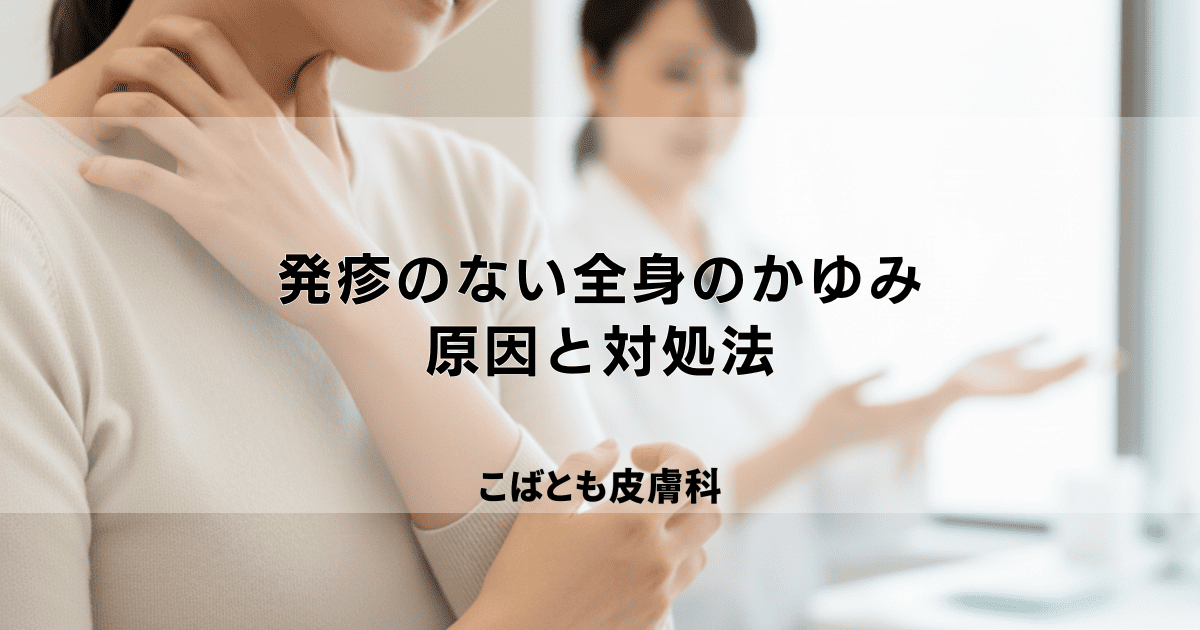目に見える発疹や湿疹はないのに、なぜか全身がむずむずとかゆい経験はありませんか。多くの方が経験するこの不快な症状は、つい我慢してしまいがちですが、体からの重要なサインである可能性があります。
単なる肌の乾燥が原因であることも多い一方で、背後にはアレルギー反応や、ときには内臓の病気が隠れていることもあります。
この記事では、発疹を伴わない全身のかゆみがなぜ起こるのか、多様な原因、ご自身でできる効果的な対処法や、専門医への相談を考えるべきタイミングについて、説明します。
この記事の執筆者

小林 智子(こばやし ともこ)
日本皮膚科学会認定皮膚科専門医・医学博士
こばとも皮膚科院長
2010年に日本医科大学卒業後、名古屋大学医学部皮膚科入局。同大学大学院博士課程修了後、アメリカノースウェスタン大学にて、ポストマスターフェローとして臨床研究に従事。帰国後、同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンターにて、糖化と肌について研究を行う。専門は一般皮膚科、アレルギー、抗加齢、美容皮膚科。雑誌を中心にメディアにも多数出演。著書に『皮膚科医が実践している 極上肌のつくり方』(彩図社)など。
こばとも皮膚科関連医療機関
発疹がないのに全身がかゆい、正体とは
発疹という明確な皮膚の変化がないにもかかわらず、全身にかゆみを感じるのは不思議に思うかもしれませんが、皮膚の表面下では、かゆみを起こすさまざまな変化が起こっています。
皮膚のバリア機能の低下
皮膚の一番外側にある厚さわずか0.02mmの角層は、外部の刺激物やアレルゲン、細菌などが体内に侵入するのを防ぎ、同時に体内の水分が過剰に蒸発するのを防ぐ重要な役割を担っていて、皮膚のバリア機能と呼びます。
この機能は、角層細胞がレンガのように積み重なり、隙間をセラミドなどの細胞間脂質がセメントのように埋めることで保たれています。
しかし、加齢、空気の乾燥、紫外線、誤った洗浄方法などによって角層がダメージを受け、セラミドが減少すると、バリア機能が低下し、外部からのわずかな刺激にも皮膚が過敏に反応するようになり、かゆみを感じやすくなるのです。
また、水分が逃げやすくなるため皮膚が乾燥し、さらなるかゆみを誘発するという悪循環に陥ることも少なくありません。
かゆみを起こす皮膚の状態
| 状態 | 主な特徴 | かゆみへの影響 |
|---|---|---|
| バリア機能の低下 | 角層のセラミドが減少し、構造が乱れる。 | 刺激物が侵入しやすくなり、かゆみを感じる神経が興奮する。 |
| 乾燥(ドライスキン) | 皮膚の水分と皮脂が不足し、カサカサする。 | 皮膚表面がひび割れ、かゆみ神経が末端まで伸びて過敏になる。 |
| 微小な炎症 | 見た目には分かりにくいレベルの炎症。 | かゆみを引き起こすヒスタミンなどの化学伝達物質が放出される。 |
目に見えない皮膚の炎症
発疹として現れていなくても、皮膚の内部でごく微弱な炎症が起きていることがあります(微小炎症)。
バリア機能が低下した皮膚にホコリや化学物質などの刺激物が侵入すると、体を守るために免疫細胞である肥満細胞などが働き、炎症を起こす化学伝達物質(ヒスタミンなど)を放出します。
ヒスタミンが、かゆみを伝える知覚神経(C線維)の末端にある受容体と結合することで、脳に信号が送られ、私たちはかゆみとして認識します。
つまり、赤みやブツブツといった見た目の変化がなくても、皮膚の内部ではかゆみの原因となる炎症反応が静かに進行している可能性があるのです。
神経の過敏性がかゆみを起こす
かゆみを感じるのは、皮膚に広く分布している知覚神経の働きによるものです。
健康な皮膚では、知覚神経の末端は表皮の途中で留まっていますが、皮膚が乾燥したり、バリア機能が低下したりすると、本来は角層の下に留まっているはずの知覚神経線維が、皮膚の表面近く、角層のすぐ下まで異常に伸びてきてしまいます。
通常では何でもないような些細な刺激、衣類の摩擦や温度の変化、汗などに対しても、神経が過剰に反応してしまい、強いかゆみとして感じられるようになります。
一度かゆみを感じて掻いてしまうと、物理的な刺激がさらに神経を過敏にし、かゆみを増幅させてしまうという悪循環に陥りがちです。
日常生活に潜む全身のかゆみの原因
特別な病気でなくても、普段の生活習慣や環境の中に、全身のかゆみを起こす原因は数多く潜んでいて、多くの場合、原因を見直すだけで、症状が大きく改善することもあります。
皮膚の乾燥(皮脂欠乏症)
発疹のない全身のかゆみの最も一般的な原因は、皮膚の乾燥です。空気が乾燥する秋から冬にかけて症状が悪化する傾向があります。
また、加齢に伴い、皮膚の水分を保つ天然保湿因子(NMF)や、皮膚を保護する皮脂の分泌量が減少することも、乾燥を助長し、この状態を皮脂欠乏症と呼び、高齢者では老人性乾皮症とも言われます。
皮膚が乾燥すると、表面がカサカサして粉をふいたようになり、外部からの刺激に非常に敏感になり、すねや腰まわり、背中など、もともと皮脂の分泌が少ない部位にかゆみが出やすいのが特徴です。
かゆみを感じやすい身体の部位
| 部位 | 皮脂腺の分布 | かゆみの出やすさ |
|---|---|---|
| すね、腕の外側 | 少ない | 非常に乾燥しやすく、衣服との摩擦も多いため、かゆみが出やすい代表的な部位。 |
| 背中、腰まわり | 比較的少ない | 手が届きにくく保湿ケアがおろそかになりがちで、乾燥とかゆみが進行しやすい。 |
| 脇腹 | 少ない | 衣類の縫い目やタグの刺激も加わり、乾燥によるかゆみが起こりやすい。 |
間違ったスキンケアと洗浄
肌を清潔に保つための毎日の入浴や洗顔が、逆にかゆみの原因となっていることもあり、熱いお湯(42度以上)での長時間の入浴は、皮膚の潤いを保つために必要な皮脂やセラミドまで洗い流してしまいます。
また、ナイロンタオルなどでゴシゴシと強く体を洗う行為は、角層を物理的に傷つけ、バリア機能を著しく低下させます。
洗浄力の強いアルカリ性の石鹸やボディソープの使用も、皮膚の乾燥を招く一因なので、肌と同じ弱酸性で、アミノ酸系などのマイルドな洗浄成分の洗浄剤を選び、手で優しく泡立てて洗うことが大切です。
- 熱すぎるお湯(42度以上)での入浴
- 15分以上の長時間の入浴やシャワー
- ナイロンタオルや硬いブラシでの摩擦
- 洗浄力の強いアルカリ性の洗浄剤の使用
- 入浴後、時間が経ってからの保湿
衣類や寝具による刺激
直接肌に触れる衣類や寝具の素材も、かゆみに大きく影響し、ウールやアクリルなどの化学繊維、麻などの硬い繊維は、皮膚への物理的な刺激となり、チクチク感やかゆみを誘発することがあります。
また、締め付けの強い下着やタイトな衣類は、摩擦によって皮膚に負担をかけ、バリア機能の低下を招き、吸湿性の悪いポリエステルなどの素材は、汗が蒸発しにくく、肌表面に留まることであせもやかゆみの原因となります。
肌触りの良い木綿(コットン)やシルクなど、天然素材でゆったりとしたデザインのものを選びましょう。
肌への刺激となりうる衣類の素材
| 素材の種類 | 特徴 | 肌への影響 |
|---|---|---|
| ウール、化学繊維(アクリルなど) | 繊維が太く硬い場合があり、静電気を帯びやすい。 | 物理的な刺激でチクチク感やかゆみを誘発しやすい。 |
| ポリエステル | 吸湿性が低く、速乾性が高い。 | 汗が蒸発しにくく、蒸れてかゆみの原因になることがある。 |
| 木綿(コットン) | 吸湿性が高く、通気性に優れ、肌触りが柔らかい。 | 肌への刺激が少なく、アレルギーも起こしにくいため推奨される。 |
食生活や生活習慣の乱れ
皮膚の健康は、体の内側からの影響も大きく受けます。香辛料の多い食事やアルコールの摂取は、血管を拡張させて血行を促進し、体温を上昇させることでかゆみを強く感じさせることがあります。
また、睡眠不足や精神的なストレスは、自律神経やホルモンバランスを乱し、かゆみに対して神経を過敏にさせたり、免疫機能を低下させたりすることが知られています。
栄養バランスの取れた食事、十分な睡眠、適度な運動など、規則正しい生活を心がけることが、健やかな皮膚を保つ上で重要です。
全身のかゆみは内臓からのSOSかもしれない
セルフケアをしても一向に改善しない、あるいは日に日にかゆみが強くなる場合、原因は皮膚そのものではなく、内臓の病気にある可能性を考える必要があります。ここでは、かゆみを伴う代表的な内臓の病気について解説します。
肝臓の病気とのかかわり
肝臓の機能が低下すると、胆汁の流れが滞り、本来なら肝臓で処理されて腸に排泄されるはずの胆汁酸やビリルビンといった物質が血液中に増加し、皮膚の末梢神経を刺激することで、非常に強いかゆみが生じると考えられています。
慢性肝炎や肝硬変、原発性胆汁性胆管炎などの疾患では、かゆみが初期症状として現れることもあります。皮膚が黄色くなる黄疸や、体がだるいといった症状を伴う場合は、速やかに内科や消化器内科を受診することが大切です。
肝機能低下に伴う主な症状
| 症状 | 概要 |
|---|---|
| 全身の強いかゆみ | 特に夜間に強くなり、睡眠を妨げることもある。掻き壊しが目立つ。 |
| 黄疸(おうだん) | 皮膚や白目が黄色くなる。ビリルビンが蓄積するため。 |
| 全身倦怠感 | 体が重く、疲れやすい。食欲不振を伴うことも多い。 |
腎臓の機能低下が招くかゆみ
腎臓は、血液をろ過して老廃物を尿として排泄する重要な臓器です。
慢性腎不全などで腎臓の機能が著しく低下すると、体内に尿毒素と呼ばれる老廃物やカルシウム、リンなどが過剰に蓄積し、かゆみを起こす複数の原因(神経への直接的な刺激、かゆみを誘発する物質の放出など)に関与すると考えられています。
また、腎機能の低下は汗腺の萎縮を招き、皮膚の乾燥を悪化させることも、かゆみの大きな原因です。人工透析を受けている患者さんの多くが、つらいかゆみに悩まされています。
糖尿病による皮膚トラブル
糖尿病は、高血糖の状態が続くことで全身の血管や神経に障害をもたらす病気です。
高血糖は体内の水分バランスを崩し脱水傾向を招くため、皮膚の乾燥を起こしやすくなり、また、合併症である末梢神経障害によって、かゆみを感じる神経が正常に機能しなくなり、かゆみや痛みを感じやすくなることもあります。
さらに、糖尿病の患者さんは免疫力が低下しやすく、皮膚のバリア機能も弱まるため、カンジダなどの真菌や細菌による感染症を起こしやすくなり、かゆみの原因となることも少なくありません。
血糖コントロールを良好に保つことが、皮膚のトラブルを防ぐ上で最も重要です。
甲状腺の異常と皮膚症状
喉仏の下あたりにある甲状腺は、体の新陳代謝を活発にするホルモンを分泌しています。
甲状腺機能亢進症(バセドウ病など)では、新陳代謝が過剰になり、全身の血流が増加し皮膚の温度が上昇するため、わずかな刺激にも敏感になり、発汗も増えるためかゆみが出ることがあります。
甲状腺機能低下症(橋本病など)では、新陳代謝が低下し、汗や皮脂の分泌が著しく減少し、皮膚がひどく乾燥してカサカサになり(粘液水腫性皮膚)、強いかゆみを伴うことがあります。
血液疾患や悪性腫瘍
頻度は高くありませんが、見逃してはならないかゆみの原因が、血液の病気やがんなどです。
鉄欠乏性貧血では、皮膚の栄養状態が悪化し、乾燥やかゆみを起こすことがあり、また、血液のがんの一種である悪性リンパ腫(特にホジキンリンパ腫)では、特徴的な強いかゆみが初期症状として現れることがあります。
入浴後など体が温まったときに特にひどくなる傾向があります。その他、内臓のがんが原因で、デルマドロームと呼ばれる特殊な皮膚症状の一つとして、頑固なかゆみが現れることもあります。
薬剤やアレルギーが原因となる全身のかゆみ
普段服用している薬や、特定の物質に対するアレルギー反応によって全身のかゆみが起こされることがあり、原因がはっきりしないかゆみが続く場合は、このような可能性も視野に入れる必要があります。
薬の副作用としてのかゆみ
病気の治療のために服用している薬が、副作用としてかゆみを起こすことがあります(薬剤性掻痒(そうよう)症)。特定の薬を飲み始めてから数日〜数週間後にかゆみが出現した場合に疑われます。
原因となる薬は多岐にわたり、血圧を下げる薬、痛み止め、抗生物質、一部の抗がん剤、痛風の治療薬などが知られていて、薬疹のような発疹を伴うことが多いですが、発疹がなくかゆみだけが現れることもあります。
自己判断で薬を中止せず、必ず処方した医師や薬剤師に相談してください。
かゆみを起こす可能性のある主な薬剤
| 薬剤の種類 | 代表的な薬 |
|---|---|
| 降圧薬 | カルシウム拮抗薬、ACE阻害薬など |
| 非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs) | ロキソプロフェン、イブプロフェンなど |
| 抗生物質 | ペニシリン系、セフェム系、マクロライド系など |
食物や金属によるアレルギー反応
特定の食べ物や金属に対するアレルギー反応が、全身のかゆみとして現れることがあり、通常、食物アレルギーは蕁麻疹(じんましん)のような膨らみを伴う発疹が特徴ですが、稀にかゆみだけが生じることもあります。
また、歯科治療で使われる金属や、アクセサリーに含まれる金属が汗などでイオン化して体内に吸収され、血液を介して全身に運ばれることで、全身性金属皮膚炎としてかゆみを起こすことも報告されています。
原因となる物質を特定し、避けることが根本的な解決策です。
- 甲殻類(エビ、カニ)
- ソバ、小麦、卵、乳製品
- 果物類(キウイ、マンゴーなど)
- ニッケル、コバルト、クロム(金属)
- ラテックス(天然ゴム)
汗やハウスダストの影響
アトピー性皮膚炎の素因を持つ方は、皮膚のバリア機能がもともと低いため、汗やハウスダスト(ダニのフンや死骸、ホコリ)、花粉などがアレルゲンとなり、かゆみを起こしやすい傾向があります。
汗に含まれるアンモニアなどの成分そのものが皮膚への刺激となったり、汗が蒸発する際に皮膚の水分を奪って乾燥を助長したりすることで、かゆみが誘発されます。
また、ハウスダストなどがバリア機能の低下した皮膚から容易に侵入すると、アレルギー反応が起こり、強いかゆみが生じます。こまめに汗を拭き、シャワーで流し、室内を清潔に保つことが対策として有効です。
全身のかゆみを和らげるセルフケア
つらい全身のかゆみは、日常生活の工夫によってある程度和らげることが可能で、皮膚科での治療と並行して、ご自身でできるケアを実践することは、症状の改善と再発予防のためにとても大切です。
保湿ケアの基本とポイント
発疹のないかゆみのケアで最も重要なのが保湿です。皮膚の乾燥を防ぎ、バリア機能を正常に保つことで、外部からの刺激を受けにくい、健やかな状態を維持します。
保湿剤は、入浴後5分以内の、まだ皮膚がしっとりと潤っているうちに塗るのが最も効果的で、手のひらにたっぷりと取り、擦り込まずに優しく皮膚のしわに沿って広げるように塗りましょう。
特に乾燥しやすいすねや腕、背中だけでなく、全身にまんべんなく塗ることが大切です。
保湿剤の成分と特徴
| 主な成分 | 働き | 特徴 |
|---|---|---|
| ヘパリン類似物質 | 水分を保持し、血行を促進する。 | 保湿力が高く、乾燥によるかゆみに効果的。医療用でも多用される。 |
| セラミド | 角層の細胞間脂質を補い、バリア機能を高める。 | 敏感肌や乾燥肌の根本的な改善に役立つ。 |
| 尿素 | 硬くなった角質を柔らかくし、水分を取り込む。 | かかとなど角質が厚い部分に有効だが、刺激を感じることもある。 |
入浴時に気をつけたいこと
毎日の入浴習慣を見直すことも、かゆみ対策には欠かせません。お湯の温度は38〜40度のぬるめに設定し、長湯は避けて15分以内を目安にしましょう。
体を洗う際は、低刺激性の石鹸やボディソープをよく泡立て、ナイロンタオルなどは使わずに手で優しくなでるように洗います。背中など、手が届きにくい場所も柔らかい綿のタオルを使うなど工夫が必要です。
すすぎ残しはかゆみの原因になるため、シャワーで十分に洗い流してください。入浴剤を使う場合は、保湿成分が配合されたものを選ぶと良いでしょう。
かゆみを悪化させない生活習慣
かゆみを感じたときに、掻きむしってしまうと皮膚が傷つき、炎症が悪化してさらにかゆみが強くなるという悪循環に陥るので、かゆいときは、掻く代わりに冷たいタオルやタオルで包んだ保冷剤を当てて冷やすと、一時的にかゆみが和らぎます。
爪は常に短く切り、やすりで滑らかにしておきましょう。室内では、加湿器などを使って適切な湿度(50〜60%)を保つことも乾燥対策に有効です。
また、アルコールや香辛料など、体を温めてかゆみを増強させる飲食物は、症状が強いときは控えるようにしましょう。
- 掻かずに冷やす
- 爪は短く清潔に
- 室内の加湿
- 刺激の強い飲食物を避ける
- 十分な睡眠とストレス管理
皮膚科で行う検査と治療
セルフケアを続けてもかゆみが改善しない場合や、原因がはっきりしない場合は、皮膚科に相談することをお勧めします。皮膚科では、詳細な問診や必要な検査を通じてかゆみの原因を特定し、一人ひとりの症状に合わせた専門的な治療を行います。
問診で伝えるべき重要な情報
正確な診断のためには、患者さんからの情報が非常に重要です。診察の際には、以下の点についてできるだけ詳しく医師に伝えてください。
診察時に医師に伝えるべきこと
| 項目 | 伝える内容の例 |
|---|---|
| 症状の始まりと経過 | いつからかゆいか、だんだん強くなっているか、特定の季節に関係あるか。 |
| かゆみの特徴 | 一日中かゆいか、夜間に強いか、チクチク・ムズムズするかなど。 |
| 服用中の薬 | お薬手帳を持参する。サプリメントや漢方薬も伝える。 |
| 既往歴・家族歴 | 肝臓病、腎臓病、糖尿病、アレルギー疾患、がんなど。家族のアレルギー歴も。 |
血液検査でわかること
全身のかゆみが内臓疾患によるものではないかを確認するために、血液検査を行うことがあります。
検査により、肝臓(AST, ALT, γ-GTPなど)や腎臓(BUN, クレアチニンなど)の機能、血糖値やHbA1c、甲状腺ホルモンの値、貧血の有無、炎症反応(CRPなど)を調べることができます。
また、アレルギーが疑われる場合は、特定のアレルゲンに対するIgE抗体の値を測定することもあります。血液検査は、目に見えない体の中の変化を捉え、かゆみの根本的な原因を特定するために非常に有用な手段です。
全身のかゆみに対する専門的な治療法
皮膚の乾燥が主な原因の場合は、ヘパリン類似物質や尿素などが配合された医療用の保湿剤を処方し、かゆみが強い場合には、かゆみを抑える抗ヒスタミン薬や抗アレルギー薬の内服薬を用います。
最近では、眠気の副作用が少ない第二世代の抗ヒスタミン薬が主流です。掻き壊して湿疹になっている部分には、炎症を抑えるステロイドの塗り薬を短期的に使用することもあります。
内臓疾患が原因の場合は、皮膚科での対症療法と並行して、原因となっている病気の治療を専門の診療科で行うことが最も重要です。
難治性のかゆみに対する光線療法
保湿や内服薬、外用薬で十分に効果が得られない、特に腎臓病や肝臓病に伴う頑固なかゆみに対しては、光線療法(紫外線療法)が選択肢となることがあります。
これは、特定の波長の紫外線を皮膚に照射することで、かゆみを伝える神経の過剰な働きを抑制したり、皮膚の免疫反応を調整したりする治療法です。
ナローバンドUVB療法などが代表的で、週に数回の通院が必要となりますが、生活の質を大きく改善する効果が期待できます。
こんなサインは要注意 すぐに皮膚科へ
発疹のない全身のかゆみは、ありふれた症状だからと軽視されがちです。しかし、中には早急な対応が必要なケースもあり、以下のようなサインが見られる場合は、自己判断で様子を見ずに、できるだけ早く皮膚科を受診してください。
かゆみが日に日に強くなる
最初は気にならない程度だったかゆみが、セルフケアをしても収まらず、日を追うごとに我慢できないほど強くなる場合は注意が必要です。
特に、夜間に強くなるかゆみは、肝臓や腎臓の病気、あるいは悪性リンパ腫などが関連していることもあるため、放置しないことが大切です。症状の悪化は、体が発する重要な警告と捉えましょう。
市販薬を1週間以上試しても改善しない
市販のかゆみ止めクリームや保湿剤を1週間以上試しても、症状が全く改善しない、あるいは悪化するようであれば、かゆみは単純な乾燥だけが原因ではない可能性があります。
市販薬で対応できる範囲を超えていると考え、専門医による正確な診断と治療を受けることが、早期解決への近道です。だらだらと市販薬を使い続けることで、診断が遅れてしまうこともあります。
睡眠を妨げるほどのかゆみ
かゆみのために夜中に何度も目が覚めてしまう、あるいは布団に入るとかゆみが増してなかなか寝付けないという状態は、生活の質を著しく損ないます。
睡眠不足は、日中の集中力低下や倦怠感につながるだけでなく、心身の健康に悪影響を及ぼします。また、ストレスを増大させて、さらにかゆみを悪化させるという悪循環を生み出します。
専門的な治療でかゆみをコントロールし、質の良い睡眠を取り戻すことが重要です。
受診を急ぐべきかゆみ以外の症状
| 症状 | 考えられる背景 |
|---|---|
| 急な体重減少 | 悪性腫瘍(がん)、甲状腺機能亢進症、糖尿病など。 |
| 発熱、ひどい倦怠感、寝汗 | 内臓疾患や感染症、悪性リンパ腫など。 |
| 皮膚や白目が黄色くなる(黄疸) | 肝臓や胆道の病気。 |
他の症状(体重減少、だるさなど)を伴う場合
かゆみだけでなく、原因不明の体重減少(半年で5%以上)、ひどい疲労感やだるさ、38度以上の発熱が続く、大量の寝汗をかく、食欲不振といった全身症状を伴う場合は、注意が必要です。
このような症状は、悪性リンパ腫やその他のがん、重篤な内臓疾患など、見過ごすことのできない病気のサインである可能性があります。迷わず、速やかに皮膚科または内科を受診してください。
発疹のない全身のかゆみに関するよくある質問
- ストレスだけで全身がかゆくなることはありますか?
-
強い精神的ストレスは、自律神経のバランスを崩し、かゆみを感じる神経を過敏にさせたり、かゆみを起こす物質を体内で放出させたりすることがあります。
皮膚に明らかな異常がなくても強いかゆみを感じることがあり、これを心因性掻痒症と呼びます。
ただし、かゆみの原因が本当にストレスだけなのかを判断するには、まず皮膚の乾燥や内臓疾患など、他の身体的な原因がないことを専門医が診察した上で判断する必要があります。
- 年齢とともにかゆみは増えるのでしょうか?
-
加齢に伴い、皮膚の水分を保持するセラミドや天然保湿因子が減少し、皮膚を保護する皮脂の分泌量も低下するので、高齢者の皮膚は乾燥しやすく、バリア機能が低下しがちです。
この状態を老人性乾皮症と呼び、発疹のない全身のかゆみの大きな原因となります。
若い頃と同じスキンケアでは保湿が不十分になることが多いため、より保湿力の高い保湿剤を使い、こまめに塗るなど、年齢に応じた丁寧な保湿ケアが大切です。
- かゆい時は温めるべきですか、冷やすべきですか?
-
冷やすのが効果的です。かゆみがある部分を冷やすと、知覚神経の興奮が一時的に鎮まり、血管が収縮することで、かゆみが和らぎます。
清潔なタオルで包んだ保冷剤を当てたり、冷たいシャワーを短時間浴びたりするのが良いでしょう。温めると血行が良くなり、かゆみの神経が刺激されて症状が増すことが多いです。
入浴時や飲酒後にかゆみが強くなるのはこのためです。かゆいときは掻かずに冷やす、ということを覚えておいてください。
- 子供にも発疹のないかゆみは起こりますか?
-
子供の皮膚は大人に比べて厚さが半分から3分の1程度と薄くデリケートで、バリア機能も未熟なため、皮脂の分泌が安定しない思春期前までは乾燥しやすく、外部からの刺激に非常に敏感です。
冬場の乾燥した空気や、衣類の摩擦、汗など、些細なことが原因で全身がかゆくなることがあります。特に、アトピー性皮膚炎の素因があるお子さんは、発疹がはっきりしなくても強いかゆみを感じることがあります。
大人と同様に、徹底した保湿ケアが基本です。症状が続く場合は、小児科または皮膚科にご相談ください。
以上
参考文献
Sari DW, Minematsu T, Yoshida M, Kitamura A, Tomida S, Abe M, Khasanah U, Sanada H. Skin properties of itching without symptoms and associated factors among older adults in long-term care facilities. Drug Discoveries & Therapeutics. 2023 Jun 30;17(3):201-8.
Miyagi T, Kanai Y, Murotani K, Okubo Y, Honma M, Kobayashi S, Seishima M, Mizutani Y, Kitabayashi H, Imafuku S. Itch as a critical factor in impaired health-related quality of life in patients with plaque psoriasis achieving clear or almost-clear skin: analysis of the single-arm, open-label, multicenter, prospective ProLOGUE study. JAAD international. 2022 Sep 1;8:146-53.
Itakura A, Tani Y, Kaneko N, Hide M. Impact of chronic urticaria on quality of life and work in Japan: results of a real‐world study. The Journal of dermatology. 2018 Aug;45(8):963-70.
Torisu-Itakura H, Anderson P, Piercy J, Pike J, Sakamoto A, Kabashima K. Impact of itch and skin pain on quality of life in adult patients with atopic dermatitis in Japan: results from a real-world, point-in-time, survey of physicians and patients. Current Medical Research and Opinion. 2022 Aug 3;38(8):1401-10.
Nakahara T, Noto S, Matsukawa M, Konishi Y, Toda R, Michikami D, Murota H. Habitual Scratching in Atopic Dermatitis and Its Association with Disease Severity: Findings from Japanese Health Insurance Claims and App-Based Data. Dermatology and Therapy. 2025 Aug 21:1-9.
Zambrano A, Weinberger T. ALL THAT ITCHES ISN’T ECZEMA. Annals of Allergy, Asthma & Immunology. 2024 Nov 1;133(6):S207.
Lohani S, Tachamo N, Nazir S. Rash that itches and is all over: look beyond the skin. Journal of Community Hospital Internal Medicine Perspectives. 2016 Jan 1;6(5):32651.
Bernhard JD. Not all itches arise in the skin. British Journal of Dermatology. 2015 Feb 1;172(2):309-11.
Elston DM. What Causes Itching Without Any Rash?. InCurbside Consultation in Pediatric Dermatology 2024 Jun 1 (pp. 251-254). CRC Press.
Lonati D, Zancan A, Giampreti A, Sparpaglione D, Locatelli CA, Manzo L. An insidious skin rash without itch. Clinical Toxicology. 2012 Feb 1;50(2):149-50.