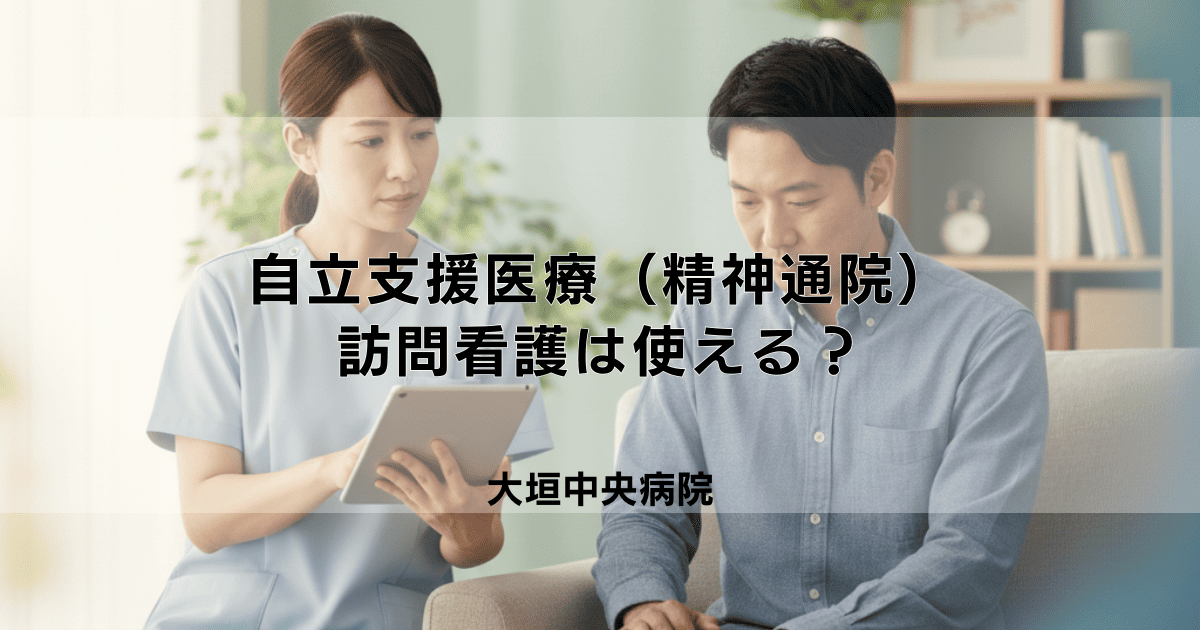精神疾患の治療を続ける中で、医療費の負担が大きくなることがありますが、負担を軽減する公的な制度が自立支援医療(精神通院)です。
制度を利用しながら、ご自宅で専門的なケアを受けられる訪問看護を併用できるのか、疑問に思う方もいるでしょう。
この記事では、自立支援医療(精神通院)を利用して訪問看護を受けるための対象者、料金体系、手続きの流れを詳しく解説します。制度を正しく理解し、ご自身やご家族が安心して在宅療養を続けられるよう、必要な情報を提供します。
自立支援医療(精神通院)の基本概要
まずは、制度の根幹である自立支援医療(精神通院)について基本的な知識を深めましょう。どのような目的で、どのような医療が対象になるのかを理解することが、訪問看護での利用を考える上での第一歩です。
制度の目的と役割
自立支援医療(精神通院)は、精神疾患を理由に継続的な通院治療が必要な方の医療費の自己負担を軽減するための制度です。精神疾患の治療は長期にわたることが多く、経済的な負担が治療の継続を妨げる要因になり得ます。
この制度は、経済的な心配を減らし、誰もが安心して治療を受け続けられる社会を目指すという重要な役割を担っていて、症状の安定や社会復帰を後押しします。
制度の背景には、精神障害のある方の入院医療中心から地域生活中心への移行を国全体で推進してきた歴史があります。地域で自立した生活を送るためには、継続的かつ適切な医療が欠かせません。
自立支援医療(精神通院)が目指すもの
| 目的 | 具体的な役割 |
|---|---|
| 医療費負担の軽減 | 自己負担割合を通常3割から原則1割に引き下げる |
| 治療の継続支援 | 経済的理由による治療の中断を防ぎ、病状の安定化を促す |
| 社会参加の促進 | 安定した治療基盤の上で、地域生活への復帰や維持を支える |
対象となる医療の範囲
制度が適用されるのは、精神疾患の治療に関連する医療全般で、精神科や心療内科での診察、処方される薬代、精神科デイケア、精神科作業療法などが含まれます。
そして、重要な点として、医師が必要と判断した精神科訪問看護もこの制度の対象となることです。その他にも、統合失調症や気分障害の方が、症状に関連して受ける内科や歯科の治療など、主治医が必要と認めたものも対象になる場合があります。
治療に必要な一連の医療サービスを包括的に支えることで、効果的な治療計画の実行を可能にします。ただし、入院医療の費用は対象外で、あくまでも地域での生活を支えるための通院医療に特化した制度です。
自己負担の原則と上限
自立支援医療(精神通院)を利用すると、医療費の自己負担は原則として1割になり、通常、医療保険では自己負担が3割(年齢や所得による)なので、負担が大きく軽減されます。
さらに、世帯の所得に応じて1ヶ月あたりの自己負担額に上限が設けられていて、上限額を超えた分は支払う必要がないため、高額な治療が必要な場合でも安心です。
ここで言う世帯とは住民票上の世帯とは異なり、申請者と同じ医療保険に加入している家族を一つの単位として考えます。父親の社会保険の扶養に入っている場合は、父親を含めた被保険者全員が同一世帯と見なされます。
国民健康保険の場合は、住民票上の世帯がそのまま同一世帯となり、世帯の所得状況によって、自己負担上限額が決定されます。
所得区分ごとの自己負担上限月額
| 世帯の所得区分 | 自己負担上限月額 | 備考 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 0円 | 自己負担はありません |
| 低所得1 | 2,500円 | 市町村民税非課税世帯で本人の収入が80万円以下 |
| 低所得2 | 5,000円 | 市町村民税非課税世帯で本人の収入が80万円超 |
| 中間所得1 | 5,000円 | 市町村民税課税世帯で所得割が3万3千円未満 |
| 中間所得2 | 10,000円 | 市町村民税課税世帯で所得割が3万3千円以上23万5千円未満 |
| 一定所得以上 | 20,000円 | 市町村民税課税世帯で所得割が23万5千円以上(重度かつ継続に該当する場合) |
訪問看護で自立支援医療は利用できるのか
次に、本題である自立支援医療(精神通院)を訪問看護で利用できるのかについて掘り下げます。制度上の位置づけや、なぜ訪問看護が対象になるのかを理解することで、安心してサービスを利用できます。
制度上の位置づけと利用の可否
結論から言うと、自立支援医療(精神通院)は訪問看護で利用でき、精神保健福祉法において、精神科訪問看護は制度の対象となる医療サービスとして明確に位置づけられています。
これは、訪問看護が単なる介助サービスではなく、治療効果を高め、地域生活を支えるための専門的な医療行為であると認められていることを意味します。
主治医が精神症状の管理や在宅での療養支援のために訪問看護が必要だと判断し、訪問看護指示書を発行することが利用の条件です。
指示書に基づき、訪問看護ステーションが計画的なケアを提供することで、、通院が困難な方や地域で孤立しがちな方も、自宅という慣れ親しんだ環境で継続的なケアを受けることが可能になります。
訪問看護が対象となる理由
精神疾患の治療は、病院での診察や服薬だけでなく、地域社会での安定した生活を支える視点が重要です。訪問看護は、看護師や精神保健福祉士などの専門職がご自宅を訪問し、利用者の生活の場で直接的な支援を行います。
病状の確認や服薬管理はもちろん、日常生活での困りごとや対人関係の悩みなど、より生活に密着した課題に対応できるのが大きな強みです。在宅でのケアは、通院治療を補完し、病状の悪化予防や再入院の防止に大きな効果を発揮します。
また、利用者だけでなく、日々支えているご家族からの相談に応じ、介護負担の軽減を図る役割も担います。
訪問看護の主な役割
- 病状や心身の状態の観察
- 内服薬の管理と指導
- 日常生活の支援と相談
- 対人関係の相談
- 家族への支援と助言
医療保険との関係性
精神科訪問看護は、通常、医療保険を利用して提供されます。自立支援医療(精神通院)は、この医療保険を適用した上で、さらに自己負担を軽減する制度です。
まず医療保険が適用され、その自己負担分(通常3割)に対して自立支援医療が適用されて1割負担になる、という二段階の仕組みになっています。
両制度を正しく併用することで、経済的な負担を最小限に抑えながら、必要な訪問看護サービスを受けられます。なお、65歳以上の方などで介護保険の認定を受けている場合、原則として介護保険の訪問看護が優先されます。
しかし、精神科訪問看護については、精神疾患を理由とする場合、年齢にかかわらず医療保険が適用されるのが一般的です。この点は少し複雑なため、ケアマネジャーや訪問看護ステーションの担当者によく確認してください。
自立支援医療で訪問看護を受けるための対象者
どのような人がこの制度を利用して訪問看護を受けられるのでしょうか。対象となる疾患や、医師による必要性の判断など、具体的な条件について確認していきましょう。
対象となる精神疾患
自立支援医療(精神通院)は、特定の診断名だけで決まるわけではなく、精神疾患により継続的な通院治療を必要とする方が広く対象となり、統合失調症、うつ病、双極性障害、不安障害、てんかん、依存症などが含まれます。
統合失調症で幻覚や妄想といった症状があり、服薬管理が難しい方や、うつ病で意欲が低下し、外出が困難になっている方などが考えられます。
大切なのは、治療を継続する必要がある状態かどうかで、症状が比較的安定していても、再発予防のために定期的な通院や服薬が必要な場合も対象です。ご自身の状態が対象になるか不明な場合は、まずは主治医に相談してみましょう。
自立支援医療の対象となる主な精神疾患
| 疾患群 | 具体的な疾患名の例 |
|---|---|
| 統合失調症スペクトラム障害 | 統合失調症、統合失調感情障害など |
| 気分(感情)障害 | うつ病、双極性障害など |
| 神経症性障害、ストレス関連障害 | パニック障害、強迫性障害、PTSDなど |
| てんかん | 全般てんかん、焦点てんかんなど |
| 物質関連障害および行動嗜癖 | アルコール依存症、薬物依存症など |
医師による必要性の判断
制度を利用するためには、主治医が申請者の病状を診断し、自立支援医療(精神通院)による治療の継続が必要であると判断することが大前提です。
その上で、訪問看護の利用を希望する場合は、さらに主治医がその方の生活状況や症状を考慮し、訪問看護による支援が治療計画上、有効であると判断する必要があります。
医師は、服薬を自己管理できるか、日中の活動性は保たれているか、家族や地域との関係性は良好か、といった多角的な視点から必要性を判断します。
通院だけでは十分にサポートできない部分を訪問看護が補うことで、治療効果が高まると期待される場合に、訪問看護の利用が推奨され、医師の判断が記載された診断書(意見書)が申請に必要です。
他の公的制度との関係
精神疾患の治療や生活を支える公的制度は、自立支援医療だけではありません。精神障害者保健福祉手帳は、税金の控除や公共料金の割引、障害者雇用枠での就労など、様々な福祉サービスを受けるための基盤となります。
また、障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限される場合に受け取れる年金であり、経済的な基盤を安定させる上で非常に重要です。制度はそれぞれ目的が異なり、多くの場合、併用が可能です。
自立支援医療で医療費の負担を減らし、精神障害者保健福祉手帳で生活面のサービスを利用し、障害年金で収入を確保するというように、複数の制度を組み合わせることで、より安定した地域生活を送ることができます。
どの制度が利用できるか、市区町村の障害福祉担当窓口や医療機関の相談員に確認することが大切です。
自己負担をさらに軽減する制度
- 重度心身障害者医療費助成制度
- ひとり親家庭等医療費助成制度
- 生活保護の医療扶助
自立支援医療を利用した訪問看護の料金体系
制度を利用する上で最も気になるのが料金でしょう。ここでは、訪問看護の料金がどのように計算され、自立支援医療を適用すると自己負担額がどう変わるのかを解説します。
訪問看護の基本料金
訪問看護の料金は、国が定める診療報酬に基づいて計算し、基本となるのは精神科訪問看護基本療養費で、訪問にかかる時間(20分未満か30分以上か)や提供するサービス内容によって変動します。
その他、早朝(午前8時以前)や夜間(午後6時以降)、深夜(午後10時以降)、休日の訪問、複数名での訪問、緊急時の訪問など、状況に応じて様々な加算がつきます。
精神科重症患者支援管理連携加算は、特に手厚い支援が必要な方に対して、多職種が連携して支援計画を立てた場合に算定され、合計額が総医療費です。
料金体系は複雑なため、契約前に訪問看護ステーションから詳細な説明を受け、見積もりを出してもらうと良いでしょう。
精神科訪問看護の基本報酬(週3日まで)
| 項目 | 報酬(1日につき) | 備考 |
|---|---|---|
| 精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ) | 5,800円 | 同一建物居住者以外への訪問(30分以上) |
| 精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ) | 4,800円 | 同一建物居住者への訪問(30分以上) |
自立支援医療適用時の自己負担額
自立支援医療を適用した場合、総医療費に対する自己負担が原則1割になり、総医療費が10,000円だった場合、医療保険のみでは3,000円の自己負担ですが、自立支援医療を適用すると1,000円に軽減されます。
自己負担額の合計が、所得区分ごとに設定された月額上限額に達した時点で、その月のそれ以上の支払いは発生しません。
例えば、中間所得2(上限月額10,000円)の方が、訪問看護で8,000円、外来診療と薬局で3,000円の自己負担が発生した場合、合計は11,000円ですが、支払うのは上限額である10,000円までです。
訪問看護の料金比較(週1回・30分以上利用の例)
| 制度 | 1回あたりの自己負担額の目安 | 月4回利用した場合の自己負担額 |
|---|---|---|
| 医療保険のみ(3割負担) | 約1,740円 | 約6,960円 |
| 自立支援医療適用(1割負担) | 約580円 | 約2,320円 |
※上記は基本療養費のみで計算した概算です。各種加算により変動します。
自己負担上限額管理票の役割
複数の医療機関や薬局、訪問看護ステーションを利用する場合、それぞれの窓口で支払う自己負担額の合計が月額上限額を超えないように管理する必要があり、そのために使うのが自己負担上限額管理票です。
サービスを利用するたびに管理票を提示し、支払った金額を記録してもらい、合計額が上限に達したら、その月はそれ以上自己負担を支払う必要がなくなります。
管理票を提示し忘れると、上限額を超えて支払ってしまう可能性があるので、必ず受給者証と一緒に携帯し、会計時に提示するようにしましょう。もし紛失した場合は、速やかに市区町村の窓口に連絡し、再発行の手続きを行ってください。
自立支援医療の申請から訪問看護開始までの手続き
実際に制度を利用するためには、どのような手続きを踏めばよいのでしょうか。申請から訪問看護の利用開始までの流れを順を追って説明します。
相談から申請窓口の確認
まずは、主治医や医療機関のソーシャルワーカー、またはお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口に相談することから始め、制度の詳しい説明を受け、ご自身が対象になるかどうかを確認します。
医療機関のソーシャルワーカーは、制度の専門家であり、申請手続きの具体的なアドバイスや書類作成のサポートをしてくれる頼れる存在です。
申請手続きは、原則としてお住まいの市区町村の担当窓口で行いますが、どこに相談すればよいか分からない場合は、まず主治医に尋ねてみるのが良いでしょう。
申請窓口
- 市区町村の障害福祉課
- 保健センター
- 精神保健福祉センター
必要書類の準備と提出
申請にはいくつかの書類が必要です。最も重要なのは、主治医に作成してもらう診断書(自立支援医療用)で、診断書は作成に時間がかかる場合があるため、早めに依頼しましょう。有効期間は通常、作成日から3ヶ月程度です。
診断書には、病名や症状、治療方針とともに、訪問看護の必要性についても記載してもらう必要があります。その他、申請書、健康保険証の写し、世帯の所得状況が確認できる書類(課税証明書など)が必要です。
近年では、マイナンバーカードを提示することで、所得確認書類の提出を省略できる自治体も増えています。必要な書類は自治体によって異なる場合があるため、事前に窓口で確認し、リストをもらっておくと安心です。
申請に必要な主な書類
| 書類名 | 入手場所・作成者 |
|---|---|
| 支給認定申請書 | 市区町村の窓口 |
| 診断書(自立支援医療・精神通院用) | 主治医 |
| 健康保険証の写し | 申請者本人 |
| 所得状況を確認できる書類 | 市区町村の窓口(マイナンバーで代用可の場合あり) |
審査と受給者証の交付
提出された書類は、自治体の精神保健福祉センターなどの専門機関で審査され、申請者の病状が制度の対象となるか、治療方針が適切かなどが確認されます。審査には通常1ヶ月から2ヶ月程度の時間がかかります。
この期間は、自治体の規模や申請の混雑状況によって変動し、承認されると、市区町村から自立支援医療受給者証と、自己負担上限額管理票が交付され、受給者証が、制度を利用できる証明書となります。
もし申請が承認されなかった場合は、理由が記載された通知書が届きます。内容に不服がある場合は、不服申し立て(審査請求)を行うことも可能です。
訪問看護ステーションとの契約
受給者証が手元に届いたら、訪問看護の利用を開始できます。主治医や医療機関から紹介された訪問看護ステーション、あるいはご自身で選んだステーションに連絡を取ります。
ステーションの担当者と面談し、サービス内容や利用頻度、料金などについて詳細な説明を受け、納得した上で契約を結びます。
契約時には、緊急時の連絡方法や対応体制、キャンセルに関する規定など、細かい点までしっかり確認しておくことが大切です。この際に、自立支援医療受給者証を提示し、制度を利用したい旨を明確に伝えましょう。
訪問看護で受けられるサービス内容
精神科訪問看護では単なる健康チェックだけでなく、利用者の生活全般を支える多岐にわたるサービスを提供します。利用者一人ひとりの状況や目標に合わせた、個別性の高いケアが特徴です。
症状のモニタリングと服薬管理
看護師が定期的に訪問し、血圧や脈拍などの身体的なチェックに加え、精神状態の変化や症状の波を観察し、ご本人の話をじっくりと聞き、不安や悩みに寄り添います。客観的な視点での観察と、ご本人の主観的な訴えの両方を重視します。
また、薬の飲み忘れや副作用の確認、正しい服薬方法の指導など、内服薬の管理をサポートし、お薬カレンダーの作成や、服薬時間を知らせる工夫など、利用者に合った方法を一緒に考えます。
情報は定期的に主治医に報告され、診察時の重要な情報として活用され、この密な連携が、より適切な治療方針の決定につながるのです。
訪問看護のサービス内容例
| 支援の分類 | 具体的なサービス内容 |
|---|---|
| 病状の観察とケア | 精神症状の評価、バイタルサインのチェック、不安や混乱への対応 |
| 服薬支援 | 服薬の確認、副作用のモニタリング、服薬方法の工夫と助言 |
| 日常生活支援 | 食事・睡眠・清潔に関する助言、金銭管理の相談、家事の段取り支援 |
| 対人関係の支援 | コミュニケーションの練習、SST(社会生活技能訓練)、家族関係の調整 |
日常生活のサポートと相談
食事や睡眠、身の回りの整理整頓など、日常生活を送る上での困りごとについて一緒に考え、アドバイスをします。例えば、食生活が乱れている方には、簡単な調理方法を一緒に試したり、栄養バランスについて助言したりします。
金銭管理や公的な手続きに関する相談に応じることもあり、役所への書類提出に同行したり、手続きの方法を分かりやすく説明したりすることも支援の一つです。
利用者がその人らしい生活を地域で送れるように、生活リズムを整え、自己管理能力を高めるための支援を、利用者のペースに合わせて行います。
訪問看護ステーション選びのポイント
- 精神科の経験が豊富なスタッフがいるか
- 24時間対応の体制があるか
- 主治医との連携が密に取れるか
- 事業所の理念や雰囲気が合うか
対人関係や社会参加への支援
孤立しがちな利用者に対して、他者との交流の持ち方やコミュニケーションの練習をサポートします。SST(ソーシャルスキルトレーニング)の手法を用いて、挨拶や頼みごと、断り方など、具体的な場面を想定した練習を行うこともあります。
また、デイケアや就労支援施設、地域の趣味のサークルなど、利用者の興味や関心に合わせた社会資源に関する情報を提供し、社会参加への意欲を引き出すお手伝いをします。見学に同行し、新しい環境への一歩を後押しすることもあります。
家族との関係調整や、家族が抱える悩みに対する相談支援も重要な役割の一つです。家族も支援の対象と捉え、情報提供や助言を行います。
自立支援医療と訪問看護を併用する際の注意点
制度を有効に活用するために、いくつか知っておくべき注意点があります。手続きや利用方法で戸惑わないよう、事前に確認しておきましょう。
指定した医療機関・事業所でのみ適用
自立支援医療は、申請時に指定した医療機関(病院・クリニック)、薬局、訪問看護ステーションでのみ利用できます。指定制度は、利用者の治療計画を一元的に管理し、医療費の適正な給付を行うために設けられています。
指定していない場所でサービスを受けても制度は適用されず、3割負担となるため注意が必要です。もし、利用する医療機関や訪問看護ステーションを変更したい場合は、事前に市区町村の窓口で変更手続きを行ってください。
急な変更は難しいため、転院や事業所の変更を検討する際は、早めに相談を始めることが肝心です。
受給者証の有効期間と更新手続き
自立支援医療受給者証の有効期間は原則として1年間で、継続して制度の利用を希望する場合は、有効期間が終了する前に更新手続きを行うことが必要で、更新の申請は、有効期間終了日の3ヶ月前から可能です。
更新には再度、診断書の提出が必要になる場合があります(病状に変化がない場合は2年に1度で済む自治体もあります)、更新手続きを忘れて有効期間が切れてしまうと、その時点から再認定されるまでの間、医療費は3割負担になってしまいます。
更新手続きの注意点
- 有効期間終了の3ヶ月前から申請可能
- 診断書が再度必要か事前に確認する
- 住所や医療保険に変更があった場合も速やかに届出が必要
他の医療との併用に関するルール
自立支援医療(精神通院)は、精神疾患に関連する医療費を対象とする制度のため、風邪で内科にかかったり、怪我で外科にかかったりした際の医療費には適用されず、通常の医療保険での自己負担です。
ただし、精神疾患の症状が原因で生じた身体的な不調(例えば、薬の副作用による便秘や、精神的なストレスによる胃痛など)に対する治療は、主治医が必要と判断すれば対象となる場合があります。
また、精神症状に影響を与える可能性がある歯科治療なども対象になるケースがあります。判断は主治医が行うため、関連が疑われる場合はまず相談してみましょう。受給者証は精神科関連のサービスを受ける際にのみ提示するのが基本です。
自立支援医療(精神通院)での訪問看護に関するよくある質問
最後に、この制度を利用するにあたって多くの方が疑問に思う点について、Q&A形式でお答えします。
- 家族が代わりに申請手続きをすることはできますか?
-
ご本人が申請手続きを行うことが難しい場合は、ご家族や法定代理人、または成年後見人などが代理で申請できます。その際には、申請書に加えて委任状や代理人の身分を証明する書類が必要になる場合があります。
ご本人の心身の状態によっては、医療機関のソーシャルワーカーが手続きを代行してくれることもありますので、まずは相談してみてください。
必要なものは自治体によって異なるため、事前に申請先の市区町村窓口に確認することが大切です。
- 利用の途中で医療機関や訪問看護ステーションを変更できますか?
-
引っ越しや治療方針の変更などの理由で、通院先の医療機関や利用する訪問看護ステーションを変えたい場合は、市区町村の担当窓口で変更の届出が必要です。新しい医療機関や事業所名を記載した申請書を提出します。
変更届が受理されれば、受給者証が新しい情報で再交付されます。手続きが完了するまでは、新しい事業所では制度が適用されない可能性があるため、変更が決まったら速やかに手続きを進めることが大切です。
- 収入状況が変わった場合、自己負担上限月額は見直されますか?
-
自己負担上限月額は、世帯の市町村民税の課税状況に基づいて決定されます。転職や離職、結婚などによって世帯の所得状況が大きく変動した場合は、次の更新手続きの際に上限額が変わることがあります。
年の途中で世帯の状況に大きな変化があった場合は、担当窓口に相談することで、上限額の再認定を受けられる場合もあります。
自己負担がより軽くなる可能性もあるため、状況が変わった際は一度相談してみることをお勧めします。
- 申請してから認定されるまで、どのくらいの期間がかかりますか?
-
申請書類を提出してから、審査を経て受給者証が交付されるまでには、一般的に1ヶ月から2ヶ月程度かかり、自治体の審査状況によっては、それ以上かかることもあります。
この期間中に受けた医療費については、後から差額を払い戻す(償還払い)制度を利用できる場合があります。ただし、領収書などを保管しておく必要があり、手続きも別途必要です。
以上
参考文献
Murashima S, Nagata S, Magilvy JK, Fukui S, Kayama M. Home care nursing in Japan: a challenge for providing good care at home. Public health nursing. 2002 Mar;19(2):94-103.
Katakura N, Yamamoto‐Mitani N, Ishigaki K. Home‐visit nurses’ attitudes for providing effective assistance to clients with schizophrenia. International Journal of Mental Health Nursing. 2010 Apr;19(2):102-9.
Setoya N, Aoki Y, Fukushima K, Sakaki M, Kido Y, Takasuna H, Kusachi H, Hirahara Y, Katayama S, Tachimori H, Funakoshi A. Future perspective of psychiatric home-visit nursing provided by nursing stations in Japan. Global health & medicine. 2023 Jun 30;5(3):128-35.
Miou M, Fujimoto H, Yotsumoto K, Hirota M, Nishigaki S, Hashimoto T. Exploring Psychiatric Home-Visit Nursing Practices for Patients with Schizophrenia and Hikikomori with a Thematic Analysis. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2024 Feb 5;21(2):181.
Kayama M, Setoya N, Doyle C. Expanding use of nurse home visiting for community psychiatric care in Japan. Psychiatric Quarterly. 2020 Jun;91(2):571-6.
Yamada N, Tanabe Y, Tanaka R, Yajima K. Support Issues for People with Mental Disorders in Group Homes in Japan. Journal of Psychiatry and Psychiatric Disorders. 2024 May 27;8:175-83.
Hanzawa S, Nosaki A, Yatabe K, Nagai Y, Tanaka G, Nakane H, Nakane Y. Study of understanding the internalized stigma of schizophrenia in psychiatric nurses in Japan. Psychiatry and clinical neurosciences. 2012 Mar;66(2):113-20.
Nagayama Y, Nakai H. Community-Based Integrated Care System for People with Mental Illness in Japan: Evaluating Location Characteristics of Group Homes to Determine the Feasibility of Daily Life Skill Training. Challenges. 2022 Aug 8;13(2):38.
Takashima Y, Blaquera AP, Betriana F, Ito H, Yasuhara Y, Soriano G, Tanioka T. Psychiatric Home-Visiting Nurses’ Views on the Care Information Required of Psychiatric Hospital Nurses. The Journal of Medical Investigation. 2024;71(1.2):162-8.
Toyoshima Y, Washio M, Ishibashi Y, Onizuka J, Miyabayashi I, Arai Y. Burden among Family Caregivers of the Psychiatric Patients with Visiting Nursing Services in Japan. International Medical Journal. 2012 Jun 1;19(2).