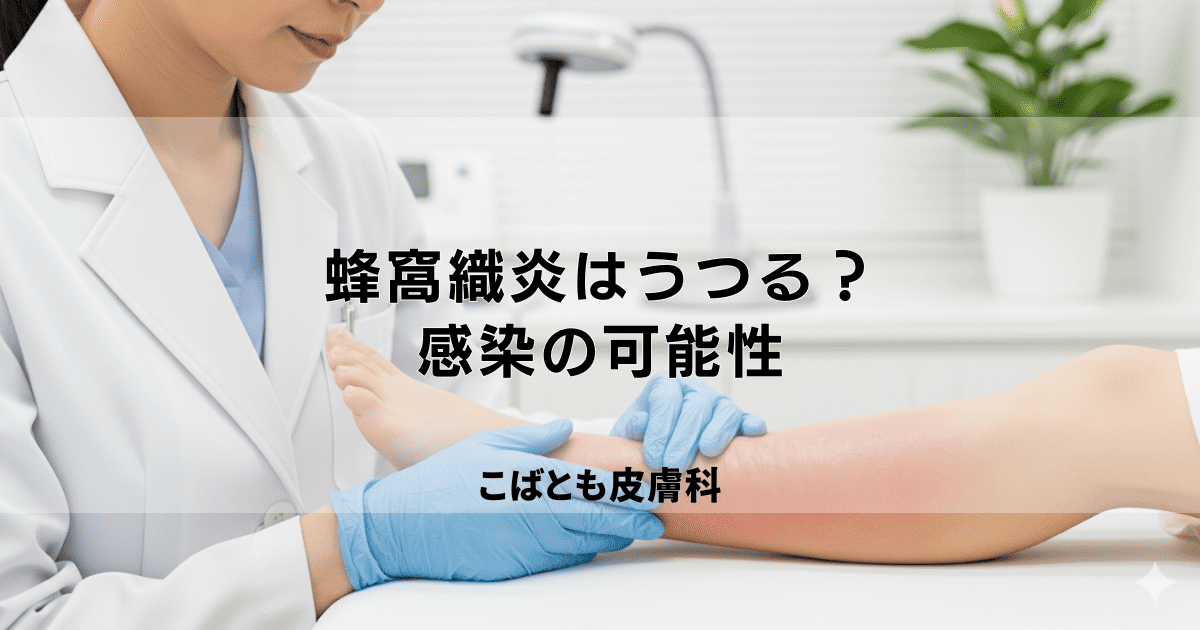ある日突然、足や腕が赤く腫れ上がり、熱をもってズキズキと痛む症状は、蜂窩織炎かもしれません。この病名を聞いて、多くの方がまず心配になるのは、家族や周りの人にうつしてしまうのではないか、ということではないでしょうか。
特に、小さなお子さんや高齢のご家族と暮らしている方にとっては、切実な問題です。
この記事では、蜂窩織炎が他の人にうつる可能性について詳しく解説します。
この記事の執筆者

小林 智子(こばやし ともこ)
日本皮膚科学会認定皮膚科専門医・医学博士
こばとも皮膚科院長
2010年に日本医科大学卒業後、名古屋大学医学部皮膚科入局。同大学大学院博士課程修了後、アメリカノースウェスタン大学にて、ポストマスターフェローとして臨床研究に従事。帰国後、同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンターにて、糖化と肌について研究を行う。専門は一般皮膚科、アレルギー、抗加齢、美容皮膚科。雑誌を中心にメディアにも多数出演。著書に『皮膚科医が実践している 極上肌のつくり方』(彩図社)など。
こばとも皮膚科関連医療機関
蜂窩織炎とは?基本的な症状と原因
蜂窩織炎という言葉自体、あまり聞き慣れないかもしれません。まずは、この病気がどのようなものなのか、基本的な部分から理解を深めていきましょう。
皮膚の深い場所で起こる細菌感染症
私たちの皮膚は、外側から表皮、真皮、皮下組織という層構造になっています。蜂窩織炎は、このうちの真皮から皮下組織という、比較的深い部分で細菌が増殖し、炎症を起こす病気です。
皮膚の表面で起こる感染症とは異なり、炎症が広範囲に及びやすいという特徴があります。
脂肪組織は、蜂の巣のように小さな区画に分かれているため、構造に沿って炎症が広がる様子から、蜂窩織炎(ほうかしきえん)や蜂巣炎(ほうそうえん)と呼ばれます。
主に足、特にすねの部分に発症することが多いですが、腕や顔など、体のどこにでも起こる可能性があります。早期に適切な治療を開始することが大事な皮膚の感染症の一つです。
赤み・腫れ・熱感・痛みが主なサイン
蜂窩織炎の症状は、比較的はっきりと現れ、最も特徴的なのは、皮膚の赤み、熱を伴う腫れ、そして触れたり動かしたりしたときの強い痛みです。症状が出ている部分と、そうでない部分の境界は、比較的ぼんやりしています。
炎症が強い場合は、水ぶくれ(水疱)や、皮膚の一部が壊死してしまうこともあり、皮膚症状に加えて、体のだるさ、悪寒、発熱、関節痛といった全身症状を伴うことも少なくありません。
もし、皮膚にこのような症状が急に現れた場合は、単なる肌荒れや虫刺されだと自己判断せず、蜂窩織炎の可能性を考える必要があります。
蜂窩織炎の局所的な症状
| 症状 | 特徴 | 注意点 |
|---|---|---|
| 発赤(赤み) | 境界が不明瞭で、広範囲に広がる。 | 時間とともに赤みの範囲が拡大する。 |
| 腫脹(腫れ) | 皮膚がパンパンに腫れ、光沢を帯びる。 | 指で押すと跡が残ることがある。 |
| 熱感 | 患部が明らかに熱を持っている。 | 正常な皮膚との温度差で判断できる。 |
| 疼痛(痛み) | 自発痛(何もしなくても痛い)や圧痛(押すと痛い)。 | ズキズキとした拍動性の痛みを伴うことがある。 |
原因菌の多くは黄色ブドウ球菌やレンサ球菌
蜂窩織炎を引き起こす主な原因は細菌で、特に多いのが、黄色ブドウ球菌と化膿レンサ球菌(A群β溶血性レンサ球菌)で、皮膚の表面や鼻の中、のどなどに普段から存在している常在菌の一種です。
健康な皮膚は、細菌が体内に侵入するのを防ぐバリア機能を持っていますが、何らかの理由で皮膚のバリア機能が破られると、そこから細菌が皮下組織に侵入し、増殖して蜂窩織炎を発症します。
原因菌の種類によって、症状の進み具合や重症度が異なる場合もあります。
細菌はどこから侵入するのか
細菌が体内に侵入するきっかけは、ごくささいな皮膚の傷であることがほとんどです。目に見えないほどの小さな傷でも、細菌にとっては十分な侵入口となります。
靴ずれ、切り傷、すり傷、虫刺されのかき壊し、水虫(足白癬)による皮膚の亀裂、アトピー性皮膚炎による湿疹、やけど、手術の傷跡などが挙げられます。
特に、水虫によって足の指の間の皮膚がじゅくじゅくしていたり、ひび割れていたりすると、そこから細菌が侵入し、足の蜂窩織炎を起こす代表的な原因となります。日頃から皮膚を清潔に保ち、傷を放置しないことが大切です。
細菌が侵入しやすい皮膚の状態
- すり傷や切り傷
- 虫刺されや湿疹のかき壊し
- 水虫(特に趾間型)
- 乾燥による皮膚のひび割れ
- 手術創やピアスの穴
蜂窩織炎は他の人にはうつらない
蜂窩織炎は、インフルエンザや風邪のように、咳やくしゃみで空気感染したり、接触によって他の人にうつったりすることは基本的にありません。なぜそう言えるのか、理由を詳しく見ていきましょう。
人から人への直接感染は極めてまれ
蜂窩織炎の原因菌は、健康な皮膚を通過して内部に侵入することができないので、蜂窩織炎の患者さんの患部に触れたからといって、その人が蜂窩織炎になることはまずありません。
仮に患部から排出された細菌が健康な皮膚に付着したとしても、皮膚のバリ ア機能が正常に働いていれば、感染は成立しないのです。日常生活において、家族や同僚にうつす心配はしなくて大丈夫で、タオルや食器の共用も問題ありません。
過度に神経質になる必要はなく、普段通りの生活を送ることができます。
蜂窩織炎の感染リスク評価
| 接触の状況 | 感染リスク | 解説 |
|---|---|---|
| 会話、咳、くしゃみ | ほぼゼロ | 空気感染や飛沫感染はしません。 |
| 患部に軽く触れる | ほぼゼロ | 健康な皮膚からは細菌は侵入できません。 |
| タオルや衣類の共用 | ほぼゼロ | 通常の洗濯で細菌は洗い流されます。 |
感染経路は主に自身の皮膚の傷口から
蜂窩織炎は、他人から菌をもらって発症するというよりは、自分自身の皮膚にもともとある常在菌が、自分自身の皮膚の傷から侵入することによって発症する、いわば自己感染の病気です。
誰もが持っている細菌が、体の防御機能が弱まったタイミングで悪さをする、と考えると分かりやすいかもしれません。
感染対策として重要なのは、他人との接触を避けることではなく、自分自身の皮膚に傷を作らないこと、傷ができた場合には速やかに適切な処置をすることです。特に足は、傷に気づきにくく、細菌が繁殖しやすい環境なので注意しましょう。
特殊な状況下での注意点
基本的にはうつらない蜂窩織炎ですが、ごくまれに注意が必要なケースもあり、それは、患部から膿が出ている場合です。
膿の中には、原因となっている細菌が大量に含まれていて、膿が、免疫力が著しく低下している人や、皮膚に傷や湿疹がある人の傷口に直接付着した場合には、感染が起こる可能性はゼロではありません。
介護の現場や、家族に免疫抑制剤を使用している方や未熟児がいる場合などです。もし患部から膿が出ている場合は、ガーゼなどで覆い、直接他の人が触れないように配慮し、手洗いを徹底することが望ましいでしょう。
ただし、これはあくまで例外的な状況であり、一般的な家庭環境で過剰に心配する必要はありません。
なぜ蜂窩織炎はうつらないと言えるのか?
蜂窩織炎が基本的に人から人へうつらないと聞いて、安心した方も多いと思います。ここでは、その医学的な根拠について、もう少し掘り下げて解説します。
感染が起こる場所は皮膚の深層部
蜂窩織炎の主戦場は、皮膚の表面である表皮ではなく、その奥にある真皮や皮下組織で、細菌はこの深い部分で増殖し、炎症を起こします。皮膚の表面には、感染の原因となる細菌が常に大量に存在するわけではありません。
膿が出ているなどの特殊な状況を除けば、患部の皮膚表面に触れても、大量の細菌に接触する機会は少ないのです。
飛び火(伝染性膿痂疹)のように、皮膚の浅い層で細菌が増殖し、病変部を触った手で他の場所を掻くことで次々に感染が広がっていく病気とは、感染の起こる場所が根本的に異なります。
原因菌は健康な皮膚を通過できない
蜂窩織炎の主な原因菌である黄色ブドウ球菌やレンサ球菌は、周りの環境や、自分自身の体に常に存在していますが、それでも私たちが常に感染症にかからないのは、皮膚が強力なバリアとして機能しているからです。
皮膚の最も外側にある角質層は、外部からの異物の侵入を防ぐ頑丈な壁の役割を果たしていて、原因菌は、角質層を自力で突破する力を持っていません。
感染が成立するためには、必ず切り傷やすり傷、水虫による亀裂といった、皮膚のバリア機能が破綻した場所、つまり細菌の侵入口が必要になります。健康で傷のない皮膚に細菌が付着しただけでは、感染は起こらないのです。
免疫力が正常であれば菌の増殖は抑えられる
たとえ少量の細菌が傷口から体内に侵入したとしても、すぐに蜂窩織炎になるわけではありません。
体には、侵入してきた細菌を攻撃し、排除するための免疫システムが備わっていて、白血球などの免疫細胞が、細菌を発見して攻撃し、増殖を抑え込みます。
蜂窩織炎が発症するのは、侵入した細菌の量が多かったり、毒性が強かったりして、体の免疫力が細菌の増殖スピードに追いつかなくなった場合です。
健康な人であれば、ごく小さな傷から細菌が侵入しても、免疫システムによって発症が防がれているケースも少なくありません。
蜂窩織炎と間違えやすい他の皮膚感染症
足や腕が赤く腫れて痛む場合、蜂窩織炎の可能性が高いですが、似たような症状を示す他の病気もあり、中には、蜂窩織炎よりも緊急性の高いものや、対処法が異なるものもあります。
丹毒(たんどく)との違い
丹毒は、蜂窩織炎と非常によく似た症状を示す皮膚の細菌感染症です。主な原因菌は化膿レンサ球菌で、蜂窩織炎よりも皮膚の浅い層(真皮上層)で炎症が起こるため、症状にも少し違いが見られます。
丹毒の場合、赤みの境界が比較的はっきりしており、盛り上がっているのが特徴で、蜂窩織炎はより深い部分の炎症なので、境界はぼんやりしています。
丹毒は顔や耳に好発し、高熱や悪寒などの全身症状を伴いやすい傾向があります。治療は蜂窩織炎と同様に抗菌薬の投与を行いますが、原因菌が特定できれば、より効果的な薬を選択できます。
蜂窩織炎と丹毒の比較
| 項目 | 蜂窩織炎 | 丹毒 |
|---|---|---|
| 炎症の部位 | 皮膚の深い部分(真皮深層~皮下組織) | 皮膚の浅い部分(真皮上層) |
| 境界 | 不明瞭(ぼんやりしている) | 明瞭(くっきりしている) |
| 好発部位 | 下腿(すね) | 顔、耳、下腿 |
接触性皮膚炎(かぶれ)との見分け方
植物や金属、化学物質などに触れることで起こる接触性皮膚炎(かぶれ)も、赤みや腫れ、水ぶくれなどを生じることがあり、蜂窩織炎と間違われることがあります。
しかし、かぶれの場合は、原因物質が触れた範囲に一致して症状が出ることが多く、強いかゆみを伴うのが一般的です。蜂窩織炎の主な症状は痛みであり、かゆみはあまり強くありません。
またかぶれは、蜂窩織炎のような発熱や悪寒といった全身症状を伴うことはまれです。原因がはっきりしない皮膚の赤みや腫れで、痛みが強い場合は、かぶれよりも感染症を疑うべきでしょう。
蜂窩織炎と間違えやすい皮膚トラブル
- 丹毒
- 接触性皮膚炎(かぶれ)
- 虫刺され(特にブユ、アブなど)
- 深部静脈血栓症
- 痛風発作
壊死性筋膜炎など緊急性の高い疾患
非常にまれですが、最も注意が必要なのが壊死性筋膜炎で、皮下の筋膜という組織に沿って細菌感染が急速に広がり、組織を壊死させてしまう、命に関わる危険な病気です。
初期症状は蜂窩織炎と似ていますが、痛みが異常に強い、赤みや腫れが驚くほどの速さで広がる、皮膚の色が紫色や黒っぽく変化するといった特徴があります。人食いバクテリアによる感染症として報道されることもあります。
このような症状が見られた場合は、一刻を争う事態で、すぐに救急外来を受診するか、救急車を呼ぶ必要があります。
虫刺されとの初期症状の比較
虫刺され、特にブユやアブ、ハチなどに刺された場合も、赤くパンパンに腫れ上がり、熱感や痛みを伴うことがあり、蜂窩織炎の初期症状と見分けるのが難しいことも少なくありません。
虫刺されの場合、通常は刺された中心部(刺し口)がはっきりしており、強いかゆみを伴うことが多いですが、刺された部分をかき壊してしまい、そこから二次的に細菌感染を起こして蜂窩織炎に移行することもあります。
虫刺されだからと安易に考えず、腫れや痛みが数日経っても引かない、悪化していくような場合は、皮膚科を受診してください。
蜂窩織炎になりやすい人の特徴と予防策
蜂窩織炎は誰にでも起こりうる病気ですが、特になりやすい体質や生活習慣があります。ご自身が当てはまるかどうかを確認し、予防に役立てましょう。
皮膚のバリア機能が低下している人
皮膚のバリア機能が正常に働いていれば、細菌の侵入は容易に防げますが、アトピー性皮膚炎や乾燥肌、慢性の湿疹などがあると、皮膚が常に炎症を起こしていたり、乾燥してひび割れやすくなっていたりするため、バリア機能が低下しがちです。
また、水虫(足白癬)は、足の指の間の皮膚をふやけさせ、亀裂を生じさせるため、蜂窩織炎の最大の危険因子の一つです。ステロイド外用薬を長期間使用している場合も、皮膚が薄くなり、感染への抵抗力が弱まることがあります。
日頃からのスキンケアで、皮膚の潤いを保ち、健康な状態を維持することが重要です。
皮膚のバリア機能を保つためのポイント
- 保湿剤によるスキンケア
- 水虫の適切な治療
- 湿疹やかゆみの放置を避ける
- 肌に優しい衣類の選択
免疫力が低下する持病がある人
体内に細菌が侵入したときに、撃退する免疫システムの働きが弱いと、蜂窩織炎を発症しやすくなります。
糖尿病の患者さんは、血糖値が高い状態が続くことで免疫細胞の働きが鈍くなり、血行も悪化するため、感染症にかかりやすく、また治りにくくなります。
他にも、がんの治療で抗がん剤を使用している方、ステロイドや免疫抑制剤を内服している方、肝硬変や腎不全、HIV感染症などの持病がある方も、免疫力が低下しているため注意が大切です。
持病のコントロールを良好に保つことが、蜂窩織炎の予防にもつながります。
蜂窩織炎になりやすい方の特徴
| 分類 | 具体的な状態や疾患 | 理由 |
|---|---|---|
| 皮膚の状態 | 水虫、アトピー性皮膚炎、リンパ浮腫 | 皮膚のバリア機能が低下し、細菌が侵入しやすい。 |
| 免疫力の低下 | 糖尿病、がん治療中、ステロイド内服中 | 体内に侵入した細菌を排除する力が弱い。 |
| 血行不良 | 肥満、下肢静脈瘤、長時間の立ち仕事 | 血流が悪く、栄養や免疫細胞が届きにくい。 |
足のむくみ(浮腫)や血行不良がある人
足のむくみ(浮腫)も、蜂窩織炎の大きなリスクです。心臓や腎臓の病気、あるいはリンパ浮腫(手術などでリンパの流れが滞る状態)などによって足がむくむと、皮膚がパンパンに引き伸ばされて薄くなり、少しの刺激で傷つきやすくなります。
また、細胞の間に余分な水分が溜まることで、細菌が繁殖しやすい環境が生まれ、さらに、血行不良があると、酸素や栄養、そして細菌と戦う白血球などが患部に届きにくくなり、感染が起こりやすくなります。
長時間の立ち仕事やデスクワークで足がむくみやすい方も、定期的に足を動かしたり、マッサージをしたりして、血行を促進する工夫が大切です。
日常生活でできる具体的な予防策
蜂窩織炎を予防するためには、細菌の侵入口を作らないこと、体の抵抗力を高めることが基本です。まず足を毎日よく洗い、清潔に保つこと。特に指の間は丁寧に洗い、しっかりと乾かしましょう。
水虫があれば、根気よく治療を続けることが最も重要です。また、乾燥肌の方は保湿剤を塗って、皮膚のひび割れを防ぎ、ケガをしたときは、傷口をきれいに洗浄し、必要に応じて保護してください。
肥満は血行不良や糖尿病のリスクを高めるため、適度な運動とバランスの取れた食事で体重を管理することも、間接的な予防策となります。
クリニックでの診断と治療法
皮膚の赤みや腫れ、痛みが急に現れたら、自己判断で様子を見るのは危険です。症状が急速に広がっている場合や、発熱などの全身症状がある場合は、速やかに医療機関を受診してください。
まずは皮膚科専門医へ相談を
蜂窩織炎が疑われる症状に気づいたら、まずは皮膚科を受診しましょう。皮膚科医は、皮膚の状態を詳細に観察し、他の似た症状の病気と見分ける専門家です。
問診では、いつから症状が始まったか、きっかけとなるケガはなかったか、持病の有無などを詳しくお聞きし、情報と視診・触診の結果を総合的に判断して、診断を下します。
多くの場合、特徴的な症状から診断は可能ですが、確定診断や重症度の評価のために、追加で検査を行うこともあります。
クリニックで行う検査の種類
| 検査名 | 目的 | 方法 |
|---|---|---|
| 血液検査 | 炎症の程度や全身への影響を調べる。 | 採血を行い、白血球数やCRP値などを測定する。 |
| 細菌培養検査 | 原因となっている細菌を特定する。 | 傷や膿があれば、それを綿棒で採取し培養する。 |
| 画像検査 | 炎症の広がりや深さを評価する。 | 超音波(エコー)検査や、必要に応じてCT/MRI検査を行う。 |
主な治療法は抗菌薬の内服や点滴
蜂窩織炎の治療の基本は、原因となっている細菌を殺すための抗菌薬(抗生物質)の投与です。症状が比較的軽い場合は、内服薬(飲み薬)が処方され、原因菌として頻度の高い黄色ブドウ球菌やレンサ球菌に効果のある薬が選ばれます。
炎症や痛みが強い場合には、解熱鎮痛剤を併用することもあります。症状が重い場合や、飲み薬の効果が不十分な場合、あるいは糖尿病などの持病があって重症化のリスクが高い場合には、入院して抗菌薬の点滴治療を行います。
点滴は、薬の成分が直接血管に入るため、飲み薬よりも速く、そして確実に効果を発揮します。
入院が必要になるケース
すべての蜂窩織炎で入院が必要になるわけではありませんが、以下のような状況では、入院による集中的な治療を検討します。まず、赤みや腫れなどの症状が広範囲に及んでいたり、急速に悪化したりしている場合です。
また、38度以上の高熱が出ている、血圧が低いなど、全身の状態が良くない場合も入院の対象となります。糖尿病や免疫不全などの基礎疾患がある方も、重症化しやすいため、早期からの入院を勧めることが多いです。
入院中は、抗菌薬の点滴に加えて、患部を高く上げて安静に保つことで、腫れや痛みを和らげます。
入院治療を検討する状況
- 症状の範囲が広い、または急速に拡大している
- 高熱や倦怠感など全身症状が強い
- 内服の抗菌薬で改善が見られない
- 重い基礎疾患(糖尿病など)がある
- 痛みが強く、日常生活に支障が出ている
蜂窩織炎の治療中に気をつけるべき生活習慣
蜂窩織炎を早く、そして確実に治すためには、処方された薬を飲むだけでなく、日常生活での過ごし方も非常に重要でし・治療効果を高め、回復を早めるために、いくつかのポイントを心がけましょう。
患部を安静に保つことの重要性
治療において最も大切なことの一つが、患部を安静に保つことで、足に発症した場合、歩き回ると炎症が悪化し、治りが遅くなる原因になります。仕事や家事も、できるだけ休み、患部を心臓より高い位置に上げておく(挙上)のが理想的です。
横になるときは足の下にクッションや座布団を数枚重ねて高くしたり、椅子に座っているときも別の椅子に足を乗せたりする工夫をし、患部に溜まった余分な水分や血液が心臓に戻りやすくなり、腫れや痛みが軽減されます。
安静にする際の注意点
- 長時間の歩行や立ち仕事を避ける
- 患部を心臓より高く保つ(挙上)
- 患部を締め付ける衣類や靴下を避ける
正しいスキンケアと清潔の維持
患部は清潔に保つ必要がありますが、ゴシゴシと強く洗うのは禁物で、刺激の少ない石鹸をよく泡立てて、手で優しく洗い、シャワーで十分に洗い流してください。入浴については、医師の指示に従いましょう。
熱いお風呂に長く浸かると、炎症が強まることがあるため、シャワー程度で済ませるのが無難です。また、原因となった傷や水虫がある場合は、その治療も並行して行います。
皮膚の乾燥はバリア機能の低下につながるため、患部の周りの皮膚には保湿剤を塗るなど、基本的なスキンケアも継続することが大切です。
食事や水分補給で気をつけること
蜂窩織炎は体力を消耗する感染症で、回復を助けるためには、栄養バランスの取れた食事を心がけることが大事です。特に、皮膚や粘膜を健康に保つビタミン類や、体の組織を作るたんぱく質を十分に摂取しましょう。
また、発熱によって体内の水分が失われがちなので、こまめに水分補給を行うことも忘れないでください。アルコールは血管を拡張させて炎症を悪化させる可能性があるため、治療中は控えるのが賢明です。
特定の食べ物が蜂窩織炎を治すということはありませんが、体全体の抵抗力を高めるという視点で、健康的な食生活を意識してください。
治療中の食事のポイント
| 栄養素 | 多く含まれる食品の例 | 期待される役割 |
|---|---|---|
| たんぱく質 | 肉、魚、卵、大豆製品 | 皮膚や免疫細胞の材料になる。 |
| ビタミンA/C/E | 緑黄色野菜、果物、ナッツ類 | 皮膚の健康維持、免疫機能のサポート。 |
| 亜鉛 | 牡蠣、レバー、牛肉 | 皮膚の新陳代謝や免疫反応に関わる。 |
処方された薬は最後まで飲み切る
抗菌薬の内服を開始すると、数日で熱が下がり、痛みや赤みも和らいでくることがほとんどですが、症状が良くなったからといって、自己判断で薬をやめてはいけません。
症状が治まっても、皮膚の深い場所にはまだ細菌が残っている可能性があり、薬をやめてしまうと、生き残った細菌が再び増殖し、再発したり、薬が効きにくい耐性菌を生み出す原因になったりします。
医師から指示された期間、処方された抗菌薬は必ず最後まで飲み切ることが、完治のためには絶対に必要です。
蜂窩織炎に関するよくある質問
最後に、患者さんからよく寄せられる質問と回答をまとめました。
- お風呂に入っても大丈夫ですか?
-
症状や医師の判断によりますが、一般的には、高熱がなく、患部に傷や膿がない状態であれば、シャワー浴は問題ありません。
ただし、長湯や熱いお湯は、血行が良くなりすぎて炎症や痛みを悪化させる可能性があるため避けた方が良いでしょう。体を温めすぎないように、ぬるめのシャワーで短時間で済ませてください。
患部は強くこすらず、石鹸の泡で優しく洗い流す程度にします。湯船に浸かる入浴については、自己判断せず、必ず主治医に確認してください。
- 子供や高齢者でもなりますか?
-
蜂窩織炎は年齢に関係なく、誰でも発症する可能性があります。お子さんの場合は、虫刺されのかき壊しや、転んですりむいた傷などから細菌が侵入することが多いです。
高齢の方は、加齢による皮膚の乾燥やバリア機能の低下、血行不良、糖尿病などの持病といった、複数のリスク因子が重なるため、発症しやすく、また重症化しやすい傾向があります。
ご高齢の方で足のむくみがある場合は、日頃から皮膚の状態をよく観察し、小さな傷にも注意を払うことが大切です。
- 一度治ったら再発しませんか?
-
蜂窩織炎は再発しやすい病気の一つで、リンパ浮腫や下肢静脈瘤、水虫といった根本的な原因が解決されていない場合、同じ場所に何度も繰り返すことがあります。
再発を繰り返すと、皮膚が硬くなったり、リンパ浮腫が悪化したりすることもあります。
再発を防ぐためには、処方された抗菌薬を最後まで飲み切って完全に治すこと、そして水虫の治療や保湿などのスキンケアを徹底し、むくみの管理を行うなど、発症の原因となったリスク因子をできるだけ取り除く努力が必要です。
- 市販薬で治せますか?
-
蜂窩織炎の治療には、医師の処方が必要な医療用の抗菌薬が不可欠です。市販されている塗り薬の多くは、抗菌成分が含まれていても、蜂窩織炎が起きている皮膚の深層部まで届きません。
また、原因菌に合わない薬を使っても効果はありません。症状が似ているからといって、自己判断で市販薬を使用すると、治療が遅れて症状が悪化したり、かぶれを起こしたりする危険性があります。
皮膚の赤み、腫れ、痛みに気づいたら、速やかに皮膚科を受診してください。
以上
参考文献
Norimatsu Y, Ohno Y. Predictors for readmission due to cellulitis among Japanese patients. The Journal of Dermatology. 2021 May;48(5):681-4.
Bystritsky R, Chambers H. Cellulitis and soft tissue infections (Japanese version). Annals of internal medicine. 2018 Feb 6;168(3):JITC17-32.
Miyachi H, Sato D, Shimizu S, Togawa Y, Sakamaki K, Yoshimura K. Seasonality and Trend of Cellulitis, Herpes Zoster, and Varicella: A Nationwide Population-based Study. JMA journal. 2025 Jul 15;8(3):903-10.
Okamoto O, Kai Y, Munemoto S, Suzuki R, Akishino K, Hashimoto H. A clinical and statistical analysis of abscess in cellulitis. The Journal of Dermatology. 2021 Aug;48(8):1162-71.
Taniguchi T, Tsuha S, Shiiki S, Narita M, Teruya M, Hachiman T, Kogachi N. High yield of blood cultures in the etiologic diagnosis of cellulitis, erysipelas, and cutaneous abscess in elderly patients. InOpen Forum Infectious Diseases 2022 Jul 1 (Vol. 9, No. 7, p. ofac317). Oxford University Press.
Saegusa Y, Yamamoto S, Shincho A, Furuoka H, Hasada J. Streptococcal Toxic Shock Syndrome Caused by Cellulitis Following a Fall: A Report of Two Critical Cases. Cureus. 2025 Mar 19;17(3).
Komatsu Y, Okazaki A, Hirahara K, Araki K, Shiohara T. Differences in Clinical Features and Outcomes between Group A-and Group G Streptococcus-Induced Cellulitis. Dermatology. 2015 Feb 12;230(3):244-9.
Cranendonk DR, Lavrijsen AP, Prins JM, Wiersinga WJ. Cellulitis: current insights into pathophysiology and clinical management. Neth J Med. 2017 Nov 1;75(9):366-78.
Simonsen SE, Van Orman ER, Hatch BE, Jones SS, Gren LH, Hegmann KT, Lyon JL. Cellulitis incidence in a defined population. Epidemiology & Infection. 2006 Apr;134(2):293-9.
Gunderson CG, Martinello RA. A systematic review of bacteremias in cellulitis and erysipelas. Journal of Infection. 2012 Feb 1;64(2):148-55.