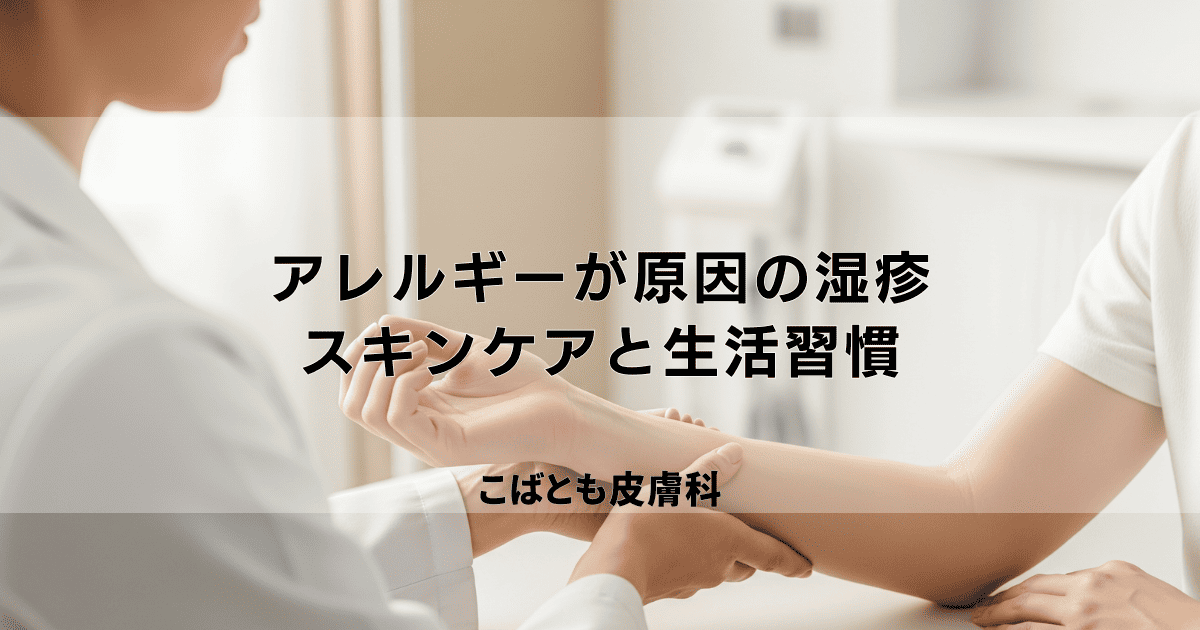繰り返す湿疹やかゆみ、原因のわからない肌荒れに悩んでいませんか。もしかしたらアレルギーが関係しているかもしれません。
アレルギーによる皮膚症状は、特定の物質に体の免疫システムが過剰に反応することで起こり、原因となるアレルゲンは、食べ物からダニ、花粉、金属まで多岐にわたります。
この記事では、アレルギーが原因で起こる湿疹や肌荒えの根本的な理解を深め、日々のスキンケアと生活習慣を見直すことで症状を改善するための方法を解説します。
この記事の執筆者

小林 智子(こばやし ともこ)
日本皮膚科学会認定皮膚科専門医・医学博士
こばとも皮膚科院長
2010年に日本医科大学卒業後、名古屋大学医学部皮膚科入局。同大学大学院博士課程修了後、アメリカノースウェスタン大学にて、ポストマスターフェローとして臨床研究に従事。帰国後、同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンターにて、糖化と肌について研究を行う。専門は一般皮膚科、アレルギー、抗加齢、美容皮膚科。雑誌を中心にメディアにも多数出演。著書に『皮膚科医が実践している 極上肌のつくり方』(彩図社)など。
こばとも皮膚科関連医療機関
アレルギーによる湿疹・肌荒れの基本
アレルギーと聞くと、多くの人が花粉症や食物アレルギーを思い浮かべるかもしれませんが、皮膚に現れる湿疹や肌荒れも、アレルギー反応の重要なサインの一つです。
まずは、アレルギーがなぜ肌トラブルを引き起こすのか、基本的な事柄を理解することから始めましょう。
そもそもアレルギーとは何か
アレルギーとは、体を異物から守る免疫システムが、特定の物質に対して過剰に反応してしまう状態を指し、本来は無害であるはずの食べ物や花粉、ハウスダストなどを、体が有害な侵入者と誤認し、攻撃を始めてしまうのです。
この過剰な防御反応が、くしゃみ、鼻水、目のかゆみといった症状や、皮膚のかゆみ、赤み、湿疹などの形で現れ、アレルギー反応を引き起こす原因物質をアレルゲンと呼びます。
誰にでもアレルギー反応が起こるわけではなく、遺伝的な要因や生活環境などが複雑に関わり合って発症すると考えられています。一度アレルギーを発症すると、アレルゲンに触れるたびに症状が繰り返されることが特徴です。
なぜアレルギーで肌トラブルが起きるのか
皮膚は、体の一番外側で外部の刺激や病原体から体を守るバリアの役割を担っていて、アレルギー反応が起こると、皮膚の内部でヒスタミンなどの化学伝達物質が放出されます。
ヒスタミンが、知覚神経を刺激して強いかゆみを起こしたり、血管を拡張させて皮膚に赤みや腫れをもたらしたりし、また、アレルギーによる炎症は、皮膚のバリア機能を低下させます。
バリア機能が弱まると、皮膚の水分が蒸発しやすくなり乾燥が進むだけでなく、外部からのアレルゲンや刺激物質がさらに侵入しやすくなるという悪循環に陥り、慢性的な湿疹や肌荒れにつながるのです。
代表的なアレルゲンと症状の現れ方
アレルギー性の皮膚症状を起こすアレルゲンは様々です。食べ物が原因の場合は食後数時間以内に口の周りや全身にじんましんが出ることがあります。
化粧品や金属が原因の場合は、直接触れた部分に赤みやかぶれ(接触皮膚炎)が生じ、また、ハウスダストやダニ、花粉などは、アトピー性皮膚炎の症状を悪化させる要因です。アレルゲンを特定することが、症状改善への第一歩となります。
アレルゲンの種類と主な皮膚症状
| アレルゲンの種類 | 原因となる物質の例 | 主な皮膚症状 |
|---|---|---|
| 食物性アレルゲン | 卵、牛乳、小麦、そば、えび、かに | じんましん、かゆみ、血管性浮腫 |
| 吸入性アレルゲン | ダニ、ハウスダスト、花粉、カビ、ペットのフケ | アトピー性皮膚炎の悪化、かゆみ |
| 接触性アレルゲン | ニッケルなどの金属、うるし、化粧品成分、薬剤 | 接触皮膚炎(かぶれ)、赤み、水ぶくれ |
自己判断は危険 専門医への相談の重要性
肌の症状がアレルギーによるものかどうかを自分で判断するのは非常に困難です。似たような症状でも、原因が全く異なる皮膚疾患である可能性も少なくありません。
アレルギーだと思って特定の食品を極端に避けることで、栄養バランスが崩れてしまうこともあり、また、市販の薬で一時的に症状が和らいでも、根本的な原因が解決しなければ再発を繰り返します。
皮膚科では、問診や視診に加え、血液検査やパッチテストなどを用いてアレルゲンの特定を行います。
日常生活に潜むアレルゲンと対策
アレルギー症状の改善には、原因となるアレルゲンを特定し、可能な限り避ける生活を心がけることが大切です。ここでは、日常生活の中に潜む代表的なアレルゲンと、今日から始められる対策を紹介します。
ハウスダストとダニ その隠れた影響
ハウスダストは、家の中の様々なものからなるホコリの総称で、その中にはアレルギーの主要な原因となるダニの死骸やフンが大量に含まれています。
ダニアレルゲンは非常に小さく軽いため、空気中に舞い上がりやすく、呼吸とともに吸い込んだり、皮膚に付着したりし、布団やカーペット、布製のソファ、ぬいぐるみなどはダニが繁殖しやすい場所です。
ダニアレルゲンが皮膚のバリア機能が低下した部分から侵入すると、アレルギー反応を引き起こし、アトピー性皮膚炎のかゆみや湿疹を悪化させます。
ハウスダスト対策のポイント
- こまめな掃除(1平方メートルあたり20秒以上かける)
- 布製の家具を減らす
- 寝具は防ダニ仕様のものを選ぶ
- 定期的な寝具の丸洗いや布団乾燥機の使用
- 室内の換気を徹底する
食物アレルギーと肌の関係性
特定の食べ物を摂取した後に、じんましんやかゆみ、赤みなどの皮膚症状が現れる場合、食物アレルギーの可能性があります。乳幼児では鶏卵、牛乳、小麦が、学童期以降では甲殻類や果物、そば、ピーナッツなどが多いです。
食物アレルギーが直接アトピー性皮膚炎の原因になることは多くありませんが、もともとアトピー性皮膚炎がある人が、原因となる食物を摂取することで皮膚症状が悪化することはよくあります。
原因食物を特定せずに、自己判断で食事制限をすることは、栄養の偏りを招き、かえって子どもの成長や健康を害する危険性があるので絶対にやめましょう。必ず専門医の診断のもと、指導を受けてください。
花粉や黄砂など季節性のアレルゲン
スギやヒノキなどの花粉は、鼻や目の粘膜だけでなく、皮膚にも影響を及ぼし、花粉皮膚炎と呼ばれる肌荒れを起こすことがあり、目の周りや首筋など、露出していて皮膚が薄い部分に赤みやかゆみが出やすいのが特徴です。
肌のバリア機能が低下していると、花粉が皮膚から侵入しやすくなり、症状が悪化します。春先に飛散する黄砂やPM2.5などの大気汚染物質も、皮膚に付着して刺激となり、アレルギー症状を悪化させる一因と考えられています。
外出時にはマスクや眼鏡、帽子を着用し、帰宅後はすぐにシャワーを浴びて皮膚に付着したアレルゲンを洗い流すなどの対策が有効です。
ペットの毛やフケも原因に
犬や猫などのペットの毛、フケ、唾液、尿などもアレルゲンとなり得、皮膚に付着したり、空気中に舞っているものを吸い込んだりすることで、アレルギー反応が誘発されます。
室内でペットを飼っている場合、アレルゲンは家のいたるところにあるため、完全に避けることは困難です。
症状を緩和するためには、ペットの体を清潔に保つ、寝室にはペットを入れない、空気清浄機を活用する、掃除を徹底するなどの工夫が必要になります。
ペットを飼い始めてから皮膚症状が悪化した場合は、一度アレルギー検査を受けることを検討しましょう。
ペットアレルゲンへの対策
| 対策項目 | 具体的な方法 |
|---|---|
| ペット自身のケア | 定期的なシャンプーやブラッシングで抜け毛やフケを減らす |
| 生活空間の分離 | 寝室など、特定の部屋にはペットを入れないようにする |
| 室内環境の管理 | こまめな掃除、換気、空気清浄機の使用 |
刺激を避けるスキンケアの基礎
アレルギーによる肌荒れや湿疹がある場合、皮膚は非常にデリケートな状態になっていて、健康な肌なら問題にならないようなわずかな刺激でも、症状を悪化させる原因になりかねません。
毎日のスキンケアでは、肌への負担を最小限に抑え、バリア機能をサポートすることが何よりも大切です。
洗浄料の選び方と正しい洗い方
肌の汚れや汗、付着したアレルゲンを落とすための洗浄はスキンケアの基本ですが、洗いすぎは禁物です。
洗浄力の強い洗浄料を使ったり、ゴシゴシこすったりすると、肌の潤いを保つために必要な皮脂や天然保湿因子まで洗い流してしまい、バリア機能の低下を招きます。
洗浄料は、肌への刺激が少ない弱酸性で、保湿成分が配合されたものを選びましょう。洗浄料は手のひらで十分に泡立て、肌の上で泡を転がすように優しく洗います。
症状が出やすい部分は、刺激を避けるように丁寧に洗い、また、すすぎ残しはかゆみの原因になるため、ぬるま湯で時間をかけてしっかりと洗い流すことが重要です。
保湿の重要性と保湿剤の種類
アレルギー症状のある肌は、バリア機能が低下して乾燥しやすい状態にあり、皮膚の乾燥はかゆみを誘発し、掻き壊すことでさらにバリア機能が損なわれるという悪循環を生み出します。
この悪循環を断ち切るために、保湿ケアは一日も欠かせません。入浴やシャワーの後は、肌の水分が最も失われやすいタイミングなので、タオルで優しく水分を押さえるように拭き取ったら、間髪を入れずに保湿剤をたっぷりと塗りましょう。
保湿剤の種類と特徴
| 種類 | 特徴 | 適した部位・季節 |
|---|---|---|
| ローション | 水分が多く、さっぱりした使用感。広範囲に塗りやすい。 | 全身、夏場、軽度の乾燥 |
| クリーム | 油分と水分がバランス良く配合。しっとりした使用感。 | 部分的な乾燥、秋冬 |
| 軟膏 | 油分が主成分。保護力が高く、刺激が少ない。 | 特に乾燥が強い部位、ジュクジュクした湿疹 |
紫外線対策の必要性
紫外線は、皮膚のバリア機能を低下させ、炎症を悪化させる要因となります。日焼けは一種のやけどであり、肌に大きなダメージを与えます。
アレルギー症状がある肌は、紫外線によるダメージを受けやすいため、季節を問わず紫外線対策を徹底することが大切です。
日焼け止めを選ぶ際は、紫外線吸収剤を含まないノンケミカル処方で、肌への刺激が少ないもの(低刺激性、アレルギーテスト済みなど)を選びましょう。
SPFやPAの値が高いものが必ずしも良いわけではなく、日常生活ではSPF15~20、PA++程度のもので十分です。汗をかいたらこまめに塗り直すことも忘れないでください。
メイク用品の選び方と注意点
肌の調子が悪いときは、できるだけメイクを控えるのが理想ですが、仕事などでどうしてもメイクが必要な場合は、アイテム選びと使い方に工夫が必要です。ファンデーションは、肌への負担が少ないパウダータイプを選び、厚塗りは避けましょう。
アイメイクや口紅は、色素沈着やアレルギー反応を起こしやすいことがあるため、症状が出ている部位への使用は控え、メイク用品は、アレルギーテスト済みやパッチテスト済みの表示がある、低刺激性の製品を選ぶと安心です。
肌のバリア機能を高める生活習慣
スキンケアによる外側からのアプローチと同時に、体の内側から肌を健やかに保つための生活習慣を見直すことも、アレルギー症状の改善には欠かせません。食事や睡眠、ストレス管理など、日々の積み重ねが肌の抵抗力を育みます。
バランスの取れた食事と栄養素
健やかな皮膚を作るためには、様々な栄養素をバランス良く摂取することが基本です。特定の食品が肌に良いと聞くとそればかりを摂取しがちですが、偏った食事はかえって栄養バランスを崩す原因になります。
皮膚の細胞の材料となるタンパク質、肌の新陳代謝を助けるビタミンB群、抗酸化作用のあるビタミンA・C・E、そして腸内環境を整える食物繊維などを意識して、多様な食材から摂るように心がけましょう。
インスタント食品やスナック菓子などに含まれる食品添加物や質の悪い油は、腸内環境を乱し、アレルギー症状を悪化させる可能性があるので、摂りすぎには注意が必要です。
肌の健康を支える栄養素
- タンパク質(肉、魚、大豆製品、卵)
- ビタミンB群(豚肉、レバー、うなぎ、玄米)
- ビタミンA・C・E(緑黄色野菜、果物、ナッツ類)
- 必須脂肪酸(青魚、亜麻仁油、えごま油)
- 食物繊維(野菜、きのこ、海藻)
質の良い睡眠が肌を育む
睡眠中には、体の成長や修復を促す成長ホルモンが分泌され、成長ホルモンは、日中に受けた肌ダメージを修復し、皮膚のターンオーバー(新陳代謝)を正常に保つために重要です。
睡眠不足が続くと成長ホルモンの分泌が減少し、肌の再生が滞ることでバリア機能が低下し、アレルギー症状が悪化しやすくなります。また、睡眠不足は自律神経の乱れにもつながり、かゆみを感じやすくなることもあります。
ストレスと肌荒れの悪循環を断つ
ストレスを感じると、体はストレスホルモンであるコルチゾールを分泌し、免疫機能を抑制したり、皮膚のバリア機能を低下させたりする作用があり、アレルギー症状を悪化させる一因となります。
また、ストレスはかゆみを増強させることも知られており、かゆいから掻く、掻くと症状が悪化してさらにストレスが溜まる、という悪循環に陥りがちです。
自分が何にストレスを感じるのかを把握し、自分なりのストレス解消法を見つけることが大切です。趣味に没頭する時間を作ったり、軽い運動で気分転換をしたり、信頼できる人に話を聞いてもらったりするだけでも、心は軽くなります。
ストレスサインの例
| 身体的サイン | 精神的サイン | 行動的サイン |
|---|---|---|
| 頭痛、肩こり、不眠 | 不安、イライラ、集中力低下 | 食欲の変化、ミスが増える |
| 動悸、めまい、疲労感 | 気分の落ち込み、興味の喪失 | 飲酒・喫煙量の増加 |
適度な運動で血行を促進
適度な運動は全身の血行を促進し、皮膚の細胞に十分な栄養と酸素を届ける助けとなり、血行が良くなることで、肌のターンオーバーが整い、バリア機能の向上につながります。
また、運動はストレス解消にも効果的であり、心地よい疲労感は質の良い睡眠へと導いてくれます。ただし、激しい運動で大量の汗をかくと、汗が刺激となってかゆみを起こすことがあります。
運動後は速やかにシャワーを浴びて汗を洗い流し、しっかりと保湿ケアをすることを忘れないようにしましょう。
衣類や寝具の選び方と管理
毎日長時間肌に触れる衣類や寝具は、皮膚への刺激となり、アレルギー症状を悪化させる原因になることがあります。素材の選び方や洗濯の方法に少し気を配るだけで、肌への負担を大きく減らすことができます。
肌に優しい素材を選ぶ
肌がデリケートな状態のときは、衣類の素材選びが特に重要で、直接肌に触れる下着や肌着は、吸湿性・通気性に優れ、肌触りの柔らかい天然素材がおすすめです。
化学繊維の中には、汗を吸いにくく蒸れやすいため、かゆみを誘発するものがあります。また、衣類の縫い目やタグ、装飾などが肌に擦れて刺激になることもあるため、デザインはできるだけシンプルなものを選びましょう。
肌に優しい衣類の素材
| おすすめの素材 | 特徴 |
|---|---|
| 綿(コットン) | 吸湿性・通気性が高く、肌触りが柔らかい。刺激が少ない。 |
| 絹(シルク) | 人間の皮膚に近いタンパク質で構成され、肌なじみが良い。保湿性も高い。 |
| リネン(麻) | 通気性・吸湿性に優れ、熱を逃しやすい。夏場に適している。 |
洗剤や柔軟剤の選び方
洗濯用の洗剤や柔軟剤に含まれる香料、蛍光増白剤、界面活性剤などが衣類に残り、皮膚への刺激となることがあり、香りの強い製品や、洗浄力の高さをうたった製品は注意が必要です。
洗剤は、無添加や低刺激性を表示している、できるだけシンプルな成分のものを選びましょう。柔軟剤は、衣類を柔らかくする一方で、化学物質が繊維に残りやすいため、肌の症状が悪いときは使用を控えるのが無難です。
洗剤の量を規定より多く入れても洗浄力は上がらず、すすぎ残しの原因になるので、必ず規定量を守って使いましょう。
洗濯時の注意点
- 洗剤は規定量を守る
- すすぎは十分に行う(注水すすぎがおすすめ)
- 香料や蛍光増白剤を含まない製品を選ぶ
- 柔軟剤の使用は慎重に
こまめな洗濯と清潔な環境づくり
衣類や寝具には、汗や皮脂、フケなどが付着し、それをエサに雑菌やダニが繁殖しやすくなり、肌への刺激となります。特に、一晩中肌に触れるシーツや枕カバーは、こまめに洗濯して清潔に保つことが大切です。
可能であれば、週に1回は洗濯するように心がけましょう。また、洗濯物は天日干しでしっかりと乾かすことで、殺菌効果も期待できます。
雨の日などで部屋干しをする場合は、雑菌が繁殖しないよう、除湿器や扇風機を活用して速やかに乾かす工夫が必要です。
アレルギー症状を悪化させないための注意点
アレルギーによる湿疹や肌荒れは、些細なことがきっかけで悪化してしまうことがあります。かゆみとの付き合い方や、汗をかいた後のケア、室内の環境管理など、症状を安定させるために日常生活で気をつけたいポイントを解説します。
肌をかきむしらないための工夫
アレルギー性の湿疹に伴う強いかゆみは、非常につらいものですが、かきむしってしまうと、皮膚のバリアが破壊され、そこから細菌が侵入して二次感染(とびひなど)を起こしたり、炎症がさらに広がったりしてしまいます。
わかっていても掻いてしまうのがかゆみの厄介なところです。かゆみを感じたときは、冷たいタオルや保冷剤を当てることで、一時的にかゆみを和らげることができます。
爪は常に短く切り、就寝中に無意識に掻いてしまうのを防ぐために、綿の手袋をして寝るのも一つの方法です。
かゆみを和らげる工夫
- 患部を冷やす
- 爪を短く切っておく
- 就寝時に綿の手袋を着用する
- 気を紛らわす
- 処方された薬を適切に使う
汗をかいた後の適切なケア
汗そのものは悪いものではありませんが、汗に含まれる塩分やアンモニア、そして汗が蒸発せずに皮膚表面に残ることが、肌への刺激となりかゆみを起こします。夏場や運動後など、汗をたくさんかいた後は、そのまま放置しないことが重要です。
できるだけ速やかにシャワーを浴びるか、それが難しい場合は、濡れたタオルで優しく汗を拭き取ります。乾いたタオルでゴシゴシこすると、摩擦で肌を傷つけてしまうので避けましょう。
汗を拭き取った後は、必ず保湿剤を塗り直して、肌の潤いを補給することを忘れないでください。
湿度と温度の管理
空気が乾燥すると、皮膚の水分も奪われやすくなり、肌の乾燥が進んでかゆみが増します。特に冬場は、暖房の使用によって室内が非常に乾燥しやすいため、加湿器などを利用して適切な湿度を保つことが大切です。
一方で、湿度が高すぎるとカビやダニが繁殖しやすくなるため、こちらも注意が必要です。また、急激な温度変化や、体の温めすぎは、血行が良くなることでかゆみを増強させることがあります。
熱いお風呂は避け、ぬるめのお湯にゆっくり浸かりましょう。
適切な室内環境の目安
| 項目 | 目安 | 調整方法 |
|---|---|---|
| 温度 | 20~25℃ | エアコンなどで調整 |
| 湿度 | 50~60% | 加湿器や除湿器、換気を活用 |
専門的な治療と向き合う
セルフケアを続けても症状が改善しない場合や、原因がはっきりしない場合は、皮膚科専門医による診断と治療が必要です。医療機関では、原因を特定するための検査や、症状をコントロールするための様々な治療法があります。
皮膚科で行う検査の種類
皮膚科では、アレルギーの原因を特定するためにいくつかの検査を行い、どの検査を行うかは、症状や疑われるアレルゲンによって医師が判断します。
代表的なものに、血液検査(特異的IgE抗体検査)があり、これは、採血によって、特定のアレルゲンに対して体内で作られるIgE抗体の量を調べるもので、一度に多くのアレルゲンについて調べることが可能です。
また、化粧品や金属などのかぶれが疑われる場合は、原因と思われる物質を皮膚に貼り付けて反応を見るパッチテストを行います。
皮膚科で行う主なアレルギー検査
| 検査名 | 方法 | 主に調べるアレルゲン |
|---|---|---|
| 血液検査(特異的IgE抗体検査) | 採血して、アレルゲンに反応する抗体を測定する | 食物、ダニ、花粉、カビなど |
| パッチテスト | 原因物質を背中などに貼り、48時間後と72時間後に皮膚の反応を見る | 金属、化粧品成分、薬剤、うるしなど |
| プリックテスト | アレルゲン液を皮膚に一滴垂らし、専用の針で軽く刺して反応を見る | 食物、花粉など(主に即時型反応) |
主な治療法と薬の種類
アレルギー性の皮膚炎の治療の基本は、スキンケアによるバリア機能の回復、原因アレルゲンの除去・回避、薬物療法による炎症のコントロールの3本柱です。薬物療法では、主に外用薬(塗り薬)と内服薬(飲み薬)が用いられます。
外用薬の中心となるのが、皮膚の炎症を強力に抑えるステロイド外用薬です。症状の強さや部位に応じて適切な強さの薬を使い分け、また、免疫の過剰な働きを抑えるタクロリムス軟膏や、非ステロイド性の抗炎症薬が使われることもあります。
かゆみが強い場合には、抗ヒスタミン薬や抗アレルギー薬の飲み薬を併用し、かゆみの悪循環を断ち切ります。
治療で使われる主な外用薬
- ステロイド外用薬
- 免疫抑制外用薬(タクロリムスなど)
- 非ステロイド性抗炎症薬
- 保湿剤
治療期間と根気強い継続の必要性
アレルギー性の皮膚疾患は、高血圧や糖尿病などの生活習慣病と同じように、慢性的な経過をたどることが多い疾患です。薬を使って一時的に症状がきれいになっても、アレルギー体質そのものが治ったわけではありません。
治療をやめたり、セルフケアを怠ったりすると、再び症状が悪化することがあります。症状が良い状態を長く維持するためには、医師の指示に従って根気強く治療を続けることが大事です。
症状が落ち着いてからも、保湿などのスキンケアを継続し、アレルゲンを避ける生活を心がけることで、再発を防ぎ、薬の使用量を減らしていくことが可能になります。
よくある質問
ここでは、アレルギー性の湿疹や肌荒れに関して、患者さんからよく寄せられる質問と回答をまとめました。
- アレルギーは遺伝しますか
-
アレルギーのなりやすさ、アレルギー体質は遺伝する傾向があると考えられています。
ご両親ともにアレルギー疾患(アトピー性皮膚炎、気管支喘息、アレルギー性鼻炎など)がある場合、お子さんが何らかのアレルギー疾患を発症する可能性は高くなります。
ただし、遺伝するのはあくまでアレルギーになりやすい体質であり、必ずしも同じアレルギー疾患を発症するわけではありません。また、両親にアレルギーがなくても発症することもあります。
アレルギーの発症には、遺伝的要因だけでなく、食生活や住環境などの環境要因も大きく関わっています。
- 赤ちゃんや子どものアレルギー対策で気をつけることは何ですか
-
赤ちゃんの皮膚は大人に比べて非常に薄く、バリア機能も未熟なため、外部からの刺激に弱く、乾燥しやすいです。
毎日の保湿ケアで皮膚のバリア機能を補ってあげることが、アレルゲンの侵入を防ぎ、アレルギー発症の予防にもつながります。
また、離乳食を始める際には、自己判断で特定のアレルギー食材を避けたり、開始を遅らせたりせず、かかりつけ医の指導のもとで適切な時期に進めることが重要です。
- アレルギー検査はどのタイミングで受けるべきですか
-
アレルギーが疑われる症状が続いている場合、まずは皮膚科を受診して医師に相談することが第一です。
アレルギー検査は、原因アレルゲンを特定し、今後の対策を立てる上で非常に有用ですが、検査を行うタイミングは医師が判断します。
乳児期の血液検査では、まだIgE抗体が十分に作られていないため、アレルゲンがあっても陰性と出ることがあります。また、検査で陽性反応が出たからといって、必ずしもそれが症状の直接の原因であるとは限りません。
症状の経過や診察所見と合わせて総合的に判断することが大切なので、自己判断で検査を求めるのではなく、まずは医師の診察を受けましょう。
- 薬を使い続けることに抵抗があります
-
特にステロイド外用薬に対して、副作用を心配して使用に抵抗を感じる方も少なくありません。
しかし、皮膚科で処方されるステロイド外用薬は、医師が患者さん一人ひとりの症状、部位、年齢に合わせて適切な強さのものを選択しています。
指示通りに、適切な量を適切な期間使用する限り、重篤な副作用が起こることはほとんどありません。
薬を使うことをためらって弱い炎症を放置するほうが、症状を慢性化させ、結果的により多くの薬を長期間使わなければならなくなる可能性があります。
まずはしっかりと炎症を抑え、症状が改善したら、徐々に薬を減らしたり、弱いものに変更したりしていきます。
以上
参考文献
Yamamoto-Hanada K, Suzuki Y, Yang L, Saito-Abe M, Sato M, Mezawa H, Nishizato M, Kato N, Ito Y, Hashimoto K, Ohya Y. Persistent eczema leads to both impaired growth and food allergy: JECS birth cohort. PLoS One. 2021 Dec 1;16(12):e0260447.
Kusunoki T, Morimoto T, Sakuma M, Mukaida K, Yasumi T, Nishikomori R, Heike T. Effect of eczema on the association between season of birth and food allergy in J apanese children. Pediatrics International. 2013 Feb;55(1):7-10.
Sasaki M, Yoshida K, Adachi Y, Furukawa M, Itazawa T, Odajima H, Saito H, Hide M, Akasawa A. Environmental factors associated with childhood eczema: findings from a national web-based survey. Allergology International. 2016;65(4):420-4.
Yamamoto-Hanada K, Pak K, Saito-Abe M, Yang L, Sato M, Irahara M, Mezawa H, Sasaki H, Nishizato M, Ishitsuka K, Ohya Y. Allergy and immunology in young children of Japan: the JECS cohort. World Allergy Organization Journal. 2020 Nov 1;13(11):100479.
Osawa R, Konno S, Akiyama M, Nemoto-Hasebe I, Nomura T, Nomura Y, Abe R, Sandilands A, McLean WI, Hizawa N, Nishimura M. Japanese-specific filaggrin gene mutations in Japanese patients suffering from atopic eczema and asthma. Journal of investigative dermatology. 2010 Dec 1;130(12):2834.
Ring J, Darsow U, Behrendt H. Atopic eczema and allergy. Current Allergy and Asthma Reports. 2001 Jan;1(1):39-43.
Hill DA, Grundmeier RW, Ram G, Spergel JM. The epidemiologic characteristics of healthcare provider-diagnosed eczema, asthma, allergic rhinitis, and food allergy in children: a retrospective cohort study. BMC pediatrics. 2016 Aug 20;16(1):133.
Worth A, Sheikh A. Food allergy and atopic eczema. Current opinion in allergy and clinical immunology. 2010 Jun 1;10(3):226-30.
Ferreira MA, Vonk JM, Baurecht H, Marenholz I, Tian C, Hoffman JD, Helmer Q, Tillander A, Ullemar V, Van Dongen J, Lu Y. Shared genetic origin of asthma, hay fever and eczema elucidates allergic disease biology. Nature genetics. 2017 Dec 1;49(12):1752-7.
Tan RA, Corren J. The relationship of rhinitis and asthma, sinusitis, food allergy, and eczema. Immunology and Allergy Clinics. 2011 Aug 1;31(3):481-91.