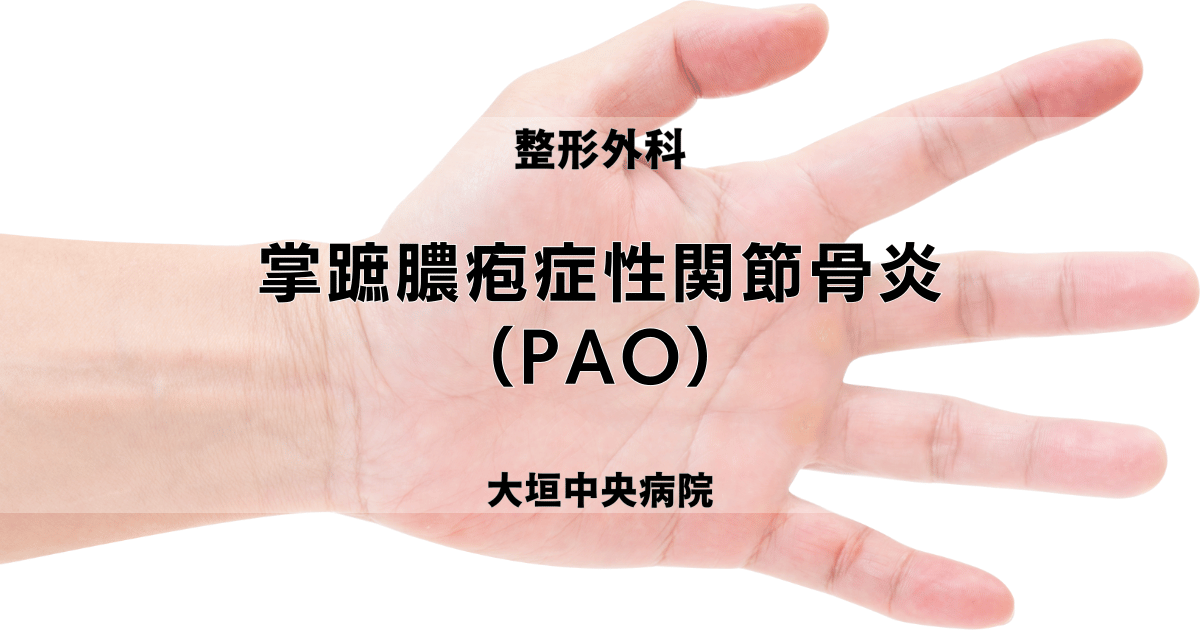掌蹠膿疱症性関節骨炎(しょうせきのうほうしょうせい かんせつこつえん, pustulotic arthro-osteitis: PAO)とは、手のひらや足の裏に反復的に膿疱(のうほう)ができる掌蹠膿疱症に併発する関節や骨の炎症です。
手足の皮膚症状とともに胸鎖関節や肋骨、脊椎などの骨や関節に強い痛みやはれを生じるため、日常生活に大きな影響を与えます。
典型的には、胸鎖関節や胸骨など前胸部の骨関節に慢性反復性の炎症と肥厚性変化を来たし、手掌・足底の膿疱性皮疹を伴います。
原因や治療法は複合的であり、皮膚科と整形外科の連携が重要です。早期に医療機関を受診して適切な治療を行うと、痛みを軽減して生活の質を改善する可能性があります。
この記事の執筆者

臼井 大記(うすい だいき)
日本整形外科学会認定専門医
医療社団法人豊正会大垣中央病院 整形外科・麻酔科 担当医師
2009年に帝京大学医学部医学科卒業後、厚生中央病院に勤務。東京医大病院麻酔科に入局後、カンボジアSun International Clinicに従事し、ノースウェスタン大学にて学位取得(修士)。帰国後、岐阜大学附属病院、高山赤十字病院、岐阜総合医療センター、岐阜赤十字病院で整形外科医として勤務。2023年4月より大垣中央病院に入職、整形外科・麻酔科の担当医を務める。
掌蹠膿疱症性関節骨炎の病型
掌蹠膿疱症性関節骨炎(しょうせきのうほうしょうせい かんせつこつえん)はSAPHO症候群※1の中でも掌蹠膿疱症を伴う骨関節炎に相当し、しばしばSAPHO症候群と同義に扱われます。
※1 SAPHO症候群(サフォー症候群):皮膚や骨、関節に様々な症状が現れる慢性疾患を指す。原因不明の病気であり、滑膜炎(Synovitis)、ざ瘡(Acne)、膿疱(Pustulosis)、骨過形成(Hyperostosis)、骨髄炎(Osteitis)の頭文字をとって名づけられたもの。
SAPHO症候群の診断基準として広く用いられるKahn基準やBenhamou基準では、「掌蹠膿疱症を伴う骨関節炎」が主要な構成要素の一つに挙げられています。
発症様式による病型
臨床像の種類として、発症様式による病型が報告されています。
海外報告では「関節炎先行型」32%、「皮膚膿疱症先行型」39%、「同時発症型」29%とほぼ均等ですが、日本の報告では皮膚症状が先行する例が約66%と多く、関節炎先行型27%、同時発症型7%とされています。
つまり、日本人患者ではまず掌蹠膿疱症が出現し、その数か月~数年後に骨関節炎を発症するケースが過半を占めます。
皮膚病変の種類による分類
また、皮膚病変の種類により「掌蹠膿疱症合併型」「尋常性ざ瘡(重症ざ瘡)型」「乾癬型」などに分類するケースもあります(実際には3者併存例もあり診断を難しくしています)。
その他の分類
なおHLA-B27抗原は他の脊椎関節炎ほど高頻度ではないものの、本症患者の数~30%で陽性との報告があり、病態的に脊椎関節炎(いわゆる炎症性腰痛疾患)のグループに含める見解もあります。
掌蹠膿疱症性関節骨炎の症状
掌蹠膿疱症性関節骨炎(しょうせきのうほうしょうせい かんせつこつえん)の症状は、手足の皮膚症状にとどまらず、骨や関節にさまざまな影響を及ぼします。
初期の段階で気づきにくい場合もあり、対策が遅れると慢性的な痛みや機能障害につながります。
皮膚症状
掌蹠膿疱症(PPP)をはじめとする皮膚症状は、患者さんの約80%以上で認められます。
なかでもPPPが約30%と代表的ですが、他にも尋常性ざ瘡(重症のにきび)の合併が約20%、尋常性乾癬の合併が約10%、PPPと乾癬の両者を合併する例が20%程度報告されています。
さらに、10%弱の人ではPPP・ざ瘡・乾癬の3つ全てがみられるとの報告もあり、皮疹が多彩なケースでは骨関節病変との関連に気付きにくく診断が遅れる場合があります。
一方で、全体の15%前後(報告により10~20%)の人では長年の経過でも皮膚症状を全く伴わないときがあり、この場合は特発性の慢性骨髄炎として扱われて見逃されるリスクがあります。
掌蹠膿疱症以外の皮膚所見として、爪の変形や指先の膿疱・鱗屑、肘膝の紅斑(掌蹠外乾癬様病変)などが認められるときもあります。
関節や骨の症状
最も特徴的かつ頻度が高いのは前胸壁(胸鎖関節および胸骨柄部)の痛み・腫れです。
胸鎖関節部に慢性的な疼痛や腫脹、圧痛を生じ、X線やCTでは骨硬化と骨肥厚、関節の癒合を来たす人もいます。
前胸壁の病変に次いで脊椎や仙腸関節など体軸骨格の疼痛が多く、患者さんの10~40%に脊椎炎や仙腸関節炎がみられます。
関節の症状で見られる主なサイン
| 症状 | 具体例 | 注意点 |
|---|---|---|
| 痛みの出現 | 胸鎖関節や肋骨に鋭い痛み | 慢性化により広範囲におよぶ可能性 |
| 腫れや熱感 | 患部が赤く腫れる | 関節の中で炎症が強まっている合図 |
| 可動域の制限 | 腕や上半身が動かしにくい | 姿勢が崩れて他の部位に影響する |
| 疲労感の増大 | 痛みで睡眠が妨げられる | 生活リズムが崩れる可能性 |
痛みだけでなく腫れや可動域の制限など複数のサインが出たときには、早めに整形外科医へ相談しましょう。
生活への影響
胸鎖関節付近や肋骨の痛みが強いと、呼吸が浅くなったり運動量が減ったりします。結果として筋力や体力が落ち、疲れやすさが増す悪循環に陥る場合があります。
さらに、痛みから姿勢が悪くなると他の部位に負担がかかりやすくなります。
症状の悪化要因
ストレスや過労、喫煙や過度の飲酒などは、皮膚症状だけでなく関節症状を悪化させる引き金になりやすいです。
長時間の同じ姿勢や偏った食生活も体力の低下につながるので、普段から注意が必要になります。
- 痛みを感じたら我慢せず休憩を挟む
- なるべく規則正しい睡眠と食事を心がける
- 喫煙習慣を見直す
- 痛みが増したときは整形外科医に相談する
痛みや皮膚症状を軽視せず、自分の身体と向き合う姿勢が大切です。
掌蹠膿疱症性関節骨炎の原因
掌蹠膿疱症性関節骨炎(しょうせきのうほうしょうせい かんせつこつえん)の原因や発症メカニズムは、いまだに明確になっていません。
ただ、自己炎症性疾患の一種と考えられ、慢性の無菌性骨髄炎(骨炎)に皮膚の角化症状を合併する疾患群と位置付けられています。
慢性感染巣に対する免疫反応
有力な仮説の一つは「慢性感染巣に対する免疫反応」です。
病変部位から検出される病原性の低い細菌※2が持続的抗原刺激となり、自然免疫系が活性化して骨への無菌性炎症を引き起こすという機序です。
※2病変部位から検出される病原性の低い細菌:いわゆる日和見菌。例として、Cutibacterium acnes(アクネ菌、ニキビ菌)やブドウ球菌などが挙げられる。
また、慢性扁桃炎や歯科疾患、副鼻腔炎など局所の慢性感染病巣が掌蹠膿疱症を誘発・増悪させることは古くから知られており、報告によれば本症患者の67%に扁桃病巣の合併がみられ、慢性扁桃炎を有する症例では皮膚・関節症状が重症化する傾向が示されています。
歯根部の慢性膿瘍や副鼻腔炎についても同様で、これら病巣感染の治療によって症状が改善する例が報告されています。
遺伝的素因
明確な責任遺伝子は特定されていません。家族内発症例の報告は散見されるものの、現時点では明らかな遺伝形式はなく多因子的背景が推測されています。
生活習慣・環境要因
喫煙は掌蹠膿疱症(PPP)発症の主要な危険因子であり、本症患者でも喫煙者が多い事実から禁煙指導が重要です。掌蹠膿疱症患者の80%以上が喫煙者との報告もあります。
複合的な要因があると考えられる
掌蹠膿疱症性関節骨炎の病因は「感染、免疫、遺伝、骨代謝の複合的要因」による慢性炎症と考えられており、特に慢性感染(扁桃・歯・副鼻腔など)に対する異常な免疫反応が骨関節と皮膚の炎症を惹起する可能性が重視されています。
掌蹠膿疱症性関節骨炎の検査・チェック方法
掌蹠膿疱症性関節骨炎(しょうせきのうほうしょうせい かんせつこつえん)には特異的な確立診断基準はありませんが、SAPHO症候群全体の診断にはKahnら(1994/2003年改訂)やBenhamouら(1988年)の提唱した基準が臨床で用いられます。
Benhamou基準と掌蹠膿疱症性関節骨炎(PAO)の診断
Benhamou基準では、以下のいずれか1つの所見を満たし、感染性病変など除外項目がない場合にSAPHOと診断するとされています。
- 重症ざ瘡の骨関節病変
- 掌蹠膿疱症の骨関節病変
- 皮疹の有無を問わない骨肥厚症
- 皮疹の有無を問わない慢性再発性多発性骨髄炎
掌蹠膿疱症性関節骨炎(PAO)の診断も基本的には「掌蹠膿疱症の既往/合併」+「無菌性の骨関節炎所見」+「感染症や腫瘍の除外」という総合判定になります
画像検査
レントゲン(X線)やCT、MRIなどの画像検査を用いて、骨や関節の変化、炎症の程度を評価します。
胸鎖関節や肋骨周辺のレントゲン検査で骨びらんや骨肥厚が確認されるときがあります。
MRIは軟骨や靭帯など、レントゲンでは見にくい部位も詳細に評価できるため、症状や疑いの程度に応じて選択します。
画像検査の結果は、治療方法や薬の選択にも影響します。
| 検査 | 目的 |
|---|---|
| レントゲン | 骨の形状、骨びらん、関節の隙間を把握 |
| CT | 細部の骨の状態を立体的に確認 |
| MRI | 軟骨、靭帯、筋肉の炎症や状態を詳細に確認 |
X線・CT
X線やCTでは胸鎖関節部の骨硬化像や関節強直、肋骨-胸骨間の骨増殖・癒合といった骨肥厚性変化(hyperostosis)が捉えられます。
四肢長管骨では骨硬化と骨膜肥厚、時に骨膜下の新生骨形成像が特徴的です。
脊椎病変は椎体前面の骨硬化や椎体辺縁の角状骨増生、また椎間板炎(septicではない無菌性脊椎炎)として描出される場合があります。
MRI
MRIは炎症初期の骨髄浮腫(bone marrow edema)や軟部の変化を検出するのに有用で、X線上で構造変化が判明するより前の早期段階で骨病変を可視化できます。
脊椎や仙腸関節など、深部病変の評価にはMRIがとくに役立ちます。
血液検査
- CRPや赤血球沈降速度(ESR)が高い場合は炎症が強い可能性
- 免疫指標が異常を示した場合は自己免疫系の関与が示唆される
血液検査では炎症反応の指標となるCRP(C反応性蛋白)や白血球数、免疫系の異常を示す自己抗体の有無などを調べます。
ただし、血液検査だけでは掌蹠膿疱症性関節骨炎の確定診断には至らないケースが多いです。そのため、画像検査や皮膚検査と総合的に判断する必要があります。
リウマチ因子や抗核抗体は、通常陰性です。
複数の方法を組み合わせた多角的な評価
画像検査や皮膚検査と血液検査を組み合わせた多角的な評価が、早期診断や病型特定の助けになります。
- 痛みや炎症の程度を客観的に把握できる
- 治療効果をモニターし、方針を適宜修正できる
- 無理のないペースで検査や診察を継続できるよう計画を立てる
複数の検査結果を総合的に解釈してこそ、正確な診断につながります。
掌蹠膿疱症性関節骨炎の治療方法と治療薬、リハビリテーション、治療期間
掌蹠膿疱症性関節骨炎(しょうせきのうほうしょうせい かんせつこつえん)の治療では、皮膚症状と骨・関節症状の両面に働きかけます。
治療目標は、炎症と疼痛のコントロールによる症状緩和はもちろん、関節破壊や骨強直による変形の予防、および炎症の慢性化による合併症リスクの軽減です。
症状の重症度や患者さんの生活スタイルに合わせて、薬物療法やリハビリテーションなどを組み合わせて行う場合が多いです。
感染病巣の除去
まず基盤に慢性扁桃炎や歯科・副鼻腔の感染がないかチェックし、存在するときは耳鼻科・歯科と連携して適切に治療します。
具体的には耳鼻科での扁桃摘出術や副鼻腔炎の治療、歯科での歯根治療や抜歯などを行います。これにより皮膚・骨関節症状が改善するケースもあり、特に難治症例では重要な手順です。
喫煙者には禁煙指導を徹底し、口腔衛生の改善も図ります。感染巣治療は原疾患治療と並行して早期に対処します。
急性期の対症療法
痛みが強い急性増悪期には安静保持や患部の安定化が有効です。
例えば胸鎖関節痛が強ければ上肢を過度に挙上・外転しないよう生活指導し、脊椎痛があるときはコルセットやベルトで支持する場合もあります(ただし、長期の固定は拘縮※3を招くため痛みが治まれば中止します)。
※拘縮(こうしゅく):怪我や病気、寝たきりなどで関節を動かす機会が減って、関節周囲の皮膚や筋肉などの軟部組織が硬くなる。その結果、関節の動きが制限される。
局所の炎症に対してはNSAIDs(非ステロイド抗炎症薬)の内服により疼痛軽減を図ります。効果不十分な激痛には副腎皮質ステロイドの短期間使用も検討されます。
さらに、胸鎖関節や胸肋関節の関節炎が局所に限局している例では、関節内ステロイド注射も疼痛緩和に有効との報告があります。
薬物療法の導入
症状が続くときはメトトレキサート(MTX)やサラゾスルファピリジン(SSZ)、レフルノミド等の従来型DMARD(csDMARD)を導入し、約3か月程度の投与で治療反応を評価します。
末梢関節炎が主体の患者さんでは、MTXやSSZが有効だったとの報告があります (ただし、日本では関節リウマチ以外への適応がなく保険外使用となります)。
一方、仙腸関節炎や脊椎炎など体軸性病変が主体の例では、MTXの効果は乏しいケースが多く、この場合は早めに生物学的製剤の併用を検討します。
生物学的製剤
生物学的製剤ではTNF阻害薬が骨病変・皮膚病変の双方に有効との報告があります。
実際、海外ではNSAIDsやDMARDで無効例の二次治療としてインフリキシマブやエタネルセプト等の抗TNFα抗体が用いられ、60%以上の症例で疼痛や炎症の改善が得られたとの報告があります。
TNF阻害薬は、体軸性病変に対して第一選択となり得ます。加えて近年はIL-17阻害薬やIL-23阻害薬など乾癬領域の新規薬剤も使用可能となっており、これらも難治例で検討されます。
ビスフォスフォネート療法
本症の骨病変に対する特徴的治療としてビスフォスフォネート製剤の投与があります。
ビスフォスフォネートは、破骨細胞の誘導抑制による骨吸収抑制効果を持ち、さらにIL-1β, IL-6, TNFなど炎症性サイトカイン産生を抑えて抗炎症作用を発揮すると考えられています。
脊椎の骨髄浮腫(炎症)に高い効果が報告されており、NSAIDsやステロイド局注で不十分な骨炎病変が速やかに寛解した例が多数報告されています。
抗菌薬療法
慢性骨炎の原因が細菌抗原だとする考えに基づき、抗生物質の長期投与が試みられる場合があります。
例えばある症例では、クリンダマイシン600~1200mg/日+NSAIDsを3か月間内服し、10日で疼痛が消失、その後18か月以上再燃なく経過した例が報告されています。
また、別の報告でも、NSAIDs無効例にミノサイクリン投与で皮疹・関節症状が顕著に改善したとされています。
抗菌薬の効果は症例によってまちまちですが、皮疹がざ瘡優位の症例ではテトラサイクリン系が奏功し得ます。
一般に3か月程度の投与で効果判定し、無効なら中止します。効果があったときも、耐性菌リスクを考慮して6か月以内を目安に終了するケースが多いです。
抗菌薬はあくまで補助療法的位置づけですが、慢性感染の免疫刺激を断つ目的で検討されます。
リハビリテーションの重要性
- ストレッチで硬くなった関節や筋肉をほぐす
- 痛みが少ない範囲で関節を動かす練習をする
- 体幹や筋力を強化して負担を軽減する
- 無理のない有酸素運動で全身の血行を促進する
痛みや炎症をコントロールしたら、リハビリテーションで関節の可動域や筋力を維持・向上させることを目指します。
関節が硬くなると姿勢や動作に支障が出やすくなるため、適切な運動療法が大切です。
リハビリテーションは理学療法士などの専門家の指導のもと行うと、より安全かつ効率的です。
リハビリの進め方
| 流れ | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 痛みの軽減期 | 痛みを抑えながら軽い運動 | アイシングや温熱療法との併用 |
| 可動域拡大期 | ストレッチや関節運動を増やす | 反動をつけずゆっくり動かす |
| 筋力強化期 | 筋トレやバランス運動 | 一度に集中せず日常的に少しずつ |
| 維持期 | 定期的な運動やケア | 疲労や再発に注意しながら継続 |
段階的な取り組みでリハビリを進めるのが、身体への負担を減らし長期的な改善を目指すコツです。
治療期間の目安
治療期間は個人差が大きいですが、軽度の患者さんでも数カ月程度は治療とリハビリテーションを続ける必要があります。
重症では、年単位でのフォローアップが必要となるケースも珍しくありません。
炎症は一時的に治まっても、再燃を繰り返す場合があるので油断せず継続的にケアを行いましょう。
- 治療薬の使用期間は症状と検査結果を見ながら調整する
- リハビリは痛みの有無に関わらず継続することが望ましい
- 症状が安定した後も定期検診を受けて変化をチェックする
自己判断で治療をやめると再燃し、長引くケースがあるので、医師の指示に従って計画的に進めてください。
薬の副作用や治療のデメリット
掌蹠膿疱症性関節骨炎(しょうせきのうほうしょうせい かんせつこつえん)の治療薬には、炎症を抑える強い効果が期待できるものもありますが、その反面、副作用のリスクを伴います。
治療におけるデメリットを正しく理解し、メリットとバランスを取りながら適した治療計画を立てます。
NSAIDsの副作用
非ステロイド性消炎鎮痛薬(NSAIDs)は痛みや炎症を緩和しますが、胃腸障害を引き起こしやすい性質があります。
胃の不快感や胃潰瘍、十二指腸潰瘍などを起こす可能性があるため、胃薬を併用しながら使う場合が多いです。
- 胃のむかつきや吐き気が続くときは医師に相談する
- 長期使用時は定期的に胃の状態をチェックする
- 服用後は水分をしっかりとる
ステロイドの副作用
ステロイドは強力な抗炎症作用を持ちますが、ムーンフェイス(顔が丸くなる)や体重増加、糖尿病の悪化や高血圧、骨粗しょう症など、全身的な副作用を伴う場合があります。
また、急に使用を中止するとリバウンドを起こすリスクもあります。
| リスク | 内容 | 対策 |
|---|---|---|
| ムーンフェイス | 顔に脂肪がつきやすくなる | 食事や生活習慣の管理が大切 |
| 骨粗しょう症 | 骨がもろくなる | カルシウム摂取や適度な運動 |
| 血糖値上昇 | 糖尿病を悪化させる可能性 | 血糖管理と定期的な血液検査 |
| 急な中止の危険 | リバウンドや副腎不全 | 医師の指示に従った減量が必要 |
ステロイドは医師の指導のもと、用量を調整しながら使用すればメリットが大きい薬です。
免疫調整薬・生物学的製剤の副作用
免疫調整薬や生物学的製剤は、自己免疫反応を抑えたり特定の炎症物質をブロックしたりする効果があります。
ただし、感染症にかかりやすくなるリスクが上がる、肝機能や腎機能への負担が増える、といったデメリットがあるため、定期的な血液検査が必要になります。
- 風邪や感染症の初期症状に注意する
- 採血や検尿などで臓器への影響をチェックする
- 異常を感じたらすぐに医師へ相談する
治療を続けるうえでのデメリット
薬の副作用以外にも、長期の通院や検査、リハビリテーションに時間や費用がかかる点は大きな負担となり得ます。
さらに、再燃を繰り返す場合は症状が完全に治まらないまま、治療を継続する必要があります。
それでも放置すると痛みが増したり合併症を招いたりする恐れがあるため、負担を最小限に抑えつつ、できるだけ安定した状態を保つことが重要です。
- 定期的な通院による時間と経済的コスト
- リハビリによる体力的・精神的負担
- 薬の副作用による体調不良の可能性
治療のデメリットを理解しつつ、医師や医療スタッフと相談しながらメリットとのバランスを考えましょう。
保険適用と治療費
以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
掌蹠膿疱症性関節骨炎(しょうせきのうほうしょうせい かんせつこつえん)の治療には複数の診療科が関わる場合があります。
整形外科や皮膚科、歯科などで検査や治療を受ける際の費用が気になる方も多いでしょう。ここでは保険適用の概要や治療費の目安を整理します。
保険適用範囲
日本の公的医療保険(健康保険、国民健康保険など)を利用すると、掌蹠膿疱症性関節骨炎の検査や治療費の多くは保険適用の範囲に入ります。
初診料や再診料、画像検査(レントゲン、CT、MRIなど)、血液検査や治療薬、リハビリテーションなども原則保険対象です。
- 大半の薬物治療や検査は保険の3割負担(一般的な場合)で利用できる
- 歯科治療においても、必要性が認められる処置は保険適用になる
- 生物学的製剤など一部の高額医療も適用条件を満たせば保険対象となる
ただし、自由診療となる特殊な薬や検査は保険適用外になる場合があるので、自分が受ける治療や検査が保険適用かどうか、事前に確認すると安心です。
保険適用の一例
| 治療・検査内容 | 保険適用の有無 | 患者負担 |
|---|---|---|
| 初診・再診料 | 保険適用 | 3割(一般) |
| レントゲン・MRI | 保険適用 | 3割(一般) |
| 処方薬(一般薬) | 保険適用 | 3割(一般) |
| 生物学的製剤 | 保険適用(条件あり) | 3割(一般) |
| 歯科治療 | 保険適用(内容による) | 3割(一般) |
治療費の目安
治療費は個々の症状や治療内容によって異なりますが、一例として大まかな費用感を示します。
- 初診・検査(レントゲン、血液検査)で約3,000~5,000円
- MRI検査を追加すると約5,000~9,000円
- 生物学的製剤を含む治療では、月あたり約1万~2万円程度
- リハビリテーション(物理療法や運動療法)1回あたり約300~500円
治療費を抑えるために
- 月ごとの医療費が高額になる場合は高額療養費制度を確認する
- 医療費控除の対象になる場合は確定申告の準備を進める
- 複数診療科にまたがる場合、通院費や薬代が重複しないよう管理する
症状が長期化して通院やリハビリが増えると、合計の出費もかさむ可能性があります。
高額療養費制度の対象となる場合は、自己負担額が一定額を超えた分が払い戻されるケースもあるので、必要に応じて制度の利用を検討してください。
医療費の負担を抑えながら、適切に治療を続けるために保険制度や公的な支援を上手に活用するとよいでしょう。
以上
参考文献
COJOCARU, SIBEL ALI ANCA; TUDOSE, IRINA; ORZAN, OLGUȚA ANCA. PALMOPLANTAR PUSTULOSIS ASSOCIATED WITH OSTEOARTICULAR PAIN. Dermatovenerologia Journal, 2022, 67.2.
PUTRA-SZCZEPANIAK, Magdalena, et al. Palmoplantar pustulosis: Factors causing and influencing the course of the disease. Advances in Clinical & Experimental Medicine, 2020, 29.1.
OLAZAGASTI, Jeannette M.; MA, Janice E.; WETTER, David A. Clinical features, etiologic factors, associated disorders, and treatment of palmoplantar pustulosis: the Mayo Clinic experience, 1996-2013. In: Mayo Clinic Proceedings. Elsevier, 2017. p. 1351-1358.
FREITAS, Egídio; RODRIGUES, Maria Alexandra; TORRES, Tiago. Diagnosis, screening and treatment of patients with palmoplantar pustulosis (PPP): a review of current practices and recommendations. Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology, 2020, 561-578.
HEIDEMEYER, Kristine, et al. Palmoplantar pustulosis: a systematic review of risk factors and therapies. Psoriasis: Targets and Therapy, 2023, 33-58.
CHENG, Alvan, et al. Treatment Patterns and Negative Health Outcomes in Palmoplantar Pustulosis Patients in Germany and the US. Dermatology and Therapy, 2024, 14.3: 627-641.
RAMCHARRAN, Darmendra, et al. The epidemiology of palmoplantar pustulosis: an analysis of multiple health insurance claims and electronic health records databases. Advances in Therapy, 2023, 40.11: 5090-5101.
YAMAMOTO, Toshiyuki. Guselkumab for the treatment of palmoplantar pustulosis: a Japanese perspective. Clinical Pharmacology: Advances and Applications, 2021, 135-143.
MIYAZAKI, Celine, et al. Treatment patterns and healthcare resource utilization in palmoplantar pustulosis patients in Japan: a claims database study. PLoS One, 2020, 15.5: e0232738.
CZARNECKA, Anna; HYNCEWICZ-GWÓŹDŹ, Anita. Palmoplantar pustulosis: Factors causing and influencing the course of the disease. 2020.