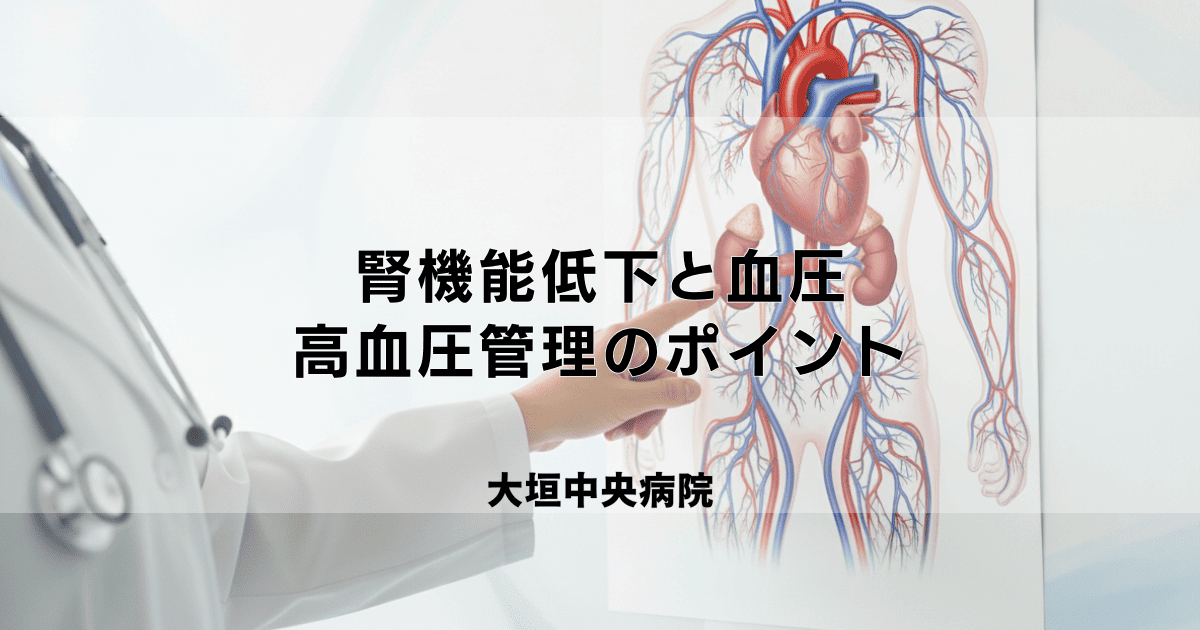腎臓の働きが静かに低下していく状態と、私たちの健康のバロメーターである血圧には、実は非常に深い結びつきがあります。
健康診断などで腎機能の低下を指摘された方や、血圧が高めであると告げられた方の中には、この二つの関係について不安を感じている方もいらっしゃるかもしれません。
この記事では、腎臓と血圧の切っても切れない関係を紐解き、腎機能を守りながら血圧を良好に保つための管理のポイントについて、分かりやすく解説していきます。
腎臓と血圧の密接な関係とは
体内で重要な役割を担う腎臓と、全身の健康状態を示す血圧、この二つは、一見すると別々のものに思えるかもしれませんが、実際には互いに影響を与え合う、車の両輪のような存在です。
どちらかのバランスが崩れると、もう一方にも影響が及ぶことがあります。
生命維持に欠かせない腎臓の働き
腎臓は、腰のあたりに左右一つずつある、そら豆のような形をした臓器です。単に尿を作るだけの臓器と思われがちですが、実際には私たちの生命を維持するために、休むことなく多くの重要な仕事をこなしています。
主な働きは、血液をろ過して体内の老廃物や余分な水分、塩分を尿として排泄することです。
ろ過機能により、体内の水分量やミネラルのバランスが常に一定に保たれ、血液がきれいな状態に維持され、もし腎臓が機能しなくなると、老廃物が体内に溜まり、深刻な事態を招きます。
それ以外にも、血圧を調整するホルモンを分泌したり、血液を作る指令を出すホルモンを産生したり、ビタミンDを活性化させて骨を丈夫に保つなど、役割は多岐にわたります。
腎臓の主な機能
| 機能 | 内容 | 身体への影響 |
|---|---|---|
| 老廃物の排泄 | 血液中の不要な物質を尿として体外に出す | 体内の浄化、体調の維持 |
| 水分・電解質の調整 | 体液の量やナトリウム、カリウム等の濃度を一定に保つ | むくみや脱水の防止、心臓機能の維持 |
| 血圧の調整 | レニンというホルモンを分泌し、血圧をコントロールする | 全身の血圧を安定させる |
血圧とはそもそも何か
血圧とは、心臓から送り出された血液が、血管の壁を押す圧力のことです。心臓が収縮して血液を送り出すときの圧力を収縮期血圧(上の血圧)、心臓が拡張したときの圧力を拡張期血圧(下の血圧)と呼びます。
血圧は常に一定ではなく、時間帯や活動、精神状態によって変動しますが、慢性的に高い状態が続くのが高血圧です。高血圧は血管に常に負担をかけるため、動脈硬化を進行させ、脳卒中や心筋梗塞といった重大な病気のリスクを高めます。
なぜ腎臓と血圧は互いに影響しあうのか
腎臓と血圧の関係が深い最大の理由は、腎臓が体内の水分量と塩分(ナトリウム)量を調整しているからです。
血液中の塩分濃度が高くなると、体はそれを薄めようとして水分を溜め込み、体内を循環する血液の量が増え、血管にかかる圧力、つまり血圧が上昇します。
腎機能が正常であれば、余分な塩分と水分を尿として排泄し、血圧を適切な範囲に保つことができますが、腎機能が低下すると、調整がうまくいかなくなり、高血圧を起こしやすくなるのです。
また、腎臓自身も血圧を上げるホルモン(レニン)を分泌しており、ホルモンの分泌バランスが崩れることも、血圧上昇の一因となります。
腎機能が低下すると高血圧になりやすい理由
腎機能の低下が、なぜ直接的に高血圧につながるのでしょうか。背景には、体内で起こるいくつかの変化が関係しています。
塩分と水分の排出能力の低下
腎機能低下が高血圧を引き起こす最も直接的な原因は、塩分と水分の排泄能力が衰えることです。腎臓は、体にとって不要になった塩分と水分を尿として体外に捨てるフィルターの役割を担っています。
フィルターの目が詰まったり、働きが悪くなったりすると、本来捨てるべき塩分と水分が体内に溜まってしまいます。
体内の塩分が増えると、浸透圧を一定に保つために血管内に水分が引き込まれ、全身を流れる血液の量(循環血液量)が増加します。
水量が増えたホースの圧が高まるのと同じように、循環血液量が増えることで血管壁にかかる圧力が高まり、血圧が上昇するのです。この状態は、特に塩分の多い食事を好む方で顕著に現れます。
高血圧の診断基準(診察室血圧)
| 分類 | 収縮期血圧(上) | 拡張期血圧(下) |
|---|---|---|
| 正常血圧 | 120mmHg未満 | かつ 80mmHg未満 |
| 高血圧 | 140mmHg以上 | または 90mmHg以上 |
血圧を調整するホルモンの乱れ
腎臓は、血圧をコントロールする上で中心的な役割を果たすのが、レニン-アンジオテンシン-アルドステロン系と呼ばれるホルモン系統です。
腎臓への血流が減少したり、腎臓内の圧力が低下したりすると、腎臓はレニンという酵素を分泌し、レニンは、アンジオテンシンという物質を活性化させ、強力な血管収縮作用を持つアンジオテンシンIIを生成します。
アンジオテンシンIIは、血管を直接収縮させて血圧を上げるだけでなく、副腎からアルドステロンというホルモンの分泌を促し、アルドステロンは、腎臓に作用して塩分と水分の再吸収を促進し、体液量を増やしてさらに血圧を上昇させます。
腎機能が低下すると、一連のホルモン系統が過剰に働き、血圧が下がりにくい状態に陥ることがあります。
- レニン
- アンジオテンシン
- アルドステロン
交感神経の過剰な活動
腎機能の低下は、自律神経の一つである交感神経の活動を活発にすることも知られていて、交感神経は、体を活動的な状態にする神経で、心臓の拍動を速めたり、血管を収縮させたりする働きがあります。
腎機能が低下している状態では、腎臓からの信号が脳に伝わり、交感神経が過剰に興奮することがあり、この交感神経の過緊張が、血管を収縮させて血圧を上昇させる一因です。
夜間や早朝に血圧が下がりにくいタイプの高血圧は、交感神経の過剰な活動が関係している可能性も考えられます。
高血圧がさらに腎臓を悪化させる悪循環
腎機能の低下が高血圧を招くだけでなく、高血圧が今度は腎臓自身にダメージを与え、さらに腎機能を悪化させるという、非常に厄介な悪循環に陥ることがあります。この負の連鎖を断ち切ることが、腎臓を守る上で極めて重要です。
腎臓の血管に動脈硬化を引き起こす
腎臓は、非常に細い血管(毛細血管)の塊である糸球体が集まってできていて、糸球体は、血液をろ過するフィルターの役割を担っており、常に高い圧力にさらされています。
高血圧の状態が長く続くと、繊細な糸球体の血管に常に強い圧力がかかり続けることになって、血管の壁が厚く、硬くなる動脈硬化が進行し、この状態を腎硬化症と呼びます。
動脈硬化が進行した血管は、しなやかさを失い、血液がスムーズに流れにくくなり、腎臓への血流が悪化し、腎臓の組織が酸素不足や栄養不足に陥り、徐々にその機能を失っていくのです。
糸球体への過剰な負担
高血圧は、糸球体内部の圧力を異常に高める原因となります。糸球体は、血液をろ過するためにある程度の圧力が必要ですが、圧力が過剰になるとフィルター機能そのものを傷つけてしまいます。
フィルターが傷つくと、本来は血液中に留まるべきタンパク質(特にアルブミン)が尿中へ漏れ出すようになり、これが尿タンパクです。
尿タンパクが出ている状態は、糸球体がダメージを受けている証拠であり、腎機能低下が進行しているサインでもあります。漏れ出したタンパク質自体も腎臓の組織に炎症を起こし、さらに腎臓の障害を加速させる要因となります。
腎機能低下で見られる主なサイン
| サイン | 説明 | 関連する症状 |
|---|---|---|
| 尿タンパク | 尿中にタンパク質が漏れ出ている状態 | 尿の泡立ちが消えにくい |
| むくみ(浮腫) | 体内に余分な水分が溜まること | 足のすねを押すとへこむ、顔がはれぼったい |
| 血尿 | 尿に血液が混じること | 尿が赤色や茶色になる |
腎機能低下の進行を加速させる
腎機能低下によって生じた高血圧が、腎臓の動脈硬化や糸球体障害を生じさせ、それがさらなる腎機能の低下を招きます。そして、腎機能がさらに低下すると、血圧はもっと上がっていくという悪循環が形成されます。
このサイクルを放置すると、腎機能は加速度的に悪化し、最終的には末期腎不全に至り、透析治療や腎移植が必要になる可能性が高まります。
腎機能が低下している場合、血圧を厳格に管理することが、腎臓の寿命を延ばす上で何よりも大切になるのです。
腎機能と血圧の状態を知るための検査
自分の腎臓や血圧がどのような状態にあるのかを正確に把握することは、適切な管理への第一歩です。病院では、血液検査や尿検査、血圧測定などを通じて、腎機能と血圧の状態を多角的に評価します。
尿検査でわかること
尿検査は、体に負担なく腎臓の状態を調べることができる基本的な検査で特に、重要なのが、尿タンパクと尿潜血の有無で、尿タンパクは腎臓のフィルター機能の障害を示唆する重要なサインです。
健康な人でもごく微量のタンパク質は尿に出ることがありますが、持続的に多くのタンパク質が出ている場合は注意が必要です。尿潜血は、尿中に血液が混じっている状態を指し、腎臓や尿路からの出血の可能性を示します。
このような異常が見られた場合は、さらに詳しい検査に進むことになります。
血液検査でわかること
血液検査では、腎臓の働きそのものを数値で評価することができ、最も代表的な項目が血清クレアチニン値です。
クレアチニンは、筋肉でつくられる老廃物の一種で、通常は腎臓から尿中へ排泄されますが、腎機能が低下すると、クレアチニンを十分に排泄できなくなり、血液中の濃度が上昇します。
血清クレアチニン値と年齢、性別から計算されるのがeGFR(推算糸球体ろ過量)です。
eGFRは、腎臓が1分間にどれくらいの血液をろ過できるかを示す指標で、健康な人では90以上ですが、数値が低いほど腎機能が低下していることを意味し、60未満の状態が3ヶ月以上続くと、慢性腎臓病(CKD)と診断されます。
eGFR(推算糸球体ろ過量)による腎機能の評価
| ステージ | eGFR (mL/分/1.73m²) | 腎機能の状態 |
|---|---|---|
| G1 | 90以上 | 正常または高値 |
| G2 | 60~89 | 正常または軽度低下 |
| G3a | 45~59 | 軽度~中等度低下 |
血圧測定の重要性
血圧の管理は、腎機能の悪化を防ぐ上で治療の柱となるため、定期的な血圧測定が欠かせません。病院での測定だけでなく、自宅でリラックスした状態で測定する家庭血圧も非常に重要な情報です。
診察室では緊張して血圧が高めに出てしまう白衣高血圧や、逆に家庭では高いのに診察室では正常になる仮面高血圧などを見つけるためにも、家庭での血圧測定を習慣にすることが推奨されます。
測定した血圧は記録し、診察時に医師に見せることで、より適切な治療方針の決定に役立ちます。
腎臓を守るための血圧管理 日常生活のポイント
腎機能の低下がみられる場合、血圧を良好な状態に保つことは、腎臓への負担を減らし、病気の進行を遅らせるために非常に重要になります。薬による治療も大切ですが、基本となるのは日々の生活習慣の見直しです。
減塩が基本の食事療法
血圧管理において、最も重要とも言えるのが減塩です。塩分の主成分であるナトリウムを摂りすぎると、体は水分を溜め込んで血圧が上がります。
腎機能が低下している場合は、ナトリウムの排泄能力が落ちているため、減塩の効果はより大きくなります。日本人の食事摂取基準では、高血圧の人の食塩摂取量の目標を1日6g未満としています。
普段の食事では、無意識のうちに多くの塩分を摂取していることが多く、まずは、加工食品や外食を控える、麺類の汁は飲まない、醤油やソースはかけるのではなく付けて食べるなどの工夫から始めてみましょう。
塩分を減らす調理の工夫
| 工夫の種類 | 具体例 | ポイント |
|---|---|---|
| 香辛料や酸味を利用 | コショウ、唐辛子、カレー粉、酢、レモン汁など | 味のアクセントになり、薄味でも満足感を得やすい |
| 香味野菜を活用 | ショウガ、ニンニク、ネギ、シソ、ミョウガなど | 香りが食欲をそそり、風味豊かに仕上げる |
| 素材の味を活かす | 新鮮な食材を選び、「焼く」「蒸す」などの調理法で旨味を引き出す | だしをしっかり効かせることも有効 |
カリウムの摂取は医師と相談を
カリウムは、体内の余分なナトリウムを尿中に排泄するのを助け、血圧を下げる効果が期待できるミネラルです。野菜や果物、いも類などに多く含まれています。
しかし、腎機能が著しく低下している場合、カリウムを十分に排泄できなくなり、血液中のカリウム濃度が異常に高くなる高カリウム血症をきたす危険性があります。高カリウム血症は、不整脈や心停止を引き起こすこともある危険な状態です。
腎機能が低下している方がカリウムを多く含む食品を積極的に摂る場合は、必ず事前に主治医に相談し、指導に従うことが大切で、自己判断でのサプリメントの利用なども避けてください。
適度な運動を習慣にする
ウォーキングや軽いジョギング、水泳などの有酸素運動は、血管を広げて血圧を下げる効果や、肥満の解消、ストレス発散にもつながります。少し息が弾むくらいの強度で、1回30分以上、週に3日以上行うのが目標です。
ただし、急に激しい運動を始めると心臓や血管に負担がかかることがありるので、まずは散歩の時間を少し延ばすなど、無理のない範囲から始め、徐々に強度や時間を増やしていくことが長続きの秘訣です。
運動を始める前には、主治医にどの程度の運動が適切か相談するとよいでしょう。
- 無理のない範囲から始める
- 有酸素運動が中心
- 継続することが重要
その他の生活習慣の見直し
血圧管理には、食事や運動以外にも見直すべき生活習慣があります。肥満は高血圧の大きな要因で、適正体重を維持するよう心がけましょう。アルコールの過剰摂取も血圧を上昇させるので、飲酒は適量を守ることが大切です。
また、喫煙は血管を収縮させて動脈硬化を著しく進行させ、腎臓に大きなダメージを与え、腎臓を守るためには禁煙が強く推奨されます。十分な睡眠をとり、ストレスを上手に管理することも、血圧を安定させる上で助けになります。
薬による血圧コントロールの考え方
生活習慣の改善を続けても血圧が目標値まで下がらない場合や、腎機能の低下がある程度進行している場合には、血圧を下げる薬(降圧薬)による治療が必要です。降圧薬は、腎臓を保護する上でも非常に重要な役割を果たします。
降圧目標は厳格に設定
腎機能が低下している場合、腎臓への負担をできるだけ軽くし、病気の進行を抑えるために、血圧の目標値は一般の高血圧の方よりも厳しく設定されます。
日本高血圧学会のガイドラインでは、尿タンパクが出ている慢性腎臓病(CKD)患者さんの降圧目標は、診察室血圧で130/80mmHg未満とされています。
目標を達成するためには、一種類の薬だけでは不十分なことも多く、作用の異なる複数の薬を組み合わせて治療することが一般的です。
腎臓を保護する作用のある降圧薬
降圧薬には様々な種類がありますが、中でも腎機能が低下している方に第一選択薬として推奨されるのが、レニン-アンジオテンシン系阻害薬(RAS阻害薬)と呼ばれる薬です。
この系統の薬には、アンジオテンシン変換酵素(ACE)阻害薬とアンジオテンシンII受容体拮抗薬(ARB)の二種類があります。
血圧を上げるアンジオテンシンIIの作用を抑えることで血圧を下げるだけでなく、糸球体内の圧力を下げて腎臓への負担を軽減し、尿タンパクを減らす効果も持っています。
主な降圧薬の種類と特徴
| 薬の種類 | 主な作用 | 特徴 |
|---|---|---|
| RAS阻害薬 (ACE阻害薬, ARB) | アンジオテンシンIIの作用を抑える | 血圧を下げる作用に加え、腎保護作用が期待できる |
| カルシウム拮抗薬 | 血管を広げて血圧を下げる | 降圧効果が安定しており、広く使用される |
| 利尿薬 | 余分な塩分と水分を尿として排泄させる | むくみがある場合や、他の薬と併用して使われることが多い |
副作用と注意点
どのような薬にも副作用の可能性があり、ACE阻害薬では空咳が出ることがあります。
また、RAS阻害薬や利尿薬は、治療開始初期に腎機能が一時的に悪化したり、血清カリウム値が上昇したりすることがあるため、定期的な血液検査で状態を確認しながら慎重に治療を進めます。
薬を飲み始めて何か気になる症状が現れた場合は、自己判断で中止せず、速やかに主治医や薬剤師に相談することが重要です。
また、他の病気で薬を飲んでいる場合や、市販の痛み止めなどを使う際には、薬の飲み合わせが問題になることもあるため、必ず医師に伝えてください。
- 自己判断で薬をやめない
- 気になる症状はすぐに相談する
- 他の薬の使用は医師に伝える
家庭血圧測定の重要性と正しい測り方
腎臓を守るための厳格な血圧管理において、家庭での血圧測定は今や欠かすことのできないものです。診察室での測定だけでは捉えきれない、普段の血圧の状態を把握することで、よりきめ細やかな治療が可能になります。
なぜ家庭血圧が重視されるのか
診察室での血圧は、緊張やストレスなど様々な要因で変動しやすく、必ずしも普段の血圧を反映しているとは限りません。
リラックスした環境である家庭で測定した血圧の方が、脳卒中や心臓病などのリスクをより正確に予測できることが多くの研究でわかっています。
特に、早朝の高血圧は心血管イベントのリスクと強く関連しており、これは家庭血圧でなければ発見が困難です。毎日の血圧を記録し、変動パターンを医師が把握することで、薬の量や種類、飲む時間を調整できるようになります。
正しい血圧測定の手順
正確な血圧を測定するためには、正しい手順で測ることが大切です。測定する機器は、できれば腕にカフを巻くタイプ(上腕式)の血圧計を選びましょう。手首で測るタイプは、手首の位置によって数値が変動しやすいため注意が必要です。
測定前には、少なくとも5分間は椅子に座って安静にし、落ち着いた状態になってから測ります。測定中の会話や体の動きは血圧を上げてしまうので避けてください。
- 上腕式の血圧計を使用する
- 測定前は5分以上安静にする
- 測定中は会話や動作を控える
測定のタイミングと記録の付け方
血圧を測定するタイミングは、朝と夜の2回が基本です。朝は起床後1時間以内で、排尿を済ませ、食事や薬を飲む前に測定します。夜は就寝前に測定するのがよいでしょう。
いずれも座った姿勢で1〜2分間隔をあけて2回測定し、平均値を記録します。血圧手帳などに、測定した日時と朝・夜の血圧値、脈拍数を記録してください。
血圧測定の推奨タイミング
| タイミング | 時間帯 | 測定前の行動 |
|---|---|---|
| 朝 | 起床後1時間以内 | 排尿後、朝食・服薬前 |
| 夜 | 就寝前 | 入浴や飲酒直後は避ける |
腎機能低下と血圧に関するよくある質問
ここでは、腎機能の低下と血圧に関して、患者さんからよく寄せられる質問と回答をまとめました。
- 一度下がった腎機能は元に戻りますか
-
一度悪くなってしまった腎機能(慢性腎臓病)を完全に元の状態に戻すことは、現在の医療では困難です。腎臓の組織は再生能力が低いため、障害を受けた部分は線維化という硬い組織に置き換わってしまいます。
しかし、腎機能低下の原因となっている病気をしっかり治療し、血圧や血糖を良好にコントロールし、生活習慣を改善することで、腎機能がそれ以上悪化するスピードを緩やかにし、透析導入を遅らせることは十分に可能です。
- 降圧薬はずっと飲み続けないといけませんか
-
多くの場合、高血圧は体質的な要因が大きく、薬を中止すると再び血圧が上昇してしまうため、生涯にわたって飲み続ける必要があります。
特に腎臓を保護するという目的がある場合、自己判断で薬を中断することは非常に危険です。中断によって血圧が急上昇し、腎機能が急激に悪化してしまうこともあります。
ただし、減塩や減量、運動などの生活習慣の改善を徹底することで、薬の量を減らせる可能性はあります。
- 食事療法では何から始めたらよいですか
-
腎機能を守るための食事療法で、まず最初に取り組むべきことは減塩です。いきなり1日6g未満を目指すのが難しい場合は、まず現在の食生活を見直し、どこに塩分が多く含まれているかを把握することから始めましょう。
漬物や味噌汁を1日1回にする、加工食品を避けて手作りする、麺類の汁は残すといった小さな工夫でも、積み重ねれば大きな減塩につながります。
減塩に慣れてきたら、タンパク質の制限やカリウム、リンの管理など、病状に合わせた次の段階に進んでいきます。
以上
参考文献
Ninomiya T, Kiyohara Y, Tokuda Y, Doi Y, Arima H, Harada A, Ohashi Y, Ueshima H. Impact of kidney disease and blood pressure on the development of cardiovascular disease: an overview from the Japan Arteriosclerosis Longitudinal Study. Circulation. 2008 Dec 16;118(25):2694-701.
Lee S, Lee S, Harada K, Bae S, Makizako H, Doi T, Tsutsumimoto K, Hotta R, Nakakubo S, Park H, Suzuki T. Relationship between chronic kidney disease with diabetes or hypertension and frailty in community‐dwelling Japanese older adults. Geriatrics & gerontology international. 2017 Oct;17(10):1527-33.
Kokubo Y, Nakamura S, Okamura T, Yoshimasa Y, Makino H, Watanabe M, Higashiyama A, Kamide K, Kawanishi K, Okayama A, Kawano Y. Relationship between blood pressure category and incidence of stroke and myocardial infarction in an urban Japanese population with and without chronic kidney disease: the Suita Study. Stroke. 2009 Aug 1;40(8):2674-9.
Higashikuni Y, Ishizaka N, Ishizaka Y, Toda EI, Nagai R, Yamakado M. Relationship between blood pressure and chronic kidney disease in the Japanese population: the lower the better even in individuals without hypertension?. Hypertension Research. 2008 Feb;31(2):213-9.
Yano Y, Fujimoto S, Sato Y, Konta T, Iseki K, Moriyama T, Yamagata K, Tsuruya K, Yoshida H, Asahi K, Kurahashi I. Association between prehypertension and chronic kidney disease in the Japanese general population. Kidney international. 2012 Feb 1;81(3):293-9.
Kadowaki T, Maegawa H, Watada H, Yabe D, Node K, Murohara T, Wada J. Interconnection between cardiovascular, renal and metabolic disorders: A narrative review with a focus on Japan. Diabetes, Obesity and Metabolism. 2022 Dec;24(12):2283-96.
Imai E, Matsuo S, Makino H, Watanabe T, Akizawa T, Nitta K, Iimuro S, Ohashi Y, Hishida A. Chronic Kidney Disease Japan Cohort study: baseline characteristics and factors associated with causative diseases and renal function. Clinical and experimental nephrology. 2010 Dec;14(6):558-70.
Sakaguchi Y, Shoji T, Kawabata H, Niihata K, Suzuki A, Kaneko T, Okada N, Isaka Y, Rakugi H, Tsubakihara Y. High prevalence of obstructive sleep apnea and its association with renal function among nondialysis chronic kidney disease patients in Japan: a cross-sectional study. Clinical Journal of the American Society of Nephrology. 2011 May 1;6(5):995-1000.
Kanno A, Kikuya M, Ohkubo T, Hashimoto T, Satoh M, Hirose T, Obara T, Metoki H, Inoue R, Asayama K, Shishido Y. Pre-hypertension as a significant predictor of chronic kidney disease in a general population: the Ohasama Study. Nephrology Dialysis Transplantation. 2012 Aug 1;27(8):3218-23.
Yamamoto T, Nakayama M, Miyazaki M, Matsushima M, Sato T, Taguma Y, Sato H, Ito S. Relationship between low blood pressure and renal/cardiovascular outcomes in Japanese patients with chronic kidney disease under nephrologist care: the Gonryo study. Clinical and experimental nephrology. 2015 Oct;19(5):878-86.