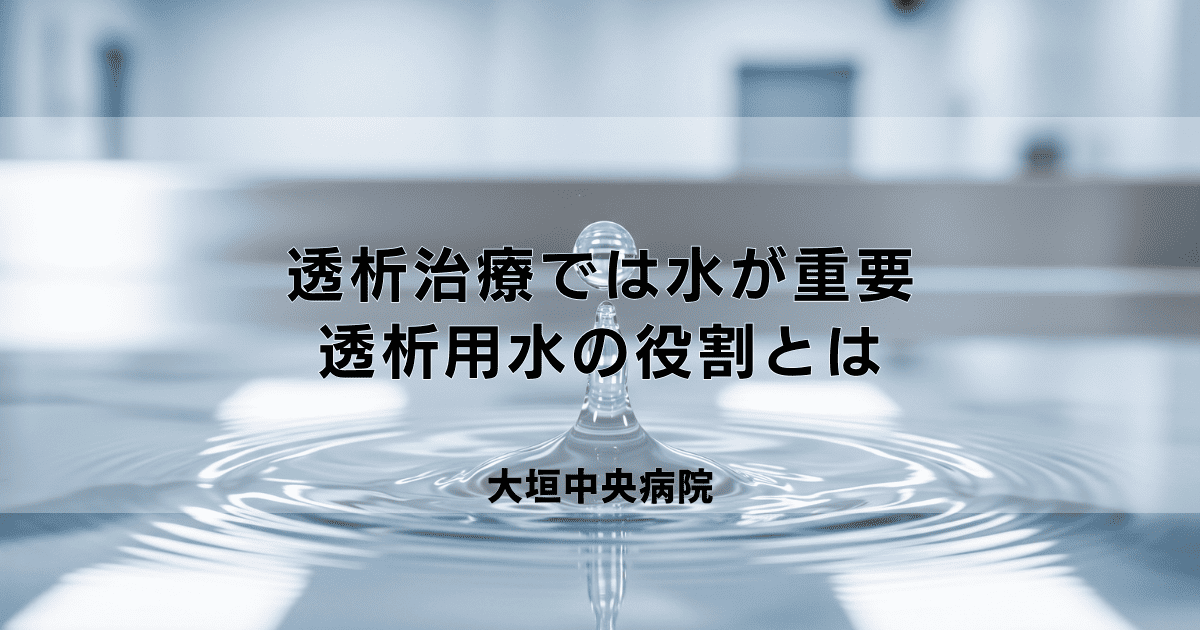血液透析が、腎臓の代わりに血液をきれいにする治療であることは広く知られていますが、治療に大量の、しかも極めて清浄な「水」が使われていることは、あまり知られていないかもしれません。
実は、透析治療の安全性と効果は、「水」の質に大きく左右されます。
この記事では、なぜ透析治療に大量の水が必要なのか、水道水をそのまま使えないのはなぜか、治療の根幹を支える「超純水(透析用水)」とは一体どのような水なのか、役割と重要性について詳しく解説していきます。
なぜ透析治療に大量の水が必要なのか
血液透析は、体内の血液を一度外に取り出し、きれいにしてから体内に戻す治療法です。この「血液をきれいにする」という働きの中心を担うのが、「水」を主成分とする透析液なのです。
透析液の主成分としての水
血液透析では、ダイアライザ(人工腎臓)と呼ばれる特殊なフィルターを介して、血液と透析液を接触させ、物質の交換を行います。
透析液の約99%は水でできており、残りのごくわずかな部分に、体に必要なブドウ糖やナトリウム、カリウム、カルシウムといった電解質などが、正常な血液に近い濃度になるよう精密に調整されています。
透析液は、血液中に溜まった尿素などの老廃物や余分な水分を、濃度の差を利用して効率的に引き抜くための媒体として機能するため、透析液の品質は、水の品質そのものであると言っても過言ではありません。
質の高い水を使わなければ、安全で効果的な透析治療は成り立たないのです。
一回の透析治療で使用する水の量
一般的な血液透析は、週に3回、1回あたり約4時間かけて行い、治療中に、一人の患者さんのために使われる透析液の量は、120リットルにも及び、これは、家庭用のお風呂一杯分に迫る量です。
なぜこれほど大量の透析液が必要かというと、常に新鮮な透析液をダイアライザに流し続けることで、血液と透析液の間に大きな濃度差を維持し、老廃物を効率よく除去するためです。
年間で計算すると、一人の患者さんあたり約18,720リットル(120L × 3回 × 52週)もの膨大な量の水が、透析液の原料として消費されることになります。
透析治療における水の消費量
| 期間 | 一人あたりの水の消費量(目安) | 身近なものとの比較 |
|---|---|---|
| 1回の治療(約4時間) | 約120リットル | 一般的な浴槽の約6割 |
| 1週間(3回治療) | 約360リットル | ドラム缶(200L)約1.8本分 |
| 1年間(52週) | 約18,720リットル | 2Lペットボトル約9,360本分 |
血液と水の間接的な接触
透析治療中、患者さんの血液と透析液は、ダイアライザの中にある半透膜という非常に薄い膜を隔てて接しています。膜は、ストロー状の中空糸が何万本も束になった構造をしており、その内側を血液が、外側を透析液が流れます。
この時、血液と透析液が直接混ざり合うことはありませんが、半透膜には目に見えない微細な穴が無数に開いており、老廃物や水分が移動します。
この膜の総面積はサッカーコートの数分の一にもなり、膨大な面積で血液と透析液が近接していることになります。
もし透析液に不純物が含まれていた場合、半透膜を通過して血液中に入り込んでしまうリスクが常にあり、透析液の原料となる水は、極めて高いレベルの清浄度が求められるのです。
水道水が透析にそのまま使えない理由
日本の水道水は世界でもトップクラスの安全性を誇り、そのまま飲むことができますが、安全な水道水も、透析治療にそのまま使用することはできません。
水道水に含まれる様々な物質
水道水には、消毒のために使われる塩素(カルキ)をはじめ、カルシウム、マグネシウムといったミネラル分、ごく微量のアルミニウムや銅、亜鉛などの金属類、目には見えない細菌やその死骸(内毒素、エンドトキシン)などが含まれています。
健康な人の場合、このような物質は口から摂取しても、胃酸や腸管のバリア機能、そして腎臓の働きによって適切に処理・排出されるため、問題になることはありません。
しかし、透析治療では、これらの物質が体の防御機能を介さずに、ダイアライザの半透膜を介して直接血液中に入る可能性があるため、状況が全く異なります。
水道水と透析用水の比較
| 項目 | 水道水 | 透析用水 |
|---|---|---|
| 摂取経路 | 経口摂取(消化管を経由) | 血液へ直接(半透膜を介して) |
| 体の防御機能 | 消化管バリア、肝臓の解毒、腎機能が働く | これらの防御機能が働かない |
| 許容される不純物 | 水道法で定められた飲用基準の範囲内 | 極限まで除去する必要がある |
血液に直接入ることで起こるリスク
もし、水道水に含まれる物質が血液中に侵入すると、様々な健康被害を起こす可能性があり、消毒用の塩素は赤血球を酸化させて破壊し、貧血を悪化させる原因となります。
アルミニウムは体内に蓄積すると、骨がもろくなる骨軟化症や、重篤な脳障害(透析脳症)を起こすことが過去に問題となりました。また、最も注意が必要なのが、細菌由来の毒素であるエンドトキシンです。
エンドトキシンが血液中に入ると、体は異物が侵入したと判断し、免疫系が過剰に反応し、発熱や血圧低下といった急性の症状だけでなく、長期的には全身で慢性の炎症を起こし、動脈硬化や栄養障害などを促進してしまいます。
健康な腎臓とダイアライザの違い
健康な腎臓は、単なるフィルターではありません。血液中から不要なものだけを選んで尿として排泄し、必要なものは体内に保持するという、非常に高度で能動的な選別機能を持っています。
さらに、血圧を調整するホルモンや、赤血球を作るホルモン(エリスロポエチン)、骨を丈夫にする活性型ビタミンDなどを産生する役割も担っています。
ダイアライザはあくまで人工物であり、機能は分子の大きさによって物質をふるい分けるという物理的な原理に基づいていて、腎臓のように有害物質を能動的に選別してブロックしたり、ホルモンを産生したりする能力はありません。
この機能的な違いが、透析治療で使う水に、水道水とは比較にならないほど厳しい清浄度を求める大きな理由です。
超純水(透析用水)とはどのような水か
水道水をそのまま使えないとなると、一体どのような水が透析治療に使われるのでしょうか。その答えが「超純水」とも呼ばれる、極めて純度の高い「透析用水」です。
この水は、水道水を原料に、専用の複雑な水処理システムを用いて、不純物を極限まで取り除いて作られます。
不純物を極限まで除去した水
超純水とは、文字通り、水(H₂O)以外の物質をほとんど含まない、純粋な水に近い状態の水です。透析治療で用いる透析用水は、超純水の一種であり、純度は半導体の製造工場などで使われる工業用の超純水に匹敵します。
水道水に含まれるイオン、金属、微生物、エンドトキシンといった、透析患者さんにとって有害となる可能性のあるすべての物質を、複数の特殊なフィルターや吸着剤、紫外線ランプなどを組み合わせて徹底的に除去します。
清浄度は、一般的な浄水器で作られる水とは比較にならないレベルであり、まさに「磨き上げられた水」です。
除去対象となる主な不純物
- 遊離残留塩素
- カルシウム、マグネシウム(硬度成分)
- 重金属類(アルミニウム、銅、亜鉛など)
- 細菌、ウイルス、真菌(カビ)
- エンドトキシン(細菌由来の内毒素)
厳格な水質基準の存在
安全な透析治療を確保するため、透析用水の品質は、日本透析医学会によって非常に厳格な基準が定められています。
基準には、含まれていても良い化学物質の濃度や、細菌、エンドトキシンの量などが細かく規定されており、世界的に見ても極めて厳しい水準です。透析施設は、この厳しい基準を常に満たす水質を維持する義務があります。
エンドトキシンの基準値は、注射用水の基準に迫るほど低く設定されており、いかに高いレベルの清浄度が求められているかがわかります。
透析用水の水質基準(一部抜粋)
| 項目 | 基準値 | 備考(予防される合併症など) |
|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | 0.1 mg/L 未満 | 溶血性貧血の防止 |
| アルミニウム | 0.01 mg/L 以下 | 透析脳症や骨症の予防 |
| エンドトキシン | 0.050 EU/mL 未満 | 微小炎症や動脈硬化の予防 |
オンラインHDF治療に求められる水質
近年、透析治療の合併症予防や症状改善に効果的とされる、オンラインHDF(血液透析濾過)という治療法が普及しています。
この治療法は、通常の血液透析に加えて、きれいな透析液(置換液)を血液中に直接補充し、その分だけ多くの水分を除去することで、より多くの老廃物を取り除くことができます。
血液中に直接液体を補充するという性質上、使用する透析液には極めて高い安全性が必要です。
オンラインHDFを行うためには、通常の透析用水の基準よりもさらに厳しい「超高純度透析液」の基準を満たす水質が必須となります。
透析用水を作るための水処理システム
水道水から超純水レベルの透析用水を作り出すためには、家庭用の浄水器とは全く異なる、大規模で複雑な水処理システムが必要で、複数の装置を組み合わせることで、水道水を段階的に精製し、水の純度を高めていきます。
前処理:大きなゴミや塩素の除去
水処理システムの最初の段階は、前処理です。まず、水道水に含まれる砂やサビなどの比較的大きな粒子をフィルター(プレフィルター)で取り除きます。
次に、軟水化装置を使って、水中のカルシウムやマグネシウムといった硬度成分をナトリウムイオンに置き換えて除去します。
硬度成分は、後段のRO膜の表面に付着して膜の性能を低下させる(スケール障害)原因となるため、ここで取り除きます。そして、活性炭フィルターを用いて、水道水に含まれる消毒用の塩素や、一部の有機物を吸着・除去します。
塩素はRO膜を傷つけてしまうため、この段階で確実に除去することが極めて大切です。
RO装置:水の純度を高める心臓部
前処理を終えた水は、水処理システムの心臓部であるRO(Reverse Osmosis:逆浸透)装置に送られます。
RO装置は、RO膜(逆浸透膜)という、水分子は通すがイオンや微粒子はほとんど通さない特殊な膜を用いて、水に高い圧力をかけて濾過します。
この仕組みにより、水に溶け込んでいるイオンや金属類、さらには細菌やウイルス、エンドトキシンといった不純物の99%以上が除去され、水の純度が飛躍的に高まります。RO装置は、透析用水の品質を決定づける最も重要な装置です。
主な水処理装置とその役割
| 装置名 | 主な役割 | 除去する物質 |
|---|---|---|
| 軟水化装置・活性炭フィルター | RO膜の保護 | 硬度成分、遊離残留塩素 |
| RO(逆浸透)装置 | 水の精製(純度向上) | イオン、重金属、細菌、エンドトキシン |
| エンドトキシン捕捉フィルター | 安全性の確保(最終防御) | エンドトキシン |
供給装置と配管:清浄度を保つ工夫
RO装置できれいになった水は、貯水タンクに一旦貯められ、その後、透析室内の各ベッドサイドにある透析装置へと配管を通じて供給され、この過程で細菌が繁殖しないように、システム全体に様々な工夫が凝らされています。
配管内に水がよどむ部分(デッドスペース)をなくし、常に水が循環するループ配管方式を採用し、また、配管の材質には、細菌が繁殖しにくい清浄な素材を使用します。
さらに、透析装置に接続される直前には、エンドトキシン捕捉フィルター(ETRF)という最終関門のフィルターを設置し、万が一にもエンドトキシンが透析液に混入しないように二重三重の安全対策を講じています。
徹底した水質管理が安全な透析を支える
高性能な水処理システムを導入するだけでは、安全な透析用水を安定して供給することはできません。
システムが正常に機能しているか、作られた水の品質が基準を満たしているかを、日々厳しくチェックする水質管理が極めて重要です。
専門スタッフによる日常点検
透析施設では、臨床工学技士などの専門スタッフが、水処理システムの運転状況を毎日、治療の開始前、治療中、終了後にわたって厳しく監視しています。
各装置の圧力や流量、導電率計などの数値を点検し、わずかな異常も見逃さないようにチェックし、また、透析治療を開始する前には、配管の末端で採取した水の塩素濃度を測定し、塩素が確実に除去されていることを確認します。
定期的な水質検査の義務
日常点検に加えて、透析施設は法律や学会のガイドラインに基づき、定期的に詳細な水質検査を行うことが義務付けられています。
月に一度は、水処理システムの各ポイントで水を採取し、細菌培養検査とエンドトキシン測定を行い、微生物汚染がないかを確認します。さらに年に一度は、専門の検査機関に依頼して、アルミニウムや銅などの化学物質の濃度を測定します。
検査結果はすべて記録・保管し、常に水質が安全なレベルに保たれていることを客観的なデータで証明し、いつでも閲覧できるように管理することが必要です。
水質検査の頻度と項目
| 頻度 | 主な検査項目 | 目的 |
|---|---|---|
| 毎日(治療開始前) | 遊離残留塩素 | RO膜の保護と患者の安全確保 |
| 毎月 | 生菌数、エンドトキシン濃度 | 微生物汚染の監視と管理 |
| 毎年 | 化学物質(重金属など) | 長期的な有害物質蓄積の予防 |
配管や装置のメンテナンス
長期間にわたって清浄な水質を維持するためには、水処理システム全体の定期的なメンテナンスが大事です。フィルターや活性炭、イオン交換樹脂などの消耗品は、メーカーが推奨する期間や水質検査の結果に基づいて計画的に交換します。
また、配管内に細菌が定着してバイオフィルムというぬめりのある膜を形成するのを防ぐため、定期的な洗浄・消毒作業も行います。
バイオフィルムは一度形成されると除去が難しく、エンドトキシンの発生源となるため、形成をいかに抑制するかが、水質管理における重要な課題の一つです。
清浄な透析液がもたらす身体への影響
徹底した水質管理によって作られる清浄な透析液は、安全な治療の基盤であると同時に、患者さんの身体に様々な良い影響をもたらします。
不純物の少ないきれいな水を使うことは、単にリスクを回避するだけでなく、より質の高い透析治療を実現し、患者さんのQOL(生活の質)向上にも貢献します。
微小炎症の抑制と合併症予防
透析液中にごく微量のエンドトキシンなどが含まれていると、患者さんの体内では免疫細胞が刺激され、慢性的なくすぶり続けるような炎症(微小炎症)が引き起こされます。
微小炎症は、自覚症状がないまま進行し、長期的には動脈硬化を促進させ、心筋梗塞や脳卒中といった心血管系の合併症のリスクを高めることが分かっていて、また、栄養状態の悪化や、貧血の改善を妨げる一因です。
超純水から作られる清浄な透析液を使用することで、この微小炎症を抑制し、長期的な合併症を予防する効果が期待できます。
清浄な透析液によるメリット
- 貧血の改善(ESA製剤の効果向上)
- 栄養状態の改善(食欲増進)
- かゆみ、不眠、イライラ感などの皮膚・精神症状の軽減
- 透析中の血圧安定化
- 長期的な心血管合併症(心筋梗塞、脳卒中)の予防
貧血治療薬(ESA)の効果改善
多くの透析患者さんは、腎臓でのエリスロポエチン産生が低下するため、貧血の状態です。
この治療のために、赤血球の産生を促す注射薬(ESA製剤)を使用しますが、体内で微小炎症が起きていると、炎症によって鉄の利用が妨げられ、薬の効きが悪くなる(ESA抵抗性)ことが知られています。
清浄な透析液を用いて微小炎症を抑制することで、鉄の利用が改善し、ESA製剤が本来の効果を発揮しやすくなり、注射薬の使用量を減らせる可能性や、より良好な貧血コントロールが期待できます。
微小炎症と身体への影響
| 微小炎症の原因 | 引き起こされる主な状態 | 清浄な透析液による改善 |
|---|---|---|
| エンドトキシン等の侵入 | 動脈硬化の促進 | 心血管イベントのリスク低減 |
| サイトカインの産生 | ESA抵抗性(貧血の悪化) | 貧血治療薬の効果改善、鉄利用の改善 |
| アルブミンの低下 | 栄養障害(食欲不振) | 食欲改善、栄養状態の向上 |
透析センター(人工透析) | 大垣中央病院(医療法人社団豊正会 )
透析用水に関するよくある質問
最後に、透析治療で使われる「水」に関して、患者さんやご家族からよく寄せられる質問と回答をまとめました。
- 自宅の浄水器の水ではだめなのですか
-
ご家庭で一般的に使用される浄水器は、主に水道水中の残留塩素やサビ、濁りなどを取り除き、水を美味しくすることを目的としています。
細菌を除去できる高性能なタイプもありますが、透析治療で最も問題となるエンドトキシンや、水に溶け込んでいるイオン、アルミニウムなどの金属類まで、透析治療で求められるレベルまで完全に取り除くことはできません。
透析用水の清浄度は、家庭用浄水器で達成できるレベルとは全く異なるため、残念ながら使用することはできないのです。
- 水質が悪かった場合、すぐに体調が悪くなりますか
-
水質に大きな問題があった場合、例えば高濃度のエンドトキシンが混入したようなケースでは、透析中に発熱、悪寒、血圧低下といった急性の症状(発熱反応)が出ることがあります。
一方で、基準値をわずかに超える程度の汚染が慢性的に続いた場合は、すぐに自覚症状として現れることは少ないかもしれません。
しかし、気づかないうちに体内で微小炎症が進行し、数年単位で動脈硬化や栄養障害といった深刻な合併症として現れてくる可能性があります。症状の有無にかかわらず、日々の厳格な水質管理が重要です。
- 在宅血液透析の場合、水はどうするのですか
-
在宅血液透析(HHD)を行う場合でも、施設での透析と同様に極めて清浄な水が必要なため、ご自宅に小規模な個人用の水処理システムを設置します。
この装置も、施設にある大規模なシステムと同様に、軟水化装置、活性炭フィルター、RO装置などを備えており、水道水から透析用水を作ります。
設置工事が必要で、患者さんやご家族には、装置の簡単な操作や日常点検を行うことになりますが、定期的なメンテナンスや水質検査は、専門スタッフが責任を持って行いますので、ご自宅でも安全な水質の透析治療が可能です。
以上
参考文献
Mineshima M, Kawanishi H, Ase T, Kawasaki T, Tomo T, Nakamoto H, Subcommittee on the Function and Efficacy of Blood Purification Therapy, the Scientific Academic Committee of the Japanese Society for Dialysis Therapy. 2016 update Japanese Society for Dialysis Therapy Standard of fluids for hemodialysis and related therapies. Renal Replacement Therapy. 2018 Mar 21;4(1):15.
TakeshiKurosawa TA. Preparation of ultrapure dialysate in Japan–clinical usefulness and short-term future. Blood Purif. 2004;22(2):55-9.
Masakane I, Takemoto Y, Nakai S, Tsubakihara Y, Akiba T, Watanabe Y, Iseki K. Bacteriological water quality in the central dialysis fluid delivery system from the survey of the Japanese Society for Dialysis Therapy. Blood purification. 2009 Jun 26;27(1):11.
Penne EL, Visser L, Van Den Dorpel MA, Van Der Weerd NC, Mazairac AH, Van Jaarsveld BC, Koopman MG, Vos P, Feith GW, Hovinga TK, Van Hamersvelt HW. Microbiological quality and quality control of purified water and ultrapure dialysis fluids for online hemodiafiltration in routine clinical practice. Kidney international. 2009 Sep 2;76(6):665-72.
Kawasaki T, Uchino J, Shinoda T, Kawanishi H. Guidance of technical management of dialysis water and dialysis fluid for the Japan Association for Clinical Engineering Technologists. Blood purification. 2009 Jun 26;27(1):41.
Uchino J, Kawasaki T. Purification of dialysis water in the central dialysis fluid delivery system in Japan: a prospective observation study. Blood purification. 2009 Jun 26;27(1):64.
Hasegawa T, Nakai S, Masakane I, Watanabe Y, Iseki K, Tsubakihara Y, Akizawa T. Dialysis fluid endotoxin level and mortality in maintenance hemodialysis: a nationwide cohort study. American Journal of Kidney Diseases. 2015 Jun 1;65(6):899-904.
Yamashita AC, Sato T. Central online hemodiafiltration in Japan: management of water quality and practice. Blood purification. 2009 Jun 26;27(1):50.
Simazaki D, Futami K, Ichimaru K, Kumagai T, Konuma S, Saito T, Akiba M. Fate of Sulfate in the Course of Japanese Drinking Water Purification Plants− Implications for Dialysis Therapy−. Journal of Water and Environment Technology. 2020;18(1):54-61.
Tsuchiyaa S. Preparation and quality management of fluids for hemodialysis. Scientific Aspects of Dialysis Therapy: JSDT/ISBP Anniversary Edition. 2016 Dec 12;189:153-9.