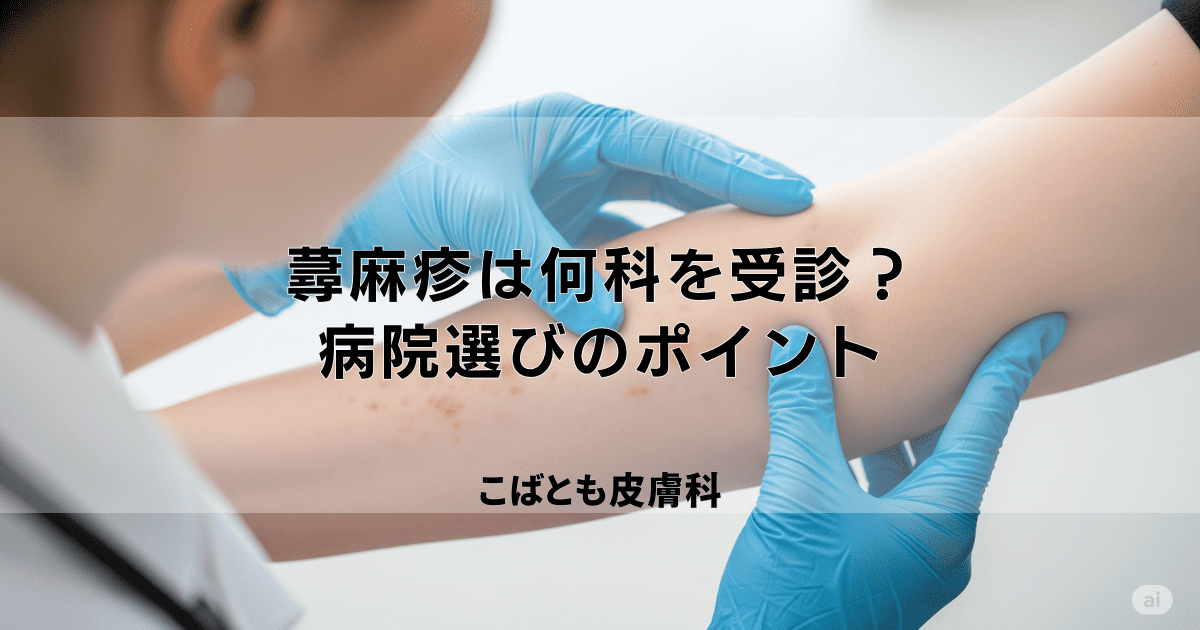ある日突然、皮膚に蚊に刺されたような赤いふくらみ(膨疹)が現れ、強いかゆみに襲われる蕁麻疹。
多くの人が一度は経験するといわれる身近な皮膚疾患ですが、いざ発症すると、そのかゆみの強さや見た目の変化に驚き、何科を受診すればよいのか迷ってしまうのではないでしょうか。
この記事では、蕁麻疹の基本的な知識から、症状に応じた適切な診療科の選び方、後悔しない病院選びのポイントまで、詳しく解説します。
この記事の執筆者

小林 智子(こばやし ともこ)
日本皮膚科学会認定皮膚科専門医・医学博士
こばとも皮膚科院長
2010年に日本医科大学卒業後、名古屋大学医学部皮膚科入局。同大学大学院博士課程修了後、アメリカノースウェスタン大学にて、ポストマスターフェローとして臨床研究に従事。帰国後、同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンターにて、糖化と肌について研究を行う。専門は一般皮膚科、アレルギー、抗加齢、美容皮膚科。雑誌を中心にメディアにも多数出演。著書に『皮膚科医が実践している 極上肌のつくり方』(彩図社)など。
こばとも皮膚科関連医療機関
蕁麻疹の正体と主な症状
蕁麻疹という言葉はよく耳にしますが、正体や具体的な症状について、正しく理解している人は意外と少ないかもしれません。まずは、蕁麻疹がどのような皮膚の病気なのか、その基本的な特徴から見ていきましょう。
突然現れるかゆみを伴う発疹
蕁麻疹の最も代表的な症状は、皮膚の一部が赤く盛り上がる膨疹(ぼうしん)と、強いかゆみで、膨疹は、突然、体のどこにでも現れる可能性があります。大きさは数ミリ程度の小さなものから、手のひら以上の大きさになるものまで様々です。
複数の膨疹が融合して、地図のような不規則な形に広がることも珍しくありません。かゆみの程度も人それぞれで、チクチクする程度の場合もあれば、我慢できないほどの激しいかゆみに見舞われることもあります。
また、かゆみだけでなく、ピリピリとした痛みや、焼けるような感覚を伴うこともあります。
数時間で消える不思議な性質
蕁麻疹の非常に特徴的な性質として、個々の発疹は跡形もなく消えてしまうという点が挙げられます。通常、一つの膨疹は数十分から数時間、長くても24時間以内にはきれいに消えます。
まるで何もなかったかのように元の皮膚の状態に戻るため、病院を受診する頃には症状が落ち着いている、という経験をした人も多いでしょう。
しかし、一つの発疹が消えても、また別の場所に新しい発疹が現れることを繰り返し、全体としては症状が数日間続くこともあります。
蕁麻疹の症状サイクル
| 段階 | 主な状態 | 典型的な時間経過 |
|---|---|---|
| 発生期 | 皮膚に赤みとかゆみが出現し始める。 | 数分 |
| 進展期 | 赤みが盛り上がり、膨疹がはっきりと形成される。かゆみが強くなる。 | 数分~1時間程度 |
| 消退期 | 膨疹の盛り上がりと赤みが徐々に引き、かゆみも和らぐ。跡は残らない。 | 数時間~24時間以内 |
蕁麻疹の見た目の特徴
蕁麻疹の膨疹は、その見た目からイラクサ(蕁麻)の葉に触れたときのような発疹に似ていることから、その名が付きました。
医学的には、皮膚の血管の周りにあるマスト細胞という細胞が活性化し、ヒスタミンなどの化学物質を放出することが原因です。
このヒスタミンが血管に作用して血液成分が漏れ出すことで皮膚が盛り上がり(膨疹)、神経を刺激することでかゆみを引き起こします。
膨疹の形は円形や楕円形が多いですが、線状になったり、リング状になったりと、多彩な形をとることがあります。色は淡い赤色から鮮やかな紅色まで様々です。
蕁麻疹と他の皮膚疾患との違い
かゆみを伴う赤い発疹は、蕁麻疹以外にも多くの皮膚疾患で見られますが、症状の現れ方や持続時間に違いがあります。
虫刺されは刺された箇所が中心で、発疹が数日間持続し、接触皮膚炎(かぶれ)は、原因物質が触れた範囲に限定して症状が現れ、水ぶくれなどを伴うこともあります。
また、アトピー性皮膚炎は、乾燥した皮膚にかゆみの強い湿疹が繰り返し現れる慢性的な疾患です。蕁麻疹は、個々の発疹が24時間以内に消えるという点が、これらの疾患との大きな違いになります。
蕁麻疹の原因は一つではない
蕁麻疹がなぜ起こるのか、原因は非常に多岐にわたります。原因がはっきりと特定できる場合もあれば、残念ながら特定できないケースも少なくありません。
アレルギー性と非アレルギー性
蕁麻疹は、大きくアレルギー性と非アレルギー性の二つに分類されます。アレルギー性の蕁麻疹は、特定の物質(アレルゲン)に対して体の免疫システムが過剰に反応することで起こり、食べ物、薬、ダニ、花粉などがアレルゲンとなり得ます。
非アレルギー性の蕁麻疹は、アレルギー反応とは関係なく、物理的な刺激や体調の変化などが引き金となって発症します。実際には、原因が特定できない特発性の蕁麻疹が最も多いです。
アレルギー性蕁麻疹の主な原因物質
| 分類 | 具体例 | 特徴 |
|---|---|---|
| 食物 | 卵、牛乳、小麦、甲殻類、果物、そば、ピーナッツなど | 摂取後、数分から2時間以内に症状が出ることが多い。 |
| 薬剤 | 抗菌薬、解熱鎮痛薬、造影剤など | 内服や注射後、比較的早期に症状が現れる。 |
| その他 | ラテックス(天然ゴム)、昆虫(ハチなど)、植物など | 接触や刺されることでアレルギー反応が起こる。 |
食物や薬剤が関わるケース
特定の食べ物を食べた後や、薬を飲んだ後に蕁麻疹が出た場合、それが原因である可能性があります。食物アレルギーによる蕁麻疹は、子どもに多く見られますが、大人になってから発症することもあります。
原因となりやすい食品は様々ですが、サバやマグロなどの青魚、豚肉、タケノコなどに含まれるヒスタミン様物質を多く摂取することで、アレルギーとは関係なく症状が出ること(仮性アレルゲン)もあります。
薬剤による蕁麻疹も頻度が高く、風邪薬や痛み止めなど、市販薬でも起こる可能性があるため注意が必要です。原因として疑われるものがあれば、医師に伝えることが大切です。
物理的な刺激が原因となることも
特定の物理的な刺激が加わることで発症する蕁麻疹もあり、物理性蕁麻疹と総称され、様々な種類があります。
皮膚を強くこすったり、圧迫したりすることで線状の膨疹が現れる機械性蕁麻疹、冷たい空気や水に触れることで起こる寒冷蕁麻疹、日光に当たることで発症する日光蕁麻疹などがあります。
また、運動や入浴などで体温が上昇した際に、小さな点状の膨疹が多発するコリン性蕁麻疹もこの一種です。このような蕁麻疹は、原因となる刺激がはっきりしているため、刺激を避けることが予防につながります。
様々な物理性蕁麻疹
| 種類 | 刺激となる要因 | 症状の特徴 |
|---|---|---|
| 機械性蕁麻疹 | 皮膚への摩擦、圧迫 | こすった部位がみみず腫れになる。 |
| 寒冷蕁麻疹 | 冷たい空気、水、物への接触 | 冷やされた部位が温まるときに膨疹が出やすい。 |
| 日光蕁麻疹 | 日光(特に紫外線) | 日光に当たった部位に膨疹とかゆみが出る。 |
| コリン性蕁麻疹 | 発汗、体温上昇(運動、入浴など) | 小さな点状の膨疹が多数現れる。 |
ストレスや疲労との関連性
精神的なストレスや身体的な疲労が、蕁麻疹の発症や悪化に関与することも知られています。はっきりとした原因が見当たらないのに蕁麻疹を繰り返す場合、背景に過労や睡眠不足、精神的な負担が隠れているかもしれません。
ストレスや疲労は自律神経のバランスを乱し、免疫機能を低下させることがあり、体の状態の変化が、マスト細胞を刺激しやすくし、蕁麻疹を起こす一因になると考えられています。
規則正しい生活を心がけ、十分な休息をとることが、蕁麻疹の管理においても重要です。
蕁麻疹が出たらまず考えるべき診療科
いざ蕁麻疹の症状が出たとき、多くの人が最初に悩むのがどの病院、どの診療科へ行けばよいかという問題です。
症状が出ているのは皮膚なので皮膚科と考えるのが自然ですが、内臓の病気が関係している可能性も耳にすると、内科も選択肢に入るかもしれません。ここでは、基本的な診療科の選び方について解説します。
基本は皮膚科への受診
結論から言うと、蕁麻疹の症状で医療機関を受診する場合、第一選択となるのは皮膚科です。
蕁麻疹は皮膚に症状が現れる病気であり、皮膚科医は皮膚疾患全般の専門家で、問診や視診を通じて、発疹が本当に蕁麻疹なのか、あるいは他の皮膚疾患ではないのかを的確に診断します。
特に、急に発症した蕁麻疹(急性蕁麻疹)の場合は、まず皮膚科を受診するのが最もスムーズな対応と言えるでしょう。
皮膚科受診のメリット
- 皮膚症状の正確な診断
- 他の皮膚疾患との鑑別
- 適切な外用薬・内服薬の処方
- 専門的な検査の実施
なぜ皮膚科が第一選択なのか
皮膚科医は、膨疹の形、大きさ、分布などを詳しく観察することで、蕁麻疹のタイプをある程度推測することができます。
コリン性蕁麻疹に特徴的な小さな発疹や、機械性蕁麻疹で見られる線状の膨疹など、視診から得られる情報は診断の大きな手がかりです。
また、蕁麻疹の治療の基本となる抗ヒスタミン薬の処方に関しても、患者さんの症状の強さやライフスタイルに合わせて、眠気の出にくい薬や効果の持続時間が長い薬などを選択するといった、専門的な知識に基づいた対応が期待できます。
皮膚科で受けられる検査と治療
皮膚科では、まず詳しい問診を行います。いつから症状があるか、どのような時に出やすいか、食事や薬、生活習慣についてなど、原因を探るための情報収集が重要です。
症状がアレルギー性を疑う場合は、原因アレルゲンを特定するために血液検査(特異的IgE抗体検査)や皮膚テスト(プリックテストなど)を行うことがあります。治療は、抗ヒスタミン薬や抗アレルギー薬の内服が中心です。
かゆみが非常に強い場合には、ステロイドの外用薬を短期間併用することもあり、症状が重い場合には、ステロイドの内服や注射が必要になるケースもあります。
皮膚科で行う主な検査
| 検査名 | 目的 | 方法 |
|---|---|---|
| 問診・視診 | 症状の把握、原因の推測 | 医師が症状や生活習慣について質問し、皮膚の状態を直接観察する。 |
| 血液検査 | アレルギーの原因検索、全身状態の確認 | 採血により、特定のアレルゲンに対する抗体(IgE)の量などを調べる。 |
| 皮膚テスト | アレルギーの原因検索 | アレルゲンと疑われる物質のエキスを皮膚に垂らし、専用の針で軽く傷をつけ反応を見る。 |
内科の受診を検討すべきケースとは
基本的には皮膚科が第一選択ですが、特定の状況下では内科の受診が望ましい、あるいは必要となる場合があります。蕁麻疹が単なる皮膚の問題だけでなく、体全体の不調のサインである可能性も考えられます。
どのような場合に内科を検討すべきか、具体的なケースを見ていきましょう。
蕁麻疹以外の症状がある場合
蕁麻疹と同時に、皮膚以外の症状が現れている場合は注意が必要です。発熱、関節の痛み、全身の倦怠感、腹痛、息苦しさなどの症状を伴う場合、背景に何らかの全身性の病気が隠れている可能性があります。
膠原病や血管炎、甲状腺疾患、内臓の感染症などが原因で蕁麻疹に似た症状が出ることがあります。このような病気は内科が専門とする領域であるため、皮膚症状だけでなく全身の症状がある場合は、内科での精査が重要です。
内科受診を検討すべき全身症状の例
| 症状 | 考えられる背景疾患の例 | 診療科 |
|---|---|---|
| 発熱、関節痛、倦怠感 | 膠原病、ウイルス感染症 | 内科、リウマチ科 |
| 腹痛、下痢、嘔吐 | 消化器系の疾患、食物アレルギー | 内科、消化器内科 |
| 息苦しさ、動悸、血圧低下 | アナフィラキシー、心疾患 | 救急科、アレルギー科、循環器内科 |
慢性的な蕁麻疹で悩んでいるとき
蕁麻疹の症状が6週間以上にわたって、毎日のように出たり消えたりを繰り返す場合、慢性蕁麻疹と診断されます。
慢性蕁麻疹の多くは原因不明の特発性ですが、中には内科的な疾患が関わっているケースもあり、ヘリコバクター・ピロリ菌の感染や、甲状腺の自己免疫疾患などが、慢性蕁麻疹の原因となることが報告されています。
皮膚科での治療でなかなか症状が改善しない場合や、原因をより深く探りたい場合には、内科的な観点からのアプローチが有効なことがあります。
内臓の病気が隠れている可能性
蕁麻疹は内臓の病気の一症状として現れることがあり、特に成人で発症した慢性の蕁麻疹では、全身の健康状態をチェックする意味でも、一度内科的な検査を受けておくと安心です。
血液検査や尿検査などで、肝臓や腎臓の機能、甲状腺ホルモンの値、炎症反応などを調べることで、隠れた病気の発見につながる可能性があります。
すべての慢性蕁麻疹に内科的疾患が関わっているわけではありませんが、可能性の一つとして念頭に置いておくことが大切です。
アナフィラキシーショックの危険性
蕁麻疹の中でも最も注意が必要なのが、アナフィラキシーの一症状として現れる場合です。アナフィラキシーは、アレルゲンが体内に入ることで、複数の臓器にアレルギー反応が起こり、生命に危険が及ぶほどの過剰な反応を示す状態です。
皮膚の症状(蕁麻疹、赤み、かゆみ)に加えて、呼吸困難、血圧低下、意識障害などの症状が急速に現れた場合は、アナフィラキシーショックの可能性があります。
この場合は、ためらわずに救急車を呼び、救急科やアレルギー科のある医療機関で緊急の処置を受けてください。
アナフィラキシーの危険なサイン
- 息が苦しい、声がかすれる
- めまい、意識がもうろうとする
- 激しい腹痛や嘔吐
- 顔色が悪い、唇が青白い
皮膚科と内科 連携によるアプローチ
蕁麻疹の診療において、皮膚科と内科は対立するものではなく、協力し合う関係にあります。それぞれの専門性を活かし、連携して治療にあたることで、より効果的なアプローチが可能になります。
診療科ごとの役割分担
大まかに言うと、皮膚科は皮膚に現れている症状そのものを抑える治療(対症療法)を得意とし、内科は蕁麻疹の背景にあるかもしれない全身的な原因を探る(原因療法)視点を持っています。
急性蕁麻疹の多くは皮膚科での対症療法で改善しますが、慢性化した場合や全身症状を伴う場合には、内科的な精査が加わることで、治療方針の決定に役立ちます。
それぞれの専門領域から患者さんの状態を多角的に評価することが、根本的な解決につながるのです。
皮膚科と内科の主な役割
| 診療科 | 主な役割 | 得意とする領域 |
|---|---|---|
| 皮膚科 | 皮膚症状の診断と治療、かゆみのコントロール | 急性・慢性蕁ма疹の対症療法、アレルギー検査 |
| 内科 | 全身的な原因の検索、背景疾患の治療 | 全身症状を伴う場合、慢性蕁ма疹の原因精査 |
皮膚科から内科へ紹介される場合
皮膚科での治療を受けていても、症状がなかなか改善しない場合や、問診・検査の結果から内科的な疾患が疑われる場合には、皮膚科医が内科への受診を勧めることがあります。
血液検査で肝機能や甲状腺機能に異常が見つかった場合や、患者さんから関節痛や発熱などの訴えがあった場合などです。
皮膚科医からの紹介状(診療情報提供書)を持参して内科を受診すると、これまでの治療経過や検査結果がスムーズに伝わり、連携した診療を受けやすくなります。
総合病院を受診するメリット
皮膚科と内科の両方が揃っている総合病院を受診するのも一つの方法です。総合病院であれば、院内で皮膚科と内科が連携しやすく、必要に応じてスムーズに他科の診察を受けることができます。
どちらの科を受診すべきか迷う場合や、複数の症状があって心配な場合には、まず総合受付で相談してみるのもよいでしょう。
病院選びで後悔しないためのポイント
適切な診療科がわかったら、次はどの医療機関を選ぶかという点が重要になります。蕁麻疹は、慢性化すると長く付き合っていくことになる可能性もあるため、信頼できて通いやすい病院を見つけることが大切です。
専門医のいるクリニックを選ぶ
皮膚科やアレルギー科を標榜していても、医師の専門性は様々です。可能であれば、日本皮膚科学会認定の皮膚科専門医や、日本アレルギー学会認定のアレルギー専門医が在籍している医療機関を選ぶと、より専門的な診断や治療が期待できます。
専門医の資格は、一定の経験と知識を持つ医師であることを示しており、病院のウェブサイトなどで確認できることが多いです。特に難治性の蕁麻疹や、アレルギーが強く疑われる場合には、専門医への相談してください。
事前に確認しておきたいこと
受診する前に、医療機関のウェブサイトなどで情報を収集しておくことをお勧めします。どのような検査が可能か(アレルギー検査など)、どのような治療方針をとっているか、医師の経歴や専門分野などが掲載されている場合があります。
また、口コミサイトなども参考にはなりますが、あくまで個人の感想であるため、情報は多角的に集めて総合的に判断することが大切です。
オンライン診療の活用も視野に
近年、オンライン診療を導入する医療機関が増えていて、症状が安定している慢性蕁麻疹の患者さんが、定期的な薬の処方を受ける場合などに活用できます。
病院へ行く時間がない、あるいは感染症のリスクを避けたいといった場合に便利な選択肢ですが、初診や症状が変化した際には対面での診察が必要な場合がほとんどです。
かかりつけのクリニックがオンライン診療に対応しているか、一度確認してみるのもよいでしょう。
蕁麻疹のセルフケアと受診のタイミング
蕁麻疹の症状を少しでも和らげ、悪化を防ぐためには、日常生活でのセルフケアも重要で、また、どのような症状が出たら急いで病院へ行くべきか、見極めも大切です。
症状を悪化させないための注意点
蕁麻疹が出ているときは、いくつかの点に注意することで、症状の悪化を防ぐことができ、まず、患部を掻きむしらないことが最も重要です。
掻くことで皮膚が刺激され、さらにヒスタミンが放出されてかゆみが強くなるという悪循環に陥ってしまいます。
また、血行が良くなるとかゆみが増すことがあるため、熱いお風呂への長時間の入浴や、アルコールの摂取、香辛料の多い食事などは控えた方がよいでしょう。
ストレスや疲労も悪化要因となるため、できるだけリラックスして過ごし、十分な睡眠をとることを心がけてください。
家庭でできる応急処置
強いかゆみがある場合、まずは患部を冷やすのが効果的です。冷たいシャワーを浴びたり、濡れたタオルや保冷剤をタオルで包んだものを当てたりすると、血管が収縮し、かゆみが和らぎます。
ただし、寒冷蕁麻疹の場合は冷やすことで症状が悪化する可能性があるため注意が必要です。服装は、皮膚への刺激が少ない、ゆったりとした木綿素材のものを選ぶとよいでしょう。
かゆみを和らげる応急処置
- 患部を冷やす(保冷剤、濡れタオル)
- 刺激の少ない衣類を着用する
- 体を温めすぎない
- 十分な休息をとる
この症状が出たらすぐに病院へ
ほとんどの蕁麻疹は生命に危険を及ぼすものではありませんが、中には緊急の対応が必要なケースもあります。
アナフィラキシーが疑われる症状、蕁麻疹に加えて息苦しさ、めまい、激しい腹痛、嘔吐などが見られる場合は、直ちに救急車を呼んでください。また、まぶたや唇が大きく腫れあがる血管性浮腫(クインケ浮腫)を伴う場合も注意が必要です。
特に喉の粘膜が腫れると窒息の危険があるため、呼吸に違和感がある場合は速やかに受診しましょう。通常の蕁麻疹であっても、症状が広範囲に及ぶ場合や、市販薬を使っても改善しない場合は、早めに専門医に相談することが大切です。
よくある質問
最後に、蕁麻疹に関して患者さんからよく寄せられる質問と回答をまとめました。
- 子どもの蕁麻疹は何科を受診すればよいですか?
-
子どもの蕁麻疹の場合も、基本的にはまず皮膚科か、かかりつけの小児科を受診するのが一般的で、小児科医は子どもの全身状態を把握することに長けており、皮膚科医は皮膚症状の専門的な診断が可能です。
食物アレルギーが強く疑われる場合や、アトピー性皮膚炎などの他のアレルギー疾患を合併している場合は、小児アレルギーを専門とする医師に相談するのが最も望ましいでしょう。
どちらを受診するか迷う場合は、まずはかかりつけの小児科に相談し、必要に応じて専門医を紹介してもらうのがスムーズです。
- 薬を飲んでも蕁麻疹が治らない場合はどうすればよいですか?
-
処方された薬を飲んでも症状が改善しない場合、いくつかの可能性が考えられます。薬の種類や量が合っていない、症状の勢いが薬の効果を上回っている、あるいは蕁麻疹の背景に別の原因が隠れているなどです。
自己判断で薬をやめたり、量を増やしたりせず、必ず処方した医師に相談してください。薬の種類を変更したり、他の薬を追加したり、あるいは改めて原因を検索するための検査を行ったりと、医師が次の対策を検討します。
- 蕁麻疹は他の人にうつりますか?
-
蕁麻疹は、自分自身の体内のマスト細胞から放出されるヒスタミンによって起こる反応です。発疹に触れたり、一緒にお風呂に入ったりしても、感染の心配は全くありません。
ただし、まれにウイルスや細菌の感染症が引き金となって蕁麻疹が発症することがあります。その場合、原因となっている感染症自体がうつる可能性はありますが、蕁麻疹という症状そのものがうつるわけではありません。
- 血液検査で原因は必ずわかりますか?
-
血液検査(アレルギー検査)を行っても、蕁麻疹の原因が必ず特定できるわけではありません。特に、6週間以上続く慢性蕁麻疹では、8割近くが原因不明の特発性であるとされています。
アレルギー検査は、あくまでアレルギー性の蕁麻疹が疑われる場合に、原因アレルゲンを推測するための一つの手がかりです。
検査結果が陰性であっても、問診などから特定の物質が原因として強く疑われることもありますし、逆に陽性であっても、それが直接症状の原因とは限らないこともあります。
検査結果は、医師が総合的に判断するための材料の一つと捉えることが大切です。
以上
参考文献
Hide M, Uda A, Maki F, Miyakawa N, Kohli RK, Gupta S, Krupsky K, Balkaran B, Balp MM. Prevalence and Burden of Chronic Spontaneous Urticaria in Japan: A Cross-Sectional Study. Journal of Clinical Medicine. 2025 Feb 11;14(4):1162.
Limpongsanurak W, Tuchinda P, Chularojanamontri L, Chanyachailert P, Korkij W, Chunharas A. Clinical practice guideline for diagnosis and management of urticaria. Asian Pac J Allergy Immunol. 2016;34:190-200.
Hide M, Hiragun M, Hiragun T. Diagnostic tests for urticaria. Immunology and Allergy Clinics. 2014 Feb 1;34(1):53-72.
Takahashi T, Minami S, Teramura K, Tanaka T, Fujimoto N. Four cases of acute infectious urticaria showing significant elevation of plasma D‐dimer level. The Journal of Dermatology. 2018 Aug;45(8):1013-6.
Fukunaga A, Washio K, Hatakeyama M, Oda Y, Ogura K, Horikawa T, Nishigori C. Cholinergic urticaria: epidemiology, physiopathology, new categorization, and management. Clinical Autonomic Research. 2018 Feb;28(1):103-13.
Tanaka T, Hiragun M, Hide M, Hiragun T. Analysis of primary treatment and prognosis of spontaneous urticaria. Allergology International. 2017;66(3):458-62.
Nakatani S, Oda Y, Washio K, Fukunaga A, Nishigori C. The Urticaria Control Test and Urticaria Activity Score correlate with quality of life in adult Japanese patients with chronic spontaneous urticaria. Allergology International. 2019;68(2):279-81.
Hide M, Fukunaga A, Suzuki T, Nakamura N, Kimura M, Sasajima T, Kiriyama J, Igarashi A. Real-world safety and effectiveness of omalizumab in Japanese patients with chronic spontaneous urticaria: A post-marketing surveillance study. Allergology International. 2023;72(2):286-96.
Hide M, Suzuki T, Tanaka A, Aoki H. Long-term safety and efficacy of rupatadine in Japanese patients with itching due to chronic spontaneous urticaria, dermatitis, or pruritus: A 12-month, multicenter, open-label clinical trial. Journal of Dermatological Science. 2019 Jun 1;94(3):339-45.
Kaneko S, Nakahara T, Sumikawa Y, Fukunaga A, Masuda K, Kakamu T, Morita E. Current status of the satisfaction levels of adult patients receiving drugs for atopic dermatitis and chronic urticaria. Journal of Cutaneous Immunology and Allergy. 2022 Feb;5(1):4-11.