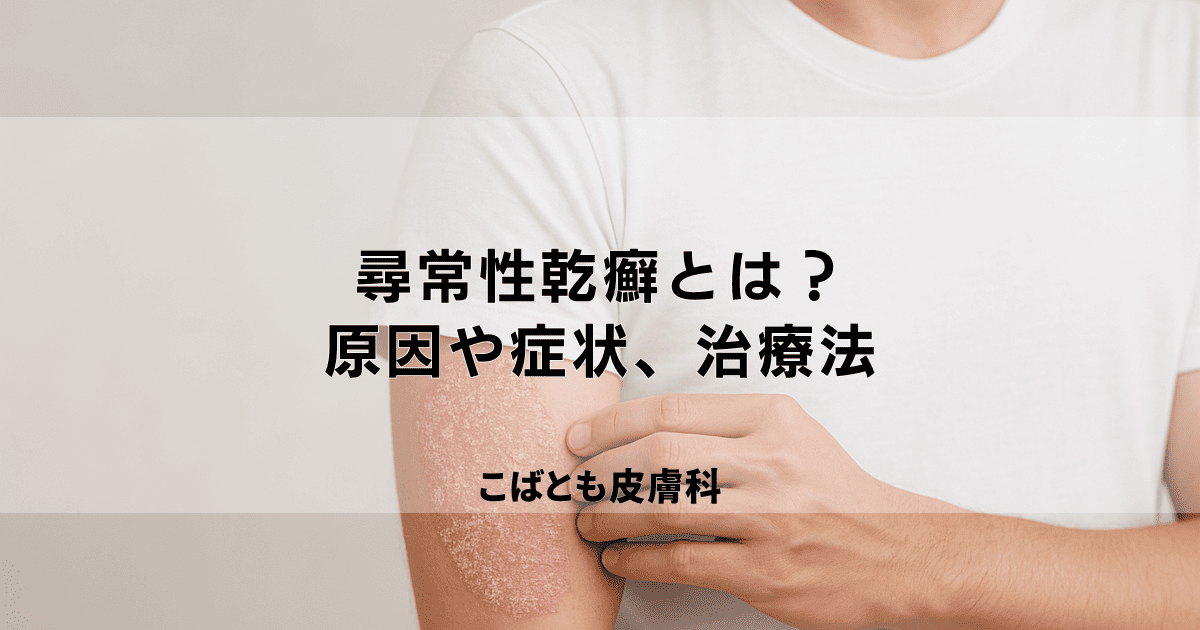ある日突然、皮膚に赤い発疹や白い粉のようなものが現れ、なかなか治らない。そんな症状にお悩みではありませんか。それはもしかすると、尋常性乾癬かもしれません。
尋常性乾癬は、単なる肌荒れとは異なり、免疫の働きが関わる慢性の皮膚の病気です。見た目の問題から、人目が気になり、つらい思いをしている方も少なくありません。
この記事では、尋常性乾癬の基本的な知識から、原因、症状、そして皮膚科で行う治療法まで、分かりやすく解説します。
この記事の執筆者

小林 智子(こばやし ともこ)
日本皮膚科学会認定皮膚科専門医・医学博士
こばとも皮膚科院長
2010年に日本医科大学卒業後、名古屋大学医学部皮膚科入局。同大学大学院博士課程修了後、アメリカノースウェスタン大学にて、ポストマスターフェローとして臨床研究に従事。帰国後、同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンターにて、糖化と肌について研究を行う。専門は一般皮膚科、アレルギー、抗加齢、美容皮膚科。雑誌を中心にメディアにも多数出演。著書に『皮膚科医が実践している 極上肌のつくり方』(彩図社)など。
こばとも皮膚科関連医療機関
尋常性乾癬の基本的な知識
尋常性乾癬という病名を聞き慣れない方も多いでしょう。まずは、この病気がどのようなものなのか、基本的な特徴から見ていきます。
尋常性乾癬とはどのような皮膚の病気か
尋常性乾癬は、皮膚が赤く盛り上がり(紅斑)、その上に銀白色の鱗屑(りんせつ)と呼ばれるフケのようなものが付着し、ポロポロと剥がれ落ちるのが特徴的な、慢性の皮膚疾患です。
尋常性という言葉は、一般的に見られる、ありふれたという意味合いで使われ、乾癬全体の約9割をこのタイプが占めます。
皮膚の新陳代謝(ターンオーバー)が異常に速くなることで、未熟な皮膚細胞が次々と作られ、積み重なって厚い角層を形成し、特徴的な皮膚症状を引き起こすのです。
症状の出方には個人差が大きく、良くなったり悪くなったりを繰り返す傾向があります。
乾癬の主な種類
| 種類 | 特徴 | 割合 |
|---|---|---|
| 尋常性乾癬 | 境界がはっきりした赤い発疹と銀白色の鱗屑 | 約90% |
| 滴状乾癬 | 水滴のような小さな発疹が全身に出現 | 約4% |
| 乾癬性紅皮症 | 全身の皮膚が赤くなる | 約1% |
他の人にうつることはあるのか
尋常性乾癬の見た目から、他の人にうつるのではないかと心配する方や、誤解されてしまうことがありますが、尋常性乾癬は細菌やウイルスが原因の感染症ではないのを知っておくことが大切です。
自身の免疫システムに異常が生じることで発症する病気のため、他の人にうつることはなく、温泉やプール、理髪店など、公共の場での接触や、家族間での共同生活においても、感染の心配は全くありません。
日本における患者数と発症年齢
日本国内における尋常性乾癬の患者数は、年々増加傾向にあると考えられています。近年の調査では、人口の0.3%程度、およそ40万人から50万人の患者さんがいると推定され、性別による差はほとんどなく、男女ほぼ同数です。
発症しやすい年齢には2つのピークがあり、一つは20代から30代の青年期、もう一つは50代から60代の中年期ですが、この年齢層以外でも、子供から高齢者まで、幅広い年代で発症する可能性があります。
尋常性乾癬の主な症状
尋常性乾癬の症状は、皮膚だけに留まらないこともあります。
皮膚に現れる特徴的な症状
最も代表的な症状は、皮膚に現れる発疹です。
乾癬の特徴
- 紅斑(こうはん)
- 浸潤・肥厚(しんじゅん・ひこう)
- 鱗屑(りんせつ)
- 落屑(らくせつ)
まず、皮膚に境界がはっきりとした赤い発疹(紅斑)が現れ、発疹は、周囲の正常な皮膚との境目が明確なのが特徴です。
そして、その部分は炎症によって少し盛り上がった状態(浸潤・肥こう)になり、表面は、銀白色の細かいかさぶたのようなもの(鱗屑)で覆われます。
鱗屑は、軽くこするだけでフケのようにポロポロと剥がれ落ち(落屑)、かゆみを伴うことも多く、患者さんのおよそ半数以上がかゆみを感じるといわれています。
症状が出やすい体の部位
尋常性乾癬の症状は、全身のどこにでも現れる可能性がありますが、特に刺激を受けやすい部位に好発する傾向があり、頭皮や髪の生え際、肘、膝、お尻、すねなどが代表的です。
このような部位は、衣服による摩擦や、日常生活での圧迫などが加わりやすいため、症状が出やすいと考えられています。
症状が好発する部位とその特徴
| 好発部位 | 特徴 | 日常生活での注意点 |
|---|---|---|
| 頭皮 | フケと間違われやすい。かゆみが強いことが多い。 | 爪を立てずに指の腹で優しく洗髪する。 |
| 肘・膝 | 衣服との摩擦で悪化しやすい。 | 締め付けの少ない、柔らかい素材の衣服を選ぶ。 |
| 腰・お尻周り | 座っている時の圧迫や下着のゴムなどで刺激を受けやすい。 | 長時間同じ姿勢でいることを避け、時々体勢を変える。 |
爪の変化と関節の症状(乾癬性関節炎)
尋常性乾癬は皮膚だけでなく、爪にも症状が現れることがあり、爪に小さな凹みができたり、爪が厚くなったり、変形・変色したりするのが主な症状です。爪の症状は、乾癬患者さんのおよそ20~40%に見られます。
さらに、乾癬患者さんの一部では、関節に炎症が起こり、痛みや腫れ、こわばりを生じる乾癬性関節炎を合併することがあります。
手足の指の関節やアキレス腱、背骨など、様々な関節に症状が現れる可能性があり、皮膚症状に加えて関節の痛みが続く場合は、早めに専門医に相談することが重要です。
尋常性乾癬の原因
なぜ尋常性乾癬が発症するのか、はっきりとした原因はまだ完全には解明されていませんが、近年の研究により、いくつかの要因が複雑に関与していることが分かってきました。
免疫システムの異常な働き
尋常性乾癬の根本には、免疫システムの異常があると考えられています。本来、免疫は体外から侵入した細菌やウイルスなどの異物を攻撃し、体を守るための大切な仕組みです。
しかし、何らかのきっかけでこの免疫システムに異常が生じ、自分自身の正常な皮膚細胞を異物と間違えて攻撃してしまうことがあり、皮膚に炎症が起きます。
さらに炎症が信号となり、皮膚細胞に対して過剰に増殖するよう命令が出され、皮膚のターンオーバーが異常に速まり、尋常性乾癬特有の症状が現れるのです。
免疫の働きに関わる主な細胞と物質
| 名称 | 主な役割 | 乾癬における状態 |
|---|---|---|
| T細胞 | 免疫の司令塔として働くリンパ球の一種 | 活性化し、皮膚細胞を攻撃する |
| サイトカイン | 細胞間の情報伝達を担うタンパク質 | 炎症を引き起こす種類が過剰に産生される |
| 角化細胞 | 表皮を構成する細胞 | 異常な速さで増殖し、厚い角層を形成する |
遺伝的な要因の関与
尋常性乾癬は、遺伝的な要因が発症に関わっていることが知られていて、血縁者に乾癬の患者さんがいる場合、いない場合に比べて発症する可能性が高くなるというデータがあります。
欧米では約30~40%、日本では約4~5%の患者さんに家族内発症が見られます。ただし、特定の遺伝子があれば必ず発症するというわけではありません。
乾癬になりやすい体質(遺伝的素因)を受け継いだ上で、様々な環境的な要因が加わることで、発症に至ると考えられています。
生活習慣や環境的な要因
遺伝的な素因を持っていても、必ずしも発症するわけではなく、発症の引き金となるのは、様々な後天的な要因です。
- 不規則な生活やストレス
- 食生活の乱れ、肥満
- 喫煙、過度な飲酒
- 薬剤(一部の降圧薬など)
- 感染症(特に扁桃炎など)
このような要因は、免疫システムに影響を与えたり、体内の炎症を促進したりすることで、尋常性乾癬の発症や悪化に関与すると考えられています。
尋常性乾癬を悪化させる要因
尋常性乾癬は、一度症状が落ち着いても、様々なきっかけで再び悪化することがあります。どのようなことが症状に影響を与えるのかを知り、日常生活で注意すべき点を把握しておきましょう。
ストレスや不規則な生活
精神的なストレスは、尋常性乾癬の代表的な悪化要因の一つです。ストレスは自律神経やホルモンバランスを乱し、免疫機能に影響を与えることが知られていて、仕事や人間関係の悩み、過労、睡眠不足などが続くと、症状が悪化しやすくなります。
また、生活リズムの乱れも体に負担をかけ、症状の悪化につながることがあります。できるだけ規則正しい生活を送り、心身を休ませる時間を確保することが重要です。
食生活の乱れと肥満
食生活も尋常性乾癬の症状と深く関わっています。高脂肪・高カロリーの食事は、体内の炎症を促進し、症状を悪化させる可能性があります。動物性脂肪の多い肉類や揚げ物、糖分の多い菓子類などの過剰な摂取は控えるのが賢明です。
一方で、魚に含まれるEPAやDHA、野菜や果物に含まれるビタミン、抗酸化物質などは、炎症を抑える働きが期待でき、バランスの取れた食事を心がけることが、体の中から症状をコントロールする助けになります。
また、肥満自体が慢性的な炎症状態を引き起こし、乾癬を悪化させることが分かっています。適度な運動を取り入れ、適正体重を維持することも大切です。
食事で気をつけたいポイント
| 積極的に摂りたいもの | 控えめにしたいもの | ポイント |
|---|---|---|
| 青魚(サバ、イワシなど) | 動物性脂肪(肉の脂身など) | 良質な油を摂取し、炎症を抑える |
| 緑黄色野菜、果物 | 糖分の多い食品、加工食品 | ビタミンやミネラルで体の調子を整える |
| 海藻類、きのこ類 | 香辛料などの刺激物 | 食物繊維で腸内環境を改善する |
喫煙や過度な飲酒
喫煙は、尋常性乾癬の発症リスクを高め、症状を悪化させることが多くの研究で示されています。
タバコに含まれるニコチンなどの有害物質が、血管を収縮させて血流を悪化させたり、体内の酸化ストレスを高めて炎症を起こしたりするためと考えられています。禁煙は、乾癬の治療効果を高める上でも非常に重要です。
また、過度な飲酒も、肝臓に負担をかけたり、体内の炎症を助長したりすることで、症状を悪化させる可能性があります。飲酒は適量を守るようにしましょう。
皮膚への刺激や感染症
尋常性乾癬には、ケブネル現象と呼ばれる特徴的な現象があり、これは、乾癬の症状がない正常な皮膚に、摩擦や圧迫、掻き傷、日焼けなどの刺激が加わると、その部位に新たな発疹が現れるというものです。
日常生活においては、皮膚への物理的な刺激をできるだけ避けることが大切で、きつい衣服や下着の着用を避け、体を洗う際にはタオルでゴシゴシこすらないように注意が必要です。
また、風邪や扁桃炎などの感染症にかかると、体内の免疫システムが活性化し、一時的に乾癬の症状が悪化することがあります。日頃から手洗いやうがいを徹底し、体調管理に努めることも悪化予防につながります。
皮膚科で行う尋常性乾癬の検査と診断
皮膚に気になる症状が現れた場合、自己判断せずに皮膚科を受診することが大切です。皮膚科では、専門医が検査を行い、正確な診断を下します。
医師による視診と問診
診断の基本は、医師による視診と問診です。視診では、発疹の色や形、大きさ、分布、鱗屑の状態などを詳しく観察し、尋常性乾癬に特徴的な所見があるかどうかを確認します。
問診では、いつから症状があるか、どのような経過をたどっているか、かゆみの有無、家族に同じような症状の人がいるか、持病や普段飲んでいる薬、生活習慣などについて詳しく尋ねます。
問診で確認する主な内容
| 項目 | 確認する内容の例 |
|---|---|
| 症状の経過 | 初発時期、良くなったり悪くなったりするかの繰り返し |
| 自覚症状 | かゆみ、痛み、関節の症状の有無 |
| 既往歴・家族歴 | 過去にかかった病気、血縁者の乾癬の有無 |
皮膚生検による確定診断
視診だけで診断が難しい場合や、他の皮膚疾患との区別が必要な場合には、皮膚生検を行うことがあります。皮膚生検は、局所麻酔をした上で、症状のある皮膚の一部を数ミリ程度採取し、顕微鏡で詳しく調べる検査です。
検査により、尋常性乾癬に特徴的な組織の変化(表皮の肥厚、真皮上層の血管拡張や炎症細胞の集まりなど)を確認でき、確定診断につながります。検査自体は短時間で終わり、痛みもほとんどありません。
他の皮膚疾患との見分け方
尋常性乾癬は、他のいくつかの皮膚疾患と症状が似ていることがあり、正確な治療を行うためには、正しく見分けることが重要です。
例えば、頭皮の乾癬は脂漏性皮膚炎と、体部の乾癬は貨幣状湿疹や体部白癬(たむし)と間違われることがあります。専門医は、発疹の境界の明瞭さ、鱗屑の色や質、好発部位などを総合的に判断して鑑別します。
尋常性乾癬と症状が似ている主な皮膚疾患
| 疾患名 | 尋常性乾癬との違い(一例) |
|---|---|
| 脂漏性皮膚炎 | 鱗屑が黄色っぽく、やや脂っぽい。境界が不明瞭なことが多い。 |
| アトピー性皮膚炎 | 強いかゆみを伴い、皮膚が乾燥してゴワゴワする。肘や膝の裏側など屈側に好発。 |
| 貨幣状湿疹 | 円形または楕円形の湿疹で、じゅくじゅくすることが多い。 |
尋常性乾癬の治療法
尋常性乾癬の治療目標は、症状をコントロールし、QOL(生活の質)を高く維持することです。現在のところ完治させる治療法はありませんが、治療を継続することで、症状がほとんどない状態(寛解)を長く保つことが可能です。
外用療法(塗り薬)
外用療法は尋常性乾癬治療の基本となる方法で、軽症から中等症の患者さんに行い、症状のある部分に直接薬剤を塗ることで、皮膚の炎症や細胞の異常な増殖を抑えます。
主に用いられるのは、ステロイド外用薬と活性型ビタミンD3外用薬です。2つの成分を配合した薬もあります。
主な外用薬の種類と特徴
| 薬剤の種類 | 主な作用 | 注意点 |
|---|---|---|
| ステロイド外用薬 | 強い抗炎症作用で、赤みや盛り上がりを抑える。 | 長期連用による皮膚萎縮などの副作用に注意が必要。 |
| 活性型ビタミンD3外用薬 | 皮膚細胞の異常な増殖を抑制する。 | 効果発現までに時間がかかることがある。血中カルシウム値への影響に注意。 |
| 配合外用薬 | ステロイドとビタミンD3の両方の作用を持つ。 | 利便性が高いが、医師の指示に従い適切に使用する。 |
光線療法(紫外線治療)
光線療法は、外用療法で十分な効果が得られない場合や、発疹の範囲が広い場合に行う治療法です。乾癬の症状を起こす免疫の働きを抑える作用のある、特定の波長の紫外線を患部に照射します。
ナローバンドUVB療法、エキシマライト療法、PUVA療法などの種類があり、治療には週に1~3回程度の通院が必要です。
内服療法(飲み薬)
症状が重い場合や、外用療法や光線療法で効果が不十分な場合、あるいは関節症状を伴う場合には内服療法を検討し、体の中から免疫の異常な働きや皮膚細胞の増殖を抑えます。
レチノイド(ビタミンA誘導体)、免疫抑制薬(シクロスポリン、メトトレキサートなど)、PDE4阻害薬などが用いられます。薬は高い効果が期待できる一方で、定期的な血液検査など、副作用の管理が重要です。
生物学的製剤(注射・点滴)
生物学的製剤は、近年の尋常性乾癬治療における大きな進歩の一つです。
これまでの治療で効果が不十分だった重症の患者さんに対して用いられ、乾癬の原因となる免疫の働きに深く関わる特定の物質(サイトカインなど)の働きをピンポイントで抑えることで、高い治療効果を発揮します。
皮下注射や点滴で投与し、投与間隔は薬の種類によって異なります。非常に効果が高い一方で、免疫を抑えるため感染症などへの注意が必要であり、高額な医療費がかかるという側面もあります。
使用にあたっては、専門医による慎重な判断が必要です。
- 既存の治療で効果が不十分
- 重症の皮疹が広範囲に及ぶ
- 関節症状を伴う
- QOLが著しく低下している
日常生活で心がけたいセルフケア
尋常性乾癬の症状を良好な状態でコントロールするためには、皮膚科での治療と合わせて、日々のセルフケアが重要になります。生活習慣を見直し、皮膚をいたわる工夫を取り入れましょう。
皮膚の保湿と清潔の維持
乾癬の皮膚は乾燥しやすく、バリア機能が低下しているため、外部からの刺激に敏感になっています。入浴後や乾燥が気になる時には、保湿剤をこまめに塗って皮膚の潤いを保つことが大切です。
保湿剤は、低刺激性のものをたっぷりと優しく塗り広げます。また、皮膚を清潔に保つことも重要ですが、洗いすぎは禁物です。
入浴時には、洗浄力の強すぎる石鹸は避け、よく泡立ててから手で優しく洗い、熱いお湯は避けてぬるま湯を使いましょう。
バランスの取れた食事と適度な運動
特定の食品が乾癬を治すということはありませんが、バランスの取れた食事は、健康な体作りの基本であり、症状の安定にもつながります。
脂肪分の多い食事や香辛料などの刺激物は避け、野菜や魚を中心とした和食のような食生活が望ましいとされています。また、肥満は乾癬の悪化因子であるため、適度な運動を習慣づけ、体重をコントロールすることも大切です。
ウォーキングやストレッチなど、無理なく続けられる運動から始めてください。
ストレス管理と十分な睡眠
ストレスは乾癬を悪化させる大きな要因で、自分なりのストレス解消法を見つけることが重要です。
- 趣味に没頭する時間を作る
- 軽い運動でリフレッシュする
- ゆっくりと入浴する
- 信頼できる人に話を聞いてもらう
また、睡眠不足も体の免疫バランスを崩す原因となります。質の良い睡眠を十分にとるために、就寝前のスマートフォン操作を控えるなど、リラックスできる環境を整えましょう。
よくある質問
最後に、尋常性乾癬に関して患者さんからよく寄せられる質問と回答をまとめました。
- 治療期間はどのくらいかかりますか
-
尋常性乾癬は、高血圧や糖尿病と同じように、長く付き合っていく必要のある慢性の病気です。そのため、治療期間が明確に決まっているわけではありません。
治療の目標は、症状をコントロールして快適な日常生活を送れる状態を維持することで、治療によって症状が改善しても、自己判断で中断せず、医師の指示に従って根気よく治療を続けることが大切です。
- 治療費はどのくらいかかりますか
-
外用薬による治療は比較的安価ですが、光線療法や内服療法、特に生物学的製剤による治療は高額になる傾向があります。ただし、日本では高額療養費制度など、医療費の負担を軽減する制度を利用できます。
詳しい費用については、治療を開始する前に担当医や医療機関の相談窓口に確認することをお勧めします。
- 完治はしますか
-
残念ながら、現在の医療では尋常性乾癬を完全に治す(完治させる)方法は見つかっていません。
しかし近年、治療法は目覚ましく進歩しており、治療を継続することで、症状がほとんどない、あるいは全くない状態(寛解)を長期間維持することが可能になっています。
- 民間療法を試しても良いですか
-
インターネットなどでは、乾癬に効果があるとうたう様々な民間療法やサプリメントの情報が見られますが、多くは科学的な根拠が乏しく、かえって症状を悪化させたり、健康被害を引き起こしたりする危険性もあります。
試してみたい民間療法がある場合は、必ず事前に皮膚科の専門医に相談してください。まずは、医療機関で標準的な治療を受けることが最も重要です.
以上
参考文献
Saeki H, Nakagawa H, Nakajo K, Ishii T, Morisaki Y, Aoki T, Cameron GS, Osuntokun OO, Japanese Ixekizumab Study Group, Akasaka T, Asano Y. Efficacy and safety of ixekizumab treatment for Japanese patients with moderate to severe plaque psoriasis, erythrodermic psoriasis and generalized pustular psoriasis: results from a 52‐week, open‐label, phase 3 study (UNCOVER‐J). The Journal of dermatology. 2017 Apr;44(4):355-62.
Torii H, Nakagawa H, Japanese Infliximab Study Investigators. Long‐term study of infliximab in Japanese patients with plaque psoriasis, psoriatic arthritis, pustular psoriasis and psoriatic erythroderma. The Journal of dermatology. 2011 Apr;38(4):321-34.
Fujita H, Terui T, Hayama K, Akiyama M, Ikeda S, Mabuchi T, Ozawa A, Kanekura T, Kurosawa M, Komine M, Nakajima K. Japanese guidelines for the management and treatment of generalized pustular psoriasis: the new pathogenesis and treatment of GPP. The Journal of dermatology. 2018 Nov;45(11):1235-70.
Takahashi H, Nakamura K, Kaneko F, Nakagawa H, Iizuka H, Japanese Society for Psoriasis Research. Analysis of psoriasis patients registered with the Japanese Society for Psoriasis Research from 2002–2008. The Journal of dermatology. 2011 Dec;38(12):1125-9.
Torii H, Terui T, Matsukawa M, Takesaki K, Ohtsuki M, Nakagawa H, Japanese Dermatological Association (JDA) PMS committee. Safety profiles and efficacy of infliximab therapy in Japanese patients with plaque psoriasis with or without psoriatic arthritis, pustular psoriasis or psoriatic erythroderma: Results from the prospective post‐marketing surveillance. The Journal of Dermatology. 2016 Jul;43(7):767-78.
Kishimoto M, Komine M, Hioki T, Kamiya K, Sugai J, Ohtsuki M. Real‐world use of apremilast for patients with psoriasis in Japan. The Journal of Dermatology. 2018 Nov;45(11):1345-8.
Saeki H, Nakagawa H, Ishii T, Morisaki Y, Aoki T, Berclaz PY, Heffernan M. Efficacy and safety of open‐label ixekizumab treatment in Japanese patients with moderate‐to‐severe plaque psoriasis, erythrodermic psoriasis and generalized pustular psoriasis. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology. 2015 Jun;29(6):1148-55.
Asahina A, Nakagawa H, Etoh T, Ohtsuki M, Adalimumab M04‐688 Study Group. Adalimumab in Japanese patients with moderate to severe chronic plaque psoriasis: efficacy and safety results from a Phase II/III randomized controlled study. The Journal of dermatology. 2010 Apr;37(4):299-310.
Saeki H, Terui T, Morita A, Sano S, Imafuku S, Asahina A, Komine M, Etoh T, Igarashi A, Torii H, Abe M. Japanese guidance for use of biologics for psoriasis (the 2019 version). The Journal of dermatology. 2020 Mar;47(3):201-22.
Komine M, Morita A. Generalized pustular psoriasis: current management status and unmet medical needs in Japan. Expert Review of Clinical Immunology. 2021 Sep 2;17(9):1015-27.