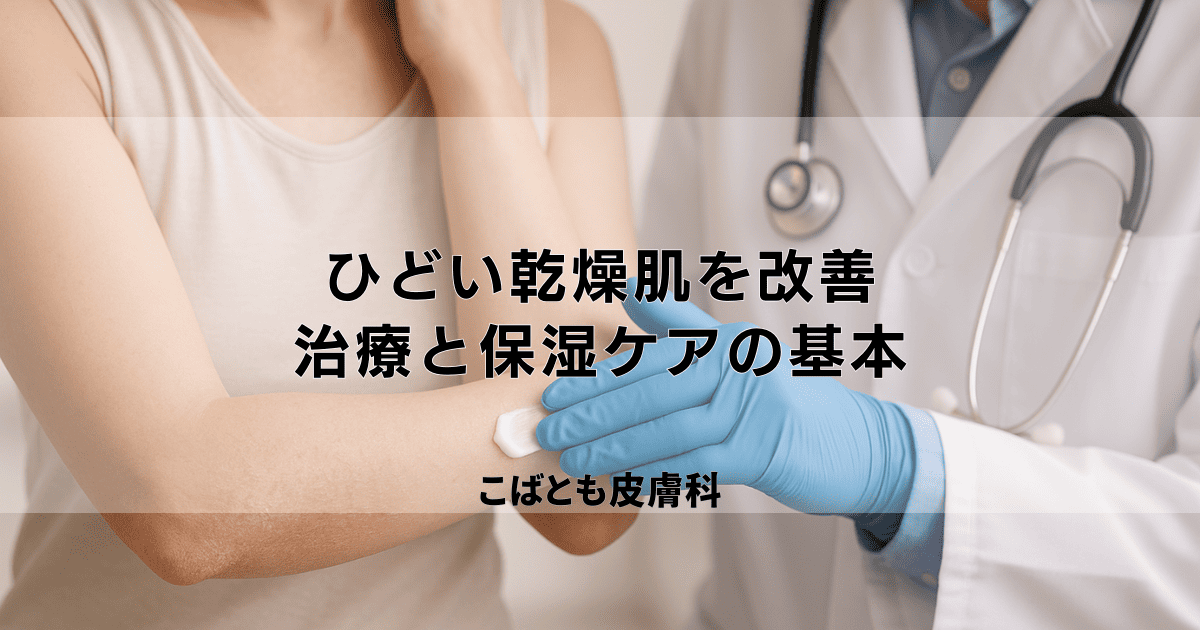冬場だけでなく、一年を通して肌の乾燥に悩んでいませんか。かゆみや粉ふき、ひび割れなど、ひどい乾燥肌の症状は日常生活にも影響を及ぼすつらいものです。
自己流のケアではなかなか改善が見られず、どうすれば良いか途方に暮れている方も少なくないでしょう。ひどい乾燥肌は、単なる肌質の問題ではなく、皮膚のバリア機能が低下しているサインかもしれません。
この記事では、皮膚科で行う専門的な乾燥肌治療から、日々の生活で実践できる効果的な保湿ケアの基本まで、肌を健やかな状態に導くための知識を詳しく解説します。
この記事の執筆者

小林 智子(こばやし ともこ)
日本皮膚科学会認定皮膚科専門医・医学博士
こばとも皮膚科院長
2010年に日本医科大学卒業後、名古屋大学医学部皮膚科入局。同大学大学院博士課程修了後、アメリカノースウェスタン大学にて、ポストマスターフェローとして臨床研究に従事。帰国後、同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンターにて、糖化と肌について研究を行う。専門は一般皮膚科、アレルギー、抗加齢、美容皮膚科。雑誌を中心にメディアにも多数出演。著書に『皮膚科医が実践している 極上肌のつくり方』(彩図社)など。
こばとも皮膚科関連医療機関
なぜ乾燥肌はひどくなるのか?
肌が乾燥する状態がなぜ悪化してしまうのか、背景にはいくつかの要因が複雑に絡み合っています。肌表面の潤いが失われるだけでなく、肌本来が持つ防御機能そのものが弱ってしまうことが、ひどい乾燥肌の根本的な問題です。
皮膚のバリア機能の低下とは
私たちの皮膚の一番外側にある角層には、外部の刺激から肌を守り、内部の水分の蒸発を防ぐバリア機能が備わっています。
バリア機能は、角層細胞がレンガのように積み重なり、その隙間を細胞間脂質(セラミドなど)がセメントのように埋めることで成り立っています。
健康な肌では構造がしっかりしているため、肌の潤いが保たれ、アレルゲンや細菌などの侵入を防ぎますが、何らかの原因で細胞間脂質が減少したり、角層のターンオーバーが乱れたりすると、角層に隙間ができてしまいます。
この隙間から肌内部の水分がどんどん逃げてしまい、同時に外部からの刺激を受けやすい無防備な状態になります。これがバリア機能の低下であり、ひどい乾燥肌の直接的な原因です。
健康な肌とバリア機能が低下した肌の違い
| 項目 | 健康な肌 | バリア機能が低下した肌 |
|---|---|---|
| 角層の状態 | 細胞が整然と並び、隙間がない | 細胞が乱れ、隙間が多い |
| 水分量 | 十分に保持されている | 蒸発しやすく、不足している |
| 外部刺激への抵抗力 | 高い | 低く、刺激を受けやすい |
季節や環境による影響
肌の状態は、私たちが生活する環境、特に季節の変化に大きく左右されます。空気が乾燥する秋から冬にかけては、外気の湿度が大幅に低下します。この乾燥した空気に肌が直接さらされると、角層の水分が奪われやすくなり、乾燥が進みます。
また、冬場は暖房器具の使用が欠かせませんが、エアコンやストーブによる温風は室内の湿度をさらに下げ、肌の乾燥を加速させる一因となります。一方で、夏場も安心はできません。
強力な紫外線は肌にダメージを与え、バリア機能を低下させ、さらに、冷房が効いた室内で長時間過ごすことも、肌を乾燥させる原因になるため、一年を通して注意が必要です。
加齢とホルモンバランスの変化
年齢を重ねることも、乾燥肌がひどくなる大きな要因の一つです。加齢に伴い、皮膚の機能は全体的に低下していきます。
バリア機能の主役であるセラミドなどの細胞間脂質や、天然保湿因子(NMF)、皮脂の分泌量は20代をピークに減少し始め、保湿成分が減少すると、肌は水分を保持する力を失い乾燥しやすくなります。
また、女性の場合は、更年期を迎えると女性ホルモン(エストロゲン)の分泌が急激に減少します。エストロゲンには、肌のハリや潤いを保つコラーゲンの生成を促す働きがあるため、乾燥をさらに進行させることにつながるのです。
間違ったスキンケア習慣
良かれと思って行っている日々のスキンケアが、かえって肌の乾燥を悪化させているケースも少なくありません。
洗浄力の強すぎるクレンジング剤や洗顔料の使用、ゴシゴシと強くこするような洗い方は、肌に必要な皮脂や細胞間脂質まで洗い流してしまい、バリア機能を破壊する原因となります。
また、熱いお湯での洗顔や長時間の入浴も、肌の保湿成分を溶かし出してしまうため避けるべきで、洗顔後や入浴後に保湿ケアを怠ったり、化粧水だけで済ませてしまったりするのも問題です。
化粧水で補った水分を肌に閉じ込めるためには、乳液やクリームなどの油分を含むアイテムで蓋をする必要があります。
肌の乾燥を招く可能性のある習慣
- 熱いお湯での洗顔や入浴
- 洗浄力の強い洗顔料の使用
- ナイロンタオルなどでのゴシゴシ洗い
- 洗顔後の保湿ケア不足
- 不十分な紫外線対策
ひどい乾燥肌が起こす皮膚トラブル
乾燥した状態を放置してしまうと、単にカサつくだけでなく、様々な皮膚トラブルへと発展する可能性があります。バリア機能が低下した肌は非常にデリケートで、普段なら何でもないようなわずかな刺激にも過敏に反応してしまいます。
かゆみや赤み、湿疹の発生
ひどい乾燥肌で最もつらい症状の一つが、我慢できないほどの強いかゆみです。肌が乾燥すると、かゆみを感じる神経線維が皮膚の表面近くまで伸びてくるため、些細な刺激でもかゆみを感じやすくなります。
そして、かゆい部分を掻きむしってしまうと、刺激でさらに角層が傷つき、バリア機能が低下することで炎症を引き起こし、赤みやブツブツとした湿疹(皮脂欠乏性湿疹)を発生させます。
一度この悪循環に陥ると、掻くことで症状が悪化し、さらにかゆみが増すという負の連鎖から抜け出すのが難しいです。
特に就寝中など無意識に掻いてしまうことも多く、朝起きたら肌が傷だらけになっていたという経験を持つ方もいるでしょう。
肌のひび割れやあかぎれ
乾燥が極度に進行すると皮膚の柔軟性が失われ、硬くゴワゴワした状態になり、このような肌は、関節の曲げ伸ばしといった日常的な動作による皮膚の伸縮についていけず、表面に亀裂が入りやすくなります。
これがひび割れで、特に、指先やかかとなど、皮膚が厚く、動きの多い部位によく見られます。さらに乾燥が進み、亀裂が皮膚の深い部分(真皮)にまで達し、出血や痛みを伴う状態があかぎれです。
乾燥による主な皮膚症状
| 症状 | 特徴 | 主な発生部位 |
|---|---|---|
| 皮脂欠乏性湿疹 | 強いかゆみ、赤み、ブツブツ | すね、腰まわり、腕など |
| ひび割れ | 皮膚表面の浅い亀裂、痛みは少ない | 指、手のひら、かかと |
| あかぎれ | 深く裂けた亀裂、出血や痛みを伴う | 指先、かかと |
色素沈着やくすみにつながる可能性
肌にかゆみや炎症が続くと、防御反応としてメラニン色素が過剰に生成されることがあります。
掻きむしるなどの物理的な刺激が慢性的に加わることで、肌はその部分を守ろうとしてメラニンをたくさん作り出し、炎症が治まった後も、茶色っぽくくすんで見える炎症後色素沈着という状態になることがあります。
一度できてしまった色素沈着を薄くするには時間がかかり、見た目の上でも大きな悩みとなります。
また、肌全体の乾燥は、ターンオーバーの乱れを起こし、古い角質がうまく剥がれ落ちずに肌表面に蓄積し、肌全体の透明感が失われ、くすんで見える原因です。
感染症のリスク増加
健康な皮膚の表面は、外部からの病原体の侵入を防ぐ重要な砦ですが、ひどい乾燥によってバリア機能が崩れ、ひび割れや掻き傷ができてしまうと、そこから細菌やウイルスが容易に侵入できる状態になります。
黄色ブドウ球菌などが侵入すると、とびひ(伝染性膿痂疹)や蜂窩織炎(ほうかしきえん)といった細菌感染症を起こす可能性があり、感染症は患部の腫れや強い痛み、時には発熱を伴うので、抗菌薬による治療が必要です。
特にアトピー性皮膚炎の方は、皮膚のバリア機能がもともと弱い傾向にあるため、乾燥によって症状が悪化し、感染症を合併するリスクがより高くなります。
皮膚科で行う乾燥肌の専門的な治療法
セルフケアだけでは改善が難しいひどい乾燥肌は、皮膚科での専門的な治療が必要です。皮膚科では、現在の肌の状態を正確に診断し、症状や原因に応じた適切な治療法を提案します。
専門医による正確な診断の重要性
ひどい乾燥肌といっても、背景には様々な原因が考えられます。単なる加齢や季節による乾燥(皮脂欠乏症)だけでなく、アトピー性皮膚炎や乾皮症、魚鱗癬(ぎょりんせん)といった特定の皮膚疾患が隠れている可能性もあります。
また、内臓の病気や服用している薬の副作用が、皮膚の乾燥として現れることもあり、皮膚科専門医は、視診や問診、場合によっては血液検査や皮膚の一部を採取して調べる検査(皮膚生検)などを通じて、乾燥の原因を的確に突き止めます。
自己判断でケアを続けることは、原因となっている病気を見逃し、症状を悪化させることにもつながりかねません。
保湿剤の処方(ヘパリン類似物質など)
皮膚科での乾燥肌治療の基本は、保湿剤によるスキンケアです。市販の保湿剤も数多くありますが、医療機関で処方される保湿剤は、保湿効果が科学的に証明されており、保険適用で処方されます。
代表的なものは、ヘパリン類似物質含有製剤や尿素製剤です。
ヘパリン類似物質は高い保湿効果を持つだけでなく、血行を促進したり炎症を抑えたりする作用も持っていて、尿素製剤は、硬くなった角質を柔らかくする効果と水分を保持する効果があり、かかとなどのゴワつきが気になる部位に適しています。
医師は患者さんの肌の状態や使用感の好みに合わせて、軟膏、クリーム、ローション、フォーム(泡)など、様々な剤形の保湿剤の中から最適なものを選択します。
皮膚科で処方される主な保湿剤
| 成分名 | 主な作用 | 剤形の種類 |
|---|---|---|
| ヘパリン類似物質 | 保湿、血行促進、抗炎症 | クリーム、ローション、軟膏、スプレー、フォームなど |
| 尿素 | 角質溶解、水分保持 | クリーム、ローション、軟膏 |
| 白色ワセリン | 皮膚保護、水分蒸発抑制 | 軟膏 |
炎症を抑えるための外用薬(ステロイドなど)
かゆみや赤み、湿疹などの炎症症状が強い場合には、保湿剤だけでは十分な効果が得られません。このような場合は、炎症を強力に抑える作用を持つステロイド外用薬を併用します。
ステロイドと聞くと、副作用を心配される方もいるかもしれませんが、皮膚科専門医の指導のもとで、症状の強さや部位に合わせて適切なランクの強さの薬を、適切な期間使用すれば、非常に効果的で安全な治療薬です。
炎症を短期間でしっかりと抑え、掻きむしる行為を防ぐことで、バリア機能のさらなる破壊を食い止め、肌が良い状態に戻るための土台を作ります。炎症が治まれば、ステロイド外用薬は徐々に減量・中止し、保湿剤中心のケアに移行していきます。
内服薬による体質改善アプローチ
外用薬による治療と並行して、内服薬が処方されることもあります。
かゆみの症状が非常に強く、夜も眠れないほどであったり、掻きむしることで日常生活に支障が出たりする場合には、かゆみを抑える抗ヒスタミン薬や抗アレルギー薬の内服が有効です。
薬は、かゆみの原因となるヒスタミンの働きをブロックすることで、つらいかゆみを和らげ、掻き壊しの悪循環を断ち切る助けとなります。また、肌の状態を改善するために、ビタミン剤や漢方薬などが補助的に用いられることもあります。
体の中からアプローチすることで、外用薬の効果を高め、より健やかな肌状態を目指します。
治療効果を高める日常の保湿ケアの基本
皮膚科での治療を始めたからといって、日々のセルフケアが不要になるわけではありません。処方された薬の効果を最大限に引き出し、良い肌状態を維持するためには、正しい保湿ケアを毎日続けることが非常に重要です。
保湿剤を塗る最適なタイミング
保湿剤を塗る効果が最も高まるのは、肌が水分を多く含んでいるときで、入浴後やシャワー後、洗顔後が絶好のタイミングです。
お風呂上がりは、肌の角層が水分をたっぷり含んで柔らかくなっていますが、同時に水分が最も蒸発しやすい状態でもあります。
肌の水分量は、入浴後10分も経つと入浴前よりも低くなってしまうというデータもあるため、お風呂から上がったら、タオルで水分を優しく押さえるように拭き取り、肌がまだしっとりしている5分以内に保湿剤を塗ることを心がけましょう。
保湿剤を塗るべき主なタイミング
- 入浴やシャワーの直後(5分以内が目安)
- 朝の洗顔後
- 手を洗った後
- 日中、乾燥が気になったとき
部位別の正しい塗り方と量の目安
保湿剤は、ただ塗れば良いというものではありません。適切な量を、正しい方法で塗ることが大切です。量が少なすぎると十分な効果が得られませんし、多すぎてもベタつくだけで効果は変わりません。
保湿剤を塗る際には、肌をこすらず、手のひらで優しく押さえるようにしてなじませ、シワに沿って丁寧に塗り込むと、塗りムラを防ぐことができます。
使用量の目安として、フィンガーチップユニット(FTU)という考え方があり、これは、大人の人差し指の第一関節までチューブから薬を絞り出した量(約0.5g)で、大人の手のひら2枚分の面積に塗るのに適した量とされています。
保湿剤の適切な使用量の目安(1FTUあたり)
| 部位 | 使用量の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 顔全体 | 約1 FTU | 目や口の周りは丁寧に |
| 片腕(手首まで) | 約1.5 FTU | 肘などの関節部分もしっかりと |
| 片足(足首まで) | 約3 FTU | 膝やかかとなど乾燥しやすい部分に重ね付けも有効 |
保湿効果を持続させるための工夫
一度塗った保湿剤の効果をできるだけ長く保つためには、いくつかの工夫が有効です。まず、特に乾燥がひどい部位には、保湿剤の重ね付けを試してみましょう。
ローションタイプの保湿剤を塗った後に、クリームや軟膏タイプのものを重ねて塗ることで、水分の蒸発をより強力に防ぐことができます。
また、保湿剤を塗った直後に綿素材などの通気性の良い衣服を着用すると、保湿剤が寝具や他の場所についてしまうのを防ぎ、肌への浸透を助けます。夜寝る前に保湿ケアを行った手足に、綿の手袋や靴下を履いて休むのも良い方法です。
日中も、乾燥を感じたらこまめに塗り直す習慣をつけることが、一日中潤った肌を保つ秘訣です。
保湿だけじゃない、生活習慣から見直す乾燥肌対策
ひどい乾燥肌の改善には、外側からの保湿ケアと同時に、体の内側から肌を健やかに保つための生活習慣の見直しが欠かせません。食事や睡眠、ストレス管理といった日々の暮らし方が、肌のコンディションに大きく影響します。
バランスの取れた食事と水分補給
健やかな皮膚を作るためには、その材料となる栄養素を食事からしっかりと摂取することが基本です。
皮膚の細胞を作るもとのタンパク質、ターンオーバーを正常に保つビタミンA、皮膚や粘膜の健康維持を助けるビタミンB群、抗酸化作用がありコラーゲンの生成を助けるビタミンC、血行を促進するビタミンEなどをバランス良く摂ることが大切です。
また、肌の潤いを保つためには、体内の水分が不足しないように、こまめな水分補給も重要で、一度に大量に飲むのではなく、1日に1.5〜2リットルを目安に、のどが渇く前に少しずつ飲む習慣をつけましょう。
健やかな肌をサポートする栄養素と食品例
| 栄養素 | 主な働き | 多く含まれる食品 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 皮膚の細胞の主成分 | 肉、魚、卵、大豆製品 |
| ビタミンA | 皮膚や粘膜の健康維持 | レバー、うなぎ、緑黄色野菜 |
| ビタミンC | コラーゲン生成、抗酸化作用 | パプリカ、ブロッコリー、果物 |
質の良い睡眠の確保
睡眠は、日中に受けた肌のダメージを修復し、新しい細胞へと生まれ変わらせるための大切な時間です。特に、眠り始めの深いノンレム睡眠中には、肌のターンオーバーを促す成長ホルモンが最も多く分泌されます。
睡眠不足が続くと、この成長ホルモンの分泌が減少し、肌の修復が追いつかなくなり、バリア機能が低下し、乾燥や肌荒れを起こしやすくなります。毎日6〜8時間程度の十分な睡眠時間を確保してください。
また、時間だけでなく、睡眠の質も重要です。就寝前にスマートフォンやパソコンの画面を見るのは避け、リラックスできる環境を整えるなど、質の高い睡眠をとるための工夫を取り入れましょう。
ストレス管理とリラックス法
過度なストレスは、自律神経やホルモンのバランスを乱し、肌の状態を悪化させる大きな要因となります。ストレスを感じると、体内で活性酸素が増加し、肌細胞を傷つけたり、血行不良を招いて肌のターンオーバーを乱したりします。
また、ストレスはかゆみを増強させることも知られています。日常生活の中で、自分に合ったストレス解消法を見つけ、心身をリラックスさせる時間を作ることが大切です。
おすすめのリラックス法
- ぬるめのお湯での半身浴
- 好きな音楽を聴く、映画を観る
- ヨガやストレッチなどの軽い運動
- アロマテラピー
- 深呼吸や瞑想
室内の湿度管理
肌の乾燥を防ぐためには、過ごす時間が長い自宅やオフィスの環境を整えることも重要です。空気が乾燥する季節には、加湿器を使用して室内の湿度を適切に保つことをお勧めします。快適に過ごせる湿度の目安は50〜60%です。
加湿器がない場合は、濡れたタオルを室内に干したり、観葉植物を置いたりするだけでも効果があります。また、エアコンの風が直接肌に当たらないように、風向きを調整するなどの配慮も大切です。
乾燥肌のためのスキンケア製品の選び方
毎日のスキンケアで使用する製品選びは、乾燥肌対策において非常に重要なポイントです。肌に合わない製品を使い続けると、かえって乾燥を悪化させたり、新たな肌トラブルを起こしたりする可能性があります。
保湿成分の種類と特徴
保湿剤や化粧品に含まれる保湿成分には、様々な種類があり、それぞれ働きが異なります。保湿成分は、大きく分けて3つのタイプに分類できます。
1つ目は、ヒアルロン酸やコラーゲン、アミノ酸類のように、水分を抱え込んで保持する水分保持タイプ。2つ目は、ワセリンやスクワランのように、肌表面に膜を張って水分の蒸発を防ぐ油性タイプ。
そして3つ目は、セラミドやスフィンゴ脂質のように、角層の細胞の間を埋めて水分を挟み込むタイプです。ひどい乾燥肌の方は、特にバリア機能を補うセラミドなどの成分や、水分の蒸発を防ぐ油性成分が配合された製品を選ぶと良いでしょう。
代表的な保湿成分と働き
| 成分の種類 | 代表的な成分名 | 主な働き |
|---|---|---|
| 水分保持タイプ | ヒアルロン酸、コラーゲン | 水分を抱え込む |
| 油性タイプ | ワセリン、スクワラン | 水分の蒸発を防ぐ |
| バリア機能補助タイプ | セラミド、スフィンゴ脂質 | 角層の隙間を埋める |
肌に優しい洗浄料の選び方
スキンケアの第一歩である洗顔は、汚れを落としながらも肌の潤いを奪わない製品を選ぶことが重要です。洗浄力が強すぎる製品は、肌に必要な皮脂や保湿成分まで洗い流してしまいます。
乾燥肌の方は、アミノ酸系やカルボン酸系の洗浄成分を主成分とした、マイルドな洗浄力の洗顔料を選びましょう。
製品のタイプとしては、洗浄時に肌への摩擦が少ない、泡で出てくるポンプタイプや、きめ細かく弾力のある泡が簡単に作れるものがおすすめです。
また、スクラブ入りの洗顔料は、肌を傷つける可能性があるため、使用は避けてください。洗い流す際は、ぬるま湯を使い、すすぎ残しがないように丁寧に、素早く行います。
添加物を避けるための成分表示チェック
バリア機能が低下している乾燥肌は、特定の成分に対して刺激を感じやすい状態です。スキンケア製品を選ぶ際には、肌への刺激となる可能性のある添加物が含まれていないか、成分表示をチェックする習慣をつけましょう。
香料、着色料、アルコール(エタノール)、パラベン(防腐剤)などが、人によっては刺激になることがあります。
これらの成分がすべて悪いわけではありませんが、肌が敏感になっているときは、できるだけシンプルな処方の製品を選ぶ方が安心です。
「低刺激性」「敏感肌用」「アレルギーテスト済み」といった表示がある製品は、選択の一つの目安ですが、全ての人に刺激が起きないというわけではないため、初めて使う製品は、まず腕の内側などで試してから顔に使用することをおすすめします。
スキンケア製品選びのチェックポイント
- 保湿成分が十分に配合されているか
- 洗浄力がマイルドか
- 香料、着色料、アルコールなどが無添加か
- 「低刺激性」などの表示があるか
よくある質問
ここでは、ひどい乾燥肌の治療やケアに関して、患者さんからよく寄せられる質問と回答をまとめました。
- 保湿剤は1日に何回塗れば良いですか?
-
保湿剤を塗る回数に、厳密な決まりはありません。基本的には、朝の洗顔後と夜の入浴後の1日2回が目安となりますが、あくまで基本であり、肌の乾燥状態は個人差が大きく、また日によっても変動します。
日中に肌のカサつきや、つっぱり感を感じるようであれば、その都度、追加で塗り直すのが効果的です。特に、手を洗った後や水仕事の後などは、こまめにハンドクリームなどで保湿することを習慣づけましょう。
- 処方された薬と市販の保湿剤は併用できますか?
-
自己判断で併用する前に、必ずかかりつけの医師や薬剤師に相談してください。ステロイド外用薬などの治療薬と保湿剤を併用する場合、塗る順番が重要になることがあります。
先に保湿剤を塗って肌全体のコンディションを整えてから、炎症のある部分にのみ治療薬を塗るよう指示されることが多いです。
また、市販の保湿剤の中には、処方薬の吸収に影響を与えたり、肌への刺激となったりする成分が含まれている可能性もゼロではありません。
安全かつ効果的に治療を進めるためにも、使用している、あるいは使用したい市販品があれば、診察時に持参して医師に見てもらうと良いでしょう。
- 食事で気をつけることはありますか?
-
特定の食品を食べれば乾燥肌が治る、というものはありません。最も大切なのは、様々な食品をバランス良く食べることです。
特に、肌細胞の材料となるタンパク質、肌のターンオーバーを助けるビタミン類、血行を良くするミネラルなどを意識して摂取しましょう。
香辛料の多い刺激物や、脂肪分・糖分の多い食品の過剰な摂取は、皮脂のバランスを崩したり、腸内環境を悪化させたりして、間接的に肌の状態に影響を与える可能性があります。
- 乾燥肌は完治しますか?
-
乾燥肌は、アトピー性皮膚炎などの特定の疾患が原因である場合を除き、病気というよりは肌質や体質に近いものです。
風邪のように薬を飲んだら完治するというものではなく、加齢や季節の変化など、様々な要因によって誰にでも起こります。
しかし、皮膚科での適切な治療と、日々の正しいスキンケア、そして生活習慣の見直しを継続することで、症状をコントロールし、乾燥やかゆみのない健やかな肌状態を長期間維持することは十分に可能です。
以上
参考文献
Tanaka K, Nagasawa T, Nomura Y, Kubota Y, Miyake A, Kawamura K, Yamaguchi Y. Clinical trial of low irritative skin care cosmetics in Japanese subjects with dry skin. Clinical, cosmetic and investigational dermatology. 2020 Nov 2:805-14.
Miyano K, Tsunemi Y. Current treatments for atopic dermatitis in Japan. The Journal of Dermatology. 2021 Feb;48(2):140-51.
Wakamori T, Katoh N, Hirano S, Kishimoto S, Ozasa K. Atopic dermatitis, dry skin and serum IgE in children in a community in Japan. International archives of allergy and immunology. 2009 May 1;149(2):103-10.
Konya I, Iwata H, Hayashi M, Akita T, Homma Y, Yoshida H, Yano R. Reliability and validity of the Japanese version of the overall dry skin score in older patients. Skin Research and Technology. 2022 Jan;28(1):28-34.
Nitta S, Matsumoto M, Sugama J, Nakagami G, Okuwa M, Nakatani T, Sanada H. New quantitative indicators of evaluating the skin care regimen for older adults with dry skin by using the digital image analysis. J Nurs Sci Eng. 2016;3(2):93-100.
Ooi K. Onset mechanism and pharmaceutical management of dry skin. Biological and Pharmaceutical Bulletin. 2021 Aug 1;44(8):1037-43.
Izumi R, Negi O, Suzuki T, Tominaga M, Kamo A, Suga Y, Matsukuma S, Takamori K. Efficacy of an emollient containing diethylene glycol/dilinoleic acid copolymer for the treatment of dry skin and pruritus in patients with senile xerosis. Journal of cosmetic dermatology. 2017 Dec;16(4):e37-41.
Itamura R, Hosoya R. Homeopathic treatment of Japanese patients with intractable atopic dermatitis. Homeopathy. 2003 Apr;92(02):108-14.
Kawamura A, Ooyama K, Kojima K, Kachi H, Abe T, Amano K, Aoyama T. Dietary supplementation of gamma-linolenic acid improves skin parameters in subjects with dry skin and mild atopic dermatitis. Journal of oleo science. 2011;60(12):597-607.
Hashizume H. Skin aging and dry skin. The Journal of dermatology. 2004 Aug;31(8):603-9.